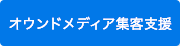先日、知人の誘いで、あるビジネスの会合に参加した。
初対面の方が多かったので、まずお互いに自己紹介をし、その後テーマに沿って議論をした。
期待してはいなかったのだが、主催者の進行が上手だったので、思いがけず有意義な議論ができたと感じた。
さて、本題はここからだ。
会合も終わり、何名かの方は後日も連絡を取りましょう、ということで、スマホでSNSのアカウントを交換しあった。
中には「共通の知り合い」がいる方も何名かいて、「世間は狭いですねー」と、雑談を交わした。
そこでふと気づいた。
あれ「名刺」って、使わなくなってない? と。
もちろん、名刺は持っているし、堅いビジネスシーンにおいては、初対面の人との名刺交換は儀式として行われている。
だが、そうしたシーンで交換した名刺を、その後も使っているのか、と言われると、実は全くと言ってよいほど使わない。
一昔前は
「名刺を整理する」
「名刺を見返す」
「名刺の電話やメールアドレスに連絡を取る」
という活動を行っていたが、現在ではもらった名刺を見返すことすら、ごく稀である。
なぜか。
フォローはSNSで送ればいいし、連絡を取り合いたい場合、SNSアカウントを伝えあったほうが確実だからだ。
名刺にかかれている情報よりも、SNSアカウントは遥かに多くの情報を与えてくれる上、大きなメリットがある。
例えば、
1.その方が転職しても、連絡先が変わらない
名刺のメールアドレスは、会社が変わると使えなくなることが多い。
2.SNSでフォローしておけば、近況がよく分かる
例えば「高島屋の店長に話を聞いたら、地方で着々と「人口減少社会への適応」が進んでいて、驚いた。」という記事で、私がインタビューした中川さんとは、高校卒業以来、20年ぶり以上であったが、SNSでちらほら近況を見ていたので、全く「久しぶり感」はなかった。
3.SNSは「友達の友達」がわかる。
その人だけではなく、その人の向こうのネットワークもわかる。
4.「現在」だけではなく「過去」のこともわかる。
経歴などが乗っている場合、専門性を把握できる
要は、名刺の情報はpoorすぎるが故に、すでに主流たり得ない。
現在でも使われている理由は単に「昔から使われていたから」だけだ。
*
実は、SNSはビジネスで利用すれば、極めて「個人を利する」仕組みとなっている。
今までは属性情報の持ち主は、良かれ悪しかれ「個人」ではなく、会社などの「組織」だった。
だが、SNSは属性情報の所有者を「組織」ではなく「個人」にした。
これは大変に大きな変化で、ビジネス上もインパクトがある。
実際、少なくない量の知識労働が「会社」ではなく「個人」に流れているのだ。
これは決して、大げさな話ではない。
事実「単なる知り合い」レベルだった方が転職した後、突然仕事の依頼の連絡をしてくることが少なからずある。
もちろん私も知人の「転職した」情報をSNSで掴んだら、それまで頼めなかった依頼をすることがある。
「あの人には頼みたいけど、企業の都合で別の担当者になるんだったら、嫌だな」という仕事はいくらでもある。
その場合、SNSを通じて直接依頼をすることもできる。
もちろん、これは「全員」がそうであるわけではない。
SNSをやっていない人(教えたくないだけかもしれない)もいるし、SNSをビジネス用途に使っていない人も大勢いるだろう。
調査によれば「SNSはプライベートのみ」という方も少なくないと思われる。
「ビジネスにおけるSNS利用に関する意識調査2017」を実施 – 81.9%の人が「仕事とプライベートでSNSを分けたい」
従来のSNSはプライベートのコミュニケーションをするためという認識が強く、調査対象者全員が、一度は仕事関係者からのSNS申請を拒否または無視したことがあると答えています。
また、そもそも「個人の能力」が重要ではない仕事についている人は、SNSの利用もへったくれもない。
とは言え、「仕事ができる人たち」が集まる会合に行くと、「ビジネス用のアカウントがない」という方は非常に稀だし、
「SNS使ってないんですよ」と言うと、「え?……あ、そうですか。 いえ、別にいいんですけど……」と、気を遣ってくれる人も多いが、まあ「別の世界の人」認定されてしまって、微妙な雰囲気になることもある。
結果として、SNSのアカウントを交換してない人は、定例的に顔を合わせる何かしらの場がない限り
「まあ、今後はめったに会わないだろうな」
「別にこの人じゃなくていいや」
となってしまう。
*
しかし、「名刺」の良さを検討しないままでは、不公平というものだろう。
そこで逆に「名刺」ならではの良さとはなんだろう?
と少し考えてみる。
まず、紙媒体の交換という儀式は、非常に簡単であること。
SNSによる情報交換は、SNSにもよるが、操作性などが悪く、若干冗長である。
「あれ?QRコードの表示って、どうやるんだっけ……?」みたいな。
次に、必要以上の情報を開示しなくて済むこと。
「組織 対 組織」の構図の中でしか仕事をしない人にとっては、SNSまで覗かれるのは嫌だ、と思う方も多いと思う。
まあ、気分的にはわかる。
ただ「ビジネス用のアカウント」を持っておけば、特にそんな悩みは発生しないのだが。
あとは……どうだろう。
「SNSが嫌いな人達」が一定数いるので、そういった人とのコミュニケーションには必須かもしれない。
「いやー、おれSNSとかわかんないんだけど」とか
「全く見ないね」とか
「若い人は好きだよねー。」とか。
「あれでしょ?SNSって、炎上したりするのが怖いんで、あんまりね……」とか。
実は炎上させるのはメチャクチャ難しいのだが、まあ、それは置いておく。
まあ、ただ、今どきSNSを全く使ってない人と、今後積極的に仕事をするかなあ……?ちょっと想像しにくいな、とは思う。
*
とはいえ、いま伸びているマーケットで活躍している人々は、間違いなくSNSを活用しているし、使い方もうまい。
というのも、SNS抜きでの情報収集や発信は、極めて限定的だからだ。
最近ではマスコミすら、SNSで流れている情報を積極的に電波に乗せている。
また、面接や営業の前に、候補者や担当者のSNSを見ることはもはや普通であると言っても良い。
いや、もっと言えば「コミュニケーション能力」の先に、「より大きな人的ネットワークを使いこなすこと」が、これからの時代の素養になる可能性すらある。
ハーバード大のニコラス・クリスタキスは、「社会的ネットワークが脳の急速な巨大化を促した」という。
絆を結び、社会的ネットワークの中で一生を送るという私達の傾向は、主としての人間の発達に大きな影響を与えてきた。
社会的ネットワークは脳の急速な巨大化を促し、そのおかげで人間は言葉を手に入れ、地球を支配する種となった。
同時に、こうした生物学的変化を通じて、人間はある能力を獲得した。
大きな集団の中で見ず知らずの相手とさえ協力し、壮大で複雑な社会を作り出す能力である。
人間を高度な知能を持つ動物に仕立てたのが「ネットワークを築く能力」だとしたら、「より大きなネットワークを使いこなすこと」が、人間のさらなる進化をもたらす可能性もある。
そんなことを考えるにつけ、「名刺を使わなくなったなあ……SNSで十分なのかも。」と思うのは、まあ、妥当なのかもしれない。
◯Twitterアカウント▶安達裕哉(人の能力について興味があります。企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働者と格差について発信。)
弊社ティネクト(Books&Apps運営会社)が2024年3月18日に実施したウェビナー動画を配信中です
【アーカイブ動画】ChatGPTを経営課題解決に活用した最新実践例をご紹介します
2024年3月18日実施したウェビナーのアーカイブ動画です(配信期限:2024年4月30日まで)<セミナー内容>
1.ChatGPTって何に使えるの?
2.経営者から見たChatGPTの活用方法
3.CharGPTが変えたマーケティング現場の生々しい実例
4.ティネクトからのプレゼント
5.Q&A
【講師紹介】
楢原一雅(ティネクト取締役)
安達裕哉(同代表取締役)
倉増京平(同取締役)
ご希望の方は下記ページ内ウェビナーお申込みフォーム内で「YouTube動画視聴」をお選び頂きお申込みください。お申込み者にウェビナーを収録したYoutube限定動画URLをお送りいたします。
お申込み・詳細 こちらティネクウェビナーお申込みページをご覧ください
(2024/3/26更新)
【著者プロフィール】
◯Twitterアカウント▶安達裕哉
◯安達裕哉Facebookアカウント (安達の記事をフォローできます)
◯Books&Appsフェイスブックページ(Books&Appsの記事をフォローしたい方に)
◯ブログが本になりました。
(Photo by Brando Makes Branding on Unsplash)