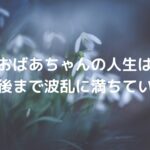「できるなら、ぽっくり死にたいよね」。多くの人がそう口にする。
母方の祖母が数年前に亡くなったが、まさにその形だったようだ。電話中に倒れてそのまま帰らぬ人となったのだという。
もともと心臓の病気を抱えていた。78歳だった。
最期ですらそのような「ぽっくり」だったが、どうだったのだろうと思っている。
最期まで波乱だったからだ。何が良いのか、わたしにはまだわからない。
おじいちゃんの遠い記憶
小学校の何年生のときだっただろうか。低学年だろう。
ある日先生がわたしのところに、
「清水さん、おじいちゃんが亡くなったらしいから、とりあえず今すぐおうちに帰りなさい」。
と耳打ちしにきた。
そこから、一家三人で北海道に向かったことだけは覚えている。
しかし正直、そのおじいちゃんに関しては遠い記憶しかない。
遺影を見て、そういえばこんな顔をしていたかもしれないなあ、という程度である。
わたしにとっての小学生のときの北海道の記憶では、ひとりになった祖母のところに宿題を持って長期間行っていたことくらいである。
当時、夏休みになるとJALの「ちびっこ一人旅」で福岡空港でわたしひとり飛行機に乗せられ、北海道に向かっていた。
千歳空港には叔父が迎えに来てくれていたのだと思う。
祖母が暮らしていたのは、小さな小さな町の平家アパートの一室。
札幌から50~60kmほど離れた、平取町(びらとりちょう)の貫気別(ぬきべつ)という地域だ。
日中は近所の木工所で働く祖母の帰りを待ちながら、部屋で宿題をする。
あるとき祖母が木工所で、機械に指を巻き込まれて大怪我をしたことも覚えている。指先が少し欠けてしまった。
また、祖母は農作業をしている時もあった。
そこに様子を見に行くと、
「さやか、タバコ持ってきておくれ」。
と頼まれ、アパートからタバコとライターを届けに行ったものだ。
働き者のおばあちゃん。畑での一服はおいしいんだろうなあ、そんなことを幼心に思っていた。
「新しいおじいちゃん」がやってきた!?
さて、そこから数年が経っただろうか。
祖母の生活が大きく変わったのである。
まだ小学生だったわたしに、母が言い出したことにわたしは仰天した。
「こんど、新しいおじいちゃんが遊びにくるけんね!北海道から九州まで車で来よるんよ!」
1500kmの距離を、各地を旅しながら祖母と「新しいおじいちゃん」が我が家にやってくるのだという。
当時は新型だった、冷蔵庫のついた白いハイエースに乗って。
状況を平たくいえば、祖母は「最初のおじいちゃん」と死別後、再婚したのである。5歳年下の公務員と。
お相手の「新しいおじいちゃん」もまた、最初の妻と死別していた。
その時、2人の共通の趣味であったカラオケの場で出会ったのだという。
「新しいおじいちゃん」がはじめて九州にやってきた時、わたしはまだ小学生だった。
でも、わたしにとっては最初のおじいちゃんの記憶は薄い。
だからその人を「おじいちゃん」と受け入れるのにそう時間はかからなかった。
いや、しかし、祖母の凄さを知った。
未亡人となってから、5歳下の旦那さんをゲットしたのである。
「おばあちゃん、やるぅ〜」
と思うくらいの年頃ではあった。祖母は魅力的な女性なのだと思った。
「新しいお父さん」「新しいお母さん」というのはドラマや物語で目にするが、
「あたらしいおじいちゃん」
というのはなかなか耳にしないことだろう。しかし、事実としてわたしの目の前にあったのだ。
本当に「じいちゃん」「父さん」だった
そして、わたしが夏休みに北海道に行って過ごす時間の内容も全く別のものになっていった。
運転が好きな「新しいおじいちゃん」は、北海道をくまなく案内してくれた。
襟裳岬から稚内、礼文島まで。苫小牧近辺から根室まで。北方四島を眺められる場所まで。
富良野、摩周、阿寒。
どれだけ北海道を満喫したことだろうか。
一通りのことろには行ったと思う。
すっかりわたしは「おじいちゃんっ子」だった。
しかし次第に、祖母は元々よくなかった足を徐々に悪くしていた。
かなり時間が経って。わたしが大人になってから。
こんどは苫小牧に新しく構えた家には、スロープや靴の着脱がしやすい工夫がされていた。
車も小さなものに買い替えていた。
そう長旅もしなくなったらしい。それでもふたりは穏やかに暮らしていた。
もちろん「新しいおじいちゃん」にも、息子はいた。
しかし一度お目にかかったかどうかくらいだ。
このおじいちゃんは、「こちらの家の人になる」ことを選択したのである。
そして、母3人きょうだいも「父さん」と呼び、それが自然なものになり、わたしにとってのおじいちゃんとは「新しいおじいちゃん」のほうになっている。
じいちゃんが古希を迎えた時には、わたしの両親を含む祖母の子供3人が北海道に集まってお祝いしていた。
日常会話でも「父さん」だった。
祖母の苗字こそ変わったが、生活実態はわたしのおじいちゃんであり、母たちの「父さん」だった。
わたしの母たちは、この「新しいおじいちゃん」の息子さんに会ったことはないと思う。
しかしそこは、誰も気にしていない。
普通だったら逆なのでは?と思われる方もいるだろうが、じいちゃんはそういう形を選んだのだ。
近くに住むバツイチ独身の叔父も、じいちゃんを「父さん」と呼び、その家に頻繁に夕食をとりに来ていた。様子を見がてらというのもあっただろう。
この「男同士の親子関係」が、のちに大きな役割を果たすことになるのだが。
そして。じいちゃんは、
祖母が死別した「前のおじいちゃん」の仏壇にも、日々きちんと手を合わせる。
ごく当たり前の日課として。
「3人」の不思議な暮らし
さらに、面白いことに。
苫小牧に構えた家では、2階に2部屋とちょっとのスペースが余っている。
「みえこさん」という、祖母と同じ年頃の女性が前の家からよく出入りし、泊まる時は泊まるという形で家族同然に暮らしており、2階の一室を自分の部屋にもしていた。
ほぼほぼ3人同居の家になっていた。
「みえこさん」はいたりいなかったりしたが、もう家族なのである。
おそらくだが「みえこさん」も未亡人なのだろう。
わたしの世話もよくしてくれた。
祖母が心臓の病気をこじらせてからは、「みえこさん」は頻繁に祖父母と一緒に苫小牧に滞在していた。
家事と祖母の手伝いをやってくれているのだ。
わたしの母が先立ってから
そして、ひとつの出来事があった。
おばあちゃんは、娘=わたしの母に、思わぬ形で先立たれてしまったのだ。
叔父の押す車椅子で福岡空港に姿を現した。おじいちゃんと共に。
家に着いて、父は義両親に土下座で平謝りである。
しかし祖母は怒るでもなく泣くでもなく何を語るわけでもなく、いつも通りの表情で父の言葉を聴いていた。
じいちゃんは、「まあ、かっちゃん、そんな思い詰めなさんな」と父の肩に手を置いた。
そして、通夜の前になって。
「さやか、ばあちゃんをお母さんの近くに連れて行っておくれ」。
祖母はそれまで、足が悪いために自力で母の側に行けなかったのである。
部屋まで祖母を椅子で運び、祖母が椅子から降りる足腰を支え、眠る母の目の前に祖母を連れて行った。
祖母はしばし、親を置いて先立った娘の顔とその姿を眺めていた。
しかし祖母はなんの言葉も発しなかった。涙するどころか、表情さえ変えなかった。
しばしの間母の顔をながめ、その深い深い瞳の中に全ての事実を吸い込み、そうして、もうこれでじゅうぶんだと言わんばかりにわたしを向いて、
「ありがとう、もういいよ」。
わたしは言われた通りに、祖母を再び椅子に乗せ、隣の部屋に移動し、じいちゃんの隣で床に座れるよう手伝った。
遠い記憶が蘇る。その昔、畑で言われた、
「さやか、タバコ持ってきておくれ」。
そう頼まれた時と、声色もまったく同じだった。
葬式どうするん?
そこから数年経って。
祖母が亡くなったという話を、親族の誰からだったか聞いた。父からだったと思う。
お葬式とかどうするん?そう聞いたのだが、父はなんだかもごもごしている。
「葬式とかはあれやけど、落ち着いたらみんなで墓参り行こうっていう話になったんよ」
と。
なんで?
なんで普通にお通夜してお葬式して、ってやらんの?
わたしは父に突っ込んだ。そこではじめて事実が明かされた。
祖母は、自分の先がそう長くないと知ったのだろうと思われるのだが、愛知の伯母家族と同じアパートの別部屋に、じいちゃんと一度引っ越したのだという。
そこでしばらく暮らしていた。
我慢していた酒もタバコもたしなんでいたという。
最後くらいは娘の近くで生活したかったのだろう。そこには、わたしの母に先立たれた悲しさもあったことだろう。
そして、じいちゃんもそれに賛同して引っ越しまでしたのである。
ところがある日。
具体的には何があったかは知らないが、おじいちゃんが伯母に大激怒する出来事が起きたという。
それをきっかけに、すぐさま北海道に帰って行ったという。
という話を父から聞き、ぎこちなさの正体がわかった。
泣きじゃくる伯母
その話を聞かされ、今度は伯母に電話をかけてみた。
泣いていた。
「わたしが全部悪いんだ。本当は見送りたいけどね、ここは親不孝させてもらおうかなと思うんよ。いいかなあ?」。
祖母が亡くなったのは、北海道に帰った後のことだった。
伯母と電話で話していた最中に倒れ、そのまま帰らぬ人となったのだという。
それは心臓病のせいなのだが、
しかし、何があったのかはわからないが
じいちゃんは頑なに、伯母が葬儀にくることを拒んでいるのだという。
「中に入れてもらえなくても近くまで行きたいけど、みんなに迷惑かけるから、親不孝だけど、行かない方がいいと思ってるんよ。いいよね?仕方ないよね?」。
そう聞かれても具体的に何が起きたのかわたしは知らない。
ただ、「それも仕方ないかもしれんね」とだけ返事しておいた。
その後、叔父にも電話をした。すると。
「いや、あれは姉さんが全部悪いんだべさ」。
そう切って捨てた。
孫のわたしはどうしたらいい?
とりあえず叔父は「父さん」と一緒にいるようだったが、それを聞く余地もない緊張感だった。わたしともコソコソ話しているのである。
きょうだいを分裂させるようなことでもあったようだ。
いま、どうしてる?
じいちゃんは伯母だけでなく、あれだけよくしてくれた「こちらの親族」との関係じたいを考えてしまったのだと思う。
叔父とは男同士だからそこは若干違う部分があるのだろう。
そして数年が経った。しかし、
「落ち着いてからの墓参り」はいまだ実現していない。
あれだけ優しかったじいちゃんを、そこまで怒らせた出来事とはなんだったんだろう。
いまだにその謎は解けない。
それよりも気になるのは、じいちゃんは今そこでどんな生活をしているのだろうかということだ。
妻と死別し、再婚してまた新しい妻と死別した。
もちろん、夫婦である以上どちらかが先に逝くのは仕方ない。
それでもきちんと「入籍」という形を選んだのにはなにか理由があるはずだ。
じいちゃん、さやかだけど?
いまどうしてる?
それを聞く術すらないのがもどかしい。
できるならまた一緒に酒を飲みたいのに。
そして祖母は、最後の手前まではどういう気持ちでいたのだろう。
素敵なパートナーといられて、トータルで幸せだったと思えていれば良いのだけど。
でも最後は、自分の娘と素敵なパートナーの間に板挟みだったかもしれない。
あるいは、我が娘ながら本気で怒っていたかもしれない。
祖母には、ますます尋ねようがない。
ティネクト(Books&Apps運営会社)提供オンラインラジオ第6回目のお知らせ。

<本音オンラインラジオ MASSYS’S BAR>
第6回 地方創生×事業再生
再生現場のリアルから見えた、“経営企画”の本質とは【ご視聴方法】
ティネクト本音オンラインラジオ会員登録ページよりご登録ください。ご登録後に視聴リンクをお送りいたします。
当日はzoomによる動画視聴もしくは音声のみでも楽しめる内容となっております。
【今回のトーク概要】
- 0. オープニング(5分)
自己紹介とテーマ提示:「地方創生 × 事業再生」=「実行できる経営企画」 - 1. 事業再生の現場から(20分)
保育事業再生のリアル/行政交渉/人材難/資金繰り/制度整備の具体例 - 2. 地方創生と事業再生(10分)
再生支援は地方創生の基礎。経営の“仕組み”の欠如が疲弊を生む - 3. 一般論としての「経営企画」とは(5分)
経営戦略・KPI設計・IRなど中小企業とのギャップを解説 - 4. 中小企業における経営企画の翻訳(10分)
「当たり前を実行可能な形に翻訳する」方法論 - 5. 経営企画の三原則(5分)
数字を見える化/仕組みで回す/翻訳して実行する - 6. まとめ(5分)
経営企画は中小企業の“未来をつくる技術”
【ゲスト】
鍵政 達也(かぎまさ たつや)氏
ExePro Partner代表 経営コンサルタント
兵庫県神戸市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。3児の父。
高校三年生まで「理系」として過ごすも、自身の理系としての将来に魅力を感じなくなり、好きだった数学で受験が可能な経済学部に進学。大学生活では飲食業のアルバイトで「商売」の面白さに気付き調理師免許を取得するまでのめり込む。
卒業後、株式会社船井総合研究所にて中小企業の経営コンサルティング業務(メインクライアントは飲食業、保育サービス業など)に従事。日本全国への出張や上海子会社でのプロジェクトマネジメントなど1年で休みが数日という日々を過ごす。
株式会社日本総合研究所(三井住友FG)に転職し、スタートアップ支援、新規事業開発支援、業務改革支援、ビジネスデューデリジェンスなどの中堅~大企業向けコンサルティング業務に従事。
その後、事業承継・再生案件において保育所運営会社の代表取締役に就任し、事業再生を行う。賞与未払いの倒産寸前の状況から4年で売上2倍・黒字化を達成。
現在は、再建企業の取締役として経営企画業務を担当する傍ら、経営コンサルタント×経営者の経験を活かして、経営の「見える化」と「やるべきごとの言語化」と実行の伴走支援を行うコンサルタントとして活動している。
【パーソナリティ】
倉増 京平(くらまし きょうへい)
ティネクト株式会社 取締役 / 株式会社ライフ&ワーク 代表取締役 / 一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルド 代表理事
顧客企業のデジタル領域におけるマーケティングサポートを長く手掛ける。新たなビジネスモデルの創出と事業展開に注力し、コンテンツマーケティングの分野で深い知見と経験を積む。
コロナ以降、地方企業のマーケティング支援を数多く手掛け、デジタル・トランスフォーメーションを促進する役割を果たす。2023年以降、生成AIをマーケティングの現場で実践的に活用する機会を増やし、AIとマーケティングの融合による新たな価値創造に挑戦している。
ご視聴登録は こちらのリンク からお願いします。
(2025/7/14更新)
【プロフィール】
著者:清水 沙矢香
北九州市出身。京都大学理学部卒業後、TBSでおもに報道記者として社会部・経済部で勤務、その後フリー。
かたわらでサックスプレイヤー。バンドや自ら率いるユニット、ソロなどで活動。ほかには酒と横浜DeNAベイスターズが好き。
Twitter:@M6Sayaka
Facebook:https://www.facebook.com/shimizu.sayaka/
Photo:Kiwihug