少し前に訪れた大学の先生から、面白い話を伺った。それは「知的な人物かどうか」という判断の基準に関するものである。
私達は「頭が悪い」と言われることを極端に嫌う。知性が人間そのものの優劣を決めるかどうかは私が判断するところではないが、実際知的であることは現在の世の中においては有利であるし、組織は知的な人物を必要としている。
だが、「どのような人物が知的なのか」ということについては多くの人々の判断が別れるところではないだろうか。
世の中を見渡すと、あらゆる属性、例えば学歴、職業、資格、言動、経済的状況などが「知的であるかどうか」のモノサシとして使われており、根拠があるものないもの含め、混沌としている。
だが、私がこの先生からお聞きした話はそういった話とは少し異なる。
彼は「人間の属性と、知的であるかどうかの関係はよくわかりませんが、少なくとも私が判断をするときは、五つの態度を見ています」
という。
エピソードを交え、様々な話をしていいただいたのだが、その5つをまとめると、次のようなものになった。
一つ目は、異なる意見に対する態度
知的な人は異なる意見を尊重するが、そうでない人は異なる意見を「自分への攻撃」とみなす
二つ目は、自分の知らないことに対する態度
知的な人は、わからないことがあることを喜び、怖れない。また、それについて学ぼうする。そうでない人はわからないことがあることを恥だと思う。その結果、それを隠し学ばない
三つ目は、人に物を教えるときの態度
知的な人は、教えるためには自分に「教える力」がなくてはいけない、と思っている。そうでない人は、教えるためには相手に「理解する力」がなくてはいけない、と思っている
四つ目は、知識に関する態度
知的な人は、損得抜きに知識を尊重する。そうでない人は、「何のために知識を得るのか」がはっきりしなければ知識を得ようとしない上、役に立たない知識を蔑視する
五つ目は、人を批判するときの態度
知的な人は、「相手の持っている知恵を高めるための批判」をする。そうでない人は、「相手の持っている知恵を貶めるための批判」をする。
知的である、というのは頭脳が明晰であるかどうか、という話ではなく、自分自身の弱さとどれだけ向き合えるか、という話であり、大変な忍耐と冷静さを必要とするものなのだ、と思う。
(2025/10/30更新)
「AIを使いたい」ではなく、「業務を楽にしたい」が真の目的ではありませんか?
本セミナーは、経営層・部門責任者のために、生成AIを組織変革の武器にする方法をお伝えします。
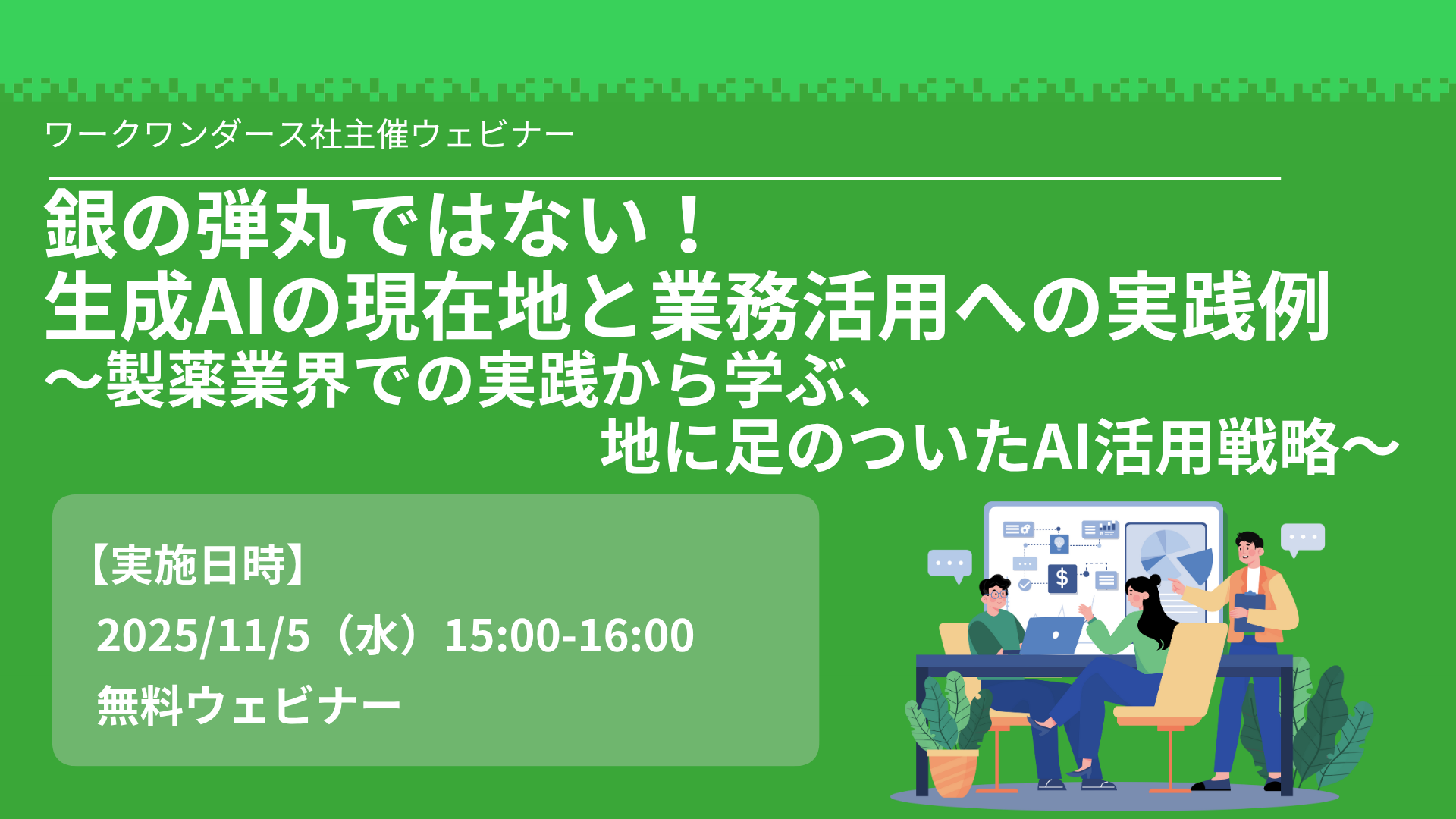
【開催概要】
・開催日:2025年11月5日(水)
・時間:15:00〜16:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員30名)
【対象者】
・情報システム部門の決裁者(部長〜役員クラス)
・DX推進部門の決裁者(部長〜役員クラス)
・生成AI活用の投資判断を行う立場の方
・組織のデジタル変革を推進する責任者
【セミナーの内容】
・生成AIの「過度な期待」と「現実」
- 「銀の弾丸」神話の実態
- 期待値のギャップが生む問題
- 生成AIの現在地と実力
・製薬業界での実践例:40名超のパイロットプロジェクト
- プロジェクトの背景と目的
- 個別業務ヒアリングで見えた現実
・期待:「なんでもできる魔法のツール」
・現実:業務特性による向き不向き
- 段階的な導入アプローチ
・期待値調整フェーズ/適用領域の選定/パイロット実施と効果測定
- 成功事例と失敗事例の詳細分析
・学びとノウハウ:地に足のついた活用戦略
- クライアントの真のニーズ(「AIを使いたい」ではなく「業務を楽にしたい」)と手段・目的の再定義
- 効果的な導入パターン/避けるべき落とし穴/組織的な成功要因
【登壇者】
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
・筆者Twitterアカウント▶安達裕哉(人の能力について興味があります。企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働者と格差について発信。)
・筆者Facebookアカウント https://www.facebook.com/yuya.adachi.58 (フォローしていただければ、最新の記事をタイムラインにお届けします)
・ブログが本になりました。














