自意識過剰で、刹那的な生き方を好むポーズを崩さない、つまりは、よくいる根暗なサブカル青年だった私は、自分は30歳までには死ぬだろうと思っていた。
気がつけば、生きる筈のない30代も終わろうとしていて、あの時代とここは地続きだったのか、という驚きとも諦めともとれない感情を抱きながら、もはや、はっきりとした感傷にも浸ることなく、無事、私は中年になった。
フリーランスのプログラマにとって、年度末は稼ぎ時だ。
その日も私は、システム開発のヘルプとして駆り出されて、依頼元である制作会社のオフィスで作業していた。
作ろうとしているものは平凡なもので、長い経験のある自分としては、スケジュールがタイトである以外は、手慣れた仕事だと思った。不安があるとすれば、システムの基本になるフレームワークを実際に仕事で使うのが初めて、ということだった。
だが、私の得意なWebシステムであることに違いはない。
フォームからの入力を受け取り、ビジネスロジックを実行して、DBにアクセスして、HTMLを出力する。全てはこの繰返しであり、その類にすぎないからだ。
私はすっかり気を抜いて、ロクに動作テストもせずに黙々とプログラムを書き進めていた。
処理の一部が全く動作しないことに気づいた。
しばらくウンウンと悩んで、どうにもならぬので、同じオフィスにいた年若いプログラマに原因を尋ねてみた。
私が書いたプログラムを見た彼は、やり方が違いますよ。と、呆れたように言った。
このフレームワークでは、このような書き方をしても実行されません。
「このフレームワークのドキュメント、本当に読みました?」とまでは言われなかった。
だが、それはきっと彼の中にある長幼の序というやつに違いなかったので、私は平静を装って席に戻ると、プログラムを急いで書き直し始めた。
結局、私はその仕事で、大した働きはできなかった。
ただ、小狡く立ち回って、表示上のズレを直すといった、細かいだけで大した技量を必要としないが、いかにも顧客にわかりやすい修正をこなして、残り少ない信用を取り繕った。
仕事が終わっても達成感はなく、ただ惨めさが残った。
年度明けの、そういった苦い酒を飲んでいると、5年ほど前に見た光景が浮かんだ。
ある自治体のシステムを納品しにいった日のことだ。
その自治体ではセキュリティ対策として、インターネットでアップロード、というわけにはいかず、私と依頼元の営業の二人は、システム一式が入ったUSBメモリを持って、役所のシステム部署を訪れた。
そこでは、同じ年格好をした4人のオジさんがパソコンに向かっていて、いかにも計算機屋といった風貌から、おそらくは全員どこかのベンダーから常駐人員として出向しているのだろうと思われた。
私達が来訪と目的を告げて、USBメモリをその一人に渡すと、確認しますので、と言い残して奥に引っ込んでいった。システム部の入り口で私達は所在なく立ちすくむよりなかった。
何を確認しているのかはわからないが、随分と時間がかかる。
自然と、話し声が耳に入った。確認作業をしている一人の他は、延々と何かのソフトウェアライセンスについての議論をしているようだった。
一人が、こうすればライセンスを遵守することになる、と言う。
もう一人が、いや実質的に利用者がこれだけいるのだから、その主張は無理がある、と言い返す。いや、そもそも無償ライセンスの条項に研究・評価目的があるのだから、それに該当すると主張することも可能だ、と一人目が反論する。
堂々巡りの議論に堪りかねて、三人目の声が、正当な稟議を通さないと責任問題になる、と辟易した口調で述べる、云々
内容や事情を聞かずとも、彼らの切迫したところのない、のんびりとした口調が、その議論に何の生産性もないことを明らかにしていた。
そのうちにUSBメモリを渡した一人が帰ってきて、大丈夫です。と私達を開放した。ドアを閉めてもなお、議論の声は続いていた。
私は「仙境」を垣間見た心地だった。
おそらくはあそこでは、竹林の賢者よろしく、年がら年中やることもない4人組がこういった会話を繰り返しているのだ、と考えて、すこし頭がクラクラした。
あれから時がたち、失意の私は、アルコールに染まった頭で、私もとうとう彼らと同類になったのであろうか、と考えていた。
実際にそうなってみるまで、まるで気づくこともなく、まんまとあの時の仙人じみた中年エンジニアになってしまった事に驚きもした。
いつのまにか私は、自分を客観視する視点を失ってしまったようなのだ。
原因として思い当たる節はいくつかあった。
一つは、自分が昔より、精神的に安定したことだ。昔の私は、まだ何者でもなく、多分に自信過剰なところがあったにせよ、社会という枠組みの中に自分の居場所を見いだせずにいた。
そういう人は自分の存在を確かめる必要に迫られ、常に周囲に目を配る必要がある。
上司の声色、顧客の社交辞令から滲み出す態度、ネットで知る同業者のスキルなどから、自分が「社会一般」より劣っているのか、優れているのか、冷遇されているのか、厚遇されているのか、偏執的な執念でそれを知ろうとする。
実のところ、このような態度が本来の目的であるアイデンティティの確立に役立つことはほとんどないが、視線が外界へ向けられた結果、自分を眺める視点も自然と遠くなって、ある程度の客観性を獲得していたのだろう。
また、失った「若さ」というものが競争的心理を内包していた事もあげられる。
活躍しているスポーツ選手や、成功した青年実業家が同い年だとか、幾分か若いと知った時、ジェラシーを抱いて心中がざわついた、という経験を覚えている人もいるのではないだろうか?
個人差は当然あるのだろうが、中年に差し掛かると、このような競争的心理が速やかに萎んでいく。
なぜか。
社会的に名声を獲得できる人間が僅かである以上、ほとんどの人は、この「同世代ゲーム」の中で敗者となる。
このゲームの参加者はあまりにも多すぎるので、この事実上の敗者に対して、誰も「勝負に負けた以上、敗者らしく振る舞え」と強制したりはしない。
敗者が、ゲームそのものを否定して、「私は私でがんばった結果が今なのだ」とか「俺には俺の道がある」といった、おそらくは若者から見れば欺瞞ともとれるような誤魔化しを堂々と表明しても誰にも責められることはない。
むしろ、潔い態度だ、と褒め称えられることすらある。
私はここで、そういった欺瞞を非難したいわけではない。
ただ、このような「敗者」の態度は「同世代ゲーム」が持っていた、常に自分を順位づけしなければ気が済まない、という性質も綺麗さっぱりなくしてしまって、これも一つ、人が客観性を失ってしまう原因の一つなのだろうとは思っている。
こうして、自分に対する客観性を失った人は、その興味を主に自分の地位や、食い扶持を構成するごく狭い範囲にとどめてしまう。世間や業界といった外の世界に対して、利用できる知識以上のものを求めることはしないし、また考えることも少なくなっていく。
業界全体の空気とか、競合他社の動向とか、革新的な技術とか、おそらくは重要なことであっても、新聞に書かれているような、通り一遍等な知識を保つのがせいぜいである。
一番の問題は、彼らが若い頃と同じ情熱を持って人生に挑んでいたとしても、客観性の欠如は、世界の境界を狭めてしまっているので、彼らがかつてアイデンティティに向けていたエネルギーの向かう先をそっくり変えてしまうことだ。
多くの場合、それはする必要のない仕事を見出して誰かに命じて、自分の力と地位を確かめることや、上司に自分の仕事ぶりをアピールすること、失敗の隠蔽、社内のゴシップを把握して、次にカバンを持つべき相手を探すのに使われて、真実のところで自己の利益と社会の利益との整合性を欠く行動をとるようになる。
今は一般に、それらは総称して「政治」と呼ばれている。
*
明け方に目覚めて、少し頭が痛む。昨晩の深酒が過ぎたようだ。
残り少なくなったウィスキーの瓶を見て、はるか遠い、同じような日のことを思い出す。
私がまだ音楽とバンドをやっていた20代の前半。練習が終わり、夜が明け、バイトのあるメンバーは欠伸をしながら帰ってしまい、私とギター担当のメンバーの二人だけが午前の迎え酒を飲んでいた日だ。
部屋のブラウン管テレビは、昼間の暇な情報番組らしく、立ち飲み屋で楽しく酒を飲んでいるオジさん達を写していた。
彼らは上機嫌に酒の旨さを語り、時には人生の深みについても語っているようだったが、ろれつのまわらぬ口調のそれは、しごく浅く、軽はずみで、番組のほのぼのとした雰囲気にも関わらず、私には彼らがずいぶんと無残で、間違って長く生きすぎた人間の末路にさえ見えるのだった。
私は氷の入ったグラスをカラカラと回しながら、「俺もそのうちこうなるんやろな」と呟いた。
隣で発泡酒を飲んでいた彼が、不思議そうな顔をした。
「なんでや?」
彼の問いに私は困惑した。年を重ねるとだいたいはこういう風になるやろ、と私は解説した。
「ならんやろ。俺らは。」
当然のことのように彼は言った。
「何があっても、俺らはこうはならんよ。なるわけない」
彼は断言した。そして、喉を鳴らして500mlの缶に残った酒を流し込んだ。
さあ、どうやろうなあ。と、現在の私は思う。
だが、今になってもまだ、あの時の彼が、あんまり自信を持ってそう言い張っているので、少し祈りにも似た、すがるような気持ちで私は彼の言葉を思い出している。
【Books&Appsからのお知らせ】 今年最後のティネクト主催ウェビナーです。
(2025/10/27更新)
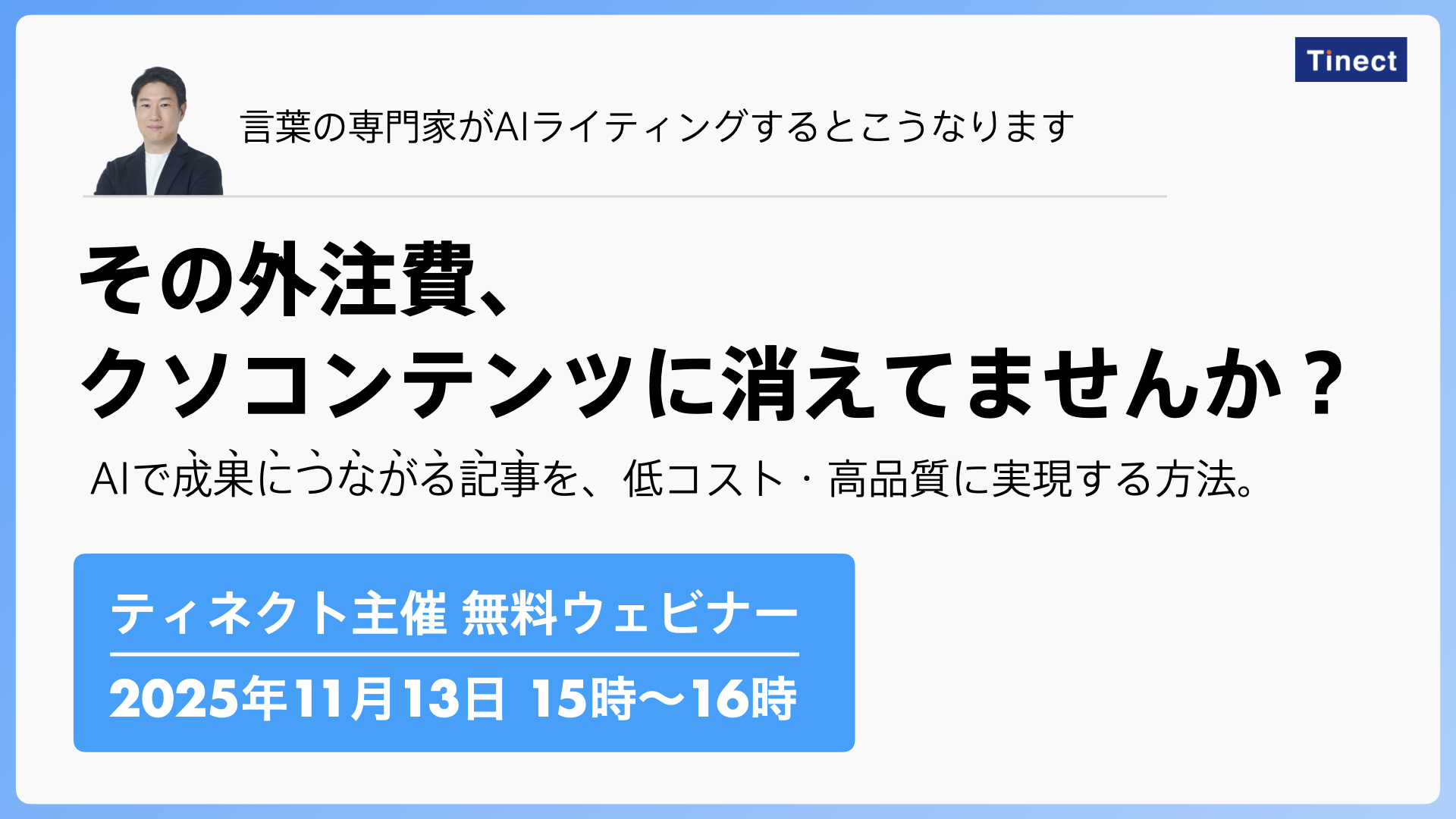
<2025年11月13日(木)実施予定>
その外注費、クソコンテンツに消えてませんか?
AIで“成果につながる記事”を、低コスト・高品質に実現する方法 —
【セミナー内容】
第1部:外注費の重さと、企業が抱える「記事制作の現実」
登壇者:倉増 京平(ティネクト 営業・マーケティング責任者)
・プロダクション・代理店が直面するコスト構造とリスク
・外注依存が招く“品質と費用”のジレンマ
第2部:いいライターが見つからない理由
登壇者:桃野 泰徳(ティネクト 編集責任者/取締役CFO)
・「書ける人」は全体の0.2%。採用・外注の限界とは
・品質管理を難しくしている構造的課題
第3部:AIで書ける時代へ
登壇者:安達 裕哉(ティネクト 代表取締役)
・生成AIで“成果につながる記事”を内製化する方法と成功事例
・AI×編集で再現性を高めるワークフロー構築
日時:
2025年11月13日(木)15:00〜16:00
参加費:無料(事前登録制)
配信形式:Zoomウェビナー
お申込み・詳細はこちらのティネクト公式ページよりご確認ください。
【プロフィール】
著者名:megamouth
文学、音楽活動、大学中退を経て、流れ流れてWeb業界に至った流浪のプログラマ。
ブログ:megamouthの葬列
(Photo:su.bo)







