入門経済思想史という本に非常に面白い事が書いてあった。
この本はアダム・スミスやマルクスといった経済学の巨匠達が、なぜあのような発想ができたのかを当時の背景等を加味しつつ説明する本なのだけど、初めに出てくる問いが非常に素晴らしい。
その問いはこうだ。
「なぜ経済学が初めて論じられたのは西暦1776年だったのだろうか?」
「もっというと、なんで1776年間もの長い間、人類は経済的発想を思いつけなかったのか?」
あなたはこの質問にどう答えるだろうか?
経済というのは、政治や宗教と密接に関連しており、それを取り出して語るのは反逆的な行為でもあった
よくよく考えてみるとアダム・スミス以前、1776年間もの長い間、経済的な考えが提唱されていなかったというのは不思議な話である。
何故、こんなにも経済学が生まれるのは遅れたのか?その問いに対する筆者の回答はこうだ。
「経済というのは、政治や宗教と密接に関連しており、それを取り出して語るのは反逆的な行為でもあったから」
これが実は私達の職場等で起きている事とも非常に関連が深いのである。
今日はこれを掘り下げていき、なぜ会社が時として合理的思考を捨て去ってしまうのかを解剖していこう。
乱世では規律を乱されると、みんなが困ってしまう
ある領主が収める土地があったとしよう。
そこでは、人々に与えられる仕事が領主の命令により決められていた。
ここに10人のパン屋がいたとしよう。
みんながみんな、決まった仕事をする分には、この土地では何も変わらない日常が続く。
ところがだ。もし、誰かが技術革新を成し遂げてしまったらどうだろうか?
具体例を出そう。パン屋Aが圧倒的に美味しいパンを、簡単に大量に作り出す事に成功したとしよう。
すると残り9人のパン屋はどうなるだろうか?
まあまず間違いなく仕事を失い、路頭に迷ってしまうだろう。
これは現代社会では普通の事である。
現代では競争や技術革新は良いものとされており、これらを成し遂げると基本的には皆から称賛される。
けど、それは現代社会がある種の余裕を持っているからに他ならない。
余裕のない社会においては競争や技術革新は、他人の仕事を奪い格差を生み出す悪しきものとされていた。
だからそんな事をしようものなら・・・密告され、領主に刑罰を与えられたのだという。
余裕なき社会では、豊かになれるかもしれない可能性以上に争いがなく、かつ領主への信仰心がキチッと保たれる事が何よりも大切
技術革新は長い目で見れば確かに豊かさを私達にもたらす。
けど、ミクロな観点でいえば平穏を著しく乱す事に繋がる。
余裕なき社会では、豊かになれるかもしれない可能性以上に、争いがなく、かつ領主への信仰心がキチッと保たれる事が何よりも大切なのだ。
仕事とは上から決められた事を、キチッとそのままやり通す事であり、それに違反し他人を出し抜く事をするだなんて、和を乱す行い以外の何物でもなかったのである。
このような環境下において、経済学なんていう全体を俯瞰するような視点を持つ事は不可能にも近い。
アダム・スミス以前は仕事なんてのは統治の手段であり、効率やらカイゼンなんてものからは酷く遠い世界の話だったのである。
資本主義社会のような競争が良しとされるようになったのは、本当に最近の事なのだ。
そしてこの古い考え方のエッセンスは、未だに私達の社会に強く根付いている。
その事を具体的なエピソードと共にみていこう。
なぜ理事長は医者に限られるのかと問うた、あるコメディカルの話
ある病院での出来事だ。
売上アップを目論み、各部署から所属長が集められ、意見を募られた時があった。
その時、あるコメディカルの方が
「理事長は経営センスがある人間がやるべきなのだから、そもそも医者だけしか理事長になれないのはおかしくないですか?」
「リハビリだろうが薬剤師だろうが、経営センスがいれば、その人が理事長になるべきではないでしょうか?」
というド・正論をぶつけたのである。
僕はこれに対して理事長を含む経営幹部がどう答えるのか、ドキドキしながら展開を見守っていたのだが、それに対する議長含む皆の回答はこうだった。
「そんな事を論じる意味がない。もっと現実的な事を考えなさい」
僕はこの回答を聞いておったまげたのだが、僕と質問したコメディカルの人以外は全員なんの疑問を持たなかったようで、この問いはそのまま黙殺され、会議は通常運転に戻った。
あの時はこの回答を全く理解できなかったのだが、今ならなぜ一笑に付されたのかがよくわかる。
病院は、冒頭のエピソードに書かれた領地みたいなものである。
理事長という権力者が全権を握るが故に、規律が保たれている。
だから理事長というトップに位置するのが院内ヒエラルキーが最上の医者であるという概念を壊す行いは、和を乱す行為以外の何物でもない。
医者≒偉いという病院内における政治・宗教問題に関するぶった切り行為は、ローマ皇帝に逆らうスパルタクスなみの反逆行為であり、そこに経済的な思考で疑問を投げかけるのは革命を仕掛けるような話だったのだ。
便利さや豊かさ、そして自由を求められるのは、封建制度を逸脱できる基盤が整った後である
「ここではこういう決まりになってるから」
僕はこの言葉が大嫌いだった。小学校の学級会や部活動、アルバイトなどで非効率的な箇所をみつける度に、全てを修正したくなっていた。
当時の僕は効率・最優先主義者という病に陥っていた。
全ての仕事は最もカンタンに、素早く成し遂げるべきである。
いまでもこの考えは僕の思想の基盤なのだけど、よくよく考えてみれば、この思想を展開できるのは、集団の規律が強固に保たれ、安全が保証された環境下という、非常に限られた条件が揃った時のみなのである。
会社では創業者一族や幹部候補生が偉く、病院では医者が偉いのは、未だにそれがないと職場の規律が保てないからだ。
だから下っ端候補生はいつまでたっても良い椅子には座れない。
合理的思考や経済効率なんかをいくら問うた所で、アダム・スミス以前の段階にある社会はびくともしない。
便利さや豊かさ、そして自由を求められるのは、封建制度を逸脱できる基盤が整った後だからである。
だからそれを求めるのなら、自分がいる場所がアダム・スミス以前の場所かアダム・スミス以降の場所なのかをキチッと見分けなくてはいけない。
あなたのいる場所は、果たしてどっちでしょうかね?
「AIを使いたい」ではなく、「業務を楽にしたい」が真の目的ではありませんか?
本セミナーは、経営層・部門責任者のために、生成AIを組織変革の武器にする方法をお伝えします。
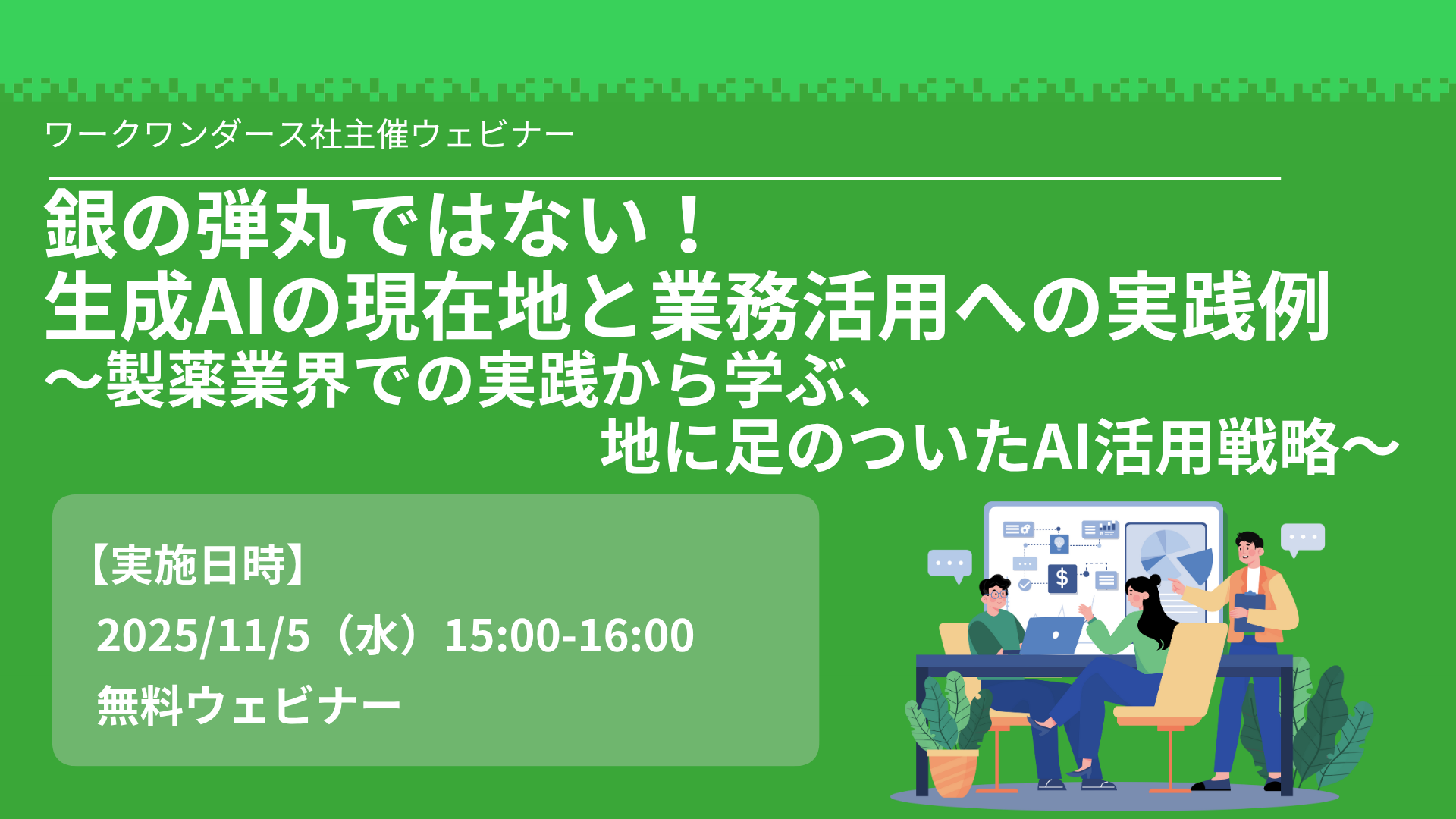
【開催概要】
・開催日:2025年11月5日(水)
・時間:15:00〜16:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員30名)
【対象者】
・情報システム部門の決裁者(部長〜役員クラス)
・DX推進部門の決裁者(部長〜役員クラス)
・生成AI活用の投資判断を行う立場の方
・組織のデジタル変革を推進する責任者
【セミナーの内容】
・生成AIの「過度な期待」と「現実」
- 「銀の弾丸」神話の実態
- 期待値のギャップが生む問題
- 生成AIの現在地と実力
・製薬業界での実践例:40名超のパイロットプロジェクト
- プロジェクトの背景と目的
- 個別業務ヒアリングで見えた現実
・期待:「なんでもできる魔法のツール」
・現実:業務特性による向き不向き
- 段階的な導入アプローチ
・期待値調整フェーズ/適用領域の選定/パイロット実施と効果測定
- 成功事例と失敗事例の詳細分析
・学びとノウハウ:地に足のついた活用戦略
- クライアントの真のニーズ(「AIを使いたい」ではなく「業務を楽にしたい」)と手段・目的の再定義
- 効果的な導入パターン/避けるべき落とし穴/組織的な成功要因
【登壇者】
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2025/10/30更新)
【プロフィール】
都内で勤務医としてまったり生活中。
趣味はおいしいレストラン開拓とワインと読書です。
twitter:takasuka_toki ブログ→ 珈琲をゴクゴク呑むように
noteで食事に関するコラム執筆と人生相談もやってます→ https://note.mu/takasuka_toki
(Photo:LinkedIn Sales Navigator)












