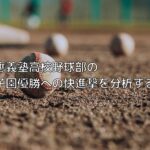第105回全国高校野球選手権大会は、慶應義塾高校の107年ぶりの日本一で幕を閉じた。
「長時間練習なし」など、従来の高校野球のイメージとは異なるユニークな指導方針も含めて今夏の大きな話題となったこの快進撃は、なぜ成し遂げられたのだろうか。ビジネスにおいて戦略を考える際などに使われる3Cのビジネスフレームワークを(多少の無理は承知だが、一種の頭の体操として)用いて、30年ほど前に慶應高校野球部員であった筆者の目線も交えつつ紐解いてみたい。
3C分析とは
3Cとは、事業戦略の構築において考慮すべき3つの要素である市場(Customers)・競合(Competitors)・自社(Company)を指し、それぞれの頭文字を取ったものである。これらはうまく統合すると、持続的な競争優位性を実現できるとされている。それぞれの要素について、慶應高校野球部にあてはめて整理してみよう。
<関連動画>3C分析 ~市場・競合・自社の分析から戦略を立案する~|グロービス学び放題
市場(Customers):市場の再定義
自身をより大きな市場の中に置きなおす
今回の慶應高校の躍進を市場という観点で振り返ると、その特徴は全国大会という「最大の市場を目指す」という「市場の再定義」と捉えることができる。
過去、慶應高校は神奈川県の4-5回戦あたりの壁をなかなか超えられない時期が続いた。当時の慶應高校にとっての市場は「神奈川県大会」であったと言っていいかもしれない。
そこから、日本一という目標を明確に掲げ、最大の市場である「全国大会=甲子園」を自校にとっての市場と捉え直したのである。市場を捉え直してからは、県内外の強豪校と練習試合を組むなどして、部員全員で本気で日本一を目指すという意識改革を長い年月をかけて進めてきた。
本当に大切なことに全力を注ぐ、そのための「考える力」を重視
また最大の市場を目指すことにとどまらず、高校野球という市場自体の再定義にチャレンジしてきたことも慶應高校の特徴である。
例えば、高校球児と言えば連想される坊主頭を髪型として指定する各校野球部も多い中、慶應高校はずっと前から髪型を自由としている。こうした「高校野球の常識を変える」さらには「高校野球の魅力や楽しさを伝える」などといった考え方は、「目標に照らし合わせて本当に大切なことに全力を注ごう」という考え方とまとめられるだろう。
が、それを実践していくには、選手個々人が色々な事象に対して自分で考えて納得することが必須である。だからこそ、慶應高校では自分で考えることを求め、それを楽しいと感じられる選手の育成に重きを置いてきたのである。
競合(Competitors):対戦相手への向き合い方
高い視座で各試合に臨む
前述のように、市場を全国大会、すなわち甲子園での日本一を目指すのであれば、当然常日頃からウォッチすべき競合や、それに応じた戦略も大きくも変わってくる。
この夏の慶應高校の監督や選手のコメント、起用法を見ていると、神奈川県大会の時点で、常に甲子園の決勝戦からバックキャスティングして綿密なプランニングを練ってきたことが明確に見て取れる。だからこそ、神奈川県大会で東海大相模、横浜という超強豪校を撃破した時点でも満足したり精根尽き果てたりすることなく、すぐに次の試合に向けての具体的な準備を進めることができた。
目標を共に追いかける同志としてリスペクトする
「市場の再定義」という大きな目標も掲げると、同じ市場でプレーする競合チームも状況によっては同志となりうる。
決勝で対戦した慶應と仙台育英は、選手の自主性を重んじるところや、監督の発信する言葉が共感を呼ぶなど、高校野球界に新たな風を運んだという点で非常に似たカラーの学校でもある。
髪型や応援といった側面はさておき、改めて純粋に選手の一挙手一投足に着目しながら決勝戦をじっくりと振り返ると、勝敗という概念を超えて、頂点を目指す試合をも楽しみ、相手をリスペクトする選手の姿から、高校野球という世界に改めて魅了されたファンも数多いはずである。
そんな2校の組み合わせだからこそ、市場全体をより魅力的に再定義することを実現した名勝負だったのではないだろうか。
自社:ビジョン・ミッション・バリューの浸透と組織のバランス
昨今の高校野球界の状況を踏まえると、甲子園の優勝に必要な要素(KSF:Key Success Factor)は、以下3つにまとめられそうだ。
- 日常から日本一を目指す高い意識の醸成
- データを駆使した自分たち及び相手チームの綿密な分析
- 猛暑の中での連戦に耐え得る体調管理や分厚い選手層の構築
ここまで見てきた市場・競合の2つの要素も踏まえ、慶應高校もこのKSFを抑えてきた。ただ最近、このあたりはどの強豪校も既に様々な工夫をしながら対処している。では、慶應高校はいかにして日本一という結果を残すことができたのだろうか?そのポイントとなるのが3つめの要素、「自社(Company)」である。
部訓の浸透による一体感
企業経営におけるミッション・ビジョン・バリューの重要性は言うまでもないが、慶應高校野球部には丁度これらに該当し得る「部訓」が存在する。「ミッション=高校野球の常識を変える」、「ビジョン=日本一になろう」、そして「バリュー=Enjoy Baseball」と捉えることができるかもしれない。ちなみに部訓の順序として1番目は「日本一になろう」で、2番目は「Enjoy Baseball」である。
この部訓は、筆者が在籍していた当時とほぼ変わっていない。時代に合わせて新しいやり方を取り入れつつも、根っこの拠り所となる指針は大切に拘り続けるという絶妙なバランスをとってきたことが、今回の躍進を大きく支えていたに違いない。
そして指針が素晴らしいとしても、それを実践し継承するのは簡単ではない。慶應高校でこれを支えているのが、野球部OBの学生コーチたちである。部員の特徴や部訓の意図を熟知しているコーチ陣が選手の育成に携わるという良き伝統が継承され続け、ミッション・ビジョン・バリューの浸透を支えていることも、慶應高校野球部の大きな強みである。
監督と選手のバランスのとれた関係
もうひとつ特筆すべきは、監督と選手の主従関係である。従来の高校野球は絶対的な主従関係のイメージが強いが、慶應高校では対等である。
自主性というと聞こえは良いが、そのバランスの取り方は非常に難しく、うまく機能しないと組織が空中分解しかねない。が、今年の慶應高校の監督や選手のコメントを見ると、指導者が信じて任せ、選手がその信頼に応えるべく自ら考え努力するという相互の絶妙なバランスが取れていたように感じる。ビジネスの世界でも、経営者やビジネスリーダーにとって「信じて任せる」ことは最もチャレンジングなテーマのひとつであるが、今回の慶應高校のやり方はひとつの成功例と言えるだろう。
野球というスポーツは部員全員で臨む団体競技でありつつも、いざ打席に立ちマウンドに上がると、1対1の個人競技の色彩が濃くなる。チーム全体で最大のパフォーマンスをあげられるよう、ミッション・ビジョン・バリューの浸透を起点として「組織力の高さ」を磨き上げるとともに、個々の選手の「高い意識の醸成」を同時に進めてきた。こうして、システマティックに日本一へ向けたto-doを一歩一歩積み上げてきたことが、今回の日本一に繋がったのである。
まとめ
2023年夏の慶應高校の躍進は、まさに市場・競合・自社のベストミックスの成し遂げた結果と言えるだろう。
「既存の市場の在り方を鵜呑みにせずに再定義する」
「市場に応じた競合を意識しつつも、時には競合を仲間として市場自体を育てる意識を持つ」
「ミッション・ビジョン・バリューは安易に変えることなく拘り続ける」
などは、企業運営にもそのまま通じるエッセンスである。 優勝を成し遂げて以来、慶應義塾関係者の盛り上がりが取り沙汰されることが多い。しかし慶應高校野球部の大躍進は、その枠を超えて、ビジネスの世界で奮闘する数多くのプロフェッショナルに向けても、とても意義深い示唆やポジティブな感情を与えてくれたと強く感じる。
(執筆:森 暁郎)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
日本で最も選ばれているビジネススクール、グロービス経営大学院(MBA)。
ヒト・モノ・カネをはじめ、テクノベートや経営・マネジメントなど、グロービスの現役・実務家教員がグロービス知見録に執筆したコンテンツを中心にお届けします。
Photo by:Mike Bowman