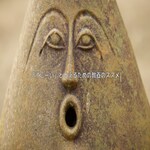『幡ケ谷バス停殺人事件』を覚えているだろうか。
2020年11月、渋谷区幡ケ谷のバス停で「ホームレス」の女性(以下Oさん)が男に殴られ死亡した事件だ。
この事件を知ったとき、なんともいえない嫌な感覚に襲われた。
殺されていたのは私だったかもしれないのだ。
私にも「明日からホームレスになるかもしれない」と覚悟した夜があった。
そのざわざわする感覚は、現役貧困女性として生きる今でも消えていない。
私は特別な人間じゃない。
最初は役所がどこにあるかも知らなかったし、今でも無知で世間知らずな人間だ。
そんな奴でもなんとか、ホームレスになる危機を回避できた。
そのことを知ってもらいたくてこの記事を書く。
(1)住まいを失いそうだが、どこを頼ればいいか分からない方
(2)路上生活・ネットカフェなどで過ごしている方
(3)上記のような人が身近にいる人
そんな方々に読んでもらえたらと思う。
「ホームレス」という言葉は暴力
Oさんのことは
「バス停で見かけ、心配していたがどうすればよいか分からなかった」
という町の人たちの声がNHKの取材で明らかになっている。
多くの人は自分や身近な人が困窮していたとしても、何をどうすれば良いか見当もつかない場合が多いだろう。
そんな時こそ貧困キャリアの私の出番ではないか。
私は野宿を覚悟した瞬間から、様々な制度のことを調べまくり、生活保護を申請した経験もある。
そのおかげで今では路上で寝泊まりすることなく最低限の生活を送れている。
Oさんは当時、メディアで「ホームレス」と呼ばれていた。
しかしこれは、本当に正しいのだろうか。
おそらく彼女は、コロナによる影響で失業したばかりだった。
バス停で夜を明かすようになったのは、失職の数か月後から。
「ホームレス」には見えない身なりを保っていたそうだ。
Oさんの学生のころからの夢は、声優かアナウンサーだった。
短大卒業後は結婚式場で司会として働くかたわら、教室にも通い、技術を磨き続けた。
劇団に所属し、ミュージカルや舞台に出演した。
海外旅行にも行った。
自立心が強い女性で「自分で会社を作りたい」とも話していたそうだ。
「ホームレス」という言葉には、Oさんが歩んできた歴史、人格や夢を丸ごとなかったことにする暴力性がある。
そんな言葉はOさんにふさわしくない。
あるいはこれは、いつぞやの夜に、私自身が誰かにかけてもらいたかった言葉かもしれない。
彼女は私だ
なぜそう思うのか、少し自分語りをさせて欲しい。
宿無し生活を覚悟した夜の少し前、私は失職した。
持病が悪化し、医師からは「就業不能」の診断が出て、転職できないことが判明した。
それを知った大家から強制退去を命じられた。
天涯孤独であること以外はつまづきもなく人生を歩んできた私は、社会についてあまりにも無知だった。
野宿する覚悟が必要な夜が来るとも、病気になるとも、失業するとさえ夢にも思っていなかったのだから。
誰よりも私自身の理解が追い付かなかった。
その時点からいろんなところに相談を開始した。
貧乏になった当初、私には「役所に相談に行く」発想が一切なかった。
「福祉事務所」という場所に至っては存在すら知らなかった。
貧乏になってから知ってものすごく驚いたのだけど、今の日本にはなんと、誰も路上で生活しなくて済む制度がすでに存在する。生活保護という制度だ。
日本の憲法には誰にでも健康で文化的な生活を送る権利がある、と書いてある。
つまり生活保護には誰でも申し込めるのだ!
こんな良い制度が存在するのに、なぜ路上生活者さんたちが存在するのか、不思議だった。それにはいくつか理由があると思う。
あくまでも個人的見解だが、理由の一つ目は、困っている人のための制度を、役所は絶対に宣伝しないから。
理由の二つ目は、福祉事務所を利用するにはちょっとしたコツが必要だから。
そのコツを、自分の経験を交えつつ、ここに書く。
詰む前に早く動いて欲しい
実はOさんが亡くなった「幡ケ谷原町」のバス停から渋谷63番のバスに乗れば、渋谷区役所にはほんの15分ほどで到着する。
とはいえ、渋谷63番のバスに乗るには230円必要で、Oさんの亡くなった時点の所持金は8円だった。
Oさんは支援の手が届くところにいた。
230円さえあれば、最悪の結果にならなくて済んだだろう―とは言い切れないのが今の社会だ。役所というところは一回行っただけではなかなか支援制度に申し込ませてはくれない。
これを「水際作戦」という。
私も「水際作戦」にあい、生活保護に申し込むまで役所に週一回ペースで数か月通った。
その度にかかる交通費には精神的にも肉体的にも苦しめられた。
貧乏すぎて食事も3日に1回くらいしか摂れなくなった頃ようやく役所に通い始めたので、いつもお腹が空いていて、毎回窓口に辿り着く前にぶっ倒れそうだった。
初めて役所の福祉課に行ったとき、厳しい顔をした窓口の人に
「困っているからといって『ハイそうですか』と助けることはできないんです。お金がもっと減ってから来てください」
と言われた。
「既に失職して来月の家賃を払うお金がないんです」
と言っても、答えは変わらなかった。
私が相談に来たということだけは記録に残してもらえたようだったけど、制度の説明は一切なかった。
不安な気持ちは鎮まることなく、私はすきっ腹を抱えて帰るしかなかった。
「お金がもっと減ってから来てください」
なんて言われたって、今よりお金がなければ交通費不足で役所を訪ねられない。
職員の言葉は矛盾だらけで、頭は混乱するばかりだった。
しばらく役所から足が遠のいた。
どうにもならず再度、窓口を訪れたとき
「なんでもっと早く来なかったんですか! 前回『また来てください』って言いましたよね?」
と、またまた怖い顔で怒られ、私は混乱と不安で目の前が真っ暗になった。
その時は知らなかったけれど、これは「水際作戦」とよばれる、役所の常套手段だったらしい。
混迷を極める今の時代、浪費できる時間など、我々にはもう残されていない。
迅速に支援に辿り着けるか否かが生死を分かつ時代だ。
そこで「水際作戦」を乗り越えるコツは、民間支援団体への相談だと思う。
頼ることは恥ではない
ここ数年、私が住んでいる地域では福祉がしょっぱくなった。それを肌で感じる。
福祉事務所の態度は、昔と桁違いに厳しい。
私が福祉課に初めて行った当時は、事前情報ゼロで窓口に行き、制度の理解もそこそこに、体当たりですべて乗り越えていく方式を取った。
相談も手続きも全て一人で行った。
しかし2024年現在、この方法は時代遅れだ。
無駄な時間がかかりすぎるし、相談者の肉体的・精神的な消耗が激しすぎる。
だからこそ、今、私と同じような境遇で苦しんでいる人に伝えたいことがある。
民間支援団体や役所への相談は、決して恥ではないということだ。
私が体当たりで数か月から数年かけて知ったことも、支援団体に聞けばものの数分でわかるかもしれない。
ただし、どの民間支援団体を信用するかについては慎重に選んで欲しい。
私には、どこの組織が良いなどと、安易なことは言えない。
なぜなら、中には「貧困者を食い物にする組織」もあるからだ。
今の時代、ネット上で口コミを含め、情報はいくらでもある。
大事なのは「だれかに頼るのは恥でない」と心得ることだ。
もう一度言いたい。
誰かに頼るのは、恥ずかしいことでもなんでもない。
どうか、まずは役所や福祉事務所に相談に行って欲しい。
役所や福祉事務所はハードルが高いならば、ネットで見かけた信頼できる支援団体に片っ端からあたってみて欲しい。
ホームレスになる前に、どうか動いて欲しい。
最後に
さて、自身の経験を基に書いてはみたけれど、気持ちはすっきりしない。
いつまでも消えない熾のように疑問がくすぶり続ける。
バス賃さえあれば、水際作戦を耐え抜きさえすれば、生活保護を受給さえすれば、やがて再就職さえできていれば―
Oさんは「助かって」いたのだろうか?
お金、生活、仕事、健康。人が抱える課題は有機的に繋がっている。
私もやりがちだが、その繋がりから切り離した状態で個々の課題にアプローチし、状況を解決した気になるのは危険だ。
そうしたアプローチは木を見て森を見ずであり、本質的解決にはならないことを、貧困と病気が私に教えてくれた。
群馬県桐生市が生活保護受給者に対し、ハローワークに行った日だけ保護費を1,000円ずつ支給していた事件などは、間違ったアプローチの良い例だろう。
必要なのは課題を俯瞰で見つめ、包括的な策を提案するシステムだと思う。
そうしたシステムが欠如する我々の社会では今もなお、Oさんのように困っている人々(私も含め)がごまんといる。
日本の生活保護は、必要とする人たちの20%から30%にしか行き渡っていない。
私は相談開始から生活保護受給までに時間がかかりすぎた。
現在路上生活ギリギリの状況にいる人たちには、そんなことが起こらないよう願いを込めてこの記事を書いた。
微力ではあるが、この記事が少しでも何かのお役に立てることを祈っている。
<文/大和彩>
Special thanks to Ms. M.Kobayashi
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【プロフィール】
大和彩
約10年前に失職したきっかけで持病が悪化、現在主治医に就労を禁止されている。働くことこそが私のアイデンティティであり、私から仕事を取ったら何も残らない、と10年前は思っていた。今現在でも一番辛いことは働けないことである。
失職して生活保護を申請した経験を基に『失職女子。(WAVE出版)』という本を書いた。
好きな食べ物はあったかいお茶とチョコレート。
Photo by:monsieuricon