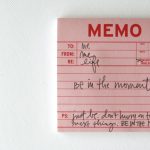学校の掛け算の採点で計算の順番が違うと減点される事例が話題になっている。
参考:掛算順序問題について親戚の現役教員に本音を聞いてみた。
インターネット上で定期的に話題にあがるこの問題だけど、事の本質は日本の雇用問題と大きく関連しており、実は根深い問題を内包している。この問題を理解する事は日本人の本質をつかむ上でも極めて大切だ。今日はその事について書こうと思う。
義務教育の本質は規則正しい生活とルールを守る事を叩き込むことにある
学校は毎日同じ時間に始まり同じ時間に終わる。教室には教師という絶対的権力者がおり、教師の決めたルールに従って全てが決定される。
こうしてみればわかるけど、学校は極めて管理された社会だ。ちょっとダルイから授業開始時間を30分遅らせてくれといったような融通は基本的にはきかない。毎日毎日、同じような生活リズムが絶対的統制者の元で繰り返し繰り返される。
子供はここで社会のルールを身に着ける。規則正しい生活リズムと、目上の者への隷従、ならびに仲間との適切な関係を築く事。これらはサラリーマン社会の基本的なルールとなっている。働いている皆さんなら十分承知の事だろう。
突然だけど、あなたは刑務所で受刑者がどのような生活をおくっているかご存じだろうか?実は刑務所生活は義務教育生活と非常に酷似している。
規則正しい生活リズムはいわずもがな、刑務所では様々なルールがあり、受刑者はそこで徹底的に”決まり”を守る事を叩き込まれる。当然、非合理だったり理不尽な事があるのだけど、”決まり”は”決まり”であり、それを守れない人間は処罰が与えられるようになっている。
昔読んだ刑務所本の中に受刑者100人へのアンケートという項目があった。そこに「刑務所に入って何が変わりましたか?」という質問があったのだけど、そこで最も多かったのが、”忍耐強くなった”という回答であった。
義務教育と刑務所での生活の類似点を考えると,おそらくだけど僕たちは義務教育を通過する過程で自分でも気が付かないぐらい”忍耐強く”なっているのだろう(そして日本の治安がいいのは,義務教育がうまい具合に国民を”忍耐強く”しているからなのじゃないかというのが僕の考察だ)
ルールはなんの為にあるのか?
刑務所は基本的には犯罪を行った人が入る場所である。普通に考えると社会のルールを守れない人達が多く集まるのだから、治安が悪くなりそうだけど基本的にはどこもそれなりに平穏に稼働している.
これは一見、当たり前の事にみえるけど実は凄い事だ。規律をしっかりと整備すれば,どんな人間を集めようが治安は整うのである。しっかりとした上下関係(看守と囚人)を元に、お上が決めたルールを囚人に順守させればその社会は整うのだ(人権は多少は損なわれるかもしれないけど)
学校もこれも全く同じである。義務教育期間の子供達は、どちらかというと自分を自分で律する事が苦手だ。自分を自分で律する事が苦手な人間が何十人も集まっている集団に、規律正しい生活をおくらせる為には、しっかりとした上下関係(教師と生徒)を元に、お上が決めたルールを遵守させる事が何よりも大切だ(多少の不合理がでるのは仕方がない)
この原則がキチンと適用されているからこそ,義務教育は成立しているのである.かけ算の順序問題は、この原理原則から漏れ出たものだ。学問的視点から考えれば、たしかに順序がどうであろうが何も問題はない。けど”教師の決めたルールを守っていない”という点から考えれば、あれは減点を食らったとしても何も文句はいえないのである。
だから学問的正しさを元にあの問題を議論するのは論点がそもそも違うのだ。”決まりですから”に”学問的正しさ”で議論をふっかけても、永遠に話は平行線のままなのだ。
教師よりも頭がいい子供の問題
とはいえ学問的正しさは真理であり、それをあまりにも蔑ろにするのも問題だというのは事実だ。
人は生まれながらにして平等ではない.あたりまえだけど,世の中には頭がいい人もいれば悪い人もいる.生まれながらにしてIQが80の人もいれば,IQが120の人もいる事ぐらい普通に生きている人ならだれでもわかるだろう。
ときどきだけど、教師よりも遥かに知恵がまわるタイプの子供がいる。僕の知人にIQが150以上とかいうとんでもない天才がいるのだけど、彼は「数学の問題文を読むと、解法より先に答えが大体わかる」と言っていた。
そんな人間なので、数学の難問を解かせると別解を3~4個は平気で思いつくのがザラだった(その多くが誰からも全く習ったこともないような方法ばかりだった)
諸外国ではそういう人間は、飛び級させて上の学年にサッサとあがらせている。学問的正しさが、規律と同じかそれ以上に評価されているからこそだろう。
けど日本では飛び級は原則的に禁止されている。何故か?それは日本社会が年功序列を元にした終身雇用により運用されているからに他ならない(飛び級や教師よりも頭がいい生徒の存在は、年功序列を根本的に揺るがしかねない存在である。クラスのリーダーである教師より、生徒がごく一部でも正しいだなんて事は学校という特殊空間ではあってはいけない)
こう書くと終身雇用制度と年功序列制度が悪者のようにみえてくるかもしれない。けど冒頭に書いたようにこの制度がしっかり稼働しているからこそ、日本の治安は驚くほど良いのである。
かけ算の順序問題は日本の治安の良さの裏返しだ。徹底した年功序列と、”決まりは決まりですから”という融通のきかない生活は一見よくないものにみえる。けど、そこから生み出された”私達の忍耐強さ”が日本の社会を住みやすくしてくれているのだ。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
プロフィール
都内で勤務医としてまったり生活中。
趣味はおいしいレストラン開拓とワインと読書です。
twitter:takasuka_toki ブログ→ 珈琲をゴクゴク呑むように
noteで食事に関するコラム執筆と人生相談もやってます→ https://note.mu/takasuka_toki