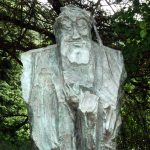いきなり古臭いインターネットミームで恐縮なのだが、なぜ童貞と処女とに価値の差があるのかを孔子が弟子に説く、というネタがある。曰く、
弟子「先生、処女を貴重だと思う男は多いです」
孔子「その通りだ」
弟子「しかし逆に童貞は女に気持ち悪がられます」
孔子「確かに」
弟子「おかしいじゃないですか、何故このような意識の違いが生まれるのですか」
孔子「それは一度も侵入を許していない砦は頼もしく、一度も侵入に成功したことがない兵士は頼りないからだ」
なるほどな、と笑わせる説話である。
だが、笑ったあなたは今後議論の場において比喩(たとえ話)を使うべきではない。
また、相手が比喩を使うことも拒否すべきだ。
なぜか。
今日はただそれだけの話をしたいので、まあ暇ならちょっと聞いていってくれ。
その比喩は、適切か
冒頭の比喩がなぜダメなのか。
結論から言うと、論点を先取りしているからである。
問題点がわかりやすくなるよう、弟子(Q)と孔子(A)の趣旨を単純化する。
Q.「処女が男に評価され、逆に童貞は女に評価されないのは何故か?」
A.「一度も侵入を許していない砦は評価され、一度も侵入に成功したことがない兵士は評価されないのと同じである」
はて。いつ”同じ”になったのだ?
これではまだ納得できない。この”同じ”には説明が要るはずだ。何がどう同じなのか?
ここでAによる解説として考えうるものはこうだろう。
A.「侵入されるべきでないという意味で女と砦は同じである。また、男と兵士はともに、攻めるべき相手を持つ立場である」
なるほどなるほど……いや待ってくれ。
Qが聞きたいのは「女が侵入を許すべきではないとされるのは何故なのか」である。
それに対しAが言っているのはこうだ。
「処女が男に評価されるのは、彼女が処女だ(一度も侵入されていない)からだ」
これは何か。同語反復である。
男と兵士についても構造は同じだ。
「童貞がダメなのは、一度も対象を攻め落としたことがないからである」。
だが、問われていたのは「なぜ女性経験がない男はマイナス評価を受けるのか、すなわち、何故男は攻め落とすことを良しとされるのか」だったはずだ。
Qはそれをおかしいと思ったから問うたのだ。
童貞で何が悪いんだ。別に女になんて興味ねーし。ていうか本気出してないだけだし。そもそも俺は女なんかより男の友情を大事にしているんだ。あるいは別にどっちでもいいんだ、だって僕たち私たち、いずれ皆この光陰を超えて等しく無に還るだけなのだもの……。
それに対しAは「童貞は童貞だからダメなんだ」と言っているだけである。
これは、答えになっていない。
*
砦と兵士の比喩を持ち出したとき、孔子の頭の中には処女と童貞に関する評価基準が先行している(でないとこの比喩が出てこない)。
だから、実は孔子は説明をするつもりで、ただ単に主張に合う喩えを、証明すべき当のものを内包した命題を引っ張ってきてしまったわけだ。
これが論点先取である。
そして冒頭でなるほどなと笑った「あなた」は、なぜこの取り違えに気付かず笑ってしまったのか。
実は、孔子と同じ評価基準を「あなた」も共有しているからである。
ここで孔子と「あなた」との間には、ひっそりと共犯関係が成立している。
同じ信念を抱いているから、「あなた」は説明になっていない説明を黙認したのである。
エコーチェンバーに陥らないためには、この共犯関係を自覚しなければならない。
不毛な論争
かつて、女性専用車両は是か非かというテーマで、Twitter上で論争したことがある(もちろん誰にだって捨て去りたい過去はある)。
論争相手は女性専用車両は撤廃すべきだと主張していた。
その理由は「男女差別だから」である。
議論の要点は下記のとおり。
A(相手)-1「同じ料金を払っているのに女性だけが乗れて男が使えない車両があるのはおかしい。差別である」
B(俺)-1「そこで制限される利益はごく小さい一方で、その車両設定がもたらすメリットははるかに大きい。だから認められるべきだ」
A-2「例えばバイキングで同じ料金を払っているのに男だけ食べられない料理があったらおかしいだろう。女だけアイスクリームを食べられると言われたら普通腹が立つはずだ」
B-2「1号車と2号車との間には、カレーとアイスクリームとの間にあるのと同じだけの質的差異があるか? あるわけがない。その喩えに乗るとすれば、正しくは同じアイスクリームが8個なり10個並んだ容器に入っており、最後の容器は女性しか食べられない、だろう。しかもその環境では、女性が他の容器からアイスを取ろうとすると、潜在的に性的侵害を被るリスクを負うことになるのである」
A-3「いやそれはおかしい。1号車と2号車との間にはどちらが改札に近いかという大きな質的差異がある。私は少しでも改札に近い車両に乗る権利を不当に奪われている(……)」
……当時もバカバカしかったが、やはり今回も書いていてバカバカしくなってきた。
要約してこれである。
何故俺はあんな無駄な時間を……。
そしてこれが問題なのだが、見てわかるとおり、手間をかけている割に議論は1ミリも深まっていない。
両者のすれ違いのポイントは、複数の価値基準を認めているか否かにある。
Aはいわば同一料金同一サービスを求めている。そこに関してAの理屈に誤りは無い。
だがBは、配慮すべき基準はそれだけではないとしている。
一部の男性らが一つ隣の車両に移動を強いられる、単にそれだけの不利益を拒否するために、切実なニーズのある女性専用車両を廃止せよというのは収支が合わないのではないか。
本来議論すべきはその差異なのだ。
だが、比喩が始まった途端、AとBは本題を放り出してどっちが上手いこと言えるか競争に取り組んでしまう(A-2、B-2)。
だがそこから辿り着いたのはA-3である。仮にA-2、B-2を削除しても大意に変化はない。
両者がそれぞれ信ずる社会正義の実現のため画面にかじりつき、懸命に打ち込んだ時間と文字列は全てムダである。
何故比喩を使った説得は徒労に終わるのか?
比喩とは、ある物事と他の共通点を見出し換言することで何らかの効果を狙うレトリックだが、主張の異なる二者間では、多くの場合そもそも議題となっている物事の評価が異なる(だからこそ主張が異なってくる)。
説得される方にとって、そこに比喩の成立に足る共通性はない。
Bが行うべきだったのは、Aが比喩を持ち出した瞬間にそれを拒絶することだ。
問うべき問いを等閑視しようとする共犯関係は拒否しなければならない。
もっと言えば、意見の異なる相手との議論に喩え話を持ち出す者は、「その喩えが適切か」という問題を増やしているだけなのだ。
そのことに気付かない時点で話にならないのである。
その比喩って「君にも分かりやすく噛み砕いてあげるね」ってこと?
喩え話に付き合うべきでない理由はもう一つあり、同じく比喩の性質に関わるものだ。
上で「比喩とは、ある物事と他の共通点を見出し、換言することで何らかの効果を狙うレトリック」と言った。
だが、実際のところ、議論のシーンでその多くは単純化のために用いられている。
ある物事について、目下の議論のポイントとなる点で共通する別の何かに喩えることで、話を分かりやすくしよう、というわけだ。
つまるところこうだ。
「君には情報量が多すぎて今の議論のポイントが理解できないようなので、私が余計な情報を剥がして、この話の本質が見えるようにしてあげるね」。
クソくらえである。
たまにマジであなた/私がバカでよく分かっていなかったパターンもあるのだがそんなことはどうでもいい。
比喩でこちらを説得しようと試みる相手は、例外なくあなた/私を舐めているのである。
そんな相手に付き合う義理はない。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【プロフィール】
著者:dudihan
文教市場ではたらく妻子持ち30代サラリーマン。
福岡県出身。
(Photo:Nigel Brown)