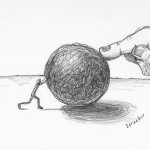事件記者時代、懇意にしてくれた捜査員が何人かいた。
そのうちのひとりが実に思い出深い。
よく一緒に飲みに行ったが、その方法も独特だった。
警察官や刑事なんて、みんな似たような公務員気質なんじゃないか?と思う方もおられるかもしれないが、そんなことはない。
あんなに人間臭さに溢れた役所も珍しいかもしれないと、いま思う。
事件記者にとって最も価値があるのは「紙」
事件記者に必要なスキルは、公表前、あるいは公表するものではなく捜査員だけが知る情報を、どの記者よりも早く正確に手に入れてくることである。
そう教わったし、そう思っていた。
情報は「夜討ち朝駆け」の立ち話で手に入れることもあるし、
懇意にしている捜査員から直接電話を受けて手に入れるということもある。
しかし、一番ありがたいのは「紙」の形で受け取ることである。
何の「紙」かというと、
発表「予定」の広報文書。「いつ発表するか」が事前に決まっている事件は多い。
もっと直接的なのは、捜査員が共有している「チャート」。
事件の全容がまさにチャート状に書かれており、そこには容疑者の住所氏名、被害者の住所氏名、それぞれの関係性、家宅捜索先と日時など、ありとあらゆる情報が詰まっているのである。
もうひとつ、意外にも重要、いやこれが取材の本質に欠かせない「紙」がある。
そもそも、記者がなぜ捜査員の自宅に押しかけることができるのか?
不思議に思った方はいないだろうか。
実は記者は、捜査員の「名簿」を手に入れているのである。
個人情報もいいところである。
しかしこれがなければ、幹部でない、現場のナマの捜査員との接点は持てない。
唯一手に入れたことがある紙
ただ、「紙」を手に入れるには相当な敏腕あるいは密な捜査員との関係が必要である。
というのも、形に残らない「その場での会話」とは違い、機密文書を業務に関係のない目的でコピーし、記者に「ブツ」を渡すわけだ。
万が一、その記者が「紙」をどこかに置き忘れたり落としたりしたら?
個人情報、捜査情報の塊である。他の省庁の広報文とはちょっと訳が違う。
当然、「誰が漏らしたのか」という犯人探しも庁内で始まる。
モノによっては、当該の警察官は懲戒の対象だ。
筆者は在職中、その「紙」を手に入れたことはほとんどなかった。
「ここで見せるから、全部メモしていっていいよ。」
ということはたびたびあったが、コピーという「ブツ」をそのままもらう腕はなかった。
すごい先輩になると、記者クラブから電話をし、FAXで送ってもらうという姿を目にしたことがある。
一歩も外に出ないまま、全ての情報が詰まった「紙」を手に入れるのである。
しかも、向こうから送られてくるのである。
「紙」を手に入れることへの憧れが増していく。
そんな中、筆者が在任中に一度だけ、捜査員から「紙」をもらったことがある。
二日酔いという仕事が慰労される世界
相手は、わたしの前任者からの引き継ぎで紹介された捜査員だ。
「人脈の引き継ぎ」というのは、毎回うまくいくとは限らない。その記者だから懇意にしていたのであってお前のことは知らん、という捜査員も多い。
しかし、彼はわたしのことも受け入れてくれる人だった。
そして、記者にとってありがたいのは、捜査員と飲む夜である。
通常、何もなければ夜回りに行かなければならない。
時間ばかりかかって実るか実らないかわからないような夜回りよりも、酒でも飲んでいるほうがそりゃあ楽である。
かつ「捜査員との関係維持のために一緒に酒を飲む」というのは免罪符にもなる。
とはいえ警察官には、酒に強い人が多い。いわゆる「ガチの体育会系」の世界なので、とことんまで付き合う覚悟が必要であり、二日酔いと寝不足は免れない。
でも、捜査員を待って夜の住宅地に立ち続けるよりマシだし、「飲みすぎて二日酔いです」というのが、堂々と昼寝をする理由として成立するのだ。
わたしもよく、記者クラブの共同スペースのソファで爆睡していた。
20代の女子が公衆の面前で何をやっているんだ、と思われようが何しようが、睡眠に勝る本能的欲求はない。
そして、飲んだとなれば多少の遅刻も許されてしまう。
むしろ「お疲れさん」と言われる。
奇妙な職場である。
きょうは北?南?
さて、その捜査員とは、時折一緒に飲みに行く仲になった。
彼との待ち合わせは、面白いものだった。
「清水さん、きょうは北にしますかね?」「きょうは南で大丈夫ですかね?」
という、互いにだけわかる隠語で場所を決めていた。
丁寧語を欠かさないところも個性的だった。
場所はそうやって打ち合わせるとして、しかし合流してしまえば普通に隣り合って飲んでいた。
多くの記者はそうだろう。
しかし、大事なことがある。
「あなたと今こうやって飲んでいるのは夜回りよりも楽だし、うまくすれば情報もらえるかもしれないと思ってるからです」
という態度はよろしくない。
というのも、公務員の情報漏洩は違法である。
それでも、あくまで「人」として意気投合しているから、多少のリスクを背負ってでも懇意の捜査員という人たちは捜査情報を提供してくれているのだ。
だから、情報を求めてがっつくのは違う。
捜査員の側が「教えたくて仕方ない」というのではない限り、そんな態度を1ミリでも見せるのは失礼極まりないことなのだ。
よって、飲んでいれば当然事件の話が出ても、その場でメモを取るわけにはいかないとわたしは考えていた。
捜査員だって、仕事終わりの一杯なのだ。プライベートの空間なのである。
事件の話が出てきたとしても、それはあくまで会話の延長であって、それが目的ではないはずだ。
しかし、「すごい先輩」の結果の部分だけに目が行っていた駆け出し記者のわたしには、そこまでの余裕はなかった。
時折トイレに行き、話の内容を覚えているうちに携帯電話のメール機能に吐き出して「下書き保存」し、メモがわりにしていた。
しかし、それを数回やった段階で気がついた。
そんなせこいことをしても、大概がなんの役にも立たないのである。
そもそも酔っ払っているから全てが雑になる。
そして、せこいことを考えている時ほど、なんの成果にもならないものだ。急いては事を仕損じる、ということだろう。
「席を空けて座って」。
さて、ある日。
その捜査員との待ち合わせは「南」だった。
ただ、いつもと彼の様子が少し違っていた。
「美味い焼き鳥屋なんですよね。で、僕は◯時◯分には店にいるから、遅れて入ってきて、1席空けて座ってね」
と言う。
はじめてそんな細かい指示を受けた。
その通りにした。彼は電話の通り、ひとりでカウンターに座っていた。
そして、間隔をおいて座ったわたし。
側から見れば完全に他人同士である。
1人で来た客同士、なんとなくその場の雰囲気で挨拶を交わしている程度にしか見えない。
その程度で、それ以上は会話もしない。
そんなの、カウンターがメインの飲み屋ではよくある光景だ。
そして。
彼は合間を見て、内ポケットから小さく折りたたんだ紙を取り出し、そっとわたしに手渡した。
そして、
「いやー、来週くらいのことなんですけどねえ」。
視線を空にやって、誰に話しかけるでもない独り言のように、彼はつぶやいた。
わたしはその紙をそのままスーツの内ポケットに入れた。
その場所で開いて内容を見ることもしなければ、何の言葉を発することもしなかった。
むしろたまたま居合わせた客のような態度で時折会話し、なんなら
「本当に」たまたま居合わせた客とも、テレビを見ながらどうでもいい会話をした。
渡されたものがどんな類のものであるか、想像がつくからである。
そしてまた、おのおの勝手にやってきて自分のペースで帰っていくすれ違いの他人のように、別々に店を出たまま、その後合流するということもなかった。
家に帰って紙を開いた。
翌週の日付が打たれた広報文書だった。
どちらが「マトモ」なのか
ガタイの良い禿げ頭の、豪快でねじり鉢巻が似合いそうなおっちゃん。
そんな風貌の彼は管理職の立場にあったので、多くの情報を持っている。
しかし、正直に言えば、その時手渡された紙の内容は、大事件とかではなかった。
毎日発表されるような「小ネタ」の域を出ないものだったし、
こういう特別な形で知るという経緯がなければ、特段ニュースにもしないであろう「よくある摘発」のひとつだった。
ただ、
「なんだ、この程度の内容の紙か〜」。
そう思いかけた自分を大きく恥じた。
ひたすら「紙を手に入れてくる記者こそ優秀」というイメージを植え付けられていた自分にはっとした。
もちろん、わたしはその捜査員に、なんでもいいから紙というものを手に入れてみたい、などと言ったことはない。
しかし、懇意にしている若い記者が苦戦しているのを目の前にして、少しでも役に立てればと思ってくれた捜査員の行動、それにあたって最大限警戒するというほうが、実はまともな感覚の持ち主なのだ。
「記者という生き物が好き」という捜査員は割とよくいる。
自分が携わった事件が報道されるのは自分や部下たちにとって励みになる、という理由もあって記者との付き合いがうまい捜査員もいる。
わたしたちはそこから風穴を開け情報を吸い取っていくのだが、振り返ればその考え方そのものも少し違う気がしてきた。
行為が間違いなのではなく、考え方の問題だ。
記者が「他社を出し抜きたい」というだけ、
捜査員が「自分達の仕事を大きく取り上げてもらいたい」というだけ、
それは違うんじゃないかということである。
もちろんそこで両者の利害が一致して関係は成り立つし、事件を潰さない範囲で、犯罪の摘発が詳細に大きくニュースになることは悪いことではない。
しかし、それだけを目的にした情報のやりとりや報道が常態化してしまうと、互いに「一般視聴者」から遠ざかってしまう。
互いにリスクを負っている。
捜査員は、情報漏洩というリスク。
記者は、情報源の秘匿を守り抜くというリスク。
自分の「ネタモト」を、その匂いまで残すことなくひた隠しにするには手間と神経を消費する。
記者が持っている情報というのは多ければ多いほど良いというのは間違いないが、そこまで体力気力を削いでまでやることかどうか、どこかしら無駄があるのでは?というかなんというか。
ただ、これが互いに強い思想を持ってのことならば話は別だ。
「馴れ合い」ではマスコミは変わらない
アメリカの歴史的な汚職「ウォーターゲート事件」を題材にした「大統領の陰謀」という映画がある。
事件を必死に追うワシントン・ポスト紙の若き記者は、謎の人物「ディープ・スロート(Deep Throat)」と会うようになり、そのディープ・スロートから「カネの流れを追え」というアドバイスを受ける。
そして事件の真相が明らかになっていく、そんな半ドキュメンタリー映画である。
この「ディープ・スロート」が当時のFBI副長官であったことは後に世に知られることとなるが、この映画での彼の振る舞いは印象的だ。
「ディープ・スロート」は記者の前に気まぐれに見えるように現れる。
かつ、彼は「ただ情報を与えるだけ」の存在ではない。
記者の問いに対し、時々ヒントを与えつつも「自分で見つけろ」「まだ分からないのか」「全体を見失うな」と、「考える」ことも促すのだ。
そして、気まぐれに姿を消していく。
「新聞は全てが浅はかで嫌いだ」とも語りつつ。
記者たちは駆け回り、関係者とギリギリの駆け引きをしながら書いた記事が袋叩きされるようなことも続いた。
なぜなら記者たちが迫っていた真実はすべてもみ消され続けていたのである。
それでも彼らは諦めなかった。
その姿を見守っていたディープ・スロートは、ようやく「君たちの命も危険だ」という警告と共に全てを明らかにした。
なにもここまでの「命のやりとり」でない限り機密情報を扱うべきではない、と言いたいわけではない。
しかし、わたしがやっていたことも、根本は同じである。
その重みの欠片もないような「情報提供者と取材者の利害の一致」をどれだけ披露しても、それは作り物にすぎない。
実際そうやって今のマスコミは時折、「リーク」と「スクープ」を履き違えている。
情報を与える方が自分に都合の良い側面だけを切って渡す「リーク」に飛びつき、検証もしないままに世にそれが垂れ流される。
「偏向報道」が生まれる土壌である。
わたしが唯一手に入れた「一枚の紙」は、世間からすればほんの小さな出来事をメモにしただけのようなものに過ぎないかもしれない。
しかしこうやって振り返ると、その一枚に込められた彼の思いは、わたしにとっては生涯に出会うかどうか分からないくらいの大きな意味を持っている。
ことの大小ではなく、そこに込められた、生真面目すぎる彼の「覚悟」を感じるからだ。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【プロフィール】
著者:清水 沙矢香
北九州市出身。京都大学理学部卒業後、TBSでおもに報道記者として社会部・経済部で勤務、その後フリー。
かたわらでサックスプレイヤー。バンドや自ら率いるユニット、ソロなどで活動。ほかには酒と横浜DeNAベイスターズが好き。
Twitter:@M6Sayaka
Facebook:https://www.facebook.com/shimizu.sayaka/
Photo:Diana Polekhina