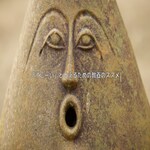こんにちは、しんざきです。
なんだか、「涼しい」を通りこしていきなり寒くなってきましたね。
最近は、春キャンセル夏とか秋キャンセル冬とか、横暴なコンボを押しつけていく戦術が流行っているんでしょうか。バランス調整でナーフして欲しい。
たいしたことではないんですが、長男から聞いた体育祭での話がちょっと面白かったので書かせてください。
書きたいことは大体以下の通りです。
・長男が体育祭で騎馬戦に参加しました
・長男のクラスでは、「敵チームを突出させておいて、一部の騎馬が左右に回り込み、側面や背面から殲滅する」という作戦を考えたそうです
・実際やってみると、部隊展開にまごついてる間に相手の勢いで正面突破されてわやくちゃになってさっぱりうまくいかなかったそうです
・みんなで作戦を話し合って実践するのも、それに失敗するのもとても良い経験ですよね
・「机上で計画するのと実行するのは大違い」とか「何事も、実行するには練度が必要」といったことを学べたのも良かったと思います
・総括しての長男の感想が「ナポレオンやハンニバルって凄いんだなと思った」だったのが、「そうですよね」以外いいようがなくて面白かったです
・色んなことから学びを得ていってくれるといいなーと思います
以上です。よろしくお願いします。
ということで、書きたいことは最初に全部書いてしまったので、後はざっくばらんにいきましょう。
先日、長男の学校の体育祭がありました。長男は男子校に通っていまして、勝負ごとが好きな男子生徒同士、勝ち負けがつく競技もそこそこ盛り上がるようです。長男自身は騎馬戦に参加していました。楽しいですよね、騎馬戦。
で、長男のクラスでは、どうも軍師的な立ち位置の子がいたらしく、「相手が突っ込んできたところを、横や後ろから挟みこむように全体で誘導したら楽に勝てるのでは?」と思いついて、そう提案したらしいんですね。
で、クラス内で話し合って回り込む部隊の割り振りや動き方について相談して、いざ実際に本番、ということになったと。
長男の話によると、その作戦の概要はざっくり下記のようなものだったそうです。
・各騎馬を、大きく「右方面担当」「左方面担当」「正面担当」の三つのチームに分ける
・正面チームは大きく前に出ないで、相手の騎馬を受け止めつつ左右チームの動きを援護する
・右チームと左チームはそれぞれ迂回して相手の側面、あるいは背面に回り込む
・敵チームの騎馬を挟み込んで撃破する
いわゆる包囲殲滅戦、カンナエの戦いでハンニバルがやってたようなヤツですね。
世界史の授業でもローマ史を勉強していたので、そこからとってきたのかも知れません。皆で戦術考えるの超楽しかったろうなー。陣形作るとか遊撃部隊作るとか、やったやった、私も昔やった。
まあ最初に書いた通り、結果だけ書くとこの作戦は大失敗で、勢いでひたすら押してくる相手に全く対抗出来ず全体が瓦解、長男のクラスは大敗してしまったようなのですが。
夕食の後に長男と議論したのですが、恐らく失敗の要因は、
・騎馬戦の練習時間がろくにとれず、動き方がちゃんと頭に入っていなかった
・フィールドの見晴らしがよく、各チームの動きが相手から丸見えだった
・そもそもフィールドの横幅が十分ではなく、左右チームも敵チームの動きに巻き込まれてしまった
・こちらが展開しようとまごついていた分、単純に敵チームの勢いが強く正面があっさり当たり負けてしまった
などの要素だろうと長男は考えているようです。妥当な分析だと思います。
で、全体を総括しての長男の感想が「ナポレオンやハンニバルって凄いんだなと思った」でして、こんな身近なイベントからハンニバルに繋げるのスケールでかいなと思いつつ、そうだよねあの人たち色々とんでもないよね、と思わず盛り上がってしまったわけなのです。面白かったです。
もちろん騎馬戦の勝ち負けは決して馬鹿にした話ではなく、本人たちにとっては大きな問題だったと思うのですが、親としては「勝ち負けはともかく、長男いい経験したなー」と思っていまして。
長男このイベントで、
・チームで話し合って計画を策定し、実行するという経験
・「計画と実践の間には大きな隔たりがある」という事実
・「練度不足だとそもそも計画通りに実行出来ない」という知見
・計画がうまくいかなかった時のリスク管理、プランBの重要性
・派手な事績の裏には無数の失敗がある、むしろ無数の失敗があるからこそ一部の事績が記憶に残るのだ、という認識
定着するかはともかく、これくらいの知見は得られたんじゃないかと思うんですよ。
まず、上手くいくいかないに関係なく、「ちゃんと話し合ってプランを立てた」ということ自体が既にエラい。
体育祭なんて生徒によってモチベーションの傾斜もあるでしょうし、別に負けたからって成績に響くわけでもありません。無難に進めるなら作戦なんて考える必要もなし、出たとこ勝負で十分でしょう。
そんなイベントにも真剣に向き合い、曲がりなりにもクラス総勢の合意をとって、「全体の作戦」として成立させたこと自体が一つの成果です。クラス仲良さそう。
で、「立てた計画が上手くいかなかった」というのも、経験値としては大変貴重です。
人間、学びや知見は失敗体験からこそ得られるものです。失敗してこそ「何故失敗したのか」ということを振り返ることが出来るし、失敗要因を検討してこそ知見になる。
今回の場合、恐らく「練習不足で複雑な動きが出来なかった」ことが最大の失敗要因ではないかと思いはするのですが、フィールドの狭さなんかも実際やってみないと分からないところで、「考えるのとやってみるのでは大違い」というのも貴重な知見です。
いざ自分たちでフィールドに立ってみれば、状況も把握出来ないし彼我の位置関係もよく分からず、どう動けばいいかさっぱり分からなくて大混乱、なんてことにもなったでしょう。
「実際にやってみた時どうなるか、可能な限り具体的に想定する」というのは、どんな場面、どんな計画でも重要な考え方です。
で、「上手くいかなかった時どうするか」を事前に考えておくのが重要、というのも、計画が失敗した時に得られる大事な知見の一つです。いわゆるプランBってやつですよね。
「あ、ダメそう」と思ったらその時点で作戦を破棄することも時には必要で、それによってリカバリが出来る場合もあるのですが、「誰がどう失敗を判断して、どうやってプランBへの切り替えを指示するのか」というのもとても大事です。
事前にリスクを想定しておいて、そのリスクが顕在化した時にどう対応するかって、考え方としてはとても重要ですよね。まあ、体育祭の騎馬戦でそんな判断が出来るかどうかはともかくとして。
それはそうと、今回長男ははからずもハンニバルやナポレオンの名前を出したわけで、もちろんあの人たちは色々とんでもない手腕の持ち主なわけですが、「難しいことを達成したからこそ歴史に名が残っている」「実際には記憶にも残らない失敗例の方がずっと多いし、成功譚にしても失敗と紙一重だったりする」というのは、それはそれで重要な認識だと思います。
輝かしい成功例を、単に輝かしいからというだけで表面的に真似しても、実際聞くとやるでは大違いで、実行の際には入念な準備と実行力が必要になる。それも、史上の出来事と彼我を比べての失敗体験から得られる知見ではないかと考えるわけです。
もちろん、上記のような話は飽くまで「そういう知見を引き出すことも出来る」という話であって、体験としては「楽しかった」「悔しかった」だけでも十分です。
とはいえ、折角なら色んな経験を積んで、将来の自分の糧にしていってくれるといいなあと、親としてはそんな風に考え、子どもたちにも色々話している次第なのです。
今日書きたいことはそれくらいです。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
著者名:しんざき
SE、ケーナ奏者、キャベツ太郎ソムリエ。三児の父。
レトロゲームブログ「不倒城」を2004年に開設。以下、レトロゲーム、漫画、駄菓子、育児、ダライアス外伝などについて書き綴る日々を送る。好きな敵ボスはシャコ。
ブログ:不倒城
Photo:Nori Norisa