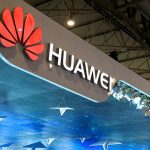“忙しくなければならない症候群”
ググってみても出てこなかった。既に誰かが言っていても不思議ではない言葉だが、そうでもないらしい。
これは文字通り、常に「忙しくなければならない」と思ってしまう人たちのことだ。575のリズムで言いやすいから私はこう呼んでいる。
忙しいことは素晴らしい。
忙しさは充実度の高さの表れである。
暇な時間があるなんて、もったいない。
そんな思いを持っている人たちが確かに存在する。
「何が悪いのか」と思うかもしれない。
そう、悪くはない。スケジュールがビッシリ埋まっていることに心から満足しているのなら、それは幸せなことだろうと思う。それに、充実した時間を過ごしたいという思いは多くの人が持っていると思う。
それをあえて“症候群”と表現しているのは、“忙しくなければならない”というある種の強迫観念が心にあり、忙しくないと不安になってしまうからだ。
私も中学生の頃から患っている。高校生までは勉強していない時間が不安だった。家族や友人とのんびりお話する時間や、移動時間、電車の待ち時間が不安だった。食事に行って料理が出てくるまでの時間さえも不安だった。
「この時間に勉強しなくてもいいのだろうか」という不安が消えないのである。
大学生になり、この不安はなくなったような気がしていた。でも、それは幻想だった。好きなだけ眠ることができる幸せ、のんびりできる幸せを噛み締めていたのだが、不安な気持ちは消えていなかった。
「私はこんな時間の過ごし方をしていていいのだろうか」という不安が常に心の中にあって、消そうとしても消えないのである。
なぜ自分だけこんなに不安な気持ちを抱き続けているのだろう、と思っていた。でも、自分だけではないことに気づいた。
それは、ある友人のスケジュールを聞いた時のことだ。
「忙しくて、数ヶ月先までスケジュールがビッシリ埋まっている」と友人は言った。
そしてそのあと「埋まっていないと不安になるから、あえてたくさん入れているんだ」と付け加えた。
当時(不安はありながらも)のんびりできる幸せを噛み締めていた私は「スケジュールがスカスカでのんびりできるのも幸せだよ」なんて言ってしまったが、実は心の中で友人に共感していた。「その感覚、わかる」と。
☆★☆★☆
そもそも、この症候群について書こうと思ったきっかけは、森博嗣さんの本『正直に語る100の講義』を読んだことにある。
59番目の講義のタイトルが「『お忙しいところ……』とよく言われるが、皮肉だろうか。」だった。
タイトルだけでも大枠は伝わるだろうが、印象的なところを引用する。
どこへ行っても、向うは、「お忙しいところ、わざわざありがとうございます」と挨拶をしてくれるのだが、そこにいる誰よりも僕は暇なのだ。
確かに社会人をやっていると、やたらと「お忙しいところ恐縮ですが」という言葉を耳にする。もちろん私も使っている。
相手が忙しいことは大前提であり、暇であることは想定していない。その上でこちらは恐縮する。そういうマナーなのだ。もちろんこの言葉に込められた意味は理解しているし、相手への心遣いが感じられるとも思っている。
ただ、毎回決まり文句のように使っている自分に、ふと疑問を抱くこともある。
この挨拶の根拠としてあるのは、忙しいことは望ましい状況である、という観念だ。逆に言えば、「暇」は悪いイメージがつき纏う。
しかし、僕は暇人なのだ。暇になることを選んだ。暇になりたくてなった。暇であることを誇りに思っている。また、他者を見ても、暇な人を羨ましく思うし、暇人を尊敬しているし、人間のあるべき姿だとも認識しているのである。こういった感覚が、珍しいということはわかっているけれど、しかし、間違っているとは思わない。
私も暇でのんびりできる時間が幸せであることを知っている。森博嗣さんの言葉に共感しているはずである。
それなのに……
そう、“忙しくなければならない症候群”だから、暇な時間の「幸せ」には常に「不安」がくっついてきてしまう。
「好奇心が強いから刺激が足りないと満たされないだけ」
「充実感を追い求めているだけ」
と思いたいが、そうなのだろうか。向上心があるからかもしれないが、森博嗣さんが書いていたように、単に暇であることに対する悪いイメージが拭えていないだけなのかもしれない。頭では「そんなことない」と思っていても、一度染み付いたものを完全に拭い去ることは難しい。
社会人になった今でも、私は“忙しくなければならない症候群”だ。平日は不安な気持ちがないのに、土日祝日(休日)はのんびり過ごせる幸せを噛み締めつつ、不安な気持ちが膨らんでいくのを抑えられない。
私以外にも患者はいる。
よく効く薬は、どこかに売っていないだろうか。
☆★☆★☆
「そんなの、薬を飲まなくても大丈夫だよ」
えっ、そうなの?
「忙しくしていればいいんだよ。だって、忙しい状態なら不安にならないんでしょう?」
あっ、そうか。
治す(=のんびり過ごしても不安にならないようにする)のではなく、最初から不安を感じない状態(=忙しい状態)を目指せばいいのか。
さて、のんびりするか、忙しくするか。
“忙しくなければならない症候群”にとって、どちらが幸せなんだろう。
ではまた!
次も読んでね!
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
[プロフィール]
名前: きゅうり(矢野 友理)
2015年に東京大学を卒業後、不動産系ベンチャー企業に勤める。バイセクシュアルで性別問わず人を好きになる。
著書「[STUDY HACKER]数学嫌いの東大生が実践していた「読むだけ数学勉強法」」(マイナビ、2015)
Twitter: ![]() @Xkyuuri
@Xkyuuri
ブログ:「微男微女」