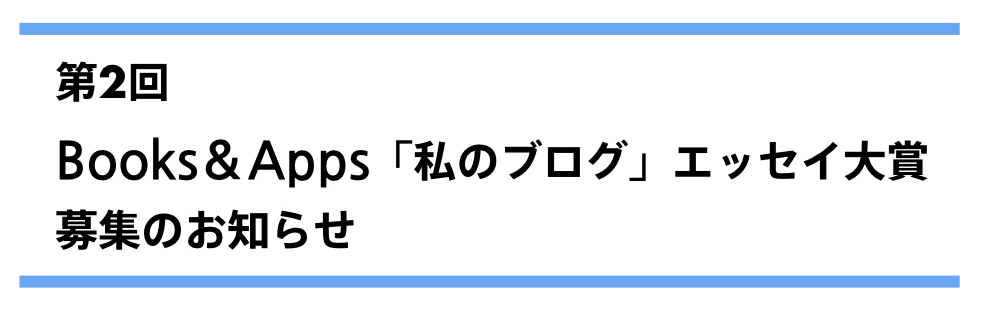若い女はそれだけでもてはやされるものなのよ、とたびたび母は言っていた。
でもそれは嘘、あるいは母が見てきた世界のお話であって、私の世界にはいまひとつ当てはまらないものなのだと、思春期以降の私は気づいていた。
女の美醜は世界観を左右する。
それは、女自身の自意識のせいもあるが、それ以上にこの世が古今東西、常に女の美醜を値踏みしてきたことを意味する。
子供の頃、母の「主観による」こういった話を聞かされてきた私は、早く大人の女性になりたかった。
今は田舎のただの芋くさい小学生でも、あと十年もすれば自動的に世の中が自分をもてはやしてくれるのだという、途方もない妄想をしていた。
***
果たしてそれから十年ほど経って大学生になっても、誰も私をもてはやしてはくれなかった。
高校は地元の女子高に通い、そこで友人と教室の隅で漫画を回し読みするという、典型的なそっち系の女子高生だった私は、クラスの華やかなグループの女の子たちとは違い、他校の男子学生との交流など当然なかった。
驚くことに同世代の男の子と口をきくのは一年に一度あるかないかであった。
その、年に一度というのも文化祭の案内だ。
しかし私はそうやって同世代の男の子と縁がないのを、完全に女子高という環境のせいにしていた。
出会いがないのだから仕方ない。
もっとも、何年か後に当時の友人たちに聞いたことによると、彼女たちは女子高時代もそれなりに恋愛、またそれに準じるものを体験していたという。
それも、男の子主導で。つまり、女子高に在籍していてもそれなりに告白などをされていたのだ。
言われてみれば当時からすでに、周囲の子たちからは
「塾でたまに見かけていました」
「駅でよく一緒になりますよね」
などといって男の子から声を掛けられたという話を聞いた‥ような気がする。
空恐ろしいことに、私はそれらの話をすっかり記憶から抹殺していたのだ。
同じ環境の自分以外の女の子たち(しかも自分と親しいグループの子)はそれなりに青春を送っていることなど、考えたくなかったのだろう。
そうして都合の悪いことは右から左へ受け流しているうちに、私は大学生になった。
大学は絶対共学と決めていた。
大学でも引き続き女ばかりの環境に身を置いていたら、いつまで経ってもこの尼僧のような生活から抜け出せないと思ったからだ。
さらに私はどうしても東京の大学へ行きたかった。
私は東京の隣の、東京コンプレックスが強いとか東京の腰巾着だとか言われる県の田舎のほうで生まれ育った。
その中でも特に東京コンプレックスを拗らせた娘だったということだろう、大学は東京の中でも人気の某オシャレエリアにある私立大を選んだ。
さあ、これから私の青春本番が始まるぞ。
田舎の女子高という環境のせいで得られなかった青春の日々をこれから存分にとり戻すのだ。
そう信じて疑わなかった。今から十数年前のことである。
そんな期待に胸を膨らませた入学式での自分の写真が、ついこのあいだ何かの拍子に出てきた。
本当に恐ろしい。
よくこんな田舎娘が、都会で詐欺の鴨にならなかったものだと感心する。
どこまでもどんくさい「ザ・田舎っぺ娘」がそこには映っていた。
髪型はなぜかキノコカットだった。無駄に髪が艶々なのが逆に痛ましくすら見える。
昔は十八が女盛りと言ったらしいだが、この惨状はいったい。
しかし浮かれていた私は、自分のその容姿や雰囲気をほとんど自覚していなかった。
確かに周りはオシャレで可愛い子が多い(実際、可愛い子が多い大学と言われていた)。
もちろん彼女たちに並ぶほどとは言えない。
しかし別に浮くほどでもないだろうと考えていた。
実家から片道二時間半を掛けて、私はせっせとそのオシャレタウンのオシャレ大学に通った。
大学生活は実際楽しかった。よい友人に恵まれ、大学のキャンパスは見渡す限り綺麗で広く、街はいつでも賑わい、キラキラと華やか。
見るもの、食べるものすべてが新鮮だった。
しかしあれほど思い描いていた、恋愛という意味での青春はやはりそこにもなかった。
片思いを恋愛と呼んでもいいのなら、それらしいものはあったが、一年生が終わらないうちに完膚なきまでに失恋した。
私なんぞは箸にも棒にも引っかからなかったといえる。
その人は少しシャイなイケメンだった。
最初から、さすがに身の程知らずという自覚はあった。
ただ、その片思いのおかげで私はいくらか自分を客観的に見られるようになった。
パンパンに張った顔をどうにかすべくダイエットし、デパートの美容部員にアドバイスを貰って化粧を覚えた。
いつの間にか、オタク趣味にもそんなに興味がなくなっていた。
オシャレに気を配りつつ、人付き合いをこなした上で、さらにオタク活動をするバイタリティもお金も残っていなかった。
大学時代はよく、母が私を羨んだ。
あんたはいいねえ、大学楽しそうだねえと。
皮肉でもなく、本気で言っていた。
「共学だし、すぐに彼氏もできるでしょう」と。
親の贔屓目に加えて、自分が二十歳前後の頃は(本人談だが)本当によくモテていたようなので、「東京の共学の大学+若い女」といったら、やさぞ華々しい青春を送るものだと疑わなかったらしい。
冒頭の母のセリフでも表れた、母の見る世界のお話である。
それが、大学一年が過ぎ、二年が過ぎても娘に浮いた話の一つもなさそうだと気づくと、母は心底不思議がった。
娘は、やれサークル活動やら飲み会やら合宿やらゼミやらで忙しく充実しているように見える。
だが二十歳を過ぎても恋人の一人もいないというのはどういうことなのだろう。
隠しているのだろうか。本気でそう訝しんでいたようだ。
実際私は、大学時代を通して、男の子と一対一のデートというデートもほとんどしたことがなかった。
友達が気を利かせてくれて、私の好きな人を呼んで複数人で遊ぶことはあったが、そのレベルから脱することはできなかった。
それに、親しい友人たちはみな気立てがよく優しかったが、どうやら私は「治外法権扱い」だったらしいのだ。
嫉妬深い女友達の好きな人や彼氏と親しく友達付き合いしていても、私は許されてしまう。
私が男っぽい性格だったこともあるのかも知れないが、同じような性格の子でも、容姿が可愛いとやはり嫉妬はされる。
女どうしの泥沼になる。
私は当時から今に至るまで、その沼に引きずり込まれたことがほぼない。
それは確かに楽だし、人と揉めないならそれに越したことはないが…なんだか寂しいではないか。
私は男と女の狭間の生物なのだろうか。
私はもういい加減、改めて自分を客観視する必要があった。
正確には自分の容姿を、だ。
少なくとも大学時代以降、私は、胸の奥で考えていることはともかくとして、表ではできる限り誰に対しても愛想よく振舞おう、一緒にいると楽しい人だと思ってもらいたい、というモットーで行動してきた。
これはモテや異性の目は関係なく私の信条だ。
裏返せば、そう振舞わないと私という人間の価値はないのだと思っていた。
つまり、本当は昔からとっくに、自分がブスだと気づいていたのだ。
綺麗な子は、黙っていればミステリアスか奥ゆかしい、よく喋るなら気取らない美人と言われる。
一方で、愛想の悪いブス、一緒にいても楽しくないブスに、なんの価値があるだろう。
そういう打ち消しがたい思い込みが根底にある。
ブス、なんと破壊力のある言葉か。
思い返してみれば、中学校時代の男子は本当に正直だった。
ブスに容赦なかった。
イベントなどでやむなく私とペアを組んだ男子は終始しかめ面で、必要な会話も最低限しかしてくれなかった。
中学校時代も女友達はそれなりにいたが、男友達は一人もできなかった。
あの年頃の男の子の多くは、たとえ性格は悪くなくてもブスとは話したくない、あまり関わりたくない、あるいは空気と同じで視界にとらえられない、といった本能を隠そうとしない。
そうだ。そういう異性の態度が辛いのも、私が女子高を選んだ理由の一つだったはずなのに、異性と関わらない高校三年間のうちにすっぽりと忘れていたのだ。
大学生ともなれば、さすがにそこまであからさまに差別する男は滅多にいない。
そのうえ、私が入学した大学は育ちの良いお坊ちゃんタイプが多く、総じて優しかった。
しかし、ブスは視界に入らないという基本的性質は変わらないらしい。
テニサー等のいわゆるイケイケサークルからは、新入生勧誘のときにもまったく声はかからなかった。
チラシ一枚貰っていない。
最終的に入った文化系サークルの新入生歓迎会でも、他の新入生の女の子たちと違って私は「彼氏いるの?」と聞かれることはなかった。
自分に都合の悪い事実は「セクハラになりそうだから遠慮してくれてるのかな」などとよくも曲解できたものである。
「普通の若い女の子が普通に生きていれば、男の人から声なんていくらでもかかる」、この母の説は、つまり自分がどうあがいても普通以下という事実を示していた。
さて、本格的に「ブス、あるいは最高でも並以下」だと自覚した私は、その後どうしたか。
私はまだ若く、恋愛を諦めることができなかった。
男性から来てもらえないなら、自分から攻めればいいんだ! と私は考えた。
テレビなどの「女の子のほうから告白されれば嬉しいから、よほど嫌でなければとりあえずは付き合う」というコメントを鵜呑みにしてしまったのだ。
結論から言えば、私の告白はどれも片っ端から玉砕した。
いや、別に手当たり次第好きになって、手当たり次第告白したわけではない。
大学時代~社会人までの間に、平均して二年に一度くらいのペースだろうか。
社会人になった後は、気になる人と二人で食事をする機会も増えた。
そこで「良い人だね」「優しいね」「話が合うね」といった言葉を、何人もの男性から貰った。
もちろんお世辞もあるだろうが、実際にすごく性格が悪い、またはまったく会話が楽しくないと思う相手には言わない言葉だろう。
それで告白したところで、結局は叶わない。
私の何が付き合うに至らない要因なのか。
卑屈極まれりと言われようと、やはり外見、と思わないでいられようか。
ついでにいえば、その卑屈さがまた重さを醸し出していて、二重苦だったのかもしれない。
女の子の場合は、何度か告白されて熱意に負けて付き合った(そして結構仲良くやっている)という話もチラホラ聞くが、男の場合はそうではないようだ。
どうやら、もう知り合った当初から、相手のことを女としてアリかナシかを判断しているようである。
結局のところ容姿が好みの範囲かどうかなのだろう。
女から告白すればたいていはオッケーされる(その後の付き合いが長続きするとは言っていない)という説は、少なくとも並以下の容姿の女には適用されないといえる。
何度かの玉砕で勉強になったのはそれくらいだ。
それに気づく頃には、私は二十代後半になっていた。
女としてのなけなしの自尊心はボロ雑巾状態だった。
***
さて、待てど来ず、押してダメ、引いてダメな私の恋愛がその後どうなったか。
現在三十代後半に差し掛かった私は、数年前に結婚している。
一応、恋愛結婚だ。
いよいよ容姿だけでなく若さも失いつつあった私は、戦略を変えたのだった。
世話焼き女房というか、母親代わりとでもいうか‥という方向へ活路を見出したのである。
大人になって立派に社会人をやっていても、実は心の奥底にはまだ母親に甘えたい、なんでも寛容に受け入れてほしい、と無自覚に飢えている男性は一定数存在するらしい。
そういった母性に対する需要と、私の好みが偶然一致して付き合ったのが今の夫だ。
少し年下である。
よくも需要と供給が合致したものだと、無宗教ながら神様に感謝する。
若い頃に私が欲していた「女として愛されたい、可愛がられたい」という願望とは少し、いや結構違っているのかも知れないが、夫婦仲は今のところ、まあまあうまくいっていると思う。
だが結婚生活の幸せとはまた別の次元で、やはり未だにあの母の言葉が呪縛になっている。
若い女はそれだけでもてはやされるものなのよ
私が若い女だった時代は二度と戻ってこない。
つまりどうあがいても、ちやほやされる青春とやらはもう手に入れられないのだ。
それは、間違って今さら浮気や疑似恋愛をしたところで得られるものではない。
私が欲しかったのは、若い女としての青春だ。
平穏な日々を過ごしておいて、まったく贅沢な話だとは分かっている。
だが、得られなかったものをすっぱり忘れるには、もう少し歳を重ねる必要がありそうだ。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【著者】
西歩
大学卒業後、教育関連企業の会社員時代を経てフリーの編集者となる。
趣味はゲーム、漫画、服飾史研究。好きな時代は古墳時代~平安時代。
(Photo:紅人 鄭)