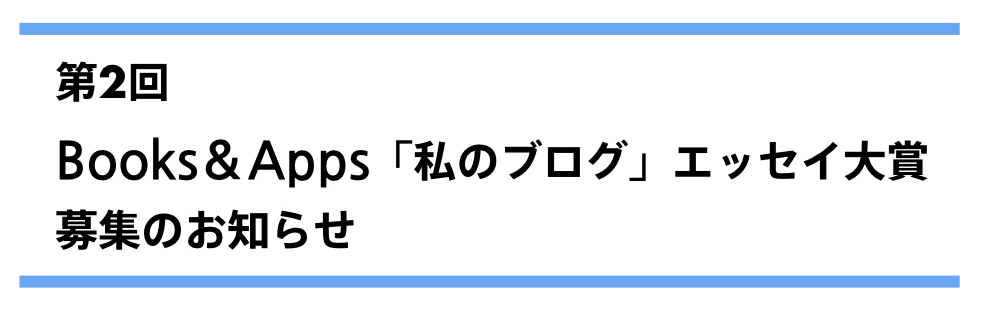サウジアラビア航空のフランチャイズのジェッダ国際航空に降り立つ。
タラップに出ると多分40度を超える高温熱風が身体を包む。
イスラム教の聖地メッカへの乗り継ぎ空港でもあるし、ジェッダの街が首都リアドに次ぐ経済中心の都市だ。
頭から足元まで白い布ですっぽり包んだアルガムディが毛むくじゃらの分厚い手を差し出し、これ以上の嬉しい喜びは無いという笑顔で迎えてくれる。
顎にも真っ黒な髭、足元は裸足に革のサンダル。表敬訪問で深い大きな商談があるわけじゃない。今後ともお互いによろしくというだけだ。
目がゴージャスな中東美人がブブカをかぶって歩くのが車から見える。
翌日、歓迎のパーティに招待された。ヒルトンホテルまでレンジローバーが迎えにくる。
市街を抜けて30分も走れば砂漠だ。地平線まで砂の海だ。陽炎で空気が揺らいでいる。
その揺らぎの遠くに白い天幕がぽつんと見える。召使が数時間前に来て砂漠を平らにし、天幕を貼り、絨毯を敷き、クッションを並べて準備したのだ。
天幕から30メートルほど離れたところには石やレンガを敷き詰めた大きな場所ができている。
石やレンガも街から運んで召使たちが準備したのだ。どうやら砂漠のバーベキューのようだ。
天幕の中には20名ぐらいの男達がいる。全員、血縁があり商売仲間だ。女性と子供は一人もいない。顔中に髭を生やした男達だけだ。暑い砂漠の中でむさ苦しい限りだ。
もちろん口には出さない、思っただけだ。冷たいお茶がだされる。私が輸出した魔法瓶からだ。
アルコールは無い。イスラムなのだ。
紹介されて一人ひとり握手をする。
アルガムディのおじさんや、兄弟姉妹の旦那や奥さんの兄弟と紹介されても全員同じ顔や名前と思えてくる。
孫悟空の抜いた毛で作られた皆同じクローンのようだ。誰が誰なのか全くわからない。
名前もどれも同じように聞こえる。
その後、水パイプを吸う人やハシシをふかす。アルコールが無くても世界中の男どもは男の世界を造る。楽しみを見つける。
アルガムディには4人の奥さんがいる。
「へぇ、4人も」
と驚くとアルガムディは
「まだ、俺は貧しいから4人しか持てないのだ、7人は養えるぐらいにならないと」
「で、彼女たちは喧嘩せず仲良くしているのですか」
「もちろんだよ、全員仲いいよ。俺の悪口や不満をお互いぶちまけて楽しんでいるよ」、
「こうして、男たちだけで息抜きするのが一番だよ、女は細かいことにあれこれうるさいからね」。
世界中、どこでも一緒だ。奥様が旦那より強いのだ。
準備が整いましたと告げに召使が天幕に来る。
アルガムディが「お見せしましょう」と言う。私も腰を上げて、外にでる。
どこからか召使がラクダを引いてきて石とレンガの上に移動する。
全員が石畳の周りに立って見物だ。
何が起こるのか全く分からない。
アルガムディが帯に挿していた黒光りのピストルを出して、「神は偉大なり」と叫んで、ラクダの首筋に銃口を当て全く躊躇することなしに引き金を引く。
「ズドン」と鈍い音だ。
「わぁ、何だ!なんだ!驚かせるなよ、突然」、残酷だなぁと思う暇もない。
イスラムでは殺生は日常で平気なのだ。
ラクダは石畳の上に横倒しになる。即死だ。銃創から血がドクドクと噴き出す。
召使が大きな刀を抜いて、ラクダの腹を首からお尻に向けて切り裂いていく。石畳が血の海になる。
召使が裸足にパンツ1枚姿でラクダの臓物を腹から両手を使って掻き出す。
頭から潜ってすべての内臓を両手で掻き出す。湯気が立っている。ものすごい血と内臓の生臭さで吐き気が襲う。
全員がかたずをのんで見物だ。砂漠なのに蠅が飛んでたかる。
砂漠も生きているのだ。
取り出した臓物はあらかじめ掘られていた穴に投げ込まれ、砂が掛けられ埋められる。
臓物を出した二人の召使がポリタンクとブラシを持ってきてラクダの腹の中を洗う。
石畳の血もキレイにブラシがけする。イスラムでは動物の血はタブーなのだ。
召使たちの身体の血も洗う。
塗れた石畳も瞬く間に乾いて行く。砂自体が焼けているし、石畳も強烈な太陽光で焼けている。
卵を落とせば目玉焼きができそうだ。
傍に大型のジープが寄せられる。
荷台には人参、玉ねぎ、ジャガイモ、キャベツ、見たことが無いカリフラワーのお化けのような野菜、などが満載されている。
すべての野菜が洗われ、皮がむかれ、切れ目が入れられている。
それらの野菜が洗われたラクダの内臓に、一人の召使が腹に潜って受け取り丁寧に野菜と羊肉のブロック、2本脚が付いたままの鶏やオマール海老、を交互に重ねて並べていく、その上に、塩、コショウに数種の香辛料が振られる。
振られるというより手掴みで投げるのだ。上品な京料理じゃない。
腹に材料を詰め終わると、タコ糸と30センチぐらいの針で割いた腹を縫う。
一人は喉元から、もう一人は尻の方からかがり縫いしていく。
縫い終わると乾いた薪、小枝、藁の束をラクダに被せガソリンをかける。火を投げ込む。
火山の噴火のように瞬間的に爆発しゴージャスな炎が黒煙と共に真っ青な雲一つ無い空に立ち上がる。
「ご主人さま、永い眠りから覚ましていただいてありがとうございます」
という願いを叶える大魔神が現れても不思議じゃない煙の場面だ。
その時を置かず全員が「アッラーフ・アクバル」と天に向かって祈る。
ぞろぞろと天幕に戻る。あとは焼きあがるのを待つだけだ。
小一時間はかかると聞く。多分、外は40度を超える温度だ。いくら水を飲んでもトイレに行かない。
コーラやスプライトも日本の物より甘い。お茶もダダ甘だ。すべて汗で蒸発してしまう。
天幕の中でも30度を少し超えているだろう。
ただ湿度が無く乾燥しているので身体にぴったりしたシャツやズボンは砂漠に向かない。
彼らの服装のゆったりした締まりのない白やベージュのコットンのショールガウンは風を絶えず入れて汗を飛ばしていく。
シエマガと呼ばれる頭巾も砂漠の砂嵐や頭上からの陽射しを防ぐ.上手くできている。
アラビア語でしゃべっているので輪に入れない。打ち解けられない。疎外感と孤独が襲う。
ひたすらお茶を飲み、立ち上がる炎と煙を見ていた。
時が経ち、直径1メートルもあろうかと言う銀の大皿に鳥や羊やエビの肉が真ん中に置かれその周りに野菜が積まれ出てくる。
山のように盛られたのを見るだけで、もう結構です、お腹いっぱいですと言いたくなる。
我々は上品だし小食なのだ。
アルガムディが採り分けてくれる。箸を持って来ればよかったと思う。
タンクの水で手を洗って手掴みで食べる。美味い。
ラクダの脂が野菜や肉に絡んで、少しワキガのような臭みがあるけど、香辛料が打ち消している。
けれど何でここにワインが無いのだ。ウィスキーや焼酎のロックはどこだと叫びたい。
アルコール抜き、女無しだ。
あるのは気の抜けた蒸発したビールだ。もちろんノンアルコール。哀しい、寂しい。
何より乗らない、はしゃげない。呑んで酔っ払うともう少し英語が飛び出すのだけど。
彼らの食べる量は全然日本人と違う。
私の一皿で家の家族全員が腹いっぱいなるぐらいある。
私は60キロ、彼らは見たところ平均85キロぐらいある。
バクバク食べる。甘いお茶を飲む。休憩に水パイプのたばこかハシシを吸う。
その煙でこちらも酔いそうだ。お腹が一杯で休止していると、アルガムディが心配して、召使に指示して私のプレートにドカンと追加の肉と野菜を盛る。
「いや、お腹が一杯だから」
とアルガムディに言う。
「お腹じゃダメ、首まで食べろ」と首筋に手を当てて、ここまでと示しながら
「このパーティはお前の歓迎の為に開いているのだから、お前が食べないと皆も食べられない、お前が食べるのを皆が見ている」と半分脅迫される。
焼酎かウィスキーがあれば、酔っ払ってごまかせる。
それもできない。食べるしか無い。
そうなるともう美味しくない。でも無理やり口に入れ込む。
蛙の腹のようにパンパンに膨らむ。
「首まで来た」とアルガムディに言う。アルガムディは召使に首を振って指示する。
そして「それじゃ、出して来い、彼が案内するから」と。
私は意味が分からないけど、立ち上がって召使の後について行く。
砂漠の砂がスニーカーに容赦なく入ってくる。
召使は砂丘に向かって行く。砂丘の裏側に回る。
召使は帯にさしていたスコップをだして30センチほどの穴を掘る。
そして、鉛筆ほどの細さと長さの革のスティックを手渡す。
先は小さな細かい革がささくれたスティックだ。
彼はそれを自分の口を大きく開けて入れて吐く動作をする。
何だか笑える。
召使はそのスティックに水をかけて私に手渡す。
彼がやったようにやってみる。
とたん、猛烈な吐き気が襲い、掘られた穴にドバっとさっき食べたものが未消化のまま出てくる。
すっきりだ。召使は人差し指を上げて「ノー、ノー」と言って、もう一回やれと促す。応じる。
するとあら不思議、またも猛烈な吐き気が襲い、同じぐらいドバッと吐く。
お腹に中が空っぽになった感じだ。すっきり気分爽快。天幕に戻る。
アルガムディが「どうだ、すっきりしただろう、下から出すより速くて便利だろ」と笑う。
「さぁもう一度首まで食べろ」。
やれやれ何だかなぁだ。そうして20名の招待客全員が入れ替わり立ち代わり吐き場に向かう。
誰もが自分の専用スティックを持参している。
世界の80%の人々が今日食べるものが無いと言うのに。金持ちが貧しい人に与えず食べてしまうのだ。そして吐くのだ。
延々と宴会が続く。その間、召使は食べない。多分、身分職業の差別だ。主人と奴隷だ。
残り物は召使達に与えられるのだろう。
太陽が沈む。大きな太陽だ。代わって煌々とした月が出て、満天の星が拡がる。
食べ疲れて、私は黙って席を立ち、天幕を離れる。
彼らの話声や嬌声が聞こえない所まで行ってみよう、腹ごなしだ。靴を脱ぐ。砂が暖かい。
10分も歩けば静寂がある。正にプラネタリュウムで見る星が降ってくる。
静寂を超える無音だ。風の音も虫の音も、何も聞こえない。死の世界だ。奇妙な世界だ。
生まれてからこのかた無音だった場所に片時もいたことが無い。
ブーンと小さな音がして空を見上げるとジェット機のテールランプが砂漠を横切っていく。
どんな人々が乗って、どこへ飛んでいくのだろうか。
キャビンは明るくて賑やかだろうな。心細くなって、砂丘を昇る。
天幕の灯りが見える。光や音は安心をもたらす。
私はその後も首まで食べ、されにもう一度吐きに砂丘の裏に行く。
やっとお開きとなる。ホテルに帰ってベッドに倒れ込む。食べ吐きつかれた。
もう嫌だ、アラビアは。
半世紀前、大学を卒業して洋紙専門の貿易商社に入って数年後、サウジアラビアのジェッダに出張で行った。
私はまだ青くシャキッとしていた。
紙の輸出は先が見える。50年ほど前のタイやインドネシヤと言った当時の発展途上国が黎明期に造る産業と言えば繊維や鉄に紙となる。
紙だけに頼っていては先行きが無いので、私は紙以外の輸出品を探し、そのメーカーの開拓と、同時に海外の売り込み先を探す。
魔法瓶の代理店として中近東やアフリカ、などへの代理店の権利を得て、輸出していた。
大した額の商いじゃない。1本がせいぜい1000円位の物なので、1000本の注文でも100万円だ。
魔法瓶1000本と言えば輸入する側からすれば大量だ。
そこで、取引先のジェッダのモハメッド・アル・アリ・アルガムディを訪ねたときの話だ。
***
それから半世紀が経った。
60歳の誕生日にランチに外出し、帰社すると机の上に走り書きのメモで「今日で定年です/社長」とだけあった。
社長室へ行くと蛻の空だったので、「お世話になりました」とメモを残す。
私物をカートンに詰めて自宅へ送る手配をして、社員や同僚に別れも告げず帰宅した。
郊外電車の中で溢れる涙をハンカチで抑えた。
若いOLが花束贈呈をしてくれる送別会も退職金も無い。
苦しい老後が始まった。
会社や仕事に自分を賭け過ぎたのが悔しく哀しい。
今日の今は自分らしく生きる時代だ。私に残ったのはアラビアのナフード砂漠での贅沢な宴会だけだ。
それ以上に何か得るものが会社に合ったか。何もない。
生きるのは食べて吐いての繰り返しだけなのだ。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【著者】
マーシー松田
印刷会社・興陽紙業株式会社貿易部を経て、同社社名変更/株式会社コーヨー21/副社長後、東京文久堂/顧問。
現在学習塾経営のクリエィティブ・オーシャン・インク代表
(Photo:halfrain)