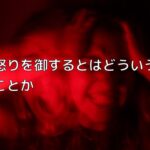「ああ、会社いくのダルいなぁ」
働いていて、こんな事を思わない人間はいないだろう。
働いていない学生だって学校に行くのはダルい。
人間というのは何らかの義務に従事させられると、そういう事を考えてしまう生き物なのだろう。
「死ぬまで使い切れないほどのお金があったら、毎日遊んで暮らせるのに」
なんだかとってもユートピアそうに聞こえる毎日遊んで暮らすだが、実際問題どうなのだろうか?
今日はその話をしようかと思う。
働かない生活は、あまりにも暇…らしい
勝間式ロジカル不老長寿という本に記載されていた話だ。
勝間和代さんの周りには50歳ぐらいになってアーリーリタイアを選ぶ人が出てきたという。
資産や収入が十分にあるこれらの人が何をしているかというと、だいたい次に集約されるそうだ。
・ゴルフ
・美食
・旅行
・別荘遊び
こうしてみると、働かない人生は自由そうにみえて、意外と多様性に乏しい。
おまけにそれらをやっていてイキイキしているのならまだしも、多くの人はあまりにも暇すぎてyoutubeやネットニュースをたくさん見てつまらないフェイクニュースや陰謀論に騙されかけたりしているのだという。
故に勝間さんはアーリーリタイヤを選ぶ人の事をまったくうらやましいとは思えず、一生働き続けたいと思うようになったそうだ。
<参考 勝間式ロジカル不老長寿>
定年後は悲惨?
この本の中で勝間さんは「定年後」という本を書いた楠木新さんと対談した際の話も載せられているのだが、楠木新さんはいかに定年後が悲惨かという事を力説したという。
楠木さんが定年を迎えたさまざまな人達に取材を行ったところ、出会った定年後の生活を暮らす方の多くが本当にやることがなく、暇そうにしているという。
定年と同時に社会的なつながりから切断され、ネットワークからはじかれ、収入も大きく減る。
こうなった人はとれる行動に選択肢がなくなる。
結果、毎日図書館に行くか、スポーツクラブに行くしかなく、生活から彩りのようなものが大きく欠けてしまうのだそうだ。
そうなってみて、あんなにも毎朝行きたくなくて震えていた会社に行く事を禁止される事が、逆に物凄くありがたいことだったと気がつくというのだから、なんだかトンチのような話である。
定年というのは労働からの脱獄なんかではなく、逆に働きたくても働けず暇という監獄へ押し込まれてしまうペナルティ的な側面も持つのである。
定年後の人生は実に長い。
多くの人は少なくとも働けない人生を30年ぐらいはやるのだろうから、その為への準備はキチンとしておくべきだろう。
楽しい事を仕事にする
このような現実を前にして、私達はどうするべきなのだろうか?
まず誰もが思いつく事の一つに、やっていて楽しい活動を仕事にするというものがある。
動画撮影に文章執筆、絵描きなどなど…私達が日々楽しんでいる娯楽作品の多くは、私達にも生み出せなくもないものばかりだ。
あなたが仮に消費者として楽しんでいるコンテンツがあるのなら、いっそそれを自分で作る側になるのも一つの手である。
現代インターネット社会において生産者をやるのはそこまで難しい事ではない。
やるかやらないか、それだけである。
生産的趣味を一つでもいいから持つ事ができれば、消費以外の時間の使い方ができるようになる。
それはたぶん思った以上に重い意味を持つ。
少なくともやることが無くて暇という状況とは無縁になれる。
そう考えると定年を迎えるまでの時間というのはある意味では副業に対する執行猶予的な期間といえよう。
現代において労働期間は単に働くだけのみならず、定年後に打ち込める何かを探す為の期間でもあるのだろう。
労働に楽しさを見出す
もう一つ大切なのは、いまやっている仕事をキチンと商品化する為の努力だ。
いくら定年という縛りがあろうが、それはあくまで会社の中における話である。
自分の仕事にキチンと汎用性があるのならば、所属機関に関係なくフリーで技術を売るは可能だ。
フリーランスと経営者には定年はない。
そう考えれば、定年というのは「65歳になって働き続けたかったら、会社に頼らず独り立ちしろ」というある種の国が決めた区切りともいえる。
その為にも今やっている仕事の何に付加価値が生じているのかをキチンと意識化し、それをいつでも切り売りできるようにパッケージ化しておく必要はある。
そういう意識を持っているか否かは、後でかなり大きく響くはずだ。
食わず嫌いせずになんでもやっておくと、人生の自由が広がる
また、多少つらくても縁ができた仕事はキッチリやっておくべきだろう。
これはお金云々というよりも、人生の自由の幅が拡張できるという点が大きい。
最初はやっててつまらなかった事でも、それなりに継続をしていると面白みがみえてくるものは多い。
どんなものであれ、市場価値がキチンとついているものは消費するだけの活動にはない妙がある。
その妙さえ見いだせれば、人生におけるやっていて楽しい活動の範囲がより広くなる。
技能は行動範囲に直結する。
美味しいパスタが作れる人生はカップ麺しか選択肢の無い人生と彩りが異なる。
カップ麺だって凄く美味しいけれど、選べるのなら選択肢は多い方がいい。
仕事もそうで、できる事は多ければ多いほどいい。
だから働けるうちに食わず嫌いせずに様々な事をやってみるべきである。
時給やらコスパ感覚やらで自分の能力向上の機会を無くしてしまうのはあまりももったいない。
自ら進んで苦労をしろとまではいわないが、多少の大変さぐらいならば人生の肥やしだと思ってやっておく価値はある。
できる事が多い人生は、できない事だらけの人生とは完全に異なる。
その間の四苦八苦だって、色々と為になるものばかりだ。
苦労は社会性の獲得に最も寄与する
苦労は良くも悪くも人を丸くし、老獪さの向上に寄与する。
それは集団生活を送るにおいて、持っていて決して損なものではない。
社会性を身につける効率の良い方法の一つは困難を乗り越える事にある。
そういった困難にぶつかるのに、仕事は良くも悪くもいいキッカケとして作用する。
そうやって心のタフさを増してゆければ、あなたは自然と大人な態度をみにつけられるようになる。
そうすればしめたものである。
大人はなろうとしてもなれるものではないが、苦労は必ず人を大人にする。
そうして大人になれれば、自然と尊敬の念も得られるようになろう。
少なくとも未熟な人間と言われるよりかはだいぶ自尊心は高まるはずだ。
合唱祭の練習で不真面目なクラスメイトに向かって、ガチ泣きしていた女の子の思い出
最後に一つ。
真面目に人生をやった方が不真面目よりも得だという話をして文章をしめよう。
やっている活動の中に面白みを見いだせるか否かも、ある意味では自分の腕次第である。
同じ人生ならば、斜に構えるよりかは真面目にやった方が得だしカッコいい。
これは間違いなく人生の真理の一つだ。
今でも思い出す事の一つに、中学生時代に合唱コンクールの練習の最中に「なんでみんな真面目に練習しないの‼」とガチ泣きして訴えかえてきた女の子の姿がある。
僕はその時「なんで一生懸命やっても1円にもならないような活動に、こんなに馬鹿みたいに真剣になっているのだろう?」と冷めた目で彼女を眺めていたのだけど、その後で自分が完全に自分が間違っていた事を痛感した。
結局、その女の子の涙の訴えが効いたからか我がクラスは実に熱心に練習を行い、皆の技量はとんでもなく上昇した。
そうして行われた合唱コンクール当日、コンサートホールにて実に美しい20億光年の孤独が鳴り響き、会場は騒然となる。
全てが恐ろしく完成された合唱の中に居た、あの時の恍惚感は今でも忘れられない。
それまでは音楽はプロの完成された演奏を聞けば十分だと思っていたが、真剣になって皆で一丸となって取り組む事でしか味わえない感情というものがこの世にある事をあの時初めて知った。
たぶん、仕事だってあの光景の再現はできるはずなのだ。
それをやるには真面目に丁寧に人生をやらないと駄目だけど。
斜に構えて、なんでも達観したかのような知った顔でやり過ごすには人生はあまりにも勿体ない。
真面目にやらないと、見えない景色というのは確かにある。
そういう景色を死ぬまでにみれるかどうかも、全てはあなた次第なのである。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
都内で勤務医としてまったり生活中。
趣味はおいしいレストラン開拓とワインと読書です。
twitter:takasuka_toki ブログ→ 珈琲をゴクゴク呑むように
noteで食事に関するコラム執筆と人生相談もやってます
Photo by :mrhayata