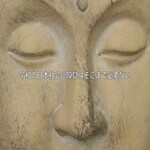あれからもう、13年が過ぎた。
東日本大震災の発生時、わたしは報道局内にいた。
個人的には、TBSへの在職期間中で最も大きな災害報道の経験である。
そのなかで、ひとつ後悔、というか、自分の想像力の至らなさを痛感した瞬間があった。
「瓦礫」の存在である。
事前に震源地を知っていることの怖さ
あの日のことは、なぜか鮮明に覚えている。
石原慎太郎氏が東京都知事選への出馬を表明する記者会見を開いており、在京テレビ局はすべてそれを生中継していた。
きょうはこの話題で持ちきり。経済部の出番はなさそうだなあ、という、ゆるい空気の中、それを見ていた。
その最中に、緊急地震速報が鳴った。
局内には気象庁から提供される情報をリアルタイムで反映しているモニターがあり、それを見れば、震源地が宮城県沖であることはわかる。
そこから実測値が更新されながら、モニター画面内では、同心円が広がっていく。
その同心円の線が地図上で東京に触れた瞬間、「くるぞ」とわかって身構えたが、想像以上の揺れがやってきたのだ。
都内で外を歩いている人たちは「地震だ!でかい!」と思うだろう。しかし、揺れる前にどこが震源地なのかは知らないから、これがとてつもない地震だと知る由はない。
しかしわたしたちは、揺れる前から震源が遥か遠い宮城県沖であることを知っているのである。尋常ではないことがその瞬間にわかる。
オンエア中の番組を即中断し、報道局からの特番に切り替わる。
あの歴史的な出来事の第一報
このように「トタ」で始まる報道特番には当然、進行表などない。最初の数十分をしのぐためのなんとなくのテンプレートが存在するだけだ。
気象庁から発信された情報、自前の報道局内で24時間回している固定カメラに収録された地震発生時の様子の映像、その程度しか手持ちの情報がないまま、しかし一度開いた特番枠は中断できない。
状況によっては何時に終わるなんてことも決まっていない。
しかも今回は、地元の系列局も大きく被災している。
通常ならば地方局の準備が整い次第そちらにスタジオを渡すのだが、当該地域の局と連絡が取れなくなってしまったのである。
東京から当該地域の市役所などに電話をかけようにも、電話は繋がらない。もどかしい時間が長く続きながらも、しかし何らかの情報は更新していかなければならない。
現場は東北にもかかわらず、都内で起きたちょっとしたボヤを見つけては大騒ぎせざるを得ないのはこのためである。
そんな時、経済産業省記者クラブの担当記者から1本の電話を私は受けた。
のちに歴史的大惨事となる、福島第一原発についての話だった。
正しく対処したつもりだった
東京電力から経済産業省記者クラブにひとつの「資料投げ込み」があったのだ。
担当記者は「とりあえず」ということでその記者発表の紙を、私がいる本社にFAXで送ってきた。
内容は、ひとことでいえば
「福島第一原発で外部電源喪失、電源車が現地に向かっている」
というものだった。
この第一報をどう扱うか?
いくら新しい情報に困っているからと言っても、これは「とりあえず手元に止めておく」というのが通常の判断である。
中途半端な情報はパニックを引き起こす。
ここまでは良かったはずだった。
しかし、この後、わたしは自分の無能さを知ることになる。
自分が悔しくて仕方なくなった
福島第一原発で異変が起きていて、しかし修復に向かっている。
ほかの情報を処理しつつも、そのことは気にはかけていた。今後どのような経緯をたどるか、絶対にウォッチしておかなければならないことだからだ。
何かあれば続報が来るはずだ、そう思っていた。
しかしその思いはしだいに揺らいで行った。
何時間経っても「電源車に接続完了」「電源供給を開始」といった情報が入ってこないのである。
ずいぶんと続報が遅い。
こんなに時間がかかる理由は何かと、さまざまなことを自分の頭の中でシミュレーションした。
現場ではどんなことが起きうるだろうか?
それを可能な限り想定し、当局に質問としてぶつけることが記者の仕事でもあるはずだ。
これだけの時間が経過しても、電源車を接続できない理由を色々と考えてみた。
しかしこのときわたしは完全に、ひとつの可能性を見逃していたのである。
現実はこうだったのだ。
第一報の段階で「電源車が向かっている」のは事実である。
しかし、
「向かっているが、瓦礫のため近づけない」のもまた事実だったのである。
そうならそう早く言ってくれよ!と思うかもしれない。
しかし、その後の東京電力の対応を見ればみなさん想像のつくことだろう。
質問しなければ何も出てこない、あの状況だ。
「瓦礫で近づけない可能性もあると考えるのですが、実際どうなっているのですか?』
そう質問しなければいけなかったのである。
もちろん、瓦礫のことを知ったとしても「電源車が近づけない」と速報することはなかっただろう。
この非常事態でわたしたちが伝えるべきは、「視聴者が少しでも安全な行動を取れるよう、参考となる情報」である。
報じることで逆に混乱を引き起こす情報を、無責任に世に放つわけにはいかない。
「では周辺に住む我々は何をしたらいいのか?」という質問に答えられないような、単なる騒ぎはこのシチュエーションでは引き起こすべきではないという判断だ。
とはいえ、状況を正しく知っていれば、何か心構えをする材料にはなったのではないか。
なぜその可能性を想像できなかったのか。
ましてや津波が直撃していたなど、想像外の想像外だった。
その想像力の貧困さを、わたしは今でも悔しく思っている。
この場を借りて、後輩たちにひとつ言いたい。
記者の仕事というのは、記者会見を聴きながらバチバチとノートパソコンを打つことではない。
相手の言葉を聞き漏らさず、コンテクストを嗅ぎ取り、顔色を凝視し、いかに相手が何を隠しているか。行間から情報を得てそれを対象に投げ返し、少しずつ真実に近づいていくことである。
メモを取るだけの人間にそんな高給を払う価値があると思っているのか?
瓦礫の自己無限増殖
それはさておき、「瓦礫」というのは、多くのところで「無視できるもの」とされているのかもしれない。
しかし、瓦礫が瓦礫を生む恐ろしい事態が、いまこの自然界で起きている。
「ケスラー・シンドローム」という言葉をご存じだろうか。
宇宙科学の世界で、いまもっとも懸念されている出来事のひとつである。
いま、宇宙開発がかつてより身近なものになり、民間の小型ロケットが低予算で打ち上げ可能になっている。
しかし今、地球の軌道は「瓦礫」で溢れている。
運用が終わった衛星、打ち上げミッションを果たした後のロケット本体。これらはすべて「ゴミ」である。
かつては「ビッグ・スカイ理論」といって、宇宙のような広い3次元空間ではモノとモノが衝突する可能性は稀であるとされていた。
しかし似たような軌道にこれらの「ゴミ」が溢れ続けた結果、懸念されているのがこの「ケスラー・シンドローム」、言ってみれば「ゴミの無限増殖」である。
ISSが1日で地球を16周するように、宇宙ゴミもまた秒速数キロというスピードで軌道を周回している。すると、どんな小さなものでも、瓦礫同士がぶつかると、衝撃でさらに小さな瓦礫を生み出す。
こうして瓦礫の数が増えていくのである。瓦礫の自己増殖、これがケスラー・シンドロームである。
ひとたびこの状況に陥ると、それ以降いっさいの打ち上げをやめたとしても瓦礫の増殖は止まらないとされている。
ストレスを無限増殖してどうする?
さて、あの日の報道フロアにはその初期段階のようなものも見られた。
発災直後。
当該地域の系列局との連絡が断絶されてしまった。これは訓練にはない出来事だった。
指揮をとる編集長が苛立ちを見せ始める。
その苛立ちが、周囲に伝播する。
何時間後だっただろうか。翌日だっただろうか。なんとか福島の系列局が、懐中電灯でスタジオを開いたのが一番近い距離だった。
宮城と岩手の状況はわからない。
ただ、お天気カメラが捉えた悲惨な津波の映像と、自衛隊から提供される悲惨な火災の映像が送られてくるだけだ。
ようやく仙台、盛岡と放送体制が整っていくが、ロジが思うようにいかないこと、起きる現象が多すぎることに、だんだん苛立ち、ついに局内には怒号が飛びかうようにもなる。
ADさんは常に走っている。彼らの走りで床が揺れているのか余震で揺れているのか、わたしたちにもストレスになってくる。
しかし、わたしは内心思うことがあった。
「本当に全員が全力で走る必要あるんだろうか?」
「そんな大きな声出さなくても聞こえるけど?」
考えてみれば、これらは「ストレスの無限自己増殖」である。
議論や喧嘩で出てくる大声ではないのだから、普通に話せばいい。
ただ、「災害ハイ」「もどかしさ」で、次第に声が大きくなっていく。その心理はわからんでもない。
しかし、上に立つ人の声が大きくなれば、なんだか自分も緊張している風を装わなければならないような気がして、ADさんは「走らなければ」と感じてしまう。
あるいは、わたしくらいの中間層には、単なる雑音が与えられる。
上に立つ人間がストレスを現場でぶちまけることによる「ストレスの自己増殖」というのは存在するのだ。
そして。
中には、その余計な疲れを「きょうはがんばった」と自分を褒める要因にする人間が出てくる。
いや、これはポジティブシンキングの持ち主で良いことかもしれないが、満足の軸がぶれている。
「きょうはタイプミスなくメモを取れた」ことで仕事をした気になる記者を増殖させるだけだ。
いや、それは違うだろう?
TBSに入社した直後の私は、ある先輩から「なぜマスコミの社員には高い給料が支払われるのか」という話を聞いたことがある。
それは、「社会に対する責任を負う仕事であるから」だと彼は説明した。
その通りだと思う。
しかしマスコミに限らず、「上司に対する責任」に終始する人間も社会には多いのではなかろうか。
上司がテンパってるから自分もでかい声出さないとやる気ないみたいに見えるかな、みたいな。
申し訳ないが、いまの日本社会には、そのようなブルシットジョブに給料を払う余裕などない。
組織の内側にストレスを撒き散らしている余裕はないのだ。外を思え。外のコンテクストを読み取り、外に寄り添う人間たれ。
わたしはそう思う。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【プロフィール】
著者:清水 沙矢香
北九州市出身。京都大学理学部卒業後、TBSでおもに報道記者として社会部・経済部で勤務、その後フリー。
かたわらでサックスプレイヤー。バンドや自ら率いるユニット、ソロなどで活動。ほかには酒と横浜DeNAベイスターズが好き。
Twitter:@M6Sayaka
Facebook:https://www.facebook.com/shimizu.sayaka/
Photo:Library of Congress