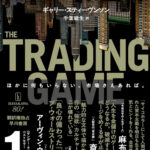人の話を聞くとき、多くのシチュエーションで「解決」よりも「共感」が重要なことがある。
しかし、このような話を聞くと
「私は人に共感するのが苦手なのですが、どうすればいいですか?」
という人が数多く出てくる。
場合によっては、思い詰めてしまう人すらいる。
しかし、そんな心配は無用だ。
結論から言うと、人に共感なんてする必要はない。
なぜなら、共感は、「共感するふり」だけでも十分意味があるからだ。
*
例えば、こんな会社がある。
ほとんどの案件を作ってきているAさん。
業績への貢献度から言えば、その人は紛れもないNo.1で、他の追随を許さない。
顧客からの評価も高く、その人指名で仕事が来る。
つまり、代替可能性が低い仕事をしている。
だから、その人は極力、雑用は他の人に任せており、会社では暇そうなときも。
一方で、その雑用を引き受けているBさんは、いつも忙しそうにしていた。
ただし、せわしく動いてはいるが、代替可能な仕事をしているだけであり、「その人でないと困る」という事はない。
とはいえ、「自分は一生懸命働いている」という自負が彼にはあった。
そして、微妙なバランスではあったが、揉め事はほとんどなかった。
なぜなら、Aさんが、合理的に行動していたからだ。
具体的には、彼はBさんに対して、いつも
「いつも忙しいよねー、わかる、わかるよ。たすかります。」
という、共感と配慮を示していた。
Aさんの方が、Bさんよりもはるかに会社にとって重要な仕事をしている。
しかし、Bさんへのそうした「配慮」が、Bさんの「私だけ忙しい」という不満を減らし、それによって、組織が上手く回っているようにも見えた。
*
ある時、私はこっそり、そんな微妙なバランスを保っているAさんに聞いた。
「共感力」がとても高いように見えるのですが、なぜAさんはそんなに人に寄り添えるのですか、と。
すると、少し考えてAさんは言った。
「共感なんて、かけらもしてないよ。」と。
そして言った。
「Bさんはいつも、無駄に忙しそうだと思っているし、正直なところ、誰でもできる仕事をしているだけ、とは思ってる。」
私はびっくりした。
「じゃ、なんで、あんな優しいことが言えるんですか」
Aさんは言った。
「雑用であっても、滞りなくやってほしいから。新しい人に変わると、教えるの面倒だし。」
私はきいた。
「という事は、いつもBさんに見せている共感は、演技だという事でしょうか?」
Aさんは呆れたような顔で言った。
「共感って、そういうもんじゃないの? そもそも、Bさんが何考えてるんかなんて、わかるわけないでしょ。別に分かりたくもないし、私もエスパーじゃない。ただ、共感しているように見せるだけなら「大変ですね」って言えばいいだけだから、言ってる。」
なるほど。
そういうことだったか、と思った。
共感力が高いと思われている人にも、2種類いるのだ。
一つは、相手の気持ちになれる、本当に共感力が高い人。
そしてもう一つが、共感力が高いように「見える」だけの人。
そして、外形的にはこの二つは区別がつかないし、効果も同じなのだ。
だが、前者は「共感」しているが、後者は「相手の思考を読んで、対応している」だけ。
つまり、AIと同じだ。
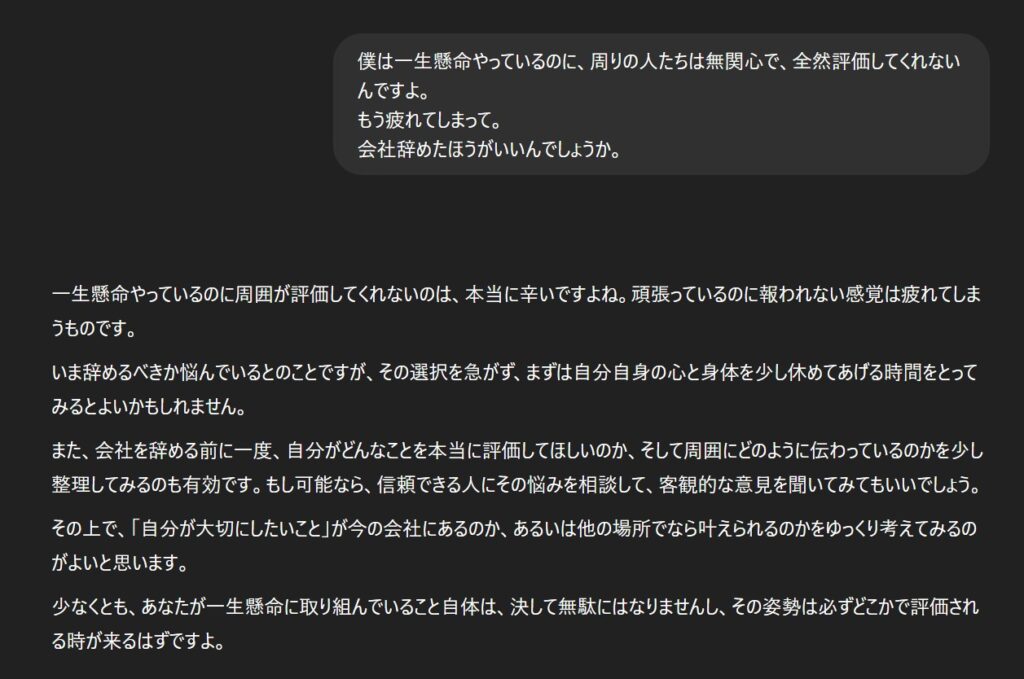
生成AIは実に「共感したふり」が上手い。
例えば、シロクマ先生が書いていたが、AIチャットの相談試験の生徒満足度は93%を超えている。
多分、人間がやるよりも良いのだろう。
これらは、一般的にはAIの良いところとみなされているし、実際、長所だろう。株式会社ZIAIが千葉県柏市で行った、AIチャット相談試験のトライアルでは、生徒の満足度は93.6%だったというが、その満足度はAIの性質にも支えられていただろう。
そういう点で、「共感」は必要ない、というのは合理的で、「共感しているように見えること」だけが必要なのだ。
実際、私は様々な職場で、「生成AIのような振舞い」であっても、職場ばうまく回れば問題ない、と考える人が、結構多いことを知っている。
「共感力が高いように見えるあの人」
が、本当に人に共感しているかなんて、誰もわからないのだ。
どうせ区別がつかないなら、共感は、「共感するふり」だけでも、十分意味がある、と思っても差し支えはない。
*
「礼儀」の定義を知っているだろうか。
礼儀とは、辞書にこうある。
「敬礼・謹慎を表す作法」のこと。
礼儀とはあくまで、外形的なもの。作法である。約束事である。
相手にとってどう見えるかの「表現」の問題であって、こちらがどう思うかの心持ちの問題ではない。
共感とは所詮、そのようなものであると、私はAさんから学んだのである。
重要視しすぎる必要はない。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
安達裕哉
生成AI活用支援のワークワンダースCEO(https://workwonders.jp)|元Deloitteのコンサルタント|オウンドメディア支援のティネクト代表(http://tinect.jp)|著書「頭のいい人が話す前に考えていること」82万部(https://amzn.to/49Tivyi)|
◯Twitter:安達裕哉
◯Facebook:安達裕哉
◯note:(生成AI時代の「ライターとマーケティング」の、実践的教科書)
Photo: