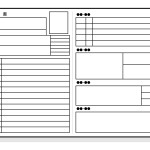ある意味衝撃的なコラム
少し前になるが、新聞に衝撃的なコラムが掲載された。
全国紙の文化欄で、書いたのはベテランの小説家だった。内容は、京都アニメーション事件とその被告について。
まとめると、
- この被告には小説やアニメに関わる資格などこれっぽちもなく、
- 言葉のセンスも整合性も想像力もない。
- 人の心を動かす物語など書けるはずがない。
と小説家は犯罪者を罵倒していた。
小説家の言うことは正しい。いかなる理由があれ、犯罪者は犯罪者であり、身勝手な理由で大量殺人を犯した被告なら同情の余地など少しもない。
ただ言えるのは、犯罪者を非難するのは簡単で、この内容の常識的なコラムならテレビコメンテーターでも書ける。
正しすぎるのだ。被害者や被害者の遺族の側に立って犯罪者と犯罪を糾弾するのは社会的に当然のことで、その犯罪者が書いたアニメだか小説だかを読みたくなんかないに決まっている。言わなくてもすでにみんなが思っている。
私にとって、小説家がこの正しすぎるコラムを書いたことがなにより衝撃だった。
誤解のないように念押しすると、私は別に犯罪者を擁護しようというのではない。
この事件に限らず、犯罪者も社会の一部であり、なんの因果もなく犯罪が起きることはない。
そして場合によっては、ある事件の犯人が自分だったかもしれないと想像することはあるし、想像しなくてはならない。
そして少なくとも小説家であるならば、その程度の想像力はあるはずだ。
想像力があれば、むしろこの犯罪を生んだ私たちへの厳しい問いかけでも良かったはずだ。ひたすら犯罪者を非難するだけでは、地下鉄サリン事件の時に「とにかく早く死刑にしてしまえ」と迫ったジャーナリストたちと変わらない。
言葉のセンスも想像力もないのは、小説家のほうではないのか。人の心を動かす物語など書けるはずがない、とは、自分のことを言っているのではないか。
常識的な小説家
小説家は一般的な世間や時代の流れに対して少しでも違った角度の視線がないと成り立たない。サッカーで言えばディフェンスの裏へ抜けるような攻撃で、ある小説家は「月の裏側」と表現したこともある。
犯罪者の側に立ち、犯罪者から見た世界を想像しなくてはならない。
小説家が常識的になり大人しくなると、小説はつまらなくなっていく。
中上健次は1990年、連続殺人犯の永山則夫が日本文藝家協会から死刑囚であることを理由に入会を断られた際、この決定に抗議して柄谷行人、筒井康隆とともに協会を脱会している。
小説家は政治家や評論家や法律家やジャーナリストがいえないことを小説に書かなければ意味がない。
犯罪者や社会的な異物の視点からしか見えない世界を、徹底的に個人の低い目線で物語へ組織していく作業こそ小説家の仕事なのだ。とこのように小説とはこうだ、といえるものでもないのは百も承知で言わなくてはならないほど事態は深刻なのである。
ただ、新聞ではなくても大手出版社の雑誌などでは、コラムも小説もポリコレ的にかコンプラ的にか知らないが慎重になっていることは確かだ。小説家が常識的になってしまったのではなく、常識的な小説家しか発表できなくなってしまったという一面がある。
たとえば犯罪を非難しない内容なら「犯罪者を擁護している」と取られかねないからだという。これと同じで、「女性蔑視と取られかねない」「人種差別と取られかねない」「障害者差別と取られかねない」などなど、連鎖しているのだ。
さらに言えば、「女性蔑視と取られかねない」「人種差別と取られかねない」「障害者差別と取られかねない」内容であっても、書くのが女性だったり外国人だったり障害者だったり、つまり当事者であればいくらか許されているという奇妙な事態まで発生している。
変えるべきは言葉ではなくまず実態
出版社やマスメディアの自主規制が小説家を常識的にしてしまっていることは、しかし出版社やマスメディア自身もよくわかっている。
よく言葉狩りといわれるが、問題は言葉狩りではなく、言葉の先にある文化まで狩られてしまうことにある。
たとえば差別的とされる言葉について。世界には様々な言語があり、国ごと・文化ごとに言語があり、それぞれの言語や言葉に体系があり、歴史がある。
差別的であるという理由だけで多様性に富んだ言語の世界から言葉を抹殺していき、しかもそれが正しいとされどんどん進行すればどうなるかはわかりきっている。
差別用語を使うことはコンプラやポリコレに反することから控えられるのが当然のようになっており、私も原則的には賛成する。
しかしたとえば熊が人間にとって危険だという理由で大量に殺害してしまえば、森の生態系は崩れて植物にも影響がある。生物の多様性を脅かす。
言葉と言語の多様性を破壊し、使うべきとされる言葉を限定し、言語の統一化が進めば、言語体系が崩れ、その地域、その国の文化や歴史が破壊されるのと同じことなのだ。
たとえばジェンダー視点から「女優」とか「奥さん」とか「嫁」といった言葉が不適切だとして、言い換えが進んでいる。
私自身も小説で関西弁の「嫁はん」をセリフで使ったら校閲からチェックが入ることがある。「妻」なら問題ないというのだが、関西人は自分の妻のことを間違っても「うちの妻は~」とは言わない。言葉狩りは単にその言葉だけを消滅させるだけでなく、標準語を起点にしている以上、結果的に方言を圧迫する機能があるのだ。
そもそも関西弁が方言で、関東弁が標準であるとはせいぜいこの100年くらいのことで、歴史的にそんな事実はない。1000年以上京都が都で、関東弁は「お国ことば」だった。
ある人にとって「不愉快だから」とか「差別なのでは」といった理由であらゆる言葉や表現を規制できるなら、どんな言葉や表現でも誰かを不愉快にしたり差別する可能性はあるため、ほとんどの表現ができなくなっていく。
いずれにしても、本来差別解消は人間の生理的な拒否感や嫌悪感や誤解から解消しなくてはならない。人の中にある差別的な心情や現実や実態という本来取り掛かるべき本質部分をすっ飛ばして、言葉を抹消してなくなったとするのはなんら本質ではなく、なくなった気がしているだけ、私たちが政治を批判する時に言う「やってる感」と同じだ。
しかも私たちは少なくとも一度同じことを経験している。
80年前の言論弾圧や適性語の言い換えといった表現規制は、今となっては戦争と共に「なぜあんなことをしてしまったのだろう」という反省対象になっている。
「差別を助長する・子供の教育に悪い・悪い風潮を助長する・不適切ではないか」といった規制が、いつのまにか自由な表現や言論を封じていき、芸術分野や小説への弾圧へ向かえば、かつて私たちが戦争に巻き込まれていったいきさつと驚くほど重なっている。
特に日本人は最近で言うとコロナの自粛警察などでもわかるとおり、どっと一方向へ流れる習性が強い。
やはり半世紀後か来世紀にならなければ、反省の機会は訪れないのだろうか。
「君と世界の戦いでは、世界に支援せよ」
差別的とされる言葉に対する抗議は、主に社会的弱者や被差別サイドから告発される形でスタートする。
かつては差別されがちなマイノリティの立場での抵抗的で告白的なテーマの文学はそれなりの魅力があった。
ところが今でいうLGBTQや多言語・人種系、あるいはジェンダー・障害者など今まで被差別的とされた分野がマイノリティでなくなった今、告白的・抵抗的にそれをテーマとしたところで文学にはならない。
マイノリティが表面上はどんどん受け入れられていく社会は、それだけ見ると寛容な社会に見える。
しかし言い換えれば異物をなくして分類可能にする「みんな同じで、みんな良い」緩やかな管理社会。一方でまだ容認されていないとされるマイノリティなら攻撃対象となる。
2024年現在、LGBTQやジェンダー関係の小説は無数に書かれており、障害者の小説が賞をとったりもしている。書きやすくなったので、それが増えるのは自然ともいえる。
しかし、小説本来の意義やおもしろさでいえば、書きづらい、言いづらいことを書くからこそ切実で読んだ人に刺さる。
フランツ・カフカに、「君と世界の戦いでは、世界に支援せよ」という言葉がある。
犯罪や差別は憎い。筆舌に尽くしがたい憤りを覚える。しかし怒りに任せて叩きまくったり死刑にするのが効果的なのか。多くの被害者や遺族が言う、「もう2度とこんなことが起きてほしくない」、そのためにはまず加害者の側に立ち、加害者から見た世界を描写することからはじめるしかないだろう。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
かのまお
ライター・作家。ライターとしては3年、歴史系や宗教、旅行系や建築などの記事を手がける。作家は別名義、新人賞受賞してから16年。芥川賞ノミネート歴あり。
Photo by:Super Snapper