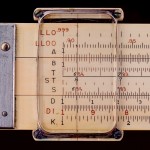「鬼滅の刃」が絶好調だ。
あえて説明する必要もないが、劇場版の興行収入がえらいことになっていたり、単行本の売り上げがドえらいことになっていたり、最終巻を求めて長蛇の列ができたり、めちゃくちゃ転売されたり、わけわからんコラボグッズが出たり、とんでもない状況だ。
見ると、町ゆく子どもたちのマスクまでどこかで見たような柄のものになっている。
これはもう社会現象と言っても過言ではないのだろう。
この「鬼滅の刃」はすごい。
たぶんどえらい作品だ。
そんなもの詳しくなくても分かる。
ただ、「たぶん」と表現しているのは、実はまだ観たことがないからだ。
そう、僕はこの作品に全く触れていないのだ。
原作も見てなければアニメも見ていない。もちろん劇場版も見るつもりはない。
やはり、たとえ末端といえども文章を書いたりして表現活動をしている者として、こういった作品は必ず抑えておく必要がある。
社会現象は多くの人に暗黙のうちに共有される事象であり、それをもとに表現をしていくことは基本中の基本だからだ。
そういった意味で必ず読まねばならない作品なので、単行本を全巻、近所のヴィレッジヴァンガードで購入した。
最終巻もつい先日、Amazonから届いた。
それらは威風堂々と本棚に並んでいる。
だからいつでも読める状態ではあるのだ。ただ、それでも僕は読まない。
様々なメディアから嫌でも流れてくる「鬼滅の刃」の情報は、この漫画が確実に面白いことを物語っている。
おそらく、読めばはまる。めちゃくちゃはまる。泣く。グッズ買う、コラボグッズも買う、劇場にも何度も足を運ぶ、「ストロングゼロの呼吸」とか言い出す。
それくらいドはまり間違いなしだ。それはわかりきっている。けれども、どうしても読み始める気がしないのだ。
「新しいものはしんどくてなあ、おっちゃんはもうこれだけだよ」
鬼滅の刃と対峙すると、あの時、そう言ったおっさんの言葉が思い出されるのだ。
あれは小学生の頃だった。
ちょうど、鬼滅の刃に夢中になっている現代の小学生と同じように、僕たちはビックリマンチョコに夢中だった。
シールだけ入手してチョコを捨てる子どもが続出し、社会問題になった時期だったと思う。
当時、うちの母親はアル中だった。
学校を終えて家に帰ると、彼女はだいたい飲んだくれて眠っていた。
彼女はちゃんとしているときとアル中状態な時の落差が激しく、普段は元気でちゃきちゃきしているのに、いったん闇の領域に足を踏み入れるとそれが長く、そして重かった。
いま思うとなかなかにひでー家庭環境だなと感じるけれども、当時の僕はそれが普通だと思っていた。
ただただ、今日の夕飯はどうなるんだろう、弟にも食べさせないと、また父親が帰ってきて夫婦喧嘩になったら嫌だな、ということだけを考えていた。
ある日のことだった。
いつものように学校から帰ると、やはり母親は飲んだくれて眠っていた。
昼間だというのに居間は暗く、酒の匂いに満たされていた。
いつもなら、やはり同じように夕飯の心配をして、僕と弟が夜に食べるものあるかなと冷蔵庫を開けるのだけど、その日は少し様子が違った。
台所をゴソゴソしていると、母親がやってきたのだ。
酒の匂いをプンプンさせて亡霊のような佇まいでやってきた。
足元はおぼつかず、あまり呂律もまわっていないようだ。
当時はそういうものだと思っていたが、大人になってやっとわかる。
相当の量を飲んでいないかぎりこうはならない。
「ごめんね、ごめんね」
母は泣きながらそう言った。
そして、ボロボロになった財布からこれまたしわくちゃの千円札を数枚取り出して言った。
「これでお酒を買ってきてほしい」
一線を越えたな、子ども心にそう思った。
これまではどんなに追い込まれても自分で準備した酒を飲んでいたようだった。
バレバレだったが、隠れて飲んでいるという体裁だけは保っていたのだ。
それが、ついに子どもに酒を買いに行かせるまでになったのだ。
彼女もまた相当に追い込まれていると感じたし、確実に何かを踏み越えて未知の領域へと入り込んだと感じた。
彼女は彼女で苦しかったんだと思う。
「いいよ、買ってきてやる。なんてやつ買えばいい?」
僕は彼女のことをかわいそうに思った。
だから、千円札を受け取り承諾した。
そして彼女は申し訳なさそうに付け加えた。
「鬼ごろしってやつを買ってきてほしい。1.8リットルのパックのやつ」
日本酒だったか焼酎だったか忘れてしまったが、当時は「鬼ごろし」という比較的安価な酒が売られており、彼女はその鬼ごろしのヘビーユーザーだった。
生まれ育った町は漁師町で、飲んだくれの多い風土だったけど、その飲んだくれたち御用達しの酒、それが「鬼ごろし」だった。
たしか緑と白のパッケージに何体かの鬼が水墨画みたいに描かれていたように思う。
そして相撲取りみたいなフォントでドーンと「鬼ごろし」とかかれていた。
それを買ってきてくれとのことだった。
千円札を握りしめて小走りに酒屋へと向かう。
なんだかすごく胸が痛かった。
正体不明に胸が痛かったのを今でも思い出す。
家から少し離れた場所に、駄菓子とちょっとした日用品を売っている商店と酒屋を合体させた店があり、この辺で酒を買うとなるとそこしかなかった。
正直なところ、あまり行きたくない場所だ。
店の前では、駄菓子屋パートの入口のところで同級生たちがビックリマンチョコに興じており、やれ、お守りシールがどうとか、箱の左側列の後ろから4番目にヘッドシールが入っている確率が高い、などと大騒ぎしていた。
「ビックリマン、入荷したらしいぞ! ひとり3個まで!」
僕の姿を認めた同級生が声をあげる。
当時はあまりにビックリマン人気が高すぎて、入荷すると大騒ぎになったし、個数制限が設けられていることがほとんどだった。
僕らにとって、あの40個だかのビックリマンチョコが敷き詰められた箱は煌びやかな宝石箱に近かった。
いつかは箱買い、そんな夢を抱いていたように思う。
「いや、買わないんだ」
それどころではないので、同級生の誘いを断る。
ビックリマンではなく鬼殺しを買わなければならないのだ。
彼らのことを無邪気だと思った。
親のことも夕飯のことも弟のことも、なにも心配せずビックリマンに興じることができる彼らを羨ましいとさえ思った。
お前らは親に頼まれて鬼ごろしを買いにきたりしないんだろうな、そう思うと無性に羨ましかった。
駄菓子屋パートの入口を通り抜け、酒屋パートの入口に向かう。
ガラガラと立て付けの悪い引き戸を開けると、思った以上に大きな音がした。
その音を合図に、中にいた大人が一斉にこちらを見た。
この酒屋は、角打ちという形態をとっていた。
今で言うところの酒のイートインみたいなシステムだ。
酒屋なので酒を売っているのだけど、ちょっとしたカウンターが備えられていて、買った酒をその場で飲めるようになっていたのだ。
はやい話、酒屋と立ち飲み屋が合体したスタイルだ。
前述したように、生まれ育った街は漁師町で、朝の仕事を終えた漁業関係の人が昼間っからこの角打ちで飲んだくれていた。
おまけに、酒屋の店主がなかなかセクシーなマダムだったので、多くのおっさんがそのマダム目当てに通っていた。
僕らが店の周辺で遊んでいると、この酔っ払いたちが絡んできて冷やかしたり、怒鳴ったり、立ちションしたり、あまりいいものではなかったのでこの酒屋パートにはあまり近づきたくはなかった。
ただ、今日は違う。
鬼ごろしを買うために入らねばならないのだ。
「おやおや、お酒ですかな? まだ早いぞー」
南海ホークスの帽子をかぶったおっさんが冷やかすように声をかけてきた。
これだからこの場所は嫌いなのだ。
同時に周囲の大人たちがドッと涌き、からかうように笑った。
「おれは中学から飲んでたぜ」
「本町の沢田は小6かららしい」
「あいつは嘘つきだ」
そんな、田舎町のくだらない大人にありがちな謎のマウント合戦が繰り広げられた。
「鬼ごろしをください!」
そんなおっさんどもは無視をして、カウンターの奥でクソ細長い魔女みたいなタバコをふかしているマダム店主に注文した。
「お、鬼ごろしか!」
「あれはいい酒だぞ」
「俺の血液は鬼ごろしでできている!」
また、やいのやいのと冷やかし、囃し立てるおっさんたち。
特に南海ホークスのおっさんはひどくて、歌舞伎っぽい独自の鬼ごろしポーズを「鬼ごろし!」と叫びながらコミカルに決めて見せた。
また、ドッと店内が湧いた。
「1.8リットルのパックにやつください。いくらですか?」
おっさんどもを無視してマダム店主に詰め寄る。
マダムは酒の棚からそっと位牌でも取り扱うような手つきで1.8リットルパックの鬼殺しを手にした。
「おつかいかなー? お父ちゃんが夜に飲むお酒かなー?」
南海ホークスが囃し立てる。
僕はキッと睨みつけて言い放った。
「違います。お母さんのやつです。もうお酒を飲まないと何もできないみたいなので」
僕の言葉に、店内の時が停まった。
あれだけ囃し立てる笑い声が、凪のように止まったのだ。
「お母ちゃんが……?」
南海ホークスが急に真剣な顔つきになった。
かなり深刻な空気が流れた。
それから、ご飯はどうしてるだとか、それ以外の家事はどうしてるだとか、そんなありきたりな質問が続いた。
「絶対にダメだ、そんなのダメだ。おい、売らないでくれ」
南海ホークスがマダムにそう告げる。
面倒なことになった。いいから売ってくれよと思った。
現代では、たとえお使いであっても子どもに酒を売ってくれることはない。
けれども当時は当たり前のことで、子どもがお使いで酒を買うなんてそう珍しいことではなかった。
だから急に深刻なトーンになってしまったことに戸惑いを隠せなかった。
「いいから売ってくださいよ、鬼ごろし」
そう懇願するが、南海ホークスは引き下がらない。
ゆっくりと首を横に振った。
「ダメだ」
確固たる信念みたいなものを感じる勢いだった。
そもそも売る売らないは店主であるマダムの権限で、南海ホークスはただの客だ。
なんの権限もないのだが、それでも絶対に売らないという鬼気迫るものを感じた。
雰囲気からなんとなく他の客や南海ホークスが言いたいことが分かった。
おそらく、母ちゃんがアル中気味であることが良くない、と言いたいのだ。
家庭をほっぽり出し、子どもをほっぽりだし、潰れている、そんなやつに売ってはいけない、みたいなことを言いたいのだと思う。
けれども、家庭をほっぽり出して酒に飲まれているのは、昼間から飲んでいるここの面々だって同じだし、彼女だけが酒に飲まれてはいけないなんて理由はない。
みんな等しく苦しいし、酒に逃げたく思うのかもしれない。
この世で母親だけがそうなってはいけないなんて理由はないはずだ。
母親だって苦しいのだ。
「鬼ごろし売ってください。母さんだって苦しいんです」
母親がそうなるのは良くない、みたいなありきたりのセリフを言われる前に先回りしてそう告げた。
何が良いのか、何が悪いのか、わからない。
ただ、彼女のために鬼ごろしを買わねばならなかった。
南海ホークスは首を横に振った。そしてゆっくりと口を開いた。
「いいか、酒に飲まれて潰れる、それが良くないことなんてここにいるみんな分かってる。だから俺たちがお前のお母さんにとやかく言うつもりも資格もねえよ。みんな酒に飲まれたい。苦しいからな。ただな、お前が買っちゃならねえ」
南海ホークスは真っすぐと射抜くような視線をこちらに向けていた。
「お前が買うとな、大きくなった時、自分も加担したって後悔するんだ。これからお前の母ちゃんがもっと酷くなるかもしれない、病気になるかもしれない、取り返しのつかないことになるかもしれない。その時に、あの時、酒を買って加担したのは自分だって後悔する」
その言葉は、なんだかずっと感じていた違和感みたいなものの答えだったようだった。
僕は、ただただ泣いた。
ダムが決壊したかのように、声を押し殺してずっとずっと泣いていた。
何を思っていたのだろか母が可哀想だったのだろうか、自分が可哀想だったのだろうか。いまとなってはよく分からない。
結局、鬼ごろしは売ってもらえなかった。
ただ、南海ホークスをはじめとする面々が、依存になりにくく、それでも満足する酒を選ぼうとということになった。
ビールがいいだとか、酎ハイみたいなものがいいだとか、そんなことを真剣に話し合っていたと思う。
とにかく、鬼ごろしは良くない、あれは鬼を殺すのではなく鬼を作る酒だ、そう言っていた気がする。
もちろん、選ぶのもおっさんたち、金を出すのもおっさんたち、お前が加担したことにはならない、そういってビニール袋を渡された。
「これを飲ませれば大丈夫だ」
おっさんたちは本当に真剣に相談していた。
負担なく、依存なく、それでいて満足いくもの、たぶん、弱めの酒を選んでくれたんだと思う。
母は鬼だったのかもしれない。
でも、これを飲めばいつかきっと良くなるはず。
この酒は鬼を倒すためのものだ。
そう信じ、ビニール袋を抱えて来た時よりも足早に家へと向かった。
居間にはまだ酒の匂いが充満しており、闇のように真っ暗だった。
3枚くらいの布団がぐちゃぐちゃに折り重なったその奥に、鬼がいた。
「これ、いいらしいから飲みな」
そう言って渡す。
おっさんたちが選んでくれたのはビンだった。すこしボテッとしたビン、暗すぎてラベルは見えない。
「ごめんね、ごめんね」
母はそう言って蓋を開け、一気にかっこむ。
よほど飲みたかったらしい。
「いいから、いいから」
そう言った瞬間だった。
ブホーーーーー!
母は、ちょっとノリの良いマーライオンみたいに口に入れたものを吐き出した。
グレートムタの毒霧のように吐き出した。
なんだなんだ、あいつら毒でも盛りやがったか。
そう思い、急いでビンのラベルを見る。
そこには衝撃的な文字列が並んでいた。
「めんつゆ」
酒ですらねえ。めんのつゆじゃねえか。
あいつらなに考えてるんだ。「めんつゆ」じゃねえか。
僕の記憶が確かならヤマキの「めんつゆ」だったと思う。
どうやらビールはダメだ、思ったよりアルコールが強いだとか、ああでもないこうでもないと議論するうちに迷走してしまい、最終的に「めんつゆ」になったようだった。
悪いことに、酒屋は日用品を売る商店と繋がっていたため、「めんつゆ」の在庫もあった。しっかりあった。
不思議なことに、あのあと、母は闇の領域に足を踏み入れることが減った。
そして、いつのまにか酒なんかとんでもないみたいな状態になっていた。
もしかしたら「めんつゆ」が効いたのかもしれない。
鬼ごろしではなく「めんつゆ」こそが鬼を殺す刃だったのかもしれない。
ストロングゼロが入ったグラスを傾けながら思い出す。
こうしておっさんになり、眠る前にストロングゼロを飲むようになってよく分かる。
苦しかった母も、南海ホークスも、あの時の僕も、みんなのことがよく理解できる。
それでも「めんつゆ」を選んだ経緯だけはちょっと理解できない。
あのあと、公園で遊んでいると、南海ホークスが箱を持ってきてくれたんだった。
「ほらよ、子どもはこういうのを買いに来るもんだ」
そういって、ビックリマンチョコを箱ごとくれた。
夢にまで見た宝石箱だ。
入荷してきたやつをマダムに頼み込んで一箱ゆずってもらったらしい。
満を持して、左の列の後ろから4番目のチョコを開封する。
キラキラのヘッドシールだった。
狂喜乱舞する僕に南海ホークスは言った。
「好きという気持ちはいいことだ大切にするといい」
その時の僕にはその意味が分からなかった。
本当に一箱まるまるビックリマンチョコが貰えることが信じられなかった僕は、妙に遠慮してしまい、半分はおっちゃんが持って帰って開けてくれと言った。
おっちゃんもビックリマン集めようよと提案したのだ。
僕の提案に対し、南海ホークスはチョップのように右手を前にだし小刻みに左右に振った。
「もう新しいものはしんどくてなあ、おっちゃんはもうこれだけだよ」
そう言って酒を飲む仕草を見せた。
その時から今に至るまであの時の南海ホークスの言葉の意味が分からなかった。
ただ、同じくらいの年齢になり、空前のブームである「鬼滅の刃」に対峙してやっとわかった。
そう、新しいものはしんどいのだ。
人でもモノでも、何かを好きになり、のめりこんで夢中になっていくことは幸福なことだ。
けれども、同時にそれらは色々なものを消費する。
気力だったり、体力だったり、経済力だったり、様々だ。
何度かそれらを繰り返してきた人のいくらかは、それ以上の摩耗に耐えられない瞬間がやってくる。
新しいものが受け入れられなくなってしまう。
それを老化と言ってしまえばそれまでだが、おそらくは防衛本能なのだろう。
みんな、何かを好きになり、何かに夢中になり、なにかに摩耗し、何かに失望し、何かに傷つけられてきた。
のめりこむことに対して待ち受ける結末は幸福でないことがままある。
それらを知った時、自分を守ろうとするのではないだろうか。
これ以上はきつい。そう思うのだ。
あの時、母は鬼だったのだろうか。
母も何かから自分を守ろうとしたのかもしれない。
摩耗の果てがそうだったのかもしれない。
ただ、そこで逃げる先がお酒だったのは少し可哀想なことだ。
「鬼滅の刃」に対峙した僕は、その気持ちがなんだかよくわかる。
きっと摩耗するのだ。
だから読むのを躊躇してしまう。
好きになるのが分かりきっていて、もうあまり何かを好きになりたくないから。
「でもまあ、まだ酒に逃げるのは早いよな」
でも、僕はまだまだ大丈夫だ。
まだまだ何かを好きになる余地がある。
母のこと、南海ホークスのこと、あの日の自分、めんつゆ、それらを思い出しながらストロングゼロを飲み「鬼滅の刃 1巻」を手に取る。
ストロングゼロの呼吸!
そう叫びながらページをめくる。
なにかを好きになることの大切さを噛み締めながら。
「AIでここまでできるの!?」その場で“魔法”を体感。
マーケティング業務の生産性を劇的に変えるAIツール「AUTOMAGIC」。
本セミナーでは、ツールの設計者でありコピーライターでもある梅田悟司氏が、開発の背景から具体的な使い方までを徹底解説。
リアルタイムのライブデモを交えて、“自分で・すぐに・プロ品質”のコンテンツを生み出すワザを体験できます。

こんな方におすすめ
・自社サービスの魅力をもっとラクに言語化したい
・企画・コピー・SEO記事を“今すぐ・自分で”作成したい
・社内でAIツールを導入したいが、現場の負荷が心配
・提案資料づくりに追われるマーケター・営業担当者
<2025年5月30日実施予定>
AUTOMAGIC使い方セミナー|トップコピーライターが教える“魔法のようなAI活用”の実践法
「商品情報を入れるだけ」で高品質コンテンツが次々と生成される—— そのプロセスを、開発者本人が実演・解説する特別セッションです。【セミナー内容】
1. AUTOMAGICとは?
・ツール開発の背景と目的
・構築されたプロンプトの思想
・なぜ“実用で使えるクオリティ”が可能なのか?
2. 入力から出力までの流れ
・入力情報の整理ポイント
・出力されるコンテンツの種類(キャッチコピー/SEO記事/企画提案 etc.)
3. ライブデモ:その場でコンテンツ作成
・実際の商品情報をもとにリアルタイムで生成AIが出力
・参加者からのリクエストにも対応
4. 質疑応答・個別相談タイム
・導入前の不安や活用方法について、その場でお答えします
【登壇者紹介】
梅田 悟司(うめだ・さとし)
コピーライター/ワークワンダース株式会社 取締役CPO(Chief Prompt Officer)/武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 教授
代表的な仕事に、
・ジョージア「世界は誰かの仕事でできている。」
・タウンワーク「バイトするなら、タウンワーク。」
・TBS『日曜劇場』『VIVANT』のコミュニケーションディレクションなど。
著書『「言葉にできる」は武器になる。』はシリーズ累計35万部以上。
生成AI時代の「言葉の設計者」として、AUTOMAGICの開発にも参画し、プロンプト設計を担当。
日時:
2025/5/30(金) 14:00-15:00
参加費:無料
Zoomビデオ会議(ログイン不要)を介してストリーミング配信となります。
お申込み・詳細
こちらウェビナーお申込みページをご覧ください
(2025/5/22更新)
【プロフィール】
著者名:pato
テキストサイト管理人。WinMXで流行った「お礼は三行以上」という文化と稲村亜美さんが好きなオッサン。
Numeri/多目的トイレ
Twitter pato_numeri
Photo:Emma Thomas,Ignat Gorazd