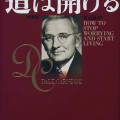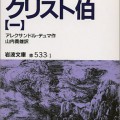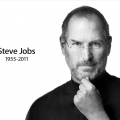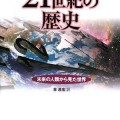家庭料理って、素晴らしいです。自分で作ったものを自分で食べるわけですから、安心だし、安価だし、何より美味しいです。ちょっと田舎に遠出して、「道の駅」なんかによっちゃった日には、新鮮な農産物を買ってきたりして。
家庭料理って、素晴らしいです。自分で作ったものを自分で食べるわけですから、安心だし、安価だし、何より美味しいです。ちょっと田舎に遠出して、「道の駅」なんかによっちゃった日には、新鮮な農産物を買ってきたりして。
休日に仕事の話をするつもりは特に無いんですが、料理って、結構仕事に通じるところもあるんで、面白いです。基本が大事なところとか。逆に基本をしっかり覚えると、いくらでも自分で工夫できるんで、どんどん幅が広がります。
で、料理を始めるなら、やっぱり定食から憶えるのがいいと思います。品数がある程度あって、毎日でも食べられる飽きさせないメニューを覚えると、料理も楽しくなります。おぼえるなら、こんな順番がいいでしょうか
下に、お手軽に料理するやり方を書きます。
1.ご飯の炊き方(ついでに炊き込みご飯とかも)
炊飯器。憶えるなら米の研ぎかた、水加減だけでOK!炊き込みご飯は、具を入れて、水を出汁に変える。コツは、炊き上がったらすぐに蓋を開けて蒸気を逃がすことだけ。
2.お味噌汁の作り方(具は冷蔵庫に入っているものならなんでも美味しい。野菜でも、肉でも魚でも、とりあえず入れる)
まず出汁をを取ろう。最近は鰹節などがパックになっているだし袋みたいなものが売っているので、それと水を鍋に入れて煮る。沸騰して出汁が取れたら具を入れて、味噌を入れて一煮立ちさせる。10分で出来ます。
3.魚の焼き方(あじ、さんま、さば、キンメ、ほっけ、鮭、かます、イワシ、など。生魚は面倒なのでヤメる。干物がおすすめ)
スーパーで買ってきて、弱火~中火でフライパンで焼く。グリルや網は不用。洗い物も少なくてすみます。
4.煮物の作り方(じゃがいも、レンコン、人参、こんにゃく、ごぼう、しいたけ、カボチャ、大根、ふき、ひじき、切り干しだいこん、里芋、豚肉、鶏肉、どれでも作り方は一緒)
小さい鍋を用意する。切った材料をざっと炒めて、酒、醤油、砂糖、水を入れて、アルミフォイルで落とし蓋をして水が減るまで、時々かき混ぜながら煮る。コツは火加減を弱めに。
5.炒めものの作り方(煮物が面倒な場合)
まず醤油、酒、砂糖、塩、ミソを小さいカップに入れて、合わせ調味料をつくる。(味見してください)切った野菜と油をフライパンに入れて、動かさずに焼き目がつくまで焼く。一旦取り出して(ここ重要!)肉を入れて焼き、焼き目がついたら、取り出しておいた野菜と合わせ調味料を入れて、かき回して出来上がり。
はい、定食の出来上がり。
文字だけだとよくわからん、という人は、この本がお勧めです。レシピはそんなに多くないのですが、基本が身につく献立がたくさん。ちょっと古い本なのですが、いい本です。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。