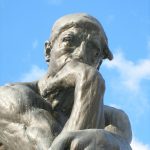長崎に行ってきた。

長崎という街は、私にとって2つの出来事があったという点で、訪れてみたい場所だった。
一つは、核兵器を使用された街であること。
もう一つは、キリシタンへの弾圧があったこと。
いずれの事件とも、「ある集団が、別の集団に対して、非道な行いをした」という点で共通している。
「人は時として酷いことをする。」と、他人事のように思う人も多いかもしれない。だが、このような行為は、歴史的に見れば、特に世界中で珍しいものでもない。
大量殺戮は現代に至るまで頻繁に発生している。
なぜか。
個人レベルでは忌避したくなるような行動でも、集団や権威によって正当化さえできてしまえば、「正義」や「秩序」の名のもとに、人間はかんたんに一線を超えてしまうからだ。
*
かつて私は、ある一つの部門の責任者をしていたことがある。
売上目標の達成、コストの管理、人事評価……やるべきことはたくさんあった。
そしてその中で、経営陣から一つの難しい要求があった。
それは「経営方針」の浸透と、違反者の処罰だ。
経営方針の浸透、というと世の多くの人は「形だけ」というイメージがあるかもしれない。
だが、私が所属していた部門は中小企業向けのコンサルティングを行っている部門だったので、自社のマネジメントは、中小企業向けの「商品」を実験する場だった。
そして、中小企業に抽象的な「経営方針」はあまりウケない。「明らかで、すぐに効果のあるもの」が、中小企業に売れる。
そのことから、私の所属していた部門の経営方針は、かなり具体的だった。
例えば、
「他人のせいにしない(原因自分主義)」
「変化を常に受け入れよう」
「まずは量を追求し、それを質に転換させる」
といった具合だ。
これであれば、社員が「他人のせいにした」瞬間、「それは方針に違反している」と指摘できる。
変化を要求して、それを拒んだ場合にも、あるいは「効率が悪い」などと言った発言も、「それは方針に違反している」と、指摘できる。
こんな「経営方針」が、100以上(!)もあったのが、当時の私が所属していた部門だった。
もちろん、これだけの方針があれば、違反者もでる。
「お客さんのせいにするな!悪いのはあなただ!」と。
「なぜ上司の指摘を受け入れないんだ!あなたは違反者だ!」と。
「◯件テレアポをしていない!あなたは違反者だ!」と。
今見れば、つくづく理不尽な話だ。
「時と場合による」を無視して、原理原則を常に適用しようとすることに、そもそも無理があるのだ。
しかし、当時の私は、経営者のこの方針に、全力で従っていた。
無論、ときおり、私もこの「経営方針による統制」が理不尽に感じることはあった。
が、私は管理職であり、体制側であった。
また、経営陣が大真面目にこれに取り組んでいるのを見て、「今の会社には必要なのかもしれない」と、自分を納得させていた。
しかも、各々の方針は、それなりに正しいことを言っている。反対のしようもない。
だが、中には、強く反発する現場の人間もいる。
それが数回続くこと、つまり経営方針、および経営陣に対して批判を繰り返す人物は「我が社には合わない人物」という経営陣からの烙印が押され、評価を下げられた。
そんな活動に邁進していたある日、私は上司に呼ばれた。
質問がある、という。
「なあ、彼の最近の様子はどうだ?」と上司は言った。
彼、というのは最近経営方針への違反を起こした、中途採用の人物だ。
私は
「最近、方針への違反は起こしてないと思います。きちんと指導しました」
と答えた。
しかし、上司はそれを聞いても険しい表情を崩さなかった。
「そうか、しかし、最近聞いたところでは……」と、上司は、彼の体制への批判、経営方針の違反状況を語る。
私は「そうですか。それは困りましたね。きちんと指導します」と答えた。
しかし、最後に上司は言った。
「彼は、うちの会社には合わないと思うんだよね。」
それは要するに、「クビにしろ」という命令だった。
もちろん、私はそれに従った。
「秩序」の名のもとに。
だが、振り返ると私はそれ以来、自分を「善良」であるとみなせなくなった。
組織が要求する「秩序」の名のもとに、私はある人物に制裁を加え、組織から排除することを実行してしまったからだ。
「クビにする」のと「爆弾を落としたり、拷問したりするのは違う」という方もいるかも知れない。
だが、私は実感として、思う。
本質的にはおそらく、なんの違いも、ない。
だって、それが「正義」だったから。
「秩序」を守るために必要な行為だったから。
そのように言い訳すれば、人間はかなりの非道な行為に手を染めることができるという、実感が私にはある。
*
長崎のキリシタン弾圧と、それに伴う信仰のゆらぎを描いた、遠藤周作の「沈黙」という作品がある。
カトリック教会から厳しく批判された、問題作だ。
遠藤周作は「拷問に屈した弱者」と「信仰を守り通した強者」の面から、作品を描いた。
だが、私はこの作品を読み「弾圧をした側」に興味を持った。

例えば、上はマーティン・スコセッシが映像化した、雲仙で熱湯を浴びさせられる、映画での拷問のシーンだ。
実際にそれが行われた「雲仙地獄」に行ってみれば、いかにその拷問が苛烈であったか、容易に想像ができる。

こんな行為が平然とできる人は、もはや普通の神経ではないと間違いなく思うだろう。
だが、侍たちは「お役目」を黙々と果たした。
もちろん、彼らは「秩序」を守るためにやったのだ。
昔の人は道徳観が違う、という方もいるかも知れない。
しかし、原爆はどうか。それが落ちたのはたったの数十年前である。
人間の本質はあまり変わっていない。
人間に非道な行いをする側は、何を考えていたのだろうか。
正義を語るのは、どんな気持ちだろうか。
自分が正しいと思って、それを実行したのだろうか。
後悔はあったのだろうか。
死ぬ前に、非道な振る舞いを気にしただろうか。
組織や体制、システムが要求する「正義」に基づいて、人を裁いたり、制裁を加えるのはとてもかんたんだ。
なぜなら「私は悪くない。私が行っていることは正しい」といい切れるからだ。
だが、私が長崎で見たのは「正義」の名のもとに行われた、非道な行為の数々であり、それを実行した人々の記録だった。
*
いま、私は現実でもインターネットでも、極力「正義を語る人」やら「秩序の守り手」には近づかないと決めている。
「正義」を語ることもできない。
私は弱く、そして「正義」「秩序」を語って、いともかんたんに私は体制に与し、人に非道な行いをした前科があるからだ。
長崎は、そういう意味で、私にとって特別なのである。
◯Twitterアカウント▶安達裕哉(人の能力について興味があります。企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働者と格差について発信。)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
◯Twitterアカウント▶安達裕哉
◯安達裕哉Facebookアカウント (安達の記事をフォローできます)
◯Books&Appsフェイスブックページ(Books&Appsの記事をフォローしたい方に)
◯ブログが本になりました。