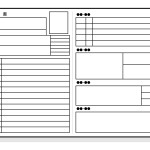日本プロ野球史上に残る名選手・名監督であった野村克也氏が2020年2月11日、永眠された。
享年84。
本塁打、打率、打点の全てでトップとなる三冠王に戦後初めて輝いただけでなく、強肩のキャッチャーとしても知られた名選手だった。
もっとも、現役を引退したのが1980年だったので、おそらく選手としての野村を記憶しているのは50代以上の世代だろう。
30~40代には、監督としての野村の方が印象深いかもしれない。
そして、テレビのゴールデンタイムからプロ野球中継が無くなってしまった昨今においては、おそらく20代より若い世代にはプロ野球そのものが、縁遠いものになっているのではないだろうか。
野球に興味がない人も多い時代になってしまったが、そんな世相にあっても、野村が残した「ID(Important Data)野球」は、全ての経営者、ビジネスパーソンが学ぶべき価値がある考え方だ。
その名の通り、運用方針、作戦、指揮命令をデータに基づいて意思決定し、あるいは指示を出し、組織と部下を動かそうという考え方である。
そこに曖昧さは一切ない。
「いいか、クサいところを攻めろ」
などという、いかにも頭の悪い指導者の指示もなければ、「はい!」と答えるような無意味な素直さも要求されない。
精神論が幅を利かせ、「練習中は水を飲むな」と、根性が何よりも重視されていた昭和~平成初期のスポ根とも無縁だ。
野村の采配は常にデータに基づき、相手の強さを避けて味方の強さを活かし、勝てる可能性を最大化するよう組織と個人に要求するものだった。
そして、「そこまでやってもダメだったら、仕方がない」と達観し、その結果責任を全て引き受け、21世紀の理想的な指導者像の一つの形を築いた。
このようなリーダーとしての生き様を学び、ビジネスに活かさない手はないはずだが、では具体的に経営者やリーダーはここから何を学び、何をどう実践すれば良いのだろうか。
大逆転-コンチネンタル航空奇跡の復活
若い世代には余り聞き覚えのない航空会社かもしれないが、かつてアメリカに、コンチネンタル航空という大手航空会社があった。
2012年にユナイテッド航空に吸収合併されてすでに存在しないが、合併当時の企業規模は全米4位を誇り、1996年にはAirline of the yearを受賞するなど、堂々たる名門であったと言ってよいだろう。
しかしこのコンチネンタル航空。
かつて、連邦破産法Chapter11(日本の会社更生法に相当)の適用を2度も受けるなど、散々な経営状態の会社であった。
経営再建当時、従業員は社章を外して行動し、勤務先を身内に聞かれても、誰もコンチネンタルの社員であることを話さない惨状だったという。
それほどまでに、コンチネンタルの社員であることを人に知られることそのものが恥であると、従業員が考えていたということだ。
それもそのはずで、1990年代の初頭、同社は全米の主要航空会社10社の中で
・定時到着率最下位
・乗客の手荷物紛失率 ワースト1位
・乗客10万人あたりの苦情件数 ワースト1位
[1]と、会社として末期とも言える状況にあった。
おまけに、オーバーブッキングなどを理由として、予約をしたにも関わらず乗れない乗客の数も常に首位争いを繰り広げていたというおまけ付きである。
端的に言って、
「乗れるかどうかあてにならない。乗れたとしても、いつ飛ぶのか、いつ着くか、どこに着くかわからない。運良く目的地に着けても、荷物が無いかもしれない。」
航空会社だったということだ。
こんな会社が、乗客から支持されるわけがない。
そして3度目の破産を目前に控えた1994年2月、同社の再建を託されてCEOに着任したのが、後に「コンチネンタル奇跡の復活」と呼ばれる事になる成功を指導した、ゴードン・ベスーンであった。
私事で恐縮だが、私はかつて倒産寸前の会社でターンアラウンドマネージャーを引き受けたことがある。
もちろんコンチネンタルとは比べ物にならない小さな会社ではあるが、それでも業績が傾き、数次に渡るリストラと給与カットで従業員の怨嗟を招いている組織には、独特の空気があることを知っている。
経営者は個人的に憎悪の対象になり、誰も成果を上げる事に興味などない。
組織として最も大事な、組織や経営層に対する信頼も一切ない。
そのため、ゴードン・ベスーンの前任者であるフランク・ロレンゾは従業員から襲撃されることを恐れ、執務室に非常ベルを設置し、IDカードで入退室を管理し、さらに自社便で移動する際にも、運ばれてきたソーダを決して口にしなかったという。[2]
そんな組織でCEOについたゴードン・ベスーンはまず何から着手しただろうか。
それは、
・従業員との約束を必ず守ること
・約束は客観的に誰でも理解できる内容であり、曖昧さが一切ないこと
・成果に必ず、信賞必罰で報いること
であった。
経営層や従業員がお互いを信用せず、成果に興味がないということは、「仕事の約束を守るという、最低限の責任感がない」ということだ。
そんな組織では、誰も定められた納期までに、自分に任された仕事をやろうとしない。
経営を任されたところで、どれほどのリーダーであってもまず上手くいかないだろう。
そのため彼は、まずは経営層や従業員がお互いを信頼し、まともに機能する組織を作り直すところから始めた。
具体的には何か。
それはぶっちぎりの最下位であり続けた定時到着率を、全米主要航空会社10社の中で5位以内に押し上げることができれば、全ての従業員に65ドルの特別ボーナスを支給するというものだった。
決して、「顧客満足の向上」「お客様第一主義」などという曖昧なスローガンではない。
客観的に誰にでもわかる目標を設定し、従業員一人ひとりが「そのために何をすれば良いのか」まで、毎日の行動レベルに落ちる目標を掲げることから始めた。
当たり前と思われるかもしれないが、こんな事ができる経営者・リーダーがどれほどいるだろうか。
自分自身のことを振り返って
「常にお客さんのことを考えなさい」
などと、経営トップ、中間管理職、一般従業員でまるで言葉の解釈が違う、極めてリスキーで頭の悪い指示をしていないと、言い切れるだろうか。
そして期待通りの成果物や行動が出てこなかった時に従業員を責めて、その「成果」に対し「叱責」という裏切りで報いて、部下や組織を大いに失望させたことはないだろうか。
いうまでもなくこの場合、どうとでも解釈できる指示を出したリーダーに問題がある。
このようにしてリーダーは部下を無能と罵り、部下は上司を「信頼できない」と不信感を募らせ、組織は負のスパイラルを一直線に落ちていく。
ゴードン・ベスーンは、このようにしてコンチネンタル航空が“墜落寸前”の組織に陥っていたことを知っていた。
だからこそ、誰の目にも明らかな客観的目標を設定し、経営層・中間管理職・一般従業員の「言葉を統一」し、そして成果に対し明確に報酬を出すという、信頼関係の醸成に努めることから始めた。
結果として、この施策は大いに効果を発揮して、数ヶ月のうちに同社は定時到着率全米5位に入る。
そして最初のボーナスである65ドルの小切手を手にした従業員の中には息子をスーパーに連れていき、「好きなシリアルを何でも買ってやる」と胸を張った者もいたという。
またある女性は長年我慢していた欲しかったものをやっと買えたと、笑顔で語ったそうだ。[3]
想像してほしいのだが、何度も給与をカットされ、プライドもズタズタにされながらただ生活のためだけに我慢し働いていた従業員が、素晴らしい目標を組織の皆で勝ち取り、特別ボーナスを手にしたらどんな反応が起こるだろうか。
「今度のボスは信頼できる」
「俺たちだって、やればできるんじゃないか!」
そんな無邪気に喜ぶ様子が、目に見えるようではないだろうか。
そしてその後もゴードン・ベスーンは、問題に対する解決方法こそケースバイケースであったが、
・従業員との約束を必ず守ること
・約束は客観的に誰でも理解できる内容であり、曖昧さが一切ないこと
・成果に必ず、信賞必罰で報いること
という方針を次々に実行に移し、組織はたちまち、すごい勢いでスパイラルアップしていった。
このような「勝利の味」を覚えた組織は本当に、強い。
1996年3月、コンチネンタル航空の定時到着率はついに83%を記録し、全米でトップに立った。
さらに同年、Airline of the yearを受賞する奇跡の復活を遂げることになる。
ここまで、ゴードン・ベスーンのCEO着任から僅か2年である。
これほどまでに、組織とはリーダーが変わると様変わりできる、大きな可能性を秘めている。
野村克也は何がすごかったのか
そして、野村克也という名監督についてだ。
今でこそ常識だが、スポーツで勝つために必要なこととは、目的に向かってやるべきことを数値化し、あるいは客観的な行動に落とし、個々の選手と組織にやるべきことを理解させ、徹底させることに尽きる。
先の例で上げた65ドルのボーナスも、実は単なる動機づけの手段であったわけではない。
コンチネンタル航空は、飛行機の遅延などで負担が必要となる乗客の食事代や振替輸送費、ホテル代などの補償に月間500万ドルを浪費していた。
そして65ドルのボーナスを全従業員に配ることでかかるコストは、250万ドル。
つまり、250万ドルの投資で500万ドルの浪費をカットすることに成功したのである。
野村が編み出したID野球とはこのように、状況を可視化し、数値化し、トレードオフも考慮に入れながら、戦力の向上に繋がるあらゆる施策を組織に徹底することであった。
もっと単純に言えば、「それぞれの立場で解釈が変わる可能性がある言葉の統一」であったと言ってもよいだろう。
その施策は単に、組織論だけにとどまらない。
40代以上の世代には馴染み深いかもしれないが、野村は他球団で戦力外通告を受けクビになった選手を一流選手に生まれ変わらせる手腕にも長けていた。
その奇跡は「野村再生工場」と言われ、野村に拾われたことで人生が変わり一流選手として生まれ変わることができて、今も彼を生涯の恩人と崇拝する選手・元選手も多い。
しかしそのカラクリは、実は単純なものだ。
有名な事例で言えば、かつて先発ピッチャーとして球界を代表する名選手であった江夏豊を招聘した際に、「戦術に革命を起こそう」と、彼をリリーフ専門の投手にコンバートしたことであろうか。
先発完投が投手の名誉であるとされていた時代に、江夏ほどの超一流選手をリリーフにコンバートした発想もすごいが、その結果先発投手としてはすでに成績が厳しかった江夏が一転、大活躍の場を得たことである。
ありきたりの言葉で言えば「適材適所」であり、野村は終始一貫、選手の長所を伸ばし活かすことを考え続けた。
もちろんその前提には、定量化・数値化された組織の現状を冷徹に分析し、不足している機能を補うという「ID野球」があった。
その本質は、全てのビジネスパーソンが学ぶべき考え方と言ってもよいだろう。
スポーツ界に革命を起こし、多くの人の尊敬を集め続ける野村克也という偉人の逝去に際し改めて、心からのお悔やみを申し上げたいと思う。
本当に、お疲れさまでした。安らかに、お休みください。
なお余談だが、今回ご紹介した「大逆転-コンチネンタル航空奇跡の復活」の著書の中でゴードン・ベスーンは、65ドルという成功報酬について、「少ないのではないか」という批判に対し、
「20ドル紙幣が3枚、5ドル紙幣が1枚、道端に落ちているのを見かけたら、あの不動産王ドナルド・トランプだって、腰をかがめて拾うに違いない」[4]
と記している。
この著書は初版1刷が1998年なので、少なくともそれ以前に書かれた文章であることは間違いがない。
つまり現・アメリカ大統領のドナルド・トランプは、20年以上も前から大富豪の象徴として、アメリカで存在感があったということになりそうだ。
とはいえさすがのゴードン・ベスーンも、彼が後にアメリカ大統領になることまでは、予想できなかったのではないだろうか。
AUTOMAGICは、webブラウザ上で商品情報を入力するだけで、
・ターゲット分析
・キャッチコピー
・ネーミング
・キャンペーン企画案
・商品紹介LPの文章
を自動で出力します。
登録すると月間20,000トークン(約2記事程度)までは無料でご利用できます。
↓
無料登録は
こちら(AUTOMAGICサイト)へ
詳しい説明や資料が欲しい方は下記フォームからお問合わせください。
↓
AUTOMAGIC お問合せ・資料ダウンロードフォーム

【著者プロフィール】
株式会社識学
人間の意識構造に着目した独自の組織マネジメント理論「識学」を活用した組織コンサルティング会社。同社が運営するメディアでは、マネジメント、リーダーシップをはじめ、組織運営に関する様々なコラムをお届けしています。
webサイト:識学総研
参照
[1]日経BP社「大逆転-コンチネンタル航空奇跡の復活」10P
[2]日経BP社「大逆転-コンチネンタル航空奇跡の復活」23P
[3]日経BP社「大逆転-コンチネンタル航空奇跡の復活」151P
[4]日経BP社「大逆転-コンチネンタル航空奇跡の復活」40P