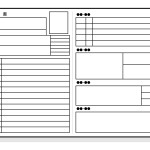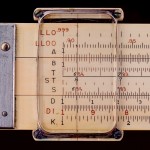人間の本質というものは、分かるようで分からない。
なぜなら、それらは必ずしも一定ではないし、偶然が引き当てる「本質」もあるからだ。
*
2016年8月、私は熱狂的なサンバの都市・リオデジャネイロにいた。
そう、リオ五輪を観戦するためだ。
リオに到着してまず驚いたことは、いい意味での「ハリボテ感」だった。
オリンピック会場近くを探索したところ、道路のど真ん中に大きな穴を発見。
遠目からでも分かる巨大な穴の奥には、なんと、頭から突っ込んだ自動車が葬られているではないか。
これが日本ならば大惨事。
しかしリオでは、このようなアクシデントは日常茶飯事なのだろう。道行く人々は巨大な落とし穴をチラ見しながら、さほど興味もなさそうに通り過ぎて行くのだ。
落とし穴に近づいてみると、見えていた自動車のさらに奥に、別の車のケツが見えた。
(・・・玉突き事故みたいに、落とし穴にハマったんだな)
車の持ち主と思われる男性二人が、穴の近くでどこかへ電話を掛けている。
狼狽する様子もないので、こちらもまた慣れた日常の一コマなのかもしれない。
そのまま道路を進むと、工事途中の土手につきあたった。
さっきまでの都会の喧騒など嘘のよう。オリンピック開催のために、やむなく自然に手を加えたのだろう。
地肌むき出しの土手を右へ曲がると、突如、地面の状態が変化した。
ついさっきまで、大きな穴が空いているとはいえアスファルトで舗装された道だったのが、急に砂利だらけの林道に変わったのだ。
幸いにも私はビーチサンダルだが、ヒールを履いた女性などとてもじゃないが歩けない。
そのくらい、粘土質の土壌とこぶしほどの瓦礫が転がる、リアル・オフロードが出現したのだ。
さらに驚愕したのは、そのオフロード沿いに建てられた簡易フェンスの施設――そう、未完成かと見紛うようなオリンピック施設の裏側だった。
メイン会場ではないにせよ、世界が注目するリオ五輪の競技施設であることに変わりはない。にもかかわらず、正面と両サイドは道路も含めてなんとか完成させたが、裏側は間に合わなかったのだ。
時間的な問題か、はたまた金銭的な問題かは分からない。
だが、ハリボテと言っても過言ではないオリンピック施設の裏側を、瓦礫に躓きながら感慨深げに見つめるのであった。
行きはよいよい、帰りはコワイ
しかし思い返すと、私は海外入国時に拒絶される傾向にある。
早い段階では、ビザの申請にロシア大使館を訪れた時点で、3カ所ある窓口をすべて閉鎖され締め出されたことがある。
出国前にもかかわらず、すでに入国拒否をくらったわけだ。
小学生の頃には、ロンドン・ヒースロー空港の入国審査で、このようなやり取りがあった。
「Are you a boy?」
「No, I am a girl」
当たり前だが私は女だ。パスポートにも記載してあるし、短髪とはいえどう見ても女だろう。
そんな私に向かって、なんという低レベルな質問をするのか。
だが、その次の言葉には驚きを隠せなかった。
「No, YOU ARE A BOY」
ゆっくりと、そしてハッキリとこう言い切られた。
一瞬、何が起きているのか理解できなかったが、小学生でも知っている「Boy」だけは聞き取れた。
そして言うまでもなく、私は否定した。
「No, I am a GIRL」
Girlを強調してみる。しかしなぜ、このような茶番を強いられるのか理解に苦しむ。
すると入国審査官は、半笑いで首を横に振りながらこう言った。
「No, No. You are a BOY」
こうして私は、人生初となる別室へと連れていかれたのだ。その時の両親の苦い表情は、未だに忘れられない。
大人になってからも似たような状況が続いた。
メキシコへ向かう途中のトランジットで、ロサンゼルス国際空港に降り立った時のこと。入国審査官にこう言われた。
「You are suspicious」
Suspiciousという単語に馴染みはないが、意味くらいは分かる。「疑わしい」とか「不審」を意味する言葉だ。
しかしなぜ、今、私に向かってその単語が使われているのか、皆目見当がつかない。
トランジットの時間は短いので、こんなところで油を売るわけにはいかない。そこで私は彼に質問をした。
「私のどこが怪しいですか?」
すると相手は、小声でこう答えた。
「すべて」
これを聞いて私の怒りは頂点に達した。
あぁいいだろう!気が済むまで討論しようじゃないか!その前に、日本語と英語が堪能な通訳を呼んでもらおうか!
しばらくして、日本人と思しき女性通訳がやってきた。ホッとする私に向かって、彼女が放った一言はコレだった。
「你好(ニーハオ)!」
*
そして今回、リオデジャネイロからの帰り道。
日本への最終乗り換え地は、ダラス・フォートワース国際空港だった。
ここまでの間、大きなトラブルにも見舞われず、2週間の南米行脚は無事に終わりを迎えようとしている。
と、そこへ不吉なアナウンスが流れた。どうやら空港全体が電気系統の故障に見舞われており、フライトスケジュールが変更されているとのこと。
カウンターで新たな搭乗券を発行してもらうよう、繰り返し告げている。
実は私、帰国翌日の朝一に、代理がきかない重要な仕事を入れていた。
そんな危なっかしいスケジュールにしなければいいのだが、なんせ2週間も日本を離れていたため、それなりに仕事が溜まっているのだ。
それでも「まぁ、何とかなるだろう」と気楽に構え、長蛇の列の最後尾に並んだ。
20分ほどして私の順番が回って来た。アメリカ人特有のビッグなフォルムの女性が担当。
彼女は慣れた手つきでカチャカチャとキーボードを叩くと、二枚の新たな搭乗券を発券してくれた。
「Have a good trip!」
こんなにもあっさりと終わっていいのだろうか?だが手渡されたチケットを見て、私は青ざめた。
それは、現在地であるダラスからシカゴへ飛び、シカゴで一泊してから日本へ向かうスケジュールだったのだ。
(冗談じゃない!人生を左右する重要な仕事が入っているんだ。泳いででも日本にたどり着かなければならないんだ!)
慌ててビッグマムに噛みつく。これじゃ困る、明日日本に到着する便にしてほしい…と強く懇願する。
すると彼女は涼しい笑顔でこう言った。
「あなた、後ろを見てみなさいよ。みんな急いでいるし、事情があるのよ」
そして指先でシッシとやりながら、
「Next!!」
と、強い口調で私を追い払った。
万事休す。私はシカゴで無駄に一泊してから、帰国するしかないのだろうか――。
賄賂とは、相手の本質を掴むこと
シカゴ経由のチケットを握りしめながら、私は再び最後尾へと並んだ。
カウンターには2人の航空会社スタッフが座っており、それに対して100人以上のフライト難民がたむろっている。
誰もが皆、怒りと不安そして疲弊した表情で、自らの順番を待っている。
中には頭を抱えて泣いている女性もいる。見ず知らずの他人だが、きっと彼女と私は同じ心境である。
そうこうするうちに一時間が経過した。
あと5人くらいで私の順番となる。この辺りから、スタッフと顧客の会話を盗み聞きし始めた。
隣りのカウンターで、肘をつきながら会話をするビジネスパーソンがいる。見るからに立派な出で立ちの男性に対して、スタッフの表情は引きつらんばかりの営業スマイル。
(なんか裏ワザでもあるのか?)
よくよく聞いてみると、その男性はユナイテッド航空の上級会員らしい。そしてあっという間に、彼が希望するフライトチケットが発行されたのだ。
これは、カネを積んだところでひっくり返すことのできない、圧倒的なヒエラルキーを突きつけられた気分である。
我々凡人にはどうすることも出来ない、透明で頑丈な防弾ガラスの壁が立ちはだかっているのだ。
そこで私は考えた。
これは「お涙ちょうだい路線」か、「日本人という勤勉で堅実な民族性の強調」で推すしかない――。
私の二組前には日本人の家族が並んでいた。父の拙い英語でなんとか交渉を試みるも、冷酷なビッグマムの前に儚くも散った。
そして子どもは泣きだした。
「パパ、わたし水泳大会に出れないの?」
その言葉を聞いて私の胸は痛んだ。こんな幼い子どもの小さな楽しみを奪うなんて。許すまじ、ビッグマム!
私の直前の客は横柄な態度を取っていた。
アメリカ人だが、自分がどれほど忙しく世界を飛び回っているのかを、自慢交じりに説明している。
私もビッグマムも、飽き飽きした表情で聞き流した。
「Next!!」
(キタッ!!)
とうとう私の出番が回って来た。本日二回目の登場である。
ビッグマムと目が合うと、彼女はやや怪訝そうな表情を見せたが、私は構わず話し始めた。
「日本人というのは、ちっぽけで愚かな民族なの」
はぁ?というような、呆気にとられた顔で私を見つめるビッグマム。
「火曜日の仕事に間に合わなければ、私は・・・命を断つしかないのよ」
だからなに?と言わんばかりの表情で、モニターを見ながらカチャカチャと指を動かすビッグマム。
そこで私は慌てて涙を見せた。
(伝われ!働く女同士の絆っ!)
ダメだ。ビッグマムには通用しない。そこで私は涙を拭き取ると、今度は真顔で交渉を始めた。
「日本ならばどこでもいい。関西でもセントレアでも、この際、北海道でも九州でもいい。日本の土地に私を上陸させてほしい」
彼女にグイッと近づきながら、目を見開き静かに交渉を続けた。
東京じゃなくてもいい、とにかく日本に上陸できたなら、新幹線を使って火曜日の朝一の任務に間に合わせる。
すると、沈黙を続けていた彼女の口から、思わぬ言葉が漏れた。
「ほんとうに成田じゃなくていいのね?どこか田舎の空港みたいだけど・・・」
(やった!この際もうどこでもいい、田舎でもどこでも降ろしてくれ!)
「Hanedaっていうところになら、一席だけ空きがあるわ」
(Haneda・・・ハネダ?!)
その瞬間、ビッグマムがホイットニー・ヒューストンに変わった。
私は思わず、カウンター越しに手を差し出す。それを見たホイットニーは、鼻で笑いながら軽く握り返してくれた。
私の本来のチケットは成田空港行きだった。それが空港内の電気トラブルのせいでシカゴ行きになり、それでも身を賭して粘った結果、羽田空港行きのチケットを引っ張り出したのだ。
こんなラッキーがあるだろうか!
喜びを抑えきれない私は、もう二度と会うことはないであろうホイットニーへ、感謝の気持ちを込めて小さなプレゼントを渡した。
リオ土産として購入した、ハローキティの安いキーホルダーだ。
――ありがとう、ホイットニー。
「Awww, soooo cuuuute!!!!」
なんという声を出すんだ?!というほどの雄たけびをあげる彼女。握りしめたキティちゃんにキスをしながら、頭上にかざして何度も歓喜の声を漏らす。
その姿を、後ろに並ぶ難民らが不愉快そうに睨んでいる。
すると彼女が、突然、このような独り言をつぶやいた。
「さっきの座席は誰かがブッキングしてしまったわ。もうファーストクラスしか空いてないわね」
そう言いながらホイットニーは、ファーストクラスの搭乗券を発券すると、素早く私の手のひらにねじ込んだ。そして大行列などお構いなしに、カウンターを閉めてしまったのだ。
さらに化粧ポーチらしきものを取り出すと、そこへキティちゃんのキーホルダーを付けようとしている。
・・・なんと彼女、ハローキティが大好きだったのだ。化粧ポーチも、携帯電話のカバーも、ハンドタオルもすべてキティちゃんだった。
つまり、私がたまたまプレゼントしたハローキティは、紛れもなく大当たりの賄賂だったのだ。
振り返るとそこには、終わりの見えない長蛇の列が。そしてホイットニーは、上機嫌で休憩に行ってしまった。
*
私はユナイテッド航空の上級会員ではないが、安物のキーホルダーで同じステータスに、いや、それ以上の待遇を手に入れたわけだ。(了)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
URABE(ウラベ)
早稲田卒。学生時代は雀荘のアルバイトに精を出しすぎて留年。社会人になり企業という狭いハコに辟易した頃、たまたま社労士試験に合格し独立。現在はライターと社労士を生業とする。
Photo by Phil Mosley