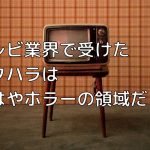彼岸花は、自然の賜物であると同時に文化の賜物でもあると思う。
なぜならどんなに美しくとも、どんなに生き生きと咲いていても、故人を、過去を思い出させるからだ。2023年の彼岸も、私はそうやってメランコリックなことを考えながら過ごしていた。
ちょうどそのタイミングで過去を振り返る書籍に出会った。ライター・編集者の速水健朗氏が著わした『1973年に生まれて』だ。氏は私と同じ石川県出身で、年齢は私より少しだけ上、といったところだ。昭和の残滓を透かし見るべく、私は『1973年に生まれて』を手に取った。
ところがこの本、私の記憶とちょっと違った昭和を映し出していた。
ちなみに我が家は、母親は専業主婦。父親(46年生まれ)はサラリーマン。子どもは2人とも団塊ジュニア世代。核家族で団地(のちにマンション)暮らし、マイカー族。日曜日にはドライブに出かけ、帰りにロードサイドのファミレスで食事をする。まるでサンプルとして抽出されたような家族である。そこまで自分に特化した話を書くつもりはないが、サンプル程度に記しておく。
この本を手に取るまで知らなかったが、筆者の速水健朗氏は出身こそ石川県だったが、転勤族だった。
だから氏の述べる「サンプルとして抽出されたような家庭」とは、団地やニュータウンで過ごした核家族然とした昭和世代としてのもので、三世帯同居や両親の共働きが当たり前な、北陸地方の地域共同体のソレとは違っている。
団塊ジュニア世代の物語を読みたくて『1973年に生まれて』を手に取る際には、だから注意する必要がある。転勤族は基本的に核家族的で、実家の血縁や地域共同体の地縁から遠い世界を生きている。
『1973年に生まれて』は、私の知っている昭和より、平成のさきがけとしての昭和の核家族世帯、そして昭和から令和へと続く日本のサブカルチャーの変遷について該博な書籍だ。
ずっと前から日本のサブカルチャーの幅広い範囲について発信している氏のルーツとして納得いく内容であると同時に、今日に至るサブカルチャーの変遷を幼少期からよく見ていた人だったことが窺える書籍だ。
ともあれ、私が見た昭和はそれとは違っているし、「昭和とはこういう時代だった」という印象も同様だ。
速水健朗氏の記す昭和は令和へと繋がっていく昭和だが、私が生きた昭和は彼岸花の肥やしとなって埋もれていった昭和、若者が都市へ出ていって過疎化し、サブカルチャーがメインカルチャーのような顔つきをするようになり、単身世帯が増えていくうちに消えていったような昭和だ。
どうか彼岸花に免じて、今日は、昭和時代に生き、死んでいった人の話をさせていただきたい。
子どもは自由だった、しかし死がすぐそばに潜んでいた
昭和時代という言葉にはさまざまな切り口があろう。が、今日は「昭和は死が今より間近にある時代だった」をメインテーマに、地域共同体の昭和を思い出してみたい。
私は石川県でも地域共同体のよく残っている集落で生まれ育った。都市部から少し離れていたので、いわゆる転勤族・団地族とみられる人はほとんどおらず、たいていの家庭で祖父や祖母が一緒に暮らし、親戚やいとこも結構近くに住んでいた。
三月になると女児のいる家では立派なひな壇が飾られ、五月になると男児のいる家では立派なこいのぼりが立てられていたものだ。
そうした地元の内側では、子どもたちはどこでどう遊んでも基本的に自由で、たいていは数人、ときには十数人の子どもの集まりが空き地で草野球をしたり路上に落書きをしたりして遊んでいた。
子どもがどこでも遊べるとは、自由であるとともに危険を伴うことでもある。実際、交通事故に遭う子ども、池や川で事故死する子どもは珍しくなかった。
たまたま私の学区・私の学年には在学中に命を落とした同級生はいなかったけれども、ひとつ上の学年や下の学年はこの限りではなく、同級生のなかにも大きな交通事故に遭ってしばらく欠席する者はいた。
私自身、かなり危ない思いをしたことがある。
一回目は四歳の時。保育園の同じクラスの子二人と私は近くの川に遊びに行っていた。もちろん大人がついていったわけではない。
私たちは夕方遅くまで川辺で水遊びをしていたのだけど、気が付けば私一人になっていた。サンダルが片方、川に流され、探しても見つからず、泣きながら帰宅した私は叱られたのだけど、自分が叱られている意味もよくわからなかった。
二回目は小学校三年生の時。雷魚が住んでいる大きな沼に友人と釣りに出かけた時、私は脚を滑らせて沼に落ちた。
泳ぎには自信があったが、沼の岸辺がツルツルと滑っていつまでも這い上がれず、だんだん疲労が募ってきた。このとき、友人が機転をきかせて長い棒を差し出してくれ、そのおかげで私は這い上がることができた。もし一人で行動していたら、それか友人のそばに長い棒がなかったら、どうなっていたかわからない。
今日では、昭和や20世紀をリバイバルするさまざまな文物を見かける。それは昭和風の居酒屋や特撮番組のリメイクだったり、昔流行ったアニメのリバイバルだったりする。確かにそれらも昭和の思い出だ。
でも昭和といって私が思い出すのは、死の気配、いや、今日に比べて命のことをあまり重たく考えていない、当時独特のセンスだ。
昭和時代の子どもは地元のどこにでも、それこそ資材置き場から港湾施設まで遊び場にできたし、高い木に登ったり、立ち入り禁止地区に入り込んだりしていたが、そのかわり命を落としかねないリスクを冒していて気付かなかった。この、昭和ならではの命のセンスがリメイクされたりリバイバルされたりすることは無い。
令和において虐待やネグレクトとみなされるもの、いじめや暴力とみなされるはずのもの、プライバシーの侵害や迷惑行為とみなされるものが私の地域共同体には横溢していた。
テレビをつければ芸能人は身体を張った芸をしていて、私たち小学生はそれをゲラゲラ笑いながら観ていた。テレビに映らない暗がりでは、もっときついことが行われていたに違いない。
高齢者の命と、その死について
高齢者も今とは異なっている。今日でも北陸地方は三世帯住宅が多いことで知られるが、実際、どこの家にもじいばあがいて、その年齢は50~60代、顔や腕には年輪が深く刻まれ、見た目も社会的立場も高齢者そのものだった。
男性は80代までほとんど生き残っておらず、女性は明治生まれの曾祖母のいる家庭がところどころにあった。
80代の曾祖母のいる家庭の祖母の心境はいかばかりだっただろう? それとも北陸地方の嫁は姑なるものが平気だったのか?
まさか! 北陸地方の家々は世間体を重んじるから、平静を装った嫁と姑の間にも相応の摩擦があったと想像する。実際、私の家にも近所の家から漏れ聞こえてくる声からも、嫁と姑の確執が察せられる瞬間はあったからだ。
とはいえ、子どもにとって地元のじいばあは頼もしい存在だった。なかには子どもを疎んじる高齢者もいたが、そんな高齢者の家はたちまち子どもたちに知られ、避けられてしまう。
顔見知りのじいばあの大半は地元の子どもには寛容で、裏庭や縁側を通る際、お菓子を出してくれたりすることもよくあった。
地元の子どもたちが好き勝手に遊んでいる割には事故や事件が少なく抑えられていたのも、じいばあが見守り、ある程度は世話してくれたからに他ならない。
当時は「こども110番」などというステッカーを貼った家などなかった。どこの家のじいばあも子どもの味方だったから、そんなものは要らないのが当然だったわけで、あのステッカーこそ、地域共同体の形骸化の象徴なのだ。
高齢者の話に戻ろう。そうした顔なじみである地元のじいばあは、たいていポックリと亡くなっていった。地元で誰かが亡くなるたび、有線放送で葬儀のおしらせが町内に届けられた。
80歳や90歳で亡くなる人は少なく、60歳や70歳で亡くなる人、それも、つい先日までピンピンしていたはずの人が急ぎ足で冥土に去っていくことが多かった。
そうした有線放送のたび、両親や祖父母の誰かが喪服で出かけていき、帰ってきた大人に玄関で塩をまくのが私の役割だった。
現在の私は知っている。そうして速足で亡くなる人々の死因が脳出血や脳梗塞や心筋梗塞で占められていたことを。
当時の人々を早く死に至らしめ、早く老けさせた健康リスクの親玉は動脈硬化だ。その動脈硬化をもたらす悪玉コレステロールのメカニズムが発見されたのは1976年だから、当時の田舎のじいばあがそれを知っていたとは考えにくい。
高血圧への意識も低かっただろう。夏が始まる頃、地元では一斉に梅干しが漬けられる。梅干しをはじめ、塩気のあるものへの抵抗感は今よりずっと低かった。
タバコを吸い、副流煙をも気にせず、飲酒運転にも無頓着なあの頃の大人たち。そうして彼らは好きなように飲み食いし、好きなように生きて、呆気ないほど速足にあの世に去っていった。
私の祖父もそれを体現しているような人物だった。健康を顧慮しない生活をし、腎臓を痛め、六十歳を過ぎた頃に脳出血に襲われ、入院生活と自宅療養で二年ほど過ごした後に亡くなった。
当時の入院は看護師がすべての世話をみてくれるわけではなく、祖父の入院中には付き添い人なるおばさんが雇われていた。今日のような介護保険制度は無く、退院後の祖父を看ていた祖母や母は本当に大変そうだった。
その祖父の葬儀は浄土真宗の寺院で執り行われた。祖母に連れられてお寺の行事に参加したり、幾人かは寺子屋に通って勉強やお経を習うなど、北陸の子どもにもゆかりの深い宗派だ。
例のごとく葬儀の予定が有線放送で流され、祖父の亡骸は大きな寺院に安置され、葬儀の日には近所の人に手伝っていただいた。
令和ならよほどの大人物の葬儀と見まがうような葬儀ののち、祖父の遺体は昭和風の金ぴかの霊柩車に運ばれて火葬場に向かった。そして子どもは初七日まで、大人は四十九日が済むまで精進料理を食べて過ごした。
死の間近な社会から、死が間近ではない社会へ
こんな具合に、昭和時代において死とは、無頓着のために唐突にやって来るかもしれないものであると同時に、還暦の前後にもなれば大口を開けて待ち構えているもの、だからといって特段に不安がるわけでもないものだった。
それだけではない。地域共同体を介してより多くの死が告知され、葬儀をとおして共有され、みんなで見送り、みんなに見送られるものだった。
昭和と令和には大きな違いがいくつもあるが、この、命の軽重の感覚、そして死というものと日常との距離感も無視できない違いのひとつだ。
そうした違いはエビデンスをもって追いかけることもできる。たとえば子どもの事故死のパーセンテージや葬祭規模といったものを統計的に追いかけると、実際、昭和時代の終わりになってもなお、子どもが死ぬという事態は今より多く、高齢者が高齢者となる時期は早く、葬儀をとおしてより多くの人がより多くの死をシェアしていたことが裏付けられる。
逆に言うと、令和とは命がきわめて重くなった時代であり、私たちは死というものが日常から遠く隔てられた社会を生きている、と言うこともできるだろう。
病床にあった祖父を世話した私の祖母は、令和のはじめに百歳で亡くなっている。そのときの葬儀はいかにも令和風の家族葬で、精進料理も省略されていた。そうした家族葬を執り行うのは近所の人ではなく、葬祭センターの専門家だ。義理も付き合いも不要な「なめらかな葬祭」は、今日風のものだと思うし、地域共同体なるものが消失し、核家族や単身世帯の増えた社会にふさわしいものだと思う。
それを批判する気はないし、私自身、そのように専門分化された葬祭に助けられる立場だと心得ている。それが令和の社会だ、ということも。
ただ、秋風に吹かれながら彼岸花を眺めるこの時期になると、人間が生まれて老いてやがて死ぬという摂理に対して鈍感なこの社会が、なんだか不思議なものに見えてくるのだ。
死が近すぎるのは考え物ではあるけれども、いやしかし、たった半世紀ほどの間に随分と死からも遠いところにたどり着いたものである。
そうして死を圧倒的に遠ざけながらも、まだ遠ざけ足りないかのように私たちはアンチエイジングに励み、高価な抗認知症薬を求め、なかには不老不死こそが人類の救いだと思い込んでいる人もいる。それらは昭和のセンスとはあまりに違い過ぎていて、過去を回想する時、私はめまいのようなものに襲われる。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【プロフィール】
著者:熊代亨
精神科専門医。「診察室の内側の風景」とインターネットやオフ会で出会う「診察室の外側の風景」の整合性にこだわりながら、現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信中。
通称“シロクマ先生”。近著は『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(花伝社)『「若作りうつ」社会』(講談社)『認められたい』(ヴィレッジブックス)『「若者」をやめて、「大人」を始める 「成熟困難時代」をどう生きるか?』『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて』(イースト・プレス)など。
twitter:@twit_shirokuma
ブログ:『シロクマの屑籠』