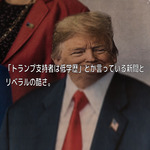ひと月ほど前のこと。仕事仲間との会食、麻雀を終え、終電に近い電車に乗り込むと、年配らしき男性(推定60代)がうつ伏せに倒れていたので驚いた。
もっと驚いたのは、倒れていた男性に声をかけ、寄り添っていたのが、20代の若い男性1人だったこと。
その若い男性は、手と膝を床につけ、倒れた年配男性をのぞき込みながら、必死に声をかけていた。
車両には20人ほどの乗客がいたと記憶しているが、ある人はスマホの画面に目を落とし、またある人は「(若い男性に)任せておけばいいか」といった様子で、見て見ぬふりをしていた。
中には寝ている風の人もいたが、乗客が地べたに、うつ伏せで倒れているのだから、気がつかない訳はないと思うのだが……。
電車は発車していたため、私は2分後に到着した自宅最寄り駅で下車すると、車掌さんと駅員さんに急病人がいることを告げた。
車掌さんらは、うつ伏せに倒れていた乗客に声がけしたが、ほとんど反応がなかったので、脳血管の類いの急病か、ただの酔っ払いだったのかは分からない。ただ、遠巻きに見守るだけの人が多いこと、中には全く無関心だった人もいたことに衝撃を受けた。
と同時に、倒れていた年配男性に必死に寄り添っていた若い男性の責任感、行動力に感銘を受けた。
今も、勇気、責任感、気配りに満ちた、あのカッコいい若者の姿が忘れられない。
倍ほども歳の離れた若者に、当たり前だが、なかなか行動に移せない、人として大切なものを教わった気がする。
あの一件以来、せめて、公の場では、周囲への気配りを欠かさないように意識している。高齢者や目の不自由な人、体調の悪そうな人への気配りは当然だが、バッグや衣類に「ヘルプマーク」をつけた人にも、より留意するようになった。
ご承知の通り、ヘルプマークとは、何らかの支援や気配りが必要であることを周囲に伝えるマークのこと。
赤色の下地に、白色のプラスマークとハートが描かれている、ステッカーのようなものを、誰でも一度や二度は見たことがあるのではないか。
これは、「いざの場合は支援や援助をお願します」という救急要請の合図。支援が必要な人なら誰でも装着できる。
明確な基準はないが、東京都福祉局によれば、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としている方が対象という。
このヘルプマークを身に着けた人を見たら、声掛けする、席を譲る、避難の援助をする、といった気持ちを持つことが大切になる。
ヘルプマークは、都道府県や市区町村の福祉課、保健所、市民センター、都営地下鉄の各駅(東京都)などで配布されているが、自分で作成して装着しても構わないという。
私も、数年前、ある特異な脳血管障害の影響で、症候性てんかんと診断され、ヘルプマークを持っている。ただ、何度かてんかん発作を経験し、また、てんかん治療薬の効果もあって、ある程度、病気を管理できるようになったので、まだヘルプマークをつけたことはない。
ぱっと見、健康だけが取り柄のように見える私でさえ、そうした持病があったりする。外見ではなかなか分からないが、実は支援や気配りを必要としている人は、予想以上に多いのが実情ではないだろうか。
そんな中、先日、少し込み合った電車に乗ると、9割以上の乗客がスマホに目を落としていた。LINEやメール、ゲームや音楽、アプリといったものに夢中で、周囲に気配りする余裕、隙間はほとんどない様子。
スマホとにらめっこする人の群れ。
今や当たり前の光景だが、よくよく見ると、気色悪く、人間味が感じられない空間、風景に思える。車内の様子を見渡し、周囲に気を配っている人が、何か奇異な目で見られる現状に違和感を覚える。
言葉を換えれば、公共の場が、自分だけの空間と勘違いしている人の多さに、危機感さえ募る。これでは、周囲に困っている人がいても気づかないし、逆に不審な人物がいても、危険な出来事が起こっても、俊敏に対応できない。
公共交通機関や街中などの「公共の場」は、その言葉の通り、不特定多数の誰もが利用する場所。
言うなれば「みんなの空間」で、だからこそ、互いに気配りするのが不可欠だが、今はスマホの影響もあってか、「自分だけの空間」といった状態になってしまっている。
どこまで「自己欲求」を追求する環境になれば気が済むのか-
どこまで「周囲への気配り」という大切なものをなくせば気が済むのか-
私自身も、電車内でスマホを見ることが少なくないので、人のことは言えないが、暗い気持ちになる。
とはいえ、人は捨てたもんじゃない。
先日、ヘルプマークはつけていなかったが、80代と思われる杖をついた高齢女性が、ふらつきながら電車に乗ってきた。
気になって高齢女性を注視していると、20代と思われる女性がすぐに立ちあがり、笑顔で席を譲った。
その高齢女性は歩く速度が遅いためか、下車駅が近づくと席を立とうとしたが、ふらついて倒れそうになった。すると、隣に座っていた学生風の男性が、高齢女性の体を支え、一度座席に戻した。
座ってからも、直接触れてはいないが、肩のすぐ後ろに両手を回し、高齢女性を支える思いを体現した。
下車駅に到着すると、高齢女性はふらふらと立ち上がり、ドアへ向かったが、乗客が乗り込んできて、ホームに出られない状況に。すると、向かい側に座っていた年配の女性がすぐに席を立ち、高齢女性を支えて、ホームまで誘導した。
高齢女性は後ろ姿のまま、右腕をゆっくり上げて、感謝の気持ちを伝えていた。
席を譲った20代の女性、隣の席で高齢女性を支えた学生風の男性、そしてホームへ誘導した年配の女性。人として当たり前のこと、しごく自然の行動だが、高齢女性を支えた「ワンチーム」の気配りを見て、晴れやかな気持ちになった。
公共の場に限らず、気配りが人の原点だと思うが、その「気配り」というワードが確実に希薄になりつつあるのが現代。“気配りのすすめ”なんて言うと大げさだが、せめて公共の場では「気配り」という最低限のマナーを忘れないようにしたい。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
小鉄
取材記者を経て、現在はフリーの執筆者。全国の地方都市を取材拠点に、最近は自身の現状も踏まえ、「生活苦」にスポットを当てた執筆に注力。趣味は地方巡りで、滞在地の史跡、神社仏閣、夜の街には欠かさず足を運んでいる。
Photo by:heino eisner