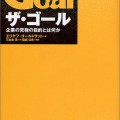かつて自分は研修講師をしていた。年間100回以上。その「何かを講師として人に伝える」というのは非常に有意義な体験だったが、それとともに「教える」ことの難しさも学んだ。
かつて自分は研修講師をしていた。年間100回以上。その「何かを講師として人に伝える」というのは非常に有意義な体験だったが、それとともに「教える」ことの難しさも学んだ。
私が行っていた講義は大体が2時間から3時間、長いものでも5日間程度のカリキュラムのもの。それほどボリュームがあるわけでもない。そして講義を受けている人々は100%社会人であった。そして、講義の後には必ず「アンケートを取る」といったことをしていた。
大抵の方はいわゆる「満足した」という回答をする。
そして、一部の人は「ものすごく役に立った」あるいは、「全く役立たずだった」という回答をする。そして、我々はそういった「役立たずだった」というアンケートの結果を受け、講義やテキストを改良してゆく。
そして、そういった不満の大半は、「講義がわかりにくい」というものではなく、「もう知っていることだった」というものだった。
たしかに「知っていること」について講義をされても、「今さら」ということで講義はつまらないものになるだろう。それは納得である。
しかし、面白いのは追跡調査の結果だ。
私は担当顧客の許可を得て、「もう知っていることだった」とアンケートに回答した方にインタビューを行い、「知っていることを実践しているか」を聞いた。すると驚いたことに大半の方が、「知っているけど、実践はしていない」と回答したのだ。
なるほど。
これは問題である、ということで、さらに顧客へインタビューを行うと、更に面白いことがわかった。アンケートに「満足」と回答した人ですら、
「講義で聞いた内容を実践しているか?」
という質問に対して、「実践している」と回答した人は2割程度しか存在しなかったのである。
「ノウハウ」を聞いて満足しても、「実践」はしない。したがって、私が行っていたセミナーは、「単なるエンターテインメント」として捉えられていた、ということである。
「ザ・ゴール」という有名な本がある。「制約条件の理論」という有名な経営理論をわかりやすく物語調で解説した本だ。(物語としてはとても面白い、オススメである)
著者はイスラエルの物理学者であり、コンサルタントでもある「エリヤフ・ゴールドラット」である。
この本は約250万部も世界中で売れ、多くのビジネスマンに読まれたという。しかし、ゴールドラットは後の本の「あとがき」でこのような趣旨のことを述べている。
「ザ・ゴール」を読んだ殆どの人達が、私のメッセージに共感し、それを「常識(コモンセンス)」とも呼びながら、しかしそれを現場には導入しなかったのだ。
つまり、これほど読まれた、わかり易い内容の本であっても「実践する」ということはまた別次元の話だということだ。
彼の分析では理由は3つあった。
1.「ザ・ゴール」のメッセージを社内全体に広く伝えることができない
2.「ザ・ゴール」で学んだことを、現場での実際の作業にどう置き換えたらいいのかわからない
3.評価基準の変更を容認するよう意思決定者を説得できない。
ゴールドラット氏の苦労が忍ばれる。
さて、ゴールドラット氏は以上のような原因をあげたが、私個人としてはもっと深い所に原因があると思う。それは、セミナーで紹介したことが「ものすごくカンタンで」「個人レベルでも実行できる」ことであっても、同じように実践されないからだ。それも、「セミナーで不満」という人ではなく、大半が「満足」という中でである。
ここから、私はひとつの知見を得た。
「大半の人間は、変化を嫌う」
それも、一般的にそう思われているよりも遥かに変化を嫌う。しかし、それだけではない。ノウハウを実践した人々が、それを「実践しようと思ったきっかけ」を調べると、面白いことがわかった。
きっかけは、上司の命令でもなく、同僚のススメでもない。理由は
「今までやっていたことの延長だったから」
というものであった。
大変面白い。すなわち、ガラケーからスマートフォンへの移行も、生活習慣の変更も、あるアプリを使うかどうかも、何を食べるかも、結局は「今と少しだけ違う」ことしか、殆どの人はやろうとしないということだ。
「実行するかどうか」は、「論理の正しさ」によって実行されるのではない。「過去にやっていたこと」によって実行されるのだ。
ここからわかるように、「ノウハウを学ぶ」ということと、それを「実践する」ということは天と地ほどの開きがある。おそらく、コンサルタントが「口だけ」と揶揄されるのはこういった所に原因があるのだろう。「ビジネス書」や「自己啓発」などが役に立たないと言われるのも、同じようなことが原因であると思う。
人の行動を変えようとしてはいけない。変えようとするのではなく、ちょっとだけ付加するのだ。それがさらにうまくいくように。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。