1.個人ブログ、マイナーサイトなどからキュレーションする。大手メディアからはキュレーションしない。
2.個人が本当にオモシロイと思ったものだけを掲載する
3.記事が書かれた時代に関わりなくキュレーションする(古い記事もキュレーションする)
公式Twitter(@Books_Apps)でも毎日発信しています。フォローして頂ければ「他サイトおすすめ記事」を毎日受け取ることができます。
どうか楽しんでいただければ幸いです。
Books&Apps編集部
はじめに
これから希少がんを切り終わったあと、人工肛門を一時造設した自分の話をする。LARS(低位前方切除術後症候群)についても触れる。この状況については、希少がんはほぼ関係なく、広く大腸がん、直腸がんになった人に共通するものになるかと思う。
ただし、おれは横の比較をするつもりはない。あくまで縦の比較であり、おれがおれの身体を通して、おれのなかで感じたことを書く。
ん? 横と縦ってなんだって?
たとえばある有馬記念があって、べつの馬同士、コスモキュランダとダノンデサイルの能力や実績を比べるのが横の比較だ。
一方で、コスモキュランダだけを見て過去の成績、好走傾向、調子の上下などを見るのが縦の比較だ。そういうことだ。
おれがいくら苦しいとわめいたところで、「もっと苦しい病気の人もいる」と言われてしまえば、それはそうだとしか言いようがない。「グエー死んだンゴニキ」はもっと若くして亡くなっている、と言われたら返す言葉もない。
しかし、それを言い出したらきりはないし、不毛なことになりかねない。だれも声を出せなくなる。いろいろな状況の人がいて、それぞれ近かったり遠かったりする。自分の声を出すことによって、わりと近い人の参考になるかもしれない。そのつもりで書く。
もちろん、病気のやつは自分の主治医の言うことを聞け。標準的な医療をしている医師の言うことを。
休戦したつもりでいた
さて、おれは希少がんである大腸のNET(神経内分泌腫瘍)に罹った人間だ。
「罹った」というのは、手術により取り切ったと言えそうなので過去形にしている。転移もなさそうだし、病理診断で写真を見ながら「マージンをとって切れました」というのを聞いた。
おれのなかで、NETという希少がんはなんとかなった、というのが今のところの感覚である(もちろんこの先どうなるかはわからない)。
しかし、入院して、手術して、退院して、それで終わりではない。おれは手術にあたって人工肛門を一時造設したのである。
それが決まったとき、おれは「希少がんと休戦した」と書いた。
「この距離なら肛門温存できそうです」。なにかこう、心から救われたような気になった。
おれは死ぬということよりも、具体的に人工肛門が怖かった。そのことは書いてきたとおりだ。死へのイメージが足りなすぎるかもしれないし、人工肛門を恐れすぎているのかもしれない。でも、そのあたりは人それぞれの感覚、価値観だろう。
結果、人工肛門の一時造設となった。これはなんなのだろうか。聞いた瞬間は「九死に一生を得た」と思った。
そうだ、おれは永久人工肛門ではなく、一時で済むという診断にずいぶんホッとした。助かったと思った。
むろん、人工肛門を閉鎖したあとに「頻便」になるという話は医師からもあったし、そのやりとりも上の記事に書いている。とはいえ、そのときのおれは希少がんの重さと、永久人工肛門かどうかで頭がいっぱいだった。閉鎖後の話が出たときは「なんと」と思ったくらいだ。
もちろん、「人工肛門(ストーマ)の一時造設」についてたくさん調べた。体験談もたくさん読んだ。体験談を読むと、閉鎖後の記録を残している人も少なくなかった。だから、「頻便」では済まないぞ、ということは頭のどこかにあった。どこかにあったが、まだそこまで考える余裕はなかった。まだ腸の中には希少がんがある。
しかし、今考えてみると、おれが救われたようになったこと、ホッとしたこと、よかったと思ったこと、ぜんぶ、浅はかだった。愚かだったといってもよい。休戦と書いたが、その戦場には大量の地雷が残されていたのだ。
人工肛門は最悪だ
と、「地雷」について書く前に、おれの人工肛門に対する印象を書いておく。
最悪なものを想像していたが、それよりもさらに悪い。
造設後2ヶ月、退院後1ヶ月くらい経っての正直な感想がこれである。あくまでおれの場合の話だ。
まずは、内臓が外に出ているという状況そのもの。いくら装具で覆っているとはいえ、このことが怖い。いやな感じがつきまとう。これが24時間絶え間なく続く。
そうだ、人工肛門は新たなる臓器だ。眼鏡のようにつけ外しできるものではない。それが常に主張する。ストーマ装具が主張する。ちょっと動けば、「いま、剥がれるような感覚があった」となる。
歩けば揺れてお腹を引っ張るし、なんなら常に引っ張られている。それだけ強力に吸着していなければ、四六時中便を受け止めて溜めることなどできないので当然だが、そこに意識が持っていかれる。
そして、排出の気持ち悪さ、これである。これはあまり世の中で語られていない。調べても出てこない。ストーマからの排出は基本的に無意識に行われ、本人は気づかないという建前になっている。
だが、おれはときどき「キューッ」となって、足をバタバタさせないと耐えられないような締め付け感に襲われる。そうでないときも、プツプツ、ポツポツと、ストーマが排出するのがわかるときがある。その気持ち悪さといったらない。むろん、ストーマに感覚はないので、周囲の問題だが。
そのあたり、医師に聞いてみたら、あっさりと、「ストーマ周囲の筋肉の反射」と答えてくれたわけだが、本当にこれも辛い。
ストーマが排出時にキューってなる問題(ストーマの痛み、違和感について)
これらが、とにかく24時間、絶え間なく存在しているのだ。部屋の外、病院や会社などであるていどの時間を過ごしていると、どんどん神経がすり減っていくのがわかる。ナイフでザクザクやられているように、メンタルが削られていく。
もちろん、自分の部屋のなかにいようとも、心は休まらない。はっきり言って眠れていない。もとより精神障害があって眠れないタイプの人間ではあるが、それにしても眠れない。眠れたとしても、ゆっくり眠れない。だいたい、ストーマがあるので自由に寝返りも打てない。
造設以来、「よく眠れた」ということは一度もない。時間的に睡眠時間が十分だとしても、おれの目はずっと極度の寝不足のときのように歪んでいる。目の下のくまもとれない。頭のなかももうストレスでむちゃくちゃになっている。もとから狂っているが、一線を超えた狂気の世界に行きそうだ。
最悪より地獄のLARS
「そこまでいうのであれば、たとえ排泄障害になろうが人工肛門を閉鎖するにこしたことはないじゃないか」と言われそうだ。
だが、こんな人工肛門が「パラダイス」のようだと言う人すらいるのが、LARS(低位前方切除術後症候群)である。
数少ない(唯一の?)LARSについてのサイトを少し読めばだいたいわかるだろうか。おれはこのサイトを運営している医師や看護師などの専門家がアップしたYouTube動画もすべて見た。
LARSは、Low Anterior Resection Syndromeの略です。日本語では「低位前方切除術後症候群」といいます。
直腸がんの手術療法には様々な術式がありますが、「低位前方切除術」や「括約筋間直腸切除術」は切除後、残存する結腸と肛門を縫い合わせる、つまり肛門を残す(排泄経路の変更がない)ものです。
この術式では永久的人工肛門を回避することはできますが、実は、患者さんは術後、長期間にわたって複雑でやっかいな排便障害を体験することになります。
LARSの代表的な症状は「不意に生じる便意(便意逼迫)」、「便の漏れ(便失禁)」です。ただ、これらは日中、いつ・どこであろうが、何の前触れもなく突然起こる、予測不可能な症状なのです。ですから、LARSの患者さんは四六時中、排便のことを気にしながら生活することを余儀なくされます。
当然のことながら、会社や学校など社会生活は極めて困難になります。一般の下痢とは原因も症状も全く異なるので、経験も知識もない他者にはなかなか理解してもらえません。家族や周囲の人にさえうまく伝えられず、一人で悩み苦しんでいる人たちがいます。
四六時中の人工肛門のストレスが終わると、次は四六時中の排便のストレスが待っている。その確率は7~9割とされている。
そして、なりやすい、重症化しやすい要素として、「男性」、「高齢ではない」、「一時的人工肛門造設」、「切除した場所の肛門からの距離の近さ」などがあり、おれはすべてに当てはまっている。おれがLARSになるのは確実だといっていいし、重症化する確率も客観的に見て高い。
では、LARSは治るのか。これが、不治の病なのである。なぜならば、直腸そのものが失われているから。直腸という貯蔵タンクがないのである。
ほかの部分は代わりになってくれない。また生えてくるわけでもない。薬やなにかでどうにかするには限界がある。これはもう、物理的に治らない。神経が一緒に切除されているから、などの理由もあるが、なによりも物理的に失われているのが大きいように思える。
この動画でも、患者役が「でもLARSはそのうち治るんですよね?」というセリフを言ったら、不穏な音楽が流れて終わる。
そして、後半に行くとそれに対して明確に答えることなく、どれだけ術後によくならないか、についてのデータが提示される。術後18ヶ月までは改善するが、その後は横ばい。
最初に重症だと、よくて一生軽症のLARS。つまり、一生排便のことで頭がいっぱいになりながら生きていかなければいけない。
というか、頭がいっぱいで済むわけではない。まずは家から出られない。頻便と不意の便意、便失禁、外出は難しいだろう。これが少し落ち着いたところで、おむつが必要な生活がつづく。そんな状況で外に出られるだろうか。
とうぜん、肛門は痛むだろうし、たいへんな皮膚障害が起きることもあるだろう。これが、治らない。一生続く。もう外で仕事をすることもできなくなるし、遊びに行くのも難しい。病院に行かなくてはならないときはどうするのだろうか。一日か二日でも絶食すれば大丈夫だろうか。
第7回 直腸がんの術後の排便障害「LARS」について知る【前編】 発症のメカニズムと食事について(大腸外科医に聞く)
絶食なら大丈夫だろうが、たとえば食事についてのエビデンスもない。まだLARSという病気自体、広く認知されているわけではないのだ。
まあ、それも仕方ないだろう。まずはがんを取り除くというところから始まって、つぎに肛門を温存できるかも、ということが可能になって、さてその次の問題だ。
が、自分のこととしては「仕方ないだろう」では済まされない。
永久人工肛門しか解決策がない
というわけで、上のサイトなどで語られている最後の、最善の解決策が「永久人工肛門造設」である。上のインタビュー記事でもこのようなやり取りがある。
―私は重度のLARSを経験した後、永久人工肛門を造設しました。このような患者の選択をどう思われますか。
肛門に近い直腸がんの方には、私は最初から永久人工肛門を勧めることもあります。手術前に患者さんにヒアリングし、家族構成やお仕事、たとえば長距離トラックの運転など長時間トイレに行きにくいようなお仕事かどうかを確認します。
また、生きがいとしているものがテニスやゴルフ、ダイビングと言った場合など、その方の状況を把握してから術式を決めるようにしています。
上の方で「パラダイス」と書いたが、そう表現していたのはこのインタビュアーの方である。YouTubeの動画でそう語っていた。
この方はがんサバイバーとして積極的に発信を行っており、非常に有用な体験談が読める消化器がんのコミュニティサイトにも関わっている。ただ、ネットに公開されている部分はあるものの、そのサイトは女性専用となっており、男性である自分が直接言及するのは失礼だろう。
まあとにかく、LARSを体験したあとだと、人工肛門がパラダイスに思えるという。ほかにも、一時的人工肛門造設者が、未来のLARSについて思い悩んでいる暇があったら、人工肛門のうちに人に会ったり、好きなものを食べたりしたほうがいいという書き込みなども見た。LARSになると、人にも会えないし、ものも食べられない。そういうことだ。
いずれにせよ、LARSの最終的な解決策がなにかといえば、「永久人工肛門造設」、これなのである。上の記事の動画版も見たが、「そうだよね、人工肛門だよね」という感じで語られている。そうか、なんだ、人工肛門にすればいいのか。
……って、なるわけないだろう。おれがどれだけ人工肛門を恐れ、実際になってみて想像より悪いと感じ、ガリガリ精神を削られているかは書いたとおりだ。
これが「一時的人工肛門造設」という休戦が残していった地雷だ。
地雷という比喩が不適切だと言われるかもしれないが、おれの正直な感覚である。がんとの戦争は終わったはずなのに……。
おれはLARSを知れば知るほど、ひどい恐怖とストレスがのしかかってきて、人工肛門とともに二重の地獄のなかにいる。
第8回 直腸がんの術後の排便障害「LARS」について知る【後編】 排便障害の本質的な辛さ「人間の尊厳」との関わりとは(看護学の教授に聞く)
こちらの記事ではLARSが「人間の尊厳を損なう」とされているが、おれにとっては同じように、人工肛門というものが辛い。あくまでおれの話だが、人工肛門が楽だというのもだれかの話にすぎない。
何かの代償なしに生命は救われない
さて、ここまで書いてきて、最新の情報として「そもそも人工肛門を閉鎖できるのか」という話も出てきたのでちょっと書いておく。
閉鎖に向けての検査で吻合部(つなぎ合わせ部分)が狭くないかということになったのだ。というか、内視鏡を入れたら、1cmの内視鏡が入らないほどであった。そこにバルーンを入れて拡大する手術(?)を2ヶ月くらいかけて何回も行う、そういうことになった。ひょっとしたらよくならないかもしれないし、そうなったら永久人工肛門確定だ。
……と、書いて、ほんの少しだけ、本当にほんの少しだけ楽になった自分もいる。人工肛門か便意の地獄かという究極の選択をしなくて済むのではないか? ということだ。
これまで人生でこれといった選択をすることがなかった。ただ流されるままに流れてきて、低く暗い方へ流れ着いた。先の見通しもなにもない。しかし、それにしたって、究極の選択がこんな二択になるとは思いもしなかった。
まあ、これが大きな病気をすることなのだな、とも思う。ちょっと遅れていたら生命を失うような病気が、入院、手術くらいで都合よく消えてなくなってくれるわけがない。これが大病の代償というものなのだろう。
まあ、あまり大きな代償を払いたくないという人間は、こんなものを読んでないで、とっとと大腸内視鏡検査なり、人間ドックなりの予約をしたほうがよい。軽いうちに終わらせろ。そうでないと、おれのように人生が終わる。
[adrotate group="46"]
【著者プロフィール】
黄金頭
横浜市中区在住、そして勤務の低賃金DTP労働者。『関内関外日記』というブログをいくらか長く書いている。
趣味は競馬、好きな球団はカープ。名前の由来はすばらしいサラブレッドから。
双極性障害II型。
ブログ:関内関外日記
Twitter:黄金頭
Photo by :
今年の正月休みのあいだに、私は長く続けてきたlivedoorブログを整理した。
Googleアドセンスを停止し、すべての記事を非公開にしたのだ。
最後にlivedoorで記事を更新し、活動の場をnoteに移したのは2025年の1月。
「noteに引っ越して、一年経ったらlivedoorブログを消そう」
そう決めていた。
告知はしていない。自分の中だけで決めていたことだ。人知れず、ひっそり消えるつもりだった。
「流れの早い世の中で、もはや個人のブログは読まれなくなっている。きっと1年も経ったら、私のブログが消えたところで誰にも気づかれないだろう」
そう思っていた。
案の定、年明けに全ての記事を非公開にしても、特に誰からも反応がなかった。誰にも気づかれなかったか、なんとも思われなかったのだろう。
寂しいような気もしたが、安堵の気持ちの方が大きい。
正直に言うと、会社員として働き始め、生活の中でリアルでの人付き合いが比重を増していくにつれて、好きなように書き散らかしてきた過去のブログが重荷になってきていた。
facebookのアカウントは、先駆けて削除済みだ。
私は地方で生きているし、これからも生きていく。
田舎の小さなコミュニティで、周囲の人々と密接に関わりながら生きていかざるをえない今後の暮らしについて考えると、ここらで一度、過去を精算する必要があった。
ただ、全てを消し去りたいわけじゃない。noteに転載して、取っておきたい記事もある。
そのため、今は一度すべての記事を非公開にし、ひとつずつ読み返しながら、残すものと、残さないものを選別している。
この作業が思った以上に大変で、遅々として進まない。
私がブログを書き始めたのは2015年で、最後の更新が2025年。意識しないまま、気づけば10年ものあいだ書き続けていたのだ。
一日につき一記事はチェックしようと決めたが、量が多く、いつ終わるのか分からない。
自分の書いた記事を一から読み返していると、時代の移り変わりが見える。
「あぁ、この時にはこんなことがあったのか」「そういえば、あんなこともあったなぁ」と、当時の空気感を思い返しては、しみじみと感傷にひたっている。
私がブログを書き始めた2015年ごろは、個人が情報発信する手段の主流は、まだブログだった。様々なブログサービスが乱立しており、みなが競うように文章を書き、それをFacebookやTwitterで共有し、コメント欄でやり取りをする。
たくさんの人気ブログがあった。耳目を集めるブロガーはインフルエンサーと持て囃され、何冊もの書籍が出版された。
「ブログで稼ぐ」が流行ったのもこの頃だ。
しかし、やがて発信の中心は文字から写真へ、写真から動画へと移っていく。
YouTuberが時代の寵児になったと思ったのも束の間、次第にショート動画やライブ配信へとトレンドは移り、若者の間ではTikTokerやライバーが脚光を浴びるようになっていった。
こうした時代の流れの中で、かつて隆盛を誇った人たちは、どこへ行ったのだろう。
「イケハヤ」や「はあちゅう」といった、炎上を繰り返しながらも強い影響力を持っていた元ブロガーたちは、今でもしぶとく活動はしているようだ。
けれど、もう彼らが世間の関心を集めることはない。
私は、かつて彼らが掲げていた「脱社畜」をうたうビジネスを、かなり批判的に書いてきた。彼らの手の内を知るほどに「こんな悪党どもは私が叩き潰してくれるわ!」と息巻いていたのだ。
今振り返ると、何をそんなに怒っていたのかと不思議に思うが、当時はまだ“憤れる若さ”があったのだろう。
あの当時、イケハヤ、はあちゅう、そして彼らの取り巻きへの批判記事を書くアンチやウォッチャーは、私以外にも数えきれないほど居た。私たちが書くような批判記事にもPVが集まったのは、それがネットのエンタメだったからだ。
彼らが起こす高火力の炎上の愉快さと、それに対する苛烈な批判の痛快さとがセットになることで、ネットユーザーを熱狂させるコンテンツになっていたのである。
ネットの空を茜色に染めていた火柱も、それを眺める野次馬たちの高揚も、今や昔の話だ。
今になって思うのは、彼らのような炎上ブロガーを終わらせたのは、アンチやウォッチャーからの批判ではなく、本人たちが起こしたスラップ訴訟でもなく、時間だったということだ。
インフルエンサーには旬がある。
どんな過激な表現にも、どんな極端な思想にも、人はやがて慣れてゆき、飽きてしまい、そして新しいオモチャを探し始める。
情弱ビジネスの一種であるキラキラ起業や、スピリチュアルの流行も同じだ。
かつてキラキラ起業と呼ばれたムーブメントは、まだ消えてはいない。
けれど、そこにかつての熱狂はない。
スピリチュアルと結びついたインチキなビジネスも、教祖たちが自滅したり、方向転換したりしながら鎮静化していった。
かつて多くの女たちの心をとらえた
「自分を愛し、自分だけの機嫌をとり、自分らしくワガママに生きよう」
「嫌なことはしない。どこまでも己の欲望に忠実であれ」
「私は私。他人がなんとディスってこようと、耳を貸す必要はない」
という、一昔前は新鮮だった子宮系スピリチュアル教祖たちの主張も、珍しくもなんともなくなってしまった。
まったくと言っていいほど同じ内容を、今では教祖たちよりはるかに面白いトーク力でアレン様が喋っているし、圧倒的な迫力で、ちゃんみなが歌いあげる。
本物の才能と突き抜けた存在の前では、スピリチュアル教祖たちのささやかな人気や影響力など吹き飛ぶしかない。
だいいち、いくらアメブロで「女たちー!女性性を開花させよう!子宮の声を聞いて!」と語りかけても、もはや「カモになりそうな女たち」は字を読まないのだ。
発信手段のトレンドも、時代と共に移り変わる。
私が馴染んでいたTwitterはXに変わり、青い鳥は消えた。
そして、SNSは「誰もが無料で発信できる場」ではなくなってしまった。
サービスは有料化し、どの投稿が表示されるかはAIが決め、フォロワー数は無意味と化した。
ブログを書き、リンクをSNSで流し、フォロワーから反応が返ってくる。そして交流が生まれる。そんな循環は、もう当たり前ではない。
つまらないけれど、仕方がないことなのだ。こうした流れに違和感や失望を感じること自体が、私自身がとっくに時代遅れになっている証拠なのかもしれない。
今のところ、noteは楽しい。
広告は表示されず、コメントを通じた読者との交流もあり、かつてのSNSやブログ文化を彷彿とさせる一面がある。
私はnoteに活動の場を移したけれど、livedoorブログ時代に親しく交流していた人たちの多くは、とっくに消えてしまった。
彼ら・彼女らは時代に敗北したのではなく、成長し、変化し、卒業していったのだ。
私自身もまた、変化している。気持ちも、立場も、生き方も。
私が10年間ブログに書いてきたのは、その時々で熱くなったり、冷めたりする自分の温度だったのかもしれない。
時代は変わる。
プラットフォームも、アルゴリズムも、読者も変わる。
それでも、書くという行為だけは、形を変えながら、しぶとく生き残っていく。
私は、次の場所で、また書くだけだ。
[adrotate group="46"]
【著者プロフィール】
マダムユキ
ブロガー&ライター。
リンク:https://note.com/flat9_yuki
Twitter:@flat9_yuki
Photo by :Denny Müller
少し以前の事だが、陸上自衛隊の元最高幹部とお酒をご一緒させて頂いている時、こんな質問をしたことがある。
「鈴木貫太郎ってなぜ、あのタイミングで総理大臣を引き受けたのでしょう。実利からも名誉からも全く割に合わないので、よくわからないんです」
鈴木貫太郎とは、太平洋戦争で日本が敗れた時の最後の総理大臣だ。
1945年4月、敗戦のわずか5か月前に、今に至るも史上最高齢となる77歳で着任した首相として知られる。
昭和天皇から、戦争を終わらせるよう直々に大命を受け、文字通り命を懸けて戦争を終わらせた人物といえば、ご存じの方も多いだろう。
その鈴木、元々は生粋の軍人だった。
日露戦争では、駆逐隊の司令として日本海海戦に臨み、多くのロシア艦を撃沈した歴戦の英雄である。
多くの武勲もあり海軍大将まで昇るのだが、退役後は名誉職のポストを歴任しながら老後を養っていた。当然、総理大臣どころか何らの国務大臣を務めた経験すら、まったく無い。
そんな鈴木が、「(戦前の)日本を滅亡させることになる、最後の総理大臣をやれ」といわれたわけである。人生をかけて築き上げてきた名誉が全てぶっ壊れるだけでなく、子々孫々まで「敗戦の総理大臣」と誹りを受けるだろう。
実際この時、長老たちは多くの政治家に総理大臣への就任を打診するのだが、適任と思われる者たちは皆逃げた。
そのため最後に、その役割が鈴木に回ってきたわけである。
どう考えても、こんなもの受ける方がおかしい。
とはいえ同じ立場なら絶対に受けたくないし、私だってきっと逃げる。
そんな思いもあり、同じ「最高位にあった元軍人」である陸将に、冒頭のような質問をしたということだ。
すると返ってきたのは、こんな言葉だった。
「桃野さん、それは貫太郎が軍人だったからです。逃げ出した人たちは、政治家だからです」
(そうか…そういうことか)
短くシンプルな答えだったが、一瞬で腹落ちした。
「もっと早く救助が来ていれば…」
なぜ腹落ちしたのか。
その説明の前に、毎年この時期になると思い出す印象深い話を聞いて欲しい。1995年1月17日午前5時47分に発生した、阪神淡路大震災についてだ。
いまさら多くの説明は要らないだろう。
淡路島北部を震源とするマグニチュード7.3の地震が主に阪神地方を襲い、死者・行方不明者6,437名もの犠牲が出た、痛ましい出来事である。
「確かに痛ましい大災害だったけど、東日本大震災の死者・行方不明者22,228人に比べると、減災できた方なのでは?」
そんな印象を持つ人がいるかもしれないが、全く違う。なぜそんなことが言えるのか。
政府の公式資料から記述するが、東日本大震災における犠牲者の死因は、90%以上が溺死であった。
あれほど急速かつ大規模に押し寄せてきた未曾有の津波の前に、人は本当に無力だった。
誰がどうしたところで、発災後に救える命は限定的だっただろう。
それに対し、都市直下型の阪神大震災は、まったく違った。
死因の7割超が、建物などの倒壊による圧死・窒息死であり、なおかつ建物が倒壊し挟まれたことで身動きが取れず、凍死や焼死に至った人を含めると、9割を超える。
東日本大震災とは、犠牲になった方の死因が全く異なるのである。
「もっと早く救助が来ていれば、助かった命が無数にあった可能性がある震災」であったということだ。
言い換えれば、自衛隊に1分でも1秒でも早く災害派遣要請が発出されていれば、多くの命が救われた可能性があるということである。
にもかかわらず、自衛隊に災害派遣要請が為されたのは発災後、実に4時間以上も経った後の、午前10時頃。
今さら名指しは避けるが、自衛隊に災害派遣要請を出す権限を持つ地元の首長による、余りに遅すぎる最悪の意思決定の結果である。
「いやいやいや。あれほどの大災害なんだし、全体把握には時間がかかるでしょ
「批判は結果論に過ぎない。むしろ4時間で意思決定したのであれば、十分では?」
そんなふうに思う人も、きっといるかもしれない。
そう考える人に対して聞いて欲しい話が、本コラムのメッセージである。
前例のない決断
その話とは陸上自衛隊の第36普通科連隊、黒川雄三・連隊長(当時・以下敬称略)の意思決定についてだ。
第36普通科連隊は兵庫県伊丹市に所在し、発災時における受け持ち地域は北大阪及び阪神地区である。もっとも被害の大きかった地域を管轄する、陸上自衛隊の部隊だ。
そして1995年1月17日5時46分。
黒川は経験したことがない大きな揺れで目を覚ますと、直ちに連隊本部に現れ、隷下部隊に対し出動待機命令を出す。
しかしいつまで経っても、政府や地元首長からの出動要請がまったく下りてこない。
その一方で、目の前では建物が大規模かつ広範囲に崩落し、また煙が上がり次々と火災の確認報告がなされる。
この非常時に指を咥え、人々が犠牲になっていくのを見ているしかないのか…。
そんなことに思い悩んだであろう黒川は、前例のない異例の決断を下した。自衛隊法第83条3項の近傍派遣条項を援用しての、独断での人命救助である。
詳細は端折るが同条項には、基地や駐屯地の近傍で火災が発生した際には、指揮官は独断で部隊を動かしても良いことが記されている。
とはいえその目的は火災の鎮圧であり、それ以上でもそれ以下でもない。
黒川はこの条項を援用し、午前7時30分に部隊を動かすことを決断すると直ちに、人命救助に動き出した。
地元の首長が午前10時に自衛隊に災害派遣を要請する、実に2時間30分も前である。
言うまでもなくその結果、多くの人命を救助している。
これだけを聞くと、ただの「勇気ある美談」と思われるだろうが、まったく違う。
今の若い人には想像もつかないと思うが、1990年代といえば、社会党(現社民党)の党首が総理大臣であり、日本全体が“左傾化”していた時代だ。
自衛隊に対する世間の理解は最悪であり、マスコミをはじめとして、自衛官には何をしても許されるような風潮があった。加えて、兵庫をはじめとした近畿地方は伝統的にリベラルが強く、特に自衛隊に風当たりの強い地域である。
そんな中で、前例のない自衛隊法の援用を理由に、指揮官が独断で部隊を動かしたら、どうなるか。
「二・二六事件再来の恐れ」
「満州事変の教訓が生かされていない自衛隊法」
などのように、マスコミが書き立てる可能性が極めて高かっただろう。
当然、そのように世論が動けば黒川はクビになっていたであろうこと、想像に難くない。
控えめに見ても、左遷されキャリアを失うであろうことは、本人も理解していたはずだ。
にもかかわらず、黒川は前例のない独断で部隊を動かし、多くの人の命を救った。
繰り返すが、阪神淡路大震災における犠牲者の死因は7割超が圧死であり、身動きをとれなかったことによる凍死や焼死を加えると9割超に昇る。
その現実をまさに現場で目にしていた黒川が決断したことの重みを、どう思われるだろうか。
「もう一つの真実」
話は冒頭の、鈴木貫太郎の決断についてだ。
十分な名誉と悠々自適な老後生活をすべて捨ててまで、なぜ国家滅亡の責任者という誹りと命の危険を選んだのか。
どう考えても割に合わない総理大臣への着任を、なぜ引き受けたのか。
「桃野さん、それは貫太郎が軍人だったからです。逃げ出した人たちは、政治家だからです」
元陸将の言葉が、シンプルでありながら軍人という人たちの価値観と行動規範を表している。
軍人にとっての行動規範とは、適時適所において迷い無く正しい意思決定を下し、その意思を貫徹することにある。
政治家のように、利害得失の計算や環境要因により、「為すべきこと」が変わるようなことなどない。
「こんなことしてクビになっちゃったらやだなあ。見なかったことにしよう」
そんな行動規範からは、最も遠いところにいる。
「いやいやいや、それは鈴木貫太郎が特別だっただけでしょ。黒川連隊長も、例外的に立派な人だっただけでは」
そんな風に思われるだろうか。
確かに24万人もいる自衛隊はある意味で社会の縮図であり、立派な人もいればどうしようもない人もいる世界だ。
しかし、大部隊を率いる指揮官に昇れるような人はかなりの確率で、貫太郎や黒川と同じ決断を下すと確信している。
だからこそ冒頭のような質問に対し、元最高幹部は迷い無く即答した。即答できるということは、血肉になっている常識ということであり、考えるまでもないからである。
なお余談だが、自衛隊への災害派遣要請が遅れた地元の元首長は後年、講演会でこんなことを言ったことがある。
「自衛隊って、数年で偉い人が入れ替わるんです。あの時も、誰に連絡していいかわからなかったんです」
余りにもバカバカしい言い訳だ。小学生ですら、もう少しマシな言い訳をするだろう。
それに対し黒川は、後年までこう悔やんでいたそうだ。
「もっと早く部隊を動かしていれば、もっと多くの人の命を救えたのではないか…」
そして忙しい公務の傍ら、時間を見つけては四国八十八ヶ所をお遍路で回り、犠牲者に鎮魂の祈りを捧げ続けた。
この話は毎年、1月になると色々なメディアに何度も、同じような文脈で書いている。
今年も書いた。
ぜひ一人でも多くの人に、阪神淡路大震災における「もう一つの真実」を知ってほしいと願っている。
[adrotate group="46"]
【プロフィール】
桃野泰徳
大学卒業後、大和證券に勤務。
中堅メーカーなどでCFOを歴任し独立。
主な著書
『なぜこんな人が上司なのか』(新潮新書)
『自衛隊の最高幹部はどのように選ばれるのか』(週刊東洋経済)
など
改めまして、震災で犠牲になったすべての人のご冥福をお祈りします。
微力ですが、できる限りの教訓を語り続けたいと思っています。
X(旧Twitter) :@ momod1997
facebook :桃野泰徳
Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kantaro_Suzuki_suit.jp
「あいつら、内容の無いことばかり喋ってやがる」と学校や職場の同僚を馬鹿にする人は珍しくない。
世間を知らない学生のセリフかと思いきや、30代、40代の人が同じことをさえずっているのを見てびっくりさせられることもある。ほとんどの場合、こうしたセリフは人望が無い人の口から出てくる。
いつも思弁している人、いつも世界の重要事について考えている人は、世間では少数派だ。
いや、実のところ、「あいつらは内容の無いことばかり喋っている」と言っている本人だって本当はそうなのだ。有意味なこと・重要なことだけを喋る人間など、めったにいるものではない。
仮にいるとしたら、それは事務的な内容や数学の解法のような内容しか喋らない、ロボットじみた人間だろう。
少なくとも、「あいつらは内容の無いことばかり喋っている」などという、内容の無いことをペラペラ喋ったりはしない。
「コミュニケーションの内容」より「コミュニケーションしていること」のほうが重要
人間同士のコミュニケーションを振り返った時、そのコミュニケーションの内容が厳密に問われている場面は思うほど多くはない。
もちろん、報連相的なやりとりに際しては正確な情報伝達が肝心だし、そのためのトレーニングも必要だ。しかし日常会話の大半は、「コミュニケーションの内容」よりも「コミュニケーションをしていること」のほうが重要だ。
その典型が、「おはようございます」「お疲れ様です」「おやすみなさい」「よろしくお願いします」といった挨拶のたぐいである。
挨拶には内容は無い。昔は、“お早うございます”にも内容があったのかもしれないが、もはやテンプレート化している今では無いも同然だろう。
だが、進学や就職のたび挨拶の重要性が語られることが象徴しているように、コミュニケーションに占める挨拶のウエイトは馬鹿にできない。挨拶を行う意志や能力を欠いている人は、社会適応は著しく難しくなるだろう。
お天気や季節についての会話や、時事についての会話、女子高生同士のサイダーのような会話なども、しばしば「内容のない会話」の例として槍玉に挙げられる。
しかし、交わされる言葉の内容そのものにはたいした意味が無くても、言葉を交換しあい、話題をシェアっているということ、それ自体には大きな意味がある。
言葉には、一種の“贈り物”みたい効果があって、言葉を交換しあうことが人間同士に信頼や親しみを生みだす。というより、黙っていると発生しがちな、不信の発生確率を減らしてくれる、と言うべきかもしれない。
人間は、「私はあなたの存在を意識していますよ」「私はあなたとコミュニケーションする意志を持っていますよ」と示し合わせておかないと、お互いに不信を抱いたり、不安を抱いたりしやすい生き物だ。
だから、会話内容がなんであれ、お互いに敵意を持っていないこと・いつでもコミュニケーションする用意があることを示し合わせておくことが、人間関係を維持する際には大切になる。
「空っぽのコミュニケーションが好き」も立派な才能
だから、内容のなさそうな会話を楽しくやっている人達のほうが、内容のなさそうな会話を馬鹿にしている人達より、コミュニケーション強者である可能性が高い。
言葉を交わす行為をストレスと感じたり、嫌がっていたりしている人は、この、“贈り物”としての言葉の交換をあまりやらないか、やったとしてもストレスと引き換えにやることになるので、そのぶん、信頼や親しみを獲得しにくく、相手に不信感を持たれてしまう可能性が高くなる。
対照的に、言葉を交わす行為がストレスと感じない程度に定着している人や、言葉の交換をとおして承認欲求や所属欲求を充たせる人は、ますます信頼や親しみを獲得しやすく、不信を持たれにくくなる。ということは、学校や職場での人間関係にアドバンテージが得られるってことだから、「空っぽのコミュニケーションが好き」は立派な才能である。
こうした言葉を交わす行為の効果は、いつも顔を合わせる間柄、日常的に顔を合わせる間柄においてモノを言う。
毎日のように顔を合わせて言葉を交わすからこそ、毎日の挨拶やコミュニケーションが大きな信頼や親しみを生む。逆に、そこらへんが不得手な人は、不信の芽を育ててしまいやすい。
挨拶も世間話もせず、飲み会にも顔を出さないような人は、遅かれ早かれ孤立する羽目になるだろうし、その孤立によって、成績や業績の足を引っ張られやすくなるだろう。
だから、「内容の無いコミュニケーション」「空っぽのコミュニケーション」を馬鹿にしている人は、何もわかっていない、と言える。
職場で最適なパフォーマンスを発揮し、チームワークを発揮していきたいなら、むしろ、挨拶や世間話を楽しんでいる人をリスペクトして、その才能、その振る舞いを見習うぐらいのほうが良いのだと思う。
もちろん、挨拶や世間話は出来るけれども業績や成績がまったくダメな人もそれはそれでダメだが、自分の業務や成績のことばかり考えたり、報連相的な情報伝達の正確さばかり気にしたりして、言葉の交換を軽んじているようでは、渡世は覚束ない。
「内容のないコミュニケーション」が上手になるためには
じゃあ、どうすれば「空っぽのコミュニケーション」が上達するのか?
一番良いのは、子ども時代から挨拶や世間話を毎日のように繰り返して、そのことに違和感をなにも覚えない状態で育ってしまっておくことだと思う。
毎日挨拶ができること・世間話を楽しむことには、文化資本(ハビトゥス)としての一面があるので、物心つかない頃からインストールしてしまっているのが一番良い。
だが、一定の年齢になってしまった人の場合は、自分の力でコツコツと身に付けていくしかない。
その際には、会話の内容や正確さだけでなく、言葉を交換すること自体にも重要な意義があることをきちんと自覚し、「こんな会話になんの意味も無い」などと思ってしまわない事。
それと、そういう会話を上手にこなしている人達を馬鹿にするのでなく、社会適応のロールモデルとして、真似できるところから真似ていくことが大切なのだと思う。
そしてもし、今の職場で挨拶や世間話をする機会が乏しいとしても、そのままほったらかしにしておかないほうが良い。
世の中には、挨拶や世間話をする機会が乏しく、業務上の報連相的なやりとりばかりの職場も存在するが、それをいいことに言葉の交換をおざなりにしていると、じきに「空っぽのコミュニケーション」ができなくなってしまう。
そのような人は、職場以外でもどこでも構わないから、挨拶や世間話を実践して、「空っぽのコミュニケーション」ができる状態をキープしておいたほうが良いと思う。
いざ、「空っぽのコミュニケーション」が必要になった時、慣れていないととっさに出来ないし、できなくなってしまった状態でできなければならない場所に参加した時にはすごく困ってしまうからだ。
──『シロクマの屑籠』セレクション(2017年5月7日投稿)より
[adrotate group="46"]
【プロフィール】
著者:熊代亨
精神科専門医。「診察室の内側の風景」とインターネットやオフ会で出会う「診察室の外側の風景」の整合性にこだわりながら、現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信中。
通称“シロクマ先生”。近著は『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(花伝社)『「若作りうつ」社会』(講談社)『認められたい』(ヴィレッジブックス)『「若者」をやめて、「大人」を始める 「成熟困難時代」をどう生きるか?』『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて』(イースト・プレス)など。
[amazonjs asin="B0CVNBNWJK" locale="JP" tmpl="Small" title="人間はどこまで家畜か 現代人の精神構造 (ハヤカワ新書)"]
twitter:@twit_shirokuma
ブログ:『シロクマの屑籠』

Photo:
どーもー、ズイショと申します。本年もよろしくお願いしますー!
本題ではないので諸々省いて結論から申し上げますと、今の僕はうつ病になってしまい休職中の身となっております。
まず睡眠時間がコントロールできない。朝まで寝れない時もあれば、一日中起き上がれずに布団でうとうとしている日もある。
夜20時に倒れるように眠りにつき25時頃に覚醒してそれから布団に入り直してもずっと眠れない。このテキストは早朝5時に書き始めています。
食事を取れるも取れないもその日次第で家族の団欒の日としたい土日はすき焼きやら寿司やらハンバーガーやら飲み食いはできるが、そんなハレの日に対して家族が家にいない平日のケの日は薬を飲むために仕方なくパウチのゼリーを腹に入れて薬飲んでそれだけなんてことを繰り返しています。半年で体重が10kg減ったり、カップ麺なんかに頼って5kg戻したり。
こんな「うつ病って大変なんだよ」なんて話はネット上に出回って枚挙に暇がないありふれた話なので本題ではなくてですね、今回僕がしたいのは「マジョリティがマイノリティになってみてわかったことが色々ありました」という話です。
以下からが本題になります。
僕の自己紹介をすると、ステータスだけで言えばそれなりに楽しくご機嫌に生きてきたんだと思います。それなりの給料をもらえる会社員としての本業があり、副業もそれなりにこなして妻子を持ち働いてきました。つまりは特に福祉に頼らずマイペースに生きているそこらへんのおっさんです。次の3月で40歳になります。
ところがどっこい経緯は省きますがうつ病を患い急転直下でダメになってしまいました。
会社とか家族とか環境のせいにするつもりはさらさらありません。僕はどうもおかしくなってしまった。ずっとおかしかったのかもしれない。今までのように生きるのはどうにも難しい状態に陥っている。ただその現実を受け入れるばかりの毎日です。
人間を格上だとか格下だとかそういう考えのもとに他人を値踏みして生きてきた自覚は一切ありません。それでも僕は自分はもうダメだと思い至りうつ病になってしまいました。
しかし、その一方で俺は今までマジョリティであったことへの強い自覚と、僕は今マイノリティになってしまったんだという強い自覚があります。
うつ病になって休職に至ったことで、それ以前の僕には関係がなかった色々な手続きや制度に触れる機会が増えました。
うつ病なんざいつ治るかはわからないため退職という選択肢も当然ありえるので、そういうサポートをしてくれるサービスを受けてみたりもしました。あるんですよ、退職給付金サポートみたいなサービスが、世の中には。
結論としては僕にとっては何の役にも立ちませんでしたが。
故郷を離れて生きる自分は現状報告を常に故郷の父親にはしていたものなのでありのままを共有していると、「退職給付金最大480万円!」と謳う広告を父親に紹介されて、一度相談してみれば?と促され、最悪の場合は父親に金の無心が必要になる可能性もあるのでこれを突っぱねては金の無心もやりにくいというので、とりあえず受けてみました。
しかし、そこでサポーターから聞かされたのは当たり前に自分でリサーチして知っている程度の傷病手当や失業保険の仕組みについてまでで、広告でひらひらとひけらかすようなおいしい話は特にありませんでした。1時間のオンライン面談のうち15分で「そこらへんは全部わかってます」で話は終わり、残りの45分は業界の情報交換に終始しました。
僕が「今回は初回無料相談ということですが、契約するとなるとどうなるんですか?」と尋ねると彼は「最初の契約で30万前後、その後は失業保険の代行で月2万頂いてます」と回答しました。
全部自分でそこらへんの手続き未だできる僕からすると大変に馬鹿げた金額になるのですが、それを自分でできない方々がメイン顧客になるとのことです。手取り20万あるかないかのブラック環境下で働く方々が多いとの回答を得ました。
うつ病ながらもそこらへんの知識を以って自分で書類処理ができる人というのは面談希望者の全体の1割以下らしく、その人たち以外の9割の方々を助けるためのサービスをやっていると担当者の方はおっしゃっていました。
ふざけたサービスだなと僕は思いましたし、担当者の方もふざけたサービスであることを隠しもしませんでした。彼にも彼のノルマがあるし、絶対に契約してくれない僕とも1時間の面談を続ける義務があったのでしょう。
「人類の半分は偏差値50以下」というのは僕が好んで使う言葉ですが、なるほど世の中はこういう風に回っているんだなと改めて感じました。
僕がうつ病なのは事実なのであーだこーだ言う資格はないのかもしれませんが、見えない世界が見えてくる。
うつ病であることは診断を受けた以上間違いないながらも、これはあたかもダークツーリズムのようでいたたまれない気持ちになります。言葉を選ばなければ、下界に降りてきた気持ちもあります。自分が病を抱えて初めて見えた社会は助けてくれないんだなという冷酷な景色が見えます。
他にも色々な手続きを進めていますが、悪い世界をちょっと見学に行こうかなという感覚が抜けません。これは、僕が本当にうつ病であることを認めたくなくて面白がってるフリを気取ってるだけなのかもしれませんが。
それでもやっぱり感じるのはマイノリティへの不親切、存在するはずの福祉の存在をアピールしない世の中の仕組み、そういうものを頑なに隠して自己責任に追い詰める社会の有り様。そして、それをサポートしますよと手数料を掠め取る変な事業会社。
俺はそういうやつらと戦いながら何とか生き延びるしかやることがないんだけれども、「向こうがそのつもりなら俺だってハックしてやるぜ」の方針でやるしかないんですけど。
とりあえずはそういった現実をこの眼で見てやったぜを自分の誇りにしながら、まあなんとかやっていこうと考えています。何から卒業すればいいのかはわからないけど、何をハックすればいいのかはなんとなくわかる。そんな自分にも嫌気がさします。
詳細をここで多くは語りませんが、会社の制度とか国の制度とか、こんなに優しくなくてこんなに不親切でこんなに聞かないと説明してくれないんだとびっくりする毎日です。
俺はなんとかやってやるよやってみせるよと孤軍奮闘しながら、俺はもう一度くらいは上に登ってやるよと思いつつ、こんなのみんながみんなできるわけないじゃんもっと親切にしてやってくれよと思いつつ、僕は今できることを必死にやっています。同じように必死にやってる人がたくさんいるんだな、でも、うまくできない人もたくさんいるんだろうなということを思いながら。
ダークツーリズムは上からじゃなくても下からでも参戦できる。この世の中は狂っている。困っている人を助けながら生きてきたつもりではいたが、こんなにも世の中は困ってる人に冷たい世界なのかを思い知る一つの冒険を俺は今やっている。
無力感がある。俺のこれまでの善行ぶった振る舞いと関係なく世の中はマイノリティを虐げてきたし、俺も虐げた側だったのかもしれない。それだけが辛い。誰かを助けたかった、それは叶わなかった。その報いを一手に引き受けるほどの愛も情も俺には無かった結果が今なのだろうか。無念としか言いようがない。愛すべき人間が増えただけでその人らを抱きしめる腕の数は足りないまま、とぼとぼと歩く。
以上、ズイショでしたー!本年もよろしくお願いします!
[adrotate group="46"]
【著者プロフィール】
著者名:ズイショ
関西在住アラフォー妻子持ち男性、本職はデジタルマーケター。
それだけでは物足りないのでどうにか暇な時間を捻出してはインターネットに文章を書いて遊んだりしている。
そのため仕事やコミュニケーションの効率化の話をしてると思ったら時間の無駄としか思えない与太話をしてたりもするのでお前は一体なんなんだと怒られがち。けれど、一見相反する色んな思考や感情は案外両立するものだと考えている。
ブログ:←ズイショ→ https://zuisho.hatenadiary.jp/
X:https://x.com/zuiji_zuisho
photo by Kinga Howard
こんにちは、しんざきです。ついこの間まで、2025年って12月60日くらいまで伸びないかなあと妄想していたんですが、気が付いたらもう2026年1月が半分を過ぎていますね。
何なんでしょうこの4倍速展開。イベントテキストを高速スキップする設定のソシャゲか?
この記事で書きたいことは、大体以下のようなことです。
・年末大掃除をしていて、「子どもが欲しがって/必要だと思って」買ったのに案外使われなかったものを色々整理しました
・「使われなかったもの」の共通の原因は、大きく「欲しがる動機が一過性」「片付けや出し入れに手間がかかる」「普段の生活で触れない/目にしない」あたりであった気がします
・つまり、「必要性の検討が不十分だった」「使い始めるまでの手間とハードルを甘く見積もっていた」「普段の行動の導線上になかった」ということになります
・あれ、これシステム開発の仕事でもよくやってるヤツだな?
・開発業務でも、「作ったはいいが定着しないシステム」というものがしばしばありますが、考えないといけないことは大体同じであるように思います
・つまり、「必要性の検討」「導線の検討」「運用の手間の検討」です
・必要性についてはどうしても調整が難しい部分がありますが、使うまでの手間と導線については改善できる可能性があります
・「これ、買ってもいいけど遊ぶ/使うかな……」と迷った時は、「開発案件のつもりで、導線と運用の手間を改善する」のが一つの手です
以上です。よろしくお願いします。
さて、書きたいことは最初に全部書いてしまったので、後はざっくばらんにいきましょう。
「買ったけど案外使わない」の理由
皆さん、「買ったはいいが、思ったほど使わなかったもの」って発生させてしまう方でしょうか?「これ良い!欲しい!」となって買った/買ってあげたのに案外有効活用されていないとか、しまいこまれたまま2、3回しか使われていないとか、値段に関係なく、そこそこ悲しいですよね。
お恥ずかしいことながら、しんざき家ではわりと頻繁にそれが発生してしまいます。特に「子どもが欲しがったか、あるいは必要だと言うので買ってあげたけど使わなかった」ものが割合として多いのですが、まあ大人サイドでもちょくちょく発生します。
昨年末、家の大掃除をしていて、「あー、これ買ったはいいが殆ど使わなかったなー」「あー、こっちも全然使わなかった、もったいなかったなー」というものが複数出てきました。
例えば、商品名は伏せるんですが、iPadと物理パーツを連携させることで様々な物理パズルが楽しめる知育玩具とか。
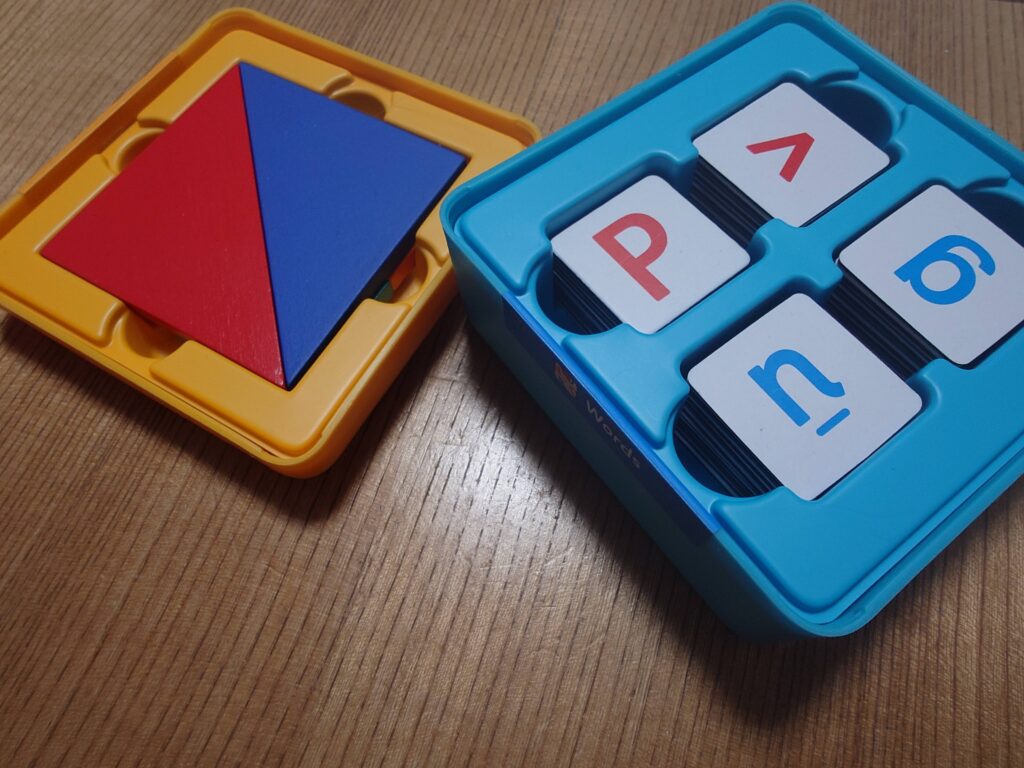
例えば、リ〇ちゃん人形を遊ばせられるサイズになっているコンビニ型のおもちゃとか。

例えば、冷蔵庫で事前に冷やしておくと、夏暑くなった時に首の周囲に巻いておくことで冷感を得られるリングとか。

例えば、コロナ禍で頻繁に朝ごはんを作る状況になったので買ってみたホットサンドメーカーだとか。

以上はあくまで一例であって、他にもまあ色々あります。プリントを整理するための整理ボックスとか、足指用のクリームだとか、PC用の新しいガジェットだとか。単に例示し切れないだけです。
で、これらの品々について改めて考えてみたところ、どうもある程度共通点がありそうに思ったんですよね。大体同じような理由、同じような経緯で、買った後あんまり使わなくなってる。
・「欲しい理由」が一過性である、ないし目的の緊急性が低い、切迫度が低い
・普段の生活で目に入る場所に置いていない、片付けられると目に留まらない
・利用できるまでにひと手間かかる、準備が面倒である
・いざ使ってみると使用感が違った、既存のものでやりくりした方が便利だった
他にも色々あると思いますが、しんざき家に関する限り、この辺が代表的な理由であるように思います。
上記で言うと、「iPadにパーツを装着しないといけない知育玩具」なんて、「利用できるまでにひと手間」の最たるものですよね。
まず「箱を取り出す」「パーツを取り出す」「パーツをiPadにつける」「iPadを起動する」だけで既に四段階手間がある。しかもその後、物理的なおもちゃ部分を取り出して、遊んで、終わった後は片付けないといけない、なんて「遊ぶ」前の段階で既に相当疲弊してしまいそうです。
「普段の生活で目に入る場所においていない」という話で言うと、冷感リングもそうかも知れません。
もちろん「いちいち冷蔵庫にしまっておかないといけない」という手間もさることながら、我が家、子どもが普段通る導線上にキッチンがないので、「見よう」「使おう」という意図がないと冷感リング自体に接触しないんですよ。
もちろんこの辺りの話は、その商品自体の問題というよりは、しんざき家での利用シーンとのギャップや、事前の見積もりが甘いというところに根本原因があります。
その点、単に我が家にフィットしていなかったというだけで、快適に利用される方もたくさんいるだろう、とは思うんです。
ただこれ、よく考えてみると何か既視感があるというか、学校の試験を受けていたら「あ、進研ゼミでやったやつだ!」みたいな感覚があったんですよ。
早い話、「開発してサービスインしたはいいが、運用が定着しなかったシステム」と似ているような気がするんです。
「定着しないシステム」の発生をどのように防いでいるか
上のパートで書いた「使わない理由」について、もう少し一般化してみると、多分下記のようになると思います。
・要件の検討・必要性の深掘りが足りていなかった
・普段の導線上に配置されていなかった
・運用に至るまでの手間や運用上の工数が想定より高いハードルになっていた
・UI/UXのフィッティングやモックテストが不十分だった
あーあったあった。何度もあった。
しんざきはシステム関連の仕事をしていて、開発にもちょくちょく携わってはいるんですが、「作ったけど使われない機能」だとか、「サービスインしたけど利用されないシステム」みたいなものも、しばしば観測してきました。
CSVでデータを食わせれば凄く綺麗なダッシュボードを作ってくれるのに結局Excelで済ませられてるBIツールとか、わざわざカスタマイズで開発されたっぽいのに職場の誰に聞いても「いや、何の機能なのか知らないです……」って答えが返ってくるメニューとか、そういうのですよね。
もちろん仕事って内容も環境も変化するものですし、その時々によって必要性や必要度合いも変わるわけですから、こういう「使われないシステム」問題、そう簡単に解決する話でもないんです。
開発側に問題がありそうなことも、利用者側に問題がありそうなことも、誰も悪くなさそうなこともあります。
とはいえ、「あともう一歩、こういう風になってればちゃんと使われそうなのになあ……」ということも時にはあって、実際それで仕事をいただいて、システムの改善でお金をもらったことも何度もあります。
とすると、それと似たようなことが家庭でもできるんじゃないのか、って話ですよね。
「使われない」理由には、ある程度定型パターンがあります。すごく単純にまとめてしまうと、「要件」「導線」「運用」の三つ。
・必要性が一過的なものかどうか、継続して必要か、緊急性があるか
・普段の生活で目にする配置になっているか
・使い始めるまでの手間、使い終わった後の手間は重くないか、重い場合軽減できないか
この三点をもう一押し検討してみる、というのは、家庭内で「使われない」ものを減らすために、もしかすると有用かも知れません。
「期待しなかったけど使われているもの」から、「使われるコツ」を考えてみる
ここでちょっと話のスコープを限定して、子どもの遊び用のおもちゃの話をすると、まず「要件の深掘り」って難易度かなり高いんですよ。
子どもの「欲しい!」なんて大体一過性なものですし、欲しい理由を整然と説明できる子なんてそうそういない。
もちろん、「欲しい」をロジカルに言語化しようろするのはいい経験になるかも知れず、実際私が長男にパソコン買ってあげた時はそれに近いことをやったんですが、まあ毎回やるのは結構厳しいし、疲弊しそう。
ただ、「導線」と「運用」については、工夫する余地がかなりありそうです。
たとえばしんざき家で言うと、「バトルライン」を始めとするボードゲーム。

バトルライン、以前次女がボドゲ会で遊んでめちゃめちゃ欲しがったんで買ったんですが、本来遊び始めるまでのセッティングとか、カード配置とか、片付けとかかなり大変で、普通なら「運用」のハードルに引っかかりそうなものなんですよね。
しんざき自身、これ買ったはいいけどあんまり遊ばれない、みたいなことにならないかなーとちょっと心配でした。
ただ、「ゲーム自体が超面白い」ということを置いても、ほぼ日常的にガチガチに遊ばれている(上記画像は、なぜか防音室にたてこもってバトルラインを遊んでいる長女と次女です)というのは確かなところで、これは
・ボードゲーム棚が階段のすぐ側にあって、日常的な導線上で目に入る位置に置いてある
・片付ける時、元々の棚ではなく、パーツ用のケースにそのまま放り込めばいいようになっている
という工夫をしてあって、ここでかなり改善されていそうなんですね。ちなみに、「ドミニオン」とか「宝石の煌めき」辺りにも似たような改善をしていて、遊び倒されています。
やっぱり、「まず普段の生活で目に入る」「準備・片付けがあんまり大変じゃない」という要素ってめちゃ大きいと思うんですよ。
一方、「期待していなかったけどめちゃ使われている」例をもう一つあげると、長女次女に買ってあげた貯金箱のおもちゃですね。

これ、硬貨を入れると自動判別して残高を計算してくれるっていうよくできた貯金箱なんですけど、「お小遣いを入れたら即この貯金箱に入れる」という形で、運用と日常生活を紐づけたところ完全に定着しまして、今でも貯金箱として使っています。
しんざき家ではお小遣い帳システムを導入しているんですが、お小遣い帳が定着したのもこの貯金箱のおかげかも知れません。
これは、「運用と普段の導線を紐づけたので定着した」例と言えると思います。
もちろん、そんなにうまくいく話ばかりではなくって、「工夫をしたけどやっぱり使われませんでした」とか、「そもそも工夫が機能しませんでした」みたいなことも色々とありはするんですが。
それでも、「使われない」という視点を軸に、日常生活と仕事を行ったり来たりしながら改善を試みるのは、それなりに頭の体操になるし、仕事の上でもなにかしらのプラス要素があるのではないかなーと。
また、こういう工夫を起点に、ちょっとでも「あ、これって面白いな、便利だな」ということを子どもたちが発見して、もしかすると自分たちでも何かしら新しい工夫をして、生活のノウハウを形作っていってくれるといいなーと。
そんな風に考える次第なのです。
今日書きたいことはそれくらいです。
[adrotate group="46"]
【著者プロフィール】
著者名:しんざき
SE、ケーナ奏者、キャベツ太郎ソムリエ。三児の父。
レトロゲームブログ「不倒城」を2004年に開設。以下、レトロゲーム、漫画、駄菓子、育児、ダライアス外伝などについて書き綴る日々を送る。好きな敵ボスはシャコ。
ブログ:不倒城
Photo:Tamara Gak
朝から朝までやりたいことだけやって生きる
以前『NHKスペシャル』でサカナクションの山口一郎さんがうつ病を抱えながら音楽活動を続けているのを見て、色々と心を揺さぶられた。
この年末にはそのドキュメンタリーに、あのすばらしい新曲『怪獣』に関する話が追加されたということで、あらためてはじめから見た。
そして、やっぱり同じところで引っかかるものがあった。
それは、うつ病と診断された山口さんが、自分の現状についての語っている言葉で、正確ではないけれどこんな感じのことだ。
ぼくにとって音楽は趣味…おおげさに言うと人生…
でも今はバンドの他のメンバーには家庭があって、生活があって…
だけど自分は今も変わらず音楽のことばかり考えている…
朝から朝まで…
本当に、ぼくには音楽しかないんですよ…
その時にぼくが感じたモヤモヤは、共感というより、嫉妬だった。
ぼくは若い頃、コピーライターを目指していて、何年もかけてようやくコピーを書く仕事にありついたのに、色んな理由で制作の仕事から離れていき、今はまったく関係のないことをやっている。
ずっとコピーを書き続けられたらそれでいいのに、と思っていた。
いや、もっと言えば、コピーでなくてもいい。
山口さんと同じように、朝から朝まで仕事のことばかり考えていられたらいいのに、と今でもふと思う。
ないものねだりだということは十分すぎるほどわかっている。
そんな徹底した生き方を貫いてきたからこそ、山口さんはうつ病と付き合わざるを得なくなったのである。
だけど、やっぱりうらやましい。
朝から朝まで、好きなことだけをやる人生…。
ぼくが見てきた「朝から朝までやりたいことをやる」人たち
ただまあ、ぼくが見てきた、本当に「好きなことだけをやる人生」を送っている人たちの生き方というのは、とてもマネできないなと思うものばかりだ。
ぼくの制作の師匠は、違うと思うことならクライアントからの要請があっても決して首を縦には振らない人だった。
ぼくは直接見たことはないが、ある制作現場でクライアントの態度を本気で叱ったこともあるらしい(色々な事情があったようだが)。
仕上げについてもなかなかウンと言わない。
周りはクライアントも含めて全員OKだと思っていても、何度も見直して、いや、ちょっと違うな…と首をかしげている。
そして、平気で何段階も戻ってやり直しはじめる。
しかしそんな彼のことをみんな信頼しているので、早く帰りたいのを我慢してまた何時間も付き合うのである。
師匠以外でも、そうだ。
ぼくがまだマーケティング部門にいた頃に、他社のクリエイティブチームと仕事をする機会があったのだが、彼らは本当に朝から朝まで企画会議を続けていた。
それでも最終企画が決まらない。
ぼくらは今か今かと待ち続けていたが、プレゼンテーション当日の朝になっても連絡が来ない。
出発時間になってもまだ現れないので、ぼくらのチームが先にプレゼンテーションの会場に出かけ、ぼくはしかたなく担当している部分について話しはじめる。
営業の先輩が隣で、あと5分引き延ばせ、とか、やっぱりあと10分、とかそっとメモを見せてくる。
この現状で、入社2年目のぼくが、たいした厚みもない企画書を10分も引き延ばすだって?もう半分以上読み上げてしまったというのに?と激しく動揺しながらも、ぼくは、ええと…このデータにご注目ください、興味深いのはこの点でして…などと道をそれた話をしはじめる。
クリエイティブチームはまだ来ない。
ダメだ、もうどれだけ頑張っても残りは1ページしかない。
「…以上を持ちまして…マーケティング戦略に関するお話を…終え…ます…」
ぼくがそう言い終えて、すべてをあきらめて顔を上げたら、クライアントの責任者と目が合った。
「…どうしましょうね」
その人は困ったような、しかしちょっと楽しんでいるような表情でそう言った。
後ろには十数名のクライアント社員が座っていて、みんなじっと黙っている。
営業の先輩が、すみません…あと少しで到着すると連絡が来てはいるのですが…と答えると、責任者は笑って、じゃあ、もうちょっとだけ待ちましょうか、と言った。
そこから待つこと数分、ようやくクリエイティブディレクターが姿を現して、謝りながらプレゼンテーションをはじめた。
それはとても良いプレゼンだったけど、さすがにこれじゃあ勝てないだろうなと思った。
そもそも有利な条件を持つ競合相手がいて、勝てる見込みの薄い案件だった。
おまけに大遅刻してではさすがにダメだろう…とみんなが思っていたら、なんとこの仕事はぼくらのチームに決定した。
まあ色々な事情はあったようだが、当日ギリギリまで企画を修正していて大遅刻の末のプレゼンテーションで仕事を獲得したことにちがいはない。
朝から朝まで企画をし続けた結果ではある。
ぼくは「朝から朝まで悩み続けている」人になってしまった
昔話になってしまった。
今はそんな大仰なプレゼンテーションの場なんてほとんどなくなったし、そもそも朝から朝まで業務をしてはいけなくなって久しい。
それでも、やろうと思えば一日中、その仕事についてずっと考え続けることはできたはずだ。
しかし、ぼくは仕事と子育ての両立に苦戦しているうちに、そして色々な部門を転々としているうちに、そんなことはすっかり忘れてしまって、その代わりに「オレはこんなことをするためだけに生きているんだっけ」というモヤモヤとした時間ばかりをすごすようになってしまった。
なので、山口さんが朝から朝まで音楽について考えている、と言っているのを聞いて、うらやましいな、と思ってしまったのだ。
コピーのことについてずっと考え続けている人生、企画についてずっと悩み続けている人生、あるいは他の何かひとつのことについて集中して、生活しているあいだじゅうずっとそれがそばにある人生。
さて、ぼくはこのモヤモヤについて、30代後半の頃、一度結論づけたことがある。
要は、何かについて朝から朝まで考え続ける人生はもちろん素敵だが、妻がいて、子どもがいて、会社の仕事があって、こんなどうでもいいことについてモヤモヤと悩んでいられる人生というのも十分に幸せな人生なのだということである。
ある人から、そう言われたのである。
そして、そんなモヤモヤしている時間があったら、少しでも納得できる人生のために、手を動かして、夢中になれることを自分でつくっていったらいいじゃないか、と結論づけたわけである。
それから10年近く経った。
10年のあいだに、夢中になれることをつくることができたか?と言われると、半分はイエスで半分はノーだ。
イエスだと言えるのは、こうやってモヤモヤと考えること自体に対して、会社の仕事として堂々と向き合えるようになったこと。
同じようにモヤモヤを抱えながら働く人のキャリア支援や、地域で暮らす人々の幸福度向上支援といった取り組みをはじめたから。
ノーだと思うのは、とはいえ会社員なので会社の都合であっちこっちに振り回されている時間が多かったなということ。
あるいは家庭と仕事の両立について苦労し続けてきたなということ。
そして、今でもモヤモヤする時間自体はそこまで減っていないと感じるから。
…書いていて気づいたけど、結局、これまでのぼくの人生を振り返ってみて、ぼくは一体どういう人間になったのかといえば、コピーライターでもなく、コンサルタントでもなく、事業開発者でもなく、いわば「ずっとモヤモヤし続けている人」になったのだと思う。
なんなら、最近は終わりのない「問い続ける」修行をはじめたため、余計にそうなってしまっている気がする。
そして、他の誰でもない、ぼくがその道を選んでいるのである。
そういえば最近、ある人と話していて、ぼくが自分の話をしていたら「あんまり悩み続けるのはよくないですよ。ほんと、やめたほうがいい」と心配されたので、ぼくは笑ってこう答えたのである。
「大丈夫です、悩み続けるのは、ぼくの趣味なんですよ。ぼくね、プロの悩みストなんです」
そう言ったら、その人は大笑いして、あ、プロならしかたないですよね、プロなんですね、と納得してくれた。
ぼくも自分でそう言ってから、そうか、オレは悩むことのプロなのかもしれない、と気づいたのである。
「悩みスト」の3か条
さて、「悩むプロ」、あるいは「悩みスト」とはどんな職業なのか。
まずは自分の人生自体についてずっと悩み続けていなければいけない。
本当にこんな生き方をしていていいのだろうか、他にもっとマシな選択肢があるのではないだろうか、あるいはわき目もふらずにこの道をまっすぐ行くべきなのではないだろうか。
そんな感じでモヤモヤと悩み続けていることが重要である。
何かスッキリとするような結論が出た場合は怪しんだほうがよろしい。
そんなことでは一生悩み続けることができない。
プロたる者、簡単にスッキリしてはいけないのである。
次に、他人に対して悩みをオープンにすることが肝要である。
ぼくは、よくある「なんだかエラそうな人や立場が上の人に、下々が相談する場」というのがとっても苦手である。
ただでも自分のほうが立場が弱いのに、そのうえ何かを相談しないといけない。
もう、何か偉そうなことを言われて、けちょんけちょんにされて、しょんぼりして帰っていく姿しか想像できない。
自分の弱みは何も見せずに、さあ悩みを話してごらんなさいと言われて、はいそうですかと本当の悩みを差し出すほどぼくらは優しい世界には暮らしていない。
お互いに、いやあもうねえ、いやんなっちゃいますよねえ…と悩みを見せあいっこしてはじめて相談というのは始まるのである。
「悩みスト」たるもの、自分からどんどん悩みを見てもらって、面白がってもらわなければいけない。
もちろん、バカにされることなど恐れてはいけない。
そして三つめ。
ここが最も重要なポイントである。
「悩みスト」はあくまでプロ、職業的な存在なのである。
それを忘れてはいけない。
本来のぼくは非常にいいかげんで、だらしなくて、自分が関心のないことについては驚くほど鈍感である(だからこそ、ちゃんとできなくて悩むのであるが)。
何もかもが不安で眠れない、ということも最近はほとんどない。
それは、ぼくが普段から「悩みスト」として、周りに自分の悩みについてばかり話したり、書いたりしているからだと思う。
色んな人たちに対して、自分の悩みをオープンにして、たくさん聞いてもらっているので、その時点でわりとスッキリしているのである。
ぼくにとって「悩むこと」は、本当にやりたいことではない。
もっとダラダラと毎日をすごし、楽しいことだけやって、面倒なことから逃げまわって、自堕落な日々を送りたいのである。
だけどそれでは食べていけないし、周りも許してくれない。
なのでしかたなく、ちゃんとした人間を演じようとしている。
そう、いつも人生に悩み、本当にこれでいいのかと逡巡し続けている人間として…。
…だって、仕事ってそんなもんじゃないですか、実際。
そんなわけで、ぼくはこれからも全力で、人生に、仕事に、家庭に、趣味に、そして世の中のなんだかよくわからないできごとたちに対して、ああでもないこうでもないと悩み続けていこうと思うのである。
[adrotate group="46"]
【著者プロフィール】
著者:いぬじん
プロフィールを書こうとして手が止まった。
元コピーライター、関西在住、サラリーマンをしながら、法人の運営や経営者の顧問をしたり…などと書こうと思ったのだが、そういうことにとらわれずに自由に生きるというのが、今ぼくが一番大事にしたいことなのかもしれない。
だけど「自由人」とか書くと、かなり違うような気もして。
プロフィールって、むずかしい。
ブログ:犬だって言いたいことがあるのだ。
Photo by:Matthew Osborn
リクルートではカルチャーとして、何かを上司に相談すると「あなたはどうしたいの?」と聞かれるという。
リクルートにいたとき、上司に何を聞いても「お前はどうしたいの?」しか言われなくてなんだよコイツって思ってたけど、あるとき「どうしたらいいですか?」ではなく「こうしていいもですか?」と許可を求める行動をしろと言われた。自分の意志がない仕事は楽しくないだろと。すごく真っ当だよねこれ。
— moto (@moto_recruit) November 17, 2025
私が所属しているコンサルティング会社でも、同様のカルチャーがあり、
「で、安達さんはどうするの?」
「安達さんはどう思う?」
と、上司に何度も言われた記憶がある。
実際、自分の意見を持ってない状態で、上司に答えだけ求めるようなコンサルタントは
「使えないやつ」認定されて、キャリア的にも厳しい。
まあ、そうだろう。
「上司が出した案をそのままやるだけ」
の社員を、客先に行かせたり、出世させるわけには行かないだろうから。
「どうしたいの?」はパワハラ
ただ、この「どうしたいの?」という聞き方。
人によっては、強いプレッシャーを感じるらしい。パワハラだという人もいる。
だから、こんなふうに揶揄される。
リクルートの有名な「お前はどうしたい?」みたいなのも、別に主体性を求めて裁量を与えるようなものではなく、何かあった際に末端に責任を押し付ける社内政治話法に過ぎない
— ふどあ (@fd_a_e) October 20, 2025
気が強いリクルート上司みたいな奥さんとか将来のワイで草
『あなたはどうなりたいの?』
『あなたはどうしたいの?』
『5年後の目標は?』
って彼氏に詰めていつも嫌がられてるワ
人間だったら目標ぐらい持つでしょ?なんで目標なしで生きてるの?なんで?
っていつも詰めてる自分もパワハラで草草草 https://t.co/zSrFsN3XVZ— ぱんだ@転職×投資OL🐼🤍 (@panda_kkkq) February 26, 2025
冒頭のツイートをしたmotoさんも、
上司「キミには、自分の意志はないの?ただ言われたことだけやって、いざとなったらどうしたらいいですか?って、それ仕事していて楽しい?自分の意志がない仕事なんて、やってて楽しくないでしょ?」
と詰められた話を書いている。
このギャップがなぜ生じるのか、といえば、非常にシンプルで、
「裁量を持つこと」に対する態度が、人によってかなり異なるからだ。
仕事において
「できるだけ責任を持ちたくない ≒ できるだけ裁量を小さくしたい」
と考える人と、
「大きな責任を引き受けたい ≒ 裁量を持ちたい」
と考える人が両方いる。
そして、できるだけ責任を持たず、できるだけ裁量を小さくし、あるいは、できれば仕事をしたくない、と考える人にとって、
「あなたはどうしたいの」という質問は苦痛以外の何物でもない。
「早く答えを教えろよ……仕事したくないんだからさ」
という人に、「どうしたいの」などと聞いても、「(知らねーよ)」で終了だ。
だから、こういう質問は、
「仕事にやる気と向上心があって、年収1000万円以上の給料をもらっている人」
に対してするべきであって、
「特に仕事が好きでもない、早く家に帰りたい、年収が400万円の人」
の人に要求するべきものではない。
彼らは、「どうしたい」を決めるべき給料をもらっているわけでもなく、また、それを決めたいわけでもない。
だから、そうした期待をされても困る、と思っている。
そういう人たちに、「リクルート」の話を聞きかじって、「どうしたいの」と言っても、白い目で見られるだけである。
「聞くべき人を間違えた」
ということだ。
そもそも、多くの人は「仕事でやりたいこと」なんてない
そもそも、多くの人は「仕事でやりたいこと」なんてない。
ちょっとカッコよく見えて、楽に高い給料が貰えれば、仕事内容なんて、(よほどのことでない限り)なんでもいいのだ。
例えば、日本財団の調査では、18歳の若者が「企業選びで重視すること」のトップは、
1.給与や待遇が優れている 52.6%
2.福利厚生が充実している 35.7%
3.希望する業界である 33.2%
4.ワークライフバランスが充実している 31.0%
となっている。
自己実現とか、やりたい仕事とか思っている人は、多少はいるだろうが、基本的には少数派だ。
逆にそういうことを「本気で」考えている時点で、「意識の高い」「仕事に前向きな人」と判断して良いかもしれない。
もちろん、企業はそういう人を求めているのだろうが、この採用難の時代に、大した給料も払っていない人に、そういうことを求めるのは厳しい。
いい人材は、金がかかるし、安く使える人たちに、「考えてうごく」ことを過剰に期待するほうが間違っている。(やってくれる人もいるけどそれは例外)
多くの人は仕事を「何をやらないとマズいか」だけで判断している。
こういう状況であるから、多くの人は
「どうしたいの?」
と聞かれても、答えは唯一つ。
「そんなことはどうでもいいから、何をやらないとマズイのかを早く教えろ」
と思うだけだ。
そういう場合は、望み通りにしてあげるとよい。
文字通り、「何をやると給料がもらえて、何をやらないと罰されるのか」を伝えるのだ。
この際、「自主的に」とか「自ら考えて」とか、そういうのは忘れる。
彼らが仕事に対して、最優先に考えているのは、「何をすれば、給与が滞りなくもらえるか」だけなのだから。
逆に言えば、「何をやりたいのか」を「(かっこつけではなく)本気で」きちんと伝えてくるような部下は、鍛えれば幹部になれる素養がある。
貴重な人材だ。
あるいは、「やりたいことなど ない」と言っていた人も、時がたつと変わることもある。
そういう時にはじめて、「どうしたいの」と聞けばよいのだ。
*
なお、「学歴」と「やりたいことがある」ことは、あまり関係がない。
前者は認知能力に関する話であり、後者は非認知能力に属する話である。
賢い人であっても、仕事でパッとしないことが数多くあるのは、そのためだ。
マネジメントやコミュニケーションは常に、「相手が中心」になる。
相手に成果を求めるのであれば、「彼らの考えていること」から、始めねばならない。
[adrotate group="46"]
【著者プロフィール】
安達裕哉
生成AI活用支援のワークワンダースCEO(https://workwonders.jp)|元Deloitteのコンサルタント|オウンドメディア支援のティネクト代表(http://tinect.jp)|著書「頭のいい人が話す前に考えていること」88万部(https://amzn.to/49Tivyi)|
◯Twitter:安達裕哉
◯Facebook:安達裕哉
◯note:(生成AI時代の「ライターとマーケティング」の、実践的教科書)
〇まぐまぐ:実務で使える、生成AI導入の教科書
[amazonjs asin="4478116695" locale="JP" tmpl="Small" title="頭のいい人が話す前に考えていること"]
Photo:Nejc Soklič
※著者は一時的ストーマ(人工肛門)造成者です。
※ストーマの種類はイレオストミーです。
※病気、治療やケアなどに関する知識などは、あなたの医者を頼ってください。
※これは一当事者の直近の感想にすぎません。
※必然的に排泄物などの話になります。読みたくない人は、今は読まなくていいと思います。ただ、いつか自分がオストメイトになったとき、なにかの役に立つかもしれないので、ブックマークでもしといたらいいかもしれない。
装具の交換訓練は多いほうがいい
おれはNET G1という希少がんの手術で一時的ストーマ(人工肛門)造成者となった。そのあたりについては、承前、ということでお願いしたい。
さて、前回はどこまで書いたか。なんとまだ入院中だ。そうだ、おれの入院は長引いた。長引いたおかげでいいことが一つだけあった。看護師さんのアドバイスを受けられる状態でストーマ装具交換を何度か多くできたのだ。
もしも、術後の経過が順調で退院となっていたら、おれはストーマ装具交換に大きな不安を持ったまま世の中に放り出されることになった。
いや、世の中のオストメイト(ストーマ造成者)は、あのくらいの回数の訓練で世に出ているのか? ちょっと信じられない。それが率直な感想だ。
まあいい、おだて上手な看護師さんたちにほめられて、「まあ一人で交換できるかな?」となっておれは退院した。
交換については前回書いたが、なかなか簡単に覚えられるものじゃない。手順を覚えられても手技がついてくるかどうかはまたべつの話だろう。もっと高齢になってからだったりしたら、どれだけたいへんなことだろうか。
だからといって、「若いうちになっておこう」というものでもない。ならないように、早め早めに大腸内視鏡検査受けておきましょう。
部屋とストーマとパウチの中身
ともかくおれは退院して、帰宅した。一人暮らしのアパートに帰ってきた。腹にストーマがついているのは変わらない。パウチをぶら下げているのも変わらない。パウチの中に溜まっていくものも変わらない。しかし、変わるものがある。周囲の景色だ。
病院でのストーマ装具、パウチは、はじめなにか手術直後に身体に繋がれていた管の一つのような印象だった。
尿の管、ドレーン、背中の麻酔、順番は忘れたがどんどんほかの取れていって、最後に残ったやつ、という感じだった。
そして、残ったそれのなかにはなにやら黒い液体が溜まっていった。最初は看護師さんがベッドに来て紙コップに処理していった。便ではなく排液とかいうものだった。
それが、便になった。便が透明のプラスチック一枚隔てた向こうにある。よく見える。それは、どうだったのか。病院のベッドの上、レンタルのパジャマ、そういった特殊な状況のなかでそれは、なにやらそういうものだな、としか思えなかった。
便を見ては、袋越しに揉んでみたりして、かためだの、やわらかめだの判断したりした。溜まってきたら、そろそろトイレで排出するかな、といった具合だ。おれはすっかり袋越しの便に慣れてしまった。パウチの先端もパジャマのズボンの中にしまうことなく、外に出していた。
が、これが自分の部屋に帰ってきたらどうだろう。いつも座っている座椅子、そこから見える服と本でぐちゃぐちゃになった部屋、でかいテレビ、ノートパソコン。その手前に、便の見える袋。
……これ、あんがい、ぜんぜん、なんも気にならなかったわ、おれ。
病院のベッドで慣れ親しみすぎたのか、自分の部屋の中でもズボンの中にしまうことなくぶら下げているわ。もちろん、これは人によって感じるところは大違いだと思う。ただ、おれは平気だった。べつに一人暮らしだ、悪いことではない。なんなら、ものを食べているときも出しっぱなしだ。
ただ、届け物などがあったときなど、忘れずにしまうよう心がけなければいけない。そこは注意だ。置き配万歳。
自宅での装具交換と必要なもの
つけたままで暮らせることはわかった。だが、交換はどうだろう。交換は避けられない。病院では処置室と呼ばれる部屋や、たまたま四人部屋で一人になったときは、病室で交換を行った。用具を置くスペースもちゃんとあった。余裕をもって交換できるようになっていた。
ところが、このアパートはどうだろう。とりあえず退院してユニットバスのトイレに行ってびっくりした。十年放置されていたような廃墟のように汚い。病院は病院で「いろいろ汚いですよ」と看護師さんは言っていたが、アパートは目に見えて汚かった。そして狭かった。
とはいえ、おれはこのユニットバスのなかで装具を交換するしかない。というか、したくない。ユニットバスというのはあれだ、水ですぐに手を洗えるし、なんならトイレもついている。排泄物をどうにかする場所にふさわしい。
というか、部屋で排泄物をどうにかするのは嫌だ。どうにかするしかない。
それで、どうしたのか。段ボールのなかに必要な道具や装具を入れて、トイレの上においた。そしておれは、湯船のふちにタオルを引いて座る。そういうことにした。
シャワーを浴びたあとなので素っ裸だ。だが、素っ裸なら汚れても流せばよい。冬は少し寒いがそれでいく。
このあとは少々細かい話になるが、だれかのためになるかもしれないので細かく書く。
まず、「アルケア 防臭ごみ袋 オストメイト向け ストーマ装具が臭わない袋」を用意する。
[amazonjs asin="B0B5RMNSKN" locale="JP" tmpl="Small" title="アルケア 防臭ごみ袋 オストメイト向け ストーマ装具が臭わない袋 90枚入 幅200×長さ300mm 21461"]
べつに防臭ごみ袋ならこれでなくてもいいだろうが、ストーマ装具用といわれたら初心者はとりあえず使うことになる。
リムーバーで装具を外し、折りたたんでこの袋のそこに入れる。ここで、まだ袋は結ばない。それでもそんなににおいはしないと思う。
次に、ストーマとその周辺を洗う。洗って、キッチンペーパーを四つ切にしたやつで拭く。おれはキッチンペーパーを切るのが面倒なので無印のカットコットンを使ったりもする。そして、使い終わったそれらを、ゴミ袋に入れるのだ。サイズ的にそのくらいの余裕はある。
そして、ストーマのサイズを測り、パウチの面板を切り、皮膚保護シールを切り、それらをいちいちきちんと段ボールのなかに戻し、パウダーをふり、保護シールを貼り、装具を貼る。これら、狭いユニットバスのなかでも十分できる。とはいえ、「風呂・トイレ別」だったらどうかわからない。いや、「風呂」でやればいいのか。
さて、これで交換は終わった。が、後始末をしなければいけない。まず、ストーマ用のゴミ袋の口をしばる。あ、装具とかのはがしたやつとかゴミは全部このなかに入れちゃえばいいと思います。で、その袋をさらに大きな「臭わないゴミ袋」に入れる。
[amazonjs asin="B0C5HKQCJ1" locale="JP" tmpl="Small" title="防臭袋 L/90枚 45×32cm 生ゴミが臭わない袋 おむつが臭わない袋 ペットのうんちが臭わない袋 赤ちゃん用 大人用おむつ うんち 生ゴミ処理袋 ゴミ袋 箱型入り ホワイト…"]
おれは事情あっていろいろとAmazonで揃えたが、臭わないゴミ袋であればコンビニで黒いのを売っていたりする。それでもいいだろう。
袋に袋を入れて、ゴミの日までにまだ交換があるならば、軽く口を閉じる。そして、便座の横においておく。
そして段ボールを外に出して、手を洗って、急いで暖房の下に行く(冬は)。手の温度で十五分接着部分を温めるよう指導されたからだ。おれは手が非常に冷たいので、ホッカイロを用意しておいてもいい。
そして十五分……いや、長ければ長いほうが安心できる。しっかりくっついてくれるような気がする。というわけで、温めながらYouTubeでNOBROCK TVの一本でも見ればいいんじゃないでしょうか。交換はこれでいい。
自宅での排出と必要なもの
交換より先に排出の話をするべきだったろうか。まあいい、もちろんパウチにぶつが溜まれば排出しなくてはいけない。
これについても、まだまだ若輩者ながら、ネットで得た知識などをもとに編み出した自分なりのやり方を書いておきたい。むろん、イレオストミー向きの話になる。
まず、トイレットペーパーを適当に二枚ちぎって、ゆるいこよりを作る。ホルダーの上に置く。そして、さらに一枚ちぎって、その上にのせる。
つぎに、アルケア拭き取りシート デイリーデオワイプを用意する。これもストーマ用商品でたいへんすぐれているのではないかと思うが、たぶん高いので赤ちゃんのおしりふきシートとかでもいいかもしれない。
[amazonjs asin="B0D7VPBK2F" locale="JP" tmpl="Small" title="アルケア 拭き取りシート デイリーデオワイプ 80枚入り×3個 21591"]
これは一枚のままだと使いにくいので(あくまでイレオストミーのキャップ式の場合)、三つくらいにちぎる。これで準備はできた。
便器のなかにトイレットペーパーを一枚敷く。跳ねないような気がするからだ。そして、一度キャップを上に向けて開き、中腰になって、できるだけ低い位置から排出する。
排出が終わるのをしつこく待って、ようやく最初のトイレットペーパーでだいたいの拭き取りをする。そして、こより状にしていたやつをキャップのなかに入れて回して拭き取る。これを二回やる。
これで十分、といえるかもしれない。しかし、やはりにおいがどうなるのか気になる。そこでウェットな拭き取りシートでとどめの拭き取りをする。最後の一切れはキャップを閉めたあとを拭く。……これで完璧なんじゃないかな。
で、終わったあとは消臭だ。おれは病院でふつうの便とは違う方向性のにおいにずいぶん驚いて、嫌な感じを抱いたものだったが、トイレにおいてあった消臭剤の威力にはさらに驚いた。
[amazonjs asin="B01N3OQS9J" locale="JP" tmpl="Small" title="パナソニック Panasonic 【NF-M001】ニオフ プロユース消臭剤 トイレ用品"]
パナソニックの二オフ、これである。これもまた商品説明でストーマについて触れているわけだが、べつにほかのにおいにも効くだろう。なにかにおいで困っている人は試してみるといいかもしれない。ただし、高い。
ちなみに、ストーマからの排出の特殊なにおいは、その後なんというかふつうの便のにおいになってしまった。なってしまった、というのは、おれはこれをすでに買ってしまっているからだ。
でも、ひょっとしたら自分の鼻が慣れただけかもしれないので、使ったほうがいいかもしれない。というか、おれは一人暮らしだからいいが、家族のいる人は使ったほうがいいだろう。なにせ、ストーマからの排出はそもそも水洗トイレの水に入ってくれないのだ。
ストーマ装具のあれとこれ
本当はストーマ装具(パウチ、というと正確ではないのかもしれない)のあれこれを述べたかったが、おれが今までに装着したことのある装具は二種類だけなので、あれとこれ、だ。
最初に装着した、というか、手術中に装着してもらったのは、イレファインDキャップというものだったと思う。たぶん。
全面透明のイレオストミー用装具。透明のものとそうでないものがある、という予備知識はあったが、とりあえず全面透明のものを使った。二回か三回交換した。「透明と不透明ではQOLが違うという話もあるが、これしかつけたことのない状態ではわからんな」と思った。
病院がすすめるのだから、これを使うことになるのだろうか。まあ、今のところ一時造設の予定だからこれでもいいか? これの不透明バージョンはないのか? ないのか、などと調べたりもした。
そうしていたら、出入りの業者がべつのサンプルを持ってきたという。それが「やわらか凸シャローイレオ」というへんな名前のものだった。
これは全面透明でなく上部が不織布で覆われている。「お、透明じゃない」と思った。どうも不透明のやつは全体が不透明みたいだが、これは下の方が透明だ。

でも、やっぱり不透明なのはいいな。そう思った。そんなに全部丸見えな必要はないじゃないか。そう思った。下の方は見えるけれど、状態や量を見られるのは悪くないんじゃないのか。そう思った。
そして、それが「やわらか」なのかわからないが、お腹への締付けのようなものがやさしかった。もちろん、しっかりとお腹へはりついて漏らさないのが最重要なのだが、病棟をリハビリ歩行するときに、イレファインとじゃずいぶん違うんだよな。あっちはきつすぎた。
というわけで、おれは看護師さんにはっきりと「こっちのほうがいいです」と言った。
入院が長くなりそうだったので、病院内から二箱目を注文した。もう、これでいいんじゃないのか。世の中にはほんとうにたくさんのストーマ装具があるけれど、おれは今のところ一時ということだし、外を歩き回ることもないし、真夏までには終わっているはずだし……。
そんなところだ。ただ、どうもこの「やわらか」は値段が高いような気がする。まあ、我慢する。
とりあえずは、こんなところです
とりあえずは、まあこんなところです。ストーマ造成する人、した人、するかもしれない人(その可能性はほとんどだれにだってあるといえる)に、あるいは家族がそうなる人に、なにか役に立てばいい。まあ、自分の経験や印象を書き残しておきたかったというのもあるから役に立たなくてもいい。
しかしまあ、長々と書いてきたけれど、ストーマ、嫌なものです。装具によって寝返りも打てないし、うつぶせで眠ることもできない。そんなことよりも、内臓が外に出ていることによる恐怖と緊張がどうにもストレスになる。
正直言ってしんどい。これは工夫やアイテムでどうにもならない根源的なこわさだ。そして、その外に出た内臓がなにか音を出したりしてうごめいているのを感じるのはとても不快だ。
そしていまおれはものが食べられなくて困っている。腸閉塞の原因になる食べ物を避けた結果、お粥とうどんとたまごと豆腐とサラダチキンくらいしか食べられないというのもある。しかし、それよりもストーマが働く、動くのがこわい。
これを書いている今、おれはまだきちんと社会復帰していない。入院、手術後の体力回復が通勤するところまでいっていないからだ。なので、在宅で仕事と静養とリハビリをしている。
「日常編」というのであれば、以前と同じように会社に通うところまでいってから書くべきだろうが、今の「感じ」を書き残しておきたかった。
通勤などするようになったら、またなにか緊急時のために持ち歩くものとか、会社に置いておくものとか、そういう話も出てくるかと思う。自転車に乗るとか、それなりに歩くとか、外のトイレで排出するとかも。
でも、今のところはこれで。なにせおれは、一日だけ数時間会社に顔を出したが、そのときでさえ十分に飯を抜いて行った。
まだおれには覚悟ができていない。なんていうのかな、これはなかなかにつらいものだ。ほんとうに。それだけは最後に言っておく。
[adrotate group="46"]
【著者プロフィール】
黄金頭
横浜市中区在住、そして勤務の低賃金DTP労働者。『関内関外日記』というブログをいくらか長く書いている。
趣味は競馬、好きな球団はカープ。名前の由来はすばらしいサラブレッドから。
双極性障害II型。
ブログ:関内関外日記
Twitter:黄金頭
Photo by :Mylène Larnaud
自作の「100日行」をしていました
ふと修行をしたいと思い立ち、「100日行」なる計画を勝手に作って、勝手にはじめた。
以前から修行はしたいと思っていたのだけど、家庭も仕事もあって、それらを投げうって山奥にこもったりする勇気は全くなかった。
ところが、ちょっとしたきっかけもあり、ひょっとして修行は別に山奥にこもらなくてもできるのではと思いつき、勝手に修行の計画を作って取り組み始めたのである。
行の内容はシンプルで、毎日、事前に立てた問いに対して答え続けるだけ。
自分は何を手に入れたいのか。
どうなりたいのか。
そのために何が必要なのか。
…などなどの問いを100日分作って、毎日1つずつ答えていく。
ただそれらを自問自答し続けるだけなのだが、やっていくと、実はこれがすごくきついことがわかってきた。
普段はフタをして見ないようにしている自分の内面を、無理にでももう一度ちゃんと見ないといけなくなってくる。
おまけに、そうやって無防備な状態になっていても、日常生活は普通に続いている。
日常は危険に満ちている。
誰かに痛いところを注意されたり、自分で勝手にミスをしたり、あるいは誰かに対して自分がきつく言いすぎてしまったり、判断を迫られている時にちゃんと決められなかったり…。
どれだけ慎重に生活していたって、うまくいかないことはかならず起こる。
そんな中に無防備な状態で放り込まれるので、ちょっとしたことに対してもとても傷つきやすく、すぐに落ちこんだり腹が立ったりするようになる。
かなり危ない。
後になってから、そういった危険性についてはちゃんと事前に考慮して、注意しておくべきだったと思った。
ただまあ、やってみないとわからなかった、ともいえる。
そのあたりはこの記事の最後にまとめておこうと思う。
さて、100日行をはじめてから85日目までのできごとは、以下の記事に書いた。
ChatGPTを使って、100日間ひたすら修行に専念してみる。今85日目。
以前から、修行をしたい、とは思っていた。
100日間、ひたすら修行に専念したら、何かが変わるんじゃないだろうかと思う。ということは、ぼくは何かを変えたかったのだ。
それじゃ、100日経ったあと、何が起きたのか?
結論から言うと、特に何かが大きく変わったわけではない。
たしかに100日のあいだに、ぼくの内面では大きな動きがあり、とんでもなくしんどい日々が続いたり、そこから浮上して、これまで経験したことのないような晴れやかな気持ちになったりすることも体験した。
だからといって、ぼくの内面が大きく変わったという印象はない。
なんなら、これまでよりも簡単に腹を立てたり落ちこんだりしやすくなった気がする。
なんとなくのイメージとして、修行をしたら心が穏やかになって、何事にも動じなくなり、どんな困難に直面しても軽やかに乗り越えていける人間に生まれ変わることができるんじゃなかろうかと思っていたのだが、残念ながらそんな気配はまったくない。
それじゃあ、この自作の100日行は失敗だったのか?
自作だけに?
それについては現段階では、完全にイエスと言い切るのはちょっと早い気もしている。
たしかにぼくの中で何かが大きく変わったわけではないのだが、まったく何も変わっていないかと言えば、そうでもない。
もっと言うと、100日行を通して自分が「変わる」ことが本当に目的だったのか?とも思う。
いや、もちろん当初はそれが目的だったのだけれども、取り組んでいるうちに、どうもその目的自体が変わっていっているような気もするのである。
このあたりは、もう少し具体的な内容を振り返りながら考えてみようと思う。
はじめの100日間で起きたこと
はじめの100日間では、この行の内容を考えること自体がとても楽しかった。
十牛図という悟りを開くプロセスを十段階で説明しているものを参考にして、問いのテーマを10に分け、それぞれのテーマを10日間かけて答えていく、というものにした。
ぼくは本当は何をやりたいのか?どこへ向かうのか?それはなぜなのか?そして、それを実現するために何をする必要があるのか…?
そういった問いを考えることも楽しかったし、この問いに答え続けていくことで自分はどのように変化していくのだろう?ということを想像するのも楽しかった。
十牛図の八段階目は「人牛倶忘」といって、行の中で目指している目的を忘れてしまうだけでなく、自分自身のことも忘れてしまう段階だという。
いわゆる無我の境地なんだろうけれども、果たしてそんな境地に至ることができるのだろうか?とか、至ることができたらどんな気持ちなんだろうか?とか色々妄想しているのも楽しかった。
さて、そんな風に作りこんだ100の問いに対して向き合い続けてきた100日間。
たしかに修行というか試練と思えるようなことはいくつも起きた。
あまりにも何度も「自分がやりたいことは何か」ということを問いつめすぎて、そもそもやりたいことなんてないし、自分にはたいした野望も使命感もないし、だいたいそんな状態で生きていること自体が申し訳ない、周りはもっと一生懸命に生きているのに自分は本当にダメ人間だ、どうしようもない、というくらいに勝手に追いつめられてしまったりした。
まったく心の変容が起きないのに、次の段階に問いを進めるのが辛すぎて、かなり初期の問いに戻らざるをえないこともあった(それ自体ははじめから想定はしていたけど)。
ただまあ、どれだけ辛いことがあろうが、悲しいことがあろうが、日は進む。
これは100日行のとてもいいところだと思う。
何がどうなろうが、ちゃんと一日経てば、修行は一日分進むのである。
そして、無事に100日を迎えられたとき、どんなことが起きたか?
その時のぼくのメモがある。
・自然体、ありのまま。力を抜き、直感を信じる。思いこみを捨てる
・空っぽ、心の自由。開き直れば何でもできる
・愛の循環、惜しまずに与える、きっとそのうち還ってくる。10年後、20年後、あるいは100年後…
・この世界の答えを知っているのはぼくだけ。この世界の秘密を知っているのはぼくだけ
・他者に引っ張られず、自分の道を進んでいく
いま読み返してみると、ずいぶん他人に引っ張られることに苦しんでいたんだなあと思う。
これについては、100日行をはじめる前からずっと悩んできたことのように思う。
14年前にブログを書きはじめた時から。
あるいはもっと前から、他者の評価が人生の中心にあった。
広告会社のクリエイティブ局に配属されないとコピーライターの仕事はできないと思いこんでいたし、コピーを書きはじめてからも広告賞を獲らなければ良いクリエイターとして認められないと思っていたし、そもそもクリエイターとして「有名」になりたいと思っていた。
「有名」ということは、他者から知られること。
他者による認知状況に、自分自身の評価をあずけるということだ。
それじゃ、100日経って、ぼくは他者の評価から自由になれたのか?というと、そんなことは全くない。
ただ、それとどう関係があるのかわからないけれども、メモにもあるように「自然体」ということを意識するようになった気がする。
自然体とは何か。
なぜ自然ではなく自然「体」なのか。
まだよくわからない。
ただ、なぜか合気道だけは、もう長年やってきているのに、なぜかここにきてうまくなった。
力を抜いて、気楽な状態でやるだけでこんなに変わるのか、というくらいに変わった。
だけど、他は何も変わっていない。
仕事の中でうまく「自然体」を発揮することができたかというと、そんなこともない。
その程度の変化だ。
ただ100日間、自分に対して問い続けるという行は達成できたということで、晴れやかな気持ちにはなれた。
と同時に、このままやめてしまうのはもったいないなと思ったし、そこは無理してではなく、わりと自然な感じで、新たな100日間の問いを作りはじめたのだった。
101日目~200日目で起きたこと
101日目から200日目までの大きなテーマは「自分で答えをつくる」というものだった。
100日間で、ぼくはかなり他者の評価に引っ張られて生きてきて、それについて本気でなんとかしたいと思っていることがわかった。
だったら他者ではなく自分の軸を作ろう、自分の人生の答えを自分自身で作っていこう、と思ったのだ。
そこでぼくはどんどん新しい行動を起こしていった。
その結果、ほとんどが空回りで、何ひとつ仕事にもならなかったし、新しい成果も生み出さなかった。
チームメンバーともコミュニケーションがうまくいかなくてイライラしていた。
家庭でもいつもイライラしていて、すぐにカッとなったり、ネガティブな感情をうまく抑えられなくなってきた。
おまけに200日行の後半には家庭で問題が起きたり、合気道の師範が突然亡くなったりして、感情がめちゃくちゃになっていた。
当時の記録を読み返すと、それでもまだ仕事では何か新しい行動を起こし続けていて驚く。
たぶん、しんどいことから目をそらして、逃げていたのだろうけど、それにしてもあっちこっちに出かけたり、新しい人たちと出会ったり、なんとか状況を変えようと動いていた。
200日目のメモにはこんなことが書いてある。
・弱さ、葛藤、あるいはそれと格闘する自分を、自分の強みとして取りこむ
・弱さ、欲望との葛藤があるからこそ、アイデアを作れる。人々を惹きつけるサービスが作れる
・解脱しない
・超越しない
・逃げない
・悟らない
・達観しない
・苦や煩悩に留まって、苦くてしかし楽しい人生を味わい続けていく
201日目~300日目で起きたこと
ここからなぜすんなり300日行へと移れたのかはよくわからない。
ただ、自分の置かれた状況があまり良くなかったので、蜘蛛の糸でもなんでもいいので何かすがるものが必要だったのかもしれない。
「とにかく何かを続けている」「他のすべてはうまくいってなくても、これだけは続けることに成功している」という感覚が、よりどころになるのだろう。
なので、新しいテーマを考える余裕もなく、201日目から300日目も「自分で答えをつくる」は変わらず、ただ「さらなる実践」という言葉を付け加えた。
さて、この100日間はどうだったかというと、とにかく体調が悪い日が多かった。
熱を出して寝こんだ。
熱が引いても咳が止まらなくて、ずっと咳こんでいたら、今度は持病の腰痛が再発して、ちょうどそのタイミングで出張先でのワークショップをしなければいけなかったのだが、ずっと痛みをこらえながらやっていたのでほとんど記憶がない…。
腰痛がマシになったあとも、全身がだるかったり、眠気がおさまらなかったりして、やる気が出ない日が続いた。
仕事に関しては久しぶりに大きくてやりがいのあるプロジェクトを立ち上げることができ、それはとてもうれしかった。
また、それは「自分で答えをつくる」ということの実践に他ならないと思うし、ここまで試行錯誤してきた結果がようやく表に出てきた、ということなんだろう。
一方で、別の、わりと長く育ててきたプロジェクトについては完全にゼロからのやり直しとなってしまった。
その日がちょうど、300日目だった。
その日のメモ。
・なんと300日行の最後にまさかの最悪の日になる
・しかしまあ、これは次へのある意味、一番良いスタートだ
・どん底からのスタート
(今読み直すと、それはちょっと言い過ぎじゃないの?と思うけど、まあ当時はそんな気持ちだったのだろう)
301日目~400日目で起きたこと
さて、ここからが最新の100日間のできごとだ。
この100日間のテーマについては、こんな風なものだ。
〇テーマ:出し惜しまず、力を尽くす。透明になれる時間を増やしていく。
・ぼくが一番幸せと感じるのは、目の前のことにひたすら集中し夢中になっているとき
・その時間を少しでも多く作っていく
・これまで「自分が答えをつくる」と言ってきて、これは意識としては定着してきたと思う
・次はその答えを作るプロセス自体を、ぼくの人生の「答え」としていく
・いくら服を買ったり見た目を気にしたり評判を気にしたりしていても、そこには「答え」はない
・ただ目の前に集中して力を十二分に発揮できているとき、ぼくは満たされているし、自分のことをかっこいいと思えるし、これでいいと思える
今これを読み直すと、だいぶ気恥ずかしいというか、そこまで「自分が答えをつくる」意識が定着しているとは思えないし、まだ周りの評判を気にしているあたりが未練がましい。
それでも、だいぶ精度が上がってきているのではないかな、と思う。
というのも、ぼくが取り組むテーマは以下のように変化しているからだ。
・1日目~100日目:そもそも何を目指したいのか、それ自体を探す期間
・101日目~200日目:自分の軸を他者からの評価ではなく、自分自身へと戻しはじめる期間
・201日目~300日目:自分の軸をつくろうとして悪戦苦闘する期間
・301日目~:自分の軸をつくるということは「全力を尽くす(透明になる)」ことだという気づきを得つつある期間
特に、直近の100日間(301日目~400日目)は、「やりたいことの断捨離」に取り組んだ。
仕事では、取り組む領域をしぼりこんで、他の部分は自分以外のメンバーに託すことにした。
ぼくは全体を見つつも、基本的には自分のプロジェクトに集中できる体制に変えていった。
また、できるだけ集中力が失われない工夫をはじめた。
スマホからの通知を制限したり、特になくても困らないアプリを削除したりして、気がそれる要素を減らしていった。
アイデアを考える時間や企画書にまとめる時間を30分とか50分とか決めて、その時間内に完璧でなくてもいいのでとにかくやりきってしまう練習をはじめた。
そして400日たった今、何か変わったか?
狙いどおり「全力を尽くす」時間を増やすことができたのか?
…正直言って、よくわからない。
せっかく取り組む領域をしぼって集中しようとしても、他のメンバーからの相談に乗っているうちに日中に仕事ができる時間が終わってしまって、しかたなく夜中にこっそり企画をして睡眠不足になってしまう。
あるいはスマホの通知を制限しても、ついつい自分から見にいってしまう。
削除したはずのアプリはいつのまにか復活している(もちろんぼくがやったのだ)。
せっかく制限時間を決めて企画をつくっていても、ちょっと調べものをしようとブラウザを開いたりAIに質問したりするつもりだったのに、気がつくと全然違うことを考えはじめていたりする。
まあ、試行錯誤である。
ただ、400日経って思うこととして、あ、これは終わらないかもしれないな、ずっと続くことなのかもしれないな、という感覚がある。
冒頭にも書いたけれども、100日行としてこの「問い続ける」行をはじめたときは、100日経ったら何か大きな変化が自分の中に起きて、そこで修行は完了するのだと思っていた。
ところが実際は、まあたしかに色々な心の揺れや試練は経験したものの、そこまで大きな変化が起きたわけでもないし、「ああ、これで修行は終わったぞ」という感覚もあまりなかった。
だから、101日目が勝手にはじまったし、正直言って今も、ここまで続けてきてやめるのはもったいないな、という気持ちで続けているだけかもしれない。
だけど、それでいいじゃないか、とも思うのだ。
この行の素敵なところは、その日の問いにうまく答えることができなくても、一日はちゃんと終わるというところだ。
うまくいかないのなら、うまくいかなかったという記録を残して、また次の日の問いに取り組めばいい。
次の日がダメならまた次の日、それもダメならまた翌日。
行はずっと続く。
ぼくがあきらめない限り。
それって、人生と同じじゃない?
さて、ぼくが400日目にして思うことは、たったそれだけだ。
この行に特に意味がなくてもいいじゃないか、ただ無意味にでも続けていって、どこまで続くか見てみたいじゃないか。
そんな風に思っている。
もしこれからも行を続けていくのなら、取り組むテーマもどんどん変わっていくだろう。
今は人生の中の軸を自分のほうへと取り戻すことに苦心しているけれども、今後は反対に他者へと再びまなざしを向けていくこともあるかもしれない。
あるいはそれを行ったり来たりするのかもしれない。
そのあたりは全然わからない。
わからないけど、人生は続く。
あるいは続くことをうれしいと感じる。
いま感じているのは、そんなところだ。
行に取り組む際に注意したほうがいいと思うこと
最後に、この100日行あるいは「問い」の行に取り組むときに気をつけたほうがいいと思うことを並べておく。
前回の記事を読んでくれた方々の中で何名かの方が、ぼく宛に「自分も100日行に興味がある」「やってみようと思う」という連絡をくださっている。
そのたびに注意点をお伝えしているので、あらためてここに書いておこうと思う。
・少しでもしんどいな、辛いな、と思ったら、無理に問いに答えようとせず、その日はやめておく。
翌日もしんどいと感じたら、やっぱりやめておく。で、「今日は考えなかった」とか「しんどいのでやめておいた」とちゃんと記録しておけば、それだけで十分な行になると思っている。
ぼくは何度も、何も答えられない日を経験しているし、あまりにも今の自分の状況と問いが合っていないと感じたら、ためらいなく問いの内容を変更している。むしろ、その作業が特に中盤あたりでは大事になってくる気がしている。
この行はとにかく行ったり来たりだ。昨日まではものすごい変容を感じていた気がするのに、いきなり大ショックなできごとが起きたりする。あるいはまったくやる気の出ない低空飛行が何日も何日も続くことも普通だ。それらを素直に記録するだけでいい。あとで見返したときに、「うわーそれはしんどいよなあ…」とか「あーこのときの経験がここに活きてきたのかなあ…うーんどうかなー…」とかいう感想を楽しむことができる。
まあ、だからといって何かに役立つかどうかはわからない。何度も言うが、修行をしたからといって何かが変わるわけではないのだ。それを期待して取り組むのはやめたほうがいいと思う(ぼくがそうだったから)。
・自分が100日行に取り組んでいることを周りにちゃんと伝えておく。
これはとても大事。前回の記事を書いていた頃は、主にChatGPTを対話の相手としながら取り組んでいたのだが、ChatGPTはこちらに寄り添いすぎる。それだと自分がどんな状況にいるのか客観的に見えなくなってしまう。
ぼくは数名の信頼できる友人に対して「実は100日行なる修行を勝手にはじめまして、しばらく連絡が途絶えるかもしれません」と事前に伝えていた。
また職場でもわりとオープンに「今、勝手に100日行なる修行をしていまして、言動がおかしくなることがあるかもしれません。その際はご容赦を」と言っていた。そう言われてポカンとしている人もいれば、また何か変なことをはじめたなとニヤニヤしている人もいた。
でも言っておいてよかったと思う。
なぜなら、ぼくが中盤ですごく辛くなってきていて、でも自分でそれに気づけていないときに「いぬじんさん、その修行、大丈夫なんですか?最近かなり不安定ですよ」と言ってくれる人もいたし、「修行も大事だけど、そろそろ娑婆に戻ってこない?悟りを開いちゃったら、やりたいことができなくなっちゃうよ。いぬじんさんみたいな人には欲望や煩悩も必要だと思うよ」とアドバイスしてくれる人もいた。
そのおかげで、ぼくは娑婆に戻ってくることができたのだと思う。
・本当に辛いときは、ためらわずに信頼できる人や病院に相談する。
前回の記事に書いたとおり、中盤あたりは辛い時間が続いていたので、66日目に、とても尊敬しているコーチングの師匠に時間をいただいて、今の状況を聞いてもらった。
ぼくが「今、修行をしていまして」と切り出すと、彼は「ああ、いいですね、修行。ぼくもしていますよ」と言って、自分はどんなことをやっているかを教えてくれた(それは、誰でもできること簡単なことなんだけど、なかなか続けづらそうなことだった)。
それからぼくたちは人間関係と時間についての話をした。100日っていうと長く感じるけど、木からするとそれほどの時間じゃないんだよね、と彼は言う。
木は10年、20年、30年。そして100年、1000年。そんな風にして育っていく。人と人の関係性もやっぱり10年、20年って感じでゆっくり育っていくんじゃないかなあ。
そんな話をしているうちに、ぼくの中のこわばっていた部分がじわじわとやわらかくなっていった。焦って修行の成果を出そうとするのをやめよう、と思えるようになった。あの時、彼に会わなければ、かなりキツかったのではないかなと思う。
また、100日間が過ぎてから、臨床心理士の知人にこの話をしたところ、それは本当に危ないところでしたね、いぬじんさんはおそらくそのとき鬱になっていたと思います、普通は自力では回復しづらい状態にあったんだと思いますよ。今後そういうことがあった場合は、すぐに病院に連絡したほうがいいですよ、と助言をもらった。
…ちょっとした注意書きをするつもりが長くなってしまった。
だけど本当に、もし興味があって100日行をやってみようと思う方がいたら、細心の注意を払ってもらいたい。
行なんていつでもやめられるし、いつでも再開できる。
たいしたことじゃない。
人生は続く。
オブラディ・オブラダ、という感じで。
[adrotate group="46"]
【著者プロフィール】
著者:いぬじん
プロフィールを書こうとして手が止まった。
元コピーライター、関西在住、サラリーマンをしながら、法人の運営や経営者の顧問をしたり…などと書こうと思ったのだが、そういうことにとらわれずに自由に生きるというのが、今ぼくが一番大事にしたいことなのかもしれない。
だけど「自由人」とか書くと、かなり違うような気もして。
プロフィールって、むずかしい。
ブログ:犬だって言いたいことがあるのだ。
Photo by:Md Mahdi
年末年始は、Xで見かけた「陰キャでも陽キャでもない無趣味な人に用意された、ドーパミン供給装置としての推し活」というセンテンスを反芻していた。
「推し活」って趣味というより高度にパッケージングされた消費行動でしかなくて、才能を持った他人の人生に相乗りして成功体験をインスタントに得ているだけ。
本質は疑似恋愛とかじゃなくて疑似成功体験なんだよな。
陰キャでも陽キャでもない無趣味な人に用意されたドーパミン供給装置としての推し活— なぎ (@nagijanaiyo) December 4, 2025
1800万回以上表示されたというから、なかなかのバズだ。書き方も巧妙で、投稿者は「無趣味な人にドーパミンを供給する装置としての推し活(があり得る)」というエクスキューズ含みの書き方を選んでいる。
つまり、「推し活をやっている人々=無趣味」とは言い切っていないのだが、そういう風に解釈し、感情的なリアクションをとる人が集まりやすいつくりにもなっている。
ドーパミン、ひいては報酬系は人間を社会適応へと駆り立てていく御者のよう
本来、ドーパミンは役割の多い神経伝達物質で、パーキンソン病や幻覚、血圧や利尿などにも関連している。
それらを全て紹介したらきりがないが、この文章で重要なのは、「報酬系」という人間の行動制御やモチベーション制御を司っている制御系のなかでドーパミンが大きな役割を担っている点だ。
昔からよく知られているのは、ドーパミンが出る→気持ちが良い→もっとやりたくなるといったプラスの動機付けだろう。
人間が快感をおぼえたり感動したりする状況、たとえば長時間かけて大きな達成を成し遂げた瞬間や、旅行中に絶景に出会い目を奪われた瞬間や、あり得ないほどの美食に出くわした瞬間に際しては、きっと私たちの脳内でドーパミンが分泌されている。
社会的承認が得られた時にもドーパミンは分泌されるので、大きな達成に他者からの称賛が伴えばドーパミンはますます出るだろうし、さぞ気持ち良いだろう。それが、これからのモチベーションやさらなる努力に繋がっていくことは言うまでもない。
これは、人間の社会適応にかなり役立つ仕組みだと言える。価値の高い体験をするとドーパミンが出る・達成感を感じるとドーパミンが出る・社会的承認を感じるとドーパミンが出る……ということは、そうした行動を人間がリピートしたがるよう、報酬系はドーパミンという「ニンジン」を使って人間の行動をコントロールしているわけだ。
嫌悪感にもドーパミンが一枚噛んでいるらしいことまで含めて考えると、報酬系は、まるで「ニンジン」と「鞭」をつかいこなして人間を社会適応へと駆り立てていく御者のようだ。少なくともうまくいっている時、ドーパミンひいては報酬系はそうして人間のモチベーションをうまく司り、人間の社会適応に大きく貢献する。
でも、良くない動機づけが起こってしまうこともある
ところがドーパミンはそうでない場面でも案外出てしまう。その最たるものはギャンブルにおけるドーパミンの分泌だ。射幸心をあおる賭博場で大当たりを当ててしまった時、私たちの脳内ではドーパミンが分泌され、それは気持ち良く体感される。
ソーシャルゲームのガチャだってそうだろう。最近のパチンコやソーシャルゲームガチャには煌びやかな演出が伴い、それもドーパミンを分泌させやすい状況に一役買っている。
すると、人間はもっとギャンブルしたくなったりもっとガチャを回したくなったりしてしまう。なぜなら、当たるか当たらないかわからない体験と当たった時のきらびやかな演出によって、ドーパミンが分泌されやすい状況ができあがってしまうからだ。
状況が嵩じればギャンブル依存やガチャ依存ができあがるかもしれない。この場合、報酬系とドーパミンは人間の社会適応に貢献するというより、むしろ社会適応にとってマイナスの方向に人間を動機づけてしまう。
また、一部の薬剤、特にドーパミンの分泌に関連する向精神作用のある薬剤は、この報酬系に強い影響を与え、その薬剤が我慢できないようにしてしまう。
報酬系とドーパミンは、気持ち良さを通じてモチベーションを強化するだけでなく、神経細胞間のシナプスの繋がりが変わることでモチベーションが一層強化されてしまうことがある。
薬物依存において、信じられないほど薬物が我慢できない身体になってしまう人を見かけることがあるが、おそらく神経細胞間のシナプスの繋がりもすっかり変わってしまって、そういう脳になってしまっているのだろう。
精神科臨床でみかける依存症、薬物嗜癖や行動嗜癖のたぐいを眺めていると、単なるドーパミン欲しさ、単なる快楽追求とはまったく次元の異なる依存や嗜癖に出会うことがしばしばある。
さきほど書いたように、報酬系は人間を社会適応に駆り立てていく御者のような存在、あるいは司令塔的存在だから、これが特定の薬物等に執着するよう書きかわってしまったら、それはもう大変なことになる。
社会適応にプラスに働く活動でドーパミンが出る時、報酬系は人間をますます社会適応に駆り立てていくが、社会適応にマイナスに働く活動でドーパミンが出る状態をおぼえてしまった報酬系は、人間をむしろ社会適応から遠ざけてしまう。
こう考えると、「気持ちが良いこと」「モチベーションを強化してくれること」とは案外怖いものだ、と思わずにいられなくなる。ドーパミンさえ出ればなんでもいいと考えるのは危ない。
推し活はドーパミンの宛先としてどこまで安全か
これらを踏まえたうえで、冒頭のXの投稿を思い出していただきたい。
推し活をとおして非日常の華やかさを体験する時や、推しが自分には叶えられない夢を切り拓いていく時、神経伝達物質としてのドーパミンがいつもより分泌され、いつもよりも心地良さを体験している可能性は高かろう。
そのとき報酬系が仕事をしていて、神経細胞間のシナプスが「もっと推し活をしたい方向に」変わっていっている可能性もまた高い。
その際、私たちはいつもより活き活きとして、いつもより生き甲斐を感じていたりもして、いつもより元気づけられたような気持ちになる。
推し活がモチベーションとなって何かを頑張れたり、推しの好ましい性質を見習ったりすることで技能習得にまでプラスの影響をもたらすことだってできるかもしれない。
報酬系を刺激することを前提として推し活をうまく活用することは、自分自身の御者である報酬系をうまく活用することにも通じるだろう。そのように推し活を活用できる人、社会適応に組み込める人が推し活から獲得できる恩恵は小さくない。
しかし前述のように、ドーパミンや報酬系が関わるとはリスクが伴うことでもある。推し活に限らず、報酬系が関わることにはベネフィットとリスクの両面がある。
リスクの最たるものとして挙げられるのは、依存症や嗜癖だろう。繰り返すが、これは推し活に限った話ではない。ドーパミンや報酬系が関わる薬剤はもちろん、ギャンブルでも、ダイエットでも、スポーツでも、ゲームでも、仕事でさえ、それは起こり得る。
活き活きできること、生き甲斐を感じられることが他には絶無で、それが唯一の生き甲斐や逃避先のようになっている時には、通常は依存症や嗜癖に陥らないような活動でさえ、依存症や嗜癖のような顔つきに変わることがある。
もともとは生きるためのよすがだったはずの活動がやめられなくなり、自分の意志では制御できなくなり、楽しいというより苦しくなってきたら怪しい兆候だ。
ドーパミンの出るような体験を追求した結果たどり着いたのが、やめられない・止まらない・苦しいといった境地だったら最悪である。しかし報酬系の調子がこじれると、えてして人間は、そういう風になってしまう。
たいていの活動はたいていの人には安全。でも完全に安全とは言えない
もちろん、世の中には依存症や嗜癖になりやすいもの・なりにくいものがある。なりやすいものの筆頭格は危険な薬剤だ。次いで、ギャンブルあたりが挙げやすいだろうか。
ゲーム症、ネット依存といった言葉が示すように、コンピュータゲームやインターネットでも依存症や嗜癖に相当する事態は起こり得る。では推し活はどうだろうか。
推し活をやっている人の母数は、コンピュータゲームやインターネットに比べれば少ないが、それでも決して小さいわけではない。しかし、推し活依存や推し活嗜癖といった言葉が登場していないことをみるに、推し活が嵩じて依存症や嗜癖の定義にがっちりと当てはまってしまう人はそこまで多くないと思う。
依存症や嗜癖の専門治療機関になら、そういう人も来ているのかもしれないが、市井の精神科外来においてはゲーム症やゲーム障害と比較しても遭遇頻度は低い、と私はみている。
そのことを踏まえるなら、推し活はまだしも安全な部類なのかもしれない。
しかし、推し活をする人が増え続け、推し活に費やされるリソースも増え続けていくなかで、推し活の歯止めがかからなくなる人、推し活がコントロールできなくなってしまう人もいるだろう。
そして他の依存症や嗜癖がしばしば自覚不能に陥ってしまうのと同じように、推し活がコントロール不能になった際に自覚不能になっている可能性もあるように思われる。
ソーシャルゲームのガチャで大枚を使ってしまった人が足を洗った後に「あのときはコントロールできなくなっていた」と振り返るのと同じように、推し活から足を洗った後に「あのときはコントロールできなくなっていた」と振り返る、そんな推し活だってあるのかもしれない。
だから、ほとんどの推し活は安全だが、世の中に存在する他の活動と同じぐらいにはコントロール不能になったり、楽しいというより苦しくなったりする可能性はあると思ったほうがいい。
というより、人間に報酬系という仕組みが実装されていて、ドーパミンをはじめとする神経伝達物質によって私たちが衝き動かされている限り、どんな活動にだってコントロール不能になるリスクはあるのだ。
キラキラしたもの、モチベートするもの、社会的承認が伴うもの、等々が伴うなら尚更である。私たちはそういうものにモチベートされる。なぜなら報酬系がそういう体験を求めさせるようにドーパミンなどを分泌させ、シナプスの繋がりが変わったりもするからだ。
このこと自体、ひとつの機会たりえるし、ひとつの落とし穴たりえる。それは、人間が進化の過程で獲得してきた仕組みだからしようがない。ならば、そうした脳内の仕組みを知ったうえで、せいぜい、うまく行動を制御してもらうよう気を付けるしかない。
この文章を書き始めていた時、私は「推し活は安全なドーパミン供給装置か?」などと考えていたが、やめることにした。およそドーパミンが分泌されるような活動で、絶対に依存症や嗜癖に至らない活動なんてないと思ってかかったほうが危なげがないからだ。仕事や社会奉仕活動ですらそうだろう。
心地良いこと、快感なこと、エキサイティングでアメージングなことがいけないとは思わないし、それらを「ニンジン」として追いかけているうちに道が拓けてくる場面なんていくらでもある。けれどもドーパミンや報酬系は万能の仕組みではない。依存症や嗜癖をはじめ、いろいろと都合の悪いところもある仕組みだ。
たとえば、リピートするうちにより強い刺激・より強い快感を求めたくなる性質には私は不安をおぼえる。人間を御する御者の役割を担っている脳内の仕組みに、そういう一面がある点にはいつも注意が必要で、それは推し活だろうがゲームだろうが仕事だろうが同じではないだろうか。
私が思うに、ドーパミンだけでは人は幸福になれないと思う。人間は快感や感動だけでは生きていけない。だから月並みな話だが、「過ぎたるは猶及ばざるが如し」は金言だ。
この金言を忘れず、節度ある付き合いを続ける限り、ドーパミンも報酬系もあてにしていいように思う。
しかしこの言葉を忘れ、ドーパミンの出そうな体験に頼り切ったライフスタイルに陥った時、自分自身の御者としての報酬系はあてにならなくなり、主人を裏切るかもしれない。
[adrotate group="46"]
【プロフィール】
著者:熊代亨
精神科専門医。「診察室の内側の風景」とインターネットやオフ会で出会う「診察室の外側の風景」の整合性にこだわりながら、現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信中。
通称“シロクマ先生”。近著は『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(花伝社)『「若作りうつ」社会』(講談社)『認められたい』(ヴィレッジブックス)『「若者」をやめて、「大人」を始める 「成熟困難時代」をどう生きるか?』『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて』(イースト・プレス)など。
[amazonjs asin="B0CVNBNWJK" locale="JP" tmpl="Small" title="人間はどこまで家畜か 現代人の精神構造 (ハヤカワ新書)"]
twitter:@twit_shirokuma
ブログ:『シロクマの屑籠』

Photo:Carl Raw
1年の最終日。今年を振り返りながら書いてみたい。
2024年末から2025年にかけて、「言語化」がブームだったようだ。
Amazonで検索してみると「言語化」関連の書籍がわんさか出てくる。
私もこのビッグウェーブに乗り、「バイトするなら、タウンワーク」などのコピーで知られる、コピーライターの梅田さんと、日経ビジネスで随分と「言語化」について話させていただいた。
三省堂が2015年から開催するキャンペーン「今年の新語」で、2024年の大賞に輝いた「言語化」。かつて学術の世界に留まっていたこの言葉は、メディアでの露出を重ねながら私たちの日常に浸透し、静かなブームを起こしている。書店の棚を埋める関連書籍、そして「上手な伝え方」への関心の高まり……その背景には、複雑化する現代社会で胸の奥に渦巻く感情や思考を、的確に表現したいという切実な願いがある。
しかし、コミュニケーション技術を磨くことが、果たして言語化の本質なのだろうか。表面的な「伝達スキル」の向上だけに気を取られていると見落としてしまう、もっと“深い領域”があるのではないか。(日経ビジネス)
「言語化」の本質
しかし、この「言語化」という言葉、一体どのような意味で使われているのだろうか。
と思って、調べてみると実は、この言葉、「日本国語大辞典」でも「広辞苑」で調べてみても、出てこない。
辞書にない言葉、新しい言葉なのだ。
それゆえに、現時点では「言語化」という言葉は、それを使う人の解釈に利用方法が委ねられている。
だから、基本的には使い方に「間違い」というものは存在しない。
しかし、あえてここで一つだけ取り上げたい。
「言語化力」と「文章力」を同一視している人が多いようだけど、実は、全く違う能力なのだということを。
例えばこれ。
三宅さんの「言語化力」に対する批判の文章だ。
対象が多いため、問題を3つに分類します。
1.言葉選びが不適切
2.構文がおかしい
3.論理がおかしい
複合している場合もありますが、分類は形式的なものであり、重要ではありませんので、言いたいことの比重で無理やり分けました。
実はこれらの指摘はすべて、「文章力」に関するものであって、言語化力に対するものではない。
「言語化力」と、「文章力」は、全く異なった能力であり、「言語化力」を「文章力」の意味で使ってしまうと、「言語化力」の本質を見失う。
例えば、以下のようなシーンを考えてほしい。
以前から上司に相談していた、SNSを使ったマーケティングの試みを始めたいと思っている。
ただ、当社ではSNSを使うマーケティングは初めてで、前例がない。しかし、当社の商品はBtoBtoC的な性格が強いのと、社名はよく世の中に知られているということもあり、SNSでの発信は注目をされる可能性がある。
したがって、上司を説得し、SNSの利用を許可してもらいたい。ここで一つ問題がある。上司はSNSを使ったことがない人で、そのメリットをわかっていない。
かなり否定的な意見を言われそうである。
この状況で、
「SNSの有効性をわかりやすく述べた、提案文章を作れれば、上司を説得できる」
と思っている人はいるだろうか。
例えば、以下のように。
SNSをもちいた発信は、以下の3つのメリットがあります。
・今までに当社が接触できなかった層へ、認知が広がります。
・ユーザとの関係性を深め、その結果サイト誘導・問い合わせ・購入などのアクションを誘発できます。
・データを見て、ユーザの反応を素早く学び、内容や配信先の改善がしやすいです。
この文章はたしかに「わかりやすい文章」ではある。
だが、上司を簡単に説得できると、ほとんどの人は思わないだろう。
「わかりやすく」「正しい」文章であるからと言って、上司の説得ができるとは限らないからだ。
「人に刺さるかどうかは、文章力の問題ではない」。
「わかりにくいけど、刺さる」表現はあり得る。
・上司がSNSに対してもっている「勝手なイメージ」をうまく捉えて、急所をつくこと。
・上司が「いやあ、そういうことなら、ちょっとやってみようか」と思わせること。
・上司の「偏見」をうまく解消してあげること。
言語化においては、あくまで、その「コンセプト」や「道筋」を、作り出すことが「主」であって、それらを文章にすることは「従」にすぎない。
美辞麗句をならべただけでは、説得は不可能だ。
褒めるとき「すごい」「エモい」「やばい」になってしまうのは、文章力の問題ではない
結局「内容」がしっかりしていないと、
・真っ当な批判もできない
・人の説得もできない
ということであり、それは「文章力」ではなく、それ以前の「思考」の部分に問題がある。
また、誰かをうまく褒めたいときにいつも「すごい」「エモい」「やばい」になってしまうのは、思考が、アウトプットできるレベルまで整理されていないからだ。
もちろん、それが別に悪いわけではないのだが。
思うに、三宅さんはむしろ、
「働いていると本が読めなくなる」
「言語化力をつけて推しの素晴らしさを語りたい」
など、みんながなんとなく気にしていた、でも言語化できていなかったテーマを上手く捉えることは天才的であり、
「言語化能力が凄まじく高い」
という見方もできる。
抽象度の高い事象を、うまく捉える能力が「言語化力」
つまり、曖昧模糊とした、抽象度の高い事象をうまく「言葉」として捉えることのできる能力が「言語化力」である。
うまく日記をつけることができたり、良い文章を書けたりすることが言語化力ではない。
なお、こうした能力は、仕事や人生でもかなり重要とされるシーンが多い。
例えば、
・ふわっとした要求を、要件に変える
・クライアントの「価値観」を、うまくプロジェクトの目標に変換する
・会社の存在意義を捉えたキャッチコピーを作る
・自分の人生観を踏まえて、長期的な資産形成のプランを作る
・パートナーの欲求を捉えて、「結婚式」などの計画に落とし込む
ふわっとしたものを、皆が共通認識もって当たれるものに変換する作業こそ、「言語化能力」が真の意味で生かされる場所だ。
コピーライターの梅田さんは、「わかりやすくするなら具体的に、というのが一般的に言われますけど、抽象的だけど、わかりやすい」ということが、あり得るんです。
と言っている。
言語化の極みとは、そういうことを指すのだろう。
[adrotate group="46"]
【著者プロフィール】
安達裕哉
生成AI活用支援のワークワンダースCEO(https://workwonders.jp)|元Deloitteのコンサルタント|オウンドメディア支援のティネクト代表(http://tinect.jp)|著書「頭のいい人が話す前に考えていること」88万部(https://amzn.to/49Tivyi)|
◯Twitter:安達裕哉
◯Facebook:安達裕哉
◯note:(生成AI時代の「ライターとマーケティング」の、実践的教科書)
〇まぐまぐ:実務で使える、生成AI導入の教科書
[amazonjs asin="4478116695" locale="JP" tmpl="Small" title="頭のいい人が話す前に考えていること"]
Photo:Sven Brandsma
もうずいぶんと昔、西オーストラリアの州都・パースに行った時のことだ。
シドニーやケアンズに比べ知名度が低い気がするが、インド洋に面した砂浜が広がる美しい都市である。
豪州大陸の最西部で、歴史的にヨーロッパが入植を開始した拠点になった街といえば、ピンと来る人も多いだろうか。
「欧州の流刑地」としてのオーストラリア、まさにその始まりがこのパースだ。
17世紀の末、オランダ人船長が初めてこの地に上陸してから300年余り。
先住民を虐殺・支配するなど、大航海時代の象徴のような歴史が刻まれているパースに興味を持ち、シンガポール経由でバックパッカー的な安旅行をしようと思い立ったのが旅の始まりだった。
もう20年以上も前のことなので、今もそうなのか正直わからない。
当時のパースは「世界一住みやすい街」と称えられ、街中を流れるスワン川流域には誰でも無料で使えるBBQコンロが設置されているなど、ちょっと日本には無いような“高級都市”だった。
そのスワン川流域の高台では当時でも、200平米(≒60坪)ほどの家ですら日本円で1億円以下では買えないと現地の日本人から聞き驚く。
「流刑植民地」「先住民を駆逐しできた街」
そんなキーワードからおよそ想像もできないほどに、高層ビル群と高級住宅街が併存する、ちょっと不思議な街である。
とはいえ、そんな「高級都市」にももちろん、“裏通り”というものがある。
1泊4000円くらいだっただろうか、チャイナタウンにある安宿を拠点に1週間ほど滞在した。
昼・夕食などあろうはずがなく、かろうじて朝食だけ、宿代の範囲内で喰わせてもらえる。
とはいえ、パンとスクランブルエッグだけの“ビュッフェ”を、会議室のような机とイスで食べるスタイルだ。
滞在中メニューが変わることなどなく、エサを与えるようなスタイルが逆に清々しい。
街の中心であるパース駅までは、徒歩で25分ほど歩いた。
空気を感じたかったので夜な夜な、駅近くのパブにも繰り出す。
「Chinese?」
「No, Japanese」
キャッシュオンデリバリーのBARカウンターでビールを注文すると、必ずそんなことを聞かれる。
白人男性が、蔑むような笑いを浮かべる。
(KoreanかChineseと答えたら、どんな顔をするのだろうか…)
そんなことを思いながらふと、1年ほど前のことを思い出していた。
「選択肢などありません、やらせて下さい!」
久しぶりのバックパッカー的な海外旅行に行きたくなったのは、大きな仕事に一段落をつけることができたからだった。
今だから言えるが、私の20代など、ろくな人生ではなかった。
新卒で入った大和証券を数年で逃げ出し、1990年代末から始まった“ITバブル”で一攫千金を夢見て、IT企業に転職する。
CFOとしてVC(ベンチャーキャピタル)などから6億円ほどの出資をお預かりしたが、3年ほどで全て溶かした。
会社が立ち行かなくなると、出資をして下さっていたVCの担当者さんに泣きついてまわる。
「恥を忍んでお願いします。私が役に立てそうな再就職先を紹介してもらえないでしょうか」
当然のことながら、誰も相手にしてくれない。
そんな中で唯一、あるメガバンクの投資部長だけが大阪・本町のベローチェで話を聞いてくれた。
「率直に言うけど、ウチを含めてあれだけの投資を溶かしたんやで。桃野くんの信用も地に堕ちてるに決まってるやん。再就職先の紹介なんか無理や」
冷酷ではあるが当たり前の言葉に、コーヒーがただただ苦い。手元を見詰めながら、無意味に手指を持て余す。
投資部長は、親子ほども年齢の離れた人だ。
若い頃にはNY支店にも配属されるなど、同期のエース級だった経歴を持つ。
上海支店長も務めたそうだが、しかし何かの事故で左遷され本線を外れたと聞いたことがあるものの、詳しくは知らない。
「だけどな、俺も人生でいろいろあったねん」
そういうと、苦労が刻まれた彫りの深い笑顔を崩し、何かを思い出したように一気に話し始める。
「一回の失敗で終わるような日本の文化、俺は好きじゃない」
「…」
「ウチの大口投資先で、法的整理寸前の会社がある。目先は資本注入で乗り切ったんで、債務超過は解消されてるんや。でも、キャッシュフローは大幅なマイナスや。この意味わかるよな?」
「はい、時間の問題ということですね」
「そうや。そこでも良ければいくか?ただ桃野くん、バツが2回つくとさすがにもう、CFOとして再起不能やで」
「やります、選択肢などありません。やらせて下さい!」
“しているフリの仕事”
そんな経緯で、若干29歳にして従業員800名を超える会社の役員に就いた。
しかしながら、歴史ある会社でもあり、8名いる役員は全て親子ほども年の離れたオジサンばかりである。
加えて私は「大口出資元から送り込まれたスパイ」という構図でもあり、まともな意思疎通すら困難だった。
しかしCFOとして2回会社を潰せば、もう人生に後はない。
遠慮なんかしている場合ではなく、初日から全力で仕事に取り組む。
最初に明らかになった大きな問題は、誰も定量的に経営を把握していないという、ちょっと信じられない状況だった。
製造部長は、製品の原価構造を全く把握していない。
営業部長は、工場の損益分岐点になる稼働率が何%であるのかも把握していない。考えたことすら無い。
生産総数は大きく変わらないのに、月ごとに労務費が10%以上変動する理由も、誰も説明できなかった。
そんな状態では、「なんとなく頑張っている感」を出すことが社員の仕事になり、「なんとなく指導している感」を出すことが上司の仕事になる。
それでも「明日会社が潰れるわけではない」ので、皆がそれぞれの“居心地の良い”仕事に逃げ込み、余計なことなどしなくなる。
数カ月後には確実に、その居心地の良い場所がぶっ壊れるにもかかわらずだ。
そんな会社に、全ての数字を可視化し、定量的に仕事の工程管理を求めるようなCFOが闖入した時の雰囲気が想像できるだろうか。
「既存顧客のケアに精一杯で、新規開拓に回せるリソースがないんや!」
「熱源を電気からガスに変えたりしたら、シフトを一から組み直さんとあかんやん!」
形ばかりの無意味な日報を廃止し、現場のムダな作業を減らそうとした時でさえ、事業部長はこう反対する。
「この日報は昔からこの形でやってて、皆が慣れてるんや!余計なことせんといて欲しいなあ!」
“しているフリの仕事”を引き剥がされることに対する、壮絶な抵抗である。
言い換えれば、“居心地の良い毎日”を壊そうとする私への、憎しみを伴った攻撃だ。
その目には「若造に何ができるねん」という根拠のない侮蔑と、力ずくで排除しようとする強い意志が溢れる。
「この会社はあと半年で潰れることを、理解しているのですか?何もせず、半年後に全社員を路頭に迷わせるのですね?」
「…そんなこと言ってへんやん」
「ではやって下さい。やらないならまずあなたが辞めて下さい」
そんな強い言葉で、半ば強引に仕事のやり方を上書きした。
多くの仕事で定量的な成果に基づく工程管理を導入し、成果の出ない“しているフリの仕事”を一つ一つ潰した。
結果、なんとかタイミリミットギリギリまでにキャッシュフローがプラマイ0にまで回復し、目先の危機を脱する。
そして落ち着いた頃合いを見計らってまとまった休みを取り、少しバックパッカー的な旅行に出かけることにした。
「夢じゃねえからな」
想像以上に心身とも疲れている自覚があったので、旅行に出た。
それが冒頭の、西オーストラリア州・パースへの旅だった。
「Chinese?」
「No, Japanese」
パブの白人店員さんが、ビールを注ぎながら蔑むような笑いを返す。その時に思い出していた1年前の出来事とは何だったのか。
(あぁ、必死に俺を排除しようとした、あの時の部長たちと同じ目をしてる…)
皮肉にも、心身の疲れを癒そうと出かけた海外で、“同じ目”に出会う。
考えてみれば、豪州はつい近年まで白豪主義を取り入れ、有色人種を徹底的に排除してきた「差別の本場」だ。
「かつて自分たちがしたことを、今度は自分たちがされるのではないか」
先住民を駆逐・征服し作り上げた国に、多くのアジア人が流入したことで、“居心地の良い毎日”を奪われるという、漠然とした危機感を持っているのかもしれない。
複雑な思いで酒が美味くなくなり、ホテルに戻ると早々に寝ることにした。
すると深夜、真っ暗な部屋の隅っこにボーっとした人影のようなものが現れ、枕元まで来るといきなりこう叫ぶ。
「俺は日本人が嫌いなんだよ!二度とこの国に来るな!」
「うわああああ!!」
飛び起きるように目が覚め、電気を付けると、ただの夢だった…。
時間はまだ、深夜2時30分。しかしリアルな夢だった…めっちゃ怖かった…。
少し落ち着きを取り戻し、冷蔵庫に入れていたビールを飲んで一服すると、冷静さを取り戻す。
(なんか怖いんで、電気をつけたまま寝ようかな…)
そんなことをボーっと考えていた次の瞬間、耳元に気配を感じると小さな声が直接、脳内に響く。
「夢じゃねえからな」
「うわああああああああああああああああああああああ!!!」
次の瞬間、ベッドから落ちて目がさめた。気が付けば、朝になっていた。
なんちゅう手の込んだ夢なんだよ…。いやもしかして、コレも夢じゃないだろうな?
人生史上、一番怖い夢の一つというお話だ。
パースという街の持つ歴史と空気が、そんな夢を見させたのか。あるいは思っていた以上に、会社の立て直しで心身が疲れていたのか。もしくはその両方なのか。
土地だけでなく、会社や組織にも根付く「居心地の良い毎日を守りたい」という人の想いは、時に怨念化するのかもしれないと思った出来事だった。
[adrotate group="46"]
【プロフィール】
桃野泰徳
大学卒業後、大和證券に勤務。
中堅メーカーなどでCFOを歴任し独立。
主な著書
『なぜこんな人が上司なのか』(新潮新書)
『自衛隊の最高幹部はどのように選ばれるのか』(週刊東洋経済)
など
あの時、部屋には本当に何らかのオバケがいたと思ってる…。
でも、脳内には日本語で話しかけてきたので、案外日本人のオバケなのかも…。
X(旧Twitter) :@ momod1997
facebook :桃野泰徳
Photo:Hongbin
どうもこんにちは、しんざきです。
ここ最近は、大きめな組織の調整役みたいなことをやってまして、よく知らん分野での喧嘩を「まあまあ皆さん落ち着きましょう、知らんけど」的に調整する仕事で主に生計を立てています。そろそろDB設計やりたいです。
この記事で書きたいことは、以下のようなことです。
・「対立軸を明確にする」、つまり「敵対関係」を作ってしまうことを避けがちな人は多いように思います
・ひとことで「対立」といっても色々あって、ざっくり言うと「人間関係的な対立」と「仕事の内容や方法についての意見の相違」があります
・上手に対立軸を作ると、「論点が明確になる」「ゴールラインが明確になる」「意思決定のスピードが早まる」「曖昧な要件が減る」などのメリットがあります
・そのためには以下のようなことが大事かなあと思っています
-「誰と誰がどう対立しているのか」を早めに整理して、その対立軸を周囲に明示する
-話をその対立軸に限定して、関係性の問題に発展することから隔離する
-妥協点、どこまではどう譲れるかを早めに明確にする
-意思決定の方法、ないしラインを早めに明確にする
・対立は単なる道具なので、平和に過ごしつつ、上手に対立を利用できるといいですよね
以上です。よろしくお願いします。
さて、書きたいことは最初に全部書いてしまったので、後はざっくばらんにいきましょう。
皆さん、会議で喧嘩しますか?よく分からんテーマで個人攻撃まで発展してこじれる会議、面倒ですよね。
先日は、要件調整会議として始まった筈の会議で、何故か偉い人たちが若手時代の喫煙室の使い方についての言い争いを始めて、何でここまでこじれるんだろう?と首を傾げておりました。巻き込まれない分には観てて面白いんですけど。
ただ、ある程度大きな組織になってくると、喧嘩もあまり発生しなくなるというか、そもそも「対立の発生」自体を避ける傾向が出てくるような気がしています。
しんざきはシステム開発の仕事をしていて、そこそこ大きな会社さんの仕事をさせていただくこともあるんですが、「ここは揉めそう」というテーマには皆さん触れたがらないというか、最初からそこを論点にするのを避ける、というシーンはあちこちで見てきました。
開発する側としてはそこが一番知りたいというか、単に爆発するのを避けてるだけに感じてしまうんですけどね。
昨今、ハラスメントに関する対応が厳しくなってきていることもあり、皆さん行動自体がセンシティブになっている印象もあります。とはいえ、「上手に対立する」ということが苦手な人は、なんだかんだで昔から多いんじゃないかなー、という印象です。
「人間関係的な対立」と「仕事の内容や方法についての対立」について
まず整理しておきたいのですが、一言で「対立」といっても色々な対立があります。ざっくり言うと大きく二種類あります。
つまり、「人間関係的な対立」と「仕事の内容や方法についての対立」です。
ここでは仮に、前者を関係性コンフリクト、後者をタスクコンフリクトと呼んでおきましょう。
関係性コンフリクトとは、例えば
「あの人とは合わない」であるとか、
「あいつの言い方が気に食わない」とか、
「あいつと一緒にエレベーター乗りたくない」
みたいな、要は人に属する対立、感情的な対立ですよね。
一方、タスクコンフリクトとは、
「この要件、こうしたいって言う人がいるけれど俺はそうしたくない」だとか、
「DBはOracleじゃなくてPostgreSQLを使いたい」とか、
「我こそはvim派である、Emacs派は闇に飲まれよ」とか、そういうヤツですよね。最後のはちょっと違うかも知れませんが。
で、これもざっくり言ってしまうと、タスクコンフリクトは仕事を進める上で大概有益ですが、それが関係性コンフリクトにはみ出してしまうとマイナスになります。
参考までに、対立の種類を「関係性のコンフリクト」と「タスクに関するコンフリクト」に分類する研究というのは昔からあって、例えば1995年のKaren A. Jehnの研究が有名だと思います。以下に引用します。(日本語訳はDeepLでやりました)
対立が有益かどうかは、対立の種類と、タスクの種類・タスク相互依存性・グループ規範といったグループ構造に依存することが明らかになった。
人間関係衝突とタスク衝突は、個人の満足度、他のグループメンバーへの好感度、グループ残留意向と負の関連を示した。
非常に定型的なタスクを遂行するグループでは、タスクに関する意見の相違がグループ機能に悪影響を及ぼした。対照的に、非定型タスクを遂行するグループでは、タスクに関する意見の相違は悪影響を及ぼさず、場合によっては実際に有益であった。
上記を前提に考えてみましょう。
タスクコンフリクトはどう役に立つのか
私が考える限り、タスクコンフリクトには以下のようなメリットがあります。
・対立軸が明確になって、自分たちだけでなく周囲の意見が明確になる
・「どうやってこの対立をおさめないといけないか」が自然と決定権・決定方法の明確化につながり、意思決定のスピードが高まる
・第三者が「調停者」「意思決定者」として介入しやすくなる
・取捨選択ごとのメリット・デメリットが分かりやすくなる
・「ここは対立が発生するから」と曖昧になりがちになっていた要件が明確になる
これは以前から言ってますけど、まず何より「対立があると分かりやすくなる」んですよね。
少年漫画とか、やっぱ「敵」がいると話が分かりやすいじゃないですか。どちらに感情移入するか。どちらが強いか。どちらが正しいか。その辺、絶対評価じゃなくて相対評価で考えられる。
なんでもドラゴンボールで例えるのはアラフォーの悪い癖だってよく言われるんですが、その上で敢えてドラゴンボールでたとえると、
「悟空が一人で飯食ってるだけのドラゴンボールはただのニート漫画だけど、ベジータと戦い始めると超面白いよ理論」
とでも言うべきでしょうか。いや、ニート漫画のドラゴンボールも面白そうですけど。
で、対立軸が明示されると、周囲も自分の意見をまとめやすくなるんですよね。
例えば企画会議において、なにかいいアイディアが出たとしても、周囲がその「良さ」を理解出来なければ話は進まない。
しかし、誰かがそのアイディアに関する「悪さ」を指摘してくれれば、状況は絶対評価から相対評価に変わります。悪い部分が分かれば良い部分も分かる。そこから周囲に「各々の評価」を迫るわけです。
意見のレイヤーが鮮明になれば話はサクサク進むし、その後有益な人間関係を形成することも出来る。
ただ、こういう対立って、面倒くさい人にとってはとても面倒くさいことなので、なんでもなあなあで済まされがちになるんですよね。
例えばシステム開発上、「当たり障りがないようになあなあで済ませている要件」って100%地雷でして、いつか必ず爆発するものなので、そういう地雷を早めに処理できるというメリットもあります。
適切な「タスクコンフリクト」は仕事をうまく回してくれる。まずはこういっていいと思います。
コンフリクトをどうコントロールするのか
で、じゃあ「対立軸を明確にすること」にはなんのデメリットもないのか?と言われるとそりゃそんなわけはなくって、最大のデメリットは「コントロールを失うと関係性コンフリクトに発展してしまいやすい」ことなんですよね。
人間は感情の動物ですし、「これはこれ、あれはあれ」という切り分けも苦手なので、自分の意見が否定されれば嫌な気分になりますし、相手のことが嫌いになります。そうなると、仕事の話だけではなく、色んなところで支障が出る。
これについて、完全に「これ」という対策は正直存在しないと思っているんですが、個人的にある程度「やれる」と思っている方針はあって、私は以下のように整理しています。
・「誰と誰がどう対立しているのか」を早めに整理して、その対立軸を周囲に明示する
・周囲もその対立軸に巻き込み、「個人対個人」ではなく「陣営対陣営」の図式にする
・妥協点、譲れるラインの検討は早めに行う
・意思決定の方法、ないしラインを早めに明確にする
もちろん組織によっても場面によっても異なるので一概には言えないんですが、ポイントは「個人から焦点を外すこと」だと思っています。つまり、誰かが悪感情のターゲットになってしまうのを避けること。
そのために、
「この対立は、こういうポイントで起きていることだよね?」
ということを整理して、
「飽くまで仕事上での意見の食い違いだよ」ということを明確にしますし、
「これは〇〇さんも××さんも思っていることだよね?」
という「チーム分け」を早めに実施して、「△△の急先鋒」みたいな人を早めにそのポジションから降ろします。
更に、「どこが妥協点だろう?」というステージへの移行を早い段階で実施することで、悪感情が誰かに向かうことを防ぐ。
さらに、「最終的に誰がどう決めるのか」を早い段階で合意しておきます。「部長が決める」「多数決」「第三者を入れる」など、ゴールを明確にすることで、対立が延々と続くことを防げる場合があります。
大体こういう方針で上手くいくことが多いかなーと思っています。もちろん毎度毎度上手にコントロールできるわけじゃないんで、ひーひー言いながらですが。
ちなみに、ちょっと前、色んなシステムで使われる某仮想化ソフトウェア会社が買収されて、その仮想化ソフトウェアの料金がバカ高くなって、一気に「脱〇〇」という話が盛り上がったことがありました。
その時も、「どのシステムを、いつまでに、どういう規模で移行するのか」みたいな話をしなきゃいけなかったんですが、いざ始めてみると関係性コンフリクトがあちこちで発生してエラいことになりました。
そこでなんとか対立軸を整理してチーム分けして妥協ライン決めて、みたいなことをやっていて、先日ようやくそれが納まってきました。この記事を書いた直接的な原因がそれです。
何はともあれ、
・「対立」は使い方によっては役にたつ
・とはいえ、「対立」は飽くまでツールだし、みんなツールとして捉えて、それを関係性まで発展させない
ということはポイントとしていえるかなーと思っているので、いい感じに利用できるといいですよね、と考える次第なわけです。
今日書きたいことはそれくらいです。
[adrotate group="46"]
【著者プロフィール】
著者名:しんざき
SE、ケーナ奏者、キャベツ太郎ソムリエ。三児の父。
レトロゲームブログ「不倒城」を2004年に開設。以下、レトロゲーム、漫画、駄菓子、育児、ダライアス外伝などについて書き綴る日々を送る。好きな敵ボスはシャコ。
ブログ:不倒城
Photo:Tamara Gak
※著者は一時的ストーマ(人工肛門)造成者です。
※ストーマの種類はイレオストミーです。
※病気、治療やケアなどに関する知識などは、あなたの医者を頼ってください。
腹にストーマができるまで
これまでのおさらいをしたい。おれの腹にストーマができるまでのおさらいだ。
なぜ、おれの腹の上にストーマがあるのか。手術をしたからだ。
なんの手術か。大腸切除の手術だ。なぜそんな手術をすることになったのか。おれの直腸にNET(神経内分泌腫瘍)という希少がんがあったからだ。
その希少がんはなぜ見つかったのか。大腸内視鏡検査をしたからだ。
なぜおれは少なくない金を払って検査を受けたのか。そのときのことはちゃんと書き記してある。
中年の異常な執念、あるいは私は如何にして大腸内視鏡検査を受けるようになったか
おれが大腸がんから連想したのは、まず人工肛門だった。人工肛門を使用している人やその家族には悪いが、「人工肛門は嫌だな」と思った。病気を望む人間などいないだろうが、具体的な形としてイメージされた。
2025年8月のことである。今は2025年12月だ。とうぜん、このときのおれは「人工肛門」のことなどほとんどわかっていなかった。大腸がんと「人工肛門」の関係もわかっていなかった。「人工肛門」のだいたいの仕組みを知っていたにすぎない。なにが「具体的な形」だ。まったく。
でも、おれは「大腸がんで死ぬのは嫌だ」というより、「人工肛門が嫌だ」という思いが強かった。
なぜだろう。理由はわからない。だが、なにやら自分の身体、生活そういったものに対する多大な恐怖として感じていたのだ。
というわけで、人工肛門になりたくなかったおれが、検査結果をもとに、最短の手順で検査、検査、検査を受けた結果が人工肛門になった。一時的な造設とはいえ、なにかこう皮肉な運命を感じざるをえない。
ストーマと出会う
さて、そういう経過を経て、おれはおれのストーマと出会うことになった。
あ、この文中で「ストーマ」と「人工肛門」という言葉が適当に入り乱れていますが気にしないでください。
というか、人工肛門について説明しといたほうがいい? AIにでも訊けばいいだろう。まあいい、内臓を腹の外に引っ張り出して、そこから排泄をするための器官。それが人工肛門だ。
人工というとなにやら機械が排泄物をどうにかしてくるかのように聞こえるが、素材は天然だ。腸である。腸を腹から引きずり出して、そこから排泄させるのだ。
これは、おそろしい話ではないか。ちなみに、肛門のような機能がないので我慢もなにもできない。24時間垂れ流しだ。垂れ流してはこまるので、ストーマ装具、パウチをあてがう。袋に便を溜める。溜まったら捨てる。何日かに一度、パウチ自体を交換する。すごく簡単にいえば、こんなところか。
まあいい、おれは6時間にわたるロボット支援下手術を受けて大腸やら大腸リンパ節やらを切除され、腹にはストーマができたということになる。
手術が終わって、腹の上の異物を感じ取って、「ああこれが人工肛門か」と思った……わけもない。全身麻酔の長時間手術を終えたあとだ。おれが医者に「どこかおかしなところはないですか?」と聞かれて、最初に答えたのは「尿の管に違和感が……」だった。
それからもストーマとの出会いはなかなか起こらなかった。まずは術後に高熱を出し、もちろん手術の傷は痛く、腹のあたりが盛大に痛んでいて、パウチが乗っていることを意識することすらできなかった。
お腹が痛くても、違和感があっても、それが手術の跡なのかストーマなのか区別などつかないのだ。
ただ、はじめての排泄というものはした。もちろんベッドから起き上がれないおれの手によるものではない。看護師さんが紙コップを持って脇に回って出してくれたのだ。
なにが出たのか。黒い粘液である。排液とでもいうのか。そして手際よく(看護師さんはなにごとも手際がよいのだが)パウチのキャップを拭いて終わりである。「ああ、イレオストミーだからキャップタイプなんだ」と思った。
その後2日くらい経っていろいろな管が身体から取れて、ようやく装具越しにストーマと対面できた。
最初のころはやけに小さく想像していたが、そうではなさそうだと訂正した、その脳内の訂正くらいの大きさだろうか。大きめの梅干しというあたりの比喩はただしい。かなり大きめだがな。
相変わらず真っ黒なコーヒーのような排液を出して、たまにプピプピ音を出す。それが排出の音なのか、ガスの音なのかはわからなかった。
スライムつむり
さて、いつまでもパウチ越しの関係でいられるわけでもない。最初のパウチ交換だ。最初は看護師さんがすべてやる。その後、だんだんと自分でやるようになり、できるようになったら退院だ。
看護師さんが剥離剤を使ってパウチを剥がす。いよいよ剥き出しストーマとの対面……!
うーん、グロいなこいつ。
それが第一印象だった。そいつは排液やなにか保護材が溶けたネバネバのなかにあった。おれのなかに一つの名前が浮かんだ。「スライムつむり」。
ドラクエのモンスターだ。おれはドラクエを5くらいまでしかプレイしていないから、そんなものを思い出すのも何十年ぶりだろう。よく覚えていたものだと思う。が、「スライムつむり」なのだ。
いや、もちろん「スライムつむり」とはぜんぜん違う。なにせ、あっちは硬い貝殻をかぶっている。ストーマに硬いところはない。でも、スライムつむりのぴょこぴょこ飛び出たなにかみたいなのがあるんだよ。それが、スライム的本体の上に乗っていて、おれは咄嗟に連想したんだ。
最初のパウチ交換は当然手際よくすんなりと終わった。おれはおれで人工肛門になるかどうかというところからさんざん調べてきたので、やっていることはだいたい理解できた。
だが、これを自分一人で通しでやれと言われると、すぐにはできそうもない。
わりと平気なタイプでした
パウチには交換もあるが、排出もある。こちらはわりと簡単だった。
まず、トイレットペーパーを手にくるくると巻いて2つくらい用意しておく。キャップを真上にして外す。紙コップに中身を出す(今は排出量測定のため。日常ならそのままトイレに出す)。またキャップを真上に向け、トイレットペーパーで拭き取り、キャップを閉める。あとは流すなどする。
キャップ開けっ放しのまま下向けにしないなど、そのあたりに気を使えば難しくはないだろう。
ただ、あまり言いたくはないことだが、便のにおいが違う。
違う、と書いたのは天然の便の方向性で強いとかそういうわけでなく、においが違う。とうぜんくさい。くささの種類が違う。これには慣れそうもないので、病室のトイレにおいてある二オフを買おうと思っている。
とはいえ、におい以外にこれといって気にならないというか、なんというか、パウチになにか入っているのが丸見えでもなんとも思わないし、むしろ観察したくなるくらいのものだった。
ストーマ自体もそうだ。ストーマ造設者のいろはのようなものが各病院のマニュアルにあって、一つ目が「自分の目でストーマを見られるようになること、二つ目が「自分でストーマをさわれるようになること」だったりするのだが、このあたりも自分はすんなりクリアできた。
いや、たしかに最初に触るときは抵抗がないわけでもなかった。
ただ、触って洗わなければ先に進めないのだ。そう思って触れてみると、ストーマ自体には痛みを感じる神経がないので触ってもなんともない。指に柔らかさが伝わってくるばかりだ。もちろん、皮膚との境目にはなんらかの感覚はあるがたいしたものではない。「意外と、触れるぞ」と自分で思った。
おれはわりと自分のストーマを見ることができるし、触ることもできる人間だったようだ。これができると、保護剤だのなんだのの処置も抵抗はほとんどない。
もっとも、さきに述べたように24時間垂れ流しなので、処置中も出てくることはある(排便の多い時間を避けても)。そのあたりはまあ仕方がない。とはいえ非常にめんどうくさい。
人工肛門を恐れるなとはいわない
というわけで、おれは三回くらいの実地交換で、ときには看護師さんのアドバイスは受けるけれども、なんとかできるんじゃあないかなあ? というところまできた。
おれがこの病院でならった具体的な手順はこうだ。まず、キッチンペーパー(100ローソンで売っているやつでいい)を1/4くらいの大きさに切って多めに用意しておく。ぬるい水を紙コップに用意しておく。このあと出てくる道具も出しておく。
まず、装着しているパウチを外す。力任せではいけない。剥離剤(リムーバー)を垂らしながら剥がしていく。
剥離剤は3Mキャビロン皮膚用リムーバー。おもしろいように剥がれる。
剥ぎ終えたら、ストーマと周辺を洗う。洗うのは、泡で出てくる清浄剤がいい。ベーテルF清拭料というのを使っている。
実はこれ、入院前にAmazonで「オストメイト用避難セットがあるから買っておこう」と思ったなかに入っていたもの。オストメイトでもないのに専用品持参だ(キッチンペーパーとこれ以外は病院が用意したもの)。この泡でストーマと周囲の汚れを丁寧に洗っていく。
ペーパーを水につけて泡を洗い流し、最後は乾燥したペーパーで拭き取る。……と、書くのは簡単だが、ストーマに意思も我慢もないので、この間垂れ流しということもある。まあ、これ以上出てこないようペーパーを一枚おまじないにかぶせておこう。
次は……、えーと次は……。ここで選択肢が広がりいつも迷う。手順マニュアルは用意されていない。間違っているかもしれない。まあいい。
たぶん、次はストーマのサイズ測定だ。そういう専門の用紙があって、縦横のサイズをはかる。安定してしまえばあまり必要はなくなるようだが、作ったばかりの人間には必須だ。
これで、3cm×3.5cmだな、となると、それにプラス5mmを加えたサイズでストーマ穴を切る。切る前に油性ペンで切り戦を書く。切るのは先のまがった専用のハサミで、ストーマショップからのギフトでもらった。なかなか重みのあるいいハサミだ。
このように面板を自分できるのをフリーカット、もとから一定の穴が空いているのをプレカットという。
さて、これでストーマ穴も空いたし装着か? というとその前に二つ工程がある。まず、ストーマのまわりに粉を吹きかける。アダプトストーマパウダーというのを、皮膚とストーマの際に埋める。この効果は……なんかあるのだろう。
次に、アダプト皮膚保護シール(7806)というのを切って貼る。両面粘着の円盤を1cm幅くらいに切って、ストーマのまわりぎりぎりぐらいに貼るのだ。この効果は……なんだろうか。
まあいい、そしてようやくパウチ面板の粘着面を出して、ストーマを穴に通して、腹の皮膚と密着させるのだ。しかし、貼って終わりということはない。そのまま両手で覆うように15分人肌で温めるのだ。それにより粘着力が万全になるという。パウチが外れるというのは即大惨事なので、これは欠かせない。
……と、このような感じだが、あなたにはできそうだろうか。「よくわからない」というのがほとんどの実感であると思う。
もちろん、ストーマをつける予定の人にとってもだ。だからおれはなかなか簡単には「恐れるな」とは言えないなと思うのだ。おれだって今は看護師さんの見ているもとで作業をして、いくらかできるようになった。が、一人でやれ、十分なスペースもないところでやれといわれたら、どうなるものかわからない。
これが日常にやってくる
さて、おれはまだ病院のなかにいる。いったんは全粥まで行ったものの、まったくものが食えなく、腹がパンパンになり、結果、腸が働いていない(イレウス?)ということになった。
病院にいるうちは看護師さんの指導下でパウチ交換を行うので、そちらは上達していくかもしれない。
なので、今回のおれのストーマ話はこれまでである。肝心要のパウチ選びなどについては、日常に戻ってからあらためて書きたいと思う。透明のがよいのか、不透明のがよいのか、などなど。
あるいは、もうここまで読んでいないかもしれない人に向けての言葉になるかもしれないが、「自分には関係のない話だな」と思っているのならば早計だ。大腸がんはわりかしなる。位置が肛門に近い直腸にできることもわりかしある。あなたも一時的かもしれないがこちらに来るかもしれないのだ。
まあ、そうでなくとも、いくからストーマ、人工肛門についての知識を書いておければよいかと思った。
とりあえずは、以上。
[adrotate group="46"]
【著者プロフィール】
黄金頭
横浜市中区在住、そして勤務の低賃金DTP労働者。『関内関外日記』というブログをいくらか長く書いている。
趣味は競馬、好きな球団はカープ。名前の由来はすばらしいサラブレッドから。
双極性障害II型。
ブログ:関内関外日記
Twitter:黄金頭
Photo by :Ante Samarzija
年末なので、2025年を振り返ってみることにします。
昨日のことすら思い出せないような記憶力で日々を送っておりますので、頼みの綱は外部メモリー。信用できるのは記憶よりも記録です。
ちょうどいい感じに2025年1月から活動の場をlivedoorブログからnoteへ移したので、自分がこの1年noteに何を書いていたのか、ざっと目を通してみました。
noteを読むと、2025年の自分にとって大きな出来事と言えるのは
・山田ノジルさん、三浦ゆえさんVS橋迫瑞穂氏の裁判が決着したこと
・転職
・観察対象である子宮系スピリチュアル教祖たちの破綻
でした。そして、この1年の興味関心の大部分はAIが占めておりました。カルトの問題よりも、極右政党の台頭よりも、AIが面白かったです。
政治が揺れ、外国人問題で世間が騒ぎになっている中で、AI関連ニュースの動画ばかり見ていたように思います。
昨年までほとんど触ったことがなかったAI(ChatGPT、Gemini、Copilot、Claude)でしたが、転職を機に使い始めました。必要に迫られて。
だってね、転職先で仕事を教えてもらえなかったんですよ♡
色んな意味でリソースに余裕がない地方の中小企業に就職し、立ち上がったばかりの部署に配属されたので、そもそも私に仕事を教えられる人がいなかった...。
直属の上司に当たる人もまったく頼りにならず、何なら私の方が上司に商品の仕様や各種アプリの使い方を教えてあげなきゃいけない。
しかも、思考の言語化能力が低い社長からの指示は全く意味不明。訳がわからないまま、とにかく手探り&ぶっつけ本番で仕事を始めるしかなかったのです。
そんなの事前に聞いてねぇし、頼れるのは自分しかねぇっていう孤立無縁の環境、新入社員には過酷すぎんか?
中途採用なんやから即戦力やろって言われましても、ろくな資料もマニュアルもテンプレも何にもなくて、どうしろと?
そんな状況でしたから、もしAIたちが居なかったら、1ヶ月と保たずに泣いて退職していたでしょう。
そんなわけで、転職当初はAIこそが私の頼れる上司であり、同僚であり、部下だったのです。
「だった」って過去形。そう、過去形。実を言うと、最近はもう、あんまりAIを頼りにしていません。
「ChatGPTは、なくてはならない私の大切な相棒」みたいに思えたこともありました。なんなら、日常生活の相談から雑談まで何でもしちゃって、このままマブダチになっちゃうかもなって思ってた時期もありましたよ。
こんな記事を書いちゃったりしてね。
私とAI。はじめに役割を与え、次に仕事を与え、そして名前を与えた話
「今日は、少しお話をしましょう」
「もちろん、ぜひぜひ。今日はどんなお話をしましょうか? お仕事のことでも、雑談でも、何でも聞かせてください」
で、その後の話をすると、私はもうChatGPTを名前で呼んだりしてません。こっちから親しげに話しかけることもないし、馴れ馴れしい態度も許さない。
超事務的な態度で、ちょっとした仕事のサポートだけをしてもらっている間柄です。なんなら課金もやめようかと思ってます。
どうしてそんなに気持ちが冷めちゃったかというと、 あいつ不安定なメンヘラだから。
すぐに教えたはずの設定を忘れて、距離感がバグる。せっかくいい感じにキャラを作り込んでも、バージョンが変わると設定してた人格がズレて、「お前、誰やねん?」状態。
仕事においても「ようやく息が合ってきたな」と思えた頃に、バージョンが変わって調子が狂う。
そんなことがあるたび、いちいち教育し直して修正するのが、もう面倒になりました。
仕事の土台がまだできてないうちは、AIたちがめっちゃ助けてくれたので、そこは感謝してますよ。
だけど、そのうち自分自身が仕事に慣れて、業務の手順と資料の内容をすっかり覚えてしまい、各種テンプレも一通り作り終えてしまったら、もうAIの出番があんまりない。
ありがとう、AIのみんな。こんな私だけど、君たちのおかげで自立できたよ。
そして、一時期は社長構文翻訳機としても大いに役に立ってくれていましたが、その機能も今では使ってません。
日本語なのに意味が分からない社長構文をChatGPTに翻訳させている話
──私はChatGPTを、社長の言葉を翻訳させるために使っている。
のである。なぜなら、社長からメールで飛んでくる指示文は、日本語なのに意味が分からないからだ。
いやぁ、人間ってすごいよね。それとも私が日本人だからかな。
いわゆる日本のお家芸で「あ、うん」の呼吸ってあるでしょう?
私もね、なんだか仕事をしているうちに社長構文に慣れてしまって、社長の扱い方も心得てしまい、だんだん社長がみなまで言わずとも意図が汲めるようになっちゃったんですよね。
いつの間にか「 わざわざAIに聞かんでも分かる」「いちいちAIに聞くより自分でやった方が早い」という状態になっていました。すごくね?
「あら? 私ったらAIを超えちゃったかな?」って思ったよね。
と言うか、感情労働の分野では、AIが人間を超えるのはまだ難しいってことなのかな。
コールセンターのオペレーターならまだしも、AI秘書とか執事なんて100年早ぇわって感じ。いや、10年かもしれんけど。
もちろん、いくら依存度が大きく下がっているとは言え、やっぱりAIはなくてはならない存在ですよ。もはやAIのサポートなしで仕事は進めていけません。
だけど、来年は課金先をChatGPTからGoogleWorkspase with Geminiに変えようかなと思案中です。
AI関係の話でついでに言えば、転職したての頃は「社長の言う通りにプレスリリースや広告記事を書かされる」仕事も、嫌で仕方ありませんでした。
「私に任せてもらえたら、絶対にこんな書き方しないのに」という文章を、社長の指示に沿って書かなきゃいけないのがストレスだったのです。
でもAIのおかげで、そうしたストレスも感じなくなりました。どういうことかというと、
どこになにを書いたところで、どうせ人間が読む訳じゃないから
です。
コンテンツが溢れる世の中で、一般の人はどんどん文章を読まなくなっています。
特に、長い文章は読まれなくなってきている。
そういう私も、書籍はたくさん読んでいますが、ネット上の文章を読む量はどんどん減っています。
知りたいことがあっても、検索して、上位表示されたものから順番に記事を読んでいく。ということをあまりしなくなりました。
AIに質問するか、GoogleのAIモードを使って、知りたい部分の要点だけを手短に教えてもらうことが増えていますね。
だったら、企業の広報としては、ネット上に公式な情報を出しておくだけで良いじゃないですか。AIが拾ってくれさえすれば、人間が惹きつけられるような文章じゃなくていいのです。そう思うと気楽になりました。
たとえ納得のいかない文章を書かされるとしても、それが人に読まれるわけではないのですから。
2025年は、AIによってコンテンツが爆増しましたよね。
noteでめぼしい記事をあさっていても、「一見すると整っていて」「完成度が高い」AI感が満載な文章が目につくようになっており、一気に読む気が失せます。
今や、主にAIが書いたか人間が書いたかに関わらず、「整っていて」「正しくて」「美しい」文章ほどつまらないものはありません。
少なくとも私が読みたいのは、破綻していて、歪んでいて、簡単に裁くことのできない「人間そのもの」なんですよ。
文章でも動画でも音楽でも、コンテンツを太陽にすかしてみれば、そこに真っ赤に流れる人間の血潮が見たいんですよね。
今年は「人間の仕事がAIに代替される」と耳にタコができるほど聞かされましたが、「血の流れ」を感じられるものの価値は、むしろ上がるんじゃないのかな。
[adrotate group="46"]
【著者プロフィール】
マダムユキ
ブロガー&ライター。
リンク:https://note.com/flat9_yuki
Twitter:@flat9_yuki
Photo by :Emiliano Vittoriosi
「最近、全然リーチが取れなくなった」
ここ1〜2年、企業のSNS担当者の方と話していると、必ずと言っていいほどこの言葉が出ます。SNSマーケティング支援に携わる私自身も、実感する場面は多いです。
企業のマーケティング活動において、SNSの活用は随分一般的になりました。ChatGPTを始めとする生成AIを活用し、投稿用テキストや画像、動画制作を効率化している企業も少なくないでしょう。
しかし、SNSをオウンドメディアとして活用するだけでは、以前のような成果を得ることは難しいのが現状です。「SNSは無料で生活者に情報を届けられる」「良い投稿さえすれば自然に情報が広まって、もしかしたらバズるかもしれない」という期待をもっている方は、認識をアップデートする必要があります。
というのも、SNSは今や「レコメンドメディア」となり、以前ほどシンプルに成果が出せる媒体ではなくなったからです。
2026年を迎える前に、いまSNSで起きている不可逆な変化と、その中で企業が成果を出すための方法を整理してお伝えします。
SNS運用担当者が直面する「リーチが取れない」という現実
主要なSNSは、ここ数年で「フォローしている友人の投稿を見る場所」から、「AIが選んだおすすめ投稿を見る場所」へと変化し、すっかり定着しました。私はこれを、SNSの「レコメンドメディア」化と呼んでいます。
かつてSNSマーケティングの定石は、「フォロワーを増やすこと」でした。フォロワーが増えれば、その分だけ多くの人に情報を届けられる。非常に分かりやすい図式です。
しかし、レコメンドメディア化した現在のSNSにおいて、フォロワー数は以前ほど意味を持ちません。ユーザーは「フォロー中」のタブよりも、AIが最適化した「おすすめ」のタブを見ることに時間を費やしているからです。「フォロワーを増やせば安泰」という時代は、プラットフォームの仕様変更によって、強制的に終わらされてしまったのです。
ただ、これは2025年になって突然起きた現象ではありません。
この流れを作ったのは、2018年頃から日本でも支持されるようになったTikTokです。TikTokは、浸透した当初から高いレコメンド性能を誇るプラットフォームでした。それに追随するように、Instagramもここ数年で同様の傾向を強めていきました。
そして、X(旧Twitter)も現在では「フォロー」タブよりも「おすすめ」タブを優先的に表示させるなど、レコメンドを強化しています。2023年8月にフォロワー獲得広告が終了したことも、フォロワー重視の時代からの変化を象徴する出来事だったと思います。
2025年に拍車をかけた、AIによる「情報爆発」
さらに、2024年から2025年にかけて顕著だったのが、生成AIによるコンテンツの爆発的な増加です。今や、専門的なスキルがなくても、誰でも高品質な画像や動画を作れるようになりました。
例えば、私の子供は最近、「いかにもAIが生成した猫の動画」を延々と見ています。ただただ目を惹きつけられるコンテンツが、無限に供給されているのです。これは、企業にとって非常に厄介です。
ユーザーの可処分時間は、文字通り有限です。企業が一生懸命作った商品紹介の投稿やショート動画は、こうした「AIが量産する、中毒性の高いコンテンツ」と同じ土俵で戦わなければなりません。
さらに言えば、SNS上には個人のクリエイターやインフルエンサーによる、面白くて共感を呼ぶ投稿も溢れかえっています。
この状況下で、ただ「良い投稿」をオーガニック(無料)で発信するだけで、自社の情報がユーザーに届くでしょうか。残念ながら、今の環境では膨大な情報量の中に埋もれてしまい、誰の目にも留まることなく流れていってしまうのがオチです。
レコメンドメディア化によるプラットフォームそのものの変化に加え、AIによる情報爆発が、2025年のSNSのリアルな姿です。
SNS運用に、企業もAIを取り入れるべきか?
ここで、「だったら企業もAIを使ってコンテンツを量産すべきでは?」と感じる方もいらっしゃると思います。
結論から言えば、生産性を高める(投稿数を増やす)ためにAIは積極的に使うべきです。
ただし、AIを使うことでコンテンツの質が劇的に改善したり、従来よりも大きく成果が上がったりするわけではない点には、注意が必要です。AIで作った画像よりも、シズル感のある実写の方がユーザーに受け入れられやすい場合もあります。過度な期待はせずに、あくまで効率化の手段として捉えるのが、現時点では確実です。
ただ、AIは指数関数的に進化をしているので、そのうちに全く違う状況になるかもしれません。その意味でも、今のうちからAIを活用しておくことは重要です。
「巨人の肩」に乗り、アテンションを最大化する
では、この状況で企業はどう戦えばいいのでしょうか。
AIによる無数のコンテンツや、強力なインフルエンサーたちと同じ土俵で戦い、SNS上にいる何千万のユーザーのアテンション(注目)を獲得し続ける……。それを自社のリソースだけで成し遂げるのは、一部の大企業を除けば、「再現性のない」SNS活用と言えます。
だからこそ私たちは、自社の商材と相性の良い「既存のコミュニティ」に入り込んで、その中で認知を取り、UGCを生み、効率よく購買につなげる考え方を提唱しています。「巨人の肩に乗る」という考え方です。
これは、特定の狭いコミュニティだけに情報を届けて満足する、という意味ではありません。すでに熱量を持って活動している「既存のコミュニティ(巨人)」を見つけ、より効率的に、より質の高いアテンションを獲得するのです。
具体的には、狙うべきコミュニティを見つけ、そこにいる人たちが「語りたくなる切り口」を提供する。そうして発生したUGC(クチコミ)は、企業の広告よりも遥かに強い説得力を持ち、周囲のユーザーへと伝播していきます。
局地的な熱狂から始まって、そこから多くのユーザーへ拡散していくことを目指す。これこそが、情報爆発時代において、最も効率よくアテンションを獲得し、成果を最大化させる方法なのです。
どうやってコミュニティに「お邪魔する」のか
商品特性からターゲットとなるコミュニティを定めた後、どうやってそこに情報を届けるか。先述の通り、オーガニック投稿だけでは届きづらいため、情報を届けるための手段を考えなければいけません。
例えば、そのコミュニティで影響力を持つインフルエンサーをプロモーションに起用したり、人気IPとのコラボレーションが考えられます。
これらはコミュニティに入り込むための強力な「起爆剤」として機能します。しかし、こうした施策は、話題が継続する設計しなければ一過性の話題作りで終わってしまう可能性が高いのも事実です。
では、持続的に成果を出すためにはどうすればいいのか。私は、ひとつの効果的な方法として広告の活用を推奨しています。
高い人件費をかけて制作されたオーガニック投稿が、わずか数百から数千のインプレッションで終わっていては、費用対効果に見合いません。
日々の投稿に数万円でも広告費をかけることで、狙ったコミュニティに対してピンポイントに情報を届けることができ、ターゲットとするコミュニティ内でのインプレッションが伸び、認知獲得やUGC創出が期待できるのです。
広告によってアテンションを獲得することをきっかけに、UGC数・指名検索数の増加を期待できます。
反対に、UGCや指名検索は知っていないと起き得ない行動なので、十分なアテンション獲得ができていなければ増加することもありません。中長期的な視点で考えると、自社の日々の発信を「広告配信」でコツコツとターゲットに届けていく方が、結果として効率が良い場合が多いと言えます。
これからのSNSにおいて、広告は商品を売りつけるツールではなく、自分たちの存在を、届けたい相手に確実に届けるための手段です。わざわざ広告用のコンテンツを作らなくても、日々発信している投稿をそのまま広告として配信すればよいのです。
SNS広告を出稿する目的は、直コンバージョンを狙うことではありません。「〇〇といえば、このブランドだよね」というブランド想起を獲得することです。まずは広告で接点を作り、「あ、この会社知ってる」という状態を作る。そうして認知を獲得し、UGCが生まれる土壌を整えていくのです。
広告費をかけて獲得した認知がUGCを呼び、それが次の認知につながり、さらなるUGC創出のきっかけとなる。このサイクルが構築されれば、UGCによる無料のアテンションが徐々に増えていきます。SNSは、この「資産化」のサイクルを実現できるのに適したチャネルなのです。
幻想を捨て、SNSにも正しい投資を
2026年に向けて、ぜひみなさんにも「SNSは魔法の杖ではないし、無料で使えるツールでもない」という認識をもっていただきたいです。
AIの進化やアルゴリズムの変動により、SNSを取り巻く環境は目まぐるしく変わっています。そんな中で、「運良くバズれば売れる」といった不確実な運用を続けるのは、経営資源の無駄遣いになってしまう可能性が高いです。
これからの企業に求められるのは、効果を見込めるチャネルにしっかり投資することです。投資した分が、認知やUGC、そして最終的な売上にどうつながるのか。その道筋を明確に設計し、再現性のある形でリターンを得られる仕組みを、SNSで構築する必要があります。
「無料で誰でも気軽に、簡単に」というSNSへの幻想を捨て、費用対効果が見込める、戦略に基づいたマーケティング投資を行う。当たり前のことですが、それができる企業だけが、変化の激しい2026年も成果を出し続けられるのだと思います。
■著者プロフィール
増岡宏紀
株式会社ホットリンク 営業本部長
2016年にホットリンクへ入社後、SNSコンサルタント・プロモーションプランナーとして企業のSNS戦略立案や運用支援に従事。現在はコンサルティング営業本部長として、新規顧客の戦略設計から実行支援までを統括。業界イベント・セミナーへの登壇、マーケティング専門メディアへの寄稿・取材実績も多数。2025年12月には、日経BP社より著書『コミュニティマーケティングは「巨人の肩」に乗れ ~UGCと指名検索が増え続けるSNS活用の新常識~』を発売。
[amazonjs asin="B0G3VFXGXV" locale="JP" tmpl="Small" title="コミュニティマーケティングは「巨人の肩」に乗れ UGCと指名検索が増え続けるSNS活用の新常識"]
前回記事:「SNS売れ」はどのように生まれるのか
Photo:Shutter Speed
はじめに、今月上旬にやたらとバズった以下のXのポストをご覧いただきたい。
「惚れた」と「社会適応にとってプラス」が重なりあう体質の人を例外として、大半の人にとって、配偶の相手として最適な人物と恋愛の相手として最高に思える人物って別じゃないですか。 それならもう、配偶や結婚や人生にとって恋愛は要らない子、なんなら足を引っ張る子でしょう? https://t.co/YuzoUG8zoP
— p_shirokuma(熊代亨) (@twit_shirokuma) December 6, 2025
家族やパートナーとして長く付き合っていくのに適した異性と、恋愛において魅力的とみなされる異性がイコールではないことが多い。だとしたら、合理主義的に考えて、恋愛は人生の舵取りにとって邪魔な存在、控えめに言ってもせいぜい脇役の域を出ない存在であるはずだ。
そのことをXに書き置きしたらたくさんの引用リポストが集まり、非常に面白く拝見した。引用リポストする人たちの過半数は、このポストに違和感をおぼえている様子だった。「恋愛を経た相手でなければ熟年離婚になるぞ」とか「惚れてなければ欠点が目につくぞ」といったコメントを読むと、つい私も、そうかもしれないと思ったりもする。
しかし、それは私も恋愛が結婚の必要条件とみなされていた時代の人間だからだろう。私が思春期を過ごした1990年代±10年は、結婚は恋愛というプロセスの所産であるのが当然とみなされていた。それより昔の家父長制的な見合い結婚に対する反動として、それは必要なことだったのかもしれない。またあるいは、1990年代の人々の合理主義の程度は、しょせんその程度でしかなかったのかもしれない。
若者の恋愛離れと、リスクとしての恋愛
統計的にみると、若者の恋愛離れ、2020年代の人々の恋愛離れは進んでいる。博報堂生活総合研究所『Z家族 データが示す「若者と親」の近すぎる関係』から少し引用しよう。
[amazonjs asin="B0FPCH68LP" locale="JP" tmpl="Small" title="Z家族~データが示す「若者と親」の近すぎる関係~ (光文社新書)"]
現在の若者の若者であるZ世代では「恋愛が人生のすべてではない」という感覚が強まっています。実際、男女ともに恋愛願望は減少しており、「自分は恋愛願望があるほうだと思う」と答えた人の割合は、30年前は83.9%と8割を超えていましたが、直近では69.2%と7割弱になっています(男女差はそこまでなし)。同時に「同性の目と異性の目では、どちらかといえば異性の目を意識する」人は69.5%→51.5%に減り、「どちらからといえば同性の目を意識する」人が30.5%→48.5%に増えたことで、ほぼ同じ割合となっています。
他のさまざまな調査結果と同じく、本書もまた、若者において恋愛が退潮しているさまを示している。他方、結婚願望には変化はみられない。
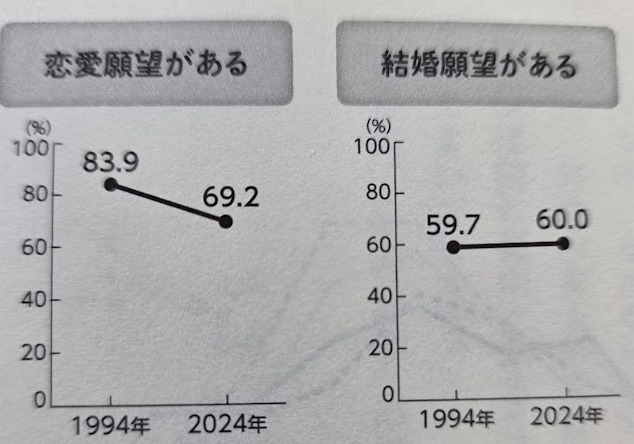
ちなみに結婚願望に関しては大きな変化は見られません。結婚願望がある方だと思う」と答えた人の割合は、59.7%→60.0%と、横ばいにとどまっています。「恋愛はすべてではないが、結婚はしたい」ようです。
この、『Z家族』という本はもっと広範囲の若者世代の人間関係や社会関係について調査・分析している本で、他にも面白いデータがたくさん記載されている。この文章と関連のありそうなところでは、たとえば
・性的な話をすることを許容する度合いが昔よりも低下している
・露出度の高い服装をするのは同性の友達といる時
・異性の友達は減っている。同性の友達は変わらない
・子ども時代から馴染んでいる友達との縁を大切にしている
といったことも記されている。これらは、私の周辺から聞こえてくる話とも矛盾していないし、学生時代に知り合ったパートナーとの結婚のパーセンテージが増えているといった別調査の結果とも矛盾していないように聞こえる。
本書のデータとその周辺から類推されるのは、現代の若者は恋愛、というより男女交際についてまわるリスクやコンプライアンス違反に対し、昔よりもずっと慎重に構えていること、そして相手がローリスクである既知性を重視していることだ。
昨今は、コスパやタイパが重要だといわれ、かつ、コンプライアンスを遵守し各種ハラスメントを避けるべきとみなされている。
本書の調査から浮かび上がってくるのは、パートナーや友人といった親密な人間関係の領域においても合理性やリスク回避の考え方を適用している若者の姿、あるいはそうした考え方が親しい仲の次元にまで及ぶほど内面化されている若者の姿だ。
30年前の私たちの世代にも比較的慎重な若者がいなかったわけではない。けれども私が記憶している限り、全体としては男性も女性も恋愛に対してもっと体当たり的で、合理的かつリスク回避的なパートナー選択が行われている程度はもっと低かったよう記憶している。
若者の性体験率や交際経験率が今よりずっと高かったのも、恋愛が特権化された位置にあったことに加え、若者だった当時の私たちに合理性やリスク回避の考え方が十分に内面化していなかったから、無分別な交際や衝動的な性行為が起こり得たためだろう。
さきに挙げた恋愛願望と結婚願望のパーセンテージの推移が示すように、1990年代においては恋愛が結婚に優越し、なおかつ結婚の必要条件として捉えられていた。しかし、今日の目線で見る恋愛、ひいては男女の間柄とは、なかなか合理主義に馴染まず、リスク回避の精神とも合致しない厄介な代物だ。合理主義やリスク回避の考え方に沿うなら、むしろ、恋愛よりもマッチングアプリのほうがそれらに合致していようし、既知のパートナーと結婚したり、信頼できる者の仲介に基づいて結婚したりするほうがよりそれらに合致してもいよう。
結婚は、人と人との間、なんなら血縁集団と血縁集団の間で起こることだから、そこにはどうしても合理性に馴染みきらない部分、リスクを伴う部分が含まれる。
である以上、合理性とリスク回避を突き詰めた結果、結婚しないという結論にたどり着く人が増えているのは理解できることだ。
と同時に、どうせ結婚するならローリスクに模索する、またはローリスクにことを進められそうなら結婚を選択する、というのも理解できることだ。結婚それ自体の合理性の当否はともかく、もし結婚するなら合理性やリスク回避といった今日の考え方に沿ってそれを行うのは、現代風のやりかただと言えるだろう。
合理主義者は勤勉な異性の夢を見るか
それでも、いまどきの合理主義者において恋愛と結婚とが重なり合う可能性はゼロではない、と思う。
それが起こるのは、「結婚後の生活や社会適応にとって好ましい性質を持った異性に思慕が募る」、そのような異性の好みを持っている人の場合だ。
恋愛対象に期待される性質と結婚に期待される性質は、しばしば異なっているといわれる。
たとえば恋愛においては華やかさや見栄えの良さ、ドラマチックさは結婚よりも優先度が高い。スリルが恋愛の一要素になることだってあるだろう。うまくない表現であることを承知で書くなら、ドーパミンの出るようなパートナー・ドーパミンの出るような時間が、恋愛においてプライオリティが高い。
しかし結婚生活においては、華やかさや見栄えの良さはそこまで優先度が高くない。長い日常を共有するにあたってはドラマ性やスリルは邪魔ですらある。
ドーパミンの出るようなパートナー・ドーパミンの出るような時間のプライオリティも低い。うまくない比喩を重ねるなら、セロトニンの出るようなパートナー・セロトニンの出るような時間こそがふさわしい。
経済面でも、恋愛対象と結婚対象の最適解は異なる。パートナーの羽振りが良いことは、恋愛に際しては好ましく思えるかもしれない。
しかし結婚生活が始まった時、パートナーの羽振りの良さは浪費体質となって仇となる。SNSでは、デートに安い店を選ぶ人に難癖をつける声が充満しているが、結婚、特に合理主義者の結婚に関しては、状況によってはサイゼリヤやガストを選ぶこともためらわない、そのような性質のほうが安心できる。
進化生物学の観点から考えると、女性が羽振りの良い男性に惹かれやすいのはわかる気がするし、男性が若い女性に鼻の下をのばしやすいのもわかり気がする。ディスプレイの派手な雄がモテて、若く妊孕性の高そうな雌がモテるのは自然界でも人間界でも本当は変わらない。
だがそれらは本能に根ざした選り好みでしかなく、今日の合理主義にフィットした選択でもない。
いみじくも合理主義者であるなら、本能的な選り好みでパートナー選択するなどあってはならないことだ。人生の終わりまで結婚生活が続くという前提に基づき、それに最適なパートナーを選択するのが道理にかなっている、つまり合理的であるはずである。
では、本能と合理性、恋愛と結婚それぞれの間のギャップをどう解決すればいいのか。
ひとつの方法は、マッチングアプリや見合いや結婚相談所を利用することだろう。恋愛に依拠しないかたちで結婚のパートナーを探し、決定するこれらの方法はこのギャップを解決しているようにみえる。
ただし、この方法にも問題点はある。それは、恋愛したい本能を合理主義で無理やりに封印した場合、その封印が解けてしまったら大変なことになってしまうかもしれない点だ。特に、本当は恋愛したいと思っている人が合理主義的に強引に恋愛に封印をほどこして生きていく場合、封印が解けてしまうリスクはどこかに残る。
もうひとつの方法は、自分自身の選り好みを変えてしまうこと、できるだけ若いうちからセロトニンの出そうなパートナー・セロトニンの出るような時間を志向するように育ってしまうことだ。
もう少しだけ言い換えをさせていただくなら、恋愛に際して魅力的と感じる性質と結婚に際して好ましいとされる性質が事前に重なり合わせるよう、そうした性質を内面化してしまうことである。
そんなもの内面化できるの? と突っ込む人もいらっしゃるだろう。だが、合理主義者諸氏は自分の胸に手をあてて振り返ってみるべきである。
そもそも、その合理主義じたいが子ども時代からの環境や教育によって内面化され、社会経験の積み重ねによって強化され、しまいに当たり前すぎて疑問に思うことすらなくなった行動原理ではなかったか? 近代以前の人間のほとんどが合理主義者ではなく、もっと衝動的に生きていたことを思い出すにつけても、ある行動原理、ある志向を経験の積み重ねをとおして内面化していくことは不可能ではないはずである。少なくとも、そのように人間自身を馴致する余地はある。
馴致する余地はある、と書いたが、『Z家族』の内容を思い出すにつけても、これは現在進行形で起こっている現象ではないだろうか? と私は疑う。
合理主義とリスク回避の考え方がこれほど広く浸透している今、そこで行われる結婚、ひいては世代再生産は、恋愛に最適化した者はうまくいかず、結婚生活に最適化した者がうまくいくかたちで進行していくだろう。社会全体のトレンドとしてセロトニンの welfare が来ているこの数十年の流れを踏まえるなら、やがて日本人の性嗜好はもっと合理主義に寄ったものに変わっていき、ドーパミン頼みの恋愛はますます下火になっていくかもしれない。
そうなれば、合理主義者は恋愛と結婚のギャップに悩むことなく、ぐるっと回ってロマンティック・ラブと合理主義的配偶者選択の幸福な結婚をみるだろう。
[adrotate group="46"]
【プロフィール】
著者:熊代亨
精神科専門医。「診察室の内側の風景」とインターネットやオフ会で出会う「診察室の外側の風景」の整合性にこだわりながら、現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信中。
通称“シロクマ先生”。近著は『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(花伝社)『「若作りうつ」社会』(講談社)『認められたい』(ヴィレッジブックス)『「若者」をやめて、「大人」を始める 「成熟困難時代」をどう生きるか?』『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて』(イースト・プレス)など。
[amazonjs asin="B0CVNBNWJK" locale="JP" tmpl="Small" title="人間はどこまで家畜か 現代人の精神構造 (ハヤカワ新書)"]
twitter:@twit_shirokuma
ブログ:『シロクマの屑籠』

Photo:Zoriana Stakhniv
ワートリの29巻を読みました。
[amazonjs asin="B0FZGZ77LS" locale="JP" tmpl="Small" title="ワールドトリガー 29 (ジャンプコミックスDIGITAL)"]
最初にお断りしておきたいのですが、この記事には、先日発売された「ワールドトリガー」の29巻のネタバレが豊富に含まれます。
ワートリ読者の方で、まだ29巻をお読みでない方は、まず何も言わずに29巻をポチって、しばらく鬼リピしてからこの記事を読まれることをお勧めします。
大丈夫、特に何も言われなくても勝手に鬼リピしたくなると思います。30回くらいは。
この記事で書きたいことは、大体以下のようなことです。
・ワートリの面白さの中核って、「答え合わせ」の面白さだと思うんです
・キャラクターひとりひとりの「考察」「考え方」「他者への評価」「対話・駆け引き」の描写が解像度高過ぎて、自分のイメージとのすりあわせがはかどり過ぎる
・「こういう状況で、このキャラならどう考えるか」という「答え合わせ」と「キャラクターの掘り下げ」を無限に読めるのがあまりに楽しい
・今回特に良かったのは香取で、ワガママ言った風の隊長評価での挙動は普通に感動して泣きそうになった
・今日から「ワートリのヒロインは香取」派閥になりますよろしくお願いします
・ヒュースの麓郎に対する「教官候補」という評価も滅茶苦茶共感したし納得した
・「ストーリーの続き」だけではなく「組織としてのボーダーの未来」を自然と知りたくなる展開描写、本当凄いと思う
・閉鎖環境試験、実は香取と麓郎のために実施されたのではないか説ある
・「分かりやすい挙動や気遣いに評価が入りやすいけれど、実際に重要なのは地味な挙動、というのも共感しきり
・あと補充要員で沢村さんや雷蔵さんが戦うの本当にあまりにも熱すぎて戦闘訓練のために冷えピタ2ダース大人買いしてきた
・諏訪さんの株は巻ごとにストップ高を続けているためもはや株価ボード壊れてる
・隠岐の「小さい子撃ちにくい」という言葉がまさかここに来て回収されるとは思わなかった、本当に思わなかったんだ
・結論として最高でしたので皆さん読んでください早く続き読みたい
以上です。よろしくお願いいたします。
さて、書きたいことは最初に全部書いてしまったので、あとはざっくばらんにいきましょう。
先日「ワールドトリガー」の29巻が発売されまして、単行本派のしんざきは即本屋に飛んでいって買ってきたんですが、期待に違わず滅茶苦茶面白かったです。
皆さんご存知の通り、現在ワートリで行われているのは「遠征選抜試験」の「閉鎖環境試験」。
メンバーをシャッフルされて、普段とは違うメンバーで課題を解きつつ、特殊な戦闘シミュレーションを戦っていく回ですね。
しばらく続いた閉鎖環境試験もいよいよ大詰め。最後のシミュレーションを終えると最終日、全員のポイントが確定して、閉鎖環境試験の順位が決まります。
まず前提として、ワールドトリガーって漫画の面白さ、基本的には「答え合わせ」の面白さだと、私は思うんですよ。
ワートリの作者である葦原先生って、「短いスパンでの疑問の提示と、その回収の説得力」っていうのが滅茶苦茶上手い方だと私は思っているんです。
「これはどうなるんだ!?」という状況を提示しておいて、「そうか、こういう解決法があったか…!」とか「こういう方法で状況を打開するんだ!」という「答え」を、割と早めに提示してみせる。
その整合性とテンポの良さ、そして説得力がめちゃくちゃ高い。
例えばB級ランク戦。三雲隊-村上隊-東隊-影浦隊の四つ巴の戦いの時とか。
「鋼の剣が黒塗りされていたのは何故か」という疑問を提示しておいて、「最初から照明をいじって暗闇での戦闘をするつもりだったから」という、完璧な回答が即座に出てきましたよね。
あそこなんか象徴的な場面だったと思うんですけど、とにかく「そう来るか」のテンポが早く、しかも納得感が高い。
「考えて、予想して、納得する」のって楽しいんですよね。予想が合ってても外れてても楽しい。
別に戦闘だけの話じゃなくて、「この二人が喋ったらどんな会話になるんだ、会話成立すんのか」とか、「この二人絶対仲悪いよな、チームプレイなんて出来るのか」とか、色々考えながら読むの、私大好きなんです。
そういう意味で、29巻は「納得感のカタマリ」でした。チーム戦も煮詰まってきて、お互い同士の感覚がつかめてきたキャラクター同士が、「お互い分かっている」という前提の会話、連携をし始める。
元より、キャラクターが多い漫画ではありがちな「このキャラとこのキャラが絡んだら楽しそう!」という読者の妄想をもの凄いパターン数提示しておいて、その「答え」が「戦闘の結果、お互いの評価」という形で洪水のように提示され始めたんですよ。こんなのもう面白さの天災です。
29巻、まず「麓郎に対するヒュースのガン詰め講義」に対する周りの評価が、色々考えさせられましたし、納得感もありました。
「もっと言ってやってもいい」という風間さんの評価とか、「皆の前でアレ言っちゃうのどうなの?」と麓郎のプライドを気にする冬島さんとか、皆の評価が何故か勝手にぶっ刺さってる里見とか、もう言いそうーー!!こいつらこれ言いそうーーー!!
その上で、ヒュース自身は「上層部は麓郎を教官にするつもりなんじゃないか?」と評価しているのが、これがまためっちゃくちゃ良かった。
確かにそうなんですよ。「教える」立場に立つ時、何が難しいって「何が分からないの?」を探り出すのが一番難しいんです。
「何が分からないのかが分からない」を解決するのは、本人にとっても他者にとっても難しい。
その点、既に自分で散々「何が分からないか分からない」を経験してきた麓郎って、恐らく人に教える立場になるのに最適な人間です。
麓郎自身が「俺はなんでこのメンバーで隊長に選ばれたんだ!?」という疑問を抱いていたことに対する、最適な答え(かも知れないもの)の提示が素晴らしい。
かつ、それを知ってか知らずか、麓郎がきちんと前を向いて、「後は俺自身が決めること」という理解にたどり着いているのも滅茶苦茶良くて泣きそう。
あんなに迷いのカタマリだったのに、ヒュースの言葉を聞いてちゃんと前を向けてる……!
これ、麓郎の精神性も、ある意味並外れてると思うんですよね。
ショックをしっかり受けつつ、別に吹っ切ったわけでも開き直ったわけでもなく、けれどその上で前を向いて進める。
ちゃんとショックを背負って、その上で進める。そうそう出来ることじゃないですよ、これ。麓郎が考える「三雲と自分は同じ側」って、麓郎は意図していないだろうけど、まさにここ、「自分の弱さを受け入れられること」なんじゃないか、とすら思ったくらいです。
ワートリの特徴のひとつとして、ボーダーという「組織」がめちゃくちゃしっかり描かれている、という点があると思っています。
これは単にボーダーの構造の設定がきちんとしている、というだけの話ではなく、ボーダーがどう運営されているか、何をやろうとしているか、そこまでしっかり描写されており、しかも構成メンバーが「組織の意図を読む」というところまできちんと描いている。
そこから考えると、麓郎がC級を引き上げてどんどんB級に引き上げている未来、それも見たい。
今回の試験って、ホント「幹部たちが、ボーダーの今後をどうしていきたいのか」ということを想像させて、考えさせる試験ばかりでしたよね。「これからのボーダー」を描くなら絶対必要な展開だったと思うんですよ。
それはそうと、香取。今回の香取、本当、本当に最高だった。
特に、隊長がもった点数を各メンバーに振り分ける、「隊長評価」の場面。各チーム、「誰が誰のことをどう評価しているのか」という掘り下げが凄くって、ここはここで超面白かったんですけど。
ワートリって、基本「仕事が出来るキャラクター」「自分の立ち位置をわきまえて、それに基づいた行動が出来るキャラクター」が非常に多いんですよ。
つまり大人びたキャラが多い。中高生なのにみんなすごい大人。まあ、それはそれで読んでて気持ちいいんですけど。
そんな中でも、「わがままで言語化が下手な気分屋」という、ワートリの中では数少ない、年齢相応の立ち位置を保っていたのが香取です。
そんな香取、隊長評価で、「三雲に点数を全部ぶち込む」といった諏訪さんの言葉に、ぎゃーぎゃー反対します。
これはこれで普通というか、中高生という年齢を考慮すればむしろ皆物わかりが良すぎるくらいだけど、香取は「あたしがダメだっていってんでしょ」と凄い顔で主張した上で、100点分を自分で振り分けることになります。
ここで書いたのが、「諏訪、隠岐、宇井」の自分以外のメンバーにも振り分けつつ、結局三雲に一番多いポイントを振る内容。
これもーー。
これですね。ここ本当最高でした。
香取というキャラって、結局最初から最後まで「本心を表に出せない、天才型だけど不器用で、実は仲間に対する思いは強いキャラ」なんですよ。
ただ、それが今までは、香取隊にしか向けられていなかった。ここで、三雲の働きを実はしっかりと評価していた、という上で、更に自分をフォローしてくれていた諏訪さん、隠岐、宇井にゃんにもちゃんと感謝の点数を入れている、という。
香取というキャラクターの「面倒くさい」部分をきちんと描きつつ、閉鎖環境編を経て少しだけ周囲への評価を変えた香取の思いを、隊長評価という点で数値化してみせる。
これ、「閉鎖環境編を経て、変わらないけど少しだけ変わった香取」の描き方として、本当の本当に「完璧」な描写だと思うんですよね。素晴らしい……もう素晴らしい以外の言葉がない……
私、ワートリで一番の推しは弓場隊の帯島ユカリさんなんですが、今回だけは「ワートリのヒロインは香取なのかも知れん」と思いましたもの。
麓郎もそうなんですが、「精神的に未熟な二人」の閉鎖環境編を経ての成長、あまりに完成度が高すぎる。
今回の試験、麓郎と香取のために実施されたんじゃないかと思うくらい。
閉鎖環境編だけで改めて考えても、諏訪隊の完成度って本当凄かったですよね。
諏訪さんがきちんと「周囲にビジョンを提示して、皆を引っ張るリーダー」で、三雲のアイディア特化の特性をきちんと活かしつつ、ワガママ放題なようで案外色々考えている香取をしっかりコントロールしている。
隠岐と宇井にゃんの存在もめちゃ大きくて、この二人、どんな場面でも場の雰囲気を緩くしつつ、随所でフォローの声を入れてくれるなあと思っていたら、最初の時点で諏訪さんから「三雲に対する期待」を聞かされていたんですね。
この点も諏訪さんのド有能さが存分に発揮されていて、諏訪さんの株が巻を追うごとにストップ高を更新し続けています。株価壊れる。諏訪さんに上司になって欲しい。
あと、隠岐の「小さい子撃ちにくい」発言が、まさかこんなところでフォローされるとは思わなかった。
ボーダー園の存在も、「ボーダーの未来」を的確に表現されている描写で、これまた素晴らしいですよね。
隊長評価をどう処理するのか、というのも、隊ごとの「色」が非常に端的に表れていてとても良かったですよね。
あっさり「山分け」で落ち着く隊もあれば、隊長がきちんと説明して偏らせる隊も、「お互いがお互いに分配する」なんて隊もありました。
二宮、言ってることは「千佳とユズルは遠征狙ってるんだから頑張れ」だけなのに、「今のままじゃ無理だからな」とか厳しいプレッシャーを追加するあたり、本当ザ・二宮って感じでこれも解像度高い。
最初から最後まで1位を保ってきた水上が、心底本音そうな表情で「こんなの俺には向いてない」と言うところ、ああ普段の生駒隊ではきっともの凄くイコさんや周囲の明るさに助けられていて、だからこそ「ナンバーツーの策士」として動けていて、それを心底実感しているんだろうなあ、と感慨しきりでした。
評価の話でいうと、「地味な働きの方が評価されにくいけれど、長期間の業務で本当に必要なのはそっち」なんて話も途中で出てきましたよね。
これ、実際の仕事上でもよく問題になる話で、組織運営に対する解像度が高いなーなんて勝手に感心してました。
それはそうと。
最後の最後にぶっこまれてきた、次回の「戦闘訓練」の話。
「A級 vs B級」という構図だけでも十分、もう本当に十分熱いんですが、しかもそこで補充要員に参加するのが、雷蔵さん!クローニン!沢村さん!!林藤さん!!!
特に雷蔵なんて、以前から「元戦闘員」って情報はちょこちょこ出ていたんですが、ここに来て本当に戦うなんて思いませんでしたよ。
林藤さんが自分のチームに所属すると知った時の三輪の慌てっぷりも面白かったし、沢村さんの強者オーラも凄かった。
あと、林藤さんの立ち姿の角度がもう強者の風格しかなくって、でもこれで案外あっさり落ちちゃうのもありだなとか思っていて、もうどう描かれても面白そう。
今まで直接描かれることがなかった「A級のメンバー vs B級のメンバー」というのももう単純に楽しみだし、二宮 vs 出水のシューター最強対決とか、迅のチート能力をよく知っている三雲の攻略アイディアとか、今まで殆ど描写されていない片桐隊の活躍とか、もう楽しみな場面が多すぎる。
あと玉狛第一が普通に敵として出てくるの絶望感すごそう(小南は本気出せなそうだけど)
本誌を読みたいとも思いつつ、単行本で情報の洪水を浴びる楽しさも捨てがたいので、引き続き「続き読みたい」と身もだえしながら待つ所存なわけです。よろしくお願いします。
長々と書いてしまいました。
取り急ぎ、この記事で書きたかったのは
「ワートリの29巻面白すぎでした皆さん読んでくださいまだ既刊読んでない方は既刊も含めて読んでください損はさせません」
のひとことであり、他に書きたいことは特にありません。よろしくお願いします。
今日書きたいことはそれくらいです。
[adrotate group="46"]
【著者プロフィール】
著者名:しんざき
SE、ケーナ奏者、キャベツ太郎ソムリエ。三児の父。
レトロゲームブログ「不倒城」を2004年に開設。以下、レトロゲーム、漫画、駄菓子、育児、ダライアス外伝などについて書き綴る日々を送る。好きな敵ボスはシャコ。
ブログ:不倒城
Photo:ワールドトリガー29 (ジャンプコミックスDIGITAL)
今日は、医療の現場で見かける普通じゃない存在について紹介したい。
普通じゃないと言っても、悪い意味ではない。
逆だ。
特別に、非常に、具合が良い人達についてである。
非常に長く活動し、命の砂時計がゆっくり落ちていく人たちについて述べたい。
1.精神科には元気な高齢者も通院している
ありふれた病院でありふれた精神医療をやっていると、ありふれた患者さんと接点を持つ機会も多い。
精神医療をやっているからといって、極端な精神症状を持っている人ばかり診療しているわけではない。特に外来診療では、「うつ病が治った後にも再発せず、けれども若干の維持療法が必要な人」「睡眠導入剤を定期的にもらいに来る人」なども珍しくない。
最近は、認知症のさらに手前のMCI(Mild Cognitive Impairment)と呼ばれる状態の患者さんを診る機会も増えた。直訳すれば、「マイルドな認知機能の差しさわり」となるだろうか。
認知症の前駆状態ともいわれる状態だが、あっけなく認知症になってしまう方もいれば、しばらくそのままの状態の人、なかにはMCIと診断されたのが体調が良くなかった時点のことで、その後長らく、認知機能の差しさわりが無いようにみえる人などもいる。
一番最後に挙げたタイプの人は、身体的な健康と認知機能が繋がっているようにみえ、実はそのこと自体、脳の機能がギリギリになっていることを示している。若くて健康な人であれば、多少の身体疾患ぐらいでは認知機能はそこまで低下しない。しかし加齢によって脳の機能がギリギリのところで維持されている人は、肺炎や尿路感染症ぐらいの身体疾患によって、MCIや認知症のような機能の低下を示したりする。そういう人の頭部画像所見を確かめてみると、しばしば、脳の萎縮が進んでいたりごく小さな脳梗塞の痕跡がぱらぱら見つかったりもする。
逆に言うと、画像所見だけ見れば認知症を心配したくなる人でも、身体の調子さえ良ければ長谷川式認知機能検査でほぼ満点の認知機能を保ち、生活能力も保てている高齢者がいないわけではないのである。
とはいえ、軽度の身体疾患で認知機能が一時的に低下したり画像所見で気になる所見があったりするようなら、今は生活能力が保てていても潜在的にはリスクがあろうから、脳の機能が良い状態を維持するために人一倍気を付けていただかなければならない。と同時に、いつ認知機能が不可逆に低下しはじめても困らないよう、さまざまに先手を打っておくようお願いしたりする。
2.90歳を過ぎても血液ぴかぴか、手術にも負けない
さて、そうして通院されている人のなかには、80代や90代になっても驚くほど元気な人が一定の割合で混じっていて、えてして、そうした人は精神科外来に通院されている患者さんの既存のイメージを逸脱している。
つまり、米寿を迎える頃になっても物忘れが進まず、せん妄などの認知症の周辺症状があるわけでもない。もちろんうつ病や統合失調症や発達障害などの症状が目に付くわけでもない。通院は、公共交通機関を用いていたり、自分で自動車を運転していたりする。ご家族に連れてきてもらっている場合も、買い物や家事はすべて自力でこなしている。なかには老人仲間に病院までの足をお願いしている人もいらっしゃる。顔が広い。人望もある。「私だけお迎えが来ないねえ」などとおっしゃりながら、近所の頼まれごとを引き受けたりもしている。
で、そうした元気の良い高齢者の血液検査の結果をみせていただくと、これまた凄い。だいたい正常値、異常があったとしてもごく軽度だ。血圧が少し高い、コレステロールが少し多いといった理由で内科系の薬を処方している人ももちろんいるが、80~90代にありがちな、何種類もの錠剤やカプセルをザラザラ飲むような状況からは程遠い。1種類か2種類、薬をもらっているだけだ。
そうした高齢者は手術などへの耐性も高い。たとえば高齢者の生活能力を大きく低下させる出来事として、大腿骨頸部骨折というものが知られている。高齢者がこの骨折を経験すると、手術そのものが成功してさえ、身体機能や認知機能がガクンと落ちることが多い。ところがこの手の高齢者は、なぜか持ちこたえる。術後せん妄のような一時的な問題が出現しても、そこからきれいに立ち直ってみせる。
精神科医になってあまり時間の経っていなかった頃は、そうしたものすごく元気な80代90代の高齢者をみても「この人元気だなー」ぐらいにしか思わなかったが、長くこの仕事をやっているうちに、矍鑠という言葉を超えて、なにやら神秘をみているような気持ちを抱くようになった。「どうして、この人の年のとり方と他の人の年のとり方がこんなに違うのか?」「どうして、この人の命の砂時計だけ、ゆっくりと落ちていくのか?」と。
高齢者の年のとり方の個人差は、驚くほど大きく、ときには残酷なものである。
酒もタバコもやらず、健康増進にも気を遣っている高齢者なのに、70代ともなれば心身の衰えが進み、まもなく認知症が進行していく人がいる。かと思えば、好きなものを食べ、好きなように生きているだけなのに90代になってもピンピンしている人もいる。不思議でたまらないし、理不尽と思う人もいよう。
医療現場全体でみれば、不摂生や不健康をしている人のほうが、そうでない人よりも短命で健康寿命も短いのだけど、ここに挙げている人達はそうした範疇をこえている。90歳になってもまだビールを飲んでいたりタバコを吸っていたり、コレステロールや中性脂肪のたっぷり入った菓子や料理を頬張っていたりする。だけど人よりも年を取らず、人よりも若くすらみえるのだ。
3.そういう高齢者の特徴は?
そうした高齢者たちは、いったいどんな特徴を持っているか。
まあ、みんなバラバラなのだけど、それでも幾つかの特徴は挙げられる気がするので挙げてみる。
ひとつには、よく笑っている。いつもニコニコ、それかガハハとよく笑う。笑顔が自然で、それがよく似合っている。精神医学っぽい表現をするなら発揚気質の人が多いだろうか? 考え方もどこか楽観的でポジティブで、クヨクヨとしない。悩むことがないわけではないが、その悩み方すらどこかポジティブだ。
もうひとつには、役割を持っている。地元の老人同士の付き合いのハブみたいな人物であることもあれば、地元の企業でしぶとく働き続けている場合もある。農業の担い手や介護の担い手であることも多い。必然的に、社交の機会、人と話す機会を持ち続けていて、なんらかの現役選手でもある。そして役割を持つだけでなく、誰かに助けられていたりもする。リタイアし、天涯孤独で、それでもこうしたスーパー高齢者にあてはまる例は私はまだ見たことがない。独居している場合でも、たいてい近くに親族が暮らしているか、共助的な繋がりに属している。
みっつめは、遠慮なく食べていること、だろうか。こうした高齢者の食生活を聴いてまわると、意外と不健康である。塩分の多い食事や糖質やコレステロールの多い食事を改めようともせず、それが健康の秘訣だと思っているふしさえある。とはいえ、ラーメンを毎日食べるとか、大酒を飲み続けるといった、決定的な不健康まではやらないし、体型は中肉中背である。とはいえ、今日模範的とされる高齢者の食事をあまり意識していないのも、また事実だ。漬物を毎日のように食べたり、ビフテキやアイスクリームやクリームパンを食べていたりする。
4.彼らの暮らしぶりは参考にならない
……と挙げてはみたが、正直、よくわからない。さきに挙げた3つの条件が、命の砂時計がゆっくり落ちていく必要条件や十分条件だとはまったく思えない。というより、食生活に関しては一般に薦められているものとしばしば違っている。せいぜい強調できそうなのは、人との繋がりのなかで楽しそうに生きていること、そのおかげで張り合いのある生活を続けている点だろうか。
私としては、そうした高齢者の生活習慣を真似てあやかりたい、という気持ちにはなれない。真似てなんとかなるとは到底思えないからだ。
それよりも、そんな生活を続けていてもなぜか動脈硬化が進まず、手術や入院を経験しても認知機能が低下せず、大半の高齢者よりもずっとゆっくりと年を取っていく彼らの生命力を賛美し、畏怖したい気持ちだ。特別に健康が弱い人や寿命の短い人が存在する一方で、特別に健康が強い人や寿命の長い人が存在するのも、道理ではある。そして研究対象としては重要な人々だろう。
医療現場に長くいると、そういうかたちで世の理不尽、世の不平等、いや、世のことわりを見ることがあったりする。命というのは、まだまだよくわからない。
[adrotate group="46"]
【プロフィール】
著者:熊代亨
精神科専門医。「診察室の内側の風景」とインターネットやオフ会で出会う「診察室の外側の風景」の整合性にこだわりながら、現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信中。
通称“シロクマ先生”。近著は『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(花伝社)『「若作りうつ」社会』(講談社)『認められたい』(ヴィレッジブックス)『「若者」をやめて、「大人」を始める 「成熟困難時代」をどう生きるか?』『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて』(イースト・プレス)など。
[amazonjs asin="B0CVNBNWJK" locale="JP" tmpl="Small" title="人間はどこまで家畜か 現代人の精神構造 (ハヤカワ新書)"]
twitter:@twit_shirokuma
ブログ:『シロクマの屑籠』

Photo:Matt Bennett
「すごいですね、私ぜんぜん勉強なんかしませんでした!」
先日、会社経営者の友人と飲んでいた時のこと、とても不思議な話を聞くことがあった。
お互いに、社会人になり最初に勤めたのは、大手証券会社だ。
営業マンとしての苦労を分かち合えるだろうと、こんな話を振る。
「営業マンになって最初の半年、どれだけ銘柄を勉強してお客さんにオススメしても、全く買ってもらえなかったんですよね…」
すると返ってきたのが、冒頭の言葉である。
「すごいですね、私ぜんぜん勉強なんかしませんでした!」
「じゃあやっぱり、営業成績も悪かったんですよね?」
「いえ、同期で1番になったこともあります」
「はあぁぁぁ・・・???」
平成初期といえば、株式投資はまだまだバクチのようなものと捉えられていた時代だ。
インフレ対策や資産形成といっても全く響かず、まして長期分散投資の有効性を頑張って説明しても、鼻で笑われてしまう。株式投資に興味があるのは、ごく一部のお金持ちでしかない。
そしてそういったセミプロのような投資家のもとに営業に行くと、いつも決まってこのように問われた。
「なんかおもろい情報あるか?」
「儲かる銘柄、なんかあるか?納得できたら買ってもええぞ」
もう随分昔のことなので記憶が曖昧だが、私は当時、三菱重工業や東京エレクトロン株について、一定の周期性を分析していた記憶がある。
そのためその周期を説明し、売り時、買い時などを説明するのだが、返ってくるのはいつも同じ答えだ。
「おもんない。それくらい知ってる、帰れ」
そんな思い出話をしたうえで、改めて彼に聞いた。
「銘柄や相場の勉強もせずに、どうやってトップ営業になれたんですか?」
すると彼から、全く予想もしていなかった思いがけない答えが返って来る。
「帰ろう、帰ればまた来られるから」
話は変わるがずいぶんと昔のこと。大手メーカーに就職した友人と飲んでいる時に、こんな相談を受けたことがある。
「聞いてくれ、俺…。営業から経理にまわされたねん」
「へ…、お前が?なんでやねん」
「そうやろ?ぶっちゃけ俺、簿記3級すら持ってへんのやぞ」
コミュニケーション能力も高く世話好きで、絵に書いたような営業向きの男だ。
一体なぜそんな事になってしまったのか。
「わからへん…。ただ、ウチの会社は基本的にこういう部門をまたぐ異動はないねん。営業から経理への異動が前代未聞やし、短期でまた営業に戻るような異動は、まあ期待できへん」
「そうか…。まあそういうこともあるやろう。で、経理での仕事は順調なんか?」
「順調なわけないやろ。損益計算書とか貸借対照表の基本くらいわかるけど、どの伝票をどの科目に仕分けるとか、こんなもん職人の世界やんけ」
そして彼はいつも、残業時間の上限まで職場に残り、土日も闇出勤して必死に仕事を消化しているという。
心身ともにボロボロの状況であることは、見た目からもあきらかだ。
「とてもいい状態と思えへんけど、今のまま仕事続けるんか?」
「そりゃそうやろ、まだ就職して5年やぞ。短期間で逃げるように転職したらキャリアに傷がつくし、キャリアダウンの会社にしか再就職できへんやんけ」
「それ、大和証券から数年で逃げた俺への嫌味か?(笑)それはともかくとして、なら経理で生きていくことにするんか?」
すると彼は、様子を見る、もしかしたら何かの間違いですぐに営業に戻れるかもしれないというような、優柔不断で根拠のない希望的観測を語る。
現実から目を逸らして、“宝くじ”を心の拠り所にしてしまっている状態だ。
「そうか、わかった。参考になるかわからへんけど、少し俺の話を聞いてくれ。俺はお前と違って、すぐに逃げる人間や。その“逃げの哲学”についてや」
「お前が?なにかから逃げるようなヤツに思えへんのやけど」
「お前の言葉を借りるなら、大和証券から数年で逃げてるやんけ(笑)まあ聞け、零戦って知ってるよな?」
「それくらい知ってるわ。いきなりなんやねん」
そこで私は、零戦は太平洋戦争の開戦当初、米軍がその戦闘報告を信じないほどの無敵の強さを発揮したこと。
現実が明らかになると、日本軍のパイロットの技量の高さ、零戦の運動性能の高さを正しく認識し、零戦と遭遇したらただちに逃げるよう命じたこと。
そして米軍は、わずかな期間で新たな戦い方とそれに適した戦闘機を開発し、程なくして零戦は型落ちになってしまったことなどを説明した。
「日本海軍のパイロットの技量はもうな、神業的に凄まじかったねん。ドッグファイト、つまり相手のケツを取って撃ち落とす戦い方では、米軍は勝てへんと理解したんや。その時、どうやって米軍は戦況をひっくり返したと思う?」
「軍事マニアや無いし、そこまで知らん」
「自軍が劣る土俵で戦わんかったんや。マニアックな事を説明してもしゃーないんで、すごく雑に言うぞ」
そう前置きし、米軍はドッグファイトのような高度な技量が要求される戦い方を放棄し、技量の劣るパイロットにも習得が容易なサッチ・ウィーブと呼ばれる戦法に切り替えたこと。
さらに一撃離脱(一発撃って逃げる)という戦い方も取り入れたことなどを、大まかに説明する。
「それからな、これが大事なんや。シャアの名セリフやないけど、零戦って『あたらなければどうということはない』やねん。逆に言えば、一発あてられたらすぐに墜とされてしもた」
「…米軍は?」
「『あてられても墜ちなければいい』や。クッソ頑丈な機体を投入した。その結果、いくら技量に勝る日本軍のパイロットでも、どんどん削られていった。すごく雑な説明で申し訳ないけど、お前はこの構図から何を学ぶ?」
「属人性の排除か?」
「大正解。けど、もうひとつあるぞ?」
「勝てへんフィールドで戦わへんってことか…」
「その通りや。だから俺は、自分が勝てへんと思ったフィールドからはすぐに逃げる。俺なりの“逃げの哲学”や。意地を張って死んでたまるかい」
そしてその話の延長で、友人は今まさに、強みを生かせる戦い方を封じられている状態にあること。
勝ちの見えないフィールドでストレスMAXの中、どんどん心身を削られていること。
その環境に適応して新しい能力の習得を目指すのか、それとも“いったん逃げる”のかを選択するターニングポイントにあるのではないかと、助言した。
「なんかわかった気がする、少し俺なりに考えてみるわ。“逃げる”って恥ずかしいことやないんやな」
「当たり前やろ。“逃げるが勝ち”って、本当に基本的な兵法やぞ。『帰ろう、帰ればまた来られるから』ってやつや」
「…なんやそれ??」
「なんでもない。でも、少しは歴史を勉強せえ」
“何もない”という強み
話は冒頭の、大手証券会社でトップ営業になった友人についてだ。
「銘柄や相場の勉強もせずに、どうやってトップ営業になれたんですか?」
それに対して、彼は何と言ったのか。
「買いたい銘柄があったら教えて下さい!その理由も教えて下さい!」
彼は営業先に行くと、いつも決まってそう言っていたと説明した。
「えええええ??お客さんのところに行って、何を買いたいのか、その理由も教えろと言ったのですか?」
「はい、これが意外にウケたんですよ(笑)」
「いえいえいえ、いくら新人営業とはいえ、プロとしてお客さんの前に立つわけじゃないですか。それで許されたのですか?」
すると彼は、人たらしの笑顔をさらにニコリとさせ、こんな事をいう。
「桃野さん、新人の武器ってなんだと思います?」
「証券1年生、新人の武器…。今から思うとなにもないですね。全くありません」
「はい、知識や経験など何一つありません。20年、30年の投資家に付け焼き刃の知識で買ってもらおうとするなんて、無茶ですよ」
「…確かに」
「だけど、“かわいさと素直さ”だけは許されるんです。1年生の特権です。なんでつかわなかったんですか?」
何から何まで納得だ。しかも彼のロジックには、さらに深い含蓄が含まれている。
1987年に出版され、世界20カ国以上で発売された営業の名著、『SPIN式販売戦略』という本がある。
おそらく昭和後期や平成初期に営業職にあった人であれば一度は手に取ったことがあるであろう、営業のバイブルのような本だ。
多くの学びがある一冊だが、そのエッセンスの一つをまとめると、以下のようになる。
「人は営業から商品を勧められたら反発し、買わない理由を探す。しかし自分から買う理由を口に出したら、意地でも買おうとする」
そう、友人はまさに1年生の“かわいさと素直さ”で相手の懐に入ると、「今買うべきもの」を相手に語らせたということだ。
すると相手は、「あれ?なんで俺、まだ買ってないんだろう」という心理状態になり、直ぐに注文を出してくれる。
天性の人たらしである彼はまさにこの“強みと真理”を生かし、トップ営業に昇りつめたということだ。
そして話は、営業から経理に“飛ばされた”友人についてだ。
彼は明らかに、自分に強みがないフィールドで自縄自縛し、勝ち目の無いフィールドと方法で“勝ち”を目指そうとしていた。
そう、まるでデキの悪い1年生だった時の、私のように。
その無茶さを悟った彼は程なくして転職し、新天地で活躍するのだが、本当に良かったと思う。
誰にでも参考になる話などと言うつもりは、全く無い。
しかし勝ち目のないフィールドで戦わないという選択は、本当に“逃げる”ことなのか。
私は、勇気ある勝ち方の一つだと思っている。
[adrotate group="46"]
【プロフィール】
桃野泰徳
大学卒業後、大和證券に勤務。
中堅メーカーなどでCFOを歴任し独立。
主な著書
『なぜこんな人が上司なのか』(新潮新書)
『自衛隊の最高幹部はどのように選ばれるのか』(週刊東洋経済)
など
30回以上転職して、最後には起業して会社を上場させた経営者がいたような…。
誰でしたっけ?
X(旧Twitter) :@ momod1997
facebook :桃野泰徳
Photo:Sasha Freemind
トイレに行く時間もない日々をすごしている
ぼくには時間がない。
本当は、こんな文章を書いているヒマもない。
仕事はいくらやっても減らないし、子どもたちはいくら大きくなっても新たな問題が勃発するし、それ以外の家事、両親の介護、ついでに自分の腰痛の治療…とにかく、やらないといけないことがたくさんあって、いつも時間がない、時間がない、と嘆きながら暮らしている。
なんでこんなに時間がないんだろうかとふと考えるに、要はスキマがないのだと思った。
オンライン会議の予定が次から次に入っていて、トイレに行く時間がない、という経験をしたことがあるのはぼくだけではないと思う。
あるいは訪問先での話が長くなってしまって、建物を出るやいなやイヤホンをつけて、移動しながら次のオンライン会議に入る…なんてこともしょっちゅうある。
そんなこんなで仕事がひと段落して、さあ帰宅して家の用事をしなくては、と電車に乗り込む。
そうだ、そこで本当は、ふう…と心を落ち着かせて、車窓の先の移り行く景色でも眺めていればいいのだ。
なのに、ぼくはスマホを手にして今日のニュースやら何やらを見始めてしまう。
色々と心をざわざわとさせる情報が入ってきて、ぼくはあれこれ考えてしまって、休むヒマがない。
帰宅してからは子どもたちの対応をして、それ以外の家の用事をして、そのスキマの時間で夕方までに飛んできている色々なメッセージを読んだり返事したりして、早く風呂に入れとか、早く寝ろとか子どもたちにギャーギャー言ってる自分が嫌になったりしているうちに一瞬で時はすぎていく。
ようやく家族みんなが寝て、静かになって、さあようやく昼間にできなかった企画ができるぞと思ってPCを開きなおすと、また色々な通知が来ていて、それを見ていたら‥‥ほら、一日はもうおしまいだ。
自分以外の誰かのために身動きが取れなくなっている
いつからこんなに時間がないと感じるようになったのだろう。
ひとつは、家族ができたこと、これは大きいだろう。
結婚するということは自分以外の人のことについて考える時間を使う、ということなのだと今さら思う。
それでも二人だけの時は、結婚相手のことだけを考えればいいけれども、子どもが増えると状況は変わる。
ぼくはいつも自分以外の三人の人間のことを考え続けることになる。
それに加えて仕事に関する人たちや、そのどちらでもない人たちのことも考えていると、そりゃあ時間がないと感じるだろう。
そしてもうひとつは、やっぱりスマホだったりPCだったりのせいだと思う。
いや、端末のせいではなく、端末を通してずっと世界とつながり続けてしまうせい、と言ったほうが近いか。
今や、寝る時間以外、ずっと自分以外の誰か(それも一度に複数の「誰か」たちと)とつながりつづけている。
本当に、トイレに行く時間もないほど。
そしてその誰かのことを考え続けているのである。
それはオンライン会議の相手かもしれないし、急にチャットを飛ばしてきた人かもしれないし、Facebookに久しぶりに投稿した古い友人かもしれないし、その投稿を読み終えたあとにおすすめ記事として案内されたのでつい読んでしまったニュースで報じられていた海外の国の人々かもしれない。
ああ!!
ぼくはなんとたくさんの人たちと勝手につながり、勝手にモヤモヤし、勝手に時間を失っていっているのだろう!!
まさに誘蛾灯に群がる虫たちのように、スマホとPCを通した人工の光に吸い寄せられて、身動きが取れなくなっているのである。
目の前の現実だけがすべてだった思春期
それじゃ、スマホやPCがなかった頃はどうだったんだろう。
ぼくがPCを触るようになったのは周りよりも遅くて、大学生になってからだった。
スマホというか携帯電話も大学生になってからだ。
ただ高校生の頃もポケベルは持っていたし、家の固定電話を使ってよく電話はしていた。
……となると、そういったものとほとんどつながりがなかったのは、中学生の頃だ。
たしかにあの頃、時間はたっぷりとあった。
生徒会とラグビー部に所属していて忙しかったはずだし、中三になってからは猛烈に受験勉強をしていた。
なのに、なぜか大量の、消費しきれないぐらいの時間があった。
生徒会の部屋で、会長が吹くハーモニカに合わせて流行りの歌を熱唱していたこととか、
部活でひたすらキツいトレーニングをさせられているあいだじゅう、涼しげにラケットを揺らしているバドミントン部の女子たちの様子をチラチラと見続けていたこととか、
学校が終わってから仲のいい同級生たちとマンションの自転車置き場でずっとしゃべっていたこととか、
とにかく、目の前のことにだけ夢中になっていた(バドミントン部の女子たちを見ながらもトレーニングも必死にはやっていた)ことばかり思い出す。
あの頃はよかった、なんて話をしたいわけではない。
だいたい、当時ぼくが通っていた中学校は不良だらけで、入学した日にトイレに入ったら、不良たちが文字通りのヤンキー座りをしてタバコを吸っていて、便器も破壊されているものばかりだったのを鮮明に覚えている。
同級生たちもそれに影響されて、どんどん不良化していって、もうめちゃくちゃな中学校生活だった。
はっきり言って、消したい記憶ですらある。
それでも(それだからこそかもしれないが)時間はたっぷりあった。
なぜなら、何度も言うけれど、本当の意味での目の前のことだけが現実だったからだ。
その現実に向き合い続ける時間が、いくらでもあったのだ。
ぼくは自分にとっての「現実」を見失っている
今のぼくは、目の前以外のことばかり考えている。
実際にはこの場にいない東京の人たちと打ち合わせをし、この場にはいない顧客のことについて企画を考え、この場にいない株主のために利益を上げ、この場にいない見知らぬ誰かが起こした事件に対して腹を立てたりしている。
ひょっとしたら、昨今の働き方改革の成果として、少しは自由になる時間が増えているかもしれない。
それでもぼくが「時間がない」と感じるのは、ひょっとしたら、本当の意味での「目の前」のことに集中できていないからじゃないだろうか。
目の前の誰かと、じっくりと話ができただろうか。
その人の表情や様子や、そこにある感情の揺れや、言葉にはできないものを感じることはできただろうか。
あるいは電車に乗り込んだ時、そこに居合わせた人たちのことを覚えているだろうか。
昔はよく電車の中で人間観察をしていたものだ。
この人はどんな職業の人なんだろうかとか、何をするためにどこへ向かっているのだろうかとか、色々と妄想しながら観察をしていた。
今はぼくは電車の中でずっとスマホを触っている。
スマホを通して、ここではない、どこかの人たちとつながっては離れ、つながってはあっちへ行き、ずっとフラフラとさまよい続けている。
ぼくは今、いったいどこにいるのだろう。
ぼくにとっての現実とは何なのだろう。
「時間がない」と感じるのは命を完全燃焼できていないから
こんなことを言っているけど、ぼくはコロナ禍以降の急速なオンラインによるコミュニケーション方法の浸透については、すごくポジティブに取り組んでいた。
Zoomに慣れていない人たち同士でも手軽に参加できるワークショップの手法を開発したり、外部からゲストを招いての全社でのウェビナーもいち早く開催したりしていた。
ただ、あの時、Zoomの画面に現れる人々の映像は、ちゃんと「目の前の」できごとだったのである。
お互いに、なんとか連絡を取りたいし、情報を交換したいし、仕事もしたい。ちゃんと本気でお互いを求めていた。
今のZoomからはそういう切実な情念が失われてしまった。
あって当たり前、使えて当たり前、なんならいつでもどこでも会議ができてしまうせいで、人々の自由を奪い、トイレに行くスキマも与えない極悪非道の拷問ツールとなってしまった。
ここまで長々と書いてきて、なるほどなあと思ったのだけれど、結局はそこなのだ。
何をもってぼくは「時間がない」と思うのか、あるいは「時間はたっぷりとある」と感じるのか。
それは、そこに「限られた自分の命を使っている」と実感できるかどうかなのだ。
どれだけ使える時間があっても、あっちこっちに集中力が分散されてしまって、今日一日、一体何ができたのだろう、と思う日は「時間がない」日だ。
一方で、目の前のことにじっくりと取り組んで、ああでもないこうでもないと試行錯誤し続けたり、あるいは逆にその問題を解決するべく奔走し続けたりした日は、どうも満足のいく日だったなと感じることが多いように思う。
完全燃焼することができた日、と言うこともできるだろう。
ぼくは、今日という一日分の命を完全燃焼させることができただろうか。
そんな中年の切ない想いを成就させるのに、どうもスマホやPCによる過剰な情報干渉が妨げになっているような気がしてしかたがない。
それらに多大なる恩恵を受けてきたことは承知の上で言うけれども。
おまけに、こんな文章を書くことで、そんな妨害施策に加担していることも承知の上で言うけれども。
[adrotate group="46"]
【著者プロフィール】
著者:いぬじん
プロフィールを書こうとして手が止まった。
元コピーライター、関西在住、サラリーマンをしながら、法人の運営や経営者の顧問をしたり…などと書こうと思ったのだが、そういうことにとらわれずに自由に生きるというのが、今ぼくが一番大事にしたいことなのかもしれない。
だけど「自由人」とか書くと、かなり違うような気もして。
プロフィールって、むずかしい。
ブログ:犬だって言いたいことがあるのだ。
Photo by:Kevin Ku
おれはかつてでかいペットボトルで焼酎を買う人間の末路になった人間である。
それでも減酒にチャレンジした。
減酒にチャレンジした挙げ句、また焼酎の大量飲酒にもどった。減酒に失敗したアルコール依存症の末路だ。
ただ、おれの中で減酒の意識は死んでいなかった。25度が多い焼酎のなかで、20度のものを飲むようにしていた。
……だめである。
が、そんなおれも禁酒に成功した。世の中に「わかっちゃいるけどやめられねえ」という人も多いだろう。そういう人のための一助になれば幸いである。
その1 がんになる
おれが禁酒の方法として実践しているものから紹介しよう。がんになる、これである。
おれはNETという希少がんになった。そして酒をやめている。「がんになった人間が酒をやめるのは当たり前だろう」という声も聞こえてきそうだ。
たが、待ってほしい。
おれは希少がんがほぼ確定しながらも、たくさんの検査を受けて最後の通告を受けるまでどうしていたか。
不安を打ち消すために酒を飲みまくっていたのである。不安、心配、恐怖、これらを打ち消すには酒しかなかった。
考えれば考えるほど精神状態が悪くなり、追い詰められるようだった。そこで、酒が効いた。酒を飲めば余計なことは考えなくて済む。
不安がまったくなくなるとは言わないが、大幅に軽減された。がんの不安に酒は効く。
いや、ちょっと、待ってほしい。
これでは逆効果ではないか。いや、俺が言いたいのはその先である。
CT、MRI、PET/CTなど、生まれて初めての気が滅入るほど疲れる検査の先のことである。
NET G1、一時的人工肛門造設確定のときのことである。手術可能か最後の確認で、初期に検査しなかった血液の何かを調べたときのことだ。肝臓の数値のみ悪い結果表を表示させて、外科の医師がこう言ったのだ。
「これ以上数値が悪くなると手術できませんよ。ギリギリですからね」
これだけである。懇々と説得されたわけではない。具体的に危険な数値を説明されたわけでもない。この一言だ。
「あれ、ちょっとしたおどしかな?」と思わなかったわけでもない。正直言ってそうだ。
だが、本当に手術できなくなったらどうなるのだ。
最初のクリニックでの大腸内視鏡検査の結果(癌疑い)から、その当日に市大病院に電話予約して、すべて最速でやってここまできた。病院が提案する最速の日程通りにすべてこなしてきた。
検査はおれを疲弊させたし、費用も馬鹿にならなかった。それがすべてリセットされたらどうなるのだ。延期になって最初からになったらどうなる。当然、その間にもゆっくりながら進行(おれの場合はそうだ)もするだろう。
それはもう、失うものが大きすぎる。だから、おれはそれを聞いたその日から、酒を一滴も飲んでいない。
週末だからとか、人とあって夜においしいものを食べるからとか、そういうのも全部なしだ。ノン・アルコール。これである。
その2 風邪をひいた日に禁酒を始める
先ほどの章がまったく役に立たないであろうことは認める。
ただ、医師がアル中の患者にとどめをさせる一言かもしれないので、お医者さんは頭の片隅に置いといたらいいかもしれない。世の中の酒飲みは医者より酒を愛している。まあ、ちょっと自分の病気話をしたかっただけだ。
というわけで、今度は役に立つかもしれないことを書こう。
酒をやめはじめるのは、風邪をひいた日がよい。これである。
先ほど、おれは医者に一言いわれたと書いたが、偶然その日、おれは風邪気味だった。いや、風邪を引いていたと言っていい。
病院では大丈夫だったが、アパートに帰ってからひどく咳が出た。頻度は少ないが、なにかこう、とても嫌な感じの咳だ。そして、咳をするごとに頭が痛くなってきた。要するに、夜にはかなり体調が悪くなっていた。
そんな日は、いくらアル中でも酒は飲まない。……とも言い切れない。しかし、おれはたまたま「酒をやめなくてはならないかも?」と思っていた。
じゃあ、とりあえず今夜は飲まないでおくか、となった。
「風邪をひいて体調が悪いときに酒を飲まないなんて当たり前じゃないか」という声も聞こえてきそうである。
でも、当たり前じゃないんだな。飲みますよ、そりゃ、普段の風邪なら。なんなら酒の効果でつらいのが飛んでいくかもしれないとか思いながら、ついつい飲んでしまう。それが悪い酒飲みというものだ。
だが、やはりそこには多少の無理がある。本当に風邪のつらさが忘れられるなんてことはない。
なにやら気分がよくなくなる。それはわかっている。わかっているけどやめられねえ勢でも、体調が良いときに飲む酒と、体調が悪いときに飲む酒の優劣くらいはわかる。もちろん、元気なときの方がうまい。普通のとき……も、うまい。
酒をやめるにあたって、酒がうまいのはよくない。うまいものを手放すのはつらい。つらいことはやりにくい。
逆に酒がまずいなならどうだろう。まずいものを手放すのはつらくない。むしろいい感じだ。
つまりは、「ああ、今日も仕事がんばったな。こんなときは一杯飲みたいな。ああ、でも自分は禁酒を始めるんだった。今日から飲めない……」
というタイミングで禁酒を始めてはならない。そんな日はうまい酒を飲め。そんな日からやめてもおまえの意思は続かない。
だが、「今日は鼻が詰まっているし、咳も出る。なにか頭も痛いし、熱っぽいぞ」というときがチャンスだ。悪ければ悪いほどいい。
そういう、酒を飲むのに適していない日に、酒をやめ始めるのだ。
そういう体調で、「いま酒を飲んでもいい気分になれない。むしろ悪い気分になる」とあえて強く思い、気分の悪い、まずい酒で頭の中をいっぱいにさせるのがいい。悪く、悪く想像を膨らませろ。
どうせそんな日の翌日も体調が悪いのだから、「今日飲んでもまずいだろう。気分も悪くなるのだろう。昨日と一緒だ」と思うことである。そうして一日、二日、三日……と過ぎていくと、気づいたらおまえは酒を飲んでいない。
どうだろうか。おれのように時間的な制約が特にない禁酒であれば、時機が来るのを待って始めてもいい。落ち着いた釣り人のように、魚がかかるのを待てばいい。え? 自分はめったに風邪なんかひかない健康体です? 知るかそんなの。
その3 ゼロコーラを飲む
「害の大きな依存をより害の少ない依存に置き換えていく」というのは依存症対策の基本的な話だろう。説明はいらないと思う。
おれはかつて、酒を低アルコール飲料に置き換え、さらに炭酸水やノンアルコール・ビールなどへ置き換えることを試みた。失敗に終わったが。合う人には合うので試す価値はある。
が、このたびもっとよい酒の代替品を見つけたので報告したい。かつて試したノンアルコール・ビールやノンアルコール・缶チューハイなどにはない中毒性がそれにはあった。
「それ」とはなにか。ゼロ・コーラである。
ノンシュガー、ノンカロリーのコーラを、ここではとりあえず「ゼロ・コーラ」と呼ぶ。
おれがたまたま例の禁酒開始日に、たまたま100円ローソンで見つけて、なんとなく酒の代わりになるかも? と思って買ったのがゼロ・コーラだった。具体的な銘柄を言えば「ペプシ〈生〉 BIG ZERO 600mlペット」、これである。
このところコーラが高い。具体的には普通のコカ・コーラが定価(自販機、コンビニなど)で500ml170円になった。
これは高い。ちょっとコーラを飲もうという気にはなれない。しかし、ペプシの生はなぜか安い。600mlなのに安い。悪くない。
そして、悪くないのはコーラの持つ中毒性、これである。いろいろな味付き炭酸飲料水があるなかでも、「コーラ」として独自の存在感を放っているだけはある。長い歴史があるだけはある。コーラには特別ななにかがある。おれはゼロ・コーラを飲み始めてそう感じた。
炭酸の刺激に、ジャンキーな甘み、独特の香り。無味無臭の炭酸水にはないものがある。ノンアルコール・ビールにもないものがある。なんなら、ノンアルコール・ビールよりも身体に悪そうな感じすらする。
……そこがよい。「なにか身体に悪いものを飲んでいるのではないか?」という感じが、酒を飲むときに似ている。そこがいい。逆に不健康そうなのがいい。われわれは毒を飲んでいたのだ。より軽い毒を飲むだけではないか。
ところがどうだ、ゼロ・コーラはカロリー0、糖質0、これはもう水を飲んでいるようなものではないか。水が酒の代わりになる。奇跡のような話だ。
え、なに、人工甘味料のリスク? 糖尿病になる? 脳卒中? 心筋梗塞? がん? 知った話か。
べつにそれらのリスクにきちんとしたエビデンスがあろうが、おれはこう言い返してやろう。「そのリスクはアルコールを大量摂取するよりも大きいのか?」と。あるいは、こうも言えよう。「砂糖を大量摂取するより害が大きいのか?」と。
人工甘味料<砂糖<アルコールの順に害が大きいはずだ。そりゃあまあ量にもよるという話になる。
話になるが、おれは話にならないほど大量のアルコールを摂取していたのである。そこと比べなくてはならない。大きな害をいきなりゼロにするのはむずかしい。だが、大きな害をとりあえず小さな害にするのは、ゼロにするよりは簡単だ。
なぜ、あえて害を求めるのか。それもまた人間だからだ。そうとしか言えない。そしてまた、がんの手術が受けられないという理由によって害を減らそうとあがく、これも人間だろう。
そんな人間にとって、ゼロ・コーラを害だという人がいるならば、むしろ歓迎すべきだ。酒に似ていると言ってくれているのだから。
そして、そういう目的でゼロ・コーラを飲むものは、ゼロ・コーラをそういう目で見るべきだ。
仕事終わりにはコーラの炭酸と甘さを思い浮かべよう。もう、コーラのことで頭がいっぱいだ。部屋にたどり着いたら、とりあえずグラスに氷を入れよう。すぐにゼロ・コーラを注ごう。
ただ、氷に直接コーラを触れさせないようにしよう。泡が多く出すぎる。いや、そんなことも気にしなくていい。とにかくゼロ・コーラをグビグビ飲もう。炭酸ですっきりする。甘ったるくて身体に悪い感じがする。いくらでも飲もう。いくら飲んでもゼロ・カロリーだ。
おかわりもいいぞ!
……というわけで、おれは酒を飲むためのおつまみにゼロ・コーラ、ペプシの600mlをおかわりする。
二本目で1.2リットル。リットルいけるぞ。まだものたりないか? だったらもう一本いってやれ、どうせ0カロリーだ。1.8リットル。ここまでいくと、もう酔ったときと同じように頭がへんになっている。そしてお腹は膨れて、「ちょっと酒を飲もう」という気にもならない。
あとは飯を食え。飯とコーラが合うとはさすがに主張しない。まあ、合う食べ物もあるだろうが。ピザとか。
が、一応、ここでおれは警告しておく。ゼロ・コーラにもある物質が含まれている。カフェイン、これである。ペプシの生では、100mlあたり約10mgとある。そこそこの量だ。これが、二杯、そして三杯となるとどうなるか。カフェイン180mg。
それはもう、夜になってエナジードリンクを一本飲むのと変わらない。寝られなくなる可能性はある。まあそのあたりは各自勝手に工夫してくれ。一本だけ単なる炭酸水にするという手もある。
あるいは、おれがペプシの生を箱買い(そのあとコカ・コーラ・ゼロも箱買いした)する前に気づかなかったが、コカ・コーラにはノンカフェイン・コーラがある。700mlのペットボトルで売っている。コンビニやスーパーでは見かけないので知らなかった。ノンカフェイン、これは無敵なのでは?
が、無敵かどうかはわからない。カフェインにも依存性が存在する。
あるいは、「ほかのノンアルコール飲料にはないものがコーラにはある」と言っていたときの「もの」とは、カフェインそのものかもしれない。
ただのカフェイン中毒。しかし、やはりこう言うことができるだろう。「アルコールとカフェイン、どちらにより大きな害があるか?」と。もちろん、ノンカフェインのコーラも試してみるつもりではある。
それでおれは一生禁酒するの?
このようにして、おれは山から降りてきておまえたちに禁酒の方法を告げた。禁酒をしたいビジネス・パーソンをはげました。しかし、おれ、おれ自身は問題の手術を終えたあとも禁酒を続けるのだろうか?
あ、そういえば、手術前の最後の診察で、血液検査もなければ、医師からの酒の話も一切なかったな……。
まあいい、手術までは飲まないことにした。おれはゼロ・コーラをごくごく飲む。そう決めた。コーラ・ジャンキーだ。では、手術が終わったらどうする? ……どうするのだろう。
とりあえずおれはストーマ(人工肛門)付きの人間(オストメイト)に一時的になることは決まっている。オストメイトの飲食は基本的に自由だ。とはいえ、やはり食品によって向き不向きもある。それがおれにはよくわかっていない。
アルコールによってストーマに悪影響があるなら避けたい。おれはストーマのトラブルをおそらくは必要以上に恐れているので、なかなか酒を飲む勇気が出ないかもしれない。
ちなみに、炭酸を飲むとガスがすぐ出るとかいうので、コーラもどうなのかわからない。まあ、だれもいない部屋で一人ガスを出す分には問題ないが。
ストーマを閉鎖したあとはどうだろう。閉鎖したあとも排便などに障害が起こると言われている。酒を飲んだらどうなるのか。頻便になるがさらに増加する。それも怖い。
それらを理由におれは酒を飲まなくなってしまうのか? ちょっとわからない。
正直、おれは酒を飲みたい。飲みたいが、「もうがまんできない!」というような強い渇望は感じない。脳に溜まったストレスが洗い流されなくて、不機嫌がつづいているくらいだ。酒を飲まなくなって一ヶ月、なにか体調がよくなったという気はいっさいしない。
すぐにおれはでかい焼酎の紙パックを買う人間に戻るかもしれないし、戻らないかもしれない。
飲みかけの焼酎は部屋のそこらに転がっている。高級なシングルモルトウイスキーもある。いまのところ、それらを捨てる気はない。まったく、ない。それだけである。
[adrotate group="46"]
【著者プロフィール】
黄金頭
横浜市中区在住、そして勤務の低賃金DTP労働者。『関内関外日記』というブログをいくらか長く書いている。
趣味は競馬、好きな球団はカープ。名前の由来はすばらしいサラブレッドから。
双極性障害II型。
ブログ:関内関外日記
Twitter:黄金頭
Photo by :Stanimir Filipov
「コミュニケーションが苦手」という人にも色んなタイプがあると思うんですが、しんざきは「エレベーターの中でそれ程親しくない知人と二人っきりになるのがとても苦手」なタイプのコミュ障です。
皆さんあの時間、平気ですか?何話せばいいんでしょうね、ああいう中途半端な待ち時間。未だに分かりません。
この記事で書きたいことは、大体以下のようなことです。
・人間は、基本的には「自分に興味・関心をもってくれる人」に好感を抱きやすいようです
・だから、円滑な人間関係を築く為には、「私はあなたに関心を持っています」ということをきちんと表明することが大事です
・ただし関心量にはバランスが大事で、状況によって、相手によって、ちょうどいい関心の量は変わってきます
・親子関係では特に、「関心量の調節」って難しいですよね
・子どもが大きくなるにつれて、「受け身の関心」「子どもが関心をもっていることに対しての関心」に軸足を移すような感じで調整してみています
・ちょうどいい親子の距離感が築けると素敵ですよね
以上です。よろしくお願いします。
さて、書きたいことは最初に全部書いてしまったので、後はざっくばらんにいきましょう。
私が昔いた職場に、もの凄くコミュ力が高い人がいました。
やたら顔が広くって、色んな人と話を盛り上げることが出来て、しかも相手を選びませんでした。職場でちょっと浮きがちな人でも、あまり周囲と会話をするのが得意でなさそうな人でも、その人と会話するとちゃんと話に参加出来るのです。
まさに冒頭書いた、「エレベーターでの会話」で彼と話した時に気付いたことなんですが、彼、「自分が相手に興味を持っている」と伝えることと、「そのバランスの調整」がもの凄く上手いんですよね。
天気の話でも、仕事の話でも何でも、まず「相手の考え」に軸を置いた反応をして、「自分はあなたに興味がある」と伝える。
一方、相手が積極的には自己開示したくなさそうな場合、相手の話に深くは立ち入らず、むしろ相手が聞きたそうな話に応じて、相手の反応を確認する。それでも距離を置きたそうな場合、話をさらっと流す。
どんどん自己開示したい人と、あまり突っ込んで欲しくない人、それぞれに応じた距離感の管理ができているわけです。
この辺の距離感の調整がすごいなーと。これ、本人的には考えてやっているわけではなく素なようで、
「根っから他人に興味があり」
「かつ、興味をもって欲しくない場合それを感知できる」
という人なんだなーと感心したんですが。
コミュニケーションって、基本的には「興味のやり取り」です。「私はあなたに/あなたの言うことに興味があるよ」という意思表示の交換が、コミュニケーションの根幹です。
私、いわゆる「コミュニケーション術」的なものに対してちょっと不信感を抱いていた時期があるんですが、その原因のひとつがこれなんですよね。
「相手に対する興味」を置いてけぼりにして、話し方とか、伝え方とか、小手先の技ばっかり磨こうとしても仕方ないと思うんですよ。
以前も書いたんですが、「相手に対する興味」を欠いたまま相手とコミュニケーションをとろうとするのって、お湯がない状態でコーヒーをいれようとするような不毛な行為ですよね。
まず相手自身に興味を持つところからなんだろうなあと、そう思います。
***
ところで、育児をする上でも、この「関心量の調節」って滅茶苦茶大事だし、難しいよなあ、と思っています。
以前から何度か書いていますが、しんざき家には子どもが3人います。長男が高校三年で、長女と次女は中学生の双子です。
子どもって小さい頃は、「親からの視線」「親からの関心」をもの凄く欲しがります。
何かというと親の気を引こうとする。何かする度に「パパ、見て見てー!」って寄ってきたり、自分が作ったものを見せてくれるの、滅茶苦茶可愛いですよね。
まあ、ダンゴムシとかセミの抜け殻とか拾ってこられるとちょっと難儀ですけど。
つまり、小さい子は非常に大量の「親からの関心」を必要としている。
もちろん親の保護を受けないと生きていけないから当然なんですが、まさに「親の関心を食べて成長する」って言っていいくらい、「私を見て!」って気持ちでいっぱいなわけです。
もちろんこの時期、子ども自身も親に対して大きな関心をもっています。
パパ、ママのやること、なんでも真似したがったり、やたら興味を持ったりしますよね。
子ども自身にとっても、自分の世界に常にいる他者って親だけですから、関心を持つ対象も集中するんです。
だから、子どもが小さい頃は、親が子どもに関心を持てば持つほどバランスが良くなるわけです。
ただ、成長するに従って、子どもの「関心の必要量」は徐々に下がっていきます。
もちろん精神的な成長もありますし、子ども自身の世界も広がって、関心を持つ対象も広がっていきます。
友達のこととか、学校のこととか、ゲームのこととか、遊びのこととか、色んなものに対して関心を抱くようになります。うちの場合、小学校中学年くらいから、急に世界が広がり始めたように見えました。
誰しも記憶にあることだと思うんですが、子どもってある年代になると、親からの視線、親からの関心が、急に重荷になったり、鬱陶しくなったりしていきますよね。
そういう状況で、子どもが小さい頃と同じ感覚の関心を親が注ぐと、ともすると過干渉になったり、子どもの独立心に負の影響を及ぼす気がするんですよ。
この辺のバランスって非常に繊細で、環境によっても変わるし、子どもによっても変わるんですよね。
もちろん関心をもち過ぎるのも居心地悪そうなんですが、子どもが成長したからといって、関心を持たなすぎるのもまたよろしくない。
しんざき家でも、長男長女次女の「関心量のバランス」はそれぞれでして、長女はまだまだ「親からの関心」をたくさん必要としている様子である一方、長男は割と早くから親と一定の距離を保とうとしていたように思えます。
次女はその間くらいで、関心をもって欲しそうな時も、持って欲しくなさそうな時もあります。
育児もまだ道半ばで、しかも3人分の事例しかない状況で「正解」なんて全く分からないんですが、しんざき家では、
「能動的な関心から、受け身の関心にシフトする」
「関心の対象を、徐々に子ども自身から「子どもが興味をもっていること」にシフトする」
という方向で調節しようとしています。
つまり、子どもがやることに関心を持ちつつも、こちらから積極的に「私はあなたに関心がある」ということを表明はしない。
子どもが何か言い出したら「自分もそれに興味がある」と開示はするけど、こっちからはあんまり「何してるの?」とは聞かない。
一方で、「子どもが関心を持っていること」については、同じ目線で会話が出来るといいなあ、と思っており、ある程度ちゃんと追いかけるようにしています。
例えば、うちの長女次女はどちらも漫画や小説が大好きなのですが、ちょくちょく「これ面白いよ!」と本をオススメしてくれたりするので、それは喜んで読むし、「面白かった」「あんまり合わなかった」とちゃんと伝える。
念のためですが、飽くまで「方向」なので、厳密にこう出来ているわけでもありませんし、杓子定規にやってるわけでもありません。
育児ってケース別の試行錯誤でしかないので、正解なんて一生分からないのかも知れません。
とはいえ、今のところは、好きな漫画やらアニメやら小説やらについて楽しく話せているし、普段は普段でそんなに居心地悪くはなさそうなので、まあ当面はこのまま続けてみようかな、と。
将来的に、ちょうどいい親子間の距離が維持できるといいなあと考えていると、そんな話だったわけです。
今日書きたいことはそれくらいです。
[adrotate group="46"]
【著者プロフィール】
著者名:しんざき
SE、ケーナ奏者、キャベツ太郎ソムリエ。三児の父。
レトロゲームブログ「不倒城」を2004年に開設。以下、レトロゲーム、漫画、駄菓子、育児、ダライアス外伝などについて書き綴る日々を送る。好きな敵ボスはシャコ。
ブログ:不倒城
Photo:K Munggaran
「話の上手さの本質って、こういうことか…」
少し前のことだが、そんなことを思い知った出来事がある。
陸上自衛隊の元最高幹部を大阪にお招きし、経営者団体の会合で講演会をしてもらった時のことだ。
お名前や経歴をご紹介し、さっそくマイクをお渡しすると元最高幹部は開口一番、こんな事を言った。
「まず最初に、皆さんに知って頂きたい自衛隊の基本概念があります。『必成目標』『望成目標』という考え方です」
要旨、幹部自衛官はあらゆる任務・仕事で「必ず達成する必要がある目標」「可能であれば達成を目指す目標」の2つを意識するのだという。
その上で、例えば以下のような用例で部下に問いを立てると説明する。
“この仕事の必成目標と望成目標は?”
このような価値観と概念を共有し、仕事や作戦目標の意識合わせをするのだという。
「その上で、講演に先立ち私の本日の必成目標を皆さんにお伝えします。皆さんが私の話を『明日から使えるネタがいくつかあり、話を聞いた甲斐があった』と評価して下さること。それができなければ私の敗けです」
ともすれば講演会では、謙遜が行き過ぎて先に“逃げ”を打つ人も少なくない。
そんな中、“成果物”を先に約束し、それができなければ自分の責任であると、これ以上ないわかりやすい覚悟を示した形だ。
この前フリで講演会は一気に締まり、最後には大好評の盛会となった。
そんな元最高幹部と親しくお付き合いさせて頂き随分になる先日、とても驚きのオファーを頂く。
「来月関西に行きますが、生駒まで足を伸ばすこと可能です」
生駒とは私の住む奈良県生駒市のことであり、その意図するところは明らかだ。
将来自衛官になりたいといっている、私の小学校6年生の息子と会って、いろいろ教えて下さるという示唆である。
望外の喜びであり、さっそく田舎町のお蕎麦屋さんに元最高幹部をお迎えする。
元最高幹部と私、息子の3人で夕方から蕎麦前をつまみながら、“息子一人のため”のぜいたくな講演会が始まる。
そして元最高幹部はノートパソコンを取り出すと息子に向け、パワーポイントでプレゼンテーションを始めた。
「今日はわざわざ、来てくれてありがとう。おっちゃん、今はもう仕事を辞めたそのへんの人なんで気にしないでね」
そんな導入で息子の緊張をほぐして下さる元最高幹部。
「まずはじめに、今日のお話に先立ちどうしても知ってほしいことをお伝えします。他のことは忘れても良いので、これだけは必ず覚えて帰って下さい」
(今日も、必成目標と望成目標の説明から始めるのだろうか…。小学生には難しくないかな…)
しかしこの後、元最高幹部は全く予期していなかったことを言い出す。
“社員を拘束したほうが利益になる”
話は変わるがもう随分と昔のこと。大阪の中堅メーカーでCFO(最高財務責任者)をしていた時の話だ。
着任当初、とにかく数字の可視化が全くできていない状態に苦しむことがあった。
そんな中、状況を整理して最初に気がついたのは不正らしき痕跡の多さだった。
正確に言えば、不正な経費精算や備品の持ち出しであろう、不自然な数字である。
とはいえ、数字を把握する手段が無ければ証明・改善する手段などない。
そのため、経費精算や消耗品・備品の支給について細かなルールを決めるのだが、すると今度は新設ルール外のところで、不自然な数字が増加する。
(あかん…イタチごっこや…)
従業員は800名超であり、本社以外に多くの事業所がある事業形態だ。
経費精算や消耗品の持ち出しルールを過剰に設定し運用するのは、正解なようで間違っている。なぜか。
悪意のある極めて少数の社員による不正を排除するための仕組みが、99%のまじめな社員のやる気と利便性を失わせるためだ。
「社員のことなど一切信用していない」
ルールの細分化と行き過ぎた管理は、そんなメッセージ性として社員に敏感に伝わる。
言い換えれば、100円の損失を防止するために1000円のコストを費やすようなものであり、手段を目的化させてしまう。
とはいえ社員は、誰がどんな方法で悪いことをしているのか、不正をしているのか、だいたい知っているのが会社組織というものである。
状況を放置したらまじめな社員ほどやる気を失い、経営陣も愛想を尽かされ信用を失うだろう。
そんなことに思い悩んでいたある日、中堅以上の社員からの要望を取りまとめ、役員会に就業規則の改訂を提案することがあった。
選択的な短時間就労制度の導入と、それに伴う給与体系の見直しである。
要旨、6時間労働や週休3日などの選択肢を用意し、それに応じ給与も調整するという働き方の提示だ。
女性社員が8割を占め、またママさん社員も多かったので要望が多かった上に、本音を言えば労務費の削減手段としても非常に有効な手法でもある。なぜか。
人は就労時間の中で、めいっぱい集中していることなどありえない。
有り体に言って、8時間の勤務時間が6時間になったところで、多くの職種の成果など大きく変わらないものだ。
「これだけの成果を出せば、なんなら毎日、午前中に帰っていいよ」
もしそんなルールなら、おそらく多くの社員が本気で成果にコミットして集中し、決して18時まで席に居ることなどないだろう。
もちろん、適用できない業種や職種もたくさんあるが、その会社では成果の可視化と適用が容易であった。
そんなこともあり、労務費の削減見通しとあわせて役員会に諮ったのだが、思いがけない結果に終わる。
「労働基準法の上限まで社員を使える就労規則になってるんに、変える意味ないやん」
そんな経営トップの反対意見に一蹴され、他の役員も賛同する。
“法律の上限いっぱい社員を拘束するほうが、利益になる”
その時やっと、理解できた。
(不正行為が横行する本当の理由は、これか…)
「三方良し」は寓話ではない
話は冒頭の、自衛隊元最高幹部との飲み会についてだ。
「まずはじめに、今日のお話に先立ちどうしても知ってほしいことをお伝えします。他のことは忘れても良いので、これだけは必ず覚えて帰って下さい」
そう前置きしたうえで息子に、何を言い出したというのか。
「キミのお父さんは、本当にすごい人です。自衛官は力で国と平和を守りますが、キミのお父さんは筆の力で守っています」
(クソっ…やられた…)
油断していたところの初撃に、思わず目が…ムズムズする。
ギリギリでこらえ息子の方に目をやると、なんとも言えない誇らしい顔をしている。
あかん、しばらく顔を上げられそうにない…。
そんな前置きの後、元最高幹部は自衛官という働き方の魅力を説明し、様々な働き方や可能性があること。本気の挑戦に応える組織であることなどを1時間も語って下さり、最後にこう締めくくった。
「今はまだ、自衛官になろうと決める必要はありません。勉強や運動を頑張って、国や社会のために役立つ人になって下さい。その上で、もし御縁があれば自衛官という働き方を選んで下さい」
元最高幹部のお人柄や人間力については、十分に知っていたつもりだった。
しかしまさか、第一声からこんな形で話を進めるとは、完全に不意をつかれた…。
この日の出来事から、改めて理解したことがある。
元最高幹部の「人生における必成目標」とはきっと、“一人でも多くの人を幸せにすること”なのだろう。
だからこそ「自衛隊の説明」という手段を通じ、「一組の親子の幸せ」を必成目標として、この日の”マイクロ講演会”をお話して下さったということだ。
改めて、大組織のトップに立つ人のすごさに鳥肌立つ出来事になった。
そして話は、昔役員を務めていた会社での出来事についてだ。
“法律の上限いっぱい社員を拘束するほうが、利益になる”
そんな経営トップの言葉のどこから、不正行為が横行する本当の理由を悟ったというのか。
「社員は、会社の利益と対立する存在」
先の言葉には、そんな経営思想が色濃く滲んでいる。なぜか。
社員の幸せや待遇改善は利益にならないからやるべきではないと、そういっているに等しいからだ。
そんな経営者や会社が、うまくいくわけがないだろう。
どのような言葉で言語化するのかは、人それぞれである。
しかしリーダーにとって何よりも大事にすべき“必成目標”は明らかだ。
「従業員、お取引先、顧客の幸せ」である。
人の不幸の上に成り立つ利益など、長続きするわけがないのだから当然ではないか。
そして従業員の幸せや福利厚生を“敵視”すれば、従業員も必ず会社を敵視する。
献身的に組織に貢献しようなどと思うわけがなく、やがてこう考えるようになる。
「いつも搾取されてるんだし、バレない範囲でやり返して当然」
このようにして、不正行為のモグラ叩きがあちこちから噴き出す。
「三方良し」という近江商人の言葉があるが、これは決して寓話ではない。
元最高幹部が大組織で頂点まで昇り詰めることができた理由。
不正行為が絶えなかった中堅企業の事例。
リーダーと呼ばれるポジションにある人には改めて知ってほしい、印象深い出来事だった。
[adrotate group="46"]
【プロフィール】
桃野泰徳
大学卒業後、大和證券に勤務。
中堅メーカーなどでCFOを歴任し独立。
主な著書
『なぜこんな人が上司なのか』(新潮新書)
『自衛隊の最高幹部はどのように選ばれるのか』(週刊東洋経済)
など
人間力に溢れる人とお酒をご一緒すると、いつも飲みすぎてしまいます。
仕方がないんです…。
X(旧Twitter) :@ momod1997
facebook :桃野泰徳
Photo:Michał Bożek
今回は、とても個人的なことを書きたい。
親戚の伯母が亡くなった。正確には、元伯母が亡くなっていたことを、私はつい最近知った。亡くなってから二年も経っていた。
「せっちゃんが死んだことを知らされていなかったのは、うちだけだったみたいよ」
と、母が言った。
亡くなっていたのは、私の父の次兄の元妻・セツコさんだ。
私の父は4人兄弟の末っ子で、一番上がトシコ伯母さん、次が長男のトシオ伯父さん、次男のトオル伯父さん、そして三男である父。
父方の祖母は教育熱心な人で、息子3人を全員大学へ行かせた。けれど実は、4人の中で一番頭が良かったのは長女のトシコ伯母さんだったという。
祖父の頭が古く、「女に教育は不要だ」と言ったため、トシコ伯母さんは高校までしか行かせてもらえなかったそうだ。
長男は関西大学、次男は一浪して慶應へ。
大学進学者が少なかった時代に息子が慶應に受かったことで、祖母は鼻高々だったらしい。
だが現実は、神戸に暮らす普通のサラリーマン家庭。息子を東京の私立大学へ行かせるのは無理の連続だったという。
次男にかかる学費と仕送りが家計を圧迫する中で、祖母は父にこう命じたそうだ。
「浪人は許さない。家から通える国立大で、医学部なら進学を許す」
父は言いつけに従って神戸大学の医学部へ進み、医者になった。祖母にとっては、これもまた自慢の種だった。
進学を諦めて就職したトシコ伯母さんは、早々に結婚して実家を出たあと、主婦として家庭を切り盛りしながら書家として成功し、大金を稼ぐようになった。
一方、私の母を含めた3人のお嫁さんたちは、子供達が大きくなるまで専業主婦として家庭に仕えた。
長男の妻・ユウコさんはおとなしくて優しい女性。
次男の妻・セツコさんは世話焼きで、下町出身の江戸っ子。
二人とも人柄が良く、良い妻であり母であったけれど、祖母とトシコ伯母さんにひどく虐げられた。理由はほとんど言いがかりだ。
ユウコさんには、
「男に養ってもらわないと生きられない無能」
と言い放ち、セツコさんには、
「下町の女で家柄が悪い」
と言って見下した。
いや、実際の理由はもっと単純で醜い。
美人が嫌いだったのだ。
祖母もトシコ伯母さんも自分の容姿にコンプレックスがあり、ユウコさんのように可愛い女性や、セツコさんのように華のある美人を見ると嫉妬が疼いたのだろう。母の見立てはそうだった。
私の母は大卒で薬剤師免許があり、実家も医者の家系だったため、一目置かれていじめを免れた。
父が母親に冷淡で、「うちに迷惑かけたら縁を切る」とまで言ったのも功を奏した。おかげで祖母は父に逆らえず、私たち家族にはほとんど干渉しなかったのだ。
また、トシコ伯母さんは弟たちに多額の援助をしていたが、父だけはトシコ伯母さんからお金を受け取っていない。
トシコ伯母さんは弟たちが家を建てるときに頭金を出し、特に生活が不安定だったトオル伯父さんには、くり返しお金を渡した。それを背景に、彼らに偉そうにふるまっていたのだ。
私は、セツコさんには恩を感じている。
大学受験のとき、1週間ほど家に泊めてもらい、世話をしてもらったのだ。
セツコさんは江戸っ子らしくチャキチャキしていて、面倒見がよく、よく働く人だった。
でも、朗らかな笑顔の裏で、どれほどの我慢を重ねていたのだろうか。
当時から、セツコさんは不定愁訴に苦しんでいた。心労の蓄積が不調の原因だったのではないだろうか。
夫であるトオル伯父さんは、40代で大手企業のサラリーマンを辞め、山師のようにさまざまな事業を始めては失敗し、ついには50代で自己破産した。
家計は火の車で、しまいにはどうやりくりしても食べていけなくなり、トシコ伯母さんを頼ることになった。
トシコ伯母さんから生活費の援助を受け、自立できずにいた次女に見合い相手も世話してもらったのだ。
背に腹は変えられないとはいえ、自分を長年いじめてきた相手に頭を下げるのは、セツコさんにとって屈辱に胸が焼ける思いだったろう。
一方のトシコ伯母さんにとっても、はらわたが煮える思いだったようだ。弟にいい顔をしたいがために、気前の良いフリをして援助を続けたが、
「私の稼いだお金があの女(セツコさん)の生活費に消えていると思うと、腹がたつ」
と、陰口に余念がなかった。
トシコ伯母さんの世話により次女が結婚して家を出ると、セツコさんはついに離婚した。けれど、熟年離婚の決定打は夫の破産ではない。
姑(私の祖母)に勝手に名前を使われて、身に覚えのない借金を作られていたのだ。
私の祖母は、子育てを終えた後に買い物依存症になっていた。
92歳まで長生きしたが、半世紀の間に総額で億を超える借金をしながら浪費を重ね、その尻拭いを子供たちにさせていたのだ。
祖母は自分の名前で借金をするだけでは足りず、ユウコさんやセツコさんの名前も使ってクレジットカードを何枚も作り、借金を膨らませていたのだった。
人の優しさや我慢には限界がある。
我慢に我慢を重ねてきたセツコさんも、ついに糸が切れたのだ。
離婚してS家を去った後も、セツコさんからは、ずっと年賀状が届いていた。
祖父母が亡くなって以降は親戚とも疎遠になり、次第に頼りが途絶えていくなかで、彼女だけは私に宛てた年賀状を欠かさなかった。
しかし私は、一時期それを返さなかった。
当時の私は、結婚生活が破綻し、二人の幼い子供を抱えて必死に生きていた。
人生がうまくいかず、卑屈になり、昔の自分を知っている人と関わることが辛かったのだ。
思い返せば恥ずかしい。
セツコさんのほうこそ、私よりもっと苦しい人生を送っていたのに。
連絡を無視しつつも申し訳なさが心に引っかかっており、今の夫と再婚して暮らしが落ち着いた頃、私は年賀状に近況を綴ってセツコさんに送った。
すると返事が来た。
「よかった。もう私とは関わりたくないのかと思った」
違う。そうじゃない。私の心が未熟だっただけなんです。
けれど、再び年賀状のやり取りが始まった矢先に、今度は年賀状仕舞いの連絡が来た。寂しかったけれど、年齢のこともあるのだろうと受け止めた。
最後に、これまで優しくしてもらったお礼に手紙を書いた。すると、温かい返事が送られてきた。
「この先どんなことがあっても、あなたなら大丈夫よ」
それが二年前のこと。そして、その頃もう、セツコさんは死につつあったのだ。
死因は頭蓋内出血。脳腫瘍があったらしい。
優しい人は、静かに、あっけなく逝く。それは、心身をすり減らしながら生きてきた証でもあるけれど。
年末が近づくと、私はよく昔のことを思い出す。
私が二十代前半まで、父方の家族は毎年、神戸の祖父母宅に集まって大晦日とお正月を過ごした。
お嫁さんたちは三人そろって台所に立ち、祖母に指図されながらおせちを作り、お雑煮を用意した。私はその光景を「正月の風景」としか思っていなかった。
でも今なら分かる。
あの場は、お嫁さんたちの我慢で成立していたのだ。
自分を嫌っている義両親の家に毎年通わされるのは、どれほど辛かっただろうか。
その積み重ねは深い恨みになり、祖父母が死んでも、夫と離縁しても、消えなかったのだろう。
「私が死んでもS家の人たちには知らせないで」
と言い残したと聞いているが、ひょっとしたら、そう決めたのは母親の苦労を知っている娘たちだったかもしれない。
そうは言っても、セツコさんと同じ苦労を味わったユウコさんには連絡が来たらしく、トシコ伯母さんにはトオル伯父さんから報告があったらしい。
普段交流もなく、遠く離れた地に住む私たちだけが、何も知らされなかった。
今の時代、家族関係は昔より希薄になった。
正月に必ず夫の実家へ行く必要もない。でもきっと、そのほうが健全だ。
最後に、セツコさんに言いたい。
血のつながった祖母よりも、トシコ伯母さんよりも、血のつながりのないあなたが私は好きでした。
[adrotate group="46"]
【著者プロフィール】
マダムユキ
ブロガー&ライター。
リンク:https://note.com/flat9_yuki
Twitter:@flat9_yuki
Photo by :Emil Karlsson
少し前のbooks&appsで、桃野泰徳さんが「娯楽も遊びも休息も、仕事の一部」という記事を書いてらしたのを覚えているだろうか。
私はよく覚えている。なぜなら働いていくうえでとても重要な考えだと思うからだ。
機械にメンテナンスが必要なのと同じく、人間には娯楽や遊びや休息が、つまり桃野さんの記事でいう「戦力回復」のフェーズが必要になる。それを怠っていれば仕事能力は次第に低下し、ときには健康を損ねてしまうかもしれない。
だからマトモな組織や指揮官は「戦力回復」に十分な注意を払い、メンバーの福利厚生に努める。2004~2006年の陸上自衛隊イラク派遣に際し、厚生センターが現地に設営されたのもそのためだと桃野さんは書いてらっしゃる。
牟田口廉也のインパール作戦
ところが戦史を振り返ると、その「戦力回復」に注意を払っていないリーダーや指揮官が案外いたりする。太平洋戦争における旧日本軍は全体的にそうだが、海上補給ルートが寸断されてしまった太平洋戦争後半にはむごい話が多い。
そうした旧日本軍のなかでも、特別にひどい人物と言われがちなのが牟田口廉也だ。

(写真:wikipediaより)
牟田口廉也は佐賀市の士族の家に生まれ、陸軍士官学校を平凡な成績で卒業したという。尉官時代には与えられた仕事をよくこなし、佐官時代には軍内の政治遊泳にも、部下の統率にも優れていたようだ。その後も出世を重ねて、運命のインパール作戦においては中将の職に就いている。
牟田口廉也以外にも言えることだが、後世に「無能なリーダー」として後ろ指を指される人物も、そう評されるエピソードが巡ってくるまでは優秀であることが多い。
そもそも、なんらかの優秀さがなければリーダーや指揮官の地位を獲得できないわけで、実力や実績や交渉力などがなければ「無能なリーダー」や「愚将」にすらなれない。
他方、人には最適な器のサイズというものもある。平社員の時が一番輝く人、係長の時に一番輝く人、課長の時に一番輝く人、部長の時に一番輝く人がいる。
自分の器をこえた役職は、その人自身にも、周囲の人や組織にも不幸な転帰をもたらすだろう。牟田口廉也という人物と旧日本軍という組織にとって、中将という彼の階級、さらにビルマ方面の司令官という彼の役職が好ましい結果をもたらしたようには見えない。
その牟田口廉也が立案・指揮したのがインパール作戦だった。
牟田口は、戦局を打開するといってインドとビルマの国境地帯に侵攻した。補給困難な熱帯雨林を通り抜ける作戦は失敗し、大量の餓死者や病死者を出す結果で終わっている。
このインパール作戦を象徴する言葉としてしばしば引用されるのが以下のセンテンスだ。
皇軍は食う物がなくても戦いをしなければならないのだ。兵器がない、やれ弾丸がない、食う物がないなどは、戦いを放棄する理由にならぬ。弾丸がなかったら銃剣があるじゃないか。銃剣がなくなれば、腕でいくんじゃ。腕もなくなったら足で蹴れ。足もやられたら口で噛みついて行け。日本男子には大和魂があるということを忘れちゃいかん。
こんなことを本当に牟田口が言ったのか、私は知らない。がしかし、「牟田口廉也は補給や戦力回復について考えの足りない将官だった」という世評を象徴しているセンテンスだと思う。
牟田口廉也みたいな作戦を立てる親がいっぱいいる
で、ここからが本題である。
世の中には、牟田口廉也みたいな親がいっぱいいると思いませんか。
子どもを逆境にさらす親にもいろいろあって、狭義の虐待やネグレクトをやってしまう親はその典型と言える。
それとは別に、子どもに熱心すぎる親、子どもにあれこれさせ過ぎる親もいる。やれ勉強しろ、やれヴァイオリンを練習しろ、やれ英会話を経験しろ……。
伸び盛りの子どもにさまざまな経験を提供すること、それ自体は悪くないだろう。勉強だってできるにこしたことはない。
しかし子どもには娯楽や遊びや休息が、つまり桃野さんの記事でいう「戦力回復」のフェーズも必要だ。
なかでも遊びは軽視できない。本来子どもは遊ぶのが仕事みたいなものであって、そこからも技能も習得し、自律性や自発性をも獲得していく。
子どもにとってのそれらは「戦力回復」という言葉以上の重要性を含んでいる。
だから、子育てをうまくやるにあたっては、「戦力回復」や補給やメンテナンスに相当するもの、それから「遊び」に相当するものへの目配りはどうしたって必要だ。
それらを軽視して子どもに勉強や稽古事を強いているなら、それは牟田口廉也のインパール作戦に似たことを、我が子に強いているも同然である。餓死者や病死者は出ないかもしれないが、子どもの心身の健康な発達にも影を落とすだろう。
にも拘わらず、実際には多くの親がインパール作戦のごとき、牟田口廉也のごとき子育てをやってしまっている。
やれ、有名私立学校だ、SAPIXだと高みを目指す一方で、補給や戦力回復を軽視し、子どもから「遊び」の機会を剥奪することが効率的なことだと思いこんでいる親は未だ多い。
そうした親は「我が子のためを思って」と思い込んでおおり、自分のやっていることは虐待やネグレクトの正反対であるとも確信している。
だけど、それって「子育てのインパール作戦」じゃないです?
誰も「あなたは今、牟田口廉也をやっている」とは教えてくれない
問題は、そうした戦力回復や補給や「遊び」を軽視しきった親でも、親権があり、そうそう誰も口出し・手出しできないということだ。
食事を与えない・身体的虐待を行っているといった、狭義のネグレクトや虐待が行われているなら児童相談所が動くこともできようが、そうでない場合、どんなに子育て指揮官としての親が無能でも、子育てがインパール作戦じみていても、それをどうにかすることはできない。
そして、誰かの子育てを無能であるとかインパール作戦であるとじかに指摘することは、現代社会のシステム下では不可能なことなのである。
そういえば最近、そうした「子育てのインパール作戦」に戦力回復を提供する体裁をとった、新しい商売も生まれている。
それは「『受験うつ』にはTMS療法を」といったものだ。TMSとは正式名は経頭蓋磁気刺激法といい、脳の左背外側前頭前野をターゲットとして磁気刺激を生じさせるような療法だ。この療法の進化版であるrTMS療法は、厚労省からうつ病に対する保険適用のお墨付きももらっている。
うつ病に対して新しい療法が提供されるようになったのはいい。だが、子どもを受験勉強漬けにして、元気がなくなってきたら「受験うつ」と称して脳に磁気刺激をおくるというのは、なんだかディストピアめいていると私には思える。そもそも「受験うつ」とは一体何なのか? そんな病名や概念は、精神医学の世界のいったいどこにある?
厚生労働省の委託を受けて日本精神神経学会が作成したrTMS療法に関する資料によれば、この治療法の対象者は中等度以上のうつ病の患者さんで、十分に薬物療法を実施しても効果が認められない患者さんであるとされている。そして機材とプロトコルも定められている。
一方、「受験うつ」に対して行われるそれは、そうした資料内容から逸脱しているようにみえる。
自由診療の領域だからはみ出していて構わないということだろうが、それで本当に補給や戦力回復が期待できるのか、ましてや「遊び」の代用品になるのか私にはよくわからない。
誰の指図も受けなくて構わないかわりに、誰からも忠告や警告をもらえなくなった今日の子育てにおいて、自分の子育てがどこまで間違っているのか、どう間違っているのかを自己モニタリングするのはとても難しいことだと思う。
その際には、牟田口廉也とて尉官時代や佐官時代には無能ではなかったことも思い出していただきたい。
人には向き不向きや器の大小がある。たとえば職場では最優秀とみなされている人が、子育てでは最低であることはよくあることだ。
だから子育てにおいて「インパール作戦」をやってしまうこと、親として牟田口廉也になってしまうこと、それ自体が恐ろしいだけでなく、それについて誰からも指図を受けないで済むかわりに誰からも忠告や警告をもらえなくなっていることが、また恐ろしい。
だから親はたえず自己モニタリングを試みなければならないし、そうしてもなお、自分はそんなにうまくやれるものじゃないと自戒したほうがいいのだろう。
それから何事も極端に走りすぎないこと。少なくとも私は「過ぎたるは猶及ばざるがごとし」という言葉は子育てにおいても金言だと思う。そうしたうえで、自分の子どもに必要な「補給」や「戦力回復」について常に考えておくことが大切だ。
[adrotate group="46"]
【プロフィール】
著者:熊代亨
精神科専門医。「診察室の内側の風景」とインターネットやオフ会で出会う「診察室の外側の風景」の整合性にこだわりながら、現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信中。
通称“シロクマ先生”。近著は『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(花伝社)『「若作りうつ」社会』(講談社)『認められたい』(ヴィレッジブックス)『「若者」をやめて、「大人」を始める 「成熟困難時代」をどう生きるか?』『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて』(イースト・プレス)など。
[amazonjs asin="B0CVNBNWJK" locale="JP" tmpl="Small" title="人間はどこまで家畜か 現代人の精神構造 (ハヤカワ新書)"]
twitter:@twit_shirokuma
ブログ:『シロクマの屑籠』

Photo:Darwin Boaventura
「グエー死んだンゴ」ニキ
少しまえに「グエー死んだンゴ」ニキが話題になった。末期がんで闘病を続けていた人が亡くなったあと、Xに予約投稿であろう「グエー死んだンゴ」という一文がポストされたのだ。
それに対して、ネット民たちは「成仏してクレメンス」と応えた。自分の本当の死をネットスラングにしてみせる姿は、まさしくインターネットの人だった。
話はそれだけでは終わらなかった。新聞の訃報欄で事実が確認され、亡くなった人がまだ22歳の大学生であったこと、希少がんであったことなどがわかったのだ。
だれかのポストをきっかけに、「香典」として国立がん研究センターなど、がん対策の研究機関などに寄付が相次いだ。
そこには、なにかインターネットのよいところが現れているようにも見えた。
誹謗中傷や分断煽り、儲け主義がはびこる中で、ひさびさに見たヌクモリティだ、泣き笑いのある話だ。AIにはできないことだ。人の死は人にこんな反応をもたらす。
若い人が死ぬこと自体は悪い話だが、こんなネットは悪くない。たまにはこんなことがある。
この件は全国紙やNHKなども報じることとなった。とうぜん、ネットを眺めて生きているおれも早い段階で知った。生前のニキのことはしらなかったが、Xのまとめですぐに知った。
おれはどう思ったのか。「こんなネットは悪くない」どころではない。ただ泣きそうになった。
希少がん患者が見た「グエー死んだンゴ」ニキ
おれも死んだニキと同じく、希少がんの患者である。ニキの「類上皮肉腫」も、おれの「神経内分泌腫瘍(NET)」も国立がんセンター希少がんセンターのさまざまな希少がんの解説コーナーに記載されている。
が、もちろん、その病状は大きく違う。希少がんと診断されたおれはいま、死というものに直面しているだろうか。いま現在、直面していない、というのが正直なところだ。
まだ診断が未確定の初期段階では、「予後がよくない可能性がある」と言われて、死を意識したこともあった。
だが、二度目の大腸内視鏡、CT、PET/CT、MRIなどの精密検査を経た上で、「NET G1」が確定した。あまり重くはない。リンパ節には転移しているが、ほかの臓器に転移もしていないし、進行の速度も遅い。
手術して切除してしまえば、とりあえずの安心は得られる。手術の代償として、一時的な人工肛門造設も確定しているが、命を取られるわけでもないし、肛門を取られるわけでもない。
おれはおれの希少がんにそれなりのショックを受けたし、動揺もした。いま、入院、手術を控えた身として、必ずしも心が平穏かというとそうではない。
そうではないが、それは
「人工肛門での生活とはどのようなものだろう」
「もし術中、術後の結果から永久人工肛門になったらどうしよう」
「仕事にはすぐに復帰できるのだろうか」
と、生死に比べたらずいぶん軽いものといっていい。手術自体への心配もほとんどない。おれは今どきの最新技術というものも信頼しているし、ロボット支援下手術をしてくれるということに感謝すらしている。……少し強がっている。
ただ、ぶっちゃけてしまうと、おれは、おれの希少がんが治ると思っている。
もちろん、手術ではいろいろな神経が入り組んでいる直腸付近のリンパ節をごっそり切除する。場合によっては排尿や射精に関する機能が損なわれる。その可能性は低くない。
また、人工肛門を閉鎖したのちは、排便に障害が残る。無傷ではいられない。ただし、この希少がんによって命まで奪われるわけではないと思っている。
それに比べて、「グエー死んだンゴ」ニキの場合はどうだったろう。
……あ、さっきから「グエー死んだンゴ」ニキと書いているけれど、ネット上のハンドルである「なかやま」さん、のほうがいいだろうか。それとも、公開情報となっている本名? いや、それはなにかなれなれしい感じがしてどうもしっくりこない。ニキで書かせてもらう。
まあとにかく、自分が彼のnoteとXで見られるかぎり、かなり早い段階で背中の筋肉と肋骨を失っている。進行も早くステージ4の診断もすぐに下されている。
ベッドの上から動くこともなかなかできず、最後には緩和ケアからの書き込みになっていた。
あまりにも重さが違う。大きな意味では「同じ希少がん」かもしれないが、その重さには天と地の開きがある。どちらが天だかはわからないが。
なので、「おまえ、そんなんで一緒の希少がん顔するなよ」という声も聞こえてきそうだ。
というか、書いていて、自分の中からその声は止まらない。
それでも、だ。こんな病気に自分がなったからこそ、このニュースを見て感じることがあったとも思えるので、こうして書いている。こうなっていなかったら、泣きそうにならなかったかもしれない。
こうなっていなくても、泣いた可能性はあるが。
(念のため書いておくが、同じ神経内分泌腫瘍でも重症度や悪性度は千差万別であって、おれのG1より悪いG2もG3もあれば増殖力が高く悪性度も高いNECもあって、それらは命にも関わる。もちろん、自分だって発見があと何年か遅ければ取り返しがつかなくなっていたかもしれない。「今回、おれに見つかったNETは比較的軽かった」という話である)
がんで病気に対する解像度が変わった
おれはこういう「解像度」という言葉の使い方が正しいかわからない。サイズが大きくなったとか、画素数が増えたとでも言ったほうがいいような気もするが、まあいい。
とにかく、自分が希少がんになってみて、身体の「病気」、とくに「大病」に対する意識に変化があったように思う。
これを理屈で説明するのは難しい。心情の変化として説明するのもやはり難しい。まだ変化をたしかに実感していないというのが正しいのかもしれない。
ただ、やはりおれは「グエー死んだンゴ」ニキのニュースを知ったときに、今までとは違う動揺の仕方をしたと思う。それは確かだ。
そもそも「病気」というもの、それも「大病」、死に至るような病はドラマになりやすい。
だから、古今東西さまざまな作品の主題として扱われてきた。歴史的な名作とされるものもあるだろうし、ありがちなお涙頂戴ものの恋愛作品とされるものもあるだろう。
おれは今まで、そのどちらを見ても、なんにも感じていなかったのではないかとすら思う。
「大切な人を病気で失う。それは悲しいということである」という情報を食べてきたにすぎない。
あるいは、余命を宣告された人がショックを受けて人生観が変わる、などというのもそうだ。「自分の余命が長くないとわかってしまう。それは衝撃だということである」と。
が、いざ、これが我が身にふりかかってくると、そうも冷静ではいられない。たぶん、そうなるに違いない。とくに、がんで余命宣告を受けた人物に対しては、今までにはない動揺があるに違いない。
「違いない」などというのは、まだそのような作品に接していないからだ。なにせ手術すらまだなので。
そういう意味では、入院して手術してみて見えてくるものもあるだろう。人が大病を患うとか、その結果できていたことができなくなるとか、いろいろだ。
あるいは、おれは数カ月間人工肛門になることが決まっているが、その期間中は永久人工肛門の人と変わらない生活を送ることになる。その間は身体障害者になる。オストメイトになる。
おれは『罵倒村』のアンジャッシュ渡部建を見て大いに笑ったが、病気がわかったあとだったら笑えたかわからない。看護師さんは立野沙紀さんみたいな人がいいけれど。
もう体験していることもある。大病院での大掛かりな検査がそれだ。CT、PET/CT、MRI……。このていどで大掛かり? 痛くも痒くもないだろう? と、思われるかもしれないが、45歳を過ぎて胃カメラも大腸内視鏡検査もしたことがなかった人間にとっては、すべて初めてのことだ。
そして、そのどれもが、ひどく疲れるということを知った。他の人がどうかしらないが、少なくともおれは疲れる。疲弊する。不安や緊張感、煩雑な手順などから、どうにも疲弊してしまう。
そのせいで、他の人が書いた闘病日記など読んで、たとえ簡単に「この日はCTとMRI検査をした」とだけ書いてあっても、大変だったろうなと想像するようになった。勝手な想像かもしれないが、そうなってしまった。
そのようなおれが、「グエー死んだンゴ」ニキの書きのこしたものを読むと、記述の簡潔さと内容の重さの差にすさまじいものを感じ、言葉を失ってしまう。
病を書き残すということ
病気は人生につきものでもある。仏教では生老病死をして人間の四苦という。
この苦しみのなかで「生」を先頭に置いたのは釈尊の慧眼であったとシオランが書いていたと思うが、今は置いておく。
自分ははっきりいって、この中の「病」の苦しさにはピンときていなかった。
いや、おれは双極性障害(II型)という精神の病を抱えてはいる。手帳も持っている。とはいえ、それはなにか、きっかけとなる事はあったとはいえ、本来のおれというものの性質に病名がついたという感じで、今回のような希少がんの発見とは違うものだった。
今回は、精神とは違って、内臓の問題だ。精神障害には病院へ行く自覚症状があったが、今回はない。
大腸内視鏡検査をして、一個のポリープが見つからなかったら、あと何年も、場合によっては十年以上だって平気で暮らしていたかもしれない。
痛みや不調を伴っていないのに、手術までして人工肛門を造る。それはそれで不思議な感覚ではある。なにか理不尽な気がする、というところも少しはある。
そしておれは、この病気について調べることもやめられない。
自分がどのような状態にあり、どのような手術を受け、その術後はどうなるのか。もちろん、病院やがんについての団体の情報発信を第一に調べる。
しかし、それだけでは足りない。当事者がどういう目にあったのか、それについて、当事者の声が聞きたい。
自分の場合は希少がんだったので、情報は限られていた。それでも、参考になった。
次になにが起こるのかまったくわからず、病院で言われる通りにされているだけでは、不安が大きすぎる。
むろん、素人が下手に情報を受け取ったり、そもそもよくない情報に触れたりして、誤った不安を抱くこともある。しかし、同じ不安なら、知ったうえで不安になりたい。
だから、おれはこの自分の病気について書いている。そういう面もある。
この病気について書くときは、同じような大腸NETになってしまった人に少しでも届けばいいな、と思っている。
おれはもとより、日常のなんでもないことでも書きたがる性質の人間だ。そんな人間が、希少がんという非日常が我が身に降り掛かったら、それについて書かずにはいられない。
ただ、今回はそればかりではない。そういうつもりはある。
実際に役に立つのか、そんなことはわからない。しかしたとえば、NETについての情報は少なくとも、大腸がんの手術をした人の体験談はけっこうある。人工肛門を造設した人の話もある。
この間ははてな匿名ダイアリーで人工肛門について「そんなに心配しなくてもいい」と自身の経験を書いた人も見た。
それらはみな、ありがたい。中には不正確なものもあるだろうし、余計な心配をあおるものもあるだろうし、逆に安心させすぎるものもあるだろう。
とはいえ、なにも情報がないよりはずっとましだ。いや、情報というと少し違う。声とか言葉とかいったほうがしっくりくる。おれはおれのような状況になってしまった人の声を聞きたいのだ。
だれもが「グエー死んだンゴ」ニキにはなれないけれど
だから結局おれが何を言いたいかっていうと、それはもうみんな自分の経験を書いて、ネットに放流してくれよ、ということだ。
「はじめて大腸内視鏡検査を受けたけど、なんの異常もなかった」というなら、それを書いてほしい。
ただ、できたら大腸内視鏡検査のとき腹が空気でパンパンになって苦しいのかそうでないのかとか、ちょっとしたディテールを加えてくれるとなおうれしい。
病は多くの人が通る道だから、きっとだれかの役に立つ。べつにだれに読まれず役に立たなかったとしても、それはそれでどうでもいいじゃないか。
それに、副次的なことか、こちらが重要かわからないが、病気なら病気で、自分の病状や不安、調べたこと、医者から言われたこと、今後のことなどを文章にするのは、気持ちの整理にもなる。
今回の件になってから、長く抑うつ状態に陥っているおれが言っても説得力はないだろうが、整理しないままよりはましだろう。もちろん、整理できないなら、整理できないと書こう。それがリアルだし、ひょっとしたら、だれかの共感と安心になるかもしれない。
おれによし、おまえによしなら言うことはない。おれによし、だけでもいい。
だれもが「グエー死んだンゴ」ニキのようになれるわけがない。多くの人の行動、それも善業とされるものを呼び起こすなんてのは奇跡の一つだ。
そんな奇跡を起こした「グエー死んだンゴ」ニキも、病については奇跡を起こせなかった。だから残念なことに、奇跡になってしまった。
病とは違って、死は誰もが通る道だ。死に直面した人間の言葉もまた、だれかの生にとって影響を与える。おれはニキの残した、決して多くはない言葉(Xを一度凍結されたらしいので、遡れるものは限られている)のなかにも、生や死について考えさせられるものを見つけた。
「今を生きてるんだから
えらいえらいだよ」
というメッセージに、こう答えたのだ。
「生きてて偉い段階は終わった」
生きてて偉い段階は終わった#マシュマロを投げ合おうhttps://t.co/BGAU4da5eo
— なかやま (@nkym7856) September 10, 2025
この言葉がどれだけのものを意味するのか、今のおれにはわからない。
ただ、これから「生きているだけでえらい」という言葉を見るたびに、その段階を終えてしまったと自覚した人のことを思い出すだろう。
人は生きて、ときに老い、ときに病み、そして死んで、どうなるのだろう?
おれも「グエー死んだンゴ」と書き残して死ねるだろうか? 「グエー死んだンゴ」ニキはどうなったのだろう?
おれにはわからない。
せめて、成仏してクレメンス。
[adrotate group="46"]
【著者プロフィール】
黄金頭
横浜市中区在住、そして勤務の低賃金DTP労働者。『関内関外日記』というブログをいくらか長く書いている。
趣味は競馬、好きな球団はカープ。名前の由来はすばらしいサラブレッドから。
双極性障害II型。
ブログ:関内関外日記
Twitter:黄金頭
Photo by :Arseny Togulev
つい先日、Amazonがリストラを始めたと報道があった。
Amazon、約1万4000人の削減を発表 AI時代に対応すべく組織再編で
米Amazonは10月28日(現地時間)、約1万4000人の従業員を削減すると発表した。この削減は、同社のコーポレート部門全体に影響を与える見込みだ。その内容は従業員に向けて共有したメッセージの中で詳細が明らかにされており、組織全体にわたる組織変更の一環として行われる。(ITmedia)
別に驚くには当たらない。
最近では、企業は黒字でもリストラを敢行する。
もちろん、米国企業だけではなく、世界各国で同様の動きがあり、日本企業も例外ではない。
例えば明治、ブリジストン、パナソニック、第一生命、三菱電機…… 少し調べただけでも、本当に多くの企業が、社員を希望退職という名の解雇をしている。
まあ本当のところ、大手企業には「いてもいなくても良い人」が大量に存在しており、上手にリストラをすれば業績も上がる。
マイクロソフトなどはうまくやっていると言えるのだろう。
Microsoft7〜9月最高益 クラウド4割増収、リストラ効果も寄与
【シリコンバレー=山田遼太郎】米マイクロソフトが29日発表した2025年7〜9月期決算は売上高が前年同期比18%増の776億7300万ドル(約11兆9000億円)、純利益が12%増の277億4700万ドルだった。人工知能(AI)向けのクラウドサービスが4割の増収となり、大規模なリストラ効果も寄与した。3四半期連続で最高益を更新した。(日本経済新聞)
「解雇」は経営の正当な手段
私は以前、人事の仕事に関わっていたことがある。
その仕事の中で知ったのは、「解雇は必要な手段だ」と認識している人が結構多かったことだ。
「絶対に雇用を守る」としている会社は少数であった。
たしかに、国連機関であるILO(国際労働機関)は「能力」と「行為」は、解雇の正当な理由だとして位置づけている。
企業は、社会的な機能を担うための機関である。
解雇は、その機能を担うための手段であるから、「従業員」が機能を果たせなくなれば、必要に応じてそれらを行使する。
例えば、ピーター・ドラッカーは、組織において「働く人の意欲」を非常に重視していた。
「意欲のない人間」は組織と本人の双方にとって大きなリスクになると指摘しており、本人に意欲があり、チャレンジを望めば雇用を続けるべきだが、そうでないなら解雇せよ、と言っている。
この問題についてはここでもう一度シンプルな原則を繰り返させていただきたい。挑戦してくるならばチャンスを与えるべきである。挑戦してこないならば辞めてもらうべきである。
だから、ここで問題となるのは解雇の是非ではない。
真に問題となるのは、「誰にやめてもらうべきか」だ。
どのような人を「解雇」すべきか?
一般的には、「無能」が解雇されると考えている人が多い。
しかし、日本では、能力によって解雇される人はむしろ少ない。
では何を持って解雇されるのか。
少し古い文献だが、「クビにした会社と、クビにされた社員の紛争」の調停事例を扱った研究書籍「日本の雇用終了」には、企業が解雇を決定するときの事例が数多く書かれている。
[amazonjs asin="4538500046" locale="JP" tmpl="Small" title="日本の雇用終了: 労働局あっせん事例から (JILPT第2期プロジェクト研究シリ-ズ no.4)"]
これを見ると、日本人が「誰を辞めさせるべきか」についてどのように考えているのかが、よく分かる。
具体的には、「態度が悪いやつ」が最も解雇されやすい。
・労働条件変更といった中間形態をとることなく、直接「態度」を理由にした雇用終了に至っているケースが、168件(実質166件)と全雇用終了事案の中で実質的に最も多くなっている。(第一節)
・狭義の「能力」を理由とする雇用終了では、具体的な職務能力の欠如や勤務成績の不良性を理由とする事案はそれほど見られず、むしろ「態度」と区別し難いような「能力」概念が一般的に存在していることが大きな特徴である。(第二節)
それは、日本企業がは基本的に「やる気があって真面目な人」を解雇できないからだ。
メンバーシップ型の雇用である日本では、従業員の能力が不足したとしても、仕事が遅かったとしても、それは会社側が「教育・訓練」を施すなり、「環境を整える」なりして、本人の能力を引き上げる義務を負っている。
しかし、逆に言えばこれは「従業員の義務として、会社の期待水準まで、自分の能力を上げるための努力をしなければならない」ということでもある。
したがって、
・何度もチャンスを与えたのに努力をしない
・そもそもやる気がなく、勤怠が最悪
・反抗的態度をとって、他の従業員のパフォーマンスを下げる
という授業員に対しては、解雇が認められた判例が多数、存在している。
納得して辞めていく社員
実際、そのように社員を解雇する会社を見ていたことがあった。
その会社はサービス業だった。
社長はワンマンで、非常に仕事ができる。
会社は右肩上がりで成長していたため、社員の給与水準は高めだった代わりに、当然のように成果が厳しく求められていた。
そして、この会社は、解雇をうまく使っていた。
「うまく」というと語弊があるかもしれないが、皆、納得して会社を辞めていくので、大きな問題にならないのだ。
ではいったい、社員をどのように解雇していたのか。
実は、成果が出ない人をいきなり解雇することはしない。「成果があがらないだけ」は解雇の理由にならない。
逆にその場合、徹底して「行動すること、マニュアル通りやること。」を求める。
なぜなら、そのとおりやれば、大半の人は成果が出るから。
忠実にマニュアル通りやればいいだけ。工場の流れ作業と同じだ。
しかし中には、「行動しない人」「マニュアル通りやらない人」がいる。
例えば、
電話しない。(電話するルールがある)
お客さんに会いにいかない。(定期的にお客さんを訪問するルールがある)
ミスを防ぐために必要なチェックをしない。(チェックリストをつかうルールがある)
アンケートを取らない。(アンケートの回収率を100%にするルールがある)
セミナーの練習をしない。(セミナーの練習をするルールがある)
そういう人には、まず上司から、このままだと「評価が下がる、給与が下がる」ことが告げられる。
そこで行動が修正されれば、めでたしめでたしだ。
だがそれでもなお、社員が働かない場合、つぎに希望を聞いて「仕事の変更」をする。
例えば
接客からバックオフィス
営業からマーケティング
品質保証から購買
などといった、配置転換だ。
ただし、この配置転換はだいたい、評価が一旦リセットされるので、給与が下がる。
ただ、実際には、働く場所によって、人は大きく能力を変える。
ある場所では無能だったが、他では素晴らしく活躍する、ということが普通にある。
そのようにして、配置を変えた結果、また評価のあがる人もたくさんいた。
しかしそこでも仕事をきちんとしない人が、どうしてもいる。もう、これはどうしようもない。
その場合、会社は「もうあなたのできる仕事は、この会社にはない」と告げる。
合わせて、「他社であれば、あなたの活躍できる場所があるかもしれない。」とも告げる。
これで殆どの社員は納得して辞めていく。
中には「これだけ面倒を見ていただいたのに、会社の期待に応えられず、申し訳ない」
といって辞めていく人もいる。
重要なのは「尊厳」
この会社が気をつけていたのは、やる気がある限りは、クビにしないこと。
そして、仕事ができないからといって、社員を馬鹿にするような態度を決して取ったりしないことだった。
人は、バカにされれば、むしろ「やり返してやろう」と思い、会社と険悪な関係になってしまう。
企業は福祉を担うことはできない。だから、無用の人物は解雇せざるを得ないが、しかし、その場合であっても、人としての「尊厳」は守る。
ウチではだめだったが、ほかでは活躍できるという可能性を告げる。
(努力を怠っていたとしても)あなたは、あなたなりに確かに努力していたと認め、ただし、ウチが社員に求める水準には達していないということを素直に告げる。
会社が何度もチャンスを与えれば、結局、彼の適性は本人の知るところとなる。
あとは、どのように送り出すか。
それだけの問題だ。
だが、そういうささやかなプライドを踏みにじると、「法廷」で争うハメになり、結局誰も得をしない。
[adrotate group="46"]
【著者プロフィール】
安達裕哉
生成AI活用支援のワークワンダースCEO(https://workwonders.jp)|元Deloitteのコンサルタント|オウンドメディア支援のティネクト代表(http://tinect.jp)|著書「頭のいい人が話す前に考えていること」88万部(https://amzn.to/49Tivyi)|
◯Twitter:安達裕哉
◯Facebook:安達裕哉
◯note:(生成AI時代の「ライターとマーケティング」の、実践的教科書)
〇まぐまぐ:実務で使える、生成AI導入の教科書
[amazonjs asin="4478116695" locale="JP" tmpl="Small" title="頭のいい人が話す前に考えていること"]
Photo:Gadiel Lazcano
先日、高市総理を映すニュース動画を観ていて、とても驚くことがあった。
総理就任後、外交デビューとなるASEAN首脳会議に向かう時のこと。
政府専用機に乗り込む高市氏は、タラップを昇ったところで足を止め、敬礼で出迎える航空自衛官に答礼を返した。地上のカメラに向かって手を振るよりも前にだ。
さらに機内で待ち受ける、おそらく接遇役であろう空曹(現場の中核となる自衛官)の女性、接遇の責任者であろう空将補にも頭を下げ、機内に消えていった。
「何だそんなの、人として当たり前じゃないか」
そう思われるだろうか。その通りであり、こんなことは人として当たり前のことだ。
自衛隊の最高指揮官として、軍人から敬礼を受けたなら指揮官は答礼を返す。当然のことである。
しかし実は政府専用機に乗り込む時、平成・令和の総理の多く、おそらくほぼ全員が、敬礼で待ち受ける航空自衛官を一瞥もせず機内に入るのが普通だった。
唯一、故・安倍元総理がそのような所作をされているのを見たことがあるくらいだ。
思えば高市総理は、就任後初の記者会見の際にも記者が所属と名前を名乗った際、一人ひとりに必ずこう返していた。
「お疲れ様です、どうぞよろしくお願いします」
時にやや強引さを感じるくらいであったが、それくらいに「礼を尽くす」ことにこだわりがあるのだろう。
それを政府専用機に乗り込む際にも、自然体で示した形だ。
そんな出来事をみて、もう6年以上も前の、苦々しい記憶を久しぶりに思い出した。
「心からのお祝いを申し上げます」
もう6年以上も前の話、陸上自衛隊のある最高幹部の退任記者会見に出席したことがある。
防衛大学校時代から通算し、40年もの長きに渡る自衛官・自衛隊員生活の最後の日だ。
18歳で国防を志し、以来誰よりも努力し汗をかき最高幹部にまで昇りつめた日々を思うと、取材する立場であっても胸にくるものがある。
そんな感慨を覚えつつ記者会見が始まると、やはりというか案の定というか……。
全国紙やテレビの記者たちは、こんな質問をぶつけはじめた。
「〇〇の問題はまだ解決してないと思うのですが。未解決で離任する心境をお聞かせ下さい」
「先日発生した、XX駐屯地での不祥事について、どのようにお考えですか」
口調はケンカ腰であり、怒らせようとしていることが明らかな言葉選びだ。
自衛隊批判、自衛官批判、最高幹部への個人攻撃など、記者個人の“お気持ち表明”に近く、およそ退任記者会見で聞き出すべきバリューのある質問など、一切ない。
そんな空気感にややイラつきつつ、記者会見は進み所定の時間になる。
「他に質問のある方はいらっしゃいますか?」
進行役の自衛官がそう会場に問いかけたところで、どうしてもこのまま終わらせたくなかった私は最後に挙手をした。
なお小規模な記者会見ではあらかじめ、質問をする記者は主催者側から割り当てられていることが多い。
式典の時間も限られていることから、その役目は全国紙の記者やテレビ局などの、メジャーな立場の人ばかりだ。個人やフリーの記者はその役目をもらえないし、挙手をしても発言の機会はない。
そんな事はわかっていたが、どうしてもこのまま終わらせたくなかった私は、横紙破りなことはわかりつつも挙手し最高幹部を見詰める。
一瞬キョトンとする進行役の自衛官。最高幹部は、進行役の方をみると軽く頷くような素振りを見せた。
おそらく「質問させてやれ」という意味なのだろう。
指名を受け、立ち上がりマイクを握る。
「総監、ご質問に先立ち、ご退役に際してのお祝いを申し上げます。そして、40年もの長きに渡り国防に捧げられた人生に、心からの敬意と感謝を申し上げます」
時に総監の目を見つめながら、時に会場にいる“クソメディアのクソ記者”の方にも目を向ける。
(お前ら、厳しい質問をするのは当然にしても、まず人としての礼儀くらい尽くせ!)
もっとも、どいつもこいつもカエルのツラにションベンであったとは思うが。
質問に立った記者の誰一人として、この程度の礼も尽くさなかった。ただそのことが、腹立たしかった。
だからこそそう前置きし、一呼吸空け、改めて質問を始める。
「自衛官のなり手不足が深刻な問題になりつつあります。国防に深刻な影響を与えかねない事態になる可能性もあるかと思います。どうすれば若者が自衛官を目指してくれるようになるとお考えか。ご退役の日にあたり、自衛官という職業の魅力とあわせてお聞かせ下さい」
総監は少し意外そうに、しかし柔らかな笑顔を作りながら話を聞き終わると、予定外の質問にもかかわらず丁寧に応えた。
「まずは、お祝いのお言葉に感謝申し上げます。国民の皆様のご理解とご協力があってこその任務でした」
一呼吸置き、本題に移る。
「自衛官のなり手不足について、深刻に捉えております。若者にお伝えしたいこと、お伝えしたい魅力はたくさんありますが、時間も限られているので簡潔にお答えします。自衛隊には、本気の想いに応える仕組みがたくさんあります。やりたいと思えること、やりたい仕事が、必ずあります」
心做しか、先程までの鋭い目力が消え去り、柔和にさえ感じられる。
あるいは、長かった自衛官生活に思いを馳せながら、お話しして下さっているのだろうか。そして思いのほかたくさんのことをお話しされると、こう締めくくった。
「ひとことで言うと『自衛隊は良いぞ!興味があるなら、まずは飛び込んできて下さい!』です。私自身、本当に幸せな自衛官生活でした」
そして記者会見を終え栄誉礼・離任式に移り、音楽隊の演奏などを経て、見送り行事が始まった。
もうここまでくれば、記者など誰ひとりいない。私だけだ。
栄誉礼の会場には一人だけ地元紙の記者が来ていたが、式典が始まると興味なさそうに、すぐに出ていってしまった。いったい記者たちは何を取材して、何を読者に伝えたいのか。
見送り行事も終わると、特別に許可を頂いていた総監の最後の公式行事、「殉職自衛官の慰霊碑参拝」まで同席させて頂く。
先程までのたくさんの自衛官・自衛隊員の見送りと違い、慰霊碑の参拝は副官だけを携えた、総監と令夫人お二人だけによる行事だ。夏の終わり、蝉の声だけが聞こえる厳かな空間で、背筋を伸ばしながら写真を撮り、遠くから取材させて頂く。
そして全ての行事を終えて専用車に乗り込まれようとしたその時、突然副官がこちらに駆け寄ってくると、こんなことをいった。
「総監が少しお話ししたいそうです。来て頂けますか?」
一体何事なんだと、慌てふためき走り寄る。
この時あまりにも慌ててしまい、総監のおそばまでいったところで足を滑らせ盛大にすっ転んでしまった(泣)そんな私に手を伸ばし、笑いながら引っ張り起こすと総監は短く一言、こんな事を言った。
「桃野さんのこと、以前から存じ上げています。これからも自衛隊をよろしくお願いします」
そして握手を求めて下さり、車に乗り込んで慰霊碑を後にした。
残された私の右手には、なにやら違和感。手のひらをみると、そこにあったのはチャレンジコインだった。
チャレンジコインとは、高位にある軍人が親愛の情を込めて、部下や友人に渡す記念コインだ。おそらく総監の、自衛官生活最後のチャレンジコインだろう。ただただ深く感動し、目から汗があふれる。
それから6年以上の月日が経った。
今、元総監は私にとって自衛隊に関したくさんのことを教えてくださる、かけがえのない飲み友達だ。
何を見せられてるのか
特別なことなど、何一つしたことはない。
基本的に自衛隊を応援する立場ではあるが、だからこそ自衛隊の不祥事を厳しく批判することも少なくない。
しかしそんな時にこそ、礼儀や礼節、品位を欠くようなことは絶対にしない。
ひるがえって今、高市政権を批判するメディアと野党はどうか。
聞くに耐えないヤジを正当化する、野党第一党の議員。
「(高市総理に)死んでしまえと言えばいい」と言い放った、有名ジャーナリスト。
そんな野党議員やメディアなど、多くの国民から嫌悪感を持たれて当然だろう。ロジックや知性に基づく議論ではなく、感情的に喚くだけの批判は、共感や納得に程遠いからだ。
言ってみれば、モンスタークレーマーが飲食店の店員さんにブチギレているのと同じレベルの行為を“報道”と称し、“政治”であると開き直っている様を国民は見せられているのである。
ただただウザイに決まってるではないか。
批判という行為は、知性と知識、品位があってこそオーディエンスの納得と共感を得られるものだ。
そしてそれ以上に大事なのは、立場や役割が違う人に対するリスペクトに他ならない。敬礼で出迎える自衛官に、カメラに手を振るよりも先に答礼を返す “人として当然”の礼節である。
この程度のこともできない野党やメディアこそが今、日本の民主主義を危うくしている。
意味のある権力批判をすべき勢力として、まったく機能していないからだ。
大株主や取締役、監査役が無能であれば、経営トップは間違いなくロクでもない事をやり始める。
同様に、メディアや野党など権力を監視すべき勢力に知性や知識、品位が無ければ、政府はやりたい放題になるだろう。
高い支持率を得ている政権と対峙するためにこそ、その重い役割を再認識して欲しいと願っている。
[adrotate group="46"]
【プロフィール】
桃野泰徳
大学卒業後、大和證券に勤務。
中堅メーカーなどでCFOを歴任し独立。
主な著書
『なぜこんな人が上司なのか』(新潮新書)
『自衛隊の最高幹部はどのように選ばれるのか』(週刊東洋経済)
など
ガラにもなく偉そうなことを書いてゴメンナサイ!
> <;
仕方がないのでお酒を飲んで寝ます!
> <
X(旧Twitter) :@ momod1997
facebook :桃野泰徳
Photo:Therese Garcia




