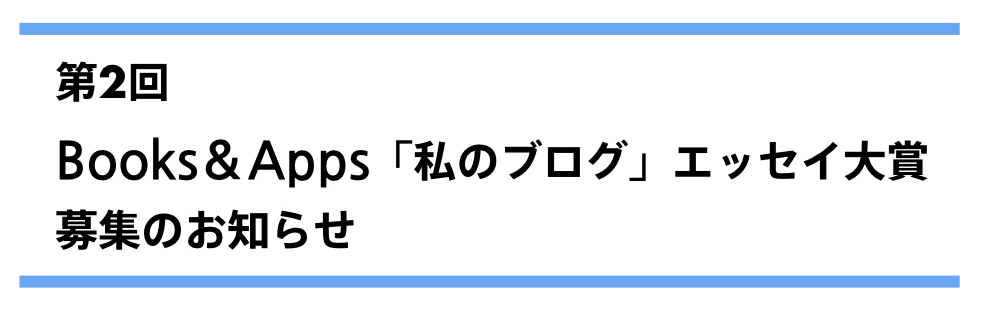少し前に大学の同級生とご飯を食べ、かつての級友たちがどうなったかについて色々と情報交換を行った。
学生時代からとても興味があった事の1つに、学校の成績と就労後のパフォーマンスがどう比例するかというのがあった。
かつての秀才達は、今も出世頭なのだろうか?その答えはまだ卒後して数年しかたってはないが、意外とハッキリと出つつあった。
「そういえば、あのパチンコばっかり打ってた奴はどうしたん?」
「あー、あいつは今、救命救急センターでバリバリ働いているわ」
「んじゃ、学年トップクラスだったあの人はどんな感じよ?」
「・・・実はあいつ、いろいろあって心の病をやっちゃって、一回ドロップアウトしたんだ。風のうわさによると、今はフリーでアルバイト医として月に数日だけ働いているらしい。もったいないよね・・・あんなに頭よかったのに」
勉強ができるにも3つのパターンがある
こんな感じで、いろいろな人を分析していった結果みえてきた現実がある。それは一口に勉強ができるといっても、3つのパターンがあったという事だ。
1つ目のパターンは「本人の能力自体が異常に優れていたパターン」だ。このタイプの人間は、本人の能力が非常に高いが故に受験勉強を難なくこなした結果、とんとん調子で医学部に入学した人が多い。
特徴をあげると、多少難しい事でも教科書を一度読んだだけで全部理解できたりとか、いわゆる地頭がいい連中だ。
これらの人達の多くは、いわゆる出世コースを歩んでいた。能力値が高いが故に本人のパフォーマンスが高く、医師として働きつつ論文をバンバン書いたりしている。
2つ目のパターンは、目標に向かって努力ができるタイプのパターンだ。
この人達は、いわゆる嫌なことに対する我慢適性が比較的高く、また必要な時は勤勉になれるタイプである。
特徴をあげると、いわゆる苦学生で、あんまし頭はよくないのだけど、医者になるために必死で努力して無理やり受験勉強を乗り越えてきた人といえる。
これらの人達は、能力がそこまで優れているわけではない。だが、タフネスもメンタルもそこそこ強く、現場で安定した労働力として非常にありがたがられていた。
出世頭ではないけれど、みんな立派に医師として地域の基幹病院で働いているようだ。
そして3つ目のパターンは、勉強自体が好きなパターンだ。
この人達は、いわゆる机に座って本を読んだり、学校の授業を受けるのが好きなタイプの人である。彼らは”勉強自体”が好きなので、成績がとてもよく、その結果医学部入試もそこまで苦労することなく突破し、また学生時代もコツコツ勉強をしていたから成績がとてもよかった。
この手の人達は、学生時代は教師陣から非常に好かれていた。いつも真面目に最前列に座って授業をうけていたし、授業後に質問にいったりして、個人的に可愛がられていた人も多かったと記憶している。
僕は学生時代、彼らをみて「まさに好きこそものの上手なれ」だなぁと羨ましく思ったものだった。あんなに勉強が好きなのだから、きっと卒業後も最先端の知識を使って素晴らしいパフォーマンスをあげるのだろうと思っていた。
だが、現実は非情である。この条件に該当する人達が実は医師としてドロップアウトした率が一番高かった。
なぜ、彼らは現場を脱落してしまったのだろうか?僕が思うに、その原因は勉強自体が好きだったからである。以下、どういうことかみていこう。
慶応の野球部卒業生の就職先が凄い理由
前にネットで慶応の野球部卒業生の就職先が凄いと話題になった事があった。
確かにこれをみるに、ほとんどの学生が有名企業への就職を決めている。彼らがなぜ企業から好まれるかといえば
①慶応に入学しているという時点で、そこそこの知的ポテンシャルがある事
に加え
②野球部というハードな練習に4年間耐えきった
という実績を買われているからだろう。
実のところ一部の職種を除いて、サラリーマンにはそこまで高度な知的技能は求められない。
会社で相対性理論を使うことなどまずないし、高等数学のような理解するだけで何ヶ月もかかるような知的労働に取り組む機会はほぼ無い。
サラリーマンに求められてるのは、上司の指示を理解して、設定された期間内に仕事をあげる事ぐらいである。あとは、しっかりと数年間仕事にコミットさえしてくれれば、何も文句はない。
究極的にいえば、労働者のパフォーマンスは
「能力値」×「目標に向かって我慢できる値」
で決まる。この事を念頭に、先の頭の良さの3分類をみていこう。
労働者のパフォーマンスは「能力値」×「目標に向かって我慢できる値」で決まる
1つ目である本人の能力自体が異常に優れているパターンだが、これはイソップ童話のカメとウサギにおけるウサギみたいなものだ。能力が高いから、特に苦労なくポンポンアウトプットを出す。
苦労もそこまでしないので、仕事における心労や肉体的疲弊も少なく、結果として「能力値」×「目標に向かって我慢できる値」が常に高い。
2つ目である目標に向かってコツコツ努力ができるタイプはイソップ童話のカメとウサギのカメだ。能力はまあまあだけど、我慢適性が非常に高く、気合と根性で最終的にはゴールにちゃんと辿り着く。
企業が体育会系を好むのは「目標に向かって我慢できる値」が高いからに他ならない。
というかそれを証明する為に、わざわざ4年間もの間、青春を部活に捧げてる人だって当然いるだろう。彼らが好まれるのは、当然の結果だ。
3つ目の勉強自体が好きなパターンだけど、これは本当に不幸だ。実は働くと、勉強というのはメインではなくなる。
あくまで勉強は自己研鑽として取り組む副次的なものであり、労働における最も大切なものはオン・ザ・ジョブ・トレーニングである。机の上ではなく、現場が一番の先生なのは労働者なら誰だってわかっているだろう。
彼らは勉強が「好き」だから、受験生時代や学生時代は成績が凄くいいけど、あくまでそれは「能力値」が高いからではなく、単にかけてる時間が多いからに他ならない。
また、勉強が「好き」だから比較的苦もなく勉強し続けられたけど、逆にいえばそれは嫌なことでも「目標に向かって我慢していた」わけではない。
結果、嫌なことでも必要であればやる、という覚悟があまり育たず、おまけに働き始めて好きだった勉強もできなくなってしまい、見事にドロップアウトする。
ウサギにもなれず、かといってカメにもかれない彼らの未来は割と悲惨だ。
僕は学友と話した帰り道、自分が心底勉強が嫌いで本当によかったと妙に感心してしまった。あの血の滲むような努力は、キチンと我慢できる能力として、巡り巡って己のためになっていたのである。
イヤイヤながらも受験勉強をやってた人間の方が労働適性が育ってたりするのだから、まったくもって人間万事塞翁が馬である。
「好きを仕事にできず潰れている人」は「好きでビジネスができていないもったいない人」
勉強が好きなのなら研究者になればいいかというと、そういうわけでもない。
研究者に必要なのはプロジェクトの企画・立案で、机に座って勉強するのとは随分と性質が異なる作業であり、研究者の適性は必ずしも勉強が好きな事とは相関関係はない。
結局、学生時代に最前列で真面目に授業をうけていたり、図書館で分厚い教科書を読んでいた学友の多くは「我慢」の必要がとても少ない楽な仕事につく傾向が多かった。
彼らの不幸は「好き」を仕事にできていないところだ。
現代の資本主義社会では、仕事は何らかの成果物を献上する事でしか成り立たない。労働力を売れるのならサラリーマンになれるし、資本を元に労働者を統率して生産を行えるのなら経営者になれる。
「勉強」はそれ単体では成果物にはならない。
実のところ「好き」を仕事にして失敗している人の多くは、それが好きなだけでビジネスモデルを全く成立させられてないところに問題がある。
例えるなら、アイドルがメチャクチャ好きなだけの人はファンとしてお金を払う位しか選択肢がないけど、秋元康さんは自身の「アイドルがめっちゃ好き」を「類まれなるプロデュース能力」と組み合わせて、しっかりビジネスをしている。
「好き」を仕事にするにあたっては、この何かプラス・アルファが凄くものをいう。
だが「勉強が好き」な人を不幸といいきるのも問題がある。
良くも悪くも、1つ目の「本人の能力自体が異常に優れているパターン」も2つ目の「目標に向かってコツコツ努力ができるタイプ」も、いわゆる「人から言われた仕事をそつなくこなしている」だけの社畜的な働き方をしているだけであって、心の底から楽しんで仕事をしているとはいい難い。
ある意味では、「勉強が好き」な人は「自分に本当の好きなもの」をみつけているという点では、サラリーマンをそつなくこなしている人よりも一歩先をいっているともいえる。
あなたは自分が本当に好きなものが何かわかっているだろうか?この作業は実は結構難しい。本当に好きなことが何なのか、よくわからないまま終わっていく人はかなり多い。
勉強自体が好きだった学校型秀才の彼らは、もう「好き」はみつけている。
あとはその「好き」を、キチンとビジネスに落とし込むという行程さえ超えられれば、人生を豊かにする為の仕事ができるようになるだろう。
だから医師社会をドロップアウトしてしまった彼らも、かつて劣等生だった僕らが受験勉強や定期試験の嵐で疲弊したのと同じように、遅れてやってきた人生の試練にキチンと打ち勝って欲しいものだね、というような事を話しっつ、学友との楽しい居酒屋漫談は終わりとなった。
あり余る能力か、我慢耐性か、好きをビジネスに結び付けられるか。
このどれかを持てた時、人はそこそこ楽しく働くことができるのかもしれない。
お互い、子供ができたら、それを教えてあげられたらいいねなんて事を語りつつ、焼き鳥を食べおわったオッサン2人は帰路につくのであった。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【プロフィール】
都内で勤務医としてまったり生活中。
趣味はおいしいレストラン開拓とワインと読書です。
twitter:takasuka_toki ブログ→ 珈琲をゴクゴク呑むように
noteで食事に関するコラム執筆と人生相談もやってます→ https://note.mu/takasuka_toki
(Photo:Tobi Gaulke)