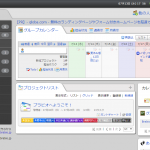よく称賛される言葉の一つに中庸というものがある。
バランスが取れているという言い方で表現する人もいるだろう。
特定の思考に凝り固まり、批判的意見もほどよく受け入れる。
これがよい立ち振る舞いだという事は、皆さんもこれまで生きてきて嫌というほど耳にしてきただろう。が、自分の知る限りこれをやれている人は超人だけである。
例えば新型コロナウイルスに対する対策で、いま現在世論は徹底した封じ込めを狙う『自粛派』と、日本人は自然状態でもRが1以下なのだから『ノーガードで大丈夫派』が喧々諤々の言い争いを繰り広げている。
時々この両者が交わる事があるが、だいたい議論は平行線である。
とてもじゃないけど、中庸なんて言葉からは程遠い。
とても興味深い事に、この両陣営ともに単純に頭の良さだけで振り分けると、それなりにどちらにも地頭が良さそうな人がいる事である。
3/11の時も似たような現象は目にしたが、またもや同じような事が繰り返されている事に僕は大変驚いた。
受験勉強や科学の世界では基本的には頭がいい人がたどり着く答えは常に同じだ。
もちろん、それは限定された条件下においての事だから、複雑な現実での意思決定とは異なるという事は重々承知してはいる。
いるのだが、この現実をみるに、どうも頭の良さというものはいつ何時も正解を叩き出せる万能な銀の弾丸ではないらしい。
それどころか下手すると誤った考え方に人を縛り続けるような呪いの作用すらありそうである。
いったい、これはどういう事なのだろうか。最近ずっと考えていたのだが、行動経済学が見事にこの事を説明していた。
確証バイアスである。
<参考文献 事実はなぜ人の意見を変えられないのか>
事実はなぜ人の意見を変えられないのか
- ターリ・シャーロット,上原直子
- 白揚社
- 価格¥2,695(2025/07/09 18:21時点)
- 発売日2019/08/30
- 商品ランキング20,313位
現代は気軽にクリック一つで自分にとって都合のいい意見を生み出せる世界
ロンドン大学の教授ターリ・シャーロットによると、実のところ今日の私達は押し寄せる大量の情報を身に受けることで、かえって自分の考えを変えないようになってきているという。
なぜなら、マウスをクリックするだけで、自分が信じたい情報を裏付けるデータが簡単に手に入ってしまうからだ。
私達は基本的には信じたいものしかみない。
人生の基本方針は自分が気持ちよくなる事である。
自分にとって都合がよくない情報をわざわざ目にしたいという欲求を持っている人は単なるマゾだ。
と、いうことはだ。
私達の信念を形作っているのは事実や科学的根拠などではなく、”欲求”なのである。
つまり、この”欲求”が変化してない状態下において、相手も自分も”考え方”が変わる可能性などありえないのである。
実は冒頭であげた僕の疑問点に関しても、既に研究によって答えがでている。
2013年に出た”Motivated Numeracy and Enlightened Self-Government,”という論文によると、分析能力が高い人の方が、そうでない人よりも情報を積極的に歪めやすい事が判明しているのだという。
改めて考えてみれば、これは確かに自明である。
推論能力に長けていて、数量に関するデータの扱いに慣れており、分析的な思考が出来る人間であれば、そういうデータをインターネットの海から出現させる事なんて朝飯前であろう。
事実や科学的根拠ではなく、”欲求”が意見を形作るモチベーションの源だという事を考えれば、誤った考えが正しい考えに修正させるだなんて事を期待するだけ馬鹿げている。
出発点も進路も間逆なのに、目的地に軌道修正が行われるだなんて事があるはずがないのである。
自分と異なった意見を前にした時、人ができるのはバランスよく意見を形成する事なんかではない。
むしろより自分の考えを先鋭化させてゆき、特定の方向に偏るのが人間という生き物なのである。
中庸は言葉では簡単に表現できるが、実行なんて並大抵の人には不可能だという事がよくわかるだろう。
TwitterのリツィートやFacebookのシェアは取り扱いが難しい
とりわけ問題を難しくしているのがSNSだ。
先程、分析能力が高い人の方が、そうでない人よりも情報を積極的に歪めやすいと書いたが、TwitterやFacebookはこれをボタン一つで簡単に加速させてしまう。
そう、リツィートやシェアである。
新型コロナウイルス問題で頭が沸騰している人のタイムラインをみにいくと、自説を裏付ける他人の意見の再共有の嵐である。
まさしく”マウスをクリックするだけで、自分が信じたい情報を裏付けるデータが簡単に手に入ってしまう”のである。
人は共感に強い価値を見出す。
あなたが家族と食事をしていて、相手が「美味しいね」といったのに対して「美味しくない」というのは、単なる意見の不一致にとどまらず相手の人格批判にまで容易にタッチする。
僕はかなり重度なグルメサイコパスなので、食事を数学の難問のように取り扱いがちなのだが、最近妻が「あんたはいっつも私の意見に同意しない!!!私のことが嫌いなのか!!!」と食卓にて大爆発し、数年遅れで食卓を挟んで行われていた会話が「建設的な意見の交換」ではなく「コミュニケーション」であった事に気がついた。
ゲーム理論では、相手がニコニコと同意を求めてきたら、自分もニコニコと同意をするのが最適解である。
そこで議論をふっかける事は戦争を仕掛ける事となんら変わりない。
相手が好意を向けてきているのだとしたら、「ん?なんかちょっと違うな」と思ったとしても全力で
「そうだね、美味しいね」
と返すのが正解なのである。
合コン「さしすせそ」は万能の鍵なのだ。
今さら聞けない!合コンの「さしすせそ」を解説します!|合コン・飲み会セッティングのRush(ラッシュ)|IBJ
合コンの「さしすせそ」をご存知ですか?
簡単に言えば合コンの「さしすせそ」とは、料理の「さしすせそ」ならぬ、女性が【男性を上手に褒める基本の言葉】のことをいいます。今回は、この合コンで使える「さしすせそ」と、上手に男性を褒めて会話を弾ませるためのコツ、使い方の注意点を自称恋愛マスターの筆者が伝授いたします。
この逆がSNSである。
異なる意見を持つ人に、自分が思う”正しい”意見をぶつけるのは、まさに我が家の食卓で僕が妻の意見に”同意しない”のと同じような効用をもたらす。
逆合コン「さしすせそ」と言ってもいいかもしれない。
人は逆合コン「さしすせそ」をぶつけられまくると、共感に強く渇望するようになる。
するとどうなるのかは昨今のSNS界隈をみていれば火を見るよりも明らかで、だいたいの人は人格が”加速”して狂化してしまう。
耳に痛い意見は伝家の宝刀だ。
お互いがお互いものすごく信用しあった関係という大前提があったとしても、抜けるのは一生に数回が限度だろう。
Twitterで議論なんて普通の人はやってはいけない。
それはゲーム理論の逆最適解なのである。
あつ森の優しい世界、SEKIROのやり直せる世界
最近、流行ってるのもあって興味がてらにNintendo Switchのあつまれ どうぶつの森(通称、あつ森)を始めたのだが、昨今のSNSに欠けた要素があまりにも満載すぎて笑ってしまった。
知らない人に簡単に説明すると、あつ森は無人島に移住し動物たちと仲良くキャッキャウフフしながら共同生活するゲームである。
シュールなものの見方をすると、タヌキチが悪徳パッケージ商品を売りつけてきて笑顔でこっちを風呂に沈めてきそうな感じもするが、まあそれはそれだ。
あつ森の世界はびっくりするほどに優しい。
みんなニコニコしてて、こちらの意見を批判してくる事なんて絶対にない。
世の中は”できる事”で満ち溢れていて、そこかしこに”小さな達成感”が満ち溢れている。
この対極ともいえるゲームがフロム・ソフトウェアのSEKIROである。
SEKIROの世界は無慈悲であり、あまりにも優しくなさすぎるのだが、現実と違って死んでもコンティニューが可能である。
その結果、プレイヤーは地獄のような試行錯誤の果てに”大きな達成感”を獲得する事ができる。
”優しさ”と”達成感”と”やりなおし可”、改めて考えてみると、現実はこの3つにひどく欠けてるよなと本当に思う。
リアル社会の気軽にタッチできる優しさには常に何らかの下心が仕込まれており、承認欲求を得ようにも並みいる強豪相手に一般人には達成感の獲得もままならず、そして間違いにも厳しい。
ネット社会のいま現在、過去の過ちはデジタルタトゥーとなって私達に襲いかかってくる有様である。
こんな世界で狂わずに中庸を歩むなんて、そりゃまあ普通の人には無理ってものだ。
けど、やっぱり狂いたくはない。じゃあどうすればいいんだって所で遊びの出番である。
例えば、あつ森やSEKIROをやり込めば、程良い感じに時間が過ぎ去る。
狂人へと”加速”してしまった人を元に戻すのは至難の業だが、ゲームで時間を程よく消費して”加速”さえしないでいられれば、勝手に世間が正しい答えを出してくれる。
封じ込めかノーガードか。
そのどちらが正しいのかなんて、普通の人がいくら無い知恵を振り絞ったところで正解は見いだせないだろう。
狂った世界から一歩距離をとって、ステイホームで時計の針が進むのを眺めるのが、多くの人にとっては最適解だ。
そして程よく時間がたった頃に、我が物顔でこういう態度をとればいいのだ。
「僕は最初からこっちが正しい答えだと思ってましたけど、世間がそれを証明してくれましたね」
ってね。
後出しジャンケンは絶対に負けない最強のカンニングなのである。
【安達が東京都主催のイベントに登壇します】
ティネクト代表・安達裕哉が、“成長企業がなぜ投資を避けないのか”をテーマに東京都中小企業サイバーセキュリティ啓発事業のイベントに登壇します。借金=仕入れという視点、そしてセキュリティやDXを“利益を生む投資”とする考え方が学べます。

ティネクト代表の安達裕哉が東京都中小企業サイバーセキュリティ啓発事業のイベントに登壇します。
ティネクトでは現在、生成AIやマーケティング事業に力を入れていますが、今回はその事業への「投資」という観点でお話しします。
経営に関わる全ての方にお役に立つ内容となっておりますでの、ぜひご参加ください。東京都主催ですが、ウェビナー形式ですので全国どこからでもご参加できます。
<2025年7月14日実施予定>
投資と会社の成長を考えよう|成長企業が“投資”を避けない理由とは
借金はコストではなく、未来への仕入れ—— 「直接利益を生まない」とされがちな分野にも、真の成長要素が潜んでいます。【セミナー内容】
1. 投資しなければ成長できない
・借金(金利)は無意味なコストではなく、仕入れである
2. 無借金経営は安全ではなく危険 機会損失と同義
・商売の基本は、「見返りのある経営資源に投資」すること
・1%の金利でお金を仕入れ、5%の利益を上げるのが成長戦略の基本
・金利を無意味なコストと考えるのは「直接利益を生まない」と誤解されているため
・同様の理由で、DXやサイバーセキュリティは後回しにされる
3. サイバーセキュリティは「利益を生む投資」である
・直接利益を生まないと誤解されがちだが、売上に貢献する要素は多数(例:広告、ブランディング)
・大企業・行政との取引には「セキュリティ対策」が必須
・リスク管理の観点からも、「保険」よりも遥かにコストパフォーマンスが良い
・経営者のマインドセットとして、投資=成長のための手段
・サイバーセキュリティ対策は攻守ともに利益を生む手段と考えよう
【登壇者紹介】
安達 裕哉(あだち・ゆうや)
ティネクト株式会社 代表取締役/ワークワンダース株式会社 代表取締役CEO
Deloitteにてコンサルティング業務に従事後、監査法人トーマツの中小企業向けコンサル部門立ち上げに参画。大阪・東京支社長を経て、2013年にティネクト株式会社を設立。
ビジネスメディア「Books&Apps」運営。2023年には生成AIコンサルティングの「ワークワンダース株式会社」も設立。
著書『頭のいい人が話す前に考えていること』(ダイヤモンド社)は累計82万部突破。2023年・2024年と2年連続で“日本一売れたビジネス書”に(トーハン/日販調べ)。
日時:
2025/7/14(月) 16:30-18:00
参加費:無料
Zoomビデオ会議(ログイン不要)を介してストリーミング配信となります。
お申込み・詳細
お申し込みはこちら東京都令和7年度中小企業サイバーセキュリティ啓発事業「経営者向け特別セミナー兼事業説明会フォーム」よりお申込みください
(2025/6/2更新)
【プロフィール】
都内で勤務医としてまったり生活中。
趣味はおいしいレストラン開拓とワインと読書です。
twitter:takasuka_toki ブログ→ 珈琲をゴクゴク呑むように
noteで食事に関するコラム執筆と人生相談もやってます→ https://note.mu/takasuka_toki
Photo by:Peter Shanks