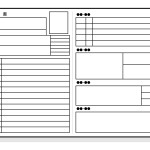ジェンナーは「使用人の息子」で人体実験していた
池上彰さんの『社会に出るあなたに伝えたい なぜ、読解力が必要なのか?』(講談社+α新書)という本のなかで、こんなエピソードが紹介されています。
極めつけはエドワード・ジェンナーです。ジェンナーは18世紀末に、致死率が20~30%にも上る感染症「天然痘」の免疫を作るために、牛の天然痘だけれども人間は罹っても軽症で済む「牛痘」に着目。
牛痘に罹った人間の膿疱から得た液を腕に摂取し、免疫を作るという「牛痘種痘法」を開発した人物です。このおかげで、天然痘は1980年に世界保健機関(WHO)によって根絶宣言が出されるに至りました。
しかしこの牛痘種痘について、子どもの頃に読んだジェンナーの伝記では「わが子に最初に摂取した」と書いてあったのですが、大人になって調べてみたところ、最初はわが子ではなく、なんと使用人の息子に摂取していたのです。なんて最低の人なんだ、と思ったものです。
これは、「伝記」を読むと、偉人たちの意外な面がわかることもある、という話の一例として挙げられているものです。
僕も子どもの頃に、「ジェンナーは牛痘の効果を証明するために、自分の子どもでその実験をした」というのを聞いて、ジェンナーの覚悟に感銘を受けたのと同時に、こういう人の身内って大変だなあ、とも思いました。
「本当は使用人の子どもで試してみた」というのを聞いて、「ひどい話ではあるけれど、子どもの親としては理解はできる」と、けっこう納得したというか、「まあ、そういうものだよね」という気がしたのです。
「使用人」に対する感覚が違う時代の話とはいえ、「ひどい」のは事実だとしても、じゃあ、自分の子どもだったら良いのか?とも思いますし。
たぶん、「子どもは親の所有物じゃない」という考え方が、僕が子どもの頃よりもずっと当たり前のものになっている影響もあるのでしょう。
僕自身も、子どもよりも親の気持ちを想像しやすい立場と年齢になりました。
結局のところ、ジェンナーにとって正しい実験方法とはどういうやりかただったのだろうか?
現代のような「治験のルール」ができあがっていない時代として考えると、現代人も納得できるのは、「自ら実験台になる」ことですよね。
しかしながら、それでもし、結果的にジェンナーが命を落としたり、致命的なダメージを受けたら、「種痘」という多くの人を天然痘から救う技術は失われるか、大きく後退することになってしまったはずです。
「人はみな平等である」はずなのだけれど、ジェンナーは、医学の進歩に貢献し、より多くの人を救うため、自ら実験台になるべきだったのか?
医師は『替えが用意しにくい』
新型コロナウイルスへの感染が拡大していくなかで、医療関係者も「患者さんとなるべく身体的な接触を減らす」ことを心がけるようになりました。
ただでさえ、体調が悪い人と接する機会が多い仕事なので、無症候性感染を含め、コロナ罹患の可能性は高いし、もし感染したら、身体が弱っている大勢の患者さんたちにうつしてしまう危険性が高いので。
新型コロナウイルス感染者の病室には外部の業者に入ってもらうことができないので、病棟の看護師たちが部屋の消毒や清掃をすべてやることになり、過剰な労働で疲弊しきっている、というのが、先日、NHKの番組で採り上げられていました。
ある病院でのコロナ対策会議では、「新型コロナウイルスに感染している、あるいは感染が疑われる患者さんと医師の直接の接触は必要最低限にして、タブレット端末を利用したり、患者さんと離れたところから看護師に指示したりして、感染のリスクを極力避けるように」というお達しが出たそうです。
それに対して、看護師サイドからは、「なぜ、自分たちよりも高い給料をもらっていて、感染予防の知識も十分あるはずの医者が最前線を避け、自分たちばかりが安い手当てでリスクを負わなければならないのか」という疑問が出ていたのです。
病院上層部の回答は「気持ちはわかるが、小さな病院で医者がひとり感染したら病院の機能は麻痺してしまうし、休むことになったら、この状況下で代わりの医者を見つけるのは難しい。病院の運営・維持のために、申し訳ないけれど我慢してほしい」というものだったと聞きました。
僕も医者の端くれとして、モヤモヤするんですよとても。
新型コロナ感染のリスクは極力避けたいけれど、「替えが用意しにくい存在だから」という理由で、専門家であるにもかかわらず、高給をもらいながら司令部で偉そうにしているというのは、あまり気分の良いものではありません。
ノブレス・オブリージュ的な考えでいけば、医者こそが最前線に立つべきなのではないか。
とはいえ、「リスク管理」とか「コスト意識」みたいなものを考えると、「いざというときに指揮をする人間がいなくなり、組織が回らなくなるから、医者はなるべく感染のリスクが低くなるように『温存』すべきだ」というのは、合理的ではあるのです。
僕の愛読書の『銀河英雄伝説』で、自由惑星同盟のヤン・ウェンリー提督はつねに前線で艦隊を率いています。
ヤン提督が、作品中唯一の直接会談の場面で、同じように自らを危険にさらすことを厭わない帝国軍のラインハルト・フォン・ローエングラムの姿勢を称賛する場面があるのです。
僕はそれを読んで「確かに、指揮官というのはそうあるべきだ」って思ったのですが、歴史というのを学んでみると、勇将・名将と呼ばれた人たちが、戦闘のなかで流れ弾に当たって命を落とした、あるいは、重症を負って指揮をとれなくなったことによって、戦況が変わって率いていた軍が敗れた、という事例はけっこうあるのです。
大坂夏の陣での真田信繁は、その「一発逆転」を狙って、家康の本陣に突撃していきました。
戦争では、戦況が行き詰まっても、指揮官は最後まで生き残っていることが多いのですが、それも、結局のところ「指揮官がいないとまともに戦えなくなるので、みんなが指揮官を守ろうとするから」なんですよね。
指揮官自身も「自分が前線に出るリスク」を考えてしまうのでしょう。
軍隊なら上官が絶対でも致し方ないのかもしれませんが、医療の現場で、こういう「あからさまなまでの優先順位の設定」に直面すると、本当にそれで良いのだろうか?と考えこまずにはいられません。
新型コロナとの闘いは、「戦争」なんだ、と言われれば、そうなのかもしれませんが……。
ジェンナー自身は、「使用人の子どもで牛痘の実験をする」ことに対して、どう思っていたのだろうか?
単純に自分がやるのは嫌だったのか、あるいは、自分自身を実験台にできるものなら、そうしたかったのだろうか。
でもそれは、大局的にみれば「社会全体の不利益」になってしまう面はあるのです。
ピロリ菌の発見は「自分への人体実験」の産物
医療の歴史のなかでは、「セルフ人体実験」をやった人というのは、けっこういるのです。
『世にも奇妙な人体実験の歴史』(トレヴァー・ノートン著、赤根洋子訳、文藝春秋)という本では、こんなエピソードが紹介されています。
1804年、アメリカ人の医学生スタビンス・ファースは、黄熱病が伝染するかどうか確かめようと決意した。彼は、「黒い吐瀉物」を吐いている患者に添い寝し、「患者の息が確実に自分の顔にかかるように」した。しかしこれは、彼の壮絶な自己実験の始まりに過ぎなかった。
黒い嘔吐物は万人受けするものではないが、ファースは嘔吐物をとろ火で煮てその蒸気を吸入した。吐き気のためについに我慢できなくなるまで、数時間にわたって吸入し続けたのである。患者の嘔吐物を犬に注射してみたところ、その犬はわずか数分で死んでしまった。にもかかわらず、彼は自分の血管に嘔吐物を注射し、両腕を深く切開してその傷口にも注入した。体に患者の血液、汗、尿を塗りつけ、患者の唾液、血液、嘔吐物を飲んだ。ブラックプディング(訳注:牛の血を固めて作ったソーセージ)でさえお代わりはお断りしている私としては、黒い吐瀉物に対するファースの食欲には頭が下がるばかりである。
こうまでしても黄熱病に感染しなかったので、彼は論文にこう書いている。「黄熱病が接触感染によって人から人に移るかどうかがはっきりしないために、黄熱病に多大の恐怖を抱いている人もいるが、これらの実験によってその恐怖は和らげられるものと思う」
これだけの苦痛を耐え忍んだにもかかわらず、彼の実験結果はほとんど注目されなかった。黄熱病の病因が明らかになったわけではなかったからである。
よくぞここまで、というか、もう、そういう性癖の人なのでは……とさえ思えてくる話です。
とはいえ、これは200年以上も前の話ですし、「セルフ人体実験」なんて、過去のマッドサイエンティストたちの遺物、だと僕も思い込んでいたのですが、こんな比較的最近の事例も紹介されているのです。
1980年代前半、オーストラリアの微生物学者バリー・マーシャルは病理学者のロビン・ウォレンと共同で、人間の胃の中に生息している細菌を研究していた。彼らは、ヘリコバクター・ピロリという種類の細菌が十二指腸潰瘍患者からは100パーセント、胃潰瘍の患者からも75パーセントの割合で見つかることを発見した。この細菌が十二指腸潰瘍や胃潰瘍の発症に関与しているのだろうか。
これを検証するため、マーシャルはチューブを自分の喉から胃に差し込み、胃壁の組織を採取した。これを検査し、彼の胃には潰瘍もピロリ菌も存在しないことを確認した。胃壁が回復するのを待って、彼はピロリ菌の培養液を飲み込んだ。
もちろん、事前に予防策はとってあった。つまり、実験許可が下りないとまずいので病院の倫理委員会には伝えなかったし、妻にも事後報告しかしなかったのである。いずれにせよ、数日のうちに彼がぐったりして嘔吐し始めたとき、妻に気づかれた。彼にとって踏んだり蹴ったりだったのは、息が「ひどく臭い」ことを妻に指摘されたことだった。胃の組織を検査してみると、潰瘍の前段階である強度の炎症(胃炎)が見つかった。
幸い、抗生物質を服用すると症状は消失した。マーシャルとウォレンはその後も研究を続け、ピロリ菌を除去すると胃潰瘍の症状が数日で消失すること、何十年来の胃潰瘍でさえ治癒に向かうことを証明した。しかし、この治療法が先進諸国の病院で広く行われるようになるまでには、マーシャルの実験から13年の年月が必要だった。その間、何十万人もの患者が間違った薬を処方されたり不必要な手術を受けさせられたりしたのである。
当初、批判者たちは胃潰瘍が感染症だとする説を一笑に付した。胃潰瘍の原因は化学的なアンバランスだと誰もが信じていたからである。胃の中に細菌がいるという説については、強酸性の胃の中で細菌が生きられるはずはないとされた。おそらく決定的だったのは、当時マーシャルが研修医で、彼もウォレンも胃腸科専門医ではなかったことだった。専門家でもないのに何が分かる、というわけだった。
専門家が一笑に付したその発見に対して、2005年、ノーベル生理学・医学賞が授与された。
いまでは多くの人に知られている「ピロリ菌」は、こんな経緯で発見されたのです。
いちおう、付記しておきます。
「マーシャルの実験から13年間の年月が必要だった」ことについて、著者は「医学の世界の権威主義」だけが原因のように書いていますが、マーシャルさんひとりに対する実験結果が、一般の患者さんに行える、安全性の高い治療に反映されるまでには、このくらいの時間がかかるのは、当然ではなかったかと思います。学会の権威云々じゃなくて。
「結果論」からいえば、13年は長い、ということになってしまうのでしょうけど。
少なくとも、いまから40年前には、「セルフ人体実験」で大きな成果をあげた研究者がいるのです。
著者によると、バリー・マーシャルさんは、自己実験を行った理由について「同意できるほど充分に説明を受けている人間は、私しかいなかったから」と語っていたそうです。
いま、ルールにのっとって行われている「治験」にしても、動物実験を経ての最初の人間での試験は「健康な人にその薬を使用して、害がないかどうかを確かめる」ことになっています。
いちおう、善意のボランティアが参加している、ということになっているのですが、「部屋にとじこめられ、血液検査などを受けるだけでかなり稼げる治験のアルバイト」の話を聞いたことがある人は多いはずです。
そういう、報酬で人を集めるようなやり方が正しいのかどうか。
とはいえ、研究者たちが毎回セルフ人体実験をやるというわけにもいかないですよね。
リスクはあるし、研究を進める効率も悪くなるでしょうし。
ジェンナーは、セルフ人体実験をやるべきだったのか?
医者は、それでもいちばん危険な最前線に立ち続けるべきなのか?
モラルや職業倫理に従うことと、組織や社会全体の「生産性」みたいなものが衝突するとき、人は、どちらを選ぶのが正しいのだろうか?
生成AIの運用を軸としたコンサルティング事業、メディア事業を行っているワークワンダース株式会社からウェビナーのお知らせです
 <2025年1月21日実施セミナー>
<2025年1月21日実施セミナー>生産性を爆上げする、「生成AI導入」と「AI人材育成」のコツ
【内容】
1. 生産性を爆上げするAI活用術(安達裕哉:ワークワンダース株式会社 代表取締役CEO)
2. 成功事例の紹介:他業種からAI人材への転身(梅田悟司:ワークワンダース株式会社CPO)
3. 生成AI導入推進・人材育成プログラム「Q&Ai」の全貌(元田宇亮:生成AI研修プログラム「Q&Ai」事業責任者)
4. 質疑応答
日時:
2025/1/21(火) 16:00-17:30
参加費:無料
Zoomビデオ会議(ログイン不要)を介してストリーミング配信となります。
お申込み・詳細 こちらウェビナーお申込みページをご覧ください
(2024/12/6更新)
【著者プロフィール】
著者:fujipon
読書感想ブログ『琥珀色の戯言』、瞑想・迷走しつづけている雑記『いつか電池がきれるまで』を書きつづけている、「人生の折り返し点を過ぎたことにようやく気づいてしまった」ネット中毒の40代内科医です。
ブログ:琥珀色の戯言 / いつか電池がきれるまで
Twitter:@fujipon2
Photo:Otis Historical Archives National Museum of Health and Medicine