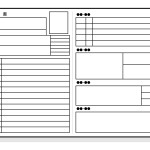ネットの風は、ときにぞっとするほど世知辛い。
2022年2月の上旬に巻き起こった、イタリアンファミリーレストラン「サイゼリヤ」を巡る話題もそうで、「サイゼリヤに男性が女性をデートに連れていく」という行為を巡ってさまざまな人が意見を述べ、ちょっと政治的なステートメントを表明したりして盛況だった。
くだらない話のように見えて切実なテーマだったから、話題の連鎖反応が起こったのだろう。
とはいえ、これ自体は長くネットを眺めている人には既出の話題ではある。
そうしたなかで私がしみじみと感じ入ったのは、以下のような枝葉の議論についてだ。
「高過ぎず気取ってなくて居心地のいいそこそこセンスのある美味しいお店」を探索・提示できる能力って、まさに文化資本ど真ん中としか言いようがない。尤も、どの分野でも「コストがかかりすぎず気取ってなくて居心地良くてセンスのある○○」って文化資本ど真ん中だよね。それらを認めたうえで文字数
— p_shirokuma(熊代亨) (@twit_shirokuma) February 13, 2022
サイゼリヤはアリかナシかで骨肉の争いをする人々をよそに、話題の周縁には「高すぎず気取ってなくて居心地のいいそこそこセンスのある美味しいお店」がベストであると指摘し、その必要性を簡潔に語る人々がいた。
いや、まったく。そのようなお店を知っていて、難なく提示できる人なら初回のデートもバッチリだろう。
いや、二回目三回目のデートの時も、PTA役員との昼食会や編集者との打ち合わせの時にもそのノウハウは役立つに違いない。
後でも触れるが、「高過ぎず気取ってなくて居心地のいいそこそこセンスのある美味しいお店」を知っていること・識別できることは、その人の人脈可能性やパートナー可能性、経済的可能性すら影響する。
ならば、それを文化資本と呼ぶのは間違っていないはずだ。
そういうお店をすぐさま挙げられる人、知らない街でもそういうお店を嗅ぎ分けられる人は、食文化に関するアドバンテージを持っているぶん、社会適応にプラスの影響を受けるし、そうでない人は社会適応にマイナスの影響を受けることになる。
仕方のないことではある。上掲ツイッターにも記したように、これは食文化に限った話ではない。
およそ、文化とか教養とか名付けられるもの全般にも当てはまるものだ。
そうやって文化は、対人関係にいつも正負の影響を与える。
これまでもそうだったし、これからもそうだろう。
だから今更、「そんな不平等はなくすべき」などと言ってもはじまらない
とはいえ田舎で暮らしていると、この「食文化に関する文化資本」へ道がとても遠く、難しく感じられたりするのだ。
「スターバックスが一番センスのある」地域に住んでいる若者はどうすればいいのか
見出しで言い切ってしまった気がしなくもないが、以下、もう少し具体的に書いてみる。
地方や田舎と言ってもピンキリだが、一般論として、地方の田舎で「高過ぎず気取ってなくて居心地のいいそこそこセンスのある美味しいお店」を知り、食文化の教養を養っていくのは難しい。
たとえば私が30代の頃に滞在していたX市を思い出してみる。
X市は人口7万人ほどで、駅前よりも国道沿いのほうが賑わっている、そんな地方都市だった。
そうした地方都市にも「高すぎず気取ってなくて居心地のいいそこそこセンスのある美味しいお店」が皆無というわけではない。
たとえば居酒屋・甘味処・蕎麦屋といった特定分野に限っていえばそのようなお店があるといえばある。
ただし、それらのお店は地域に1軒だけで、同じ分野の優れたお店と比較する余地は無い。
フレンチ・イタリアン・中華は壊滅的だ。
特にフレンチは有力候補になるだろうビストロが一軒も存在せず、高値で気取ったレストランすら存在しなかった。
イタリアンと中華は国道沿いのチェーン店がたぶんベストで、駅前には美味いけれども薄汚い街中華と、ベトベトしたスパゲティを出す自称イタリア料理店があるばかりだった。
そのような地方都市に、ある日、文化の明かりが差し込んだ。
スターバックスの出店である。
出店して以来、そのスターバックスのドライブスルーには列が絶えず、自転車置き場には高校生の自転車が並んでいた。
地元の人がスターバックスを褒めそやしているのを耳にしたし、スターバックスの品が贈答品としてチョイスされるさまも見た。
その、過大評価のようにみえるスターバックス人気を眺めるうちに、ふと、X市にはセンスが良いと言えそうな喫茶店が見つからないことを私は思い出した。
地元通がそのような喫茶店の噂をしているのを聞いたこともないし、独身時代の私がフラフラと食べ歩きしても見つからなかった。
ということは、X市では、喫茶店というジャンルで最もセンスが良いのは、問答無用でスターバックスなのだ!
中華ならバーミヤン、イタリアンならサイゼリヤといったところだろうか。
X市に生まれ育った若者が「高すぎず気取ってなくて居心地のいいそこそこセンスのある美味しいお店」をサーチ&メモリーしようとすると、おそらくそうした大手のチェーン店が記憶されてしまう。
そこから逆張りするにしても、駅前の薄汚い街中華やベトベトしたスパゲティ店を「気取ってなくて居心地のいいお店」だと思い込んでしまうかもしれない。
そのどちらにも陥らないためには、数十キロ離れた県庁所在地や政令指定都市、それか首都圏に出て場数を踏むしかなさそうだが、X市に生まれ育った若者が、そうやって場数を踏むのは困難だろう。
ひょっとしたら親が連れていってくれる可能性はあるかもしれないが、「自分でそのような店をサーチして」「自分で金を払って体験する」というプロセスまでは経験できない。
「センスのある美味しいお店」には生まれの問題が深くかかわっている
一方、関東や関西の大都市圏には無尽蔵ともいえる飲食店がある。
ひとことでフレンチといってもその価格帯やスタイル、コンセプトはさまざまだ。逆張りだってし放題。
お店の数が多いだけでなく、多様性があるから、自分の好みを反映させながらでサーチ&メモリーのプロセスを踏むことができる。
そうしたプロセスが、学生時代の、あまりお金のない時期から続けば感覚はいよいよ磨かれよう。
こうしてX市と大都市圏を比較すると、「高すぎず気取ってなくて居心地のいいそこそこセンスのある美味しいお店」を巡って、簡単には埋まらないギャップが存在していると言わざるを得ない。
かりに同収入程度の家に生まれ、同学力程度の進学能力を持った学生だとしても、X市で生まれ育った学生と、大都市圏で生まれ育った学生では、たとえば22歳時点で身についている食の文化資本の程度はだいぶ違うだろう。
「X市で生まれ育った学生さんだって、大都市圏でおいしいお店を知っている人の後をついていけばいいんだよ」と指摘する人もいるかもしれない。
そうではある。
だがたとえば、X市から東大や東工大に入学した学生が、大都市圏で生まれ育って自宅から通学している慶大生と巡り会い、そのセンスを分けていただくチャンスなどあるだろうか? たぶん、その必要性も有用性も気付かないままになってしまうのではないだろうか。
あるいは地方出身の学生にありがちなこととして、そのように食の文化資本を蓄積するためのお金や時間が足りな過ぎて、なすすべがないかもしれない。
尤もこれは、大都市圏で生まれ育った若者にも起こり得ることではある:大都市圏で生まれ育った若者のすべてが、1450円のランチメニューを気軽にトライアンドエラーできるわけではないからだ。
ここまでを概括すると、「センスのある美味しいお店」を巡っては、少なくとも3つの「生まれ」の問題が関わっていることになる。
ひとつは地の利の問題。
X市のような片田舎に暮らすのと大都市圏に暮らすのでは、無視できないほどのギャップが生じる。
X市から関東圏や関西圏におのぼりする若者は、だから文化資本のディスアドバンテージを背負いながら社会適応の戦いをやっていくか、それらを血肉にするためのプロセスを改めて踏まなければならない。
もうひとつは経済の問題。
選択するカルチャーや方向性によって幾らかの違いはあるにせよ、経済的条件によって「センスのある美味しいお店」をサーチ&メモリーするプロセスの蓄積にはどうしても差が出る。
経済的条件に優れる人ほど食の文化資本を蓄積しやすく、劣る人ほど蓄積しにくい。
三つ目は先天的なセンスの問題。
この文章では深掘りしないが、文化資本の蓄積には先天的なセンスの問題も無視できない。地の利にも経済的条件にも恵まれているのに精彩を欠く人というのは、どこにでもいる。
ならば、人間を推しはかる指標として案外信頼できるのでは?
文化資本という概念は、フランスの社会学者であるピエール・ブルデューによって、階層と関連づけられて記された。
文化資本は親から子へと受け継がれ、階層を形成する一助として機能する。
文化資本は、学力や年収に比べれば数値化されにくいが、それでも習慣や規範やマナーとして身体に染み付き、人脈、経済的成功、パートナーシップといったものの難易に影響する変数として生涯にわたって機能する。
断っておくが、ブルデュー自身はこうした文化資本について、逃れがたい運命とみなしているわけでも、手放しで肯定しているわけではない。
ブルデュー『ディスタンクシオン』の格好の解説書である『差異と欲望──ブルデュー『ディスタンクシオン』を読む』には、そのあたりについて、以下のように記されている。
彼はただ、フランス社会の現状を科学的に分析し、できるだけ正確に把握しようとしているだけなのだ。……確かにこの書物では、階級の規定性がことさらに強調されているような印象を受ける。そしてこの規定性を暴露するために、ひとまず社会空間の構造がスタティックな図表として提示されていることも、やはり事実である。しかし……無数の差異が社会を構造化しているという事実を確認することと、そうして構造化されている社会の現状をそのまま受容することが、まったく別のことがらであることは言うまでもない。
ブルデューの本を読むと、つい、いやらしい視点でカルチャーを眺めている人だと思ってしまうかもしれないし、さまざまな文化資本の積み重なりが親から子へと受け継がれ、階層を形作っていくさまを悲観したくなるかもしれない。
けれども社会学者であるブルデューは、現状肯定のためにそうしているのでなく現状認知のためにそうしている。
ブルデューは田舎からパリに出てきてそうした研究や分析をした人だったから、そういった点でも、現状を肯定したがっていたとは個人的にはなかなか思えない。
しかし、あえてブルデューが望まなかったはずの、いやらしい視点で振り返ると、実のところ、「高すぎず気取ってなくて居心地のいいそこそこセンスのある美味しいお店」のような食の文化資本のメルクマールは、「生まれ」を推測するかなり強力な指標として、あるいはその人の(センスも含めた)社会適応の程度を推しはかる材料としてあてにできるものではないだろうか。
もちろん、「生まれ」としての食の文化資本をごまかすために、後々から食文化に通暁する方法もあるだろう。
しかし成人後に食文化に通暁して「生まれ」をごまかせる人は、「生まれ」をひっくり返せる程度の能力を持っているわけだから、いずれにせよそのような人は現代社会においてなんらか、有利なポジションを獲得しているとみて構わない。
こうした、お互いの社会適応の程度を推しはかる材料として考えた時、「初デートの際にどんな店が選ばれるか」とは、誘う側にとっても誘われる側にとってものっぴきならない問題だと言わざるを得ない。
なにしろそのプロセスをとおして、誘う側、誘われる側のさまざまな要素について互いの「読み」が発生するからだ。
その読みあい次第では、相思相愛が進むこともあれば、相思相愛に水が差されることだあってあるだろう。
だからこそ、人々は自分がどんなお店に誘われるのか、また、誘い得るのかを巡って躍起になって言葉を交わす。
プレゼントや贈り物もまた然り。それらを、単純なまごころの交換でしかないと読むのはイノセントに過ぎる。
名作『孤独のグルメ』のなかで主人公の井之頭五郎は、知っている人なら知っている例の台詞を述べている。
モノを食べる時はね、誰にも邪魔されず、自由でなんというか救われてなきゃあダメなんだ
ゆえに、井之頭五郎はいつも一人でグルメに興じる。
その気持ちは私にもよくわかるし、多くの読者や視聴者にも訴求力があったから『孤独のグルメ』は売れたのだろう。
しかし『孤独のグルメ』がそのように売れていること自体、世間一般の食文化、とりわけ誰かと食事を共有するという行為に文化資本にまつわる諸問題がついてまわっていること、それがとても煩わしいものであることを逆説的に証明しているようにも思う。
誰かと食事をするという行為には、このように、どうにものっぴきならない側面がついてまわるので、センスをショートカットするための指南書らしきものが出回ったりもする。
難儀な話だが、食文化にそうした一面が存在しているのも、また事実である。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【プロフィール】
著者:熊代亨
精神科専門医。「診察室の内側の風景」とインターネットやオフ会で出会う「診察室の外側の風景」の整合性にこだわりながら、現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信中。
通称“シロクマ先生”。近著は『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(花伝社)『「若作りうつ」社会』(講談社)『認められたい』(ヴィレッジブックス)『「若者」をやめて、「大人」を始める 「成熟困難時代」をどう生きるか?』『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて』(イースト・プレス)など。
twitter:@twit_shirokuma
ブログ:『シロクマの屑籠』