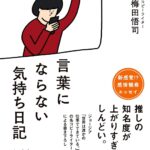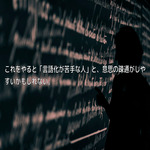少し前に、コピーライターの梅田悟司さんから、本を送っていただいた。
タイトルは「言葉にならない気持ち日記」。
この書籍について、思うところがあったので、レビューをしてみたい。
この本は、「言語化されていない感情(もやもや)を言語化する」という試みをした書籍だという。
ジョージア「世界は誰かの仕事でできている。」
リクルート「バイトするなら、タウンワーク。」
を考案した名コピーライターが、
\\118の曖昧な感情を徹底言語化!//
この本の主題は、「言語化することで、それと向き合うことができる」。
いままで形のなかった感情に言葉を与えることによって、私たちはようやく「得体の知れない感情」と向き合うことができるようになります。それはまるで、心の曇った鏡を拭き取って、自分を見つめ直すようでもあります。言葉は「心のもやもやを整頓する道具」でもあるのです。
あの気持ち悪い感覚は、こういうことだったのか。
言葉にできて、すっきりした。
この感覚こそが、もやもやを言葉にすることの意味とも言えるでしょう。本書籍では、日常生活に存在している「言葉にならない気持ち」を見つけ出し、みなさんの代弁者として、その気持ちに言葉を与えることを目的としています。
私達は正体不明の存在と向き合うことはできない。
対処もできない。
解決もできない。
スルーすることすらできない。
名前をつけ、分析を行い、それについて思索を深めることではじめて、「自分はどうすべきか」を見つけることができる。
「言語化」は役に立つ
しかし、一口に「言語化」と言っても、これはこれで、本が何冊もかけるほどの、深遠なテーマだ。
実際、梅田さんは2017年にも「言葉にできるは武器になる」(35万部)という本で、このテーマを掘り下げている。
また、Amazonで「言語化」と調べれば、大量の本が出てくる。
最近では三宅香帆さんが「好きを言語化する技術」という本で、20万部のベストセラーとなった。
こうしてみると、多くの人が「言語化」という技術(あるいは能力)に興味を持っていることは、間違いない。
さらに最近では、「生成AI」という、言語化によって膨大なマシンパワーを操ることができる装置まで出現し、「言語化能力の保持者」が非常に有利になった。
今の世の中は、「言語化する能力」が高い人が、有利に事を運べる
今の世の中は、「言語化する能力」が高い人が、有利に事を運べる。
とくに知的な仕事では、自分の思考を、他者に理解させ、そして動かす力が、とても重要だ。
要求を伝えること
アイデアを交換すること
組織や人のつながりを作ること
これらすべてにおいて「言語化能力」は、重要であり、「賢さ」の要件の一つであることは間違いない。
しかし一方で、「言語化が苦手」という人が多いのも事実だろう。
例えば、少し前にしんざきさんが、こんな記事を書いている。
「困った」を適切に言語化するのは決して簡単なことではない、という話
私、Aくんを教え始めて、すぐに「あれ?」って思ったんです。何がって、彼、「言葉でのやりとり」だとめちゃくちゃ勉強出来そうに思えたんですよ。
これは一般化してしまっていいと思うんですが、勉強が苦手な子は、自分の「わからない」を言語化出来ません。
私も、コンサルティング会社にいた当時、多くの「言語化が苦手な人たち」と出会い、彼ら、そして彼らの周りの人々が苦労しているのを見てきた。
チャットが苦手で、すぐに長電話してしまう人。(そして迷惑がられる)
会議で発言できない人。
主張を誤解されてしまう人。
「言語化」は現代人の共通の課題となりつつある。
言語化は、その対象に対する「解像度」が高くないとできない
しかしいったい、「言語化技術(能力)」とは何なのか。
これについては、少し前に書いた。
「言語化」の本質はとてもシンプルです。
では、結論からいいます。「言語化の正体」とは、一体何か。
それは「アイデア」です。(中略)「言語化」の再現性を考えたときに「言葉」は主従でいうと従だからです。
むしろ大事なのは「言葉」というよりは「アイデア」のほうです。
ですから、「良い言語化」というのは「良いアイデア」と言い換えたほうが良いくらいなのです。
だから、「言語化」は訓練で身につく能力ではあるが、身につくには時間がかかる。
実際、藤原正彦は著書の中で「言語とは表現ではなく思考でもある」という趣旨の主張をしており、知的能力と言語能力は、非常に密接なかかわりがあるとしている。
「言語は思考した結果を表現する道具にとどまらない。言語を用いて思考するという面がある。」
「言語と思考の関係は実は学問の世界でも同様である。言語には縁遠いと思われる数学でも、思考はイメージと言語の間の振り子運動と言ってよい。ニュートンが解けなかった数学問題を私がいとも簡単に解いてしまうのは、数学的言語の量で私がニュートンを圧倒しているからである。知的活動とは語彙の獲得に他ならない。」
感情、事象、人間関係など、あらゆるものに関して言えるが、それらに対する解像度が低いと、言語化が上手くできない。
知的能力を磨くことと、言語化能力を鍛えることは、ほぼ同じことであり、知識や思索の結果の果実として「言語化」が存在している。
だから「言語」だけを鍛えてもムダで、言語化したいなら、対象をよく研究する必要があるのだ。
「言葉にならない気持ち日記」の意義
話をもとに戻そう。
つまりこの書籍は、私の理解では「感情の解像度を上げる」「感情をよく観察する」ための本だ。
その結果、感情の言語化を手伝うことができるようになる、といえる。
例えば、こんな一節がある。
上司の説教が長すぎて、反省する気持ちが消滅した。
「はい、すいませんでした」と謝りながら、気づけば窓の外の景色を眺めている自分がいる。始まりは確かに自分のミスの話だったのに、いつの間にか、上司の学生時代の武勇伝を聞くことになっている。反省していた気持ちが、長すぎる説教のような謎話の波に飲み込まれるように、消滅してしまった。人間の集中力には限界がある。どんなに真剣に聞こうと思っても、ある一定の時間を超えると脳が受け付けなくなってしまうものだ。それなのに、なぜか説教だけは延々と続く。まるで、反省の気持ちと説教の長さが反比例しているかのようでもある。
(中略)短く的確なフィードバックをする方が、心に響く。それは上司の立場になった時、きっと覚えておくべき教訓なのかもしれない。
例えば、「短く、的確なフィードバック」の方が、「長い説教」よりなぜ優れているのか。
それは、この本に記述されているような感情の流れがあるからだ、と言える。
個人的に、私は人の感情について、「疎い」と評価されることが多かった。
コンサルタントという商売は、それでは非常に困るのだが、「観察と訓練」、そして「技術」によって、それを克服せねばならなかった。
そう言った背景があり、「頭のいい人が話す前に考えていること」という書籍は、感情を読め、といった話は書いていない。
単純に、私がそれを苦手としているので、言語化できないからだ。
そういう意味では、この本は「人の感情」に対する解像度が抜群に高い。
読めば、もしかしたら、「なぜ、あの人は、あの時、怒ったのか」の答えが見つかるかもしれない。
そう言う事情で、私は「人の気持ちがよくわからない人は読め。」と思った次第である。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【著者プロフィール】
安達裕哉
生成AI活用支援のワークワンダースCEO(https://workwonders.jp)|元Deloitteのコンサルタント|オウンドメディア支援のティネクト代表(http://tinect.jp)|著書「頭のいい人が話す前に考えていること」82万部(https://amzn.to/49Tivyi)|
◯Twitter:安達裕哉
◯Facebook:安達裕哉
◯note:(生成AI時代の「ライターとマーケティング」の、実践的教科書)
Photo: