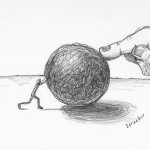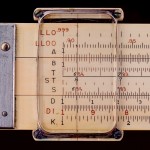父はまだ元気な歳だが、わたしは父からある遺言を預かっている。
そんなに複雑な話ではない。
ひとりっ子なので遺産相続できょうだいと揉めることもない。
そもそも、残す遺産なんて持ち合わせていない。
たったひとつ、自分が死んだらこうしてほしい、という話を聞いているだけだ。
離島に帰った父
母の死後、初盆を終えてから、父はそれまで住んでいた小倉を離れて、自分の実家である五島列島に帰る、という選択をした。
実家には父の兄夫婦が住んでいる。
なるほどそれなら、心配はいらない。
ひとりではないし、年金生活でも気兼ねなく住める家があるのは大きなことだ。
好きな釣りにも行き放題だし、なによりも一番好きな海に囲まれて生活ができる。
父は定年退職後、退職金を持って島に渡った。
使い道は、ひとつは実家のフルリフォーム、もうひとつは自分の船を買うことである。
最初の頃は、時々父に電話をしていた。
心配があったからだ。
しかし父は、わたしの思った以上に楽しそうな生活をしていることがわかった。
一緒に住んでいる伯母から、「毎日飲み歩いとるんよ〜」と聞かされてびっくりした。
しかし。
飲み歩くようなところがある場所か?という不思議があった。
そのくらい、何もない場所なのである。
私が近所を歩いていたら、そこで世間話をしていたおじいさんたちから、
「あんた、どこの子ね?」
と聞かれるような小さな集落でもある。
あるいは、やけ酒でもしているのか?と心配になったが、そういうわけではないらしい。
伯母も心配している様子はない。
いったいどういうことなのか。疑問だらけだった。
しかし、父が帰った後、最初に島に遊びに行った日に、すべての謎は解けた。
「先生」の家
「今日は「先生たち」が呼んでくれとるけん、行こうかね」。
最初に連れていかれた場所は「先生」の家だった。
「先生」と呼ばれる知人がいることは聞かされていた。
関東から、島の病院に単身赴任してきた外科医の男性だ。
「先生」はすぐ近所の家に住んでいる。
家の2階にはワインセラーに大量のワインをストックしているという。
ぶらぶらと歩いて行くと、鯛しゃぶの宴会の準備ができていた。
さらに台所では活きた伊勢海老と格闘する男性がいた。その様子を「先生」が見守っている。
「清水さんの娘さんが東京から来るっていうんやもん、それはおもてなしせんとって言いよったんよ」。
やがてぽつぽつと仲間たちがその家に集まり始める。父が一番年上だろうか。
近所の板前さんは立派な刺盛りを抱えてきた。
「これは食べきれない」見て一瞬でわかる量である。
正直、こうした「付き合い」はわたしはあまり得意ではない。
できないことはないが、全く知らない「父の飲み仲間」に囲まれるのである。
とりあえず、たらふく焼酎を飲んだ。
地元で造っているという焼酎もかなり美味しかった。それでも疲れた。
田舎まで来て「のんびり」させてくれないのである。
また、別の日にはこんなこともあった。
港をぶらぶらと歩いていた夕方、近くの家の2階から、
「お〜い、清水さ〜ん!」
と呼ぶ声が聞こえた。
伊勢海老と格闘していた男性が、こちらに手を振っている。
一仕事終えて、洗濯物を干していたようだ。
「ちょっと寄らんかね〜!」
特段用事はないので、声に導かれてその家に伺う。
「ちょっと飲まんかね」
「いいねえ」
とりあえず酒を飲む、いかにも島らしい光景である。
やがて。
「ちょっと、先生のところにワイン飲みにいかんかね?」
そして「先生」の家にお邪魔するのである。
そのまま、近くの小さなカラオケスナックへ梯子する。
家に帰って裏山を歩いていると、姫蛍が乱舞していた。
「みんなよくしてくれるっそ。やけんありがたいっそよ」。
島言葉が少し混じった父は、ずいぶんと物腰柔らかい人になっていた。
「さやかには悪いと思ったけど…」
父がいるのは上五島の若松島というところだが、これが非常に不便な場所だ。
東京から行こうとする場合、わたしの当時の自宅からだと12時間はかかる。
朝早い飛行機に乗って長崎まで行き、そこから長崎市の中心までバスで1時間ほどかかる。
そこからさらに、高速船に乗らなければならないが、これが1日4便しかないのである。
港を出て、そこから島までは1時間半くらいかかる。家に着くのは夕方6時くらいになる。
行きにも帰りにもまる1日かかる場所なのだ。もちろん、繁忙期となると、数ヶ月前単位で計画的に出発しなければ交通費はけっこうかかる。
しかしそういうわけにもいかなかった。
会社を辞める前はそれなりにお金があったので、自分の体調に合わせて遊びに行けていたが、今はその交通費もなければ、なんせまとまった休みを取るのが難しくなってしまった。
行かなくなって何年たっただろうか。
しかし、そこまで気を揉まなくても良いのかもしれない。
父はこの選択をわたしに伝えてきたとき、
「さやかには悪いと思ったんやけどね」
と言っていた。
確かに不便極まりない場所だ。
しかし、何の悪いこともない。
父には父の人生があるのだし、お互いにお互いの人生があるというのは共通認識のはずだからだ。
父と「大人同士」になった日
というのは大学生のとき、このようなことがあったからだ。
当時、烏丸丸太町のマクドナルドと、寺町通りの六角にあったミスタードーナツは良い勉強場所だった。
成人の日も、わたしと同じように特段地元に帰る予定はない、という同級生とマクドナルドで試験勉強をしていた。
いわゆる「大学デビュー」で遊び呆けていたわたしには、ありがたい同級生だった。
学期が落ち着いて、ようやく帰省した。
夫婦仲は相変わらずよくはなさそうだったが、そこは気にしない。気にしたら負けだ。
父と飲む時間はそんなに悪いものではなかったし、わたしにとってはせめてもの親孝行の時間だと思っていた。
そして、父は切り出した。
「お前ももう二十歳やね。大人よ」。
「そうやね」。
「俺、偉いと思っちょるんよ、お前いままで金貸してくれとか言っとらんやん」
「まあ、なんとかなっとるねえ」。
「これからは親子やなくて、親子やけど大人同士やと俺は思っちょる」。
「そうやねえ」。
そして本題はこれだった。
「やけんね、
これからは大人同士やけん、それぞれの人生ったい。
正直、俺はもう、お前の面倒は見らん。
そのかわり、
お前も俺の面倒は見らんでいいけん」。
突然の宣言に少し驚いた。
わたしが捻くれているのか、なんだか気持ちがすこし楽になった気がした。
何か「男の盃」を交わしたような気分にもなった。
ただ今思えばこの会話は、父なりの「子離れ」だったのではないかと思う。
自分にそう言い聞かせることで、納得しようとしていたのではないだろうか。
心臓がいくつあっても足りんから!
その会話から数年経って。
大学3回生の年を終えようとしたとき、わたしは突拍子もないことを思いついてしまう。
このままでは留年は免れられない。
就職活動のときに、留年って何か不利になるんじゃないだろうか?
であれば、何か自慢できるようなことをしておいたほうがいいんじゃないか?
当時わたしは、自転車が好きだった。
「よし、日本一周しよう!」
わたしには、ひとつ決めたら突っ走る癖がときどきある。
半期の休学届けを勝手に出して、まる2か月は朝夜とバイトをして資金を貯め、
残りの4か月で日本を回ってこようと決めた。
ただ、問題がひとつある。
こんなこと、親にどう伝えよう?反対されるに決まっている。
大人同士やから、とは言ったものの、仮にも一人娘である。
とりあえず走り始めてから考えよう、と北海道に渡って旅を始めた。
最終的には1か月かかって北海道を一周したのち、親に手紙を送った。
仰天したことだろう。
しかし、走り始めてしまえばもう止めることもできないだろうし、止まるつもりもない。
ただ、全都道府県を踏破すると決めていたわたしにとって、地元は避けて通れない。
とりあえず実家に一泊した。母は北海道に帰省中で不在だった。
出発してから2か月目だっただろうか。
もはや父にも止めるつもりはなくなっていたようだ。
翌朝出発する時に、おにぎりを作って持たせてくれた。
その頃の話を父はよく、友人や仲間にこう話す。
「俺はこいつを息子やと思っちょるんよ。
娘やと思っとったら心臓がいくつあっても足りんけん。
いや、もう娘とかおらんもんやと思っちょる」。
本心はわからない。
しかしもう「大人同士」じゃないか。そう言ったのはお父さんじゃないか。
もちろん、無事に帰ってこられたから笑い話になるのだが。
ただ、旅を止めなかったことには感謝している。わたしの「人生」にとって大きな経験になったからだ。
いや、止められても止まらなかっただろうとは思うが、良い意味で「諦めて」くれたのだと思う。
たったひとつの遺言
そして今、文字通り「大人同士」として、お互い好きな人生を歩めばいい、心からそう思って暮らしている。
いまは自転車旅のようにヒヤヒヤさせることもそうない。
無沙汰は無事の便り、とお互い思っている。というか、そうだといいと思っている。
とはいえ連絡も寄越さないのは流石に親不孝ではないか?と思われるかもしれない。
ただ、父から預かっている遠い将来の「頼み事」は実現するつもりでいる。
最後くらいは願いを叶えたいと思っている。
わたしにはそれしかできないし、親不孝だとしたらそれで許してほしい。
頼み事とは、
「俺が死んだら、お母さんの骨と一緒に五島の海に撒いてくれんかね。
それだけしてくれたらいいけん」。
というものである。
どうせ何かがあったとしても、自分の弱みを絶対に、相手がわたしと言えども見せたくない人である。
強がりを通すことだろう。
だからこそ、この遺言には重みがある。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【プロフィール】
著者:清水 沙矢香
北九州市出身。京都大学理学部卒業後、TBSでおもに報道記者として社会部・経済部で勤務、その後フリー。
かたわらでサックスプレイヤー。バンドや自ら率いるユニット、ソロなどで活動。ほかには酒と横浜DeNAベイスターズが好き。
Twitter:@M6Sayaka
Facebook:https://www.facebook.com/shimizu.sayaka/
Photo:Benny(I am empty)