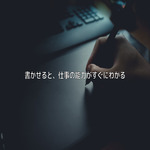様々な会社に訪問していると、それなりの頻度で「言語化が苦手な人」に遭遇する。
例えばこんな具合だ。
「プロジェクトの基本要件を一つにまとめてマネジメントしたいんだけど。 例えば、一部のプロジェクトで必要なリソースを最初に一つの大きな枠組みで決めて、それを全部に使う、そんな感じ。」
「言葉にできてるじゃない」と思う方もいるかも知れない。
だが、本当に言語化の苦手な人とは、「言葉にはできているのに、その内容が、他の人にとって難解過ぎる人」なのだ。
「言葉が出てこない」
「説明しにくい」
「なんと言えばいいのか迷う」
というのは、実は「言語の苦手な人」よりもかなりマシである。
なぜならば、「言語化できていない」という認識を自分自身で持てるからだ。
それに対して、真に言語化の苦手な人は、自分自身で「言語化が苦手」と気づいていない可能性が高い。
前職にもこんな人がいたが、
「あの人、あたまが良すぎて、言ってることがわからないよね」
と皆から言われていた。
実は、こういう人がもっとも言語化能力が低いのだ。
そして、自分自身の言語化能力の低さに気づかないので、それを修正する機会もない。
こうして、「「なにか言いたい」ということだけはわかるけど、何言ってるのかわからない人」が誕生する。
なぜ「言語化能力に難のある人」の言ってることはわかりにくいのか
しかしいったいなぜ、「言語化能力に難のある人」の言ってることはわかりにくいのだろうか。
様々な理由があると思うが、ケースとして多いのが、
1.独自言語
2.不明瞭な指示語
3.具体性の欠如
の3つだ。
例えば上で例に上げた一言の中にも、
「プロジェクトの基本要件を一つにまとめてマネジメントしたいんだけど。 例えば、一部のプロジェクトで必要なリソースを最初に一つの大きな枠組みで決めて、それを全部に使う、そんな感じ。」
この短文の中にも、
・プロジェクトの基本要件って何?
・マネジメントとは具体的には?
・一部の、と言っているが全部もわからない
・プロジェクトで必要なリソースとは?
・大きな枠組み、という言葉が抽象的すぎる
・「それ」は何を指す?
と、難解な言葉が6つも出てくる。
だからまるで、専門外の論文を読んでいるかのような気持ちになる。
論文は厳密さを追求するから、言葉が難解になるが、彼らの言葉は厳密さによって難しいのではなく、独自の言語体系と、独自の辞書をもっているから難しいのだ。
業を煮やして、
「プロジェクトの基本要件ってなんですか?」と聞き返しても、
「成功に向けて不可欠なものの集合体」とか「複数の条件がそれらを全て満たすための基準やルールみたいなもの」です。
とかいうわけのわからない回答がまた、帰ってきてしまう。
泥沼である。
こうして彼は「何を行っているのかわからない人」として認識され、コミュニケーションコストが高いので、社内からもお客さんからも、徐々に相手にされなくなっていく。
「言語化能力に難のある人」への対処法
しかし、こういう人が上司だったり、お客さんだったりすると「相手にしない」というわけにもいかない。
本人が必死に何かを伝えようとしているのにもかかわらず、「何言ってるのかわからないので無視」も、かわいそうである。
そういう状況もあり、過去に私は「言語化能力に難のある人」への対処法も習った。
それが、次の3つである。
1.書き出す
残念ながら、会話でのやり取りが「言語化能力に難のある人」とはかなり難しい。
日常会話は「なんとなく」でもいいが、仕事ではそうはいかないからだ。
そんな時は「彼が話を残らず書き留める」ことが推奨されていた。
時間はかかるが、あとから揉めないように、書かれた一つ一つの言葉の定義を確認しながら進めたほうが、結果的に手戻りが少ない。
だから、上に示した
・プロジェクトの基本要件って何?
から、一つ一つ定義と詳細化を行いながら、話をしていく。
いわば彼の「独自言語」の辞書を作るのだ。
そして、一旦辞書ができてしまえば、あとは結構楽ができる。
2.具体的なエピソードを聞く
話をわかりにくくしている大きな理由である「具体論の欠如」については
「具体的にはどのようなケースが当てはまるのでしょう?」
などと聞くところから始める。
言語化に難のある人ほど、難解な言葉を頻繁に使うが、「独自解釈」でその言葉を使っているケースが多いため、定義を確認する必要がある。
ただし、「定義はなんですか?」と聞いてはいけない。
定義をうまくできるひとは言語化能力の高い人であり、その言語化能力に難のある人に定義を聞いても泥沼化しやすい。
その場合に役立つのは「具体的なエピソードを聞くこと」である。
感覚的なものであっても、エピソードがあればかなりの役に立つ。
「一つにまとめてマネジメントしたい、とおっしゃいましたが、具体的に◯◯というプロジェクトに当てはめると、どんなことが行われていれば、マネジメントできていると判断しますか?」
と聞けばいい。
エピソードから定義をすること自体はこちらの仕事として、引き受けよう。
3.指示語は都度、確認する
「それ」とか「あれ」といった、指示語は、書き出しながら確認を取る。
面倒かもしれないが、「それ」の意味することが、不明瞭になっているケースが極めて多いため、妥協をすると後で困るのは自分だ。
例えば、
すいません。確認ですが、「それ」というのは何でしょう……?
「あれ」とおっしゃいましたが、先程言っていた「△△」のことでしょうか?
といったように、後回しにせず、都度確認をしたほうが無難だ。
要は、言った本人も「それ」が何を指すか、良くわかっていないことが多いのだ。
現代文の試験に「指示語」の問題が出ていたことは、やはりそれなりの理由があったのだな、と思う。
周りの理解も大事
以上のように、「言語化が苦手な人」とのコミュニケーションには大変なコストがかかる。
彼らは、決して頭が悪いわけではない。
が、思考と表現が噛み合わないため、「受け手がその言葉をどうとらえているのか」がうまく想像できない人たちなのだ。
東大名誉教授の加藤進昌は、著書「あの人はなぜ相手の気持がわからないのか」で、アスペルガー症候群の患者との会話には「書くこと」が助けになると書いている。
アスペルガー症候群の人との情報交換では、会話だけに頼るのではなく、要点を書き出して、視覚化、構造化することが有効です。不必要な誤解を避け、予定変更によるパニックを回避するためにもよい方法です。
言語化の能力とアスペルガー症候群の関係については私は良くわからない。
が、同じような対処はとても有効であることは、経験的にわかっている。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
安達裕哉
生成AI活用支援のワークワンダースCEO(https://workwonders.jp)|元Deloitteのコンサルタント|オウンドメディア支援のティネクト代表(http://tinect.jp)|著書「頭のいい人が話す前に考えていること」60万部(https://amzn.to/49Tivyi)|
◯Twitter:安達裕哉
◯Facebook:安達裕哉
◯note:(生成AI時代の「ライターとマーケティング」の、実践的教科書)