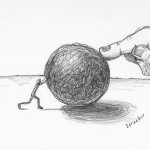僕は彼女の不幸な顔しか知らない
僕は彼女の不幸な顔しか知らない。
「遅れてごめん」
彼女は息を弾ませてそう言いつつ、カップを片手に向かいの席に座った。
「そこまで待ってないよ」
僕の言葉はカフェの喧騒に吸い込まれた。もう何度となく交わされた会話だ。彼女が僕に会いたいと言ってくる時は、彼女の人生が上手くいっていない時だ。

(Photo:Макс Радомский / Max Radomskii)
彼氏ができたり、他に夢中な趣味があったり、仕事に没頭している時、同期との飲み歩きが楽しい時、彼女は僕に声をかけない。
ただSNS上で見知った関係だけがそこにある。
彼氏と別れたり、仕事がうまくいかなかったり、そういった彼女自身が煮詰まったであろう時に僕に声がかかる。
都合が良いといえば都合が良い相手なのだろう。だから僕は彼女が上手くいっていない時の顔しか見たことがない。
彼女が結婚し、もう何年も声がかからなくなっていたが久々に声かけられ、彼女の職場近くのカフェで会うことになったのだ。
僕は無意識のうちにまた煮詰まったのだろうと彼女の心中を慮り、覚悟していた。なんとなく予想できる未来が待っていると思ったのだ。
「私ね、離婚しようかと思うの」
案の定、彼女は自分がこの世の中で一番不幸だと言わんばかりの表情でそう言った。
「もう限界」
白いカップを口に運び、一呼吸おいて射抜くような視線でこちらを見て追撃のようにそう言った。
なんとなく予想していたことだがなんだかモヤモヤした感情が僕の中に沸き上がった。
「そうなんだ」
声にもならぬ声を発し、こちらもカップを口に運ぶ。
彼女はそんな僕の感情とは関係なしに切々と語り出した。どうして離婚すべきなのか、どれだけ耐えてきたのか、女としての生き方とは、仕事のできる女、責任、決断の時、ヒトリデイキテイク、そんなネット上にいくらでも転がっているお話が次々と彼女の口から披露された。
ありきたりと言ったら失礼で、人生における大いなる決断として深く受け止めるべきなのだろうが、ありきたりな理由がそこにはあった。
決断できる健太郎君と、決断できない僕。
そんな彼女の言葉たちがカフェ内の喧騒と同化し、どこかに吸い込まれそうになった時、僕は全然関係ない健太郎君のことを思い出していた。
目の前の彼女を置き去りに、本当に健太郎君のことを考えていた。
健太郎君は中学生の時の友達で、僕の親友とも呼べる存在だった。
クラスで浮きがちだった僕と健太郎君はいつもゲームの話をしていたような気がする。確かその時はスーパーファミコンで発売されていたファイナルファンタジーIIIに夢中だった。
このファイナルファンタジーは現代でも新作が発売されている大人気のゲームシリーズで、当時はドラゴンクエストと人気を二分するロールプレイングゲームだった。
まだインターネットもないような時代で、ゲームの攻略は攻略本と口コミ頼りだった時代だ。
僕らは学校帰りにああでもない、こうでもないとファイナルファンタジーIII攻略について語り合った。
あの頃のゲームは正解が提示されないから横の繋がりがあり、とにかく面白かった。
「これから俺んちで一緒にファイファンやろうよ!」
健太郎君は満面の笑みでそう言った。アスファルトに伸びた電柱の影が少しだけ長くなっていた。
「うん、わかった」
ファイナルファンタジーだけでなくロールプレイングゲーム全般に言えることだが、友達で集まってワイワイやるような類のものではない。
一人でこっそり楽しむ種類のゲームだ。それなのに彼は一緒にやろうと言う。
違和感を覚えながらも彼の家に行くことにした。
僕は健太郎君の家に興味があった。ゲームを口実に彼の家を見てやろうと思った。
健太郎君は中学に入ってすぐにこの街に越してきたので彼の家に行ったことはない。いつも別れる地点からなんとなく場所の予想はついていたけど、どんな家なのか知らなかった。
いつもは「じゃあな」と別れの挨拶を交わす交差点を二人で通り抜け、彼の家に向かう。アスファルトに伸びた二人の影がとても長かったのを覚えている。
彼の家は我が家と同じくらいボロ屋でなぜか玄関に無数の段ボールが積み上げられていた。
あと庭先で飼っている犬の名前が「会津若松」でそのセンスが良く分からなかった。
彼のお母さんは優しそうな人で大歓迎してくれてお菓子だとかジュースだかを出してくれた。
早速、スーパーファミコンを起動してファイナルファンタジーを始める。
といっても、一緒にプレイする類のゲームではないので彼がプレイするのをずっと横で見ていた。
彼は、僕よりもやや遅れている場所をプレイしていた。僕の方がちょっと進んでいるので経験を踏まえて色々とアドバイスをしていた。
ロールプレイングゲームは一人でやるものと決めつけていたが、これはこれで楽しいと思った。
一心不乱にプレイをする健太郎君にそれを見守る僕、すると健太郎君がふいに切り出した。
「俺さ、来年になったらまた引っ越すんだ」
彼の言葉に僕はどう答えていいのか分からず、適当に返事をした。
「へえ、またお父さんの都合か何か?」
彼は首を横に振った。
健太郎君はその理由をこう説明した。なんでも、ある特殊な職業につくための学校に行くことを決意したというのだ。
こんな田舎町にはそんな特殊な学校はないので、その学校がある都会に引っ越すとのことだった。
学校に入ってしまえば寮に入れるが、その前に都会の親戚の家に身を寄せて様々な準備をする、だから引っ越すとのことだった。
「そ、そうなんだ」
僕は少なからず動揺した。それは彼がこの町からいなくなってしまうことにショックを受けたからではなかった。
彼が「決断した」ということがあまりにショックだったのだ。
同じ歳の少年が、ある職業になりたいと思い、その準備をすると決断する。
親元を離れ、街を出て知らない場所で生活していこうと決断する。
そんな決断ができる彼のことが異形の存在のように思えた。本当に人間じゃないのかもしれないと思ったほどだった。
僕は皆と同じように中学に行き高校にもいくだろう。
そこでどこの高校に行くのか選ぶという決断めいたことをするかもしれないが、基本的にそれは用意された中から選ぶ行為だ。選択であり、決断ではない。
もしかしたら僕の人生においてはこの先も決断めいた選択程度はあるかもしれないが、真の意味での「決断」は存在しないのかもしれない。そんな僕を尻目に健太郎君はガチの決断している。その事実がただただショックだった。
健太郎君「エリクサーをピンチのときに使わないのはおかしい」
決断の男は淡々とファイナルファンタジーを進めていく。ちょうど強い中ボスと対戦する場面にさしかかった。僕も苦戦したので良く知っている敵だ。

「こいつ強いぞ、落ち着いていけ」
そうアドバイスする。けれども、この中ボスをクリアしていた僕には何となく分かっていた。たぶん現在の彼のレベルではこいつを倒すことはできない。本来ならもうちょっとレベルを上げてから挑むべき敵なのだ。
「くっ、こいつ強い……!」
案の定、健太郎君は苦戦していた。みるみるとHPは減っていき、様々な魔法を繰り出すが次第にMPも枯渇していき何もできない状態に陥っていた。
ただ全滅を待つのみである。いよいよ絶体絶命となった時、彼はこう言った。
「まだいける!」
そう叫ぶとアイテムボックスを開き、あるアイテムを使うことを選択した。それは「エリクサー」と呼ばれるアイテムだった。
「ちょっと待て、貴様正気か!」
僕はついつい大きな声を上げてしまった。
エリクサーとはHPもMPも全回復してくれる物凄いアイテムである。完全に救いの神的なアイテムだ。
もちろんこの場面で使えば、瀕死のキャラたちも蘇り、また無尽蔵に魔法を使えるようになる。
ピンチの場面で使うべきアイテムだけど、それ故にものすごく希少なアイテムなのだ。
アイテムショップで販売しているわけでもなく、そうそう宝箱からポコポコ出てくるわけでもなく、大抵序盤で1個だけひょんなことから入手できて、あとはなかなか手に入らないレアな代物だ。
それをこんな場面で惜しげもなく使うなんて、気でも触れているのかと思った。
「なんで? ピンチじゃん、使うよ」
健太郎君はきょとんとした顔で言う。僕は拍子抜けした。彼は事の重大さを全く認識していないのだ。
「そんなピンチの度に使ってたらなくなるだろ。次いつ手に入るかもわからないのに。そもそもピンチになるってことはレベルと装備が足りないんだから出直して準備を整えるべきだ。エリクサーありきで攻略プランを立てるべきではない」
僕の必死の弁明も空しく、彼は何を言っているんだこいつと言わんばかりの顔をして普通にエリクサーを使った。あまりにあっさり使ってのけたのだ。僕はたまらず両手で目を覆った。もう見ていられなかった。
結局、健太郎君はその直後に中ボスを倒した。つまり、使わなくても対策して出直せば倒せた敵なのである。
なんともったいない。熱戦を終えて満足気な彼に食ってかかった。
「装備を整えて出直せばエリクサーを使わなくても倒せた。使うべきではなかった」
僕の主張に彼は反論した。
「その性能から言ってエリクサーはピンチを脱するために作られたアイテムだ。それをピンチで使わないのはおかしい」
「俺だってエリクサーがポンポン手に入るなら使っていく。ただ、いつ手に入るか分からないものを気軽に使うべきではない。使うべき時がくるまでとっておくべきだ」
「それでもピンチなら使う」
「じゃあ雑魚敵が相手でもピンチになったら使うのか」
「使う」
と完全に平行線で喧嘩みたいになってしまった。
最終的には「このエリクサー野郎!」「この保存野郎!」みたいな意味不明の罵り合いを経た後、喧嘩別れすることになった。
世界広しといえどもエリクサーで親友を失ったのは僕だけではないだろうか。
お前はきっと永遠にエリクサーを使えない
去り際に、健太郎君が僕の背中に叩きつけた言葉が妙に印象的だった。
「お前はきっと永遠にエリクサーを使えない」
「使うわ!」
僕は使うべき場面が来たら躊躇なくエリクサーを使う。失礼なことを言うな。使うべき時は使う。ただあの中ボスは絶対にその時ではない。
もうお前とは一緒に帰らない。会話すらしない。異様に腹を立てて家に帰ったのを覚えている。
もうすっかり暗くなっていた。あまりに腹が立ち過ぎたので家に帰って母親に「使うべき時がきたらエリクサーを使う」と高らかに宣言したほどだった。
母親もさぞかし意味不明で狂ったのかと思ったことだろう。
それからしばらく経って、僕は喧嘩の原因となったファイナルファンタジー3をクリアした。
結局、最後までエリクサーを使うことはなかった。
あれだけ貴重だと思われたエリクサーも物語が進行して終盤になるに連れて結構な頻度で手に入るようになっていた。
僕のアイテムボックスにはエリクサーが溢れていた。じゃあ、バンバン使えばいいじゃん、と思うかもしれないが、そもそも終盤になるとそんなにピンチに陥ることもなく、さすがにラスボスで使うだろうと思ったけどそこまで追い込まれることもなく、普通にクリアできてしまった。
結局、「その時」は来なかったのだ。
僕は激しい自己嫌悪に陥った。
確かに僕はエリクサーを使わなかった。いや、使えなかったのだ。健太郎君が言った通りだったのだ。
ただ、今更仲直りすることはできず、そのまま月日が流れ、終業式の日を迎えて健太郎君は「決断」の先へと旅立ってしまった。
最後にクラスの仲間とアドレス帳を記入しあうという謎の儀式があったが、それにも参加しなかった。僕は謝るという決断すらできなかったのだ。
*****
「それでね、離婚届を記入したの」
目の前の彼女の言葉でハッと我に返る。彼女は相変わらず自分の決断について切々と語っていた。
「じゃあ、あとは慰謝料の話とかして提出する感じ?」
全然話を聞いていなかったが、適当に話を合わせていると、彼女は不満げな顔をした。
また考えていた。どうして僕はこんな場面で健太郎君を思い出したのだろうか。
切々と離婚という決断について語る彼女の顔にあの日の健太郎君の顔がオーバーラップしていた。
「わたしは決断したらすぐだから」
カップの中身を飲み干しそう言った彼女を見て確信した。
そういうことだったのだ。彼女はエリクサーを使う人間なのだ。彼女にファイナルファンタジーをプレイさせたらきっと躊躇なくエリクサーを使うだろう。ピンチだよ、使う、そう言って使う。下手したらあまりピンチじゃなくても使うかもしれない。だから僕は彼女に健太郎君を重ね合わせたのだろう。
この世には、エリクサーを躊躇なく使える人間と、使えない人間がいる
この世には二種類の人間しか存在しない。
エリクサーを躊躇なく使える人間と、使えない人間だ。
もはやエリクサーはHPとMPを全回復してくれるアイテムではない。
先が見えない状況で「決断」できるかどうかを問うアイテムなのだ。生き方を問うアイテムと言い換えてもいい。
僕らは人生において常にエリクサーを所有している。
それを使うか使わないか、その決断は個人個人に委ねられているのだ。
彼女は僕に会う度、いつも不幸な顔をしていた。別れ、退職、転職、起業、撤退、結婚、その場面ごとに決断というエリクサーを使ってきたのだ。
そして今まさに離婚というエリクサーを使おうとしている。彼女は使ってきた人間で、僕は使ってこなかった人間だ。彼女の人生はとてもエキサイティングでドラマチックで、僕の人生はとても退屈なものだ、そう思う。
エリクサーとは人生における決断である。
ただ、その事実を前にしても僕は今でもエリクサーを安易に使うべきではない、そう言ってのける。
例え退屈であったとしても安易に使うべきではないのだ。
世間に広く発信される声はとかくエリクサーの使用を促すものだ。その方が刺激的で人々の心を掴むからだ。
嫌なら転職、起業せよ、好きなことをして生きていく、離婚すればいい、ありきたりの人生なんて、そうやってエリクサーを使え使えと攻めたてられている感覚すら覚える。
それらの声は個々に見れば全て正しい。ただ、あまりにこぞって言われ続けるのもどうかと思うのだ。
冒険が正義であり、保守的な考えは悪である。
いつの間にかそんな風潮がまかり通る世界が出来上がっているように感じる。
保守的な考えが悪の存在でそれを打ち破る革新的な冒険心溢れる主人公、なんて創作話は山ほど存在する。
そうやってエリクサーを使わないことを悪のように扱われている気がするのだ。
成功者は言うだろう。決断をすべきと。エリクサーを使うべきと。
ただ、それはあくまで成功者の言葉であって成功するための言葉ではない。決断して成功したものは決断しろと言うだろう。
エリクサーを使うことが必ずしも成功に結び付くとは限らないのだ。エリクサーを使えない生き方だって多分に大変で立派で、もっと尊重されるべきなのだ。

「もう疲れちゃったな」
空になったカップを確かめるように傾けながら彼女はそう言った。激動の人生に疲労しているのかもしれない。
本来はHPとMPを全回復する回復アイテムの最上位的存在を使い続けて逆に疲労しているのならば皮肉なことだ。
結局、ゲームをクリアするまでエリクサーを使えなかったことに激しく自己嫌悪したあの日の僕に声をかけたい。
それでいいんだと。エリクサーを使わなくていい生き方をするのもまた、人生なのだと。
きっと、健太郎君だっていまだにどこかの空の下でエリクサーを使い続けているだろう。
彼があの日の決断を実現し、夢まで到達していたとしても、それでもなお彼にエリクサーを安易に使うべきではないと言いきれる。使えなかった僕たちがもっと尊重されてもいいじゃないか。
*****
「ねえ、わたしたち結婚しちゃおうか」
しばしの沈黙の後、彼女はそう言っていたずらに笑った。僕は少し考えて答えた。
「冗談じゃない、俺はそんな重大な決断をできる男じゃないよ」
僕がそう言ってエリクサーをしまいこむと、また彼女は笑った。今度は無邪気に笑ったように見えた。
こうやって使わないことが尊重されてもいい。なんでもかんでもドラマを展開させるべきではないのだ。
まだ笑っている彼女を見て、僕ははじめて彼女の笑顔を見たような気がした。
ティネクトは、新しいAIライティングサービス AUTOMEDIA(オートメディア) の
最新資料を公開しました。生成AIの進化と共に我々使いこなす側もその最適化のため大幅にアップデートしています。
AIが“書く”を担い、人が“考える”に集中できる——
コンテンツ制作の新しい形をご紹介します。
AIが“書く”を担う。
人が“考える”に集中できるライティングサービス
著者名:pato
テキストサイト管理人。WinMXで流行った「お礼は三行以上」という文化と稲村亜美さんが好きなオッサン。
Numeri/多目的トイレ
Twitter pato_numeri