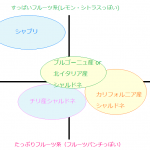新入社員が入って約半年経ち、そろそろ仕事も一通り覚えてきた頃でしょうか。
自分が社会人になった10年前くらいと比べると、今の若い人達には転職や副業、起業など様々な選択肢がより身近になっていて、自分にあわないと感じたら既に転職エージェントと話を始めてしまっている人もいるかもしれないですね(笑)。
また、最近でこそ、ダイバーシティですとか、インクルージョンとか、男性や女性、LGBT問わず、区別しないようにという流れは出てきたように思います。
ところがつい先日、まだまだ日本企業で働く女性は、それほど自由な存在にはなっていないのかなぁと思うことがありました。
それは、最近までとある大企業に勤めていた女性の先輩とお話していた時のことです。
同じ企業で働き続けるかは別として、ダラダラとした目的意識で働き始める適当男子とは違い、女性には学生時代の頃から、結婚までのイメージ、結婚後のイメージを明確に持っている人が相対的に多いように思います。
大学を卒業して、いざ社会人になるのがだいたい22歳くらいだと思いますが、産休や育休はだいたい30歳前半だとしたら、キャリアに必ず一定時間空白が生じてしまう。だから、
・医療系の資格試験を取って、とにかく休み明けに復帰できる権利を確保しておく。
・最初から外資系でバリバリ稼いで、ある程度やりきった感を持って産休後はキャリアチェンジ。
・とりあえずベンチャーで経験を積んだ後は、福利厚生の充実した大企業へ転職して産休へ。
・若いうちは代理店等で遅くまで働いても体力が持つから、とにかく最初のスタートが肝心。
など、聞けば聞くほど、とてつもなく戦略的な女性の多いこと多いこと。
でも、それだけきちんとリアルに考えられているんだなと感心もさせられます。
同じ会社で働き続けるかどうか、転職するのにもヒト悩みするような弱い男子とは違うわけです(笑)。
充実していたワークが徐々に予想とは違う形で崩れる
そして、今回ご紹介したいのは、上記で挙げた例でいうと、1番最後の例に近い?女性についての話です。
職種は一般的にいうところの営業・コンサル職。
世間一般でいうところの大企業に属していた彼女は、夜遅くまで働くのはもちろん、同期や前後の同僚から見ても明らかに高いパフォーマンスを上げていました。
彼女自身、早い時期に結婚はしていたものの、子供が産まれて休まざるを得ない時期を想定。
それまでにできるだけ給料を引き上げておき、休んでいる際の実入り(給付等は給料に連動する部分が大きい)をいかに大きく出来るかということは意識していたと言います。
いくつかの仕事をローテーションし、やっとたどり着いた現在のコンサルティング業務は、自身にとっても大変やり甲斐がある仕事で、ノルマでさえ、その充実度を計る一指標でしかなかったと言います。
そうして、彼女はとうとう十数人を部下に持つマネジメント側に行きます。
とある金融機関で、30代男性が公募で支店長になったという例外はありますが、大企業で30代半ばでのその地位は、彼女のそれまでの仕事が評価されてきた事の比類なき証だったと言えます。
しかし、彼女にとっての不幸が始まったのはそこからでした。
マネジメント、管理とは往々にしてそういうものなのかもしれませんが、挑戦するというよりは、部下の事務処理の承認業務ばかり。
「こんな事務なんて、技術革新で近い将来無くなるのに、なんでこんなことに時間を使っているんだろう。」
疑問を感じ始めた彼女は、ずっと目をかけてくれていた役員にも相談します。
そこで言われたのは、「次は部長、その次は役員の可能性もある。失敗するわけにはいかないぞ。」
その言葉を聞いた時、彼女の中には大きな違和感が生まれました。
また、以前の業務へ携わりたいという気持ち、そしてこのまでは今後の未来がとてつもなくつまらないものになってしまうのではないか、という危機感が生まれたそうです。
そして、その後彼女はその企業を後にする決意をしました。
日本では、男性と女性でまだまだステージの違いがある
少し雑な議論になりますが、男女雇用機会均等法成立からも30年以上経った今でも、まだまだ男女の間にはステージの差があるように思います。
というのも、男性は何がしかの専門性を極める方向でのスペシャリスト職みたいな自由が広がってきている一方、
何がしかの専門職につきたい女性が、単に優秀というだけで望まないポジションに貼り付けられてしまうことが多々あります。
この背景には「女性の社会進出」というにわか目標があります。
つまり、優秀な女性であれば、すべてマネジメントへ登用したがる企業が多いのです。
しかし、これは、決して自由であるとは言えませんし、望ましい姿ではないでしょう。
今回取り上げた女性以外にも、優秀だという理由だけで望まないジェネラリスト的な管理業務をさせられそうになり、辞めた女性の友人は少なくありません。
もちろん、優秀な女性がマネジメントに登用されることは企業としても日本全体からも見ても望ましいことではあるのですが、それはその本人自身がその道を望んでいるかどうかが大前提かと思います。
さて、大企業を辞めた彼女自体はどうなったかといいますと、以前やっていた営業・コンサルティング業務を探す中で、海外での新たな業務にチャレンジすることになったようです。
常に挑戦する場所に自らの身を置きたい、そのような願いが叶ったみたいです。
日本の大企業には、まだまだ「古い出世の階段」しか存在しない
全ての日本企業がこのような状況になっているわけではないと思います。
ですが、柔軟に人を使えず、人を既存のポジションに当てはめていこうとする向きはまだまだ至るところに存在します。
企業は目の前の市場やお客さまへは迅速に対応しようとビジネスをしていますが、中の人の配置についてはまだまだ古い論理で動いているところも数多いようです。
そんな企業では、結局中での評価ばかりを気にすることになり、やがては企業全体がお客さまからはほど遠いところに行ってしまうかもしれません。
女性の待遇一つとっても、そんな事がよくわかります。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【著者プロフィール】
著者:ひろすぎ
30代、都内勤務の兼業投資家。
どうやったら普通の人がお金に困らない暮らしをできるかを模索し、自ら実験する日々。株、不動産をはじめ、いくつかの事業を展開。趣味はお散歩とお酒、旅行です。
(Photo:Pietro Motta)