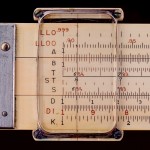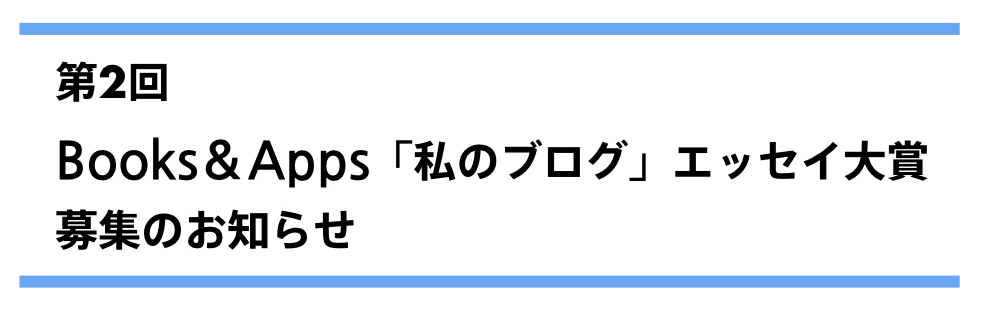「インターネットに文章を書くということ」
インターネットで文章を書くようになって18年になる。もはやベテランと言っても過言ではないだろうか。
18年も書いてきて、そこそこにお金を貰って書くようになり、好きですと言ってくれる人がいたり、連載をもったりするようになった。
手が回らなくなって断る仕事も出てきたくらいなのだから、この18年は決して無駄ではなかったように思う。ただ、18年間ずっと思い続けていたことがある。それが「才能」に関することだ。
僕は「才能」という言葉があまり好きではない。
才能とは言い訳の言葉だ。可能性に溢れた煌びやかな単語のように見せかけて、「あの人は才能があるから」「自分は才能がない」「いいよな、才能があるやつは」などと、ネガティブな意味で使われることが多いからだ。
人は誰かと自分との差異を慰めるために「才能」という言葉を使う。
諦めるために「才能」という言葉を使う。
本来は「才能」なんてものはこの世に存在しないものなのかもしれないのにだ。
そういった事情を踏まえ、18年間書き続けた上であえて言わせてもらうと、僕にはやはり「才能」がなかった。
文章を書く「才能」がなかった。
何もせずに軽い気持ちで書いたものが多くの人を魅了し、死ぬほど評価されるなんてことはなかった。
いつも文章を書いて後悔し、悩み苦しみ、誰かの文章に死ぬほど嫉妬した。
心安らぐ時間なんて存在せず、常に苦しみ、書き、また苦しんできた。その過程は決して「才能」じゃない。ただただ苦しいだけだ。
才能のない僕は、常に自分を戒めなければならなかった。何が良くて何がダメだったのか、才能がないなりに自分が書いたものでPDCAサイクルを回し、少しでも上に、少しでも実力のあるステージに行く、そう思い続けてきた。
ここに、僕が初めてインターネットに書いた文章がある。18年前に書いたものだ。
当時の僕が “インターネットで多くの人を魅了するぞ” と意気込んで書いたものだ。
僕は、このクソ文章を定期的に眺め、書き直すことにしている。そうすることで自分の位置を確認できるからだ。もしかしたら戒めという意味もあるのかもしれない。
ぜひとも、その“戒め”のクソ文章を読んでみて欲しい。
おつかい
上司のおつかいで、速達の書類を出しにクロネコヤマトまで行ったんですよ。
送料は多分、1000円もかからないだろうけど、上司が細かい札を持ってなかったので5000円渡されました。
で、遠く離れたクロネコヤマトの営業所まで車を運転してたんですけど、急に腹痛が・・・。
しかもかなりの大物。
我慢できずに、車を停め、マクドナルドまで駆けるようにしていって用を足しました。
なんとか無事に用を足し、ホッと一息。店を後にしました
で、無事にクロネコヤマトに到着したのですが、
上司から預かった金がない・・・。
落としたっぽい・・・。
そういえば、マクドナルドで若者達の集団が何やら歓喜してたような・・・。
きっとあいつらが俺が落とした5000円をゲットしたに違いない
そう思うと悔しくて悲しくて
自腹で送料を払い。お釣りも自腹で上司に返しましたとさ
手痛い出費でした。
*
これはひどい。控えめに言ってゴミだ。
よくもまあ、こんなものを世間に公表しようと思ったもので、完全に「才能」がない。
これを読んで“これから文章とか書いていこう”と思っている人は勇気を持って欲しい。こんなものを引っ提げてデビューした男でも、いま現在、まあまあ戦えているのだ。
これは完全なる黒歴史で、封殺すべき過去なのだけど、才能がなかった僕はこれに向き合わなければならなかった。
この文章の何がダメなのか、それを考えて自分で自分をアップデートしていかねばならないのである。
このクソ文章を分析してみる。
問題だらけの文章で、言葉が稚拙、改行が多すぎる、一文が短すぎる、リズムが悪い、などの問題がボコボコ出てくるが、最も問題なのは「主張のなさ」だとわかる。
これは、書くことで本人だけが満足するだけのタイプの文章で個人の日記に近い、言い換えると人に見せる文章になっていない。そこが一番の問題だ。
主張のない文章はすべからくゴミである。世の中の読む価値ある文章と読む価値ない文章の差異はこれに起因する。
読んで何を感じて欲しいか、それがない文章はどんなジャンルであっても等しくゴミだ。
そういった観点で件の文章を読むと、問答無用でゴミだ。
マクドナルドでお金を落としたというだけの話で、完全に自分の日記帳に書いておけ、という類のものだ。そこに伝えたい主張はないし、感じ取る思想もない。ただ文字が羅列されているだけだ。
では、これをどうやって書き直せば良いのか、それを考える。これに主張を乗せる形でアップデートしていこうと書き直すのだ。
こういう場合は逆説的に考えると良い。重要なとっかかりになることが多いのだ。
「おつかい」
タイトルにもなっているこの言葉に焦点を当てる。
そもそも「おつかい」とは面倒くさいものだ。言葉の響き的にも、大人が子供に頼むようなニュアンスがあり、ちょっとバカにされているような印象すら受ける。
職場の上司に「おつかい」を頼まれる、ちょっと仕事ができない僕が誰にでもできる仕事を振られたというニュアンスがあるのではないか。
その対局として「おつかい」とは「信頼」の受け渡しという、まったく逆の主張を使ってみる。
たとえ「おつかい」といえども、「信頼」していない相手に頼むはずがない。そう、僕は「信頼」されているんだ。「おつかい」とは信頼を託す行為だ。決して、仕事ができないやつに割り振るものではない。
こうすると「信頼のバトン」というキーワードが生まれてくる。それを主張に持っていくことを考えると、最後まで簡潔にまとまる。それを踏まえて書き直すとこうなる。
おつかい
忙しなく働くオフィスの中で暇そうにまどろんでいた。僕はただ茫然と、忙しそうに働く人々を眺めていた。今日は帰ってゲームでもするかと、心だけは既に帰宅していたくらいだった。
心だけが完全にトリップしていると、急に上司に呼びつけられた。いよいよクビでも言い渡されるのか、それとも怒られるのか、なんにせよ良くない何かが起こることは確定的だった。
「この書類を速達で出してきてくれないかな、急ぎなんだ。クロネコヤマトまでひとっ走り行ってきてくれ」
ハゲチャビンの上司は茶封筒をぶっきらぼうに差し出し、そう言った。完全に面倒くさいやつだ。
ハゲチャビンのやつ、僕が仕事できないからって、こんな子供に頼むみたいな「おつかい」を言い渡してきやがった。
「はあ、わかりました」
速達もクソもないだろ、その辺のポストに投げ入れてきても分からないだろう、と考えていると、心を見透かしたのか、念を押すように言われた。
「絶対にクロネコヤマトまで行くこと。速達で出すこと」
ここからクロネコヤマトまでは遠い。車じゃないととてもじゃないが行けない距離だ。いよいよもって面倒くさいことになってきた。
「いまこまかい金がないからこれで頼む」
ハゲチャビンはそう言って五千円札を差し出した。たぶん送料は1000円もしないはずだ。
「おつりはお駄賃にもらっていいですか」
と言おうと思ったが、たぶん怒られるのでやめておいた。
クロネコヤマトまでの道中、車を運転しながらぼんやりと考えた。
これは完全に「おつかい」というやつだ。
言い方は悪いが、誰にでもできる仕事だ。そんなものを任される僕、仕事において将来がないと考えることもできる。リストラ要員なのかもしれない。いよいよ身の振り方を考える必要があるのか。
「おつかいならお駄賃があるべきだよな、それならやはりおつりを……」
そんなことを考えながら交差点で停まる。見るとボランティアのおばさんが、小学生の手をひいて横断歩道を渡っていた。
その光景はなんだか印象深いものだった。
小学生はボランティアのおばちゃんを完全に信頼していて、全てを預けて横断歩道を渡っている。
もしかしたらあのおばちゃんが自殺志願者で、最後にひと花咲かせてやるわーと小学生を道連れにトラックにダイブする、なんてことは微塵も考えていない。信じ切っている。そこにあるのは信頼だ。
「信頼か……」
助手席に置かれた書類と五千円札を眺める。
おつかいを頼まれた、だからバカにされてるいなんて考えたけど、実際はそんなことないんじゃないだろうか。
速達で出せと念を押されるほどの重要書類だ。それを良くわからない馬の骨に任せるかというと、答えは否だ。逆に考えると、信頼されているからこそ、おつかいを任されたと考えることができる。
そう考えると、五千円を託すという点にも多大なる信頼が現れている。
五千円とは大金だ。それを良く分からないリストラ要員に託すだろうか。答えは否だ。
下手したら持ち逃げされるかもしれない、お駄賃にいただいておきやす、へっへっへっ、とお釣りを取られるかもしれない。そんなやつには任せられない。
そう、書類も五千円も、上司から僕への多大なる信頼の現れではないだろうか。
この世は信頼のバトンで成り立っている。
きっと上司も誰か、さらにその上の上司から信頼を受け取り、その書類が回ってきたのだ。そして今度は僕がその上司から信頼のバトンを受け取った。そう考えると、なんだか気分がいい。
「なあんだ、信頼されていたのか」
少しだけ心が軽くなった気がした。やはり人は人に信頼されると気分がいい。同じクロネコヤマトまでの道のりでも、その風景は違ったものに見えた。簡単に言うと、世界が色付き輝いて見えた。
異変が起こったのはそれからだった。
「お腹が痛い」
容赦ない、無慈悲なる腹痛が襲った。完全にやばいやつだ。
腹痛には大きく分けて2種類のものが存在する。結論を急がないものと、結論を急ぐものだ。この腹痛は完全に後者だった。すぐに結婚を迫ってくる女に近く、これ見よがしにゼクシィとか買ってくる類の腹痛だ。
「ここで漏らしたら書類を送ることができない!」
さすがにうんこ駄々漏れ状態でクロネコヤマトに行くわけにはいかない。クロネコも裸足で逃げ出す。そうなると、上司からの信頼のバトンに応えられないのだ。
「もってくれよ! 俺の肛門!」
僕は自分の肛門を信頼した。上司が僕を信頼して五千円託したように、僕も肛門を信頼してウンコを預ける。それが信頼のバトンだ。頼んだぜ、肛門!
肛門は信頼に応えてよく頑張ってくれた。道中にあったマクドナルドに飛び込み、トイレに駆け込むまで本当に頑張ってくれた。
信頼を託し、それに応えてもらえることは至上の喜びだ。だからきっと人は人を信頼し、信頼のバトンを渡すのだ。よく頑張った、肛門。
清々しく、晴れやかな気分だ。信頼とはこんなにも気持ちが良いものなのだ。
クロネコヤマトに到着する。書類を持ち、そこで気が付いた。
「五千円がない」
おかしい。本当にどこにもない。書類も五千円も、盗まれちゃいかんとマクドナルドに持って入ったことまでは覚えている。
けれども、五千円だけがきれいさっぱり消え失せていた。
「もしかして、マクドナルドで落とした?」
思えば、僕がウンコを済ませてマクドナルドを後にするとき、アウトローっぽい集団がちょっとテンション上がって湧いていたような気がする。
もしかしたら、あれ、五千円拾って喜んでいる沸き上がりだったんじゃないのか。歓喜の声だったんじゃないか。そうか、アウトローたちに拾われたのか。
自腹で五千円返す必要がある、もはやお駄賃どころではない、そう考えて落胆したが、考え方を変えればいいのである。
あの五千円は落としたのではない。託したのだ。アウトローたちが有意義に使ってくれると信じて託したのだ。
そう、彼らは今頃、あの五千円で面白おかしく過ごしているさ、そう、五千円は信頼のバトンなのだ。
上司から僕へ、僕から上司へ、その信頼のバトンこそがこの世を生きる上で必要なのである。
職場に戻ると、「たかだか書類送るだけでどれだけ時間かかってるんだ!」と五千円を損失補填した僕の気も知らないで上司が怒っていた。
別の部署に異動させるぞ! と憤っておられた。これもきっと信頼のバトンなのである。
多分上司は、僕というバトンを信頼できる部署に渡すつもりなのである。決してリストラなんかじゃない。
*
と、こんな感じに書き直すことができる。
この文章の良し悪しは別として、これであのクソみたいな「日記」から、主張を伴った「文章」に消化することができた。この世は信頼のリレーであるという主張だ。
ただし、この文章にも大きな問題がある。
それが、面白味がない、という点だ。
実はこの点がかなり重要だ。むしろ最大の問題点かもしれない。これは完全に個人の資質によるところなのだけど、この種の文章は書いていて楽しくないのだ。
僕は文章を書くことが嫌いなのである。
本当に書くことが嫌いで、できれば書きたくないとすら思っている。
そんな中で書いていくのだから、それは書いていて楽しいものでなくてはならないし、その楽しくなさは文章にも表れる。そう言った意味では、上記のリライトは全然楽しくないのだ。もっと楽しんで書かなければならない。
では僕は何を書いているときが楽しいのだろうか。
僕は自分に歯止めがきかないレベルで暴走しているときに楽しさを見出す傾向にあると自己分析できている。
それを踏まえ、とにかく楽しい、という観点でさらに「おつかい」の日記を書き直してみる。
遠くから駆け寄る軽快な足音が聞こえた。馬だろうか、力強く、リズムよく刻まれるその音に遠くから意識が戻ってくるのを感じた。
「いててててて」
異様に体が重い。おまけにあちこちが痛い。瞼を開ける。一瞬で抜けるような青空が目の前に広がった。
「ここは?」
体を起こして周囲を見回す。そこはまるで定規で引いたかのように見渡す限りに地平線が広がる平原だった。
はるか向こうには見たこともない歪な形をした山が見える。
「なんで?」
鈍痛が響く頭を抱えて思い返す。思い出せ。たしか、上司に頼まれて渋々、書類を提出しにクロネコヤマトに向かっていたはずだ。
途中でお腹が痛くなって、いよいよ漏れるか、と覚悟した時、マクドナルドが見えた。そう、そこまでは覚えている。
それがどうしてこの平原なのだろうか。記憶が繋がらない。もう一度、確かめるように周囲を見回す。見渡す限りの平原だ。
もちろん、クロネコヤマトまでの道のりにこんな場所はない。心なしか空の色も知っているものより深い青に見えた。
規則的に聞こえていた馬の足音がさらに音量をあげた。かなり近いようだ。倒れていた場所に右手先には森があった。そこから聞こえてくるようだ。
もう間近まで迫っているが、お生い茂る木々によってその姿は見えない。
「ハイヨー!」
軽快な掛け声とともに、白い塊が森から飛び出した。
「ヒヒ――――ン!」
飛び出した白馬はこちらの姿を確認すると、驚き、大きく嘶いた。
「何者だ!」
白馬の上には女性が乗っている。赤髪をなびかせ魅惑的な瞳の色をした美少女だ。
その美少女が脇に携えていた短剣をこちらに向け、大きな声をあげた。
「いや、怪しいものじゃないです。頼まれた書類を届けようとクロネコヤマトに行く途中でお腹が痛くなって、そして気付いたらここに」
必死に説明するが、馬上の美少女には伝わらない。その不思議な色をした瞳でじっとこちらを見ている。
「本当に、上司が書類を速達で出せって言ってきて、五千円札出してきたんです、ほら、この書類、五千円も、ほらほら!」
馬上から見えるよう、高く掲げる。必死の弁明が通じたかどうかは分からない。美少女は短剣を納める仕草を見せた。
「貴様はマヤベーラの者か?」
「はい? マベヤーラ?」
何を言っているのか分からない。
「マベヤーラでないとするならカーリマナフの者か。ふむ。野蛮なその顔はカーリマナフに近いな。いずれにせよ好ましい種族ではない」
まったく要領を得ないが、とりあえず短剣をしまってくれたので、警戒は解かれたのだろう、そう判断した。
「よかった、信じてくれたんですね。僕が怪しいものじゃないって」
その言葉に、美少女は首を傾げた。
「信じる? なんだそれは」
一陣の風が通り抜け、森の木々が揺れる音が聞こえた。
『上司のおつかいでクロネコヤマトに向かったらウンコ漏らしそうになって気絶し、「信じる」という概念が存在しない世界に転生し、「信じる」ことだけを武器に魔王と戦うことになった件について』
<*>
30キロほど歩くと、城壁に囲まれた街にでた。どうやら彼女が拠点とする街のようだ。高くそびえたつ城壁、その中央にある大きな扉の前に立っていた。
「そろそろこの紐を解いてくださいよ、めちゃくちゃ食い込むし、歩きにくいし」
あの平原から、ずっと両手を後ろ手に縛られたまま引きずるようにして連行されてきた。何度説明しても理解してもらえないのだ。
「黙れ。貴様はこれから裁判にかけられるのだ」
「そんなあ」
道中、色々な会話を交わしたが、どうやらこの世界は元いた世界と全く異なる異世界のようなのだ。
そして、文明のレベルは低く、なぜか「信じる」という概念が全く存在しない奇妙な世界だった。
「よう、アリル、久しいの。なんだ、その男は」
城壁内へと通じる扉がゆっくりと開き始め、その横にいた兵士がそう話しかけた。
彼女の名前はアリルというようだ。
「ふん、平原で怪しいのを捕まえてきた。おそらくマベヤーラのものであろう」
「そいつは手柄じゃねえか。じゃあ今晩中に裁判か?」
「ああそうだ。おそらく処刑だろうな」
「違いねえ」
兵士はこちらの表情を覗きこむと薄ら笑いを浮かべながら口を開いた。
「かわいそうになあ。裁判にかけられちゃもう終わりだ」
<*>
「ほう、それではそなたはマベヤーラの手の者でないと申すか」
深く重い声が法廷に響いた。
「その、マベラーヤとかいうのは全く分かりません。ただ僕は書類を届けにクロネコヤマトに、そしてマクドナルドに寄っただけです」
赤い旗が振られた。その意味は分からないが、それを合図に、裁判官と思われる位置に座る3名の老人が相談を始めた。
「信じてください!」
その言葉に、法廷内が大きくざわついた。
「い、今なんと申した?」
裁判官の一人が身を乗り出す。何だか知らないが効果があったようだ。
「信じてください!」
また大きな声で言った。すぐに脇にいた兵士が古ぼけた本を持って裁判官に駆け寄った。裁判官はその本を急いでめくった。
「確かにそうじゃ。ここにそう記述されておる」
法廷はざわついていた。けれども、どういう仕組みか分からないが、赤い旗が振られると波が引くように静まり返った。
そして、真ん中の裁判官がかしこまった口調で話し始めた。
「信じる、とはこの古文書にあるように、大昔に存在した言葉だ。それを今しがた貴殿が口にした経緯は分からぬ。ただ、確かに存在し、誰からも忘れさられた言葉だ」
裁判官は確認するかのようにゆっくりと経緯を説明し始めた。
この世界はアドラの国、マベヤーラの国、カーリマナフの集団、と3つの団体が覇権を巡って何万年も争っていた。
長い長い戦いにおいて、多くの人々が死に、多くの裏切りが生まれた。そして人々はいつしか「信じる」ことを忘れていった。
「この言葉を口にするものが現れるとは……」
裁判官たちは一様に驚いた表情を見せた。その瞬間だった。
ドゥウウウウン!
鈍い爆発音が響いたかと思うと、少し時間をおいて建物全体が揺れた。
すぐに兵士が法廷内へと走りこんでくる。
「カーリマナフの集団による襲撃です。すでに城門を突破されました」
「すぐに避難を!」
「被告人を牢へ。傍聴人は第四避難壕に退避」
兵士の声が法廷内に響き渡った。
すぐに手錠をつけられ、長い渡り廊下を引っ張られていった。どうやら逃げないように牢屋に入れるらしい。
ドゥウウウウン!
また鈍い音が響いた。そして今度はさらに激しく建物が揺れた。
「うわあああああああああああ」
衝撃は渡り廊下の屋根を崩壊させ、その破片が兵士を直撃した。
「もしかして逃げるチャンス!?」
辺りを見回しても兵士の姿は見当たらない。おそらく全員が戦闘に出払っているのだろう。
それならば逃げるチャンスだ。なにせここに残っていたら裁判にかけられ、処刑されてしまうのだから。
脇にある階段を降り、庭園に出る。そこは中庭になっているようだった。
中央に置かれた噴水が攻撃の影響で壊れており、ひび割れから水が漏れ出ていた。
キンキンキン!
乾いた金属音が響いた。見ると、一人の兵士が大勢の敵に囲まれている。どうやら劣勢のようだ。
「アリル!」
囲まれている兵士は、あのアリルだった。赤い髪をなびかせ必死に剣を振る。しかしながらカーリマナフの者と思われる大勢の兵士に囲まれ、今にも殺されてしまいそうだった。
「ヒャッハー! くらえー!」
「くっ!」
アリルに向かって大剣が振り下ろされた。
ガキン!
「貴様! どうしてここに!」
気付けば勝手に体が動き出し、手錠を結ぶ鎖で大剣を受け止めていた。
<*>
「どうして逃げなかった? あのまま見捨てて逃げていればなんとかなったかもしれないのに」
アリルは息を弾ませながら言った。
「さあ、でもアリルを助ければなんとかなると思ったんだ。逃げるよりもずっと大切だと思った」
「ふんっ、だとしたらずいぶんと見込み違いだな。もう一度貴様を法廷に突き出すまでよ」
「それでも構わないよ。そうなるって勝手に思っただけだから、それが「信じる」ってことだから」
「信じる……?」
<*>
「アドラの王として正式に依頼しよう。貴殿はこの世界を鎮められる言い伝えの戦士。なんとしても窮地にあるアドラを救って欲しい」
王の間は静まり返っていた。数万年続いた三国の争いは、近年になって急速にその均衡を失いつつあった。アドラの国の衰えが顕著になったのだ。
追い詰められた王は古文書に記された存在にすがるしかなかった。
僕はゆっくりと立ち上がり、王に宣言する。
「僕は異世界からやってきた存在です。元いた世界では、異世界に飛ぶとすごい能力とかが身についているか、もしくはおそろしく周りのレベルが低くて無双できるって信じられていました。けれども、こうして異世界に来た僕には何の力も、能力もありませんでした」
僕の言葉をアドラの王は聞き入っていた。
「でも、もしかしたらこの世界で失われた「信じる」だけがその能力なのかもしれません。それを使っていいのなら、お引き受けします」
<*>
「とまあ、そんなやり取りがあったわけよ。君のお父さんと」
馬にまたがる僕の横には白馬に乗ったアリルの姿があった。
「ふむ、それでどうやってマベヤーラとカーリマナフを滅ぼすつもりだ。戦力の大きいほうを滅ぼすならカーリナマフが先か?」
アリルの言葉に首を横に振った。
「どちらも滅ぼさない。同盟を結ぶ」
その言葉にアリルは顔を真っ赤にして反論した。
「そんなことができるはずがない。野蛮なカーリマナフ、狡猾なマベヤーラ、それらと手を組むなんて!」
「それが「信じる」ってことさ」
「くっ」
「王は、君のお父さんは信じてくれたよ。やはり王だけあって聡明な人だ。それに引き換え君は……」
「くっ!」
<*>
小太りな男が酒樽を片手に笑顔で自己紹介をした。
「俺はバックハグ! カーリマナフの戦士だ! 俺より酒が強い奴は初めてだぜ」
「いやー、元いた世界で飲んでいたストロングゼロに比べれば」
<*>
青髪の少女が静かに口を開いた。
「私はシズル、マベヤーラの古代研究所で研究をしています」
シズルはゆっくりと古文書を手に取った。
「するってえと、古文書にも詳しいわけか!」
バックハグが前のめりの体勢になる。すぐにアリルが制した。
「怖がってるじゃない。ほんと、カーリマナフの野蛮人はこれだから」
バックハグがアリルをにらみつける。シズルは二人を一瞥すると、古文書のあるページを開いて説明した。
「ええ、古文書によると、「信じる」という行為は長い争いの果てに失われたものではありません。元凶は悪しき存在である闇の王、ルヴァタート」
「闇の王ね」
アリルが続けた。
「すべてを奪いし者、か……」
バックハグも続けた。
「3つの国には、同じような童話が残されています。何万年もいがみあい、争ってきたのに、おなじような童話が残されている。それがすべてを奪いしルヴァタートという存在です。その悪しき存在が大切なものを奪っていくというお話です」
シズルの説明にバックハグが頷いた。
「それが「信じる」なのか?」
「カルトルス山脈に住む闇の王、ルヴァタート。それによって奪い去られた信じる気持ち」
「行くしかない、カルトルス山脈に」
<*>
「フハハハハハハハハ、愚かな民よ! たった4人で何ができると思ったか!」
「くっ……」
「なんて巨大な力……」
「ここまでなのか」
ドドドドドドドド
遠くから水の音がした。そして、枯れ果てた渓谷に水が注がれる。
「童話によると、ルヴァタートは水に弱い」
シズルが起き上がりながらそう言った。それを受けてアリルが呟く。
「きっとお父様だわ」
「ありえねえ! 水門を開けることはその年の農業を諦めるってことだ。そんなことをするなんて」
「お父様……」
ルヴァタートは突如押し寄せた大量の水に浸り、少しずつ弱ってきている。僕はゆっくりと立ち上がった。
「バックハグ! シズル! アドルの国は俺たちを信じて水門を開けたぞ! でもまだ水が足りない。お前らもそれぞれの国に戻って国王を説得し、水門を開けてこい!」
その言葉にバックハグが反論した。
「無理だ! 水門を開けるなんてとんでもない!」
シズルも首を横に振る。
「うちも無理です。むしろうちだけ開けずに水を確保し、優位に立とうと考えます。マベヤーラはそういう人種です」
「いいから開けてこい。お前らならできる、信じてる!」
「お、おう」
「はい!」
バックハグとシズルが傷ついた体を引きずり、それぞれの国に帰っていく。
<*>
「ずいぶんバカなことしたものね。絶対にマベヤーラもカーリマナフも水門は開けない」
「その時はその時さ」
岩陰に身を隠しながらアリルと二人で体を支えあう。
「あきれた。どうしてそんなにバカになれるの?」
「それが信じるってことだから」
<*>
ドドドドドドドド
遠くからまた水の音が聞こえた。
「そうらおいでなすった」
「うそ、そんな……」
「マベヤーラもカーリマナフも水門を開けた。バックハグとシズルがやってくれたんだ。これが信じるってことさ。悪くないだろ」
アリルはゆっくりと頷いた。
押し寄せる大量の水、ルヴァタートは半分ほどの大きさになっていた。
「さあて、童話によると水で弱らせたあとどうなるんだ?」
アリルがゆっくりと答える。
「子供の時に聞いた話では、光の存在が弱ったルヴァタートと交わりお互いに消えて、闇が晴れるって」
この岩陰もどんどん水位が上がってくる。
「光の存在が俺ってことかな」
アリルが頷く。
「じゃあいってくるわ。ここで待ってろ」
岩から飛び降り、腰まで水に浸かる。ゆっくりと歩きだすと、アリルが声を上げた。
「まって!」
振り返る。
アリルは視線を下に落としてモゴモゴと何かを言っている。
「あの、その、あの、し、し、信じてるから!」
そう言って顔を真っ赤にした。そして照れ隠しなのか少し視線を外しながら続ける。
「初めて言ってみたけど、いい言葉だね」
「任せろ!」
そう言って、ポケットから五千円札を取り出し、アリルに渡す。
「持ってろ。お守りだ。俺がルヴァタートを消し去って、この世界に「信じる」が戻ってもきっと争いは消えない。元いた世界がそうだったからな。
むしろそこからのほうが大変だ。信じるからこそ、苦しいことも悲しいこともある。それに直面するはずだ。それでも人を信じられるよう、このお札を見て思い出してくれ。このお札に書かれている新渡戸稲造って人は著書の中でそういうことを書いている」
「ニトベイナゾウ……」
アリルは五千円札を強く握りしめた。
<*>
「さあこい! ルヴァタート」
ルヴァタートに対峙する。
一瞬、ルヴァタートの闇が広がったかと思うと、手元から溢れ出した光がその闇を中和していった。
「ぐわあああああああああ」
視界が真っ暗になり、その後、眩い光が見えた。そして、この世界で最初に見たのと同じ、少し濃い青空が見えた。
気が付くと、マクドナルドの駐車場にいた。夢だったのだろうか。きっと夢だったのだろう。おそらく極度の腹痛が気を失わせ、夢を見せていたのだ。
急いでマクドナルド店内に入り、用を済ませてクロネコヤマトに向かう。
こんなおつかいでも信頼して任された仕事だ。しっかりとやり遂げなければならない。
クロネコヤマトに到着する。そこで気が付いた。五千円がない。忽然と五千円札が消え失せていた。
「アリル……」
見上げた空は、あの世界のように少しだけ濃い青空に見えた。
とまあ、こういう感じに書き直せるわけです。
皆さんもぜひとも、最初にインターネットに書いた文章を何度も何度も書き直してみてください。そうすることで自分がどの位置にいるのかわかるはずです。
僕はこうして異世界ものを書いてわかりました。やっぱり才能がない。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
著者名:pato
テキストサイト管理人。WinMXで流行った「お礼は三行以上」という文化と稲村亜美さんが好きなオッサン。
Numeri/多目的トイレ
Twitter pato_numeri
(Photo:Hefin Owen)