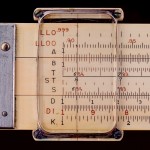原田くんは、彼氏である自分への悪口が書かれた恋人のブログを読んでしまったことがある。
自分という人間の至らない点を文章化された挙句、それをワールドワイドウェブに公開されたのだ。
彼は間違いなく、もっともそのブログを読んではいけない人間だっただろう。
だが不幸にも読んでしまった。
そして、当たり前のようにひどく傷ついた。
その日、当時大学生だった原田くんと彼女は映画を見に行った。
映画のタイトルは忘れてしまったが、おそらく単純なアクションではなく、解釈が難解なミステリーなどだったのだろう。
でもなければ、後の悲劇は起こりようがない。
彼らは映画を見て、食事をし、別れた。
一部の隙もないよくあるカップルのよくあるデートコースだ。
家に帰った原田くんはシャワーを浴びると、よせばいいのに缶ビールを片手にネットサーフィンを始めた。
ほんの軽い気持ちで、昼間見た映画について検索したのが失敗の始まりだった。
あの映画を見たほかの人たちは、どんな感想を抱いたのだろうか。
あの難解なラストシーンをどのように解釈したのだろうか。
そんなささやかな好奇心を満たそうとしたのだ。
アインシュタインだって
「大切なのは、疑問を持ち続けることだ。神聖な好奇心を失ってはならない」
と言っている。
しかし、たまたま見つけたアメーバブログを読んでしまったことで、彼はどん底につきおとされた。
そこには、映画を見た場所、時間、シチュエーションなどから判断して、自分の彼女が書いたとしか思えない内容が書かれていたのだ。
時間から察するに彼女は帰宅してすぐにこのエントリを書いたのだろう。
「来ている服がダサい」
「いつも同じような店を選ぶ」
「家まで送る素振りすらみせない」…。
彼女の批判は痛烈かつ的確だった。
帰宅して、すぐブログに書き連ねるほどストレスをためていたのであれば、なぜ直接自分に言ってくれないのか。
どうせ数時間後にネットを通じて、知らされるのだ。
ならば、オフラインでいうべきことじゃないのか。
原田くんは心の中で、そう絶叫したという。
このエピソードは彼の人生の中でも、他の追随を許さないぶっちぎりの黒歴史である。
今でもたまに思い出して、叫びたくなることがあるほどだそうだ。
おそらく、これほど惨めな瞬間を経験したことがある男は多くないだろう。
彼はそう思っていた。何年か前までは。
***
「それ、本当に友達の話なんですか?原田さんの実体験なんじゃないんすかね?」
原田くんは、職場の飲み会で、このエピソードを”俺の友達が経験した話”として披露した。
すると、数年来、同じ部署で仕事をしている原田君の後輩が勘ぐってきた。
この後輩は口が悪い。
普段から、かろうじて敬語を使いはするものの、敬意が微塵も感じられない態度で原田くんに接している。
勘が良くそれゆえに優秀な男である。
この時も、あっさりと原田くんのつまらない見栄を見破り、真相へとたどり着いた。
そして、いつも通りヘラヘラと彼のとっておきの黒歴史エピソードをイジり倒すのだろうと思った。
しかし、予想に反して、後輩は普段とは少し違ったテンションで話をつづけた。
「正直に話してくださいよ。僕は原田さんの気持ちわかりますから。昔同じような経験したことあるんですよ」
こいつは俺と同じ地獄を経験している…。
敬意の足りない後輩だが、これからは以前より良好な関係で仕事が進められそうだ…。
原田くんはそう思った。
後輩は続ける。
「自分は学生だった4年間、同じ彼女とずっとつきあってたんすよ」。
付き合っていた期間が長ければ長いほど裏切られた時のダメージは大きかったろう。
原田くんは会話のテンションを飲み会らしいものにするべく、
「絶え間ない愛を注いでたってわけだ」
とかつて流行したJ-POPの歌詞を引用して、茶々を入れる。
「まぁそういうことっすね」
後輩は少し肩をすくめただけで、テンションは相変わらずシリアスなものだった。
後輩とその彼女は大学受験の頃に池袋の予備校で出会った。
受験の前から付き合い始め、別々の大学に進学してからも関係は続いた。
概ね良好だった二人の関係に変化が訪れたのは就職活動が始まったころだった。
当時、後輩は大手新聞やTV局といったマスコミ業界を志望していた。
今も変わらず学生人気の高い業界だ。
たいしたコネもない後輩は、内定を得ることができず、就職浪人を視野に入れ始めた。
一方の彼女は、学生時代に家庭教師のアルバイトを続けてきた経験を活かし、早々に教育関係の企業の内定をゲットしたそうだ。
ここまで聞いて原田くんは、とてもありふれた学生恋愛の破局の在り方だと感じた。
そして、だからこそリアルだとも思った。
「それで結果的にふられるわけなんすけど、問題はその後なんすよね」
後輩は、別れた後に偶然にも彼女のブログを見つけてしまった。
後輩の友人が彼女と同じブログサービスを使っており、”足跡”的な機能を使ってたどり着いてしまったというのだ。
「読まなきゃよかったんですけど。いや、本当にそう思いますよ。当時に戻れるなら、クリックしようとしている自分を羽交い絞めにしますね」
そう語る後輩の顔はいつもの自信に満ち溢れたものではなかった。
いつの間にか原田くんたちのテーブルのムードは、一般のサラリーマンの飲み会とは程遠い湿っぽいものになっていた。
「なんていうんすかねぇ。すごいリアルなんですよ、ブログの形式って。1日ずつ確実に彼女の心が僕から離れていくのが、文章になってるんですから」
その日、席にいたメンバーは全員後輩より年上だったが、みんな黙って話を聞いていた。
たかだか数年の人生経験では、こういう時に掛けるべき言葉は見つからない。
それぐらい、後輩の話は重かった。
「それで僕と別れたいなぁみたいな話が最初に出てきてから数日後に、就職活動中に出会ったっていう知らない男が出てくるんです。10年以上前のことですけど、名前まだ覚えてますよ。上田さんって人でしたね」
正直、もう辞めてほしいと思った。
なぜ後輩は、こんなにすみずみまで彼女のブログを読んでしまうのか。
どうせ傷つくのはわかっている。
ならば、サラッと眺めるだけにして、二度とアクセスしなければいいじゃないか。
どうして過去にさかのぼって読み続けてしまうのか。
だが、原田くんは知っていた。
人は好奇心を抑えられない。
彼もかつてはなめるように恋人のブログを隅々まで読んだのだ。
幸いにして、自分に関する記述があったのは一つのエントリだけだったから、傷は浅くて済んだ。
そういえば、原田くんが当時彼女と見た映画のタイトルは
「好奇心は猫を殺す」
だったかもしれない。
確か元はイギリスのことわざだったはずだ。
「後はご想像の通りです。彼女は僕と別れて上田さんと付き合うんすよね。僕は、自分を嫌いになって別の男に魅かれていく恋人の様子をブログを通じて追体験したってわけです。
どうです?服とか店選びのセンスをdisられるぐらい、たいしたことなくないっすか」
そういって後輩は、氷が溶けてかなり薄くなっているであろうハイボールを飲み干した。
「そうかもしれないな。それにしても俺は今の話を聞いて、おまえとやっと腹の底からわかりあえたような気がしたよ」
後輩による唐突な黒歴史のカミングアウトによって、暗い雰囲気に覆われた席の空気を変えるべく、原田くんは可能な限り陽気なテンションでそう言った。
当初自分が披露したエピソードはあくまで”友達の話”であるという設定すら忘れていた。
それに対して、後輩は先程と同じように肩をすくめると、いきなり言った。
「先輩たちは、ピーチジョンって知ってます?」
後輩は、急にそんな質問をしてきた。
思い出話がひと段落したと安心していた原田くんたちは、意表を突かれた。
それでも出てきた単語の意味は知っている。
ピーチジョンは女性用の衣料を販売している企業だ。しかし、それがどうしたというのか。
「ここまで来たら全部話しちゃいますけど、僕、ビーチジョンがトラウマなんすよね」
原田くんたちの頭の上に、はてなマークが並んでいるのを無視して、後輩は吐き出すように一気に続けた。
「読んじゃったんすよ、彼女のブログで。『ピーチジョンの可愛い下着買ったよ』から『下着が役に立ったんだよ』っていう一連の流れを」。
後輩はハイボールを飲み干そうとしたものの、残念ながらグラスはすでに空だった。
そして、残念ながら原田くんたちは全員おっさんだった。
「下着が役に立つ」という言葉の行間に込められた意味を十分に理解できるほどに。
かつてフランスの詩人シャルル・ペローはいった。
「好奇心というものは、とても人の心をひきつけるが、往々にして多くの後悔のもとになる」と。
世の中の男女全員に伝えたい。
例え、それが全世界に向けて公開されているものだとしても、恋人のブログなんてものは読んではいけないのだ。
見つけてしまったら、黙ってブラウザを閉じるべきだ。
絶対に読んではならない。
少なくともブログの筆者と付き合っていた人間だけは。
原田くんは当時の後輩が味わったであろう絶望の深さを思い、致命傷だと思われた己の傷が軽く皮膚をかすめた程度のものだということを知った。
そして、己のトラウマを相対化し、職場の後輩との精神的絆を強めることができたという。
***
今度こそひと段落したと思われるこの話には、最後に問題が一つ残っている。
それは、これを書いている僕が原田くんの後輩であるということだ。
【著者氏名】永田 正行
大学卒業後、零細出版社に広告営業マンとして勤務。
その後、会報誌の編集者を経てネットメディアの編集記者となり、政治家や大学教授へのインタビューを多数手掛ける。
好きな言葉は「ミラクル元年 奇跡を呼んで」の西武ライオンズファン。