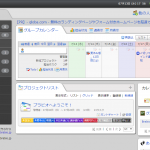先日、こんな記事を拝読しました。
この記事を読んで思ったことについて、とあるゲームの紹介を起点に語りたいなーと思います。よろしくお願いします。
***
かつてファミコンに、「キャッスルエクセレント」というめっちゃ面白いゲームがありました。
発売は1986年11月、発売元はアスキー。ジャンルでいうと「アクションパズルゲーム」に該当するでしょうか。
いくつもの部屋が複雑な構造で繋がっていて、部屋から部屋はいろんな色の扉でふさがっていて、対応する色の鍵がないと開けられない。
主人公のラファエル王子は、人間離れした凄まじいジャンプ力と、爪楊枝か?と思う程リーチが短い剣を武器に、敵をかいくぐりながら鍵を集めて、王女マルガリータ姫の救出を目指す。
PCの「ザ・キャッスル」というゲームの続編をファミコンに移植したゲームなんですけど、このゲーム、凄く面白くって、かつものすっっっっごく難しかったんですよ。
まず面白かったポイントについてなんですが、
・軽快なアクションと爽快感、それを彩るポップなBGM
・マップがとにかく広大で、どこに行っても新しいギミックがあって、「お城を探検している」というわくわく感がとても強い
・「集めた鍵をどこで使うか」というやりくりの面白さがある
・「回数を重ねるごとに少しずつ先に進めるようになる」という、自分が上手くなっていく、ノウハウが溜まっていくという爽
快感・達成感がある
・パズルが解けると滅茶苦茶気持ちいい
この辺については断言してしまってよいと思うんです。
とにかく「試行錯誤している内に少しずつ先に進めるようになっていく楽しさ」というものについては保証付き、文句のつけどころがありませんでした。
何度も何度もゲームを繰り返していくうちに、少しずつ「あ、ここはこうすればいいんだ」「こうすれば先に進めるんだ」という知見が集まっていって、段々見える景色が広がっていく。
およそ「プレイヤーに良質な達成感を与えてくれる」ゲームに悪いゲームは存在しないんですが、キャッスルエクセレントの「上達に伴う達成感」はファミコン全体を見回しても屈指のものだったと思います。
ゲーム自体の完成度の高さ、操作感の楽しさもあって、当時はずいぶん夢中になって遊びました。
ファミコンのアクションパズルゲームの中では、「ソロモンの鍵」「迷宮島」「バベルの塔」辺りと並んで、最高傑作の一角と言ってもいいんじゃないかと考えています。
とはいえ難易度の高さも折り紙つきでして、「激ムズ」と言ってしまって差支えがないゲームです。
恐らく、ファミコンのあらゆるタイトルの中でも、自力でオールクリアするまでの難易度では最高峰といっていいのではないでしょうか。
・単純にパズル・アクションの難易度が高く、ステージの構成をよく見て、きちんと考えて動かないと解けない
・マップ構成が複雑で、きちんとノートに記録しないととても覚えられない
・初見殺しのマップも多い(開始即ラファエル王子が落下し始めて、空中で特定の軌道をとらないと即死するマップとか)
・鍵は一度使うと消えるのだが、正規ルートだと鍵の数に一切余裕がなく、余計なところで余計な鍵を使うと詰む
・しかも「詰んだ」ということはしばらく進めないと分からない
・何が詰んだ原因になったのかもあれこれ検討しないと分からない
・セーブ機能前提でバランス調整されているような節があるのだが、別売りの外部記憶媒体(ターボファイルやデータレコーダー)がないとセーブが出来ない
まーなかなかしんどいですよね。
当時私、小学校低学年くらいだったと思うんですが、「買ったからにはすべてを遊び尽くす」というスタンスの私や友人たちも、結果的には「無理だ……」となりまして、攻略途中で挫折してしまいました。相当悔しかった記憶があります。
私がこのゲームをクリア出来たのは何年も後、友人のお兄さんの「キャッスルエクセレント攻略ノート」を見せてもらってからでした。
そのお兄さんのノートがまた大変緻密でして、マップすべてが図に書き出してあって、正解の攻略ルートが書き込んであることはもちろん、部屋ごとのギミックの特徴とか抜け方とかびっしり書いてありまして。
コピーの一つもとらせてもらえば良かったと思うんですが、とにかく凄まじい密度の攻略情報が詰まっていたんですよ。
当時、「これが「ゲームを攻略する」ってことなのか」と感動する一方、「このゲーム、ここまでしないと自力でクリアできないのか……自分には無理だった……」と思い知らされもしました。
「ここまで出来る人が一体何人いるんだ……?」とも思いました。
だから、キャッスルエクセレントは、私にとって「子どもの頃夢中になって遊んだゲーム」であると同時に、「初めて「ガチの攻略」というものを見せられたゲーム」「初めて攻略に挫折したゲーム」でもあるんですよ。
***
ここで話は冒頭の、匿名ダイアリ―の記事に戻ります。
キャラクターの成長を概念的に感じるためのシステムだと説明されても、俺はプレイヤーとして成長の実感をシンクロして味わいたいと思ってしまう。
だがレベルはプレイヤーの成長に対する実感を完全に失わせる。
勝利とは「レベルを上げたことで物理で殴れた」のマイナーチェンジであり、敗北さえも「レベルが足りてないので物理で殴りきれなかった」となる。
PDCAサイクルを回して試行錯誤しようにもその裏にはいつも「そもそもレベルを上げればいいだけでは?」という疑問と「どんなに頑張ってもレベルが足りてなければクリア出来ないのでは?」という不安がつきまとう。
凄まじいストレスだ。
主にRPGを対象にした、「レベル制」というシステム自体に対する苦言、という話ですよね。
正直私、この増田(はてな匿名ダイアリ―の記事作成者の俗称)が言いたいこと、分からなくもないんですよ。
つまり、
・「レベル制」というシステムを安易に運用した結果、漫然とした作業としての「レベル上げ」が常態化している
・「レベル上げ」が「試行錯誤しての上達」というゲームの楽しさの妨げになっている
ということですよね。私、作業感が強いゲームがちょっと苦手な一方、「試行錯誤を積み重ねてプレイヤースキルを上げていく」とか「敵の動きを学習して自分の行動を最適化していく」といった要素は大好きなので、そちらに重点をおいてゲームを楽しみたい、という気持ちは分からなくもないです。
ただ、「結局タイトル次第」ということは前提においた上で指摘するとしたら、
・「レベル」があっても試行錯誤の余地がなくなるわけではない(むしろゲームによっては、レベル制があるからこそ試行錯誤が成立する)
・世の中試行錯誤が好きな人ばかりではなく、レベル制がゲームを遊ぶ上での福音になっている人も数多い
という点は挙げられるかも知れません。
まず、そもそもレベル制って「難易度、ゲーム進行の調整弁」ですよね、という話があります。
難易度を下げるばかりではなく、上げることも出来る調整弁。
大筋、レベル制RPGのバランス調整というものは、「場面場面での適正レベルを決める作業」がその根っこになります。
この敵を倒すには、ざっくりこれくらいのレベルで挑むのが適正。このレベルに達すれば、この呪文が使えるようになってダンジョン攻略がだいぶ楽になる。これくらいのレベルがあれば、敵の攻撃に〇回までは耐えられるから回復が間に合う。
これは、開発者さんにとって、プレイヤーがゲームを攻略する速度をある程度調整する手段になると同時に、プレイヤーにとっても「難易度を上げる/下げる」手段の一つになります。
「楽に攻略したければレベルを上げるし、歯ごたえがある攻略を楽しみたければ低レベルで挑む」という選択の余地をプレイヤーに提供しているんですね。
「低レベルクリア」って一種の縛りプレイとして認識されていますけれど、あれ驚く程裾野の広い遊びでして、一見シンプルなゲームでも「こんな低レベルでいけるのか……!」「こんなやり方でクリア出来たのか……!」と驚かされることはしばしばあります。ミネルバトンサーガのレベル0クリアは衝撃だった。
これは、「適正レベル」があってこそ発生する試行錯誤の一例と言えるでしょう。
ただ、それとは別の話として、
「ゲームに試行錯誤をつぎ込める人、試行錯誤を求めている人ばかりではない」
という話もあると思うんです。
ジャンルこそ違え、上記のキャッスルエクセレントなんて「試行錯誤をつぎ込めばつぎ込む程面白くなる」ゲームの典型だったんですが、これが楽しめる人、周囲に何人いたかなあ?と考えると、正直そんなに何本も指を折れません。
「このゲーム面白いよ!」と言って勧めた相手、多分10人近くいたと思うんですが、殆どのケースで「難しくてよくわからんかった」と返されました。
私自身、楽しめはしたつもりですが、攻略は途中で挫折してしまったわけで、「そもそも楽しめるところまで行きつけない」という人の方が、周囲でも多数派だったでしょう。
「試行錯誤による上達の達成感」って、どうしても楽しさを感じられるようになるまでハードルがあるんですよ。
ハマるとめちゃ楽しいんですが、ハマれるまでが長い。それまでにゲームを離れてしまう人、そのゲームに挫折してしまう人、いくらでもいます。こればっかりはもうどうしようもない。
私、これまでゲームについての記事も色々と書かせて頂いていますが、「試行錯誤に伴う上達、達成感」というのは、私がゲームを楽しむ上での重要な軸の一つです。
「このゲームに試行錯誤の余地はどれくらいあるか?」「それによって、プレイヤーはどの程度「上達の快感を味わうことが出来るか?」ということを私は重視しますし、そこが刺さるゲームは大体ベタ褒めします。
ただ、そういった記事に頂く反応を見ていると、「そういうことは求めてない」という人の声も相当数あるんですよね。
何度も場数を踏んで腕を磨く、試行を重ねてプレイヤーレベルを上げるということこそ、「面倒くさい」ことに思えてしまう。
ゲームに求めるのはストレス解消であって、ゲームの中でまで頭を使いたくない、という声だってありますし、それは決して「間違っている」わけではなくって、単にゲームを遊ぶ上でのスタンスの違い、という話だと思うんです。
そういうスタンスの人が、けれど「ゲームの攻略」を諦めなくてはいけないのか?というと、決してそんなことはないと思うんですよね。
ゲームはどんな人でも楽しめるべきだし、エンディングにたどり着いた時の感動を味わう権利はどんな人にも与えられるべきです。
色んな遊び方があっていいし、どんな遊び方も否定されるべきではない。
そこから考えると、「レベルさえ上げればどんなに強力なボスでもいつかは倒せる」というシステムは、一種の重要な救済措置、大げさに言ってしまえば「ゲームの裾野を広げた偉大なシステム」と言ってもいいんじゃないかなあ、なんて思うんです。
一方、それこそキャッスルエクセレントや、最近遊んだ中ではOuterWildsのような、「プレイヤースキルのみが上がっていくゲーム」も私は大好きでして、まあ色んなゲームが栄えていって欲しいなーと。
ちなみに、世の中には「レベル上げ自体が楽しい」という人も割と数いるわけでして、「ハイドライドスペシャル」でスライムをぷちぷち潰してレベルを上げる楽しさに目覚めて以降、私自身結構レベル上げにはまっちゃう側面はあります。
ワルキューレの冒険でレベルが上がる時のファンファーレ好き過ぎる。
レベル上げが「強制」になってしまうのはイヤなんですが、「良質のレベル上げ」が楽しめるゲームについては、今後ともじゃんじゃか楽しんでいきたいなあ、と考える次第です。
今日書きたいことはそれくらいです。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
著者名:しんざき
SE、ケーナ奏者、キャベツ太郎ソムリエ。三児の父。
レトロゲームブログ「不倒城」を2004年に開設。以下、レトロゲーム、漫画、駄菓子、育児、ダライアス外伝などについて書き綴る日々を送る。好きな敵ボスはシャコ。
ブログ:不倒城
Photo by Lorenzo Herrera