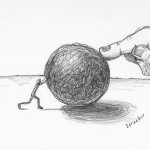紙ストローってなんか味が変になる気がするんだよね。プリントみたいな味がする。
誰かが放った紙ストローへの悪口はその喧騒へとすっと溶け込んでいった。
当たり前のように放たれている言葉だが、それは少しだけ様子がおかしい。
プリントみたいな味だなんて、プリントを食べたことがあるやつしか分からない感覚だ。それを知る人は少ない。妙なことを言うもものだと印象的だった。
昼下がりのカフェは少しだけ賑やかだ。
「なんか今日はめちゃくちゃ混んでるね!」
彼女は褐色のアイスコーヒーグラスが乗せられたトレーを両手に持ち、いそいそと対面の席に腰かけた。
「それでね、さっきの続きなんだけど、すごいのよ、マッチングアプリは」
注文前に話していた話題の続きとばかりに話し始めた。正直、まだその話題が続くのかと少し笑ってしまった。
彼女はいつも煮詰まると僕に声をかける。
前回に会ったときは離婚を考え始めた頃だっただろうか。それから月日が経ち、どうやら正式に離婚が成立したらしい。
それからさらに時間が経過し、僕に声がかかった。どうやらまた何かに煮詰まったらしい。
「色々な人と出会えるんだよ」
彼女は興奮気味に語る。離婚後の彼女は、いわゆるマッチングアプリに夢中のようだ。
マッチングアプリとはオンライン恋愛サービスで、ひとむかし前の出会い系サイトに近い形態だ。
恋愛相手となる多くの候補が提示され、この人いいかも、とアクションをするらしい。
向こうもこちらを見て、いいかもとなったらマッチングとなる、あとはメッセージのやり取りをするなり会うなりご自由に、そんなサービスのようだ。
美人であり、おまけに自撮りのスキルが高い彼女はおそらくマッチングアプリでも無双の活躍を見せているのであろう。
それは容易に想像できた。実際に彼女の口ぶりからして多くのマッチングを経て、多くの異性と会っているようだった。
それは彼女にとってとてもエキサイティングな体験だったことは想像に難くない。
「ただね……」
そのマッチングシステムへの興奮とは裏腹に、彼女は不満げな表情を見せた。やはり煮詰まっているらしい。
「やっぱりこういう出会いってダメなのかな。誠実な人がぜんぜんいないの」
そこまで言ってはじめてアイスコーヒーのグラスを口に運んだ。味を確かめるようにして褐色の液体を少しだけ口に入れ、しばらく間をおいて言葉を続けた。
「ウソばっかりだね。職業をウソついていたりとか年齢をウソついていたりとか、実は既婚者だったりとか婚約者がいたりとか、彼女がいたり、結局は私の体が目当て。まあ、私もそういうの嫌いじゃないけどね」
そう言って大きなため息をつく。
「思えば誠実な人、私の人生にいなかったな。みんな誠実じゃなかった」
前の旦那のことを思ったのだろうか、それとも目の前の僕も含むのだろうか、マッチングアプリの男だけでなく、彼女の人生において誠実な男などいなかったと言い切った。それはいささか暴論のようにも思えた。
「どこかに誠実な人、いないかな」
こうなった時の彼女はまあまあ面倒くさい。男とは、誠実とは、そもそも男女の恋とは、そんな話が延々と続く。それらは往々にして自分本位ともいえる彼女寄りの持論だ。
そこに大きな一般性はないが、彼女自身は正しさを求めているわけではない。ただ、その暴論とも思える話を聞いて欲しいだけなのだ。そんな彼女にとって僕はちょうど良い相手なのだろう。
「まあさ、いま“誠実な人はいない”って言ったけどさ、それは大きな間違いだよ。そもそもこの世に誠実な人は存在しないから」
連撃コンボのように続く彼女の言葉、息継ぎの瞬間を見計らって僕の言葉を割り込ませる。
我ながら良いタイミングだったように思う。そもそも、こうなった時の彼女はとても面倒だが、それと同じくらい、そうなった彼女に対峙したときの僕も面倒なのだ。
「どういうこと?」
彼女は眉をしかめた。
「よく誠実であることと正直であることを混同することがあるけど、それは違う。誠実と正直は全く違うものだって話。そもそも誠実は人間の内面に自然発生的に生じる状態ではない。そうしようとして到達する状態だ」
僕の言葉に、彼女はさらに分からないといった表情を見せた。
「つまり自然体で“誠実”という状態は存在しない。人は誠実であろうとして誠実に振る舞う。そこに本質がある」
そう噛み砕いても彼女は不思議そうな表情を見せたままだった。もっとわかりやすくエピソードを交えて話す必要がある。
面倒な状態が確変みたいになった僕は、さらに面倒な思い出話をはじめた。
「これは僕が中学生の時の話なんだけど、すごく傷つく事件があったんだ。あれはいま思い出しても辛いものがあるね。でも、誠実と正直についてよくわかる事件だったよ」
その年のクラス編成はまるで狙いすましたかのようなものだった。
生徒数が多く、クラス数の多いマンモス校といえる中学に通っていたが、そんなマンモス校でのクラス編成はなかなかエキサイティングなものだった。
せめて数人は仲の良い友達がクラスメイトになって欲しいと願っていたけど、結果としてはあまり仲良くない人ばかりのクラスになってしまった。
おまけに妙にやる気あふれる新任の先生が担任だった。どちらかといえば苦手な熱血タイプだ。
早くもこの1年間の中学生活に暗雲が立ち込めたような気がした。
新学年が始まり、しばらくしてからのことだった。熱血な担任が大量の小さな紙が束になったものを配り始めた。
その紙の束は40枚ほどの紙片がまとめられており、その紙片の一つ一つにはクラスメイトの名前が印刷されていた。
40枚の紙束を40人に配る、合計で1600枚の紙束だ。それはなかなか大変な作業で、なにか大掛かりなことが始まる予感がした。
「その紙にクラスメイトに関して感じた印象を書いてください。印象が書かれた紙はぜんぶ本人に渡します。そのつもりで書いてください」
熱血な担任教師は本当に大掛かりなことを言いだした。
おそらくではあるけど、クラス運営を円滑に行うためにこういうことをやりましょう、みたいなマニュアル本の影響を大きく受けたような唐突さだった。
たぶん、クラスメイトの良いところを考えさせ、人間関係とはお互いを思いやる気持ちなのですよと気づかせ、さらにはみんなあなたのこんな良いところをみていますよ、これからもそこを伸ばしていってね、と自尊心を満足させる効果を狙ってのことなのだろう。ただ、これ自体はとても残酷なことじゃないかと感じた。
まず、クラスメイト40人全員の印象を書く、これは大変な作業だ。ひとりひとりに想いを馳せ、その印象を文章化して本人が読むことを意識して書く、かなり重い作業だ。
最初こそはクラス内でも目立っている人物の良いところを記載できる。
リーダーシップがあるとかそんなところを順調に記載していく。
けれども、7,8人を超えてくるといよいよ怪しくなってくる。面倒になってくるし、そもそもそこまで印象にない人が増えてくるので思いを馳せる作業が重くなっていく。
さらに先に進むと、もうほとんど知らない人だ。印象もクソもない。なんとかひりだすようにして印象を書くのだけど、それこそ「髪が長い」とか外見的な特徴、それも当たり障りのないものになってしまうのだ。
さらには、40人もいるとけっして良い印象を抱いていないやつも何人か混じってくる。
そこに書く文章はかなり難しい。下手すると悪口みたいになってしまうからだ。
「どんな意見にも理屈っぽい反論をしてくるから苦手」
「会話の時にかならず否定から入る癖はやめたほうがいい」
みたいなことを書いては消す作業を繰り返す。そう印象を持っているのだからそう書くのが正直ということだろう。
けれども、さすがに本人が読むことを前提に考えると悪口を書いてはいけない、そんな気がしたのだ。
「いつも理論的な意見をいってくれる」
そうなるとこの辺の表現にとどまってくる。
おそらくこれはもう“正直”ではない。“真実”ではない。けれども、読む人のことを考えて傷つかないように文章を変える。
これが“誠実”なのだろう。中学生ながら僕はそう感じた。
“誠実”とは結果への責任だ。これによってどういう結果が引き起こされるか、それを考えて行動することこそが“誠実”なのだ。
なにごとも事実をそのままに記述することを“正直”であるとするならば、“誠実”はときに事実を捻じ曲げることもある。
結果、“正直”ではない状態も誠実”に含まれる。嘘を交えたり本心を隠したりして“正直”でなくとも“誠実”は成立するのだ。
「ちょっと君は正直と誠実を混同している気がしたからさ」
僕の言葉を受けたわけではないだろうけど、喧騒の一瞬の静寂をついて彼女のアイスコーヒーの氷がガラリと崩れる音が響いた。
「なにそれ? 確かに正直と誠実は違うかもしれないけど、マッチングアプリでウソをつく人は決して誠実ではないでしょ? だって私を傷つけたくないわけじゃない。自分の欲望のためじゃん」
厳重に抗議するとでも言いたげな早口でそうまくしたてた。
「そう、マッチングアプリで嘘をつく人は正直ではないし、誠実でもない。この話はそういうことじゃないんだ。じゃあ人はどういうときに誠実になるのかって話なの」
まるで大学で教鞭をとる教授のように、未使用の紙ストローを振り回し、話の続きを始めた。
なんとか苦労しながら40人の印象を書いた紙束は、中身を見ないように厳重に回収された。
担任は大きな段ボールにそれを投げ込み、キラキラとした瞳でいった。
「これを各個人あてに並べなおして皆さんに配ります。明日まで待ってください」
1600枚の紙束を明日までに仕分けるらしい。なかなか大変な作業だ。
クラス40人が僕に対して抱く印象を書いた紙が配られる。
いったいどんなことが書いてあるのだろうと思ったけど、ドキドキというよりは不安みたいな要素が大きかったように思う。あまり目立つ方ではないので、僕が苦しんだ後半の人たちのように、他の皆も僕を後半に記述しているはずだ。
きっと当たり障りのないことばかり書かれているに違いない。その気遣いを考えると少しだけ心がキュッとなった。
次の日のホームルーム。クラスはざわついていた。あの紙束を楽しみにしているのだ。
中心的な人物で目立つタイプの連中は浮足立っている感じで、みんなが褒めてくれると信じて疑っていない様子だった。
他の連中も似たようなもので「ねえ、なんて書いたのよ」「ひみつ」みたいに浮かれていた。
教室に入ってきた担任は、僕たちの予想に反して、あの紙片の束が入ったダンボールを持っていなかった。
それどころか、教卓に陣取ると、目から大粒の涙をボロボロと流しながら泣き始めた。
「先生は悲しい」
あまりの泣きっぷりに僕らは沈黙し、驚き、そして意味不明なバツの悪さを感じていた。
「どうやら先生が君たちに教えていたこと、間違っていたみたいだ。あの紙のことは忘れてください」
なんとなくだけど、先生がなにに怒っているのか分かったような気がした。
おそらくであるけど、何人かの人が“正直”に記入をしたのだろう。それを読んだ本人が傷つくことを分かっていて“正直”に思ったことを記入した。
それを読んだ先生はとても本人には渡せないと思ったのだろう。
「先生のやり方も間違っていた。あの紙のことは忘れてください。もし、もしだけど、これから1年間このクラスで過ごしてみて大丈夫そうだなって思ったら、もう一度、このクラスの最後、3月にやりましょう。先生もみんなも成長していこう」
先生は多くは語らなかったが、やはり誰かを傷つける“正直”な言葉がかなり書かれていたのだろう。それを配るわけにいかないので中止にしたのだろう。
なんとも重苦しく、バツの悪い思いをしながらその日のホームルームが終わっていったのを今でも覚えている。
それからしばらくして、社会の授業の手伝い係だった僕は、授業で使う模造紙に書かれた大きな地図を担任のところまで取りに行った。職員室に入ると、タイミングが悪いことに保護者から電話がかかってきたようだった。
「準備室に置いてあるから持って行ってくれ!」
そう指示だけして準備室のカギを渡してくれた。
準備室は様々な教科の小道具が置かれている場所で、かなり乱雑な様相を呈していた。
問題の模造紙は棚の中段に置かれていたけど、そこに到達するまでにはいくつかのダンボールをかき分けて進む必要があった。
そのうちの1つのダンボールに目が留まる。
「あのダンボールだ」
明らかにあの日のダンボールがそこにあった。お蔵入りしたやつだ。大量の紙片が投げ込まれたであろう紙片がそこにあったのだ。
蓋を開けてみると紙片もそこに詰まっていて、おそらく担任が仕分けしたのだろう、個人ごとにまとめられて輪ゴムでくくられていた。
なんだか他の人のものを見るのは悪い気がしたので、そっと自分の紙束だけを読んでみた。
「汚い」
「臭い」
「気持ち悪い」
「不潔」
「シャツがいつも同じで汚い」
「汚いので学校に来ないで欲しい」
「○○菌がうつる」
めちゃくちゃ悪口を書かれていた。
特に汚さに関する悪口はなかなかに辛辣で、僕の心を傷つけるには十分なものだった。
当時の我が家はめちゃくちゃ貧しくて貧乏だった。
制服のシャツも1枚しかなかったので洗濯するわけにもいかず、いつも汚いものを着ていた。風呂だって節約のために毎日のように入るスタイルではなかったので、まあ汚かった。
それがかなり嫌われていたらしい。
みると、悪口の書かれた紙片には担任が「これはダメ」と赤い付箋をつけていたみたいで、僕の紙片にはほぼ赤い付箋がついていた。ほぼすべてが悪口というやつだ。総スカンというやつだろう。
唯一、赤い付箋がついてない紙には「会津若松っぽい」という意味不明な印象が書かれていた。意味が分からない。
他の人の紙束には1個か2個しか付箋が付いていなかったことを考えると、ほぼ僕への悪口が原因で、あの紙片の儀式は急遽中止になったようだ。
誰もいない準備室。午後の日差しがカーテンの隙間から入り込んでいて、舞い上がる埃がキラキラと反射して光の通り道を作り出していた。
その通り道の先に佇む僕は、ただただ声を押し殺して泣いた。
「やっぱり傷つくよね」
彼女は紙ストローをクルクルと回しながらアイスコーヒーをかき混ぜた。そのたび氷がガチャガチャと擦れ合う音が響いた。
「いや、悪口を言われてショックで泣いたんじゃない。そんなやわじゃないし、嫌われていることは薄々に気付いていたからね。40人全員に汚いと罵られたってあまりなんとも思わない。泣いた理由は別なところにある」
「別なところ?」
彼女は首を傾げた。
「悪口を書いた皆は“誠実”ではなかったけど“正直”であった。皆が書いた紙片、約束を反故にしてあれを配らなかった担任は“正直”ではなかったけど“誠実”であった。ただそれだけ、正直と誠実の違いがあっただけだ」
“正直”は結果に対する責任を負わず、ただ正直に振る舞ったと自分の中で満足する行為だ。内面的ともいえる。
反面、“誠実”はそれによって生じる結果まで考慮して振る舞う行為だ。内面以外の外の部分まで考慮する行為だ。
このエピソードの中で唯一、誠実であったのは担任だけだった。
40人からの悪口を読んだら僕が傷つくだろうと考え、約束を破り、正直であることを捨てて儀式を中止にした。
僕はそれが嬉しかったのだ。先生は僕に対して誠実であった。それだけが嬉しかった。
「僕はね、先生の中で誠実に値する人間だったってことだよ。どんなに皆に嫌われてもそれは僕の支えみたいになっている」
冒頭でも述べたが、人は自然発生的に誠実な状態にならない。
“正直”は内面的なものなので自然でそうである人もいるが、“誠実”は外的要因も絡んでいて自己完結しないので、自然にそうはならない。
全ての人に対して“正直”であることは可能だけど、全ての人に対して“誠実”であることは不可能だからだ。
するとどうなるか。人はどうしても誠実に対応する人と、そうしない人を分けることになる。人を選んで誠実になるのだ。
恋人や好きな人に対して誠実であれど、そのへんの知らない人には誠実にはならない。そんなことしていたら身が持たないからだ。
「さっきに君のマッチングアプリでの言葉だけどさ……」
「誠実な人がいなかった、じゃない。単に君が誠実に扱われなかっただけだ」
「そして、誠実な人どこかにいないかな、じゃない。誠実な人はいない。君自身が誠実に扱われるように振る舞うべきだ」
少し厳しい口調の僕に彼女は不満げな表情を見せた。ただ、僕は彼女が誠実に扱われて欲しいと願っている。
遅れたからお前けつあな確定な、みたいに乱雑に扱われて欲しくないのだ。
彼女は少し考えて言葉を発した。
「どうすればいいの?」
「それはわからない。けれども、僕自身は、自分を大切にしていて、それでいて僕に対して誠実に振る舞おうとしている人には誠実に振る舞うかな。そこにヒントがあるかもしれない」
カフェの喧騒の中、彼女が反芻するかのように呟いた。
「この世に誠実な人はいない。誠実に扱われる人と扱う人がいるだけ……」
アイスコーヒーのグラスの外側を水滴が滑り落ちるのが見えた。
40枚の紙片のエピソードには続きがある。
それから月日が経ち、3月、いよいよこのクラスでの最後のホームルームの時間がやってきた。担任は見覚えのあるダンボールを担いできて、これまた見覚えのある紙束を配り始めた。
「みんなはこの1年、成長したと思う。だから約束した通りこれをやろうと思う」
またあの儀式がやってきたのだ。
「読む人のことを考えて“誠実”に書くように」
同じような流れで注意事項を説明される。ただ、最後に新しいルールが追加された。
「先生もさ、この1年でいろいろと成長したよ。そしてわかった。40人全員の印象なんて書けないよな。無理に書く必要なんてないよな。だから、どうしても書けない人のやつは白紙にしておいてくれ。それは本人には渡さない」
それは暗に、悪口を書くくらいなら白紙でだせ、ということなのかもしれない。なんにせよ、苦しんで書く必要がないのだから助かると思った。
次の日。仕分けされたあの紙片が返却されてきた。順番に返却され、それを読んだ人々から歓声があがる。
「やだー、恥ずかしい」
「うそー、そんなことないってー!」
「もう! これ咲子でしょ。こっちだって親友だと思ってるよ!」
たぶん、けっこういいことが書いてあるんだろう、みんな一様に笑顔だ。
どうしても書けない人のヤツは書かなくていいと新ルールが制定されたので、ほとんどの人が白紙で出すと思いきや、この1年でみんなクラスメイトに様々な思い入れがあるらしく、書き出すと止まらなくなったようだった。
みんなけっこうな数の紙片を返却されている。
そんな中、ついに僕の紙束が返却されることとなった。ちょっとドキドキしながら受け取る。
僕の紙片は2枚しかなかった。
ほとんどが白紙で提出されたということだろう。それはそれでなかなか淋しいものがあるけど、まあ悪口を書かれるよりはましというものだ。
1枚目を開く。
「会津若松っぽい」
だからなんなんだよこいつは。前回も書いていたじゃねえか。しつこいし意味が分からねえよ。
そして2枚目の紙片を見て絶句した。
それは、明らかに担任の字なのだ。プリントなどで見るちょっとクセのある文字がそこに記載されていた。
おそらくではあるけど、ほとんどが白紙で、1つだけ記載された紙が「会津若松」と意味不明だ。さすがにそれは良くない、傷ついてしまうと考えた先生が書いたのだろう。
こういった儀式において担任の先生がクラスメイトのふりをして参加するのはルール違反だし“正直”ではない。けれども“誠実”であるように思う。
結果、最後まで先生は僕に“誠実”であってくれたのだ。
さて、その先生の“誠実”が具現化した紙片。なにが書かれていたのか。先生は僕にどんな印象を持っていたのか。ドキドキしながらその文面を読む。
「クリケットが得意そう」
どっからクリケットが出てきたんだ。あまりにも脈略がなさ過ぎてビックリだ。狂ったか。
とにもかくにも、クリケットは意味不明であるけど、先生は最後まで僕に対して誠実だった。僕は先生の中で誠実に値する人間だったのだ。
「結局、クリケットはやったの?」
彼女の言葉に僕は首を横に振った。クリケットをやるには11人のチームが2つ必要で、22人揃える必要がある。
会津若松としかクラスメイトに書かれなかった友達の少ない僕にはどだい無理な話だった。
「せっかく先生が書いてくれたんだからやってみるのが“誠実”ってものじゃない?」
「いやあ、無理でしょ」
彼女はやけに乗り気だ。
「そのとき先生が書いてくれた紙は持ってる? どうせ捨てられなかったでしょ? それを掲げながらみんなでやろうよ!」
「いや、もってないんだ。カバンの中に入れておいたら親に見られそうになって、なぜかクリケットはともかく会津若松は見られたらなんて説明していいのか分からんし恥ずかしいと意味不明に焦っちゃってね、とっさに2枚ともくしゃくしゃにして食べて隠した。プリントの味がした」
僕の言葉にも彼女は怯まない。
「22人、集めてさ、やってみようよ! 私もやるよ!」
「やけに前向きじゃん」
僕の言葉に彼女はさらに身を乗り出した。
「だって、誠実に扱われるには誠実に、でしょ。私の周りにある誠実なことはなるべくやっていきたい。わたしはいまクリケットを助けることが誠実だと思っている」
彼女はけっこうどうしようもない人間だけど、こういう単純なところはとても誠実だと思っている。だから僕は、彼女に誠実に対応するのだ。
「じゃあやってみようか。クリケット。まずは22人集めよう。」
「うん」
また人が増えたのかカフェ内が混みあってきた。ひと通り喋り終えた僕は初めて自分のアイスコーヒーを飲む。すっかり水滴がついてグラスはグシャグシャに濡れていた。
紙ストローを通じて飲むアイスコーヒーは少し変な味で、なんだかプリントの味だった。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【プロフィール】
著者名:pato
テキストサイト管理人。WinMXで流行った「お礼は三行以上」という文化と稲村亜美さんが好きなオッサン。
Numeri/多目的トイレ
Twitter pato_numeri
Photo by CFPhotosin Photography