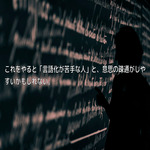「雑誌の投稿コーナーに載る為に必死に文章を練習して、他人に読んでもらう文章を書くことの困難さに気付いた人」というのがどれくらいいるのか分かりませんが、私はその中の一人です。
この記事で書きたいことは、大体以下のような内容です。
・昔、「ゲーメスト」という超面白いゲーム雑誌がありました
・読者投稿コーナーに掲載される為、いわゆるハガキ職人を目指して頑張っていました
・全然載らなかった為、兄に頼み込んで投稿内容を添削してもらいました
・その時の兄の言葉で、「文章というものは、書いた本人が読む時と他人が読む時で全く違うものになる」ということに気づきました
・兄に添削してもらうようになってめでたく投稿コーナーへの掲載の夢が叶い、以来文章を書き続けています
・載らなくても載らなくても全く飽きずに投稿し続けた、という諦めの悪さも、一つの資質だったのかも知れません
・どんな文章であれ、「レビュー」「壁打ち」って滅茶苦茶重要ですよね
以上です。よろしくお願いします。
さて、書きたいことは最初に全部書いてしまったので、あとはざっくばらんにいきましょう。
まず、「ゲーメスト」というゲーム雑誌の話から始めさせてください。
ゲーメスト。発行は新声社、創刊は1986年。創刊当初は家庭用のゲームも扱っていたものの、やがて「ゲームセンターのゲーム」の攻略に特化したアーケードゲーム専門誌となり、格闘ゲームの全盛期だった1994年に月二刊化。その後、残念ながら新声社が倒産してしまった1999年まで、ゲーメストはゲーセンを中心としたアーケードゲーム文化の重要な担い手であり続けました。
当時、アーケードゲームを中心に扱っているゲーム雑誌というのは数少なく、ある程度まとまった情報を得る為には、この「ゲーメスト」や「ネオジオフリーク」「GAME遊」、あとは「マイコンBASICマガジン」あたりしか、私の生活圏内では選択肢がなかったような記憶があります。
小学校~大学にかけてゲーセンに通い詰める日々を送っていたしんざきが、最も愛読していた雑誌がこの「ゲーメスト」です。発売日には欠かさず本屋に走って、本当に寝る間も惜しんでゲーメストのページを繰り続けていました。
ゲーメストは、本当に凄かった。熱かった。面白かった。
ゲーメストの攻略記事は、当時の自分からは想像もつかない、「大人の本気」を詰め込んだ内容でした。
STGでの避け方、稼ぎ方。レースゲームでのテクニック、アクションゲームでの各ステージの特徴や敵の動きの解説といったところから、対戦格闘でのキャラクターごとの細かい立ち回り方、技の当たり判定やキャラ同士の相性まで、とにかく恐ろしい密度の情報が載っていました。
ゲーメストを読むことは、それ自体ゲームを遊ぶことと変わらないゲーム体験でした。全然遊んだことがないゲームでも、「ゲーメスト」を読むことで楽しむことが出来た。
当時は「ゲームの攻略情報」を摂取することで、親にも怒られず、お金も使わずにゲーム体験が出来るという場面が、確かにあったのです。
記事が基本的に記名で、ライターさん一人一人の個性が際だっていたことも特筆すべきかと思います。主に投げキャラを愛用されていた「アディオスToshi」さん、豪鬼といえばこの人の「C-LAN」さん、同じオルバス使いとして何度も記事を参考にさせてもらった「K・TAN」さん辺りの名前は今でも頭に残っています。
個性豊かな攻略ライターさんたちが書く、「大人のゲーム研究」。自身ゲームをやり込んでいたライターさんたちがこれでもかこれでもかと詰め込んだ攻略情報は、「ゲーム攻略」と言えば「そのゲームをクリアしてエンディングを見ること」だという認識しかなかったしんざきには、異次元とすら思える高密度でした。「ダライアス外伝」のムックは毎日枕元に置いていました。
当時、まだインターネットは一般的なものではなく、当然「攻略Wiki」のようなものも手が届く場所にはありませんでした。
ゲーム攻略の同人誌やパソコン通信の情報を除けば、「ゲーメスト」で得られる攻略情報は、掛け値なく当時最高峰の内容だったと言っていいと思います。誤植も多かったけど。
さて。
ゲーメストには、攻略記事以外にも、様々なページがありました。
ゲームの紹介、ゲームネタ四コマ、ハイスコア集計から、お遊び企画、ゲームと何の関係もない謎の企業広告漫画まで。ホームレスのおっさん二人がゲームと何の関係もない話をしてるテクナートの広告漫画、妙な味わいがあって癖になりましたよね。
そんな中でも異彩を放っていたのが、読者投稿・交流ページである「ゲーメストアイランド」です。
イラストや漫画ももちろん多士済々だったのですが文章ネタも多く、日記風味の随筆、ゲームマナーについての議論からゲームをネタにした短編小説風のコメディまで、様々な投稿が掲載されていました。
これがまた、「アーケードゲーム」という極めて限定されたコンテクストを背景にしていることもあってか、どの投稿も自分の感性に刺さって、とにかく滅茶苦茶面白かったんですよ。
「自分も何か書きたい!」「アイランドに載せて欲しい!」と思いました。
SNSで手軽にイラストや文章を発信出来るようになった現在では、「読者投稿コーナー」への強烈な憧れというものがいまひとつ理解出来ない、という人もいるかも知れません。
昔は、ある程度オタク気質を持った人は、「自分が書いたものが投稿コーナーに載る」ということに、大抵一度や二度は憧れるものだったんですよ。
もちろん「たくさんの人に自分の創作物を見てもらいたい」という欲求も多少はあったんですが、それ以上に「ゲーメスト」というコンテンツの一部になりたい、ほんのわずかでも「ゲーメスト」という滅茶苦茶楽しい場を作る側に参加したいと、そんな思いが強かったのではないかと記憶しています。
その憧れだけを原動力に、私は投稿ハガキを量産し始めました。
ゲーセンで見た光景、ゲームをネタにした創作、ゲームの感想、あれこれ考えては文章にして、ハガキにたたきつけました。
さっぱり載りませんでした。
当時中学校に入る直前か、入った直後くらいだったのでしょうか。国語の授業以外では文章を書いた経験など一切ない子どもが書いたものです。
今から考えると惨憺たる内容だったんだろう、担当者さんもさぞかし困っただろうと思うんですが、当時は毎回毎回「すげー面白いものが書けた!」というつもりだったんですよ。
「今回こそは!」とゲーメストを開いては、真っ先にアイランドを確認して、自分の名前が見当たらないことを確認しては落胆する、という繰り返しでした。
人によっては黒歴史になるのかも知れませんが、幸いしんざきには羞恥心というものがありません。過去に投稿したハガキを読み返しては、「おかしいなー面白いのに」と思う日々が続きました。
私には5歳上の兄がいます。私と同様、兄もゲーマーです。私がゲームを始めたのは兄の影響でして、ゲーメストを購入し始めたのも兄でした。
当時、兄をゲームの先達と考えていた私は、「ねえこれ面白いよね?」と、どこから来ているのか全く不明な自信で兄にハガキを見せました。
おそらく兄も戸惑ったのでしょう。とはいえ兄は5歳下の私に対しても一切ゲームの手加減をしない男で、大抵の対戦ゲームで私をボコボコにしては泣かせていました。この時もそれと同じように対応するよう決めたのでしょうか、
「面白いとか面白くないの前に、何を言ってるのかさっぱり分からん」
と言われました。
この時兄が教えてくれたのは、細かいところは曖昧ですが、大体下記のようなことでした。
・お前の記憶や考えというものはお前の脳みその中にしかない
・お前が自分で読み返す時には、書いた時の記憶や考えが背景になって勝手に文章を補ってくれるのかも知れないが、それが通用するのは書いた本人だけ
・お前以外の人間は、文章を全てゼロスタートで読む必要がある
・お前が自分の文章を読んで感じた面白さは、他の人には一切伝わらないと思え
・それを理解した上で、きちんと背景から何からちゃんと説明して、せめて何が書かれているか分かるようにすれば、1000人に1人くらいは面白いと思ってくれるかも知れない
・その1人が投稿コーナーの担当者であることを祈れ
容赦ないですよね。でもまあ、「それはその通りだなー」と当時も思ったんですよ。
そこから、私は愚行の手順を少し変えました。広告の裏に投稿内容を書いて、それを毎回兄に読ませて、「何も分からん」と言われた文章をあれこれ直しました。
・伝えたいテーマを一つないし二つに限定して、そのテーマに沿っていない文章がないかどうかを考える
・何を指しているか分からない指示語を使わない
・スラングやゲーセン用語が一般的に意味をとってもらえるものかどうか考える
・文章の主語を意識して、文章の途中で主語や主題が変わっていないかをチェックする
・場面や話題を変える時は、「ここで話が展開しました」ということが明確にわかるような言葉を入れる
兄にあれこれ聞いて、これくらいはチェックするようになったのでしょうか。
兄もよく付き合ってくれたなーと今では思います。毎回、「何も面白くないが、まあ言いたいことは分かるようになった」と言われてから、初めて投稿ハガキに書くようにしました。
結果、私はとあるシューティングゲームをクリアした時の体験をアイランドに掲載いただき、「載ったぁぁぁ!!」と大声をあげることになりました。
以降、頻繁にとはいきませんが、ちょこちょこ投稿も載るようになり、私は「文章を書く」楽しさにじわじわとハマっていくことになるのです。
今から振り返ると、これが「自分が書いた文章を他人に読んで欲しい」と思った、ほぼ初めてのタイミングだったのではないかなーと思います。(厳密に言うと、このもう少し前、「アドベンチャーラーズイン」というゲームブックの折り込み冊子にも私は投稿しているのですが、脇道過ぎるのでここではいったん置いておきます)
この後私は「パソコン通信」に出会い、草の根ネットで様々な文章を書くようになったのですが、それも「アイランド」への投稿への情熱あっての話だったのだろうなあ、と今では思います。
身近に「文章の壁打ち」の相手になってくれる、しかもゲーセンのゲームというコンテクストを理解してくれる相手がいたということは幸運という他なく、これがなければその後ブログをやっていなかったかも知れないし、今文章を書くこともなかったかも知れません。げに、「自分の創作を他人に見てもらう」というのは、重要かつ貴重な機会なのだなーと思うばかりです。
そして、上記の文章の中で多少なりと私に誇れることがあるとすれば、それは「諦めの悪さ」でしょう。
載らなくても載らなくても飽きもしなければ自信喪失もせず、自分に甘い評価基準のまま徹底的にハガキを書き続けた点は、それはそれで文章書きとして資質の一つなのかも知れない、と自画自賛する次第なのです。
長くなりました。
時代は変わり、「投稿コーナー」のあり方も変わりました。かつてのように「雑誌に載りたい」という情熱をもって文章を書き続けている人こそ、今ではだいぶ少なくなったかも知れませんが、それでもある時代、ある時にこんな情熱が存在したんだと、その程度のことを知っていただければなーと思い、こんな文章を書いたわけです。
今日書きたいことはそれくらいです。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
著者名:しんざき
SE、ケーナ奏者、キャベツ太郎ソムリエ。三児の父。
レトロゲームブログ「不倒城」を2004年に開設。以下、レトロゲーム、漫画、駄菓子、育児、ダライアス外伝などについて書き綴る日々を送る。好きな敵ボスはシャコ。
ブログ:不倒城
Photo:yamauchi