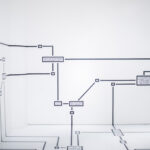ちょっと前に金ローでやってたバック・トゥ・ザ・フューチャーシリーズを録画したまんまだったので妻と2017年生まれ小学1年生の息子との家族3人で観るなどしていた。1986年生まれの率直な感想を書く。寄稿で!?
いや、面白いね。俺は「今観てもおもしろい」んだけど「今の子供が観てもおもしろい」んだね。すごいね。
そもそも父親と母親の恋のキューピッドをやり遂げないと自分の存在がヤバい!という設定はむしろ小学校低学年くらいの方が気兼ねなく楽しめるのではないか。うちの夫婦は僕がわざわざ北海道から大阪の大学に進学して妻の方も一度進学を諦めて社会人を経験してから大学に入り直して年齢は妻の方が上なのに僕の後輩として大学で出会ってそこから恋仲に落ちて今に至るという経緯なので、お互いの結構な決断と偶然がなければお父さんとお母さんは結婚してなかったしそうなるとお前は生まれてなかったんだぞという話を兼ねてから息子によくしていたので息子もバック・トゥ・ザ・フューチャーのストーリーの大筋を抵抗なく受け入れていた。なんで片方のじーじとばーばが北海道なんてクソ遠方にいるかなどの説明をするうえでの必然ではあったのだが図らずしもバック・トゥ・ザ・フューチャーを見るうえでの事前学習になっていた格好だ。
何より家族みんなで見れるタイミングとしては最適ではなかろうか。「赤ちゃんはどうやってできるの?」を限りなくふんわりしか知らないタイミングじゃないとあんまり親と観たい映画ではない。昔の若いお母さんが俺に恋愛的アプローチ積極的に仕掛けてきたりするし。俺じゃねえけど、思春期の中学生男子が観るとマーティ=俺になる。
でも今のキッズたちってそこらへんどんな感覚なんでしょうね。20世紀末の僕が中学生の時はクラスメイトに弟が近々生まれるってやつがいてそいつはまー「お前の親セックスしてるんだ」ていじられまくってましたけどそういうのってまだあるんでしょうか。インターネットでは中年夫婦のセックスやセックスレスの話題がたくさん見かけられる2025年、キッズにとってそこらへんどういう処理になってるのか中年のおじさんには知る由もありません。でもさや香の漫才で自分が生まれた時の親父がかなり高齢だったことを話す人にもう片方が「めっちゃエロいやん」と返してるのがウケてたので全くなくなってはないのでしょうか。ただ最近の若者がM-1を面白く見守ってるのかどうかもおじさんにはよくわかりません。
何にせよ「お父さんとお母さんが出会ってなかったらお前はこの世にいなかったんだよ」くらいのふわっとした認知の時にこの作品に触れられる小学1年生はかなりちょうどいいんじゃないかと思う。自分がそういう偶然の産物であるという前提を事前共有できてたところも含め。実際問題、マーティの「親の恋のキューピッド達成できなかったら自分即消滅ミッション」って心の準備できてなかったらかなり怖いよね。小学4年生の時に地獄の概念怖すぎて毎晩布団の中で震えて泣いてた俺には耐えられなかったと思う。
そしてやっぱシナリオがすごい。タイムリープとかタイムパラドックスの概念を教える教材として秀逸。日本においてここらへんの概念を前提としたコンテンツをみんな当たり前に受け入れて理解できる土壌を作ったのはバック・トゥ・ザ・フューチャーとドラえもんと言っても過言じゃないでしょう。そして過言だったらいつでもケツバットの罰を受ける準備が俺にはできている。え、今ってケツバット駄目なの!?
余談になるんですけどテレビなどのバラエティ番組では令和になった今でも罰ゲーム文化はまだ全然普通に残ってるんだけど、めっちゃ苦いお茶を飲ませたりとか電流を浴びせたりとか、ちょっとカネと準備の手間が大変なのでYouTuberは実現できるけど学校の教室ではサクッと実現できないくらいの罰ゲームがポピュラーになってきてる気がしている。子どもが安易に真似して事故が起きないことが重要であって、人が酷い目に遭ってるのを笑う文化を無くそうみたいな方向性には全然なってない気がする。あと、僕が学生だった20年前はマーティの真似してスケボーとか自転車で車に掴まるやつは存在しました。めっちゃ危ない。そういう意味では子どもが真似しにくい演出に寄ってるだけで世界は多少はマシになってるのかもしれない。
話をバック・トゥ・ザ・フューチャーに戻しますが、2017年生まれの小学1年生と一緒に観るとなるとPart2からがグッとややこしくなります。そもそも舞台が1985年始まりでそこから父親と母親が出会う1955年にタイムリープするPart1はなんとか説明できたとしても、息子からすると自分が生まれる2年前にあたる2015年が「未来」に設定されてるPart2はかなりややこしい。だって2025年現在、空飛ぶ車とかホバリングできるスケボーとかまだ無いし。大阪万博?知らねえよ!ジュラシックワールド観てても「これは本当にあった話?」と確認してくるような小学1年生に作品中の時系列と現実との関連を説明するのはかなり骨が折れるわけで、ドラえもんを俺から見ても100年後くらいの遠い未来から送り込んでくれた藤子・F・不二雄先生には説明の手間が省けて複雑さが簡略化されて感謝しかありません。
またPart2になるとタイムパラドックスに留まらず平行世界の概念が登場して、Part1ではあえて触れなかったところも含めて粋だなと感じる一方さらに難しくなっている。Part2まで見届けた時点で小学1年生の息子も必死に全体のストーリー構造を理解しようとして「ちょっと待ってドク何回死にかけてる?」とか一生懸命リビングに備え付けのでかいホワイトボードに時系列を書いて整理しようとしていました。そうなんですよね、ドクの一番かっこいいところって、自分は何回も死にかけるのに今の自分は大事にしつつ一番最初のデロリアンが走り出す前のマーティを元の1985年に戻すことを第一優先にずっと躍起じゃないですか。もともとはドクの発明から始まった話なので自分で蒔いた種じゃねえかトラブルメーカー的ポジションではあるはずなんですが、自分の引き起こしたトラブルを収束させようと責任感をもって真摯に向き合い年の離れた若い友人のあるべき未来をなにより最優先に慮りつつそれでも未知なる冒険への好奇心を抑えきれないしワクワクを隠しもしないドクというキャラクターは中年になってみるとまた違った感慨があって胸が熱くなります。もちろん、今回の金ローではかつてマーティを演じた山寺宏一がドクを演じるというのも、自分自身の年齢を重ねた作品の見方に重なってグッとくる。
Part3は、まぁなんか基本的に1985年に帰って来るために頑張るだけの話だしまぁいいか。いや、本当はPart3はドクが主役だよねみたいな話をめちゃめちゃしたいんだけど。それでもやっぱ触れなくちゃならないのは、1885年でのマーティの経験で2015年のマーティーの未来が変わって、そしてドクが「未来は君たちが決めるんだ」って言葉を残してどこかへ去っていくのはもちろん作品全体の総括として最高の流れで、三作品をかけて過去に行ったり未来に行ったりしっちゃかめっちゃかのタイムトラベルだったけど結局は17歳のマーティ少年の大冒険からマーティ少年は多くを学び大いに成長して少しだけ考え方を改めて結局これからもそういうふうにアドベンチャーと日常を繰り返しながら一本道に自分の未来を進んでいくんだな。それを教えてくれたきっかけがたまたまデロリアンだったからあっちに行ったりこっちに行ったりに見えるだけで、マーティみたいな若者の人生もドクみたいな中年の人生も誰の人生もそういうふうに真っ直ぐ真っ直ぐ進んでいくんだって思って、真っこと改めて素晴らしい映画でございました。宮野真守がドクの役をやる頃にまた観たい(みんな長生きしような)。
あと最後これ余談なんですけど、すでにPart3制作が決まってたのかすでに撮影中だったのかPart2のラストで「Back to the Future Part III coming summer 1990」って予告みたいなのが表示されて、1985年と1955年と1885年と2015年の物語を2025年に生きる立場から必死に時系列を整理してなんとかついてしていこうとしていた小学1年生の息子はどういうcomingなのかわからない1990年の追加によって頭パンクしていて面白かったです。
以上です。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
著者名:ズイショ
関西在住アラフォー妻子持ち男性、本職はデジタルマーケター。
それだけでは物足りないのでどうにか暇な時間を捻出してはインターネットに文章を書いて遊んだりしている。
そのため仕事やコミュニケーションの効率化の話をしてると思ったら時間の無駄としか思えない与太話をしてたりもするのでお前は一体なんなんだと怒られがち。けれど、一見相反する色んな思考や感情は案外両立するものだと考えている。
ブログ:←ズイショ→ https://zuisho.hatenadiary.jp/
X:https://x.com/zuiji_zuisho
photo by Roger Ce