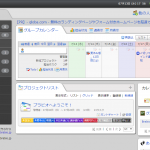ビジネスパーソンにとって、なぜ「書く力」が必要なのか
皆さんは仕事で文書を書く機会があるだろうか。 営業であれば日報を書いたり、マーケティング担当であれば、こんな風にブログ記事を書いている人もいるかもしれない。
書くことが本業ではないという人でも、お客さんや社内の関係者にメールを書く機会はあると思う。最近はチャットツールなどの発達で、仕事のやりとりはメールやチャットで済ますという人も多いのではないだろうか。
私も仕事のやりとりはメールで済ますことが多いのだが、時にメールの書き方が悪く、仕事に支障をきたすことがある。 何度もやりとりをした上に手戻りが発生し、なかなか仕事が進まない。
仕事で使う以上、メールは立派なビジネス文書だ。
そして、そもそもビジネス文書の目的は、その趣旨を読み手に理解してもらい、意図する通りに行動を起こしてもらうことだ。
いくら丁寧に時間をかけてメールを書いたとしても、依頼内容を理解してもらえない、相手が行動を起こしてくれなければ結果的には意味がない。
普段そこまで意識してメールを書いているだろうか。 最悪の場合、読み手はあなたのメールをいつもわかりにくいと感じている。読んですらいないかもしれない。
それでも「あなたのメールはいつもわかりにくいです」と指摘されることはない。心の中で「メールがわかりにくい人」という烙印を押されて終わりだ。
「書く力」が、あなたのビジネスの成果を左右する・・・というのは言い過ぎかもしれないが、隠れた必須スキルであることは間違いないだろう。
書く力を身につけるための3つのポイント
いきなり本文を書き出さず、「誰に」「何を伝えるか」を決める
わかりやすい文書を書く最大のコツは、書く前に「誰に」「何を伝えるか」をじっくり考えて決めることである。
書くのが上手な人は、共通してこのプロセスを重視している。 逆説的だが、このプロセスを怠ると後で余計に時間がかかることになる。
書くのが苦手な人は、パソコンに向かってすぐに文字を打ち始める。締め切りまでに返信してもらいたいのか、あるいは部署に回覧してもらいたいのか、メールの目的やゴールを決めずにとにかく書き始める。
結局途中で手が止まり、読み返したところで何を言いたいのかわからない文章が出来上がっている。時間もないので「ま、いいか」と送信ボタンを押すが、相手からは一向にメールの返事が返ってこない。
忙しい人ほど焦って書き出したくなる気持ちはとってもわかるが、まずはその衝動を抑えてみよう。 むやみやたらと書き始めず、「誰に」「何を伝えるか」を考える。たった1分でもいいから考える。この2つさえ決まってしまえば非常にわかりやすいメールになるし、何しろ書き手自身が楽になる。
「読み手」をできるだけ具体的に思い浮かべる
心に響かない文書は、たいてい「読み手」が不在である。特に報告書やブログ記事など、不特定多数に向けた文書で起きやすい。誰にでも受けそうな文書は、結局誰の心にも届かない。
逆に、読み手の人物像が明確になれば、どうすればその人に伝わる表現や構成になるか、自然と考えるようになる。どの言葉を選べば相手に刺さるメッセージになるのか、どうしたら行動を起こしてくれるか。 その人の気持ちを想像しながら書く。すると文章に熱がこもり、その人に伝わる言い回しや表現になる。
時にラブレターのように、時に親が子供を諭すように、どのような書き方が一番響くのかを考えながら書く。
世の中には様々なハウツーが溢れているが、何よりも大事なのは、文を書きながら相手を想う気持ちだと思っている。
たまに終始言いたいことだけを言い放った、自分よがりの文章を見ることがある。
しかし書くことはコミュニケーションの一部であり、相手がいて初めて成り立つもの。 どんな書き方がわかりやすいか、どんな言葉を付け足せば喜んでくれるか、そんな風に読み手の気持ちを想像して書けば、きっと想いは伝わるのではないだろうか。
ひたすら書いて添削してもらう
とはいえ、いきなり誰もが感嘆する素晴らしい文書が書けるようになるわけではない。
バットの素振りと一緒で、基本の型を習ったら、まずはたくさん振ってみる。その後コーチに見てもらい、フォームを改善してもらう。
文書も同じで、まずは基本ルールをおさえてとにかく書く。書いたものを添削してもらう。添削箇所をさらに書き直す。ひたすら書いて添削を繰り返すことが、書く力を身につける最短の道である。
おまけ:「書く」特訓は「考える」特訓になる
一見地味な「書く」という行為を続けていると、実はものすごいおまけが付いてくる。それは「考える力」である。
文章は、頭の中で考えたことが見える化されたもの。頭の中身がぐちゃぐちゃな人は、文章もぐちゃぐちゃである。逆に論理的な文章を書きながら頭の中がぐちゃぐちゃという人はいない。 これは「書く」だけでなく「話す」場合も一緒だ。
「メールがわかりにくい」「話がわかりにくい」と言われる人は、実はアウトプット前段階の「考える」力の弱さに原因があることが多い。
人間は自分の思考する以上に書くことはできない。だからこそ、書く前に「誰に」「何を伝えたいのか」をしっかり考える必要がある。この約束を守れば、きっとあなたの文書はわかりやすいものになるはずだし、心を動かされる人さえ出てくるだろう。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
−筆者− 大島里絵(Rie Oshima):経営コンサルティング会社へ新卒で入社。その後シンガポールの渡星し、現地で採用業務に携わる。日本人の海外就職斡旋や、アジアの若者の日本就職支援に携わったのち独立。現在は「日本と世界の若者をつなげる」ことを目標に、フリーランスとして活動中。