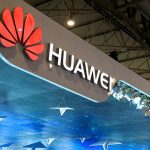誰かに仕事を依頼するのが苦手な人は結構いる。
マネジャーになったにも関わらず「自分でやったほうが早い」と手を動かしてしまう人も数多くいるが、それではマズい。
当然のことながら、相手にこちらの依頼を確実に遂行してもらうスキルは、必須であるとともにマネジメントの要諦でもある。
だが「こちらの依頼を確実に実行させる」と一口に言っても、その実践はそれほど簡単ではない。例えば、簡単な打ち込み作業を、あなたがアシスタントにお願いするとしよう。
「こちらの営業資料のデータを、急ぎ、エクセルに打ち込んでほしいんだけど」
アシスタントの方は言う。
「今日は結構忙しいんですが……」
「夕方までになんとか!」
「わかりました。」
しばらく後に様子を見ると、期待通り打ち込まれている……と思いきや、少し見ていくとなんかデータがおかしい。
「ここ、間違ってますよ」と指摘すると、「あ、すみません」と直してくれた。
だが、あなたは少し不安だった。もう数箇所、データを細かく見ていくと、他の部分も少しずつミスがある。
おいおい……、ミスだらけじゃないか……。
と、あなたはつぶやいて、アシスタントの人を呼ぶ。
「これ、他の場所にも結構ミスがあるんだけど、きちんとチェックした?」
「いえ、急ぎだとうかがったので、ひとまず打ち込みました。ミスが多少あるかもしれません。」
「かもしれません、じゃないよ。これって大事な営業のデータだよ。間違っちゃ困るんだよ。」
アシスタントの方はムスッとしている。
「わかりました。もう少しお時間をいただけますか。」
あなたは疲れてつぶやく
「こんなの、言わなくてもわかるだろうに……。」
さて、何が悪かったのだろうか。
もちろん、アシスタントの責任にすることもできる。「仕事への取り組みの姿勢がダメなのだ」と糾弾することもできよう。
だがこのアシスタントの責任にしても、同じようなことが再発する可能性はある。
実際、あなたが本当に得たいのは、「だれの責任かを特定する」ことではなく、「同じミスを起こさないこと」ではないだろうか。
そう考えていくと、これは「頼み方」がマズいという結論に達する。つまり、悪いのは発注者であるあなただ。
発注者の頼み方が変わらない限り、また同じことが起きる。このアシスタントが起こさなかったとしても、人が変わればまた起きる。
もちろん
「いやいや、どう考えてもミスをしたアシスタントが悪いだろう」という方も多いと思う。
それは理解する。
だが、たとえこのアシスタントがミス無く仕事をしていたとしても、先ほどの
「打ち込んでほしいんだけど」
という依頼は、ある意味「最低の依頼の方法」と言える。
なぜなら「仕事の品質管理水準」を相手に委ねていることになるからだ。実は「品質管理を相手に委ねる」のは、最悪の依頼の方法なのだ。
私は新米だったころ、コンサルタントの上司からこう習った。
「コンサルの現場ではお客さんに宿題を出すだろう。」
「はい。」
「例えば、営業の業務フローを作って欲しいとき、お前ならどうやって宿題を投げる」
「ええと……ぎ、業務フローを作って欲しいんですが、お願いできますか? でしょうか……。」
「ああ?そんなんでお客さんがキチンと作ってくると思ってるのか。」
「す、すみません。」
「依頼というものは、どの水準のものを作って欲しいのか、きちんと確認をしなければ、絶対にきちんとしたものは挙がってこない。」
「はい。」
「フローを作るときは、どの形式で作るか、どの粒度で作るか、どの範囲で作るか、そういったことを細かく定めないと、めちゃくちゃになるぞ。依頼前に、フォーマットをきちんと協議するんだ。」
品質管理を相手に委ねてしまう依頼の仕方は、たとえどんな水準のものが上がってきたとしても文句は言えない。それは「発注者がサボっているだけ」なのだ。
ただ、勘違いしないでいただきたいのは、「品質の水準」は相手に示すが、「品質の管理方法」は相手に任せても良いということだ。
管理方法まであれこれ指示をすると、箸の上げ下ろしまで細かく指示をすることになり、かえって効率が落ちる。
よって、先ほどの依頼であれば、このように頼むのが望ましい。
「営業の分析用の資料を、急いで作って欲しい。明日の夕方に使うから急ぎで。精緻に分析をする資料だから、ミスが絶対にないようにお願いしたい。」
「わかりました。」
「ミスをなくすために、どうするかイメージ湧く?」
「はい、前にもやりましたから。表のレイアウトはこの資料と同じでもいいですか?違うとチェックしにくくなるので。あと、私ともう一人で、ダブルチェックをかけたほうがいいですか?」
「うん、そうして欲しい。」
—————————
プロジェクトマネジメントにおける世界標準規格「PMBOK」において「プロジェクト品質マネジメント」の項目の一節には、最新の品質マネジメント手法では、以下に示す点が重要であると述べている。
検査よりも予防
品質とは計画され、設計され、プロジェクトのマネジメントやプロジェクトの成果物に組み込まれるものであり、検査によって実現されるものではない。
トヨタ自動車は「品質は上流工程である設計で作り込む。検査では品質は向上しない」というコンセプトをもち、設計を品質管理の要とする。
そう考えれば、上がってきた成果品に対して、作業者であるアシスタントにガミガミ言ったとしても、品質はほとんど向上しないことがよく分かるだろう。
依頼における品質管理は、最初の段階で「どの程度のものがほしい」をきっちり明確に示すことが肝心なのだ。
適当に依頼しておいて、「こうじゃないんだよなぁ〜」とか言ってしまう管理職は、品質管理の初歩から、勉強し直したほうが良いだろう。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)
・編集部がつぶやくBooks&AppsTwitterアカウント
・最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ
・ブログが本になりました。