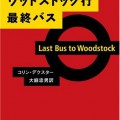推理小説は好きだろうか?小説のジャンルとしてはそれなりに昔から有るもので、1800年代前半にエドガー・アラン・ポーが最初に生み出したとされる。
推理小説は好きだろうか?小説のジャンルとしてはそれなりに昔から有るもので、1800年代前半にエドガー・アラン・ポーが最初に生み出したとされる。
個人的に、娯楽としては非常にコストパフォーマンスの高いとおもっており、数百円で長く楽しめるので、旅行の時に何も考えずのんびり読むには最高の娯楽だと思う。
さて、そんな推理小説だが、最近では色々なジャンルと融合されている。
読者に「謎」が提示され、「伏線」を散りばめ、後にそれらを回収しながら謎を解決する、という王道のストーリーを考えれば、例えば「ハリー・ポッター」なども一種の推理小説と言ってもよさそうである。
したがって、推理小説は相当の数に上っており、今から推理小説を読み始めようとする人には若干敷居が高い。そんな人は
海外モノではコナン・ドイル、アガサ・クリスティ、エラリイ・クイーン、など、国内では横溝正史、松本清張などの古典を読んでおけば間違いない。
ただ、ある程度有名どころを読んでしまって、「今更シャーロック・ホームズもな・・・」と思う方には上で紹介した「コリン・デクスター」がおすすめである。
最近の推理小説は「アガサ・クリスティが全てのトリックを使いきってしまった」と言われるように、事件のトリック自体はネタ切れを起こしている。そこで、トリックの面白さよりも主人公の性格の面白さなどで惹きつける作品も多いのだが、「純粋に謎解きをしたい」という読者にはちょっと物足りない。
ところが、「コリン・デクスター」は敢えてその課題に真っ向から取り組み、「純粋なパズル」としての推理小説を志向しているようにも見える。
「作者と知恵比べをしたい」とか、「パズルが好き」という方には超おすすめである。
なお、コリン・デクスターの処女作が上に紹介した作品「ウッドストック行き最終バス」なので、ご興味のある方はこの作品から読まれるといいだろう。
ただし、残念ながらKindleでは出ていない。早く出てくれるといいのだが。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。