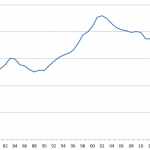みなさんは、カップラーメンを食べたことがあるだろうか。たぶん、98%くらいの人は「イエス」と答えると思う。
じゃあ、初めてカップラーメンを食べたのはいつか覚えているだろうか。これに関しては、多くの人は覚えていないだろう。
でもわたしは覚えている。
初めてカップラーメンを食べたのは、大学に入学したばかりの2010年4月のことだ。
カップラーメンの作り方は「常識」ですか?
大学に入学してバンドサークルに入ったわたしは、時間があればすぐに「コモン」と呼ばれるサークルのたまり場に行って、友だちづくりにいそしんでいた。
入学した数日後、新1年生のわたしは、先輩に連れられてコモンの奥にある「山小屋」に行った。
山小屋は数種類のメニューを扱っている小さな食堂で、ちょっとした食べ物や飲み物も売っている場所だ。
わたしはそこで、雑に並んでいる数種類のカップラーメンに目を奪われた。
実はそのときまで、カップラーメンを自分で作って食べるという経験をしたことがなかったのである。
サークルの友だちとたまり場でカップラーメンを食べる。
なんだかすごく大学生っぽい……!
というわけで、わたしは意気揚々と、とあるカップラーメンの醤油味を買った。
ええっと、カップラーメンっていうのは、たしかお湯を注ぐんだよな。
山小屋に置いてあるポットからお湯を注ごうと、ペリペリとカップラーメンのフタを剥がす。
そこで友だち数人が、目を見開いた。
「お前、なんでフタ剥がしちゃうの!?」
フタで密封されているものを食べるなら、当然フタを開けるのが当然だ。
なにが問題なのかわからず首をかしげると、「作り方知らねぇの!?」「お嬢様かよ!!」「見たらわかるだろ?」とみんなが笑い始める。
頭の上に「???」とクエスチョンマークが浮かんでいるわたしは、まじまじとカップラーメンを見てみた。
なるほど、たしかに「フタを半分だけはがしてお湯を注ぐこと」と書かれていた。
でもふつう、そんなの読むだろうか。フタがあったら、とりあえず開けるだろう。そんなにおかしいことをしたんだろうか。
「カップラーメンの作り方なんて、常識だろ?」
そう言われた。
ふつうに生きてきたわたしは、「常識知らず」らしい
わたしの母は、仕事しながらもしっかりと料理をしてくれる人だ。
朝起きると朝食が用意されていて、学校に行くときはお弁当を持たせてくれて、夜は一汁三菜が揃った食事が並ぶ。仕事でいないときは、お昼ごはんを作ってラップをかけて置いておいてくれる。わたしは、そんな家庭で生まれ育った。
高校に入ってからはコンビニでご飯を買うこともあったが、おにぎりや冷製うどんが多く、カップラーメンは食べたことがなかった(高校の食堂にポットがなかったのが理由だと思う)。
だからわたしは大学に入るまで、カップラーメンとはまったく縁のない生活を送っていたのだ。
そこで突然、「カップラーメンの作り方は常識」という言葉で、頬を思いっきり殴られた。
みんなはカップラーメンの作り方を知っているから、それを知らないわたしはふつうじゃないということらしい。
わたしからしたら、フタははがすのが「当然」だ。半分しか開けちゃいけない、なんてほうが非常識である。
わたしの知らない世界を引き合いに出して「常識知らず」と笑われたのは、すごく腹が立ったし、なによりも悔しかった。
大げさに言えば、わたしのいままでの人生やこれまでお母さんがした努力をまとめて侮辱されたように思えたのだ。
「常識」だと思っているのは自分だけかもしれない
だれでも一度は、「自分のなかの当たり前」と「ほかの人たちが共通してもっている認識」とのへだたりに戸惑ったことがあると思う。
金持ちの先輩は家事手伝いを雇っているからFAXの送り方を知らなかったし、地方出身の友だちが共通語だと思っていた言葉が方言だと知ってショックを受けていたこともあった。
わたしにとってFAXの送り方や標準語なんて「当然」だけど、知らない人は知らないのだ。それを知らなくたって、問題なく生きられる世界の住人だったのだから。
結局常識なんていうのは、その場においてのマジョリティでしかない。知っておくべき一般教養や社会通念はたしかに存在するが、だれにでも通用する「常識」なんてものは、意外に少ないのだ。
自分の価値観は絶対だけど、標準的とは限らない
「なんでそんなことも知らないの?」
「こんな常識も知らずによく生きてこれたな」
「そんなことを当然だと思っているのはお前だけだ」
こういった言葉で、気付かないうちに自分の世界を正当化して、他人の世界を否定してしまうことがある。
自分の世界の外にある「常識」を押し付けられたら、だれだってうれしくはない。それまでのことをすべて「非常識」だと言われているのと同じなのだから。
悪意がなくとも、自分の価値観が標準的であると思い込んでしまうのは、だれにでもあることだ。もちろん、わたしも含めて。
でもソレはあくまで自分にとっての「ふつう」であって、相手にとっては「ふつう」ではないかもしれない。
「常識」「当然」「ふつう」といった言葉は便利だし、使えば自分が正しいかのように思わせられるけど、時に人を傷つけたり怒らせたりすることもある。
もしなにかを「知らない」という人がいたら笑わずに教えてあげたいし、自分が知らないのであれば素直に教えてもらう姿勢でいたい。
カップラーメンの一件を思い出しながら、「自分のなかの常識を当たり前だと思わないように気をつけないとな」なんて改めて気を引き締めた。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【プロフィール】
名前:雨宮紫苑
91年生まれ、ドイツ在住のフリーライター。小説執筆&
ハロプロとアニメが好きだけど、
ブログ:『雨宮の迷走ニュース』
Twitter:amamiya9901
(Photo:emily mucha)