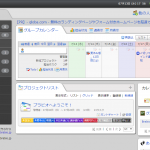先日、東洋経済さんでこんな記事を拝読しました。
文章を書くことは、観察し、驚きを見つけ、考えることです。これがステップ1からステップ3への手順に当てはまるのです。
(東洋経済オンライン)
正直なところ、この記事を書いた方は「作文が書けない子」のレベルをかなり高く見積もっているなあ、と感じました。
いや、文中のテクニック、文中の手法が悪い、というわけではないのです。ここに書かれていることは、それはそれで非常に有用、非常に有効なことだと思います。
「観察→深堀りと整理→考察」という思考法は、あらゆる表現、あらゆる論考で重要な手順です。
小さい頃からこの手順になじんでおくことはとても有益ですし、その際の教え方、かみ砕き方として、文中提示されているような言い方をするのも有効でしょう。そこについては何の文句もないんです。
ただ、ここでいう「作文が書けない子」には、かなり幅広いグラデーションがありまして、しかもそのグラデーションは一様とは言えません。
補習塾でしばらく教えていた頃の感覚値として言うならば、「作文が書けない子」の中には根本的なところで躓いてしまっている子がかなりの率含まれていて、そういう子たちには冒頭文章のような教え方は多分あまり有効ではないだろうな、と私は感じたのです。
ちょっと根本的な話をします。
「書く」という行為には、大きく「発想」と「表現」という二つのプロセスがあります。
つまり、
・何を書きたいのかを考える
・考えた内容を言葉に落とす
という段階を経なくてはいけない。これに例外はありません。どんな文章でも、必ず、例外なく、この二つのステップを踏んでいます。
で、冒頭引用文であげさせて頂いた文章は、基本的にこの二つのステップの内の第一のステップ、「発想」側に属する内容になっています。
つまり、「何を書くのか」「何を書きたいのか」ということを引き出す為のプロセスです。これはこれで大事です。
ところで、「表現」の方はどうでしょうか。我々は、「何を書きたいか」ということが決まった時、何の障害もなく、すらすらとそれを文章に書き出すことが出来るでしょうか?
勿論のこと、それがすらすらと出来る人、出来る子というのはいます。
考えることを、考える時間とそれ程変わらない速度で、がーーっと文章に出来る人もいます。お前ライターマシンかよってくらい手が速い人もいます。すごいですよね、ああいう人たち。
ただ、それは、「表現」という処理回路が、すでに頭の中に確立されているからこそ出来ることです。
考えたことを言葉に直す、適切な言葉と言葉の繋がりを想定してテキスト化する、そういう仕組みが既に脳内に出来ている。
その為には、ある程度の慣れと訓練が必要です。
そして、この「表現」という回路、それをきちんと訓練することこそが、本当に大事で、本当に必要で、なのに今現在全く不足していることなんじゃないかなあ、と、私はそんな風に思うのです。
*
あげつらう意図はないのですが、冒頭の文章から、もう一か所引用させてください。
「なんで動物園に行ったの?」「どうしてライオンを見たの?」。
そんな問いかけに「きのう、がっこうのえんそくでどうぶつえんに行きました。ぼくはえほんで見た白いライオンに会いたかったので、まっさきにライオンのところに行きました」などの答えを出してきます。
断言しますが、「どうしてライオンを見たの?」という問いかけに対して、ここまですらすらと、きちんと整理された答えを出せる子どもというのは、100人の中に10人いません。5人いるかどうかも怪しいところでしょう。
ここまでちゃんとした答えを出せる子は、恐らくその時点で既に「作文がきちんと書ける子」と言っていいのではないか、とすら思います。
では大体の子は何というかというと、自分の中に「なぜ」の答えがあるかどうかには関係なく、「なんとなく」とか「好きだから」といった数文字程度の答えを返してくるでしょう。
これは勿論、その子の思考力が劣っているとか、発想が貧困だということを意味しません。
単に、「発想した内容を言葉に落とす」という訓練と、「「なぜ?」という問いかけに対して理由や経緯を深堀りして答える」という経験が足りていないのです。それだけです。
「なぜ?」という思考は勿論重要なのですが、それに対して「何故ならこれこれこういう理由だから」という言葉を返す為には、その前段階の経験値が必要です。
そこをすっ飛ばして、ひたすら「なぜ?」という問いかけを繰り返しても、恐らく質問者と回答者の双方が疲弊するだけでしょう。
これ、もしかすると、ごく自然に文章が書ける、という人には想像しにくいことなのかも知れません。
実際、文章力を鍛えるとか、作文を書くとかのノウハウ本を見ても、「発想」に偏っていて「表現」の話はさらっとしか書いていない、もしくは全く触れられていないことが多いです。
なんなら学校教育でも、「表現」は出来ている前提で、「発想」の話をしていることが結構頻繁に観測出来ます。
*
これは、私個人の経験に基づく話です。
補習塾で教えていた頃、国語で「記述問題が全く答えられない」という子には山ほど接してきました。
自由記述の問題は勿論、なんなら「該当箇所を文中から抜き出せ」という程度の問題すらさっぱり、という子もたくさんいました。作文書くなんて夢のまた夢です。
その子たちに足りないのは何だったのかというと、根本的なところで「文章と文章の繋がり」「言葉と言葉の繋がり」のサンプルに触れる経験が致命的に足りていなかったのです。
考えを言葉に落とす為には、そもそも言葉を知らなくてはいけません。
文章にする為には、言葉と言葉の類例にたくさん触れなくてはいけませんし、その類例を学ばなくてはいけません。
小中学校には、その根本、「言葉の類例を学ぶ」時点で躓いている子が、実のところたくさんいるのです。
その子たちには、まず「発想」ではなく「表現」の訓練をしてあげなくてはいけません。
じゃあ具体的に私がどんなことをやっていたかというと、勿論色々試行錯誤したんですが、ある程度成功率が高かったのはこんなやり方でした。
・図書館に行って何冊か児童書なりラノベなりを借りてくる
・その中から、その子が少しでも興味を持てそうな本を選んでもらう
・適当なページをコピーして、そこに「どの言葉とどの言葉が繋がっているか」を赤線で全部書く
・そのつながりを説明した上で、ひたすらそのページの文章を模写してもらう
要は、「繋がりのサンプルを確認する」「それをそのまま出力する」という経験をひたすら反復してもらわないといけなかったんですね。
もとになる児童書は、ある程度言葉の繋がりの類例があれば何でもいいって感じです。怪傑ゾロリでもいいし、クレヨン王国でもいいし、ドリトル先生でもいい。
で、ひたすら書く。そのまんま書く。これによって、言葉の繋がりの類例を知るのと同時に、とにかく「言葉に落とす」「自分で書く」ということに慣れてもらう。
ある程度慣れたら、今度は簡単な記述問題に移って、自分で言葉の繋がりを探してもらう。
この繰り返しで、そこそこの率、出来ない子のサルベージをすることが出来ました。
「二行以上の文章が書けない」というところから、「400字詰め原稿用紙で一応一通り作文が書ける」というところまでもってこれた子も何人かはいました。
勿論、それでも出来ない子、ないし成果が出る前にやめちゃった子もいたんですけどね。
これ、基礎の基礎訓練みたいなもんなんで、成果が出始めるまでにはそこそこ時間がかかるんです。その間に、その子か親御さんが焦れちゃう。補習塾の辛いところです。
ただ、基本的には、「表現」を鍛える為には地道な反復練習しかない。色んな言葉と、言葉同士の繋がりに触れて、それを文字や文章に落とし込む経験をたくさん積むしかない。そうしないと「表現」の筋力ってつかないんです。
要は、「文章を書く為にも必要な筋肉は複数あるよ」「足りない筋肉を見極めて適切なトレーニングをしないと書けるようにはならないかもよ」という、それだけの話なんです。
*
最後に私が言いたいことをまとめておきます。
・文章を書く際、「発想」と「表現」の二つのプロセスがある
・「作文を書けない子」の中には、「表現」の訓練が致命的に足りていない子が結構いる
・「表現」を放っておいて「発想」の訓練だけをしても多分あまり意味がない
・なのに、「発想」だけを気にしている人が結構いるような気がする
・「表現」を鍛える為には、基本的には地道な反復訓練しかない
こんな感じです。よろしくお願いします。
一人でも多くの子どもたちが、「考えて、書く」ということの楽しさに目覚めてくれることを願ってやみません。
今日書きたいことはそれくらいです。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【プロフィール】
著者名:しんざき
SE、ケーナ奏者、キャベツ太郎ソムリエ。三児の父。
レトロゲームブログ「不倒城」を2004年に開設。以下、レトロゲーム、漫画、駄菓子、育児、ダライアス外伝などについて書き綴る日々を送る。好きな敵ボスはシャコ。
ブログ:不倒城
(Photo:angus mcdiarmid)