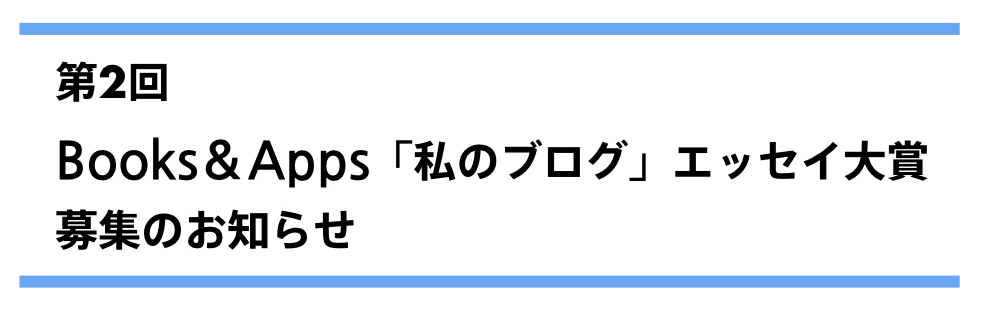「分からない」に接する、分かる側の人たちの為のお話です。
ちょくちょく書いてるんですが、しんざきは昔、小さな補習塾で塾講師のアルバイトをしていました。
補習塾っていうのは、進学塾の対義語みたいなもんでして、学校の授業についていけない子を救い上げることを主な目的とする塾です。
補習塾ですので、担当する生徒は「学校の勉強についていけなくて落ちこぼれてしまった子」が主ですし、散々叱られて勉強に対する自信は皆無、自己評価メタメタっていう子が殆どだったんですが、もう一つ印象に残っていることとして、「親子関係のギスギス問題」というものを観てとれることがしばしばありました。
教育に興味を持っていない家庭、教育についての意識がない親御さんは、そもそも「落ちこぼれてしまった我が子を補習塾に通わせてあげよう」という考えに至りません。
勉強が苦手な子は世の中に幾らでもいますが、補習塾に来るという時点で、既にある程度教育に対する意識が高いご家庭の子である可能性が高いんですよ。
で、どこの塾でもやっていることだと思いますが、その塾でも生徒のご両親と面談をして家庭の状況をお聞きする機会がしばしばありました。
私自身バイトの分際で何度も親御さんとお話したことがあるんですが、大体の親御さんに共通して感じたことが、「子どもが何故、こんなところでつまづいているのか分からない」という困惑、疑問、焦りだったんです。
例えば、私が実際に受け持った生徒の一人で、「割り算の筆算が全然わからない」という子がいました。
算数ってのは積み重ねですので、勿論実際には割り算よりももっと前に躓きポイントがありまして、その子の場合は桁数の概念と桁跨りの除算がそもそも曖昧だったことに根本原因があったんですが、けどまあ塾に来た直接的な要因はとにかく割り算の筆算です。
で、今でも覚えてるんですが、その子の親御さんとお話した時、こうおっしゃったんですよ。
「私も何度も教えてるんですが、こんな簡単なことがなんで出来るようにならないのかもうさっぱりで…」
って。
「こんな簡単なこと」。
そうなんですよね。大人にしてみれば、どう考えても「こんな簡単なこと」なんですよ。マインドセットが出来た後の大人なら、小学校の算数なんてまあ大体「簡単なこと」じゃないですか?
受験算数ならちょっと話は別ですが、まあ大抵の大人は、二桁÷一桁の割り算やら、三角形の面積の計算で悩んだりしません。筆算だろうが分数だろうが、大体は「もうわかっちゃってる」わけなんです。
自分が分かっていることについて、「分からなかった頃」を思い出すのは、どんな人にとっても困難です。
これは別に学校の勉強に限りません。仕事でも、研究でも、趣味でも同じです。
上で書いた通り、どこのご家庭も教育に関する意識をちゃんとお持ちで、なんならご自身も高学歴の親御さんが多かったので、皆さん一様に「小学校レベルの勉強で何故つまづくのか」っていう疑問を、なんだかんだでお持ちになるんですね。
要は、子どもの「分からない」にさっぱり共感出来ない。
「分からない」ことが分からない。
まずいことに、子どもって「自分に対する視線」に極めて敏感なので、「なんでこんなことが分からないんだ」っていう親の疑問は、殆どダイレクトに子どもに届いちゃうんですよ。
「あ、今、イライラされてる」って。速攻伝わります、ああいうの。
で、その「なんでこんなことが分からないんだ?」っていう意識のままで子どもに勉強を教えようとするんで、雰囲気もギスギスしちゃいますし、子どもの方でも委縮してしまって、ますます頭に入らなくなっていく。
ついでに言うと、「分からない」根本原因は大体の場合その「分からない」箇所のずっと前に潜んでいるので、いくら教えても根本的には解決出来ない。
「分からない」に共感してもらえないことはもう分かってしまっているから、どこが躓いたかを根本的に紐解こうというスタンスにはならず、なんとか表面的に、例えば丸暗記でその場を乗り切ろうとする。
結果、ますます「分からない」の質量が積み重なっていく。
救済を求めても無駄であることが分かるから、「分からない」こと自体を言い出せなくなる。悪循環ですよね。
で、そういう時、親御さんにしていたお話がありまして、まあ元はそこの塾長の受け売りなんですが。
今、お仕事で、何か新しいこと勉強されてますか、と。何か学習されてますか、と。
多分、「新しいことを身に着ける」って結構大変だと思うんですが、小学校って「ほぼ毎日」何かしら新しいことを教えられる場所なんですよ、と。
新しいことを毎日のように覚え続けるって、すっごく大変なことなんですよ。子どもだけじゃなくって、大人だって「職場が変わって何もかもイチから覚えないといけない」なんてことが起きたら、ものすごーーく大変じゃないですか。
しかも、学校の勉強って積み重ねですから、どれか一つでも取りこぼしたら、そこから延々と「なんとなくわからない」が降り積もったりするんです。
だから、お子さんがちょっとくらいまごついて、一見簡単なところで「分からない」になってしまうのも、むしろ当然だと思ってあげてください。
それを解決するのはこちらで頑張りますので、むしろ家では「ちょっとくらい出来なくたっていいよいいよ」くらいのスタンスで構えてあげてください。
そんなことを、毎度毎度お話していました。
元々、子どもの成長って非線形っていうか、行っては戻って行っては戻っての繰り返しみたいなところがありますから、親にとっては「ついこの間まで出来てたのに何で今出来ないの」みたいなこと、山のように起きるんですよね。
それは全然珍しいことではないし、深刻に悩むようなことでもない。
勿論、必要に応じて補習塾のような解決法を求めることもあるかも知れませんが、少なくとも「何かおかしいんじゃないか」と考えないといけないようなことは稀なんですよね。これは別に勉強に限らないと思います。
子どもって、案外しんどい。次から次と環境は変わるし、目にするもの全てが新しいし。
冷静に考えれば、小学校なんて「一年ごとにほぼ間違いなく周囲の環境(教室)ががらっと変わる」「大体の場合1,2年で周囲の人間関係までがらっと変わる(クラス替え)」わけでして。
大人に当てはめれば毎年転勤・転職してるようなもんです。
そりゃちょっとくらいはまごつきますし、軽くパニックになっちゃっても不思議じゃないですよ。
だから、たとえ「分からない」ことそれ自体については共感出来なかったとしても、子どもにかかる負荷については承知して頂いて、長い目でみてあげてくださいと。
そんな風にお話していたんです。
*
あれから時間が経ちました。20年近く経って、今では私自身が三児の父になりましたし、様々な場面で新入社員や後輩の面倒をみる立場にもなりました。
で、あの頃のことを、最近よく思い出しています。というか、自分の言葉が自分に刺さっています。
学生の頃と違って、やはり最近、「次から次へと新しいことを勉強し続ける」という機会は流石に少なくなってしまいました。
「分からない」を感じる機会が減ってくると、「分からない」頃を思い出しにくくなる。これは多分、私自身にとっても他人事ではないのでしょう。
ただ、たとえ「分からなかった」頃に戻れなかったとしても、「分からない」に寄り添うことは出来る。
学び続けることの大変さを思い出すことは出来る。
だから私は、子どもや部下や後輩の「分からない」には、極めて寛容に構えることにしています。
同じ質問に何度でも答えますし、「何か質問ある?」ではなく、「最初は何が分かんないか自体が分かんないと思うから、とにかく触ってみて、どこが分からないのかをちょっとずつ明確にしていこう」というようにしています。
「分かる」側と「分からない」側のディスコミュニケーションが、少しでも低減するといいなあ、と。
そんな風に考えるわけなんです。
今日書きたいことはそれくらいです。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【プロフィール】
著者名:しんざき
SE、ケーナ奏者、キャベツ太郎ソムリエ。三児の父。
レトロゲームブログ「不倒城」を2004年に開設。以下、レトロゲーム、漫画、駄菓子、育児、ダライアス外伝などについて書き綴る日々を送る。好きな敵ボスはシャコ。
ブログ:不倒城
(Photo:M Reza Faisal)