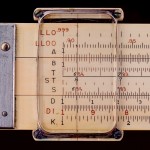今年の3月ごろ、そろそろコロナウイルス感染拡大が問題視されるようになってきて、「接触を避けよう!」というようなことがさかんにいわれるようになった。
わたくしなどは、「あの超満員の通勤電車を抛っておいて、そんなことをいっても全然意味がないだろう!」と思っていた。
ところが3月の末ごろだったか、政府が時差出勤とか在宅勤務の推奨を言い出した。
そして驚いたことに、わたくしが産業医を務める会社では、「4月から原則、全員、在宅勤務!」を宣言した。
本当に、4月になるとオフィスはガラガラになり、わたくしが利用している通勤電車も混雑が大幅に緩和し、ある時など、新宿駅で座れるという前代未聞のことまでがおきた(荻窪からお茶の水まで中央線で通勤しているが、そんなこと、中学生のときに信濃町までの電車通学を開始して以来、一度も経験したことがなかった。
今の若い方はご存知ないだろうが、昭和30年から40年ごろの高度成長期には通勤地獄という言葉があって、その混雑は現在の比ではなく、なにしろ、降車する駅の二駅前くらいから準備しておかないと、目的地で降りることができなかった。
ところで、わたくしが在宅勤務というものに偏見をもっていたのは、それが主として産休や育休をとった女性のためにある、フルタイムで出社できるまでのつなぎの勤務形態と思っていたということが大きい。
育児しながら家庭で仕事ということになれば、on off の切れ目が明確化することは考えられないし、子供をあやしながら仕事をするというon & off ということだって十分にありうる。
だからフルタイムで出社している(主として男性)社員たちは、在宅で仕事をしている(主として女性)社員を「本当にあいつ仕事をしているのか?」などと揶揄するようなことを言っていた。
後から考えてみると、フルタイムで出社していた社員も土日休日に、家まで仕事を持って帰っていたひとは多かったわけで、その意味で、すでに在宅勤務という形は一般化しようとしていたのかもしれない。
傍から見ていると、在宅勤務普及の一つの律速段階となるのはセキュリティPCが確保できるかということのようで、いくら従来、多くのひとが土日も在宅で仕事をしたとしても、全社員がそうしていたわけではないので、各部署でセキュリティPCの奪い合いが起きた。
そしてマネージャークラスの方のなかには、オフィスで直接部下の顔をみないとどうも安心できないという方もいて
「俺のところは後でいいから、ほかにセキュリティPCはまわして!」
ということをいい、また可愛い部下には先にPCをまわし、面白くなく思っている部下にはなかなかわたさず、往復4時間の長距離通勤を続けさせるという、ほとんどハラスメントの手段としてこれを利用しているのではないかというようなケースさえないわけではなかった。
聞くところでは、オフィス勤務から在宅勤務への移行が比較的スムーズにいったのは、東京オリンピックの功績が非常に大きいのだそうである。
オリンピックの期間には交通機関の大混雑が予想されたので、政府は大きな企業にはその間、極力社員を出社させず在宅で仕事させることを要請していたのだそうである。
そのため大企業においては在宅での勤務が可能になるように着々と準備が進んでいたらしい。
その水面下の準備なしには、とてもこうはスムーズな移行はありえなかっただろうという話であった。
*
さて、どこの会社においても直面しているのが
1)在宅勤務というような形態が、今回の新型コロナウイルス感染対策のため仕方なくとっている形態であり、今回の感染が終息すれば、またオフィスでの仕事という形態が主になっていくのか?
それとも
2)今回のコロナ騒動で予想外に早く対応をせまられることになったが、リモート・ワークという形態は長期的にはもとから目指すべきと思っていた方向であり、今回の騒動でたまたま早期の対応を迫られたということであるが、コロナ感染の問題が終息をしたとしても、後戻りすることなく今後も推進していく方向なのか
という、路線選択の問題なのではないかと思う。
わたくしのように産業医という立場から薄く会社組織とかかわっているだけの人間に、それはとても判断できることではないが、逆に産業医という立場であるので、コロナ騒ぎの前からの話題である「働き方改革」といったことと今回の在宅勤務推進の方向がどうかかわっていくのかということには関心がある。
たとえば、在宅勤務の推進はさらなる女性登用に道を拓くだろうか?
「働き方改革」での話題の一つである「メンバーシップ型」と「ジョブ型」の問題で、在宅勤務という形態は「ジョブ型」に親和性があるのだろか?
そして、もうすでに忘れられてしまった話題である「成果主義」といったこととも在宅勤務の問題はどこかでかかわりを持つのだろうか?
さらに、はるか昔、山本七平さんの本で読んだ「日本では会社という機能集団は、ある程度大きくなると共同体に転化しないと絶対に機能しなくなる」という論と、今回の在宅勤務の推進とがどこかでかかわるのだろうか、というような問題意識である。
もちろん、そのような大問題にわたくしなどが、明確な解答を提示できるはずもなく、できるのは、その問題の周囲をいくつか遠まわりに考えてみることだけである。
ある男性社員の話。
「ぼくは自分の辞令を会社の中できいたことは一度もありません。ある時、仕事をしていると上長がそばにきて、「お前、今晩、暇か?」ときく。
「はい」とこたえると、
「じゃあ、仕事おわったら、ちょっと一杯!」といわれる。
それでついていくと、何ということのない世間話の後、「ところで」といわれる。
「きみ、再来月から〇〇にいってもらうから」と実にさらっといわれる。
「いつもそうです。会社の中で発令をきいたことなどありません。」
ある女性社員の話。
「仕事が終わって、「お疲れ様!」と別れる。
男性陣は「ぼくたち、これから、ちょっと一杯、やっていくから」という。
それで翌朝、仕事にでてくると、前日、退社時には何もきまっていなかった今後の仕事の段取りがすでにあらかた決まってしまっている。
飲み会の場で話がついてしまったらしい。
「わたしなんか、いつも蚊帳の外です。」とその女性がいう。
もしも、在宅勤務が主となり、縄のれんでの愚痴のやりとりも、もう少し公式なアフター・ファイブの飲み会もみんななくなったら、はたしてそれでも会社組織はまわっていくのだろうか?
ひとから聞いた話で真偽のほどは不明であるが、アメリカのオフィスというのは個人の席の独立性が高く、日本人の感覚では各人に個室が与えられえているような感じなのだという。
コロナ騒動以降、日本のオフィスでも各人のスペースの間を透明なアクリル板で仕切っているところが多いが、かりにコロナ騒ぎが収束しても、このような今よりは各人の独立性を保ったオフィス環境は続くのだろうか?(コロナ以前から、「今の若い奴はとなりの席のものともメールで情報のやり取りをしていて、直接に話をしない」と年長の方は嘆いていたが。)
最近、サテライト・オフィスというのが一種の流行のようであったが、在宅勤務ならサテライト・オフィスなど不要になるのだろうか?
ある会社はオフィス移転にあたって相当な投資をして、座席のフリーアドレス化に踏み切ったが、担当の方は、「何か、中途半端なことをしちゃったかなあ?」と困惑していた。
フリーアドレス化のメリットは社員全員分の席を用意する必要がなく、オフィスの面積を縮減して賃貸料を減らせるということだそうだが、在宅勤務が常態となれば、オフィスに必要なスペースはもっと大幅に減らせる。
要するに、一部の会社において長期的な方向として目指そうとしていたことが、コロナ騒動によって否応なく促進されてきているという面があるのではないかということである。
その目指そうとしていたことというのが、会社をもっと純粋な仕事の場としていくという方向である。
そんなこと当たり前ではないかということになるが、それでは学校は単なる学びの場だろうか?
最近のニュースをみていて異様に感じるのは、たとえば、学校の給食で感染防止のために座席の間を仕切って、子供たちがただ黙々と何の会話もなしに食事している光景である。
これでは給食は単なる栄養摂取の時間である。
「人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学ぶ」のかどうかは知らないが、少なくとも幼稚園での学びが教室の中だけに限定されるということはないはずである。
そして特に日本においては、会社に「一人の人間がjobを通して人間として成長していく場」であることが期待される側面が(かつては?)とても強かった。
というのは日本の男にとっては職場以外の共同体というのがほとんど存在しないからである。
逆にいえば、日本の会社社会で女性がガラスどころか鉄製の天井につねに頭をぶつけてきたのは、女性が会社以外の場所にも共同体を持っていると思われてきたからではないだろうか?
複数の共同体を持つ人間には、「会社にすべてを捧げてもらう」といったことは期待しづらい。
会社人間とか社畜というような言葉はほとんど男性社員に対して投げつけられてきた言葉であっただろうと思う。
しかし、会社も段々と重くなってきたのだと思う。
単にjobの仕方を教えるだけはなくて、「子供をいっぱしの大人に成長させる」ことまで期待されたのでは叶わない。
そもそもグローバル化の時代に、他の国の会社においては期待されていないことを我が国の会社組織にだけ期待されるのは困る。
そんなハンディキャップを負っていたのでは国際競争には勝てない。
だから経団連なども「四月新卒一括採用などというのはもはや維持できない」と言い出す。(そもそも新卒一括採用というのは明確に法律違反なのだそうで、にもかかわらず、厚生労働省が新卒に限って法律の適応外としているので許容されているということだけなのだそうである。また、四月新卒一括採用とワンセットである定年制もアメリカ・イギリスなど多くの国ではすでに違法なのだそうである。)
新卒一括採用というのは、まさに、メンバーシップへの加入を意味するのであって、いわばやくざ組織に草鞋を脱ぐのと大差ないような気もする。
日本で体育会系の学生が採用で異様に厚遇されるのは、学生時代にすでに身をもって理不尽を体験しているということが大きいといわれている。
「星の数よりメンコの数」で、上級生絶対などという論理以前を当たり前と思える人間は使いやすいらしい。
それと対極に位置するのが派遣社員、非正規社員で、きちっとした契約とジョブ規定があって、それを遂行することだけが期待される。
正規雇用者と非正規雇用者が同一の労働をしていても賃金が異なるのはおかしい、ということが常に指摘されるが、雇う側からみれば、非正規雇用の人間にはジョブ・スクリプティングに書かれたことだけを遂行すること期待しているのであるが、正社員にはそれ+αをつねに言外に期待しているであるから、給与に差があるのは当然なのである。
*
かつて「成果主義」が「年功序列」にとってかわるこれからの日本の生きる道ともてはやされていた時、それに反対して高橋伸夫氏は「日本型の人事システムの本質は、給料で報いるシステムではなく、次の仕事の内容で報いるシステムだ」という主張をしていた。(「虚妄の成果主義」2004年 日経BB社 文庫増補版 2010年 ちくま文庫)
日本の賃金カーブは「生活費を保障する視点から設計されてきた」のだという。
この論にしたがえば、賃金とはその人がある時期にどういう成果をあげたかではなく、今そのひとはどのくらいの生活費がかかっているかによって決まるというのであるから、およそ「ジョブ型」という観点にはなじまない。
そしてもしそのひとが成果をあげたと思えば、次にもっと裁量範囲のひろい、もっと多くの部下を管轄する職責に引き上げることで報いるのだというのであれば、長期雇用を前提にしなければ日本の人事システムは機能しないことになる。
なんで高橋氏の「虚妄の成果主義」などという本を読んだのかというと、わたくしが50歳から65歳まで、ある小規模病院の責任者をしていたからで、しかも困ったことに、その病院は一部上場企業に付属する企業立病院であったため、本社から「人事考課の参考」などという分厚い本が送られてきて、事細かく考課の要点が述べられ、それによれば部下を確かAからEまでの5段階評価をせねばならず、しかもおおよそAが5% Bが25% Cが40% Dが25%、5%になることが望ましいなどとあって(正確な数字は失念)、しかも半期に一度(一年に一度だったかもしれないが、これも忘れた)その期の計画書をださせ、それについて各人と面談し、期の終わりにはその達成の度合いについてまた面談することになっていた。
しかしわたくしには考課する対象の人間は事務部長、看護科長、薬局長、放射線科科長の4わずか4名しかおらず、どうやってそれをそのパーセンテージに割り振るのだということもあったし、何よりも対象者の内の誰が優秀であるかなどということは、わざわざ面談などしなくてもおのずから明らかであって、この成果主義というのは何だか変だなあという思いがあって、それで高橋氏の本を読むことになったと記憶している。
おそらく成果主義というのは年功序列の制度の中で何となくある役職まで上がってしまったが、どうにも能力不足であることが露呈してしまったひとをなんとか降格させるための手段として以外にはほとんど役にたたなかったのではないかと思う。
そして、ある人を降格させるというのは、その上長にとっては夜道をあるきたくないような何ともいやな気分になることらしく、なるべくなら抜きたくない刀であるらしい。
結局、「日本では会社という機能集団は、ある程度大きくなると共同体に転化しないと機能しなくなる」ということが、グローバル化の進行のなかでも、これからも日本では相変わらず続いていくのかといくことに帰着するのではないかと思う。
小室直樹氏の「痛快! 憲法学」(集英社インターナショナル 2001年)に、日本人にはいかに契約の概念が欠如しているかの例として、「俺の目を見ろ、何にも言うな。黙って俺について来い。悪いようにはしない。」という言葉が挙げられている。
この言葉は対面の人間関係においてはじめて有効性を発揮する言葉であろう。
遠隔勤務のモニター越しには決して発せられることはないものであろう。
そもそもアフター・ファイブの飲み会で物事が決まる世界では、直の人間同士の接触が必須である。
オンライン飲み会ではその代用は決してできないはずである。
そして、わたくしがなぜ以上のようなことを考えるようになったかというと、わたくしが35歳で医師という資格によって組織に加わった人間であるからではないかと思う。
わたくしが見るところ、弁護士さんとか保健師さんとか、新卒すぐにではなく、ある年齢になって、何等かの資格を持って会社組織に加わった人間は、日本の組織ではまだ例外的であるジョブ型での採用の人間であって、完全には組織のメンバーであるという自覚を持てないし、まわりからも準メンバー的な扱いをされるということが大きいのではないかと思う。
昔風にいえば「渡り職人」であって、丁稚(小僧)、手代、番頭と進んで、やがては暖簾分けへと進むコースの明らかに外にいる人間なのである。
*
話がどんどん脇道にそれていくので、東京オリンピックがなければわたくしは医者にはならなかったという「東京オリムピック噺」に話を戻す。
東京オリンピックといっても1964年に実際にあった方で、その時わたくしは高校3年生。
もちろん、オリンピック開催の何年も前から日本はその準備で沸いていたわけで、その気分はわたくしから見ると何とも野蛮な「根性!」なのであった。
日紡貝塚とかいう女子バレーチームがもてはやされ、ニュースをみているとなぜか様々な会社が新入社員を自衛隊に体験入隊をさせ、寒中、川に入らせて禊?をさせたりしていた。
これをみて絶対にサラリーマンにだけはなるまいと思った。
たまたま父が医者であったので、この仕事なら自分にもできそうと思ったという以外には医者になった動機はない。
在宅勤務といった形態が定着するかどうかは、日本の会社が半世紀以上も前にくらべて根本的な変化を遂げたのかどうかということにかかっているのではないかと思う。
一見、羊の皮を被ってきてはいるが、本質は狼のままであるとすると、いずれまた元の方向に戻っていくことも十分にありうるのではないかと思う。
《日本の場合は、ボスというのは大山巌将軍でなければならないわけです。ぼんやりと君臨して、みんなを気持ちよくまとめていく。……「研究の方向はこちらである。この枠組みで、みんなでものを考えろ。君の分担は、これだ」ということはできない》
(丸谷才一・山崎正和「日本史を読む」1998年 中央公論社 での山崎氏の発言。)
「俺の目を見ろ!」というのも大山巌型の一変奏である。在宅勤務というのは、「仕事の方向はこちらである。この枠組みで、みんなでものを考えろ。君の分担は、これだ」というやりかたが通用しないところではなかなか機能しないのではないだろうか。
日本の会議というのは何かを決めるためのものではなく、「俺は聞いていない!」と後から文句をいってくるひとを出さないための儀式なのだそうである。
前日、退社時には何もきまっていなかった仕事の段取りが翌日すでにあらかた決まってしまっていることに驚く女性は、まだ会社の本当のメンバーとはみなされていないのであろう。
最近、話題のハンコの問題というのも、その一番、根っこにあるのは日本のお役所や会社の大きな特徴とされる稟議制にあるでないかと思う。
これまた「俺は聞いていない!」といわせないための制度であると同時に、ハンコをついた人間は、自分もメンバーの一員であるという安心感をもてるようになっているわけである。
はるか昔に読んだ山口瞳氏のエッセイで(「週刊新潮」に連載していた「男性自身」だったと思う)、会社で偉くなると(ヒラから課長に?)椅子に肘掛がつき、女の子がもってくるお茶に茶托がつくようになる。
これがどれほど嬉しいことかわからない人間にはサラリーマンの気持ちは永遠にわからないというようなことが書いてあった。
「お茶くみ」というのがまだ女性の立派な仕事?として存在していた時代、寿退社という言葉が厳然と存在していた時代の話である。
サラリーマン(これも最早死語か?)の悲哀を書くエッセイのタイトルが「男性自身」である。
この時代には、女性はまだ会社の正式な構成員とは認められていなかったのかもしれない。
そして、ハンコの問題のもう一つの極にあるのが、もはや日本だけしかない制度となってしまったらしい戸籍制度にあるのではないかと思う。
どうしても日本人は「家」という制度から自由になれないらしい。
印鑑には姓のみが刻まれている。
ハンコがなくなればサインになるのかしれないが、その場合はおそらくフルネームが記されるのではないかと思う。
フルネームが書かれれば、そこには個人があらわれる。
しかし姓のみの印鑑にはそれを押した個人だけでなく、そのひとが生活を支えている家庭の奥さんや子供の姿もぼんやりとではあれ立ち現れてくるのではないかと思う。
何しろ、高橋伸夫氏によれば、《賃金とはその人がある時期にどういう成果をあげたかではなく、今そのひとはどのくらいの生活費がかかるかによって決まる》というのであるから。
医者の世界でも、女性を登用しないと世界水準から遅れるという問題意識はあって、たとえば学会の座長をなるべく女性にもわりふるといったことに腐心はしているが、その女性が座長を担当するのはまずその人の専門分野にかんするものではなく、「これからの日本で女性医師がさらに活躍していくためには何が必要か?」というようなセクションなのである。
その会場には女性医師も多く顔を出しているが、しかし、その問題を女性同士で議論していても展望が拓けるとは思えない。
男性を巻き込むことが必須なはずである。
昔昔読んだ中村光夫氏の「『わが性の白書』」という小説に、ある男性が銭湯に入っている場面があった。
何でここにいるとこんなに気が晴れるのだろうとその男は考えて、「たぶん女が絶対に這入ってこないせいだろう」と思うのだった。
遠藤周作氏は夫婦喧嘩をすると、「弱い者いじめをするな!」奥さんにむかって(ついでに隣近所にも聞こえるように大声で)呼ぶことを常としていたのだそうである。
日本はジェンダー・ギャップ指数が世界でも下から数えて何番目というくらいの強固な男社会であるにもかかわらず、男は勝手に自分は弱いと思い込んでいて、ここに女性が入ってきたらひとたまりもないと考えて、イギリスのパブでさえ女人禁制ではなくなっているという時代に、頑なに男というメンバーシップを守ろうとしているのではないかと思う。
日本の会社が抱える様々な問題の根っこには、存外このことが潜んでいるのではないだろうか?
男は男同士で団結して女性を排除していかないと、一度そこに女性が入り込んできたら、あっという間に女性に駆逐されてしまう、そう勝手に思い込んでいるのではないだろうか?
「俺の目をみろ。何にもいうな。黙って俺について来い! 悪いようにはしない。」というのは絶対に男から男へしか発せられることのない言葉である。
男性上司が女性の部下に言ったら、完全にアウトである。
女性上司が男性の部下にいったら(適宜「俺」を「私」に読み替えてください)、これまたやばい。
女性上司が女性の部下に言ったら? うーん、怖い。
わたくしはリモート・ワークが普及するかといった問題にも、日本の社会の根底にある男社会の構造と「個」の未確立の問題が非常に大きくかかわっているのではないかと思っている。
(こういうことを書くとおこられることは重々承知しているが、ようやく日本でも「個」の問題は避けられない問題となってきていると思うが、それはまだ「男」の間での話題であって、女性においては「個」ではなく「女」が相変わらず議論されている段階なのではないかと思う。)
もしも男社会が次第に崩れていくとすれば、会社の形態もおのずから変わっていくであろう。
しかし、それが簡単には壊れないとすれば、また段々と、昼はオフィスに集い、夜はまたみんなで飲みに繰り出すという、会社共同体にどっぷりとつかった形態へと戻っていく可能性も、また少なからずあるのではないかと思う。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
著者:jmiyaza
人生最大の体験が学園紛争に遭遇したことという団塊の世代の一員。
2001年刊の野口悠紀雄氏の「ホームページにオフィスを作る」にそそのかされてブログのようなものを始め、以後、細々と続いて今日にいたる。内容はその時々に自分が何を考えていたかの備忘が中心。
Photo by Jason Strull on Unsplash