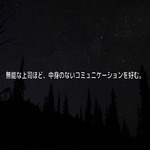最も重要なビジネススキルはなんですか?
と問われたら、なんと答えるだろう。
人によりけりだと思うが、私がコンサルティング会社で経験した限りでは、「結論から話す」がその候補の一つだと感じる。
これは誇張でもなんでもなく、「コンサル一年目が学ぶこと」の著者が、この本の最初の項目として設定していることにも現れているように、
あるいは、スキル系のビジネス書には大抵それに類似したことが書いているように、今では「結論から話せ」は、、もはやビジネス上の慣例といっても良いくらいだ。
私の場合は、入社するとまず直属の上司に「結論から」を求められた。
例えば、こんな具合だ。
私「すいません、相談があるのですが……」
上司「何?」
私「お客さんのところで、規定の説明をしていたのですが、第二条のところでお客さんから質問が出てしまったんですよ。「目的と目標はどうちがうんですか」と聞かれたので、こう答えたんです……」
上司「安達さん、結論から。」
私「あ、すいません! えー……、ちょっとお待ち下さい…………「目的と目標の違いは、定性的か定量的か」であっているでしょうか。」
上司「Noだ。その説明は間違っている。お客さんにそう説明したの?」
私「え?定性と定量の違いかと思ってました……でも「目標」を用語集で調べると……」
上司「安達さん、結論は。」
私「も、申し訳ないです。そう説明しました。」
上司「で、どうするの?」
私「やっぱり訂正が必要でしょうか。目的と目標のちがいを改めて説明するのにどういった場が必要か……」
上司「結論から。」
私「は、はい!………えー……お客さんに訂正の報告をします。切り出し方が難しいので、アドバイス頂きたく。」
上司「了解。」
こんな感じで、時には、一回の会話の中で何度も「結論は?」と言われたこともあった。
上司は淡々と「結論は?」というのみで、別に怒るわけでもないのだが、
時間を割いてもらってるな、迷惑かけてるなと思ったこともある。
そういう意味では、気長に訓練に付き合ってくれた上司には感謝である。
「なんの訓練もなしに結論から言える人」は十人に一人もいない
しかし、その後管理職になり、上司はいちいち怒ってられなかったのではないか、とも思うようになった。
「結論から言える人」があまりにも少ないからだ。
感覚的には、なんの訓練もなしに、的確に結論から言える人は、十人に一人もおらず、おそらく「結論から言う」のは、人間の生来の思考パターンとは異なる。
本来は、たぶん「出来事の順番通りに話す」だろう。
だから、例えるならば「水泳」のように、最初から出来なくても、仕方がないのだ。
そんな人に、「何でお前は泳げないんだ!」と怒っても、泳げるようにはならない。
気長に、泳げるようになるまで、アドバイスし反復訓練をするしかない。
結論から話す、がなかなかできない人へどうしたか
だから、当然のことながら、「泳ぎが苦手な人がいる」のと同様に、「いつまで経っても、結論から言えない人」も数多くいる。
例えばある新人コンサルタントは、人当たりのいい好青年であったが、なかなか「結論から言う」が出来なかった。
何回指摘をしても、結論ではなく「出来事」から言うくせが抜けない。
そこで、彼はなぜ結論から言えないのかを、経験を踏まえて少し観察した。
1.言い訳したい時には結論から言えない
まず第一に発見したのは、「言い訳」したい時には結論から言えない、という事実だった。
例えば冒頭の会話だ。
私はお客さんに間違った説明をしてしまったときに上司から「お客さんにそう説明したの?」と聞かれ、「説明しました」と結論から言えなかった。
言い訳から言ってしまったのだ。
もちろんこれは最低の選択で、言い訳をするほうが、むしろ状況を悪くする可能性が高い。
しかし、目先の嫌な出来事を回避するために、言い訳が口をついて出てしまうケースは少なくない。
したがって、「言う側」は率直に言うように心がけ、「受ける側」は「怒ったり怒鳴ったりしない」という状況を作り出せねばならない。
したがってこれは、双方の努力でいわゆる、「心理的安全性」がどこまで作れるかという話と、ほぼ同じである。
そこで、マネジャーの立場で報告を受けるときは、とにかく「相手を怖がらせない」ことに、全力を注いだ。
2.急かすと結論から言えない
第二に、回答を急かすと、結論から言えないことが多い。
例えば、「何がわからないのかわからないけど、とにかく上司に相談する」
というムーブが身についている人は、上司に「何が問題なの?」と聞かれても、即答できない。
だから、今の状況だけでも説明して、何とか上司にわかってもらおうとする。
しかしそれはたいてい、支離滅裂なので、それが上司にとっては、「結論から言ってない」ように見える。
ただしここで、上司は絶対に「早く言ってよ」と急かしてはいけない。
元々、まとめる能力が低いから、上司のところへ来ているのだ。急かせば、さらに相談に来にくくなる悪循環を生む。
では、どうするか。
これは、私の上司がやっていたことが参考になるだろう。
上司は「結論は?」と聞いて、部下がなかなか相談内容を言えない場合、おもむろに、デスクの中から紙と鉛筆を取り出して、私の話をまとめだした。(ホワイトボードまで行く時もあった)
こちらは安心して話ができ、上司はそれを文章と図にまとめる。
要するに、上司にコンサルしてもらっているイメージだ。
こんなことが何度かあると、つぎに上司は私に紙をわたし、「言いたいことをまとめてみて」と言った。
まとめたものを見せると、上司はそれを使って私にヒアリング、さらに紙を添削する。
こんなことが繰り返され、最終的には、私は相談事項がまとまっていないときは、自分で紙にまとめてから上司のところへ行くようになった。
そしてこの効果は一石二鳥だった。なにせ、「部下の相談に乗ること」と「コンサルタントがお客さん先で求められる能力の訓練」を一度にできるのだ。
もちろん、私はマネジャーになってから、上司のマネをして、これを部下に提供した。
3.クセにならないと、結論から言えない
第三に、「結論から言う」のは、一種の習慣なので、クセ付けがなされていないと、実行されない。
新人はそうしたクセがないので、クセ付けのための何かしらの仕掛けが必要だった。
そこで、上司が考案したのが、「結論から言うと」を枕詞にさせることだった。
話すたびに「結論から言うと」と初めにつけるのだ。
この制度の影響で、結論から言えない人でも「結論から言うと」とはじめに言うので、オフィス内の日本語は大変面白いことになっていた。
ただ、この口癖が普及すると、2つ面白いことが起きた。
一つは、「結論から言うと」と言ったのに、結論から言っていない場合、本人が「あ、すいません!私、結論から言ってないですよね。」と、自分で気づく。
そしてもう一つは、部下の中に「あえて結論から言わないのですけど」と切り出す人が出現した。
上司はそれも自由にさせていたが、「結論から言うと」が口癖になると、セルフチェックの効果が働くのだ。
*
以上の3つが「結論から話す」がなかなかできない原因であり、それに対して実際行われていた対処法だ。
3つとも、効果は確かにある。
とはいえ、結局のところ、「みんな、できるようになるまでに時間がかかる」と上司が認識していたことが、一番のポイントかもしれない。
つまり「結論から」は、「言うべきこと」を率直に言わなければならない、という「企業の文化」をとても強く反映している。
その文化形成なしに、表層だけマネをしても、たぶん定着は難しいだろう。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
安達裕哉
元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。
◯Twitter:安達裕哉
◯Facebook:安達裕哉
◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(webライターとメディア運営者の実践的教科書)